| Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A
Case Study in Performance Practice5 by William Geoffrey Kempster |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p80 CHAPTER 5 Canon, fuga, and imitation 1500年までに、模倣はポリフォニックテクスチャを整理および統合する主要な手段になっていった。 Hayne van Ghizeghem -オケゲムの時代の長いフレーズや横の線形のデザインに代わって、この新しいスタイルは簡潔で、モチーフフレーズであり、明確なセクションの1つなのである。動機は繰り返されたり、移調されたり、変化したりし、これらの繰り返しは、テキストの単語やフレーズの繰り返しと密接に関係している。 Pierre de la Rueほどこれが当てはまる人はいなかった。実際、作曲家がその対位法的才能を披露するために工夫した多様なメソッドは、Pierre de la Rueのスタイルの決定的な特徴である。 このため、この模倣スタイルを支配する2つの特殊技法をより詳しく見る必要がある。それはカノンと模倣であるが、カノンほど厳密に適用されていない技法は単に、「模倣」と呼びたい。 当時では、「カノン」とは用語の現代的な意味が示唆するものではなく、「パートが生まれてくるためのルール」を意味し、この時代のすべての作曲家は、厳格なカノン書法の利用可能な多くの手順に魅了されたようである。 La Rueは、カノン書法が提示する知的規律、特に、同じソルミゼーションが保持されているさまざまなcanonの記述を特に楽しんだようである。 間違いなく彼は、自身の才能への挑戦のために、このカノンを考慮した。 p81 la Rueのカノンセクションの多くが、厳密に同一のソルミゼーションで実現可能であるという事実は、これを証明しているようである。以下のBenedictus of the Missa Incessanlent:を考えてみたい。 これは四度カノンで、同じソルミゼーションの適応と考えられる。音程関係は、最後のカデンツへのアプローチまで保持されている。そこでは同じソルミゼーションが、最初のbassusIにおいては、A♭でG上のsuprasemitone cadenceにつながっていき、bassusIIにおいては、 F この時代の多くのカノンは、曲のまさに最後で若干モディファイされたように、私は、下譜での導音の選択は優れていると信じる。 例42 この例で特に魅力的なのは、最初の声部で何度も繰り返し行われる半音変化が、四度上に移調された2番目の声部で再び現れるとき、完全な対位法的および和声的な意味をなすということである。 p82 la Rueの作品のこのタイプの例の後の例でも同じことが当てはまるため、これは偶然とは見なされず、そしてそれゆえに、根拠の重みは、必然的に、 la Rueがこれらのようなカノンセクションの一般原理と同じソルミゼーションを意図したという結論につながる。 la Rueの(時代の)歌手が、この音楽を一声部からしか読まなかったという事実は、それが現代のスコア記譜に移された時には、カノンを正しく実現するために必要な半音階的変更が提供されているという証明にもなる。 厳格なカノン以外に、la Rueの音楽は一貫してさまざまな模倣書法のやり方を中心に展開されており、最終的には、16世紀のZarlinoによって、もっとも簡潔に分類された。 フーガ・・・ある時間を置いて、互いのパートが歌うこと。あとのパートは、同じ音価あるいは異なった音価で歌い、全音や半音等の関係も同じである。声部はユニゾン、四度、五度、オクターブで応答する。 模倣・・・模倣においては、(両声部間の)間の間隔は、フーガのように必ずしも一定の連続とはならない。それはやはり、ユニゾン、四度、五度、オクターブで応答するが、二度、三度、六度、七度等で書かれることもある。 Zarlinoのフーガの説明は、一見、多少大雑把に構成されているように見えるかもしれないが、その柔軟性は、関連するが別個の2つの手法を説明する試みから生じている。すなわち、”厳密な”フーガと”自由な”フーガである。 次に、彼はこの区別を明確にした。 (略) p83 模倣とフーガのこのような明確な定義は、初期の理論家の研究には見られない。 これは、当該時代には2つの概念がほぼ同義語であると考えられ、「模倣」の種類ごとの実際の違いがあまり重要ではなかったという疑問が起こる。以下は、1516年のアーロンからのものである。 パート間の模倣あるいはフーガは、通常的な、音楽作品における慣行である。それは模倣あるいはフーガと呼ばれる。なぜなら、連続する・・・声部がそれぞれの先行する音符を繰り返し、それ以外の場合は、場所は異るが同じ名前の音符を繰り返しているからである。 アーロン(1516)のこの段階では、2つの用語は両方とも同じことを意味する。すなわち、Zarlinoが厳格フーガとよぶものである。 これは、Zarlinoが上記で定義した「模倣」の概念が15世紀後半から16世紀初頭の音楽の特徴ではなかったことを意味するものではない。 大雑把な調査でさえ示されているように、このレパートリーにはテクニックが非常に豊富にある。 おそらく、この一見矛盾しているように見えるのは、理論的な領域が実践に遅れていたことを示す証拠である。 Pickerが上記で観察したように、模倣のメソッドは1500年頃では比較的新しいものであった。したがって、この時期に確立された慣行を説明するための理論や用語が、ちょうどそれが始まった15世紀の半ばでやっと体系的に成文化されたとしても、驚くべきことではない。 p84 したがって、la Rueが作曲していた時代には、我々は、カノンを記述する厳密な意味でのZarlinoのフーガと言う用語を、より限定的な意味合いで、同じソルミゼーションを特徴とするユニゾン、オクターブ、四度、五度での模倣パッセージ同様に使うことができると思われる。 (略) 私がこの問題に関係していると思う一側面は、作品の素材そのものの性質に由来している。 ジョスカンのミサ曲におけるPange linguaチャントの冒頭ピッチから形成されたRoutleyの冒頭動機の例は、この点において、優れたケースである。 確かに、この時代の最も広く利用されている聖歌のソースの1つに非常に精通していた歌手は、当然ながら、そのフリギア旋法のはっきりとした特徴を当然のこととして、保持していた。 第2→3小節、第6→7小節という両進行は、causa pulchritudinisでいう六度→オクターブという進行をよく満たしている。 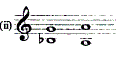 第2→3小節、第6→7小節という両進行を含んでいるという事実によってさらに信頼性が与えられた解決は、唯一可能なやり方で十分となる(以下の例43の赤線を参照)。 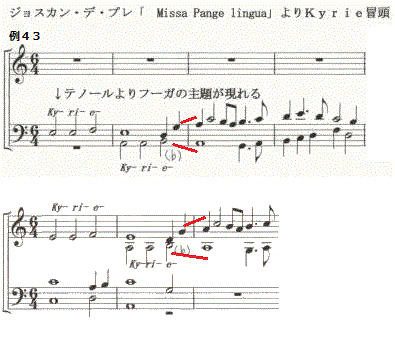 p85 私は、この原則に暗示されている同じソルミゼーションの要求が、垂直の不協和音に関する他の慣習を無効にする可能性もあると信じている。 la RueのMssa Sancra Dei genitrixでは、作曲家は、曲全体を通して、模倣ポリフォニーの基礎として、以下のチャントのincipitを使用している。 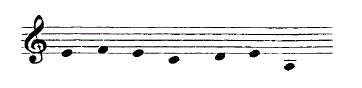 この冒頭動機が模倣的に使用される場合を除いたあらゆる場面で、このチャントはユニゾン、オクターブ、五度上、四度下で現れ、-したがってそれは、EまたはBの開始の音符で始まり-したがって、パッセージが同じソルメーションで現れることを示している。 1つの例外は次のとおりである。  p86 明らかに、ここではテノールには2つの可能性が(訳注;ラで始まるか、シで始まるか)あり、どちらにおいても、通常は回避されるはずの三全音が作られる。ただし、和声上の三全音は、チャントモデルの整合性を保持するために許容されると考えられる。 二者選択の解釈は、この冒頭動機がその最初で全音となっている全作品の中で、ここが唯一となる。確かに、どんな歌手にとっても、この部分は、やりにくいところだろう。 ここを(シで始めてそのシを)rectaB♭に正すことで、テノールパートの旋律的三全音が回避され、同じソルミゼーションが維持されるという事実は、この場合での特別利益となる。 この音楽に半音的変更を適用する際に前述した問題の多く以上に、模倣パッセージに関する意思決定プロセスをガイドする厳格なルールはない。 このようなパッセージの一部は、上記のように、フーガの概念内で考えられたか、あるいはより軽い性質で考えられたかに関わらず、同じやり方で(つまり音程が同一)、”言われるがままに”デザインされたと仮定するのが合理的なようである。 もちろん、実際には、Zarlinoが指摘したように、厳密に同一の模倣は、模倣の音程が、ユニゾン/オクターブ、五度あるいは四度と減じている順に、可能となっていた。 この理由は、ヘキサコードの音程構造が、それぞれの場合で半音となる場をぐるぐる回っていたことによる。 たとえば、前述の例の冒頭の3つの音符は、musica rectaの3つの場所でのみmi-fa-miとして表示できる。すなわち、E-F-E、B-C-B、およびA-B♭-A(それぞれ、自然のヘクサコード、硬いヘクサコード、およびやわらかいヘキサコード)である。 p87 実際には、上記以外の音程での模倣は、musica fictaに関連付けられたヘキサコードの呼び出しが必要になり、たいていこれは、より遠いヘクサコードの操作がなければ、作品の実行は不可能であった。 たとえば、連続する二度音程で、同じソルミゼーションを使って、この動機を作曲することを想像せよ。16 16 場合によっては、二度の複合音程、つまり九度が、同じソルミゼーションを実行可能にするかもしれない。 la RueのモテットPater de caelis楽譜では、たとえば、2つのカノン的応答が、連続する五度音程とともに、第3の声部が、第1の声部上で長九度を作っている。(下譜) 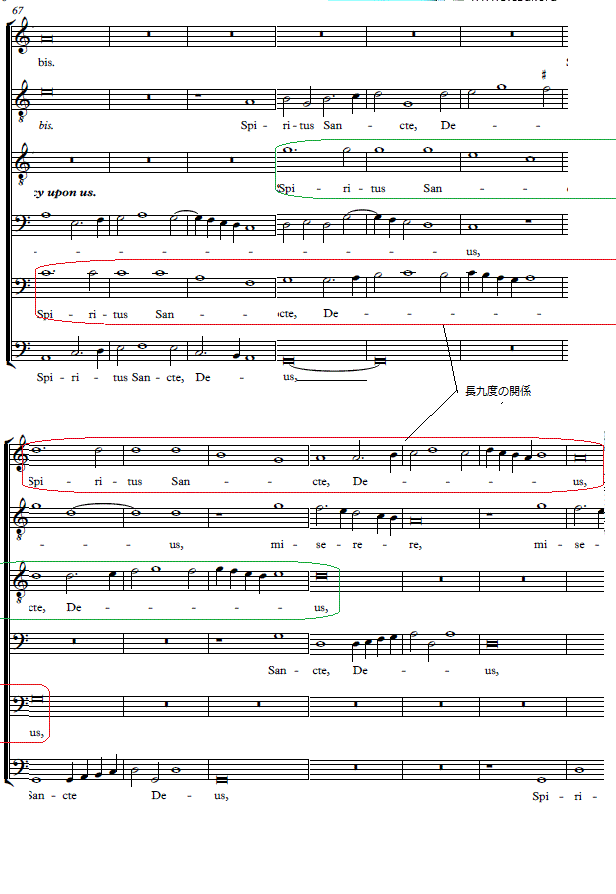 Pater De Caelis Deus ただし、模倣の間隔が非常に長いため、正確なカノンとして解釈された場合、これらの2声部がクラッシュするケースはほとんどない。 だから、la Rueが同じソルミゼーションを意図していた可能性はあると思う。 ただし、模倣の音程が上記のいずれかである場合、各ケースを個別に調べて、正確な音程の繰り返しが必要かどうかを判断する必要があるだろう。 これがmusica fictaの適用を必要とする可能性が高いという事実は、本論文自身に合致しないことはない。これは、Allaireのヘクサコードシステムの分析によって強く支持されているポジションであり、例45に示すように、模倣で使用されるパッセージ全体が全音階的輪郭を全部使っていない場合でも、適用される。 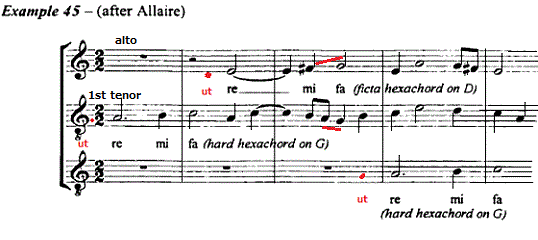 この例では、トップパートの5番目の音符は、中間パートによって確立されたパターンから出たものであるが、Allaireは、fictaF♯を複数使うことで(D上のficta hexachordを使うことで)、動機の最初のセクションと同じソルミゼーションを指示している。 p88 この例では、第3小節のオクターブが長六度でアプローチされるのならば、Allaireの結論は正当化されると思われる。そして、ここの直前のパート間の五度は完全音程となっている。17 17 この例では、第1テノールにおいて、柔らかいヘキサコードでこのパートを実現した結果、rectaとして、BをB♭で代替すると、第4小節が問題になる。この場合、Eはfa super laに従って♭化されることも予想される。だがそうすると、 アルトと三全音になってしまう(アルトは明らかに、この小節の最初のEは、E♭にはならない)。テノールは、第3小節でB♭となり、その後に第4小節でE この観点から、模倣の音程が言及された場合、基本的に同じ全音階形態を保持する模倣パッセージには同じソルミゼーションを適用するのが妥当と思われる。 ただし、模倣資料の個々の特性が決定に重要な影響を与えるため、各ケースには特別な考慮が必要となる。 この問題が音楽の印象を変える程度を例示するために。 私は、 la Rue's の世俗的作品の1つ、シャンソンTrop plus secretで特に興味深い一節を考えたい。 以下のこの曲の冒頭である。 例46 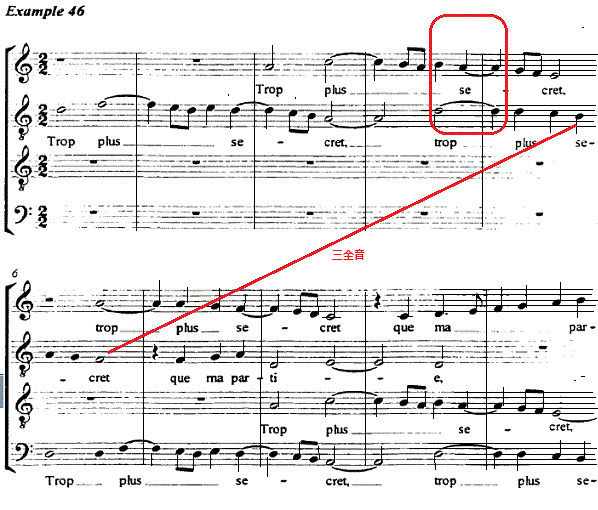 この(臨時記号のない)「ストレート」バージョンには多くの問題があるだろう。当時の歌手は、音楽の難しさも認識して、これを訂正しようとしていたことだろう。 これらの問題は、模倣パートが解決される方法とその結果の対位法として結実する。 この音楽を解釈には、次の点を考慮する必要がある。 1 動機は、それぞれのパートにおいて、2つのフルフレーズが五度間隔で、ほとんど厳密な模倣となっているように見える。 2 書かれたままに考えると、それぞれは別のソルミゼーションを要求することになる 3 第4小節で生じる長六度→五度の経過音は変更を必要とする 4 contratenorの第2フレーズに関連した強いメロディ的三全音がある(第5-6小節B→F)が、説得力がなく、柔らかいヘクサコードへのmutatioを要求する。 上記の最初の2つの点を考慮すると、この動機が真のフーガとして五度音程で現れ、それが真のフーガに非常に近いという事実を考えると、少なくとも、作曲家がそのパートらを同じやり方で記す"ことを意図していた可能性はあるだろう。 p90 したがって、上記の第3,4点は、満足な選択肢が可能であれば、解決できることが示唆されている。この可能性を調べてみたい。 第4小節の後半部分でのBがB♭となることを示唆する上記の第3点について。これは、第2小節の後半でEがE♭になることを要求することだろう。fa super laを形成する感覚で。 では、第2小節の前半はどうなるのか? 最初に読まれたとき、このメロディーのラインは孤立して取られ、歌手に装飾を思い出させたかもしれません。以下のように。 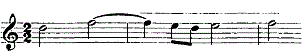 しかし、進行が最終のFまで続かなかった場合、パッセージがこの種類のものではなかったという事実は明らかであり、したがって歌手は、自然なヘキサコードの範囲を下回るラインの降下に備えて、どこでmutatioをするかという問題に直面したことだろう。 次の2つの選択肢がある。 1 第3小節にあわせて硬いヘクサコードにmutatioする。 2 第6小節終わりまでの全体のパッセージにあわせて、やわらかいヘクサコードにmutatioする。 2番目の可能性は、より節約的な解決であり、こちらがよりあり得るやり方と考える。そうすると、mutatioは、リスナーが期待したこととは異なって、メロディ形成ができる点がトリガーとなる。それはすなわち、第2小節のD re laである。特にre laは、下方へのmutatioに対して、共通軸として認識される。 これは、冒頭で採用されたアプローチとは異なっており、そのフレーズの後の部分とのつながりにおいては、通常とは異なる。前述の、この第2小節の後半でのfa super laに言及して、以下のようになる。 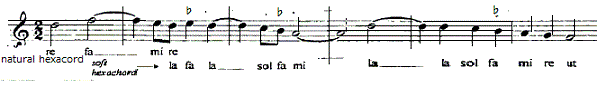 ここにはルネッサンス期の歌手に対する特別な問題は存在しないことだろう。第2小節のEにおける対斜の問題はあるが、確かに歌手は以前にこの多様性の構造に遭遇したであろう。 fa super laの実用性に関する以前の議論が明らかにしたように、この解決は、musica fictaを含まず、B♭は、fa super laでのE♭と同様、rectaの選択肢となり、(やわらかいヘクサコードとなった以降の)オペレーションは、mutatioなしでなされると考えられる。 既述したように、この解釈のさらなる利点により、次のように、最初のmutatio後に両方のフレーズが同じヘキサコードに収まる。 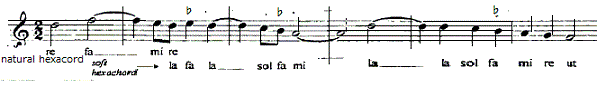 シャンソンのこの冒頭のすべての部分にこのソルミゼーションを適用した結果はどうなるだろうか? 上記の4つの問題すべては自動的に消えるだけでなく、繰り返し起こる対斜は、テキストでの”secret"という暗示とともに、直接的に強力に繰り返し生じてくる。23 23 この時代での直接の音画法は、まだ比較的まれであると考えられているが、これまで考えられてきたよりは多くの作曲ツールの使用が指摘されている。前述のJosquinのモテットPraeter rerum seriemが提供する非常に強力な例を参照せよ。 以下はこれらのまとめである。 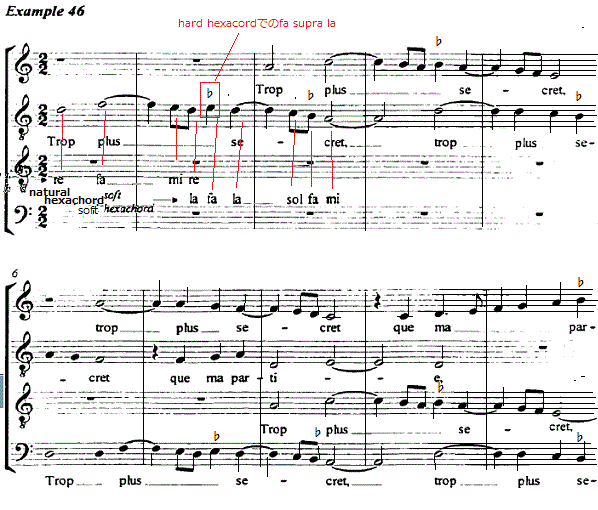 |