| On the Theory and Practice of Chromaticism in Renaissance Music6 Zhuqing Hu |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p145 Defining Beauty(Practices associated with musicaficra参照) 最後の章は、14世紀初頭にMarchetto da Padova がLucidariumを書いた頃には、音楽理論家らがすでにmusica fictaを彼らの知識に取り入れていたことを示している。 したがって、Dufayの作品における臨時記号のinflectionやTerzfreiheitの蔓延は驚くべきではない。 ただし、問題は、グィドの手の音域外のピッチの存在論ではなく、目的論に関するものである。歌詞がなければ、Dufayの作品でmusica fictaが広く使用されるきっかけは何であろうか? 音楽理論の歴史に関する現在の言説では、中世およびルネサンスの理論家がしばしば議論したmusica fictaを使用する2つの理由がある。 最初の理由はcausa necessitatisつまり「必要性のため」であり、完全協和音程を完全にしておくための必要性を指す。 増価、または減価した増大または減少したユニゾン、四度、五度、オクターブに対する、垂直または水平のいずれかの処方箋は、中世およびルネサンスの理論で最も重要な対位法的規則の1つであった。Lowinskyの“secret chromatic art”「秘密の半音階芸術」はこの主張から引き出されており、「Quid non ebrietas」での多くの♭はまた、この規則で動いているものである。 musica fictaの2番目の理由は、causa pulchritudinis「美しさのため。」である。 musica fictaに関する研究論文,で、Bergerは、caudsa pulchritudinisはカデンツでの臨時記号のinflectionsに対応している、と示唆している。 美とカデンツのこのランダムな関係の証拠は、MarchettoのLucidariumを含むさまざまな時代の論文に由来している。56 56 Berger, Musica Ficta, 122-7. そもそも、協和音と不協和音についてのLucidariumの論文5において、Marchettoは、2種類の不協和音を定義している。 すなわち、”耳と心によく合うか”、”そうでないか”、ということである。 最初のカテゴリーには3つの主要なタイプがある。三度、六度、そして十度である。これらは、「耳に合う不協和音」によって、現在不完全協和音程と呼ばれるものを意味する57。 p146 これらの不協和音または不完全な協和音が耳に合い、したがって実際の不協和音と異なるのはなぜか? Marchettoの説明は以下である。 「不協和音は不完全なものです。 それは、完全とされ得る手段によって、完全となることを要求します。 協和音程は完全である。 不協和音は、協和音から遠く離れていなければ、その完全さからも離れることはなく、完全により同化されていく。したがって、協和音の性質をより多く享受するかのように、耳に心地よくなります。 58 上記の引用は、不完全協和音程が階層的に、完全協和音程に服従することを示唆している。しかしながら、完全協和音程はその性質により、「耳と心に心地よい」ので、不完全協和音程は完全協和音程へ服従することよってのみ心地よくなる。言い換えれば、不完全な子音の存在理由 raison d’être は、最も近い完全協和音程に向かうことによって完全に到達することである。 これは、Marchettoのchromatic semitoneがゲームチェンジャーになる場である。 p147 「半音階」“chromatic”という言葉は、ギリシャ語のchromaに由来する。chromaはギリシャ語でcolorの意味である。このように、「半音階」“chromatic”という言葉は、“color of beauty,” と呼ばれます。 なぜならそれは、全音が全音階とエンハーモニックゲネラへの分割のサイズを超えて(2つのパートに)分割される不協和音の優雅さと美しさのためである。 そのために、不協和音は、それらに続く協和音に近いかもしれない。両声部は、全音が半音階的声部の上下に特定の距離で響くようなやり方で動いている。59 59 Ibid., 148-151, quoted also in Breger , Musica Ficta, 123. 特に、“color of beauty”に対するMarchettoの表現が“color pulcritudinis”であり、“elegance and beauty”は「decorem pulcritudinemque」であり、それらのcausa pulchritudinisへの親和性は明らかである。 したがって、chromatic semitoneのpulchritudoは、最も近い完全協和音程にさらに近づけることにより、不完全協和音程をより「耳に優しい」ものにすることに関係している。それは、完全化傾向をより指向的かつ強力にすることにより、不完全協和音程からその最も近い完全協和音程への対位法的動きを強化している。 Marchettoは後に、このような完全性には、片方は上がり、片方は下がる不完全協和音程の両声部の間での反行が必要であると主張する。60 彼はどのような場合にそのような進行が起こるべきかを特定していないが、Prosdocimus, Tinctoris, Zarlino を含む後の理論家は、不完全協和音程から反行で動く声部との最も近い完全協和音程への進行は、カデンツに特有であることを示している61。 61 Berger also gives a rather detailed account of cadences in Musica Ficta, 122-24. 上記での引用の2つに沿ってMarchettoが提供するさまざまな例は、カデンツでの緊張と開放であるcausa pulchritudinisのこの解釈を指示している。(例2-6.1、6.2、および6.3).62 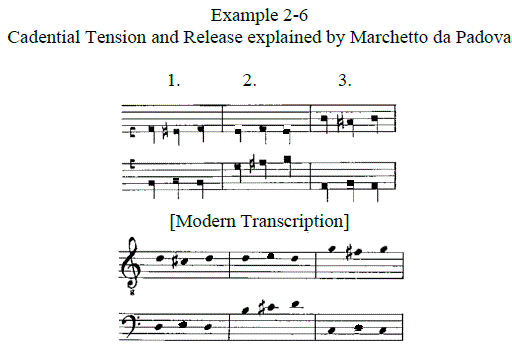 最初の進行(例2-6.1)では、上声部のCでの 実際、 Marchetto は、通常のピタゴラス調律のものよりも意図的にchromatic semitones (たとえば、C-C♯)を拡大する可能性がある。彼はこのように不完全の緊張を高め、ターゲットとなった完全協和音程での開放感を強化している。 このように、一般的な実践の時代のカデンツは主に、和声進行や中世やルネッサンス音楽のそれ、そして対位法的進行を通して定義されているが、、緊張と解放の同じ論理は両方に等しく適用されている。 Chromatic semitones,、または一般的なmusica fictaは、カデンツの緊張と開放の点での強い傾向的トーンを生成する能力のおかげで、正確に、美のために使用できる。 Bergerの研究論文で広範囲に議論されているように、causa pulchritudinis が特にカデンツでのmusica fictaの使用に注意を向けているという見解は、この用語の従来の解釈となっていが、奇妙な現象を見落としている。 p149 通常、causa necessitatisの意味合いと増価あるいは減価した完全協和音程の禁則は明らかなので、中世やルネッサンスの音楽理論家たちは、musica fictaのpulchritudoが実際何を必要としたのかはほとんど常に曖昧であった。 chromatic semitoneを説明する時にpulchritudoという言葉を使用するMarchettoの場合でさえ、causa pulchritudoが、Bergerが推奨するように、カデンツのinflectionに固有のものとして言及することは、簡単ではない。63 63 実際、Berger自身は、causa pulchritudinisの理論家の議論において繰り返されていたあいまいさと、彼がカデンツのinflectionとcausa pulchritudinisの間に確立したリンケージの間接的な性質に気づいていた。 もしもcausa necessitatisのように、causa pulchritudinisもまた、カデンツのinflectionsとしての音楽理論と実践の成文化された慣習を示しているのであれば、なぜ、causa necessitatisが理論的に非常に明確に定義されていたのか? causa pulchritudinisはとても曖昧であるのに。 causae necessitatis と pulchritudinisについての理論家の議論の特異性の対照的なレベルを視野に入れて、Thomas Brotherは最近、necessitatisとpulchritudinisの2つのcausaeが、musica fictaを使うための正反対の理由であることを示した。 「Necessitas」とは、理論家たちがそれらに愛していた厳格な対法規則の義務的遵守を意味する。一方、“Pulchritudo,”は規則ではなくオプションである。 それは、musica fictaの”システマティックに成文化されたアプリケーション”ではなく、”理論の基礎がないアプリケーション”を意味している。64 64 Thomas Brothers, Chromatic Beauty in the late medieval chanson, 10. 結局、「美」は通常、合理的な属性ではなく、質的な概念を必然的に伴うのである。Brothersは論じる。「もしわれわれが合理的構造物としての音階を考えるのであれば、inflectionは、全音階的音程の世界から逸れたものであるとみなされるかもしれない」、そして、「musica fictaは、不合理な現象としてstandしている」。65 64 Thomas Brothers, Chromatic Beauty in the late medieval chanson, 11 p150 歴史的論文での定義の曖昧さにもかかわらず、Brothersは、musica ficta pulchritudinisと世俗的なシャンソンとの特定のつながりに気づいている。 causae necessitatisとpulchritudinisを持ち出したする最初期の理論家のひとりだった、13世紀と14世紀のアノニマスIIによれば、 False musicは、必要性とメロディ自体の美しさの2つの理由で発明された。 必要性の理由は、becouase we could not have a fifth, a fourth, or an octave, as in the places examined in the chapter on proportions. 美しさのため理由は、cantus coronatusに表れている66。 「Cantus coronatus」は、文字通り、「王冠の歌」または「賞を受賞した歌」を意味する。 ただし、実際にはトロヴェールのgrand chansons courtoisのハイスタイルなジャンルを指す一般的な名前であることが示されている。67 したがって、Anonymous II が、美しいmusica fictaへの活動舞台として特定するものは、モノフォニックの世俗的な歌です。 同様のパッセージは、いわゆるars subtiliorを促進したアヴィニョン界で活躍した理論家であり作曲家フィリップ・デ・カセルタ(fl。c。1370)に帰せられた論文にも現れる。興味深いことに、作者はAnonymous II’sのcantusを別のものに置き換えている。 p151 ボエティウスは、2つの理由でmusica fictaを発明しました。sなわち、ひとつには必要のため、もうひとつにはメロディーの美しさのため。必要性の理由は、上記のように、すべての場所で協和音程になれないためである。 しかし、美しさの理由はcantelinaに表れています68。 68 Philippotus de Caserta, in his treatise edited by Nigel Wilkins, “Some Notes on Philipoctus de Caserta (c. 1360?-c.1435),” Nottingham Medieval Studies 8 (1064): 95-9, as quoted in Brothers, Chromatic Beauty in the late medieval chanson, 15-16. 上記の2つの引用符を比較することにより、Brothersの、中世の世俗歌におけるmusica fictaの「美しい使用」の安定した伝統への論議は許容される。その世俗歌は、14~5世紀のポリフォニーcantelinaへのトロヴェールのモノフォニー的なcantus coronatusで始まる。 causa pulchritudinisの意味に対する彼らの異なる理解のために、中世の音楽における“chromatic beauty”に関するBrothersの研究は、Bergerの研究からはかなり異なっている。 カデンツのinflectionとしてのBergersのcausa pulusaritudinisの説明には、神聖なそして世俗のポリフォニーにおけるカデンツでのmusica fictaの成文化、慣習化されたアプリケーションが含まれている。 このような理解は必然的に、Bergerが、作曲家が特有に書いたものよりもむしろ、理論家たちが言わなければならないことへの注意を払うように仕向けている。 一方Brothersにとって、causa pulchritudinisのうちからmusica fictaの意味合いを定義する音のは、音楽理論家次第ではない。 禁則の音程を避けるための必要なinflectionsとは異なり、これらの「美しい」、「風変わりな」inflectionsは、Brothersが書いたように、理論的な教義を支持するのに役立たない。代わりに、pulchritudo とmusica fictaの理解を「多様性、繊細さ、そして不合理さえ達成するためのツール」として示すのは、作曲家次第である。69 69 Brothers, Chromatic Beauty in the late medieval chanson, 10 and 15. Brothersは、Anonymous II とCasertaの記述に従って、主にsecular corpusに対して臨時記号の「美しい使用」を制限し、彼の研究論文は主に実際の作品に捧げられている。 すなわち、Bibliothèque nationale in ParisのTrouvère Manuscript O、ギヨーム・ド・マショー(1300〜1377)のポリフォニーシャンソン、2つの有名なars subtilior写本MSS Chantilly 564 と Oxford 213、そして最後にデュファイの初期シャンソンである。 p152 Brothersの研究で最も多くのコメントを集めたのは、おそらく一次資料で作業する際の、表記されていない臨時記号についての彼のスタンスである。 当時の作曲家や筆記者が、臨時記号のinflectionをすべて示しているわけではないことは、広く知られている。 この見解は、musica fictaをどこに適用するかについてのよく知られた規則が、それがcausa necessitatis であれpulchritudinisであれ、その当時のinflectionの細心の表記法を余計にすることを示唆している。 初期の音楽における記譜されていない臨時記号の概念は非常に一般的であるため、現代の編集慣行では、musica fictaという用語は、グィドの手の音階外の音高だけでなく、一般に、記譜されていない臨時記号も指すようになった。 記されていない臨時記号のかなり一般的な概念をSubscribingして、Bergerは、musica fictaについてのその時代に編纂された歴史的な音楽理論の知識の適用することについて、彼の3パートの研究論文の最後を費やした。70 70 Karol Berger, Musica Ficta, “Part III: Writen and implied accidental inflections,” 162- しかし、「美しい」臨時記号の規律のない性質にBrothersが重点を置いているため、特殊な表記上の特徴を額面どおりに扱う必要がある。おそらく記譜されていないmusica fictaを再作成することは、音楽理論家たちの一般的な見解を反映することしかできない。 現存する写本のソースに含まれるinflectionsの個々のバージョンのみが、それらがどれほど不十分に見えても、おそらく作曲家の個々の選択を示している。 したがって、理論家から作曲家への「美しい」臨時記号の権威を回復するために、Brothersは中世の音楽における記譜されていないinflectionの伝統の概念に挑戦している。Brothersが注目したこのような概念は、同時代の理論的著作物から支持を受けておらず、実際には、臨時記号の特殊な機能がしばしば規定し、作曲家にはinflectionを明確に表記するよう指示していることが多い71。 71 Brothers, Chromatic Beauty in the late medieval chanson, 21-44. p153 シャンソンの「美しい」inflectionsに関するBrothersの分析では、通常、作品の現存するすべてではないにしても多くの要素を考慮し、各表記の臨時記号を、可能な限り最大限に、作曲家のオリジナルな決定として扱う。 記譜されない臨時記号の伝統が中世と初期のルネサンスに実際に存在したかどうかの論争は、解決されるにはほど遠い。 Brothersの研究論文についてのレビューでは、Sarah Fuller と Peter Urquhartの両者が、記譜されないinflectionsの可能性に対する彼の完全な無視と作品の異なるバージョンで記されたすべての臨時記号を作曲者のオリジナルとして扱うという過度に無差別な態度を批判している72。 確かに、現存するソースに記譜された臨時記号の欠如の可能性は、臨時記号の表現力に関するBrothersのプロジェクトを複雑にしている。しかし、Brothersが、現代の知識の限界にもかかわらず、中世の音楽で「必要」ではないすべての臨時記号のinflectionsの表現的ポテンシャルを認識し、研究していることは賞賛に値する。 彼は、臨時記号は理論的な慣習や演奏の実践の信奉者であるだけでなく、主観的なpulchritudoのlociとも見なされるべきであるという重要な点を挙げている。 因果関係についてのブラザーズ独自の視点は、個々の作品を説得力のある効果的なケースバイケースの分析に導く。これは、Fuller と Urquhart が、他の批判にもかかわらず認めていることである。 p154 Syntax over Text Brothersの研究の美と表現力の範囲は、Bergerがデュファイの“Navré je sui” や“O beate Sebastiane.”で観察した模倣的なmi- やfa-stepsをはるかに超えている。 実際のところ、Brothersがトロヴェールのモノフォニーソングから中世後期のシャンソンへ見ているcausa pulchritudinisは、inflectionsがテキストにどのように役立つかにはほとんど関係しない。むしろそれは、Musica fictaの作曲家の微妙かつ特異な使用により、柔軟な音楽的構文がどのように作成されたかを扱っている。 音楽的構文の概念は、2つの側面で構成されている。すなわち、動きと停滞の感覚、および異なるピッチクラスまたはソノリティ間の関係である。 このような概念は中世の論文では明示的に現れないが、ちゅせいの音楽の構文の現代の論議は、その基礎を、多くの理論家が議論してきたもっとも完全音程に近い不完協和音程の直接的傾向に基づいている。 Sarah Fullerは、Machautが、不完全から完全への進行において、どのようにしてこの単純なtension-resolutionのロジックを使用したかを徹底的に調べた。or what she calls a “directed progression,” to create forward motion and to clarify the tonal orientation.74 特にmusica fictaは、このプロセスで決定的な役割を演じている。なぜなら、Marchettoが上に示したように、♯と♭は不完全協和音程のテンションを高め、完全へのその解決の直接性を高めたからである。 Fullerの分析は、それを通して臨時記号のinflectionsから生じる和声的な緊張が最終的に解決する、直接進行をマッピングし、特徴づけている。Fullerは、Machautの音楽的構文において3種類のソノリティを区別している。例2-7に示されているように。 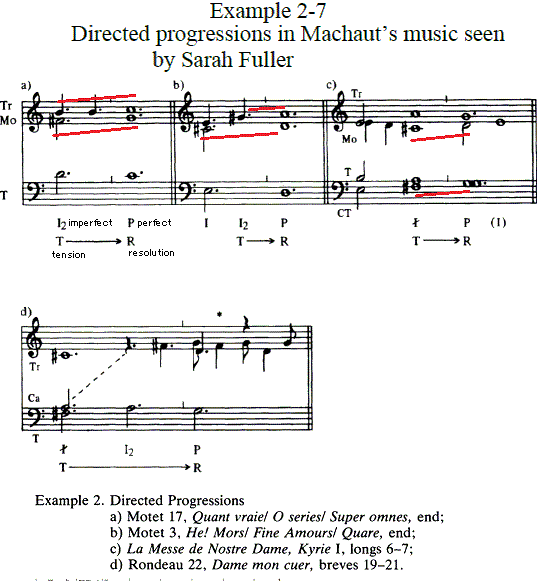 p155 オープン五度やあるいは八度は、「完全」ソノリティであり、すべての中で最も安定しており、解決を必要とせず、resisting forward motion.特に♯や♭化された導音を含む垂直の三度あるいは六度は”不完全”ソノリティを生じている。そして、結果としてオープンとなった「完全」傾向を生じるため、音が不安定になる。二重導音のソノリティは”二重に不完全”となる。それは、その2つの不完全協和音程があるため、さらに安定していない。76 76 Fuller, “Tendencies and Resolutions,” 235 これらの3種類のソノリティは、音楽の句読点の程度を変化させる。緊張が「不完全」で、解決が「完全」であるほど、構文上のpauseはより強力になる。これは、14世紀の数多くの作品のカデンツが、オープン五度に解決していく二重導音となる理由を説明している。 p156 カデンツに加えて、マショーはさまざまな種類のソノリティを慎重に使用することで、より大規模なピッチクラス間の階層関係を作成している。 たとえば、モテット「De bon espoir / Puisque / Speravi」においては、モテットの始まりのいくつかの不完全Aソノリティは、完全Gソノリティに移行し、Gがlocal tonal centerとして明確になる(例2-8).77。しかし、その終わり近くでは、不完全Gソノリティが徐々に完全ソノリティに置き換わり、GからFになり、モテットは終止となる78。 77 Example 2-8 is recreated from Fuller, “Tendencies and Resolutions,” 237. 78 Fuller, “Tendencies and Resolutions,” 234-9. 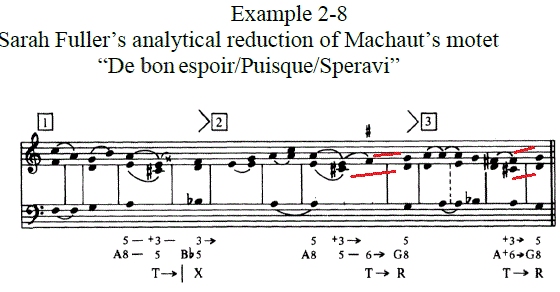 Fuller が特に独創性を見出したのは、単純な不完全から完全への進行を変化させるためにMachautが使用する無数のテクニックである。 彼は最初に不完全ソノリティを置くことがあり、通常、安定した完全フレーズを特徴とするフレーズの終わりとなり、したがって、前進運動の推進力をインストールする。 彼はまた、不完全ソノリティの解決を中断することにより、前方への衝動を拡大するかもしれない。 予想される解決を不完全ソノリティに変換するか、完全に予想外の解決に置き換えると、構文は新しいトーンセンターに向けられ、音楽に多様性が追加される。 予期しないvoice leadingでも同様の効果が得られる場合がある。Fullerの“Tendencies and Resolutions”のp252で以下のように観察している。 p157 Machautの場合、直接進行は、フレーズまたは作品を終了するための従来の公式よりもはるかに多くなります。 これは、音の方向が定義され、またはシフトし、フレーズまたはセクションのエンディングを橋渡しし、冒頭を前方への突き出しで埋めることができる重要な芸術的資源です79。 79 Ibid., 252 彼女の観察によると、マショーの直接進行は、その芸術性のおかげで、Brothersがmusica fictaの「美しい使用」と呼ぶものとしての資格があるだろう。 したがって、マショーのシャンソンがBrothersのcausa pulchritudinisについての研究の主要な例のうちにあることは、そして、彼の分析がFullerの分析と多くを共有していることは驚くことではない。 しかしながらFuller はソノリティに焦点を当てているが、Brothersは大規模なピッチデザインにおける個々の臨時記号のinflectionsの役割をより強調している。 <Biaute qui toutes autres pere> Machautの2声バラード「Biaute qui toutes autres pere」についてのBrothersの分析は、彼の臨時記号の中心へのアプローチを示している。80 80 Brothers, “Musica Ficta and Harmony in Machaut’s Songs,” The Journal of Musicology 15 (1997): 512-6. そもそも、DについてBrothersは構造的に重要だと思っている。なぜなら、シャンソンのすべての音楽フレーズが完全Dソノリティでのカデンツで終止するためである。 興味深いことに、Dカデンツではいずれも、♯化された導音Cあるいはその前の”六度の”B♮は、どちらもDに対してのドライブを大幅に強調している。 対照的に、Gは一時的な中間点の到着時にのみ示されるが、F#は、作品の音調をG方向、つまり第6,15小節(第37小節で繰り返される)に明確にし、推進する。 Gへの頻繁なドライブは、第3-4小節でのDへの単一の直接進行を覆い隠す。E♭-Dの半音進行が下のテノールで発生しているが、そしてソノリティ的には不完全なE♭-G(の和声)はその最も近い完全協和音程であるD-A(の和声)に移るが、Brothersは”写本の証拠パターンは・・・下方への導音が♯化された対位法に比べて少数派であることを明らかにしている”」ことを示唆している。81 p159 したがって、「Biaute qui toutes autres pere」での臨時記号のinflectionsは、バラードの構文の柔軟性とtonal design に貢献している。 Machautの特定のinflectionの使用と非使用は、構造的には目立つが音色的に弱いDと、構造的に目立たないが音色的に強いGを生み出す。このような組み合わせは、中世の音楽に特有の柔軟な音楽構文を例示している。作品は2つの対照的な中心の間(GとD)で変動している。そしてバラードは「単一の支配的なピッチに減じられることはできない。」82 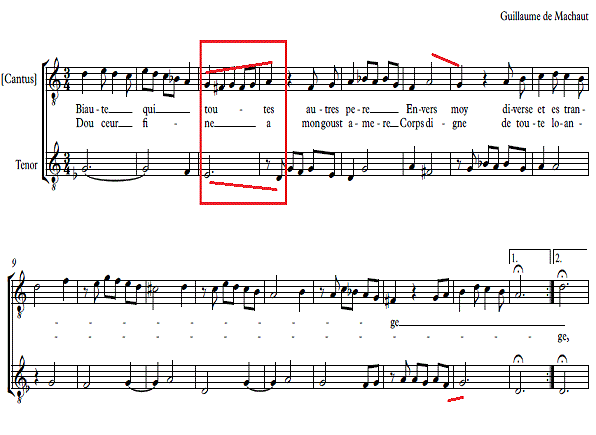 Biaute qui toutes autres pere Dufayのシャンソンでの「Terzfreiheit」のBrothersの解釈は、臨時記号の能力を緊張の解決への進行に促進させ、tonal orientation.をはっきりさせるために、正確に描かれている。 彼は、Besselerの用語「Terzfreiheit」を、それが時代錯誤的に機能的な和声を意味するだけでなく、用語「Terzfreiheit」を、用語が示唆するような調性―和声事象としてではなく、本質的にlinear phenomenonとして見ているため、拒否している。83 83 Brothers, Chromatic Beauty in the Late Medieval Chanson, 195-9. そもそも、Brothersは、“lowered third degrees”がより強いリズムを生み出すことに気付いている。たとえば、デュファイのバラード「C'est bien raison de devoir essaucier」のルフランを締めくくるF-reカデンツでは、「カデンツの三度」をA♭に下げることは、導音Eとの減四度の関係、そしてCへの導音B♮との増二度の引き金となる。(例2-9)84。 84 Example 2-9 is recreated from Brothers, Chromatic Beauty in the Late Medieval Chanson, 197. 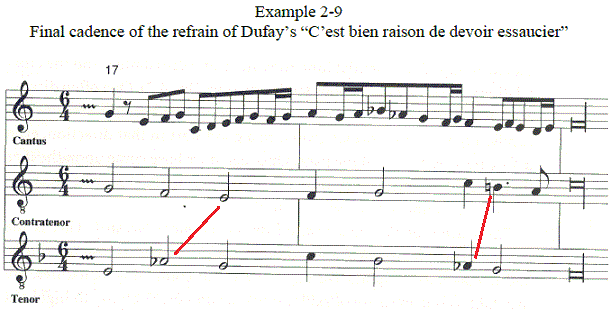 p160 これらの不協和な非和声関係は、2つの導音のトップにおけるカデンツ前のソノリティにおけるより多くの緊張を生じさせる。そして、より前方のドライブとともにカデンツでの解決を促進する。 さらに加えて、マショーの「Biaute qui toues autres pere」のinflectionした導音と同様に、“lowered third degrees”は、特に複数のトーンセンターがある場合、デュファイのシャンソンのトーンフローも指示している。 Brothersは簡潔に、ロンドー“Helas, ma dame par amours,”においてB♭(=Gの“lowered third degrees”)は、「CからGに向かって、F♯を補完する方向を確立することにserveすると書いている。85 85 Brothers, Chromatic Beauty in the Late Medieval Chanson, 192. すでに説明されているように、B♭とF♯のcross relationは緊張を生成し、Gに向かって駆動する。ただし、Bの♭化はまた、強力なCの一時的なlocal cadence あるいはtonal centerとしての到達不可能性を宣言している。 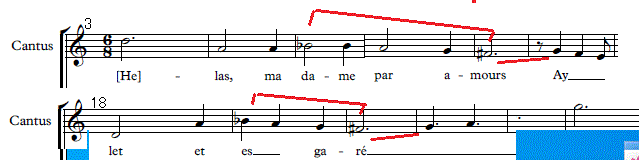 このように、B♭は、 デュファイが音の方向をCから別の場所にそらすたびに現れる。これは、ロンドーのほとんどの中間的なフレーズで発生している。 そして、デュファイがB♮だけでなく、Cの lowered third degree のE♭の助けを借りて、音の焦点としてCへの復帰を完成したことは、驚くべきことではない。 p162 causa pulchritudinisの解釈により、テキストの内容が「Terzfreiheit」を特に必要としないDufayの作品をもう一曲見てみよう。 すなわち、「O beate Sebastiane」(c.f.p134)には興味深い音調計画がある。それは、長いFの完全ソノリティから始まるが、その多くはC関連の調性で進行している。Bologneseの「フラット」バージョンのさまざまなE♭は、Cカデンツを強化し、Fへの潜在的なドライブを無効にしている。したがって、Modeneseのsharp counterpartsのような模倣的な目的の代わりに、Bologneseの(E♭を使った)“lowered third degrees”バージョンは、CがFオープニングを無視したtonal focusであることを明確にするのに役立つ。 Dufayのrotundello「Quel fronte signorille in paradiso」の終わりの突然のB♭の出現も同じ効果がある。それは音の流れをCからそらし、Gへの音の解決を高める。 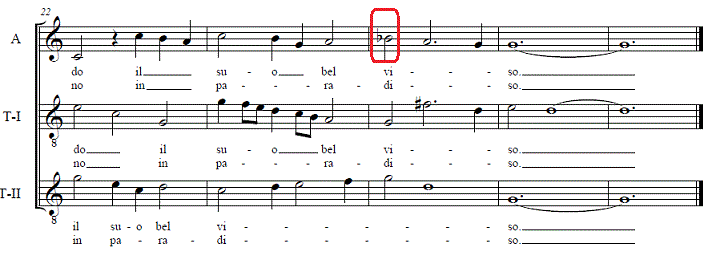 「Ne je ne dors ne je ne veille」では、Aセクションの終わりの “lowered third degree”E♭がD-miカデンツを生成することによるDへのdigression(脱線)を弱めている。 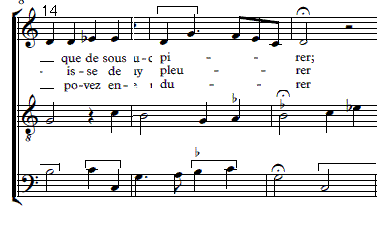 それは、Cでの冒頭の完全ソノリティと第11小節でのCの最初のカデンツに従って、音の方向の中心としてCの状態を維持している。 Bセクションの後半全体に浸透する「Terzfreiheit」は、第26-7小節でのカデンツの緊張と解決を強めることによって、そして第20小節でのGへのdigression(脱線)後のこのCカデンツへのtonal driveを明らかにすることによって、C上のtonal fucusをさらに強化している。 The Evolving Pulchritudo 上記の分析は、マショーとデュファイのシャンソンの多くで、musica fictaの美はテキストではなく構文に関係していることを示している。 テキストがどのように進むかに関係なく、臨時記号のinflectionsは、緊張とforward motionを生成し、それにしたがって音の方向を明確にする。 p163 musica fictaのこの構文機能は、14世紀の理論家が論文で議論していたことを実践する。すなわち、不完全協和音程からそれに最も近い完全協和音程への緊張―解決の進行である。musica fictaは、前者を後者にさらに近づけることにより強化される。 時系列的には、Marchettoは、マショーの作品で頻繁にそれが登場し始める数十年前に、musica ficta の体系的な知識を発展させたと思われる。 それにもかかわらず、musica fictaの構文上の使用は、音楽理論へのコンプライアンスからではなく、作品の革新から発達した。理論家たちがcausa necessitatis の意味合いをdictateし、あるいは完全音程の増価や減価を避けるためにmusica fictaを使用するときに、彼らは決して、いつどのように、緊張と前進を増すためにmusica fictaが使われ得るかを説明しなかった。 したがって、musica fictaの「不要な」機能を活用するさまざまな方法を考え出すことは、完全に個々の作曲家次第であった。 したがって、Thomas Brothers は、マショーとデュファイの作品に例示されている、ゆるくて柔軟な構文を作成するための臨時記号のinflectionのオプションの使用は、一部の理論家がcausa pulchritudinisと呼んだものであると主張する。すなわち「美」は慣習化されておらず、作曲家に特異なものなのである。 このように、少なくともDufayの作品には、「pulcher」とラベル付けできる、musica fictaの2つの使用法がある。なぜなら禁止されている音程を回避したり、理論上の指示に従っているわけではなく、どちらも作曲家の創意工夫を反映しているからである。 「O beate Sebastiane」の2つのバージョンは、musica fictaがどのように初期の「フラット」バージョンでは構文機能を果たし、後の「シャープ」バージョンでは模倣目的を果たしたかを示している。 実際、pulchritudoの考えがどのように進化したかについて、はるかに広い時系列を描くことさえできる。 実際、2つのソースに関するバーガーの研究によると、「O beate Sebastiane」の表現力豊かな「♯」バージョンは、構文上の「♭」なオリジナル版の14年後にできたものである。86 p164 Dufayのシャンソンの作品では、それは一般的に彼の初期のキャリアの頃のものだが、さらに、「Terzfreiheit」のすべてのoccationやその他の「不要な」musica fictaの使用は、テキストにはその基礎がなく、その代わりに構文上の要求を満たしている。おそらく「Navréje sui」は例外的であるが。 一方、彼の後期スタイルの代表である「Ave regina celorum III」は、「同主調の短調」を使用して、テキストの死の概念を表現している。87 87 Thomas Brothers は、モテットが「シャンソンからlowered third degreesの技術を組み込んでいる」ことを示すことによって iでは、不完全なpictureしか提供していない。なぜならそのような見解は、musica ficta の技術がシャンソンとモテットで果たす2つの機能の本質的な違いを無視しているからである。 See Brothers, Chromatic Beauty in the Late Medieval Chanson, 186; also, Brothers, “Contenance angloise and accidentals in some motets by Du Fay.” Plainsong and Medieval Music 6 (1997): 21-51. したがって、musica fictaのpulchritudoのデュファイの作品解釈は、それ以前にMachautのシャンソンで見られた構文の柔軟性から進化したように思われる。デュファイの模倣的なtext paintingは、数十年後、ジョスカンの“Absalon fili mi.”に登場した。 ブラザーズが示唆するように、musica fictaの構文上の使用をwitnessする彼の初期のシャンソンは、中世のスタイルの特徴である。88 この間、彼の後期のモテット“Ave regina celorum III”は、表現豊かな“Terzfreiheit”とともに、中世というよりもルネッサンス期の作曲のやり方の例である。89 88 Brothers, Chromatic Beauty in the Late Medieval Chanson, 199. 89 Ibid., 185-7, and 202-8. したがって、少なくとも、この論文では解決されていない疑問に対する部分的な回答を示唆することは魅力的である。 一般に、ルネサンス期の半音階主義は、中世のその前身からは異なり、音楽の構文をactivateさせるよりも、テキストの意味を模倣をする。 しかし、ルネサンス期の半音階主義のこのような定義は、むしろポイントをはずしている。 p165 Dufayのキャリアと14世紀後半から15世紀後半の過程での構文からテキスト表現的な半音階への一般的な傾向はおそらく明らかであるが、機能自体としては、最も鋭い中世とルネサンスのinflectionsへのアプローチの違いではない。 確かに、スタイル的に言えば、表現豊かな「O beate Sebastiane」の♯バージョンは、その表現豊かな臨時記号の共有された使用にもかかわらず、“Ave regina celorum III” や “Absalon fili mi”よりも、構文的な♭バージョンそして“Navré je sui”や“Quel fronte signorille,”とより多く関連している。 「Navréje sui」や「Quel fronte signorille」との間の親和性は、半音階が果たす対照的な役割にもかかわらず、半音階の機能のlocusに関係している。「Navréje sui」と「Ave regina」の違いについても同じことが言える。半音階が満たす同じ表現的目的にもかかわらず。 これまでに示したように、マショーとデュファイのシャンソンでは、構文の柔軟性を作り出す責任は、個々のinflectionにかかっている。構文の各ねじれと回転は、カデンツでの導音やそれぞれのlowering of the “third degree.”の使用または非使用停止のたびにあがってくる。 "一方、「Ave regina celorum III」の最初と3番目のトロープス部分では、1つの単一のinflectionでは、「Terzfreiheit」が全体として達成することを達成することは、できない。 “lowered third degrees”の技法は、musica fictaの構文的使用のように、局所的な効果を生み出さない。むしろ、それは、2つのそれぞれのパッセージのすべてのEとAを♭化を要求して、悲しみの全体的な影響を生み出している。 つまり、「Navréje sui」、「Quel fronte signorille」、および“O beate Sebastiane,”の2つのバージョンにおいて、デュファイにとって重要だったは、♯と♭のそれぞれがどのように音楽画に貢献をしているのか、ということである。すなわち、シャープは矢を擬態し、♭は女性の熟視の柔らかさを擬態する。♯音楽フレーズの終わりに、カデンツのドライブを追加し、フラットは、例えば、より強いカデンツの緊張を生成している。 p166 ただし、「Ave regina celorum III」では、Dufayが注目していることは、同主調への転調についてであり、またはより歴史的な言語では、C-ut調性のC-reへのmutatioである。。 そのような「転調」またはmutatioは、今度は、神の慈悲と愛する人の介入を嘆願するデュファイを描いている。しかしながら、個々ののE♭とA♭は、最初の版では、全体的な”転調”を達成するために必要なinflectionsである。 このようにして、マショーのシャンソンからデュファイの晩年の「Ave regina celorumIIIに至るまで、pulchritudoの意味合いは、構文の柔軟性から表現力豊かで模倣的なテキスト設定にシフトするだけではない。 musica ficta がそのようなpulchritudoを達成する場はまた、各局所的なinflectionから離れて移動し、全体に広がっていく。 デュファイのトロープスにおける悲しみを描くE♭とA♭の力は、もはやfa-stepsからではなく、C上のシラブルreとのaffiliation(合併)からくる。 “Absalon, fili mi.” の終わりでも、同じケースが生じている。ここでは、五度圏の♭サイドに向かうinflectionsは、終止音上に短三度を生成する以外は、音楽的または模倣的な意味をほとんどなさない—E♭ in Kriesstein 15407 and D♭ in the London manuscript—。それゆえ、終止音をutからre-stepへとシフトさせている。 それはE♭、A♭、D♭、またはG♭ではなく、全体的な音調の変化に反応している。ダビデの愛する息子の代わりに死ぬという必死の意志に対応して。 「Absalon、fili mi」の作曲家が誰であろうと、彼または彼女は、「Ave regina celorum III」に匹敵するアプローチで、♭inflectionsへの音調的および模倣的なアプローチを取った。それにもかかわらず、2つの間にはかなり大きな違いがある。 Dufayの「Ave regina celorum」の最初と3番目のトロープスでは、E♭とA♭は文字通り「inflection」である。 p167 警告なしで、ソフトb記号(♭)が発生して、個々のEとAのfrequencyとシラブルが変更される。ただし、「Absalon、fili mi」では、シフトはより緩やかに起こる。そのために、もっとも遠いstepが第83小節に生じると、83—A♭ in Kriesstein and G♭ in London—それは正当化され、期待されているようである。さらに、「Absalon、fili mi」でのスムーズな移行は、mutatioされたdeductiosの連鎖以外の何物によっても保証されない。 「Absalon、fili mi」のエンディングで(ソプラノとバスが)E♭とA♭またはD♭とG♭につながるものは、これらのステップを♭化するという作曲家の直接的な決定ではなく、deductiosのやり方である。Willaertが “Quid non ebrietas.”で行ったように。 実際、ウィラールトは、“Quid non ebrietas,”には少ない臨時記号しかつけなかった。「Absalon、fili mi」の作曲家は、deductiosに頼ることによって、音部記号なしの表記でモテットの複雑な結語を作曲したのである。 「Absalon、fili mi」がルネサンス期半音階のランドマークであると考えると、前もってやって来た多くの比較可能な作品を通した上記の旅は、 このanonymous motet がマークするものを示している。 当時、この種の作品はほとんど唯一であったために、「Absalon、fili mi」は、中世の先駆者とは異なり、「ルネッサンス期の半音階」が、テキストの意味と感情を説明するのに役立つことを示唆している。 音楽的には、♭と♯のinflectionで構成され、それは全体的な音色と聴覚効果を通じて機能し、たとえば、「同主調」への「転調」となる。 さらに、このような音色と聴覚効果は、15世紀の理論家が次第に、音程のinflectionについての議論に取り入れたものを通して、成し遂げられている。:the deductios |