| On the Theory and Practice of Chromaticism in Renaissance Music7 Zhuqing Hu |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p168 Chapter Three Romance of the Twelfth 前の2つの章は、ルネサンス音楽のchromaticismの概念と現象を中心に展開した。最初の章は、14世紀から16世紀にかけて、square b and round bの記号が、2つの異なるが互換性のない意味を伝えていることを示している。それらはグィドのシラブルのmiとfaを含み、major semitoneによる上向きと下向きのinflectionも示す。ただし、使用可能なすべてのステップを含むtonal spaceは、グィドのdeductioを移調して作成されたため、異なるステップ間でmi-fa半音が生じる。 2人のGiovannis、Giovanni SpataroとGiovanni del Lagoは、彼らの議論について意見が分かれたのは、deductioをどれだけ移調できるかであった。and thus the parameters of this tonal space. 音楽空間を “string continuum,” として捉え、スパタロ氏は、deductioは本質的にどこにでも移調できると主張している。ウィラールトは彼の「Quid non ebrietas」でそのような遠方への移調を音楽の実践に取り入れている。 さらに、最初の章では、15世紀と16世紀の理論的言説における“chromaticism”の文字どおりの意味を扱う。すなわち、古代ギリシャ人によっておそらく実践されていたchromatic genusである。 スパタロと彼の教師のRamisは、カノンがメロディックな3つのゲネラすべてを要求するいくつかの作品を作曲した。すなわち、diatonic,chromatic, and enharmonicである。これらの作品は、15世紀と16世紀に“chromaticism”と “enharmonicism”を意識的に扱った作曲家の最も初期の例であった。 p169 しかし、現代の観点から見ると、これらのtrigeneric canonsの音楽的な産生作品は、chromatic semitonesを利用しないために、半音階としては鳴らない。 スパタロが自身のモテット「Ave gratia plena」について語った議論は、彼が“chromaticism”とはどういう意味かについて考えた率直な答えを示したが、彼は、F♯を持つ3つのBマイナートライアドがchromatic momentsとして際立っている理由については説明しなかった。 第2章では、「ルネサンス」の貢献について扱っている。歴史的な論争に入るかわりに、14,5世紀に、causa pulchritudinisの意味合いは、musica fictaや臨時記号のinflectionsの使用で進歩した。 マショーとデュファイのシャンソンでは、musica fictaは構文機能を提供している。それは音の関係を明確にし、和声の勢いを作り出す。そしてフレーズの終わりを表現している。 デュファイの後期の「O Sebastiane」と「Ave Regina celorum III」ではしかし、musica fictaの使用は、テキストの意味を模倣している。 「Ave Regina celorum」では、特に、E♭とA♭を通した「同主調の短調への転調」は、デュファイが彼自身の救済のためのアンティフォンに加えたトロープス“Miserere supplicanti Dufay”の全体的な影響を描写している。 おそらくJosquinまたはLa Rueによって作曲されている可能性のある有名なモテット“Absalon, fili mi”は、悲しみと絶望を表現するために、このような「同主調の短調への転調」も利用している。 一方、デュファイの“Ave Regina celorum”の「転調」は、突然のシフトで生じるが、後の「Absalon、fili mi」では、それは、一連のdeductio mutationの流れの後に発生している。 このように、謎めいた“Absalon, fili mi”は、ルネサンスchromaticismの足跡のいくつかを例証している。すなわち、deductiosの本質的な役割と、”転調”の形式での臨時記号のinflectionsのaffectiveな使用である。 p170 From the Chromatic Semitone マーガレット・ベントは、少なくとも1つのchromatic semitoneを使用する場合にのみ、音楽のパッセージは半音階であると主張する。 この定義は、17世紀以降の調性音楽に適している。 chromaticismの主な例には、「トリスタンとイゾルデ」の序曲からのリチャード・ワーグナーの「トリスタン和声」がある(例3-1)。 アルトのDto-D♮とソプラノのA-A♯の2つのchromatic semitonesが、このパッセージのchromatic colorの原因である。 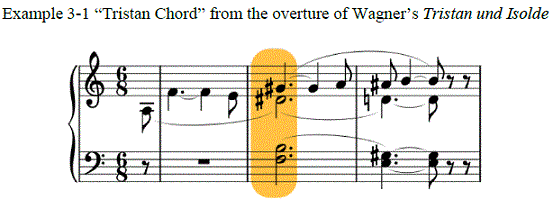 もう1つの有名な例は、ヘンリーパーセル(1659〜1695)のオペラ「ディドとエネアス」の「ディドの嘆き」である(例3-2)。Basso continuoのpassacaglia ostinatoの最初のラインは、5つの下降半音で構成され、そのうちの2つ(F♯-F♮およびE-E♭)はchromatic semitonesである。 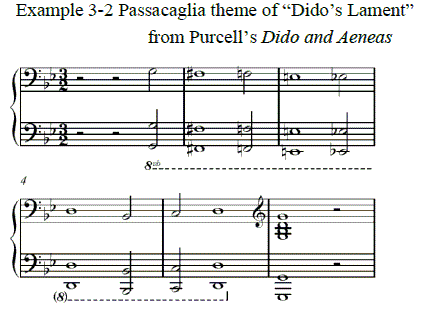 p171 しかしchromatic semitoneをchromaticismの必要かつ十分な定義と見なすと、別の疑問が続く。chromatic semitoneとは何か? または、それをnon-chromatic or diatonic semitonesと区別するものは何か? たとえば、「ディドの嘆き」のオスティナートにおいて、2つのchromatic semitonesと3つのdiatonic semitonesの違いは何か? さらに、第3小節のE♭の代わりにD♯を使用することがどのように問題になるのか? そのために、chromatic semitoneはE-E♭からD♯-にシフトするのか? 明らかに、このようなquantitativeな違いは「トリスタンコード」には当てはまらない。なぜなら、19世紀以来、ワグナーは、平均律とenharmonic equivalenceを基礎にして作曲をしていたからである。 それゆえ、ワーグナーが、例3-1第3小節で、A♯-BではなくB♭-B♮と書いていたとしても、聴覚的には異なって聞こえることはなかっただろう。 一方、17世紀の間ではまだ、平均律はより歴史的な中全音律(meantone temperament)に置き換わっていない。それゆえパーセルの場合、第3小節のE♭をD♯に置き換えたとすれば、それは、第3小節の半音がより広くなり、第3-4小節の半音はより狭くなったことだろう。 p172 17世紀よりもさらに前の16世紀は、理論家がchromatic or major semitones and diatonic or minor semitonesの区別に固執していた時代であった。それにもかかわらず、作曲慣行はすでに、平均律の中心原理やenharmonic equivalenceを想定し始めていた。 実際私は、「Quid non ebrietas」のとんでもないD-E♭♭での終止は、Willaertが平均律を支持していたかどうかは何とも言えない、と主張した。それにもかかわらず、この作品の純粋な存在は、16世紀初頭の早い段階で、平均律とenharmonic equivalenceが理論的な議論の対象であったことを証明している可能性がある。 第1章で示されているように、Spataroは、Pietro Aronとの議論で、古い理論家Aristoxenusによって説かれた平均律においてのみ、D-E♭♭のエンディングサウンドはoctaveのように響くことだろうと指摘した。3 Spataroは”より進歩した”平均律を提唱することはなかったが、彼はそのことと必然的なenharmonic equivalenceの可能性に十分に気づいていた。さらに、スパタロの教師であるRamisが、彼の論文Musica Practica(第1章を参照)において、音楽の実践に平律を使用することを提案したことを忘れてはならない。 実際、ウィラールトの「Quid non ebrietas」の10年ほどあとに平均律とenharmonic equivalenceについての談話が指摘された数十年後、マドリガル「O voi che sospirate」において、Luca Marenzio(1553-1599)は、明確に、作品の実践において、enharmonic equivalenceを統合した。この作品では、第35-40小節にて、和声的大胆さが見られる。パッセージは第35小節でのG-majorの三和音ではじまる。それは五度チェーンで♭方向を目指し、第39小節でのG♭-majorに到達する。第38-9小節には、enharmonic spellingsがある。すなわち、第38小節におけるA♭-major三和音の内部において、A♭に代わり、CantoにG♯が入り込んでいる。第38小節におけるD♭-major三和音内に、D♭に代わりQuintoにC♯が入り込んでいる。そして、第39小節のG♭-major三和音内に、G♭に代わり、F♯が入り込んでいる。 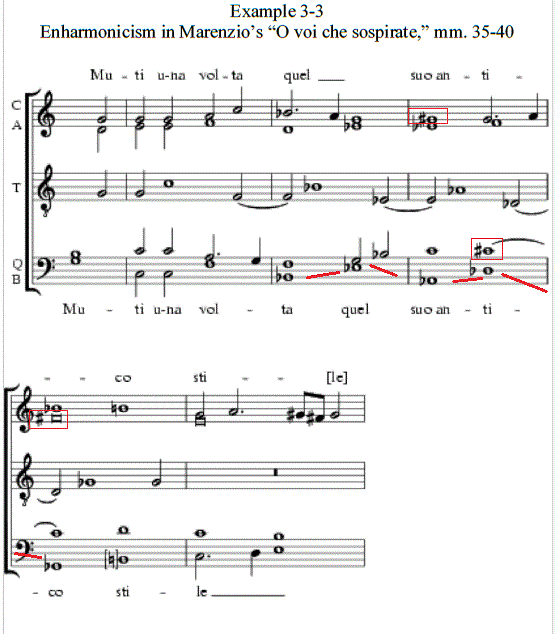 p174 「Quid non ebrietas」のD-E♭♭のように、「O voi sospirate」のenharmonic spellingsは、16世紀での平均律の可能性を示すだけで、実際に使用されていたことを証明することはできない。 ただし私は、第39小節で、マレンツィオが、Willaertの「Quid non ebrietas」 でしているように、♭スペリングを続けるようなことはしていないことに注目したい。五度チェーンでフラット領域の動きを維持するC♭トライアドの代わりに、第39小節の後半で、マレンツィオは、そのenharmonic equivalent、Bマイナートライアドを選んでいる。 もちろん、潜在的なE♭♭が、BマイナーよりもC♭マイナートライアドを好んだ可能性はある。さらに、スペリングは、マレンツィオが♭領域での冒険を続けようとはせずに、G♭メジャーから離れて、彼が第35小節で始めたところまで戻りたいことを示している。 第39小節のトライアドのスペリングは、C♭ではなく、そのenharmonic equivalentであるBとして供与されている。なぜなら、マレンツィオのtonal spaceは、2つの反対方向で無限大に拡がっていくチェーンまたはラダーとしては現れておらず、代わりにそれは、1つのラウンドの後に自然に戻る円として示される。A♭-major、D♭-major、G♭-major、およびBmajor上のenharmonic spellings(テノールでのF♯の代わりのG♭、m。39)は、五度圏の♭と♯の結合を確認している。したがって、A♭とG♯、D♭とC♯、G♭とF♯、およびC♭とBはエンハーモニックとして同等となり、第38-39小節のソノリティは、五度チェーンを形成するエンハーモニック的にハイブリッドと見なされ得る。(図3-1)。 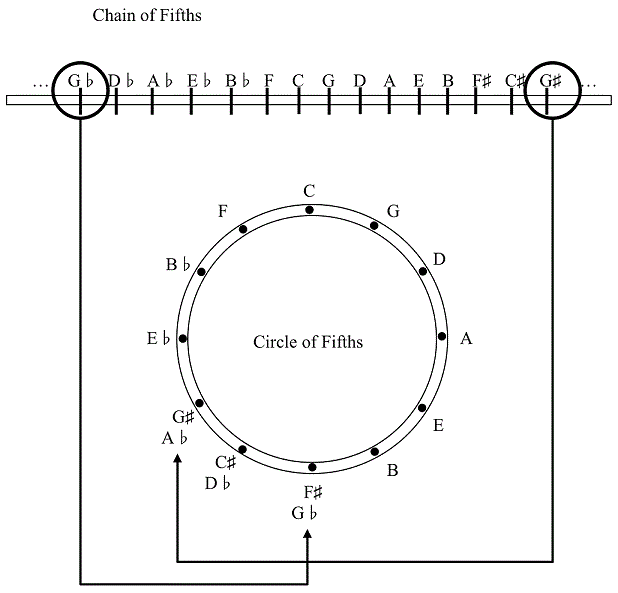 p175 このように、「Quid non ebrietas」はDとE♭♭が(平均律によって)循環的に統合される可能性があることを示唆しているが、マレンツィオの「O voi sospirate」は、明確に記譜されたinflectionsとエンハーモニックなスペリングを通して、この循環形のtonal spaceを実現することでさらに進んでいる。 “O voi sospirate”の第35-9小節でのいくつかのchromatic semitonesと対斜や、16世紀の半音階音楽でのマレンツィオの地位を考えると、平均律とenharmonic equivalenceは、ルネサンス期のchromaticismに関連がある。したがって、16世紀に音楽理論家だけが堅持していたchromatic と diatonic semitonesの聴覚の違いは、ルネサンス音楽のchromaticismの定義とは別物であることがわかる。 p176 非平均律の間の微妙な違いに加えて、G-G♯のようなchromatic semitoneとそのエンハーモニック的等価G-A♭の唯一の区別はスペリングである。スペルは表面的で些細な事あるように見えるかもしれないが、音程の幅はG-G♯とG-A♭の間の量的違いを示し、G♯とA♭の対照的なスペリングは、2つのステップとそれぞれの半音の間の定性的な違いを示している。 平均律で同等に調律した場合でも、G-G♯およびG-A♭は、chromatic semitoneおよび diatonic semitonesとして区別される。なぜなら、前者は同じdiatonic pitch collectionにおいて存在できないが、後者はできるからである。 15世紀の音楽理論と実践への調性的背景として機能するグィドの音階に関して、同じdeductioでG-A♭が生じることは可能だが、G-G♯では不可能である。 G♯とA♭の両方は、GとAの間のmi-fa半音の生成からariseしてくる。すなわち、cantus mollisのG reとA mi、cantus naturalisのG solとA la 、またはcantus durusのG utおよびA re。 第1章の理論的な議論と一致して、2つのステップの間にmi-faの半音を実現するには2つの方法がある。 まず第1に、周波数を変えずにAでfaを歌う場合、chromatic semitoneでGをG♯に上げてmiとして歌う必要がある。 つまり、新しいG♯miは、新しいE-ut deductioの元のG re、sol、またはutを、GとAのステップ間でmi-faに置き換える(図3-2)。 第2に、周波数を変えずにGでmiを歌う場合、chromatic semitoneによってAをA♭に下げ、faとして歌う必要がある。同様に、新しいA♭は元のA mi、la、またはreをGとAのステップ間で新しいE♭-ut deductioにおいてmi-faに置き換える(図3-3)。 p177 G-G♯ したがって、G-G♯やA♭-A♮などのchromatic semitones は2つのdeductiosが並置(またはひとつおいて並置;G-G♯)される必要があるが、G-A♭やG♯-Aなどのdiatonic semitones はそれぞれの1つだけのdeductioを持っている(同じdeductioに収まっている)。 In addition, the two deductios juxtaposed in each chromatic semitone are at least two and can be as far as six deductios away from each other (Figure 3-4). G♯-C、減四度、そしてE♭-G♯のような増三度といった非和声的音程においても、同じことが観察できる。なぜならこれらの音程は、 同じdeductios 内や隣接したdeductiosにおいてさえ、存在できないからである。 chromatic semitoneの本質は、それゆえ、2つの互換性のないピッチクラスの隣接が、その正確な音程幅よりも重要性となる。その互換性のなさは、1つのdeductioまたは2つの隣接したdeductiosで対応されるからである。 Defining the Diatonic Pitch Collection それでも、“chromaticism” を互換性のないピッチクラスとそのdeductios の並置として定義することは、まだ広義すぎるように見えるかもしれない。“Ave regina celorum III,”においては、完全にずばりのchromatic semitonesはなく、デュファイは本質的に、第1,3トロープスの初めのB♭ and E♭(訳注;デュファイの感情を表すためにあえて♭化したもの)を、アンティフォンの残りの部分のB♮ and E♮ とを同等に扱っている。 同様に、“Absalon, fili mi,”においても、最後の♭化した三度と六度は、このモテットの前の部分でのinflectionされていない三度と六度と同等に扱われている。 だが、Spataroのmotet “Ave gratia plena,”には謎がある。彼は、diatonic, chromatic, and enharmonic generaを同時にどのように使うのかをそこで示すように作曲したのである。 おそらくSpataroは、第11,17小節のテノール、第21小節のCantusのF♯を正確に半音として示している。なぜなら、モテットのその他のところでは、F♮と並置されているからである(Example 3-4)。だがなぜか? 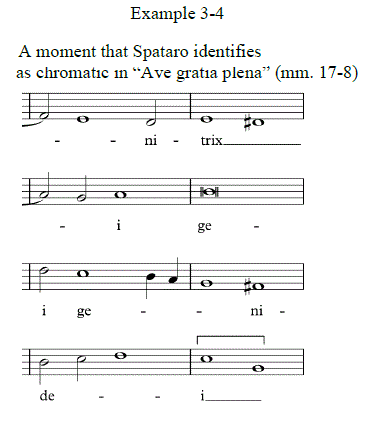 p180 これらの3つのF♯の特殊性が、テノールの最後のF♯や第32小節のバスのB♭とは異なったものとしたのは、誰かが作品の残りのF♮ and B♮と並置させたのか? Spataroは単純に、彼のモテットの中で、半音階ステップの例をリスト化するのを欲しなかったのか? もしも“chromaticism”を互換性のないピッチクラスの並置として定義することがスパタロの「Ave gratia plena」と作曲家自身の分析を完全に説明できないならば、Spataroが特に半音階的と扱った3つのF♯とモテットのその他のinfection stepの間を区別するために他に何が必要となるのか? “Ave gratia plena,”のスパロタのchromaticismに関する混乱したコメントを理解するためには、chromaticismを終わりとしてではなく、ダイナミックとして扱う方がより生産的である。 “The Study of Chromaticism,”で、ウィリアムJ.ミッチェルは、diatonicismは「秩序化力」であり、chromaticismは「拡散する力」であると示唆していry。6 6 William J. Mitchell, “The Study of Chromaticism,” Journal of Music Theory 6 (1962): 彼は、diatonicismの秩序化力は、全音階スケールと全音階ステップの識別可能な和声機能との非対称性から生じている、と論じる。一方、chromaticismの拡散する力は、平均律における半音階スケールと12の半音階ステップの識別不能な和声機能との完全な対称性から生じている。 ミッチェルは2つの力を対立的であるとして提示しているが、15世紀と16世紀のcontextにおいて、diatonicism and chromaticism明らかに等しくない。diatonicism or chromaticism,を定義する正確なやり方はまだないが、ルネッサンス音楽が全音階優位であったことや、Marenzioの“O voi sospirate”の第35-9小節での時折の半音階的パッセージでさえ、全音階的背景で機能していることは、疑いない。 このように、ルネサンス音楽では、拡散的な色度は、順序付けられたダイアトニズムに反応するものと見なすことができ、拡散的なchromaticismは、秩序的なdiatonicismに対抗して見られ、その拡散は、元のdiatonic collectionのそれらとは相容れないピッチクラスを導入することによって生じる。 p181 疑問はすなわち、拡散とは何を構成するのか、または新しい、互換性のないピッチクラスとして何をカウントするのか? 「新しい」概念を理解するために、私は最初に、「古い」または新しく導入されたピッチクラスが反応する全音階システムを調べよう。 第1章では、ルネサンス音楽での全音階のシステムを7つの重複するGuidonian deductiosとして提示した。 Mengozziは、deductiosが、歌うことや作曲において、通常の音楽的慣行での役割がほとんどなかった、と主張するが、7つのdeductio音階は、15世紀と16世紀の理論家たちが、全音階的空間について説明した支配的な構造であった。 この点で、Ramisは例外である(p49)。 第1章で説明したように、Ramisは,移調可能な音楽ユニット自体の考えよりも、グィドのdeductioの“sixthness”に対して反対した。そうでなければ彼は、Guidonian deductioへの代替として彼のpsalliturを提案することはなかったことだろう。 確かに、deductiosで構築された全音階的スペースは、まったく “sixthness” とは関係ない。 図3-5は、7つのdeductiosをオクターブの置き換えを通して、3つに減らしているものである。cantus naturalis on C ut in the middle, cantus mollis beginning on F ut on the lower side, and cantus durus beginning on G ut on the upper side. したがって、7つのdeductiosの全音階スペースは、実際には、cantus naturalis deductio supplemented with B♮ from cantus durus and B♭ from cantus mollisのステップの6つのピッチクラスとなる。 確かに、B♮からB♭への移行は、隣接していない2つのdeductiosを含んでいる。B♮とB♭の共存は、「naturalな」またはcantus durus の「調号」で設定された作品では、遍在ではないにしても非常に一般的であった。 p182 次に、7つのdeductios埋め込まれた8ピッチの全音コレクションが、スパタロが「“string continuum”ストリング連続体」(それが基づいているdeductiosのように)と呼ぶものと同じように移調できることが重要である。 cantus naturalisの全音階システムで共存する2つのBに類似して、作品は、1つの♭あるいは、E♮ とE♭でしばしば特徴づけられた15-6世紀からのcantus mollis “key”での設定となっている。このようにして、1つの♭の調号もまた、8つのピッチクラスで構成される調性スペースを意味している。それらのうちの6つはcantus mollis deductioから来ており、2つの追加のピッチのうち、C-ut deductioからのE♮は完全五度上に、B♭-ut deductioからのE♭は完全五度下に来る(図3-6)。 移調可能であるため、8ピッチの全音階スペースは、以下のように説明される。すなわちこれは、これまで主なdeductioと呼ばれた特定のdeductioの6番目のピッチクラスで構成され、deductioのmiのピッチクラスは五度上であり、deductioのfaのピッチクラスは、五度下となる。 p183 deductioまたは本質的にそのmi-faのdiatonic semitoneを「ストリング連続体」“string continuum”のさまざまな場所に置き換えると、さまざまな全音階的ピッチコレクションが生じる。スパタロがアロンへの手紙で示しているように、F♭でfaを歌い、E♭でmiを歌うと、C♭-ut deductioが得られる。 したがって、結果として生じる全音階スペースは、deductioの6つのピッチクラスで構成される。 C♭からA♭、およびG♭-ut deductioからのB♭、そしてF♭-utからのBである。 このような全音的ピッチコレクションにおけるdeductioの最重要事項を考慮して、残りの論文では、私は、deductioのutステップから生じる8ピッチコレクションを指定して、deductioのutステップを使用するだろう。 したがって、F♭faとE♭miのコレクションはC♭コレクションであり、A faとG♯miのコレクションはEコレクションとなる。 ルネサンス音楽の全音階スペースまたはピッチコレクションが、8つのピッチクラスのみから成るのであれば、currentコレクション以外のピッチクラスは,新しいコレクションの導入を意味するのか? 答えは否定的であることが判明し、15世紀と16世紀の旋法理論への短い脱線は、その理由を説明するものである。7 p184 旋法理論は、もともとは、プレインチャント、特にantiphons and responsoriesを分類するシステムとして生まれた。 システムは当初、4つのモーダルファイナルをcantus durusまたは「自然キー」:D(ドリアン)、E(フリジアン)、F(リジアン)、およびG(ミクソリディアン)を認めていた。各終止音は、音域に基づいて2つの旋法で共有されます。(図3-8)。(略) p200 Drawing the Diatonic Boundaries 結果として、deductioにおける6つのグィドのシラブルと6つの旋法の終止の集まりは、特にルネッサンス音楽への11ピッチ全音階コレクションを生み出した。11ピッチのコレクションは、スパタロの「Ave gratia plena」と、この曲においてSpataroが直接的または間接的なコメントをしたその第11,17,21小節での特殊な例でのrefreshing viewを提供している。 第11,17,21小節での3つのF♯に加えて、Spataroは、第17小節でのB-major三和音とそのD♯についてAronへの手紙で長々と論議している。 私の作品でD♯が見つかります。B上の長三度を示していますが、これはモノコードではほとんど見られない。 モノコードにない場合は使用すべきではないと言う人もいます。 私の回答は、芸術は自然を模倣すべきであり、悪を模倣すべきではないということです(“L’arte serve alla natura, et non e contra.” (“Art serves nature, and not vice versa.”) それが演奏できないのであれば、それは芸術のせいではなく、不完全な楽器のせいです。 リュートはそれを演奏することができましたが、声はより良いことでしょう。 そのような音程の区分は、熟練した歌手にとってはより身近なものです19。 上記の引用は、第17小節のCantusのD♯が、16世紀の音楽家の間でいかに稀であり、問題であったかを示している。しかし、スパタロのD♯の正当性への長々とした弁護は、不必要に思えるかもしれない。 15世紀初頭以来、D♯は常に16ステップ音階の一部であり、ステップすべてにmiと♯を持つことによって構築されている。ProsdocimusからHothbyとRamisまでの理論家たちは、誰もこれを問題にしなかった。実際、Giovanni del Lagoでさえ、D上に♯を置くことに反対しなかったであろうし、ステップは、cantus mollis, naturalis, あるいはdurus deductiosにおけるmiを持たなかったBやEとは異なるのである。 p201 なぜスパタロは、彼が(3つのメロディゲネラ(diatonic, chromatic, and enharmonic)のすべてをどのように作曲したかを示している)“Ave gratia plena,” で使用するD♯に反対する人がいるのではないかと疑うのであろうか? モテットの「調号」によれば、作品が徹底的に全音的であったならば、D♯は「Ave gratia plena」ではまったく発生していないはずである。 「調号」における♯と♭の欠如は、作品がC diatonic collectionを示す。 これは、Spataroには、11の全音階ピッチクラスがこのモテットにおいて役立つ、ということを意味する。すなわち、C、C♯、D、E、F、F♯、G、G♯、A、B、B♭である。 重要なのは、このコレクションと他の11ピッチ全音階コレクションは、半音階的スケールでの1つのステップの不足があることである。DとEの間の全音を分割するステップが欠落しているのである。 スパタロのモテットは、このステップをCantusのD♯として特徴付けている。このようにして、D♯は、「調号」とそれが示すCdiatonic collectionによって指示された11のピッチクラスの全音階境界に侵入していったのである。 第17小節のこのD♯の機能は、スパタロがこの見慣れないピッチクラスを、このモテットを支配するC全音階コレクションに導入した理由をはっきりさせる。 それ(第17小節のこのD♯)は、第17-8小節でのE上のカデンツにおいて、下側の導音として働いている。Cコレクションでは、E miの上のカデンツは、つねに、D reからE miまでの全音ステップ上昇の進行を特徴とするcantizansと、上からの導音(F fa→E mi)の半音ステップ降下を特徴とするtenorizansから常に構成されている。 5分12秒~ 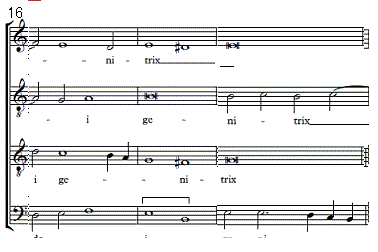 CantusとBassusの第16-17小節のふるまいはその完全な例である。しかし第 17〜18小節では、導音は、F faとしてのtenorizansではなく、D♯としてのcantizansにおいて表示される。一方、tenorizansでは、上からの導音FがF♯にシャープ化されている。 p202 したがって、第17-8小節でのEカデンツのcantizansとtenorizansは、C全音階コレクションの通常のE-miカデンツのそれらとは、異なるものとなる。ここでは、Eカデンツは、(cantizansもまた半音上昇し、tenorizansが全音上昇する)CコレクションのDカデンツに相当する、reカデンツのようになる。 ただし、Eがdeductioのreステップになるためには、その下の隣が全音ステップ下-ut-であり、その上の隣が全音ステップ上-mi(♯)である必要がある。この要求を満たすのは、ただひとつのdeductioのみ、すなわち、D-utである。それにもかかわらず、図3-19に示すように、D-ut deductioは、G、D、Aの3つの全音階コレクションに属している。 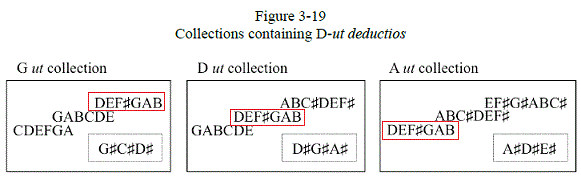 このように、第17-8小節でのE-re cadenceのD♯は、モテットの支配的な全音階コレクションを、Cから少なくとも(五度圏の♯方向への次のコレクションである)Gへと変化させている。このD♯の調性的結果は、その仲間である、テノールの第17小節のtenorizansでのF♯に光を当てている。 Spataroは第11、17、および21小節の3つの♯を llichanos meson chromaticaと呼んでいる。 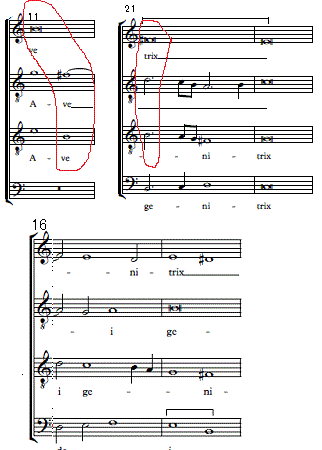 中間子クロマティカ。 レビューのために、Greater Perfect Systemでは、lichanos中間子は3番目です 中間子の四極子の昇順で、ピッチが 内容は常にEです。中間子の四弦は、昇順の2番目の四弦です。 システム全体の順序。 それはハイパトンで始まるハイパトン四弦の上にある hypatonまたはB(図3-20、第1章も参照) ケイデンシャルファイナルEの上 に |