| The Two-Part
Conductus: Morphology, Dating and Authorship1 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | その2(p25〜)へ |
| The Two-Part Conductus: Morphology, Dating and Authorship1 by Jacopo Mazzeo その1(p1〜18) Introduction: The Conductus Between the twelfth and the thirteenth century Western Europe experienced for the first time the birth of coherent extensive repertories of polyphonic music. These repertoires have long been considered to have developed in Paris, where the newly established University gave rise to a remarkable social and cultural environment. The three main repertoires generated from such a cultural ferment are: organum, conductus, and motet. 12世紀から13世紀の間に、西ヨーロッパは多声音楽の一貫した広範なレパートリーの誕生を初めて経験した。 これらのレパートリーは、新しく設立された大学が著しい社会文化的環境をもたらしたパリで長く発展したと考えられている。 そのような文化的発酵から生まれた3つの主なレパートリーは、オルガヌム、コンドゥクトゥス、モテットである。 The conductus, when compared to its contemporary cognate genres - organum and motet - has not benefited from the same substantial scholarly attention lavished on the other two. Yet its significance for the development of Western Music is critical. Theconductus was cultivated between c.1160 and 1250, with Latin texts and monophonic or polyphonic music ? up to four parts, yet mostly in two. Unlike the organum and the motet, it does not normally exploit any pre-existing musical or poetic material (although some exceptions will be discussed in this thesis). This makes the polyphonic portion of the conductus corpus the first coherent, newly composed, repertory for more than one voice. This thesis focuses on the conducti for two voices; it aims to explore the authorial and historical context in which it was created, to analyse and categorise the interaction between its syllabic and melismatic sections, and to describe its development over its life span. コンドゥクトゥスは同時代の同じようなジャンルであるオルガンやモテットと比べると、実質的な学術的な注目からの恩恵を受けていないが、、西洋音楽の発展にとってのその意義は非常に重要である。 コンドゥクトゥスは、ラテン語のテキストとモノフォニックまたはポリフォニックの音楽(最大4つのパート、さらにはほとんどが2つのパート)で、1160年から1250年の間で発展した。 オルガヌムやモテットとは異なり、通常は既存の音楽や詩的な素材を利用していない(いくつかの例外はあるが、それはこの論文で議論される)。 これにより、 コンドゥクトゥスの内容は、複数の声部のための最初の一貫性のある新しく作曲されたレパートリーである。 この論文は、2声部のための コンドゥクトゥスに焦点を当てている。 それは著者の探求を目指している。それが作成された歴史的背景、音節と旋律のセクション間の相互作用やライフスパンの発展を分析し分類している。 Defining and Exploring the Genre The conductus flourished during a period of great artistic vitality in Paris, where music played a major role in a broader cultural achievement. The Notre-Dame school contributed significantly to the development of organum, the first attested polyphonic genre. Written evidence of engagement with polyphonic music in Europe comes from theoretical sources compiled as early as the ninth century; these reveal that organum was already established as a performative practice.1 1 The early treatises Musica enchiriadis and Scolica enchiriadis feature organa in the so-called Dasian notation. Cfr. “Musica et Scolica enchiriadis: les sources,” http://gregorianchant. ning.com/group/lesmanuscritsduweb/page/musica-et-scolica-enchiriadis-les-sources; Anonymous, Musica enchiriadis and Scolica enchiriadis, Raymond Erickson and Claude V.Palisca ed. (New Haven: Yale University Press, 1995). パリでは偉大な芸術的活力の時代にコンドゥクトゥスが栄え、音楽は幅広い文化的成果の中で重要な役割を果たした。 ノートル・ダム楽派は、最初に実現したポリフォニックのジャンルであるオルガヌムの発展に大きく貢献した。 ヨーロッパのポリフォニック音楽との関わり合いの証拠は、早くも9世紀にまとめられた理論的資料にある。 これらは、パフォーマンスの実践としてオルガヌムが既に確立されていることを明らかにする。 The organum discussed in these treatises is a polyphonic elaboration of responsorial chants for the Mass and the Office. Towards the mid-twelfth century the genre was subject to re-elaborations and experimentations at the school of Notre Dame. These organa were collected in the Magnus liber organi de graduale et de antiphonario pro servitio divino multiplicando, an anthology of polyphonic settings of plainchant. The Magnus Liber is today considered the most important collection of music from the High Middle Ages.2 Its composition was credited to Notre Dame’s master Leoninus (fl.1150s-c.1201) by the later thirteenth-century theorist Anonymous IV, and indeed was originally designed for the use at the Parisian Cathedral.3 これらの論文で議論されたオルガヌムは、ミサや聖務日課のための応唱的チャントのポリフォニックな精巧性である。 12世紀半ばにかけて、このジャンルはノートルダム楽派で再精緻化と実験の場であった。 これらのオルガヌムは、多声作品のアンソロジーであるMagnus liber organi de graduale et de antiphonario pro servitio divino multiplicandoの中に収められていた。Magnus Liberは、今日、中世からの最も重要な音楽のコレクションと考えられている2。その作品は、後で13世紀の理論家Anonymous IVによってノートルダムの巨匠Leoninus(fl.1150s-c.1201)作とされていた。 もともとそれは、パリの大聖堂での使用のために設計されていたものである.3 The Magnus Liber was subsequently revised and updated by Perotinus (fl. c.1200), successor of Leoninus at Notre Dame. Several works are credited to Perotinus in contemporary sources; among them also figure several conducti, for instance Salvatoris hodie.4 Since the conductus was associated with Perotinus and his activity in revising the repertoire, it appears as a “new” genre − compared to organum − at its peak towards the end of the twelfth century and the beginning of the thirteenth. Magnus Liberはその後、ノートルダムのLeoninusの後継者であるPerotinus(fl. c.1200)によって改訂され、更新された。 Perotinusには同時代の資料でいくつかの作品が、特定されている。 それらのうちのものとして、 たとえばコンドゥクトゥスSalvatoris hodieがある。コンドゥクトゥスはペロタンとレパートリーを改訂する彼の活動と関連していたので、それは12世紀の終わりおよび13世紀の終わりに向かってのピーク時に、オルガヌムと比較して「新しい」ジャンルとして現れる。 The majority of the songs making up this repertoire are monodic, yet the number of polyphonic conducti is still relatively large. The very coexistence of the “old” monody and the “new” polyphony in one single genre makes the conductus a turning point in the history of Western music. Polyphonic conductus propelled Western civilization towards its musical future: newly composed polyphonic material and the correlated changed understanding of original authorship. Monody is the common ground that such an innovative genre shares with its musical past. このレパートリーを構成する曲の大半は単声であるが、多声コンドゥクトゥスの数は比較的多い。 「古い」単声と「新しい」多声が一つのジャンルで共存しているため、コンドゥクトゥスは西洋音楽の歴史の転換点になっている。 多声コンドゥクトゥスは、その音楽的未来に向けて西洋文明を推進した。単声作品は、そのような革新的なジャンルが音楽的過去と共有する共通の根拠である。 Despite the relevance of this repertoire within the context of Western music,scholars have not given yet a definitive hypothesis for the etymology of the term. Generally, the conductus is associated with the Latin word conducere (to escort, to lead), and thought to indicate a piece performed while carrying the lectionary to the book stand.5 Recent studies have not argued this hypothesis, nor proposed alternative etymologies for the word.6 As Gillingham has pointed out .Some confusion might have existed at the time of the production of the genre itself; in medieval sources the conductus “is substituted almost interchangeably for words such as ‘versus,’ ‘processional,’ and ‘sequence’”.7 このレパートリーが西洋音楽の文脈の中で妥当であるにもかかわらず、学者はこの用語の語源についての決定的仮説をまだ与えていない。 一般的に、コンドゥクトゥスはラテン語のconducereと関連しており、日課表をブックスタンドに運んでいる間に演奏された作品を示すと考えられているが、最近の研究はこの仮説を論じていない。 Gillinghamが指摘しているように、ジャンルそのものを産生するときには、ある混乱が存在していた可能性がある。 中世の資料では、「コンドゥクトゥス」は、「versus」、「プロセッション」、「セクエンツィア」のような言葉と同等に扱われている。 In this thesis the second-declension “conducti” will be used to indicate the plural, instead of the fourth-declension conductus. This solution is now extensively used in musicological literature, allowing for an easier distinction between singular and plural.8 この論文では、第2変化「conducti」は、第4変化conductusの代わりに複数形を示すために使用される。 この解決策は現在、音楽学文献に広く使用されており、単数形と複数形の区別を容易にすることができる。 As the etymology of the word remains dubious, so does the broader context in which the conductus was created and performed. The fact that no single concept can describe the function of this repertoire and its particular heterogeneous character certainly does not help in this sense. In fact, conductus poems may concern a variety of topics, from the liturgical and para-liturgical to the moralising or the celebratory; songs may also comment on historical events. Festivities (e.g. Christmas, Circumcision, Easter, etc.) and dedications to the Virgin Mary -or to specific saints - are only a few of the themes that may be found in religious conducti. 言葉の語源が疑わしいものとして残っているように、コンドゥクトゥスが創造され実行された広範な内容も疑わしさが残っている。 単一の概念がこのレパートリー(コンドゥクトゥス)とその特定の異種性の機能を記述することはできないという事実は、確かにこの意味では助けにならない。 実際、Conductusの詩は、様々な典礼や典礼的なものから道徳や祝福に至るまでのトピックを扱っている。 歌はまた、歴史的出来事にコメントするであろう。 聖母マリア(または特定の聖人)への祭典(クリスマス、祝宴、復活祭など)や奉献は、宗教上の倫理に見られるテーマのほんの一部なのである。 In analytical terms, the main characteristic of the polyphonic conductus is the juxtaposition of two discrete sections, the first being syllabic and called cum littera (i.e.music “with letters”); the second, melismatic, called sine littera (un-texted melisma) or cauda (tail). Such flourished sections mostly occur either at the beginning or at the end of the song. Their relation has been generally considered as rather exclusive. This thesis will be analysing in depth the two sections, cum and sine littera, to study their musical content and show that their interaction is more flexible than it has been claimed so far. 分析的用語においては、多声コンドゥクトゥスの主な特徴は、2つの別々のセクションの並置であり、最初はシラビックであり、cum litteraと呼ばれる(すなわち、”歌詞つき”); 2番目はメリスマ的であり、sine littera(un-texted melisma)またはcaudaと呼ばれる。 このような豊かなセクションは、大部分が開始時または終了時に発生する。こうした関係は、一般にはむしろ排他的とみなされてきた。 この論文では、2つのセクション、cum litteraとsine litteraを深く分析して、こうした音楽内容を研究する。。これまでに要求されてきたよりも柔軟性があることを示している。 Musical, Historical, and Theoretical Sources The two-voice conductus is recorded in a wealth of sources of various geographical and chronological provenances.9 The main bulk ? 130 works ? is found in the seventh fascicle of the manuscript Florence, Biblioteca Mediceo Laurenziana, Pluteo 29.1 (hereafter F), first analysed by Leopold Delisle in the late nineteenth century.10 Delisle inferred the manuscript’s French origins by script and illumination style, yet the dating he proposes, between 1285 and 1314, was much later than today’s accepted date. Indeed, his dating has been successively questioned several times by scholars, who first proposed the mid-thirteenth century,11 but based on study of the illumination eventually agreed on the 1240s.12 2声のコンドゥクトゥスは、様々な地理的および年代的な出典の豊富な資料に記録されている。「フィレンツェ、Biblioteca Mediceo Laurenziana、Pluteo 29.1(以下F)」の7番目の冊子は、19世紀後半のLeopold Delisleによって最初に分析された.10 Delisleはフランス語起源の写本とイルミネーションスタイルで写本の作成期を割り出したが、 1285年〜1314年という彼が提案したその作成期は、今日の受け入れられているデータよりずっと遅かった。 確かに、彼のデータは、数度にわたって、13世紀半ば説を唱えた学者らから疑問を持たれ続けていたが、最終的には1240年代とのことで落ち着いた。 Together with F, three other manuscripts make up the main sources for the Notre-Dame conductus (summarised in Table 1). These are Wolfenbuttel, Herzog-Augus-Bibliothek, Guelf. 628 Helmstadt (hereafter W1), Wolfenbuttel, Herzog-August-Bibliothek, Guelf. 1099 Helmstadt (hereafter W2), and Madrid, Biblioteca Nacional 20486 (hereafter Ma).13 Most of the conducti found in these codices are also recorded in F, yet cases of unica are not uncommon.14 F写本とともに、他の3つの写本が 、Notre-Dameのコンドゥクトゥスに対する主要な資料となっている。これらの写本中にあるほとんどのコンドゥクトゥスはF写本中にも見られるが、unicaのケースは珍しいことではない。 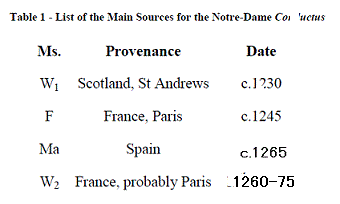 Due to its remarkable aesthetic value and to the abundance of information delivered, F is considered the “central source” for Notre-Dame polyphony. Yet, this does not mean that other geographical areas were peripheral to the production and fruition of this repertoire. Recent studies on the date and provenance of W1 have brought to scholarly attention the significance of this noteworthy source, suggesting its insular origins opposed to a Parisian one.15 Much debated was its date of compilation, firstly proposed as late as the fourteenth century, then moved back to the previous century.16 その顕著な美的価値と豊富な情報提供のために、F写本はノートルダムの多声音楽の「中心的な資料」と考えられている。 しかし、これは他の地理的領域がこのレパートリーの産生と果実の周辺域であったことを意味するものではない。 W1写本の作成年と地域に関する最近の研究は、この注目すべき資料の重要性を学術的に注目し、パリ派の起源とは反対の、スコットランド起源を示唆している15。その編纂年についてはいろいろ論議があったが、当初は14世紀後半と遅かったが、次第に 前の世紀起源へと戻っていった。 A 1976 article by Edward Roesner addresses this issue but leaves most of the key questions unanswered.17 Mark Everist, who confirms W1’s Scottish origins, proposes a date of compilation as early as the 1230s, a period when “Guillaume Mauvoisin, a Frenchman appointed to be Bishop of St Andrews in 1202, was a prelate with well-documented French sympathies”.18 Edward Roesnerの1976年の記事はこの問題に取り組んでいるが、主要な質問のほとんどは答えられていない。W1写本のスコットランドの起源を確認しているMark Everistは、この写本が1230年代の早い時期に編纂されたと提案している。それは、1202年にセント・アンドリュースの司教となったフランス人であるGuillaume Mauvoisin が修道院長だった時であった。 The manuscript W2 is currently held at the same institution as W1, yet it shares with its Scottish cognate neither the date nor the place of compilation.19 It was copied around Paris, within a span of time between 1260 and 1275.20 Ma is the last of the codices mentioned above and must also be considered a principal source for the Notre Dame school.21 Some songs recorded there are unica or find concordances only with other Spanish manuscripts.22 The codex was thought be compiled in Toledo, but it is now believed that it was produced in some Castilian scriptorium other than Toledo, around 1265.23 W2写本は、現在W1写本と同じ施設で管理されているが、スコットランド人の同族と日付や編集場所を共有していない.19 それは、1260年から1275年までの間に、パリのあたりで作られた。Maは、上記のコーディスの最後であり、ノートルダム教会の主要な源泉ともみなされなければなりません.21そこに記録されている歌の中には、ユニカがあるものもあれば、他のスペインの写本 コーデックスはトレドで編集されたと考えられていたが、約1265頃に、トレド以外のいくつかのカスティーリャ書記館で生産されたと信じられている。.23 A number of other sources of different chronological and geographical origins record testimonies of the two-voice conductus repertoire, beside the four principal manuscripts mentioned above (F, W1, W2 and Ma). A distinction between “central” and “peripheral” sources has been used in scholarly studies to categorise them, though there is little literature on the precise distinction between the two concepts.24 In this thesis the adjective “central” will not indicate a specific geographical place, but rather the repertoire in the version delivered by the main sources, in contrast to “peripheral” sources that mirror instead local traditions. It is indeed possible to frame certain geographical areas characterised by local musical customs, such as England, Gascony, Paris, as well as Northern Spain and the area around Engelberg in today’s Switzerland. This work privileges a focus on the main sources, although all extant sources that record two-voice conductus are also included in the discussion. 上記の4つの主要な写本(F、W1、W2およびMa)に加えて、時系列および地理的な起源の異なる数多くの他の資料が、2声コンドゥクトゥスレパートリーを記録している。「中央」と「周辺」の区別は学術研究では用いられているが、 2つの概念の正確な区別に関する文献はほとんどない。「中心」とは特に地理的な特殊な場所を指すわけでもなく、むしろ、地方の伝統を反映する「周辺」資料とは対照的に、主要な資料によって提供されるバージョンのレパートリーを含んでいる。確かに、今日のスイスでは、イングランド、ガーデニル、パリ、北スペイン、エンゲルベルク周辺地域などの地方の音楽習慣によって特徴付けられる地理的エリアを形作ることは可能である。この論文は、主要なソースに焦点を当てているが、2声コンドゥクトゥスを記録している現存するすべての資料もディスカッションに含まれている。 Over the last decades some remarkable fragments have been added to the abovementioned major sources in the study of Notre Dame polyphony.25 One of these fragmentary codices is the manuscript Cambridge, Jesus College QB 1 (hereafter GBCjec QB 1), which contains seventeen conducti in two or three voices.26 One of its twopart songs, Novi sideris lumen resplenduit, is a unicum. Although relatively late ー the end of the thirteenth century - GB-Cjec QB 1 embodies a remarkable testimony for medieval polyphony in Britain. The manuscript consists of four flyleaves - recording three-part conductus and motets - and 33 strips, where we find the two-part conducti relevant to this research. The first reconstruction attempted by Bukofzer was included in the RISM, but results proved inaccurate.27 This thesis will refer to GB-Cjec QB 1 according to the more recent foliation by Daniel Leech-Wilkinson.28 過去数十年にわたり、ノートルダム多声音楽の研究では、上記の主要な資料にの他に、いくつかの注目すべき断片が加えらた。こうした断片的な写本の1つは、ケンブリッジ、イエズス・カレッジQB 1(以下、GBCjec QB 1)の写本で、2-3声の17のコンドゥクトゥスを含んでいる。 2つの曲のうちの1つ、Novi sideris lumen resplenduitはunicaである。 比較的遅れて - 13世紀の終わり - 、GB-Cjec QB 1写本は、英国の中世の多声音楽の注目すべき証言者である。 写本は、3声コンドゥクトゥスとモテットを記録した4葉と、33部の切片で構成されている。そこには2声コンドゥクトゥスもこの研究に関連している。 Bukofzerが試みた最初の復元はRISM(repertoire international des sources musicales,1960)に含まれていたが、結果は不正確であることが判明した。.この論文は、最近のDaniel Leech-Wilkinsonによるfoliationに従って、GB-Cjec QB 1に言及している。 Mark Everist highlighted the relevance of two additional fragmentary sources for the study of the repertoire: Metz, Bibliotheque-Mediatheque du Pontiffroy, reserve precieux, 732bis/20 (hereafter F-ME 732bis/20) and Cambridge, Sidney Sussex College 117 (hereafter GB-Csss MS 117).29 Mark Everistは、レパートリーの研究のための2つの追加さあれた断片的な資料の関連性を強調した:Metz、Bibliotheque-Mediathequedu Pontiffroy、reserveprecieux、732bis / 20(以下、F-ME 732bis / 20)、Cambridge、Sidney Sussex College 117 -Css MS 117). A later but significant source for the conductus is the so-called “St Victor” manuscript (hereafter F-Pn lat. 15139).30 The provenance of the manuscript is uncertain, but the catalogue of the Parisian Abbey of St Victor shows it was housed there in 1513.31 F-Pn lat. 15139 contains music for monodic, two- and three-voice conducti and three theoretical treatises, two in Latin and one in French, written in the margins of folios 269r-275r. Its music was originally catalogued by Ludwig in his Repertorium, while the three treatises were edited by Coussemaker.32 より後のものであるが、コンドゥクトゥスのための重要な資料は、いわゆる「St Victor」写本(以下、F-Pn lat。15139)である。写本の出所は不明であるが、St Victorのパリ修道院のカタログは、 そこには1513. F-Pn lat写本が収容されていることを示している。 15139には、単声、2声、3声のコンドゥクトゥスと理論的な3つの論文(ラテン語で2曲、フランス語で1曲)が、Folio 269r-275rの余白に書かれている。 その音楽はもともとルードヴィヒのレパートリーでカタログ化されていたが、3つの論文はCoussemakerによって編集された。 Sixteen polyphonic conducti are recorded in the manuscript, ten of which are in two voices. All three treatises concern musical rules. The former focusses on two-part counterpoint, and can be considered the earliest treatise on music in the vernacular French; the works in Latin discuss counterpoint on a more generic scale and illustrate rules of notation and modality. Most of the manuscript was copied in the last half of the thirteenth century. However, other elements such as the writing in the margins -including the treatises - and the texts of the motets next to the clausulae, are thought to have been copied either at the very end of the 1200s or at the beginning of the following century.33 Following Meyer’s studies, which hypothesised the year 1244 as a date for the composition of some conducti, Rokseth proposed the 1248 for the remaining songs.34 Falk successively proposed a much earlier date - the first years of the thirteenth century -for the composition of some conducti of F-Pn lat. 15139 and for the compilation of the codex itself. Falk also suggested that the original bulk of F-Pn lat. 15139 could be even earlier than F and the whole repertory of Notre Dame.35 写本には16の多声コンドゥクトゥスが記録されており、そのうち10は2声である。 3つの論文はすべて音楽のルールに関係しています。前者は2声対位法に焦点を当てており、フランス語での最初期の論文と見なすことができます。ラテン語の作品は、より一般的なスケールで対位法を論じ、記譜法やモダリティの規則を示しています。写本の大部分は13世紀後半に筆写された。しかし、脇に書かれているような他の要素-論文を含む - は、1200年代の終わりか、または次の世紀の初めに筆写されたと考えられている。 コンドゥクトゥスの作曲年を1244年と仮定したMeyerの研究に続いて、Roksethは残りの曲の作曲年を1248年とした。Falkは、F-Pn lat写本の一部のコンドゥクトゥスの作曲年を、はるかに早い時期 - 13世紀の初めの年 - と提示した。写本自体のコンパイルに使用されます。 Falkはまた、F-Pn lat15139写本の元々の量がF写本やノートルダムの全レパートリーより早期に作られたと提案している。 The renowned “Codex buranus” (hereafter D-Mbs clm. 4660) records a noteworthy group of thirty-four conducti. Since all songs are monodic and notated through adiastematic neumes the relevance of the “Codex buranus” for this research might sound dubious, yet it nevertheless represents a crucial source for conductus poetry. Musical analysis of this body of music will also benefit from its inclusion in this study, as some of its songs are monodic variants of conducti delivered as polyphonies elsewhere. 有名な "Codex buranus"(以下、D-Mbs clm. 4660)は、注目すべき34のコンドゥクトゥスのグループを記録している。 すべての歌は、単声であり、adiastematic neumes で記譜されているので、この研究のための"Codex buranus"の関連性は疑わしいかもしれないが、それにもかかわらず、コンドゥクトゥスの詩のための決定的な資料を代表する。 この楽曲の音楽分析は、その歌の一部が、他の場所では多声となったコンドゥクトゥスの単声variantsであるため、この研究に含まれることで利益を得ることだろう。。 。 Certain later sources preserve music in a fully rhythmical notation and have therefore gained particular scholarly interest within the debate on conductus rhythm. Among these, the most significant is probably the “Codex de las Huelgas” (hereafter EBUlh9). It was compiled in 1325 and records music in mensural notation.36 Further sources of this sort are Darmstadt, Universitats- und Landesbibliothek Darmstadt, 3471 (hereafter D-DS 3471); Heidelberg, Universitatsbibliothek, 2588 (hereafter D-HEu2588); the “Roman de Fauvel” (hereafter F-Pn fr. 146).37 ある種の後の資料は、完全にリズム的記譜法で音楽を保存しているため、コンドゥクトゥス・リズムに関する議論の中で特定の学術的関心を集めている。 これらの中で、最も重要なのはおそらく "Codex de las Huelgas"(以下、EBUlh9)である。 それは1325年に編纂され、計量的記譜法で音楽を記録している。この種の他の資料は、Darmstadt、Universitatsund Landesbibliothek Darmstadt、3471(以下、D-DS 3471)、 ハイデルベルク、Universitatsbibliothek、2588(以下、D-HEu2588)。 "Roman de Fauvel"(以下、F-Pn fr。146).である。 Treatises Despite the relatively modest use of the word “conductus” in medieval literature (especially if compared with its contemporary genres organum and motet), an analysis of the repertoire could not be considered complete without an account of theoretical sources. In fact, treatises do not only offer the key to understanding essentially musical features, such as the rules of contemporary counterpoint, they may also deliver substantial historical information. Medieval treatises relevant to the school of Notre Dame have been first discussed by Fritz Reckow in the second half of the past century. Lately Rob Wegman has revised some dating hypotheses and proposed a new interpretation of their chronology.38 This section will only address the little number of treatises that are of specific relevance to the understanding of the historical context of the two-voice conductus corpus. 中世の文献では「コンドゥクトゥス」という言葉を比較的控えめに使用しているにもかかわらず(特に現代のジャンルのオルガンやモテットと比較して)、理論的根拠を考慮せずに、レパートリーの分析は完全であるとは見なされなかった。 実際には、論文は、現代的な対位法の規則のような本質的に音楽的な特徴を理解するための鍵を提供するだけでなく、相当な歴史的情報を提供することもある。 ノートルダム楽派に関連する中世の論文は、Fritz Reckowによって、19世紀の後半に最初に議論された。 最近、Rob Wegmanは、いくつかの作曲年の仮説を改訂し、年表の新しい解釈を提唱した。.このセクションでは、2声のコンドゥクトゥスの歴史的文脈の理解に特有の少数の論文のみを扱う。 The first of these is the De mensurabili musica by John of Garland.39 The earliest source for the treatise is I-Rvat lat.5325 (12v-30v), a Parisian manuscript copied in the 1260s.40 In the past decades it has been suggested that John of Garland was not the original author of the treatise, as his name was associated with the De mensurabili musica not earlier than the end of the thirteenth century by Hieronymus de Moravia.41 最初のものは、John of Garland.によるDe mensurabili musicaである。論文の最初の出典はI-Rvat lat.5325(12v-30v)で、これは1260年代にコピーされたパリの写本である.。過去数十年間、彼の名前が 13世紀の終わりより早くはなく、De mensurabili musicaに関連していたので、GarlandのJohnがこの論文の元の著者ではないことが、Hieronymus de Moraviaによって、示唆された。 Dating a few years later than the previous work is the anonymous treatise De mensuris et discantu, written in the late thirteenth century, probably between the 1270s and 1280s. In its first appearance in scholarly literature it figures as the fourth in a list of seven unattributed treatises. Since then, it has therefore been known as “Anonymous IV’s treatise”.42 The source for this treatise is the manuscript GB-Lbl Royal 12.C.VI (59r-80v), to which it should be added a further fourteenth-century copy (GB-Lbl Cotton Tiberius IX, 215r-224r) that was almost totally destroyed in a fire at Ashburnham House in 1731. This manuscript was copied by Samuel Pepusch before that unfortunate event, and that copy is currently known as GB-Lbl Add. 4909 (56v-93r).43 それ以前の研究より数年遅れて、おそらく1270年代から1280年代の間の13世紀後半に書かれたのが、匿名の論文「De mensuris et discantu」である。 学術文献の最初では、それは7つの匿名論文のリストの4番目のものとなっている。 それ以来、それは "AnonymousIVの論文"として知られている。この論文の原典は、写本GB-Lbl Royal 12C.VI(59r-80v)である。さらに、1731年にAshburnham Houseで火災でほぼ完全に破壊された14世紀のコピー(GB-Lbl Cotton Tiberius IX、215r-224r)を追加する必要がある。この写本は、Samuel Pepuschによって筆写され、現在GB-Lbl Add.4909(56v?93r)として知られている。 . The last treatise that will be taken into account in this section is the Ars cantus mensurabilis mensurata per modos iuris by Franco of Cologne.44 It is recorded in eight extant sources and states the principles of mensural notation for the very first time.45 The Ars cantus mensurabilis surely precedes Anonymous IV’s work. It was probably written between the 1240s and 1280s, but its precise date remains uncertain.46 Also disputed is the identification of the figure of Franco himself. In the variant of the later Tractatus de musica by Jerome of Moravia delivered in F-Pn lat.16663, the author credits the Ars cantus mensurabilis to one Johannes of Burgundy. A second source for Jerome’s treatise (I-Rv B83) seems instead to credit the Ars cantus mensurabilis to both Franco and Johannes of Burgundy, who might have simply been Franco’s colleague at the University of Paris.47 このセクションで取り上げる最後の論文は、ケルンのFrancoによるmodos iurisによるArs cantus mensurabilis mensurataである。これは8つの現存する資料に記録されており、初めに計量的記譜法の原則を述べている。Ars cantus mensurabilisは確かにAnonymous IVの仕事に先行している。 おそらく1240年代と1280年代の間に書かれたが、その正確な日付は不確定なままである。.また、さらなる論争は、フランコ自身何者か、ということである。 後のJerome of Moravia作のF-Pn lat.16663に掲載されているTractatus de musicaのvariantでは、作者はArs cantus mensurabilisをブルゴーニュのヨハネスに献呈している。 Jeromeの論文(I-Rv B83)の2番目の資料は、Ars cantus mensurabilisを、フランコとブルゴーニュのヨハネス作としている。 Other than treatises, the following chapters will be taking into account some chronicles. These do not offer much direct information on the conductus itself, nevertheless they offer invaluable historical and historiographical details, and help to draw a picture of the people that contributed to its creation. 論文以外にも、以下の章ではいくつかの歴史を考慮に入れている。 これらは、コンドゥクトゥス自体に関する多くの直接的な情報を提供するものではないが、価値ある歴史的・歴史的詳細を提供し、創造に貢献した人々のイメージを描くのに役立つ。 Notation, Modality, and Rhythm Issues of rhythm have probably been the most debated within scholarly literature on the conductus. The lack of direct information on conductus in mediaeval treatises led to contrasting speculations on the transcription and the performance of this genre. While most scholars agree that sine littera sections of conductus must be read according to the rules of modal notation, the cum littera passages still offer ample ground for debate. Before any historiographical scrutiny of rhythmic interpretations is undertaken, a brief explanation of the rhythmic modes will be of great advantage to better understanding the repertoire. The rhythmic modes (or “modal notation”) are used in all the principal Notre Dame sources. リズムの問題は、おそらくコンドゥクトゥスに関する学術文献の中で最も議論されてきた。 中世の論文のコンドゥクトゥスに関する直接的な情報が不足していることは、このジャンルのtranscription とパフォーマンスに関する観測と対照的であった。 ほとんどの学者は、コンドゥクトゥスの sine littera の部分をモーダル記譜法の規則に従って読譜しなければならないことに同意しているが、cum litteraの詩は十分な討論を要する状態である。 リズム解釈の歴史的な精査が行われる前に、リズムモードの簡単な説明は、レパートリーの理解を深める上で非常に有利である。 リズムモード(または "モーダル記譜")は、ノートルダムの主要なすべてのソースで使用されている。 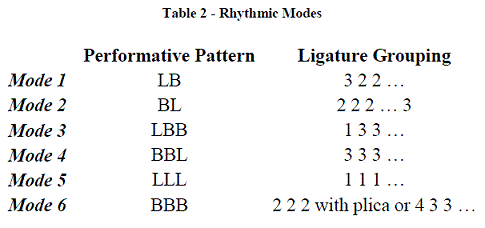 The following Music Example 1 (compare with Figure 1) shows a clear use of the first mode in a short excerpt from the conductus Ista dies celebrari.。 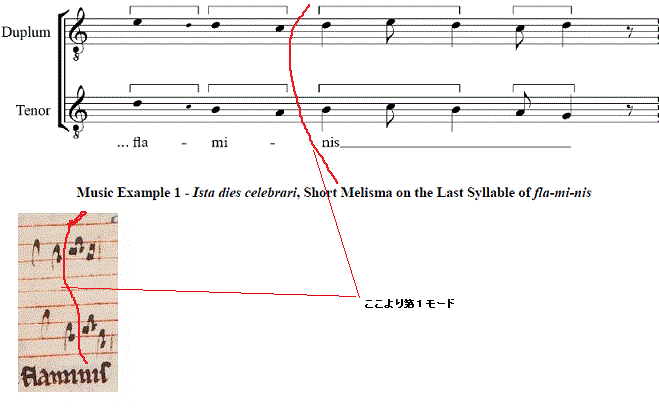 Figure 1 W1(169r(160r) In practice, the mode employed in conducti is not always as straightforward to detect as in the previous example. This repertoire was collected in anthologies several decades after its composition; it was not consequently designed to be notated through the use of the six modes. Similarly, theoretical treatises are at least a century younger than the repertoire itself, and decades younger than its main sources. Therefore, we should not expect great consistency between theoretical writings and musical sources. 実際には、コンドゥクトゥスに採用されているモードは、この例のように必ずしもはっきり同定できるわけではない。 このレパートリーは、作曲の数十年後のアンソロジーで集められた。 結果的に6つのモードを使用して記譜するようには設計されていなかった。 同様に、理論的な論文は、レパートリー自体よりも少なくとも1世紀あとに作られたわけであり、主たる資料よりもあとである。 したがって、理論的な著作と音楽的な出典との間に大きな一貫性が期待されるべきではない。 Rhythmic ambiguities are indeed common and are often due to notational limitations, in some cases solved by notators through expedients such as the so-called fractio and extensio modi. The first of these notational devices is explained by Anonymous IV, while the second is described as its opposite procedure by Willi Apel.51 An example of fractio modi is the removal of a B (quaver) from a first-mode LB pattern, where the L is normally “imperfect” (crotchet), generating a “perfect” L (dotted crotchet). On the contrary, extensio modi often occurs through the addition of an upward or downward plica to indicate the interpolation of a neighbouring pitch. リズム的なあいまい性は確かに一般的であり、しばしば記譜上の制限に起因する場合があり、場合によっては、fractio あるいはextensio modiなどの便法を通して記譜者によって解決される場合もある。 これらの記譜法の第一のものはAnonymousIVによって解説され、第2のものはWilli Apelによって反対の手順で記述されている。fractio modiの例は、第1モードのLBパターンからB(八分音符)除かれ、 Lは通常の「不完全」(四分音符)から、「完全な」L(付点四分音符)を生成している(訳注;これはextensio modiのことかと思われるが)。 逆に、extensio modiは、隣接する音高の補間を示す上向きまたは下向きのplicaを加えることによってしばしば生じる。(Apel The Notation of Polyphonic Music 900-1600 p234 参照) “Repeated pitches” may also complicate the reading of the rhythm. Since a ligature is de facto a sign drawn through a single stroke of the quill, two consecutive notes at the same pitch would result in an undistinguishable line of ink. Therefore ligatures are broken by repeated pitches even if the intentional rhythm would otherwise connect them. 「繰り返しピッチ」もリズムの読み取りを複雑にする。 なぜなら、連結符は事実上、羽の一撃で描かれたサインであるため、同じピッチで2つの連続した音符が区別できないインクラインになることがある。 したがって、意図的なリズムがそれらを結びつけたとしても、連結符は繰り返しのピッチで壊されてしまうのである。 A further ambiguity, as anticipated in the introduction of this chapter, is the absence of ligatures in the cum littera sections of conducti. Anonymous IV always distinguished between cum littera (Latin for “with letters”) and sine littera (“without letters”) passages. These roughly correspond to syllabic and melismatic music; yet, such a sharp division does not take into account the complex structure of the sections “with letters この章の最初で予想されるように、さらなるあいまいさは、コンドゥクトゥスのcum litteraセクションに連結符がないことにある。 AnonymousIVは、常にcum littera(「文字付き」のラテン語)と「文字なしの」sine litteraの間で区別をしていた。 これらは大まかに言えば、シラビックとメリスマに対応している。 しかし、このような鋭い区別は、"文字つきの”セクションの複雑な構造を考慮していない。 The sine littera portions of the music, though of challenging transcription, often present no real trouble in identifying mode and rhythmic values. On the contrary, the cum littera portions carry syllabic music, i.e. each syllable is set to one neume only (mostly a single note, more rarely a ligature). This complicates the interpretation of the whole notational system, as it jeopardises the rhythmic context formerly created by ligature patterns. 音楽のsine littera部分は、挑戦的な表記ではあるが、しばしばモードやリズムの値を特定する上で実際のの問題は起こさない。 逆に、cum littera はシラビック部分を担当する、すなわち、各シラブルは1つのネウマ符に設定される(大抵は単一の音符、よりまれには連結符)。 これは、連結符パターンによって以前に作成されたリズム的内容を危険にさらすので、記譜システム全体の解釈を複雑にする。 In order to solve the issue, an array of solutions has been hypothesised by modern scholars. One school interprets cum littera passages modally, implying that ligatures have only been broken for the necessities of the syllabic music itself. According to this interpretation, quantitative poetic meter was the key indicator to reconstruct the rhythm for syllabic music of the conductus. Long and short vowels of Latin prosody are claimed to indicate L and B notes of the rhythmic modes.52 Gordon Anderson offers further points to support this theory suggesting that later testimonies of conducti in mensural notation would provide evidence for a rhythmical reading of all cum littera music.53 この問題を解決するために、一連の解決策が現代の学者によって提起されている。 ある学派では、cum litteraがモーダルであると解釈され、シラビックな音楽そのものの必要性のために連結符が壊れているだけであることが示唆されています。 この解釈によれば、定量的な詩の音律は、コンドゥクトゥスのシラビック音楽のリズムを再構成する重要な指標であった。 ラテン語韻律の長短の母音は、リズムモードのL音符とB音符を示すと主張されている。. Gordon Andersonは、計量的記譜法での後のコンドゥクトゥスの証拠が、すべてのcum litteraのリズム読譜の証拠を提供することを示唆するための理論を支持するためのさらなるポイントを提供している。 Ernest Sanders, however, challenges this interpretation. He argues that medieval theorists did not include poetic meter within their discussions of the modal system, but he remains cautious in the complete rejection of this theory.54 He argues that conducti transmitted in later notations in thirteenth- and fourteenth-century manuscripts might simply be reworkings of the original rhythm and would therefore not offer reliable reading keys for the understanding of the former rhythm.55 He then proposes that the most rational interpretation is the isochronous declamation of the text, in which each syllable is set to a “perfect” L (dotted crotched). In his opinion, however, a few conducti would indeed require a modal reading of their cum littera music. These would be those cases in which text has been set to a known cauda of conductus (also known as conductus prosulae).56 Christopher Page, in his attempt to solve the issue, proposes a careful approach, suggesting that among the wide range of possible interpretations for cum littera music, we should include that of unmeasured rhythm.57 しかし、Ernest Sandersはこの解釈に挑戦している。彼は、中世の理論家はモーダル・システムの議論においては、詩の音律は含んでいないと主張しているが、この理論の完全な拒否には依然として注意を払っている。13世紀と14世紀の写本中の後の記譜法で伝えられるconductiは、元のリズムを再編集しているため、元のリズムを理解するための信頼できるリーディング・キーを提供することはできなかった。.そして、最も合理的な解釈は、テキストの等時性的declamationである、とした。それぞれのシラブルは完全long(付点四分音符)として設定されるのである。しかし、彼の意見では、少数のconductiは、実際には、cum littera音楽のモーダルな読譜を必要とするだろう。これらのケースは、cauda of conductus(conductus prosulaeとも呼ばれる)として知られた設定がされているケースであろう56。Christopher Pageは、この問題を解決しようとして、cum littera音楽のための可能な限り幅広い解釈をして、非計量的リズムのそれを含めるべきと提案している。 56As for instance the songs Veste nuptiali and Bulla fulminante, whose text is set to the final cauda of Dic Christi veritas. In sum, although all theories agree on a modal reading on the sine littera passages, the interpretation of cum littera music is subject to three different scholarly approaches. The first attributes modal rhythm to all syllabic music; on the opposite side stands the unmeasured realisation of cum littera sections, while a sort of perpetual fifthmode-like rhythm represents the mid-way hypothesis.58 要するに、すべての理論はsine littera のパッセージのモード的な読譜に同意するが、cum littera音楽の解釈は3つの異なる学問的アプローチの対象となる。 第1は、すべてのシラビックな音楽をモードリズムに帰属させることである。第2は、反対に、cum littera部門をすべて非計量的に理解するというもの、第3は、永続的な第5モード(訳注;Ernest Sandersの解釈)である。これはまだ、道半ばの仮説であるが。 None of these theories can be discarded, nor certainly proved. In the analysis presented here free-rhythm realisation of cum littera music is employed, since it represents the most cautious and therefore most suitable interpretation for the purposes of this work. Some very short passages . here called micro-caudae . sometimes interpolate strictly syllabic music; they appear in most cases clearly modal and are interpreted accordingly. The rhythmical reading of some other longer internal melismas is not always so obvious. When transcribing this music all cases must therefore be addressed on a one by one basis. これらの理論はどれも破棄することも、確かに証明することもできない。 ここで提示された分析では、この論文の目的に最も慎重で、したがって最も適切な解釈を示すので、cum littera音楽の自由なリズムの理解が採用されている。 いくつかの非常に短いパッセージは―ここではmicro-caudaeと呼ばれる―厳密にシラビックな音楽を補間することもある。 それらはほとんどの場合明らかにモード的であり、それに応じて解釈される。 他のより長い内部のメリスマのリズム読譜は、それほど明白ではない。 この音楽を転記する際には、すべてのケースを1つずつベースにしなければならない。 |