| A DISPUTE ON ACCIDENTALS IN SIXTEENTH-CENTURY ROME by L e w i s L o c kw o o d |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
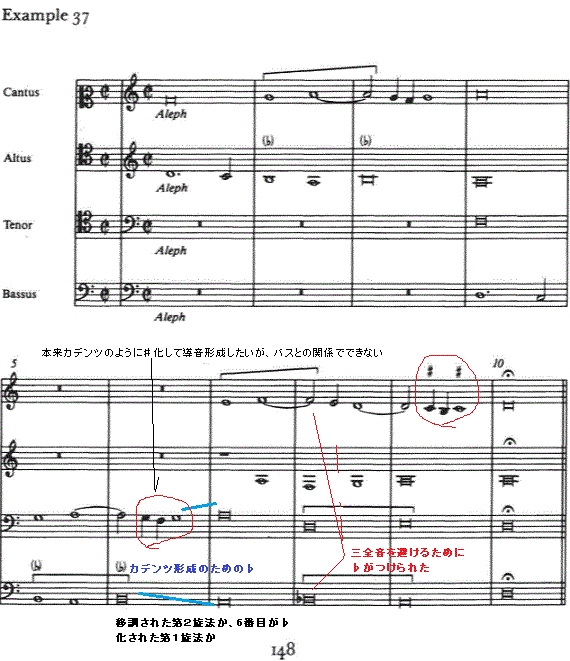 p36 ダンケルツのやや歪んだ語り口は、この論争の根本的な問題を伝えているが、(おそらく、無意識のうちに、そのコミックな含みで)、事象の実際的な側面と、演奏において臨時記号を適用する問題について、我々が喜んで受け入れたであろう多くの疑問への回答には失敗している。 (略) 論争には2つの問題がある。すなわち、ひとつは、署名と作品の旋法を中心とするもの、もうひとつは、局所的な臨時記号の適用についてである。 グィドは最初に、LamentationのバスパートはすべてB♭で歌われるべきであるとし、言葉に合わせて、署名のように、バスにB♭を挿入している。 なぜ彼がそうすべきだったのかは、Danckertsの説明や引用した例のいずれからも完全には明らかではない。Danckertsが、どの点において論争が生じたのかが不確かだからである。 彼が例として挙げた唯一のものはLamentationのAlephの最初のパッセージのみであるが、彼は、グィドがバスにおいて散発的にのみB♭を置いたのだが、バス全体がB♭化されるべきだ、と理解している。 特に興味深い点は、Alephのパッセージでは、望ましくない水平音程を抑えるために半音階を選択する要求のあるバスにおいて、conjunct においても disjunctにおいても、何ら水平的セグメントがないことである。 たとえば、Danckertsによれば、バスパートは、第8小節での特殊なB♭とともに、それより前は、d-c-b-aの音符が成立している。 p37 それゆえ我々は、もしも、B♭をずっと使うというグィドの要求が水平的考慮を基本にしたものであったならば、こうしたことは、作品の別のどこかにも現れたに違いない、と推論する。 他方、もしも彼の不満が垂直的な問題から起こっていた(よりあり得る)のであれば、第8小節の(アルト、superiusとバスとで形成されるmi contra fa)減五度が問題となり、明白に♭をつけることで、解決に向かうことになる。 バスの第8小節のこのB♭もまたオリジナルなクワイヤーブックに明記されていたというとりあえずの仮定において、その明記の存在こそが、歌手の混乱を正当化する、と考えられる。 なぜなら、その明記がはっきり書き記されていなかったとなれば、明記することが、自身で臨時記号を考えなければならなかった歌手の能力についての信頼を失ったと断言できるからである。 それゆえに、グィドのこのパッセージにおける混乱は、その完全性に関する一般的な不確実性から生じたのかもしれない。つまり、グィドが第8小節に書かれた♭をすでに見つけていたとすれば、彼は第5,6、小節もB♭で歌うかどうか、不確実だったのである。そして彼が第8小節の明記された♭を見つけていなかったが、上声部との減五度を訂正するためにB♭で歌ったとしたら、彼は、第5,6小節でもやはり、不確かであったことだろう。 さらに、グィドの要求は、これらの不可解なものを取り除く統一された手順であるり、バスにおけるすべてのBがB♭で歌われるという彼の単純で劇的な提案は、それが他の声との不幸な矛盾を引き起こさなければ、そしてDanckertsの意見では)それが旋法的整合性に違反しなかったならば、見事に問題を解決したことだろう。 Danckertsの見解の問題を考えてみよう。彼の議論のほとんどは、署名の問題にわたっている。そして、グィドの提案への彼の拒否は、旋法的な純粋性を守ることに拠っている。 彼は言う。「このLamentationは、多くの人によって、特にMaster Giovanni Scribanoによって、第2旋法に属すと言われている。それは、ReであるD sol reで終わっている」。 Alephのパッセージのみからでは、Danckertsの、第1旋法ではなく、第2旋法とすることを正当化するのは難しい。このパッセージにおけるバスが、その終止音の下四度(ラ)で、変格終止のインジケーターとみなされなければ。 しかし、Lamentationの残りにおいても、Danckertsの見方は支持されており、”旋法”による彼が意味するものの説明は、非常に伝統的で、シンプルである。they lack any recognition of the existence of difficulties in establishing an unequivocal meaning for this term as applied to polyphony. 四度と五度の全音階種のさまざまな配置としての8つの旋法についての彼の説明は、Tinctorisにまで立ち返り、より広い意味では中世にまでさかのぼる。 p38 Danckertsは、先行者Pietro Aronによって提出されたよりよい区別を差し出すことはなく、ポリフォニー作品における声楽が旋法の基本的決定因子ということについて、何ら疑問を出さない。あるいは、あるべき適切なカデンツステップについても。 1550年代の著作において、彼は、グラレアーヌスの1547年のドデカルドンにおける旋法理論の直近の改訂にも言及していない。Lamentationへの旋法の割り当てが、精巧な朗唱調の存在によって複雑になるかもしれないことを、彼はどこにも示唆していない。要するに彼は、権威と伝統の美徳だけを主張できる単純な教義を堅持しているだけなのである。 おそらく、旋法についてのDanckertsの議論のもっとも明白な側面は、まさにその、理論的な深さの欠如なのである。それは、15世紀なかばのローマの実践的な音楽家が支持することができ、それが当時の発展に関する彼の見通しを支配するという見方を示しているという意味で。 伝統への彼のアピールのパラドックスは、彼が、バスのみに♭記号をつけるというグィドの提案を拒絶するためにそれを使ったことにある。ただし、例外なくconflict signatureが一般的であった過去のレパートリーを知っているというヒントはない。 Lamentation の中での局所的な臨時記号な問題についてのDanckertsの見解は、より興味深いものである。なぜなら、それは、当時の実践的な音楽家が、この問題についてどのように推論したかを具体的な言葉として示しているからである。 フラットとしての署名を拒否したDanckertsの解決は、非常に明確な形で、臨時記号が使用されるべき基準を示している。それは以下のものである。 1)完全五度やオクターブの平行を避けるため 2)耳障りで粗雑な和音を和らげるため 3)三全音やその他のぎこちない飛躍を避けるため 「飛躍」という言葉の3番目の項目でのみの言及から、最初の2つは水平的な音程ではなく、垂直的な音程を指すことを意図していると推測でき、垂直ソノリティへのこの集中が、DanckertsのAlephのパッセージの扱いを支配している。彼の提案する解決策は次のとおりである。 1)バスは第8小節で、Bフラットを歌う。 (正しい垂直方向のソノリティを生成するため); 2)バスは第5、6小節では、 p39 後の理由は疑いもなく、興味深い。なぜならそれは、垂直ソノリティやメロディー構造の局所的かつ直接の考慮に基づくだけでなく、作品における構造要素のより大きな関係、この場合では Superius-AltoとTenor-Bassのペアの模倣を示しているからである。 確かに、この特殊なパッセージには、移調やソルミゼーションの問題は存在しない。なぜなら、模倣はオクターブだからである。しかし、このパッセージは、模倣のデバイスが、特定の臨時記号の設定を正当化し、一貫性を持たせる手段として当時の音楽家によって呼び起こされた可能性があるという証拠を差し出す。 逆説的になるが、第5,6小節のDanckertsの解決は、ひとつの問題を解決して起きながら、別の問題を惹起している。 彼は、署名と模倣と言う理由により、アルトとバスにB 以上の解釈は、Alephの旋法としてのDanckertsの定説とははっきりと矛盾する。なぜなら、アルトとバスがことごとくパッセージにおいてB♭となったならば、かれが証明しようと試みたこととは、ことごとく対立することになるからである。 ゆえに、Danckertsの前提は捻じれ、臨時記号を供給する規則とともに、このパッセージの旋法の教義的見方と調停するための別の試みが必要となる。そして、これらの問題の間の対立のより広い意味合いは、さらなる研究に値する。 |