| 4 Horizontal relation p70 (i) The prohibition of the tritone and diminished fifth 「musica fictaに関しては、これらの規則に注意する必要がある。その1つは、musica fictaは、必要な場合以外に適用することは決してないということである。なぜなら、アートにおいては、少なくとも見かけ上は、必要以上の適用はないからである。」 Prosdocimus de Beldemandisのムジカ・フィクタについての第1の規則は、気まぐれに見せ掛けのステップを導入するのではなく、必要な場合にのみ導入することを示している。 この見解は、他の15世紀の作家によっても反映されている。たとえば、Ugolino of Orvietoは、「完全に説得力のある必要性がない限り、みせかけの音楽を使用しない」と述べている。2 したがって我々は、どの音楽的文脈が、みせかけのステップの使用を必要としたかを合法的に尋ねるかもしれない。 この章では、この種のメロディーの進行について考察したい。 みせかけのステップによる修正を必要とする可能性のある旋律の進行への最も多くの言及は、三全音に関係している。 メロディ的な三全音に対する差し止め命令は、中世の時代の初めから終わりまで、事実上すべての理論家によって表明されている。 Jacques de Liegeは、およそ1321-5年頃の書物で、「昔の音楽家らは、diezeugmenonテトラコード(すなわち、 言い換えれば、すでにars antiquaの実践者らは、移調されていない全音階システムでFと さらに、同じ著者によると、♭記号は、第5,6旋法全体で(つまり、おそらくは署名として)使われ、第1,2旋法ではたまに使用された。その他の4つの旋法では非常にまれであり、第7,8旋法では特に注意深く使用する必要があった。なぜなら♭記号は、第7,8旋法を第1,2旋法に変えるからである。 Jacques de Liegeの発言は、三全音は避けるべきだが、そうした三全音についての旋法的コンテキストを考慮する必要があることを示唆している。 終止音での三全音は、もっとも忌み嫌われていることだろう。一方、構造的に重要なステップに影響を与える三全音の補正は、終止音での非和声関係(♭against E in the deuterus)や移調(tetrardusが移調されてprotusになる)を生じさせるので、望ましくない。 したがって、さまざまな旋法での♭の頻度は、tritus(第5,6旋法)では通常であり、protus(第1,2旋法)では時々使われ、deuterus(第2,3旋法)では非常に希であり、特にtetrardus(第7,8旋法)では希である。 p71 同様の、しかしより詳細な描写は、CoussemakerがSimon Tunstedeに帰した1351年の匿名のQuatuor principalia musicaeに見られる。5 このテキストは、我々に”三全音”の概念に何が含まれるかをより明確に示してくれている。 したがって、このスキルの経験によれば、誰かが固有のナチュラル音階(つまり、C-Gの音域で)を通して、低音域のletterでメロディを読み始める時、そしてGあるいはa上でmutationを行う時、もしも彼がFに下がる前にc,d,eに上がれば、彼はb 上記のテキストから、三全音に関する2つの事実が明らかになる。第1に、三全音は直接的な場合だけでなく、間接的な場合にも問題を起こす。介在するステップのすべてまたは一部によって。 第2に、三全音が適切に「解決」されても、それはoffendすることはない。Fから 非和声的、増音程(三全音)が diatonic semitone によって完全五度に適切に解決された前者の場合に、三全音がoffendしない理由を考えるのは、おそらく合理的である。 ここでも、旋法的なコンテキストが関連している。この点でのPseudo-Tunstede's の見解は、Jacques de Liegeの見解と非常によく似ている。上記の引用の中で、deuterus と tetrardus の三全音を修正しない効果についての観察は、少なくとも deuterus に関する限り、以下にqualifyされる。 deuterusの歌は、♭をほとんど許容しない。しかし、deuterusの変格は、時々♭を使う。なぜなら、protusとの関係で言われたように、低いlettersから上行すると、♭を歌うことになるからである。あるいは、高いlettersからaあるいはGへ下降する時には、そしてbへの上行、そしてここからbへの上行前のFへの下降する時には、bはb♭で歌うことになる。 Another fourteenth-century author who compiled his Tractatus de con trapuncto in Paris in 1375 provides us with a similar , if less detailed , pictures , the tritone F-q has to be avoided regardless ofwhether it is direct or indirect , ascending or descending , unless q is followed by C or the mode is tetrardus. 1375年にパリでTractatus de con trapunctoを編集した14世紀の作家は、qが直接または間接であるかどうかに関係なく、トリトンFqは、それが直接か間接かに関係なく、昇順または降順であるかどうかに関係なく、同様の詳細を提供している。 F.fa-ut [F]からb-fa.b.mi [♭/ p72 つまり、三全音F- 三全音を回避する必要性について語る多くの15世紀と16世紀の理論家のうち、私は、その議論が問題をさらに明らかにするものだけを選び出す。 豊富な情報のソースは、ティンクトリスの1476年のLiber de natura et proprietate tonorumによって提供されている。ティンクトリスは、三全音を避けたいときに第5,6旋法で♭を使用すると述べているが、次のように追加している。 三全音は避けなければならないことはまた、これらの2つのトーンだけでなく、他のすべてにも注目されねばならない。したがって、 このルールは一般的に、B-fa-B-mi acute(すなわち、♭/ そして、実際に、彼はすべての8つの旋法で例を使ってこの発言をフォローする。12 14世紀以降に嗜好が変わっており、三全音の旋法的コンテキストが無関係になっていること、あるいは、上記の14世紀の理論家が、三全音がtetrardusで発生した場合に、三全音への禁止から一般化へと舵を切るのではなく、♭がさまざまな旋法で必要とされる可能性が高い相対的頻度を示すものとして理解する必要があることが、上記で説明された。 私は後者がそうであると考える。ティンクタリスでさえ、tritus(第5,6旋法)を扱った章で問題を論じており、他の旋法よりも第5,6旋法で発生する可能性が高いことを間接的に示唆している。 ティンクトリスの発言を以前の理論家によって提供された情報と次のように合わせようとすると、おそらく時代の音楽的現実に最も近くなる。すなわち、三全音は、8つの旋法すべてで回避する必要があるが。三全音の旋法的コンテキストは、かなりの程度、以下のことが考慮されるべきである。つまり、deuterus(第3,4旋法)の終止音を持つ非和声的関係も、過度の♭の使用により移調されたprotus(第1,2旋法)へのtetrardus(第7,8旋法)のtransformation も生じるべきではない、ということ。 Tinctorisは、三全音が直接的または間接的、上行または下降のいずれかであっても、そして”人間の声が音階に沿った進行で三全音(つまり、間接的三全音)を使用する可能性がある一方で、跳躍として使用することは困難あるいは不可能である”ことを明らかにしている。13 彼の間接的な三全音の例は、( このすべては、何らかの理由でそれが回避できない場合、何が「三全音」の概念に該当するのか、どのような三全音が許容できるのかを我々に理解する手助けとなる。 私は、cが続く上行する三全音F- p73 この結論の間接的な証拠の1つは、deuterus(第3,4旋法)での♭の相対的希少性とtetradusでのその頻度に関して、我々が以前の理論家から学んだことである。すなわち、おそらく、第3,4旋法においては♭はめったに使われなかったのは、 直接的な三全音を歌うことが「困難または不可能」のいずれかであるという上記のティンクトリスの発言は、直接的な三全音を避けなければならないことを必ずしも意味するものではない。 三全音が適切に解決された場合であっても。 1482年のMusica practicaで、Ramosは、彼の同時代の人によって、”disiuncta”と呼ばれたソルミゼーションの慣行を説明している。これは、mutatioなしで1つのプロパティから別のプロパティにtransferすることで構成されている。 たとえば、cからFへのスキップを (mutatioをしない)'fa/sol―ut'と解釈するべきなのが、(mutatioをする)'fa-fa'としているなど。 彼は続ける。”直接的な三全音は、、常にdisiunctaの原因となる。そのために、1つの音符 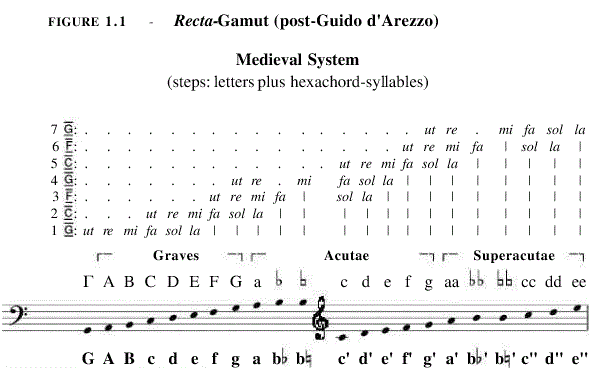 同様の証拠は、1487年のNicolaus BurtiusのFlorum libellusのパルマコピーの縁にある手書きの例で提供されている。この例には、三全音を回避するための♭の使用に関する説明が含まれている。 16 これらの1つは♭によって補正された解決されていない三全音を示し、もう1つは補正なしで残されたF- 同様に、Giovanni del Lagoは、1533年8月6日のFra Nazaro宛ての書簡で、次のように述べている。「しかし、 the immediate , or incomposite , tritoneは、その耳障りさのために歌い得ない、つまり、歌うことはできません。 。 。しかし、mediated , or composite , tritoneは、時々歌うことができる。」'18 たとえ解決されたとしても、すべての直接の三全音を避けようとする音楽家ら(おそらく大多数)がいたことは明らかである。 Franciscus は、三全音F- こうした状況では、aが繰り返される場合、特にこれら2つのaの間に休符がある場合、aの前の音符は♭となるべきである。しかし、1つのaしかない場合、 こうしたコメントから派生するであろう一般的規則では、F- p74 さらに我々は、そのような音楽の句点が、両方のやり方で機能する可能性があることを Franciscusから学ぶ。上で見たように、解決の効果を無効にするだけでなく、それが 1508年から1550年の間に11回にわたって出現したGonzalo Martinez de BizcarguiのArte de canto llanoで、同様の考慮事項を提示している。 三全音を避けるべきであるという規則のいくつかの例外の中で、 Gonzalo Martinez de Bizcarguiは、aでカデンツがひとつであれば、F- この例外を説明する例は、MartinezがF-G-a- フレーズの先頭にFがなかった場合、MartInezの例と例外は、 我々がFranciscusから学んだことと一致する。しかし、彼が先行するFで三全音を見落としていることは不可解である。おそらくこれは単なる見落としであろう。 Martinezの2番目の例外は、 そして彼の3番目の例外は、♭がtetrardus(第7,8旋法)ではめったに必要とされなかった理由を理解することを許容することである。すなわち、カデンツ的な理由によって、Fは第7,8旋法ではしばしばシャープになり、そうなると、 関連する考察は、1523年から1562年の間に4回出現したPietro AaronのToscanello in musicaで行われた。 Pietro Aaron は、「3つの連続するトーンは、それらが五度に到達しない時には常にmollifyされ、tempereされるべきである」という規則が破られる可能性があると述べている24。 彼が規則を公式化するまさにその方法は、私たちの注意に値する。上行する三全音F- ただし、これとは別に、Aaronによれば、規則が破られようないくつかの状況がある。 それらの1つは、対位法の規則により、Fがカデンツの導音として♯化する際に発生する。25 Aaronの考察は、ここでは、Martinezがこれまで論じたことに相当するが、Aaronは、1つの精妙なポイントを追加している。すなわち 我々は、Franciscus de Brugisから、F- 1545年の後期の作品Lucidario in musicaで、Aaronは、受け入れられる三全音の例を挙げている。それは、解決がさらに延長されることになるかもしれないことを示唆する。たとえば、F-a- p75 Lucidarioで論議された別のポイントは、ここで言及する価値がある。e-d-c-♭-aの進行では、(e-♭の三全音は)完全五度でフォローされるので、三全音は許容できる。これは、eを♭化するよりも好ましい。なぜならこうすると、減五度e♭-aを作り出すことになってしまうからである。 もちろん、フラットをまったく使用しないのが最善なのである。Aaronの発言は、下降する三全音が完全五度にまで適切に解決される可能性があるという私の提案をサポートしている。 Aaronは、Fと 多くの理論家たちは、間接的な三全音は、直接的なものよりも不快感が少ないという印象を与えたが、アーロンはさらにこれらの作者たちよりも寛容である。 1555年までに、Nicola Vicentinoは、彼のL'antica musica ridotta alla moderna pratticaでさらに寛容な見解を表現している。 30 Vicentinoは言う。三全音は、間接的な形式においてのみ、作曲家や歌手によって許容される。なぜならそれは、直接的に歌うと、あまりにも耳障りだからである。 ただし、この(直接的な)跳躍は作品では、たとえそれが歌うのに困難であっても、時折生じている。 なぜならそれは、驚くべき効果を持つ単語を設定したいときに、とても有用だからである。上行する三全音はすなわち、活気があり、大きな力を発揮する。逆に、下降する三全音は、葬式のように悲しい。 Vicentinoは、一定の実践でそれを歌えるようになると述べている。ではその三全音が間接的に歌われる場合、なぜ実践で直接的には歌えないのか?31 これは、新しい様式的な理想に対するスポークスマンの声であり、最終的には「第2の実践」と呼ばれる。しかし、伝統的な「初期の慣行」(直接的な三全音の禁止、ある種の間接的な三全音への寛容さ、ここでは不特定の内容)で述べられていることは、Vicentinoの前任者から学んだことと概ね一致している。 「初期の慣行」の最も重要な編集者であるGioseffo Zarlinoは、実際には次のように述べている。「tritone , semidiapente、およびそれらのような他のものは使用されてはならないが、ある種のモダンはそれらを書き、半音階としてその進行を正当化する”32。 したがって、ZarlinoとVicentinoはどちらも、新しいスタイルのハンドリングを可能にする代替スタイルのrecentな誕生を、彼らの著作に反映させている。 メロディ的三全音の禁則は、この時代に一貫した、音楽慣行の一定の特徴である。個々の理論家たちは、この禁則をよりよく理解してもらえるような、特別な考察を加えている。概して理論は、進化していく実践を描く存在ではなく、逆に、問題と取り扱う一般的なやり方のひとつに過ぎない。続いて、時系列や地域列には無関係に我々が学んだことに従うとして、まとめられる。 p76 メロディ的な三全音は、それが上行であれ下降であれ、直接的であれ、間接的であれ、禁止されている。(つまり、三全音の範囲内にある音符で満たされていること、たとえば、三全音がF- ただし、この一般的な規則には例外があります。 たとえば、F- さらに、解決は、数音符分遅れることがある(aとGも同様)。構文の中断、つまり(休符のように)、メロディの流れに句点を生成するものはすべて、三全音とその解決の両効果をキャンセルする。解決されていない間接的な三全音でさえ、その力を失い、多くの音符(Martfnezによると4つ以上)で満たされている場合、そもそも修正する必要がない。 一方、直接的な三全音トリトーンをどうするかについては、意見の相違がある。多くの理論家らは、それらを常に修正する必要があると考えており、未解決の場合にのみ修正する必要があるという理論もある。 三全音は、特に終止音との関係で発生するため、tritus(第5,6旋法)では特に回避する必要がある。一方♭は、deuterus(第3,4旋法)では稀であり(終止音と非和声関係を生成するため)、特にtetrardus(第7,8旋法)では希である。(他の旋法とは異なり、♭を一貫して適用すると、旋法的アイデンティティが破壊され、tetradusを移調されたprotusへと変更してしまうため)。 厳密に言えば解決されてはいないが、完全五度に埋め込まれている、つまりc- ただし、さまざまな旋法での三全音の扱いについて学習した内容に基づくと、このような進行がどのように処理されたかは、関係する音符の相対的な構造上の重みに依存していると推測できる。 三全音を形成することが構造的に重要であればあるほど、見出された三全音はおそらくより耳障りに響くことになるだろう。またその逆もしかり、である。 したがって、進行c- こうした考えが、三全音が、F-・・・ p77 確かに、私たちはここで、推測的な根拠に基づいて、その時代の音楽の実現性を見出している。14,5,6世紀の音楽家らが、(その概念がポリフォニーに適用され始めた)旋法内のステップのヒエラルキー同様、彼らの音楽における音符の相対的な構造的重要性についての区別や、根底にある単純な協和音程の対位法と当時の対位法理論と実践の基本的な特徴である装飾的なdiminished counterpoint の区別をしたことは間違いない。 その結果、音楽家らが、構造的に重要な音符を含む三全音は、それほど重みのない音符を含むものよりも耳障りであると判断し、耳障りな音符と少なくとも同等に重要な音符による解決は、構造的により軽い音符による解決よりも満足できるものであると仮定することが称賛されることになる。 この仮定が正しければ、我々の時代の音楽家は、与えられたコンテキストに関して機械的にではなく、音符の相対的な構造的重みの理解を伴う必要がある方法で意思決定を行わなければならないことは,明らかである。 対位法的におよび少なくともいくつかのケースでは、旋法な考慮事項についても。 初期の音楽の編集者によって想起されたメロディの”musica fictaの規則”のひとつは、la上のa音(つまり、a)はfa(♭)を歌わなければならないことを指示している。あまり強調することはできないが、簡単に述べると、いくつかの条件があるが、これは別の規則ではなく、三全音の禁止が策定された方法の1つにすぎない。 1412年に書かれ、1425年から-8年に改訂されたProsdocimus de Beldemandisは、Tractatus plane musiceにおいて、laをmiにmutatioしない限り、E上のlaを超えて上昇し続けることはできないと説明している。そのために続くFはfaとなり、Cを超えると発生する三全音を避けるためにFで歌う必要がある。33 彼は続ける。「同様の理由で、 三全音なしにFから♭/ 明らかに、この種の考慮事項は最終的に 'fa supra la'の疑似ルールを生み出した。これによれば、移調されていないシステムでは、上隣りの音符形 a- 一部の音楽家たちは、三全音を回避するためだけに'fa supra la'を行うことを思い起こし、他の音楽家たちは、前後にFがあるかどうかに関係なく、a-♭-aを歌った。 Johannes Cochlaeusは、1511年のTetrachordum musices で、第1旋法でGに移調された、'fa supra la'としてのみ正当化され得るバスでのE♭が書き出された曲の例を示している。 36 別の例では、これは第4旋法となっており、そこの対位法を傷つける'fa supra la'を禁じるためにその前後にfがない場合でも、♭♭/ p78 一方、1517年から1553年までの多くの版に登場したJohannes Cochlaeusの同時代人のGeorg Rhauは、彼のEnchiridion utriusque musicae practicaeにおいて、第5、6旋法以外のすべての旋法でb ”第1,2旋法の歌では、歌がすぐにFに引き返す場合には、laを超えて次のステップまで進む時には、常にfaを歌う。ただし、aよりも3度、あるいは四度に上昇した場合には、♭/ Rhauは、他の人と同様、F- コクレウスとラウの両者は、16世紀に彼らのフォロワーを持っている。 1533年、Stephano Vanneoは三全音に言及せずにルールを簡潔に公式化している。「ただし、laの上に音符があるところでは、それはfaの名前で呼び出されるだろう。」 '39 1537年に、非常に人気の高 かったNikolaus Listenius によってほぼ同じ言い回しがなされている。「もしも音符が1音程でlaを超えた場合、mutatioなしでfaが歌われるであろう。特に第1,2旋法においては」40 同様の式は、1550年のルイ・ブルジョアや1552年のHeinrich Faberや1556年のHermann Finck からも言われている。(ちなみに、これらの理論家のほとんどにとって、'fa supra la'のソルミゼーションはmutatioを含まなかったことに注意されたい)。 一方、三全音を回避したい場合にのみ適用可能な'fa supra la'のルールに関するラウの理解は、1528年のアグリコラと1547年のAngelo da Picitono によって共有されている。全体の上極は、Aaronによる1545年のLucidarioで丁寧にまとめられている。 人気ある音楽の処方箋を与えることを欲し、多くの過ちを知らない人々の理解を包みこむ多くの人々の不注意を考えることは、私にとっては、何ら驚きを生じさせない。なぜなら彼らは、思慮なく、laと呼ばれた音符の上にあるこの音符やシラブルが常にfaと発言されるという厳格な規則を主張するからである。それらを通して、彼らは新しい弟子を誤った理解に導く・・・ 三全音の音程が生じた場合を除いて、より甘い[つまり♭]またはより難しい[つまり そして、彼は以下を再確認する。「シラブルlaの上の音符は、必ずしも常にfaと呼ばれるべきではない」。 <まとめ> 16世紀には、'fa supra la'の規則を無分別に当てはめる人が多い。しかし、知識のある音楽家たちは、規則は単に三全音の禁則からの単なるスピンオフであることを理解している。 私は、either preferenceへの基準についての地理的または時系列的基準を発見できない。また、1500年以前に無差別に'fa supra la'の規則が適用されていたかどうかを確認することもできない。 この証拠は見つかっていない。 49 p79 16世紀の音楽を編集または実行するときに、三全音の禁止とは無関係に規則を適用するかどうかは、当時の最も賢明な音楽的見解に従うか、あるいは、洗練されていないがかなり一般的であると思われるものを模倣するかによって異なる。ソースの臨時記号の精査は、特定のレパートリーに適切なものを決定するのに役立つ。 三全音は、避けなければならない唯一の旋律的音程ではない。 減五度も修正を要求され場合がある。(平均律では三全音も減五度も同じ音程なのだが)。 15世紀後半から理論家たちは、減五度の禁止について、三全音の禁止よりも少ない頻度で議論している。不確かであるようだが、おそらく禁止は以前の音楽家たちも同様であり、理論家たちは、三全音の議論が、問題全体を適度にカバーしていると感じたというだけで、それに言及しなかったようである。 減五度が、それが垂直方向的に生じた時代を通じて禁止されていたという事実は、理論家が議論するはるか以前から、メロディックな減五度の禁則が施行されていたことを示唆している。 減五度と三全音は、非移調システムで発生する可能性がある唯一の非和声関係(減または増音程)であり、それらはしばしば一緒に議論される。 Hothbyは、La Caliopea legaleで、明示的に(減五度と三全音の)双方を禁止しており、他の多くの著者も同様である。 51 Ramosによるこれら2つの音程の議論は特に興味深い。 それにもかかわらず、オクターブを分割できる別のquantityがあるが、ほとんど音に違いはありません。つまり三全音と、B-FおよびF- にもかかわらず、それが直接的である場合、それは三全音自体と同じくらい不協和音となる。それでも、 「直接的な場合」と明示的に言います。なぜなら、それが介在ステップで進行するとき、それは、F-E-D-C-B(-C) と反対のB-C-D-E-F(-E)の上行時と下降進行の両方において、甘くて遊び心があるからです。しかし、歌は上行時にFに止まってはなりませんが、Eに戻るはずです。そして下降ジには、それは戻ってCに戻るはずです52 ラモスの場合、減五度と三全音の間のサイズと音の違いは、実際的ではなく理論的である。 両方とも等しく不協和音であり、おそらく、両方とも同じように回避する必要がある。ただし、増四度が、半音によって、外側に、完全五度に適切に解決された場合も同様に許容されるように、減五度は、間接的で、半音によって、内側に完全四度に解決されれば、それはoffendではない。 同様の情報はZarlinoから推測できる。 作曲家は時々、しかししばしばではなく、semidiapenteをメロディカルに使用することもあります。それがテキストの意味に適している場合、彼が作品が創設された旋法の自然な全音階の範囲内に留まっている限り、..。 [これらの進行を含む例を次に示します。f-e-d-c- p80 ここでも、許容し得る減五度は間接的で適切に解決されている。Zarlinoはさらに、旋法の全音階のステップのみがこのような進行に関与するべきであると規定している。(彼の例でそうであるように)それらがカデンツの導音として機能しているときでさえ、半音的にに上行または下降したステップを除外する。 三全音の場合と同様に、減五度の場合も、完全に明確ではないが、間接的なものだけが許容される可能性がある。 Giovanni Maria Lanfrancoはたとえば、両方のタイプの音程を修正する方法を説明しているが、音程が間接的である場合、これが常に行われるとは限らないと付け加えている。 54 同様に、Glarean は、減五度について言う。「それは曲の中で跳躍としてではなく、上行または下降のいずれかで継続的な動きとしては許容されている」と言っている。'55、そして少し後に、これらは三全音と減五度の両方について「飛躍的に使用されることはほとんどありません。」と述べている。 |