| FAUXBOURDON3 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| p41 MODENA, BIBLIOTECA ESTENSE LAT. MS 454/455 -ModC http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus.html http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/img/mus/i-mo-beu-alfa.m.1.12.html ModBの様式的な革新はまとめられて、エステ家のDuke Hercules 1世(I472. -1505)の宮廷からのdouble choir book 、ModCに純化され、そして今,モデナのエステンス図書館に保存されている。 このコレクションはおそらく、15世紀半ばから急速に拡大するfauxbourdonのもっとも有益なものである。それはよく組織化されていて、複写として正確で信頼できるものである。 これは、2つの声部だけが記譜され、A faulx bourdonの銘記がなされている最後の大コレクションである。すなわち、CS 15 やVer 719にみられる分離された例のように、規範の伝統を保持し、数少ない後の資料である。しかし、標準的な記譜法は、falsobordone 様式にますます支配されるようになり、そこでは、4声すべて、cantus , tenor , contratenores altus and bassus が(A faulx bourdonの)銘記を使わずに記譜されている。 ModCは、必要に応じてModC (I) とModC (II)と指定された2つのcodicesに分割された1つの音楽レパートリーとなっている。音楽は2つのchoir books に分けられているので、2グループの歌手が、レパートリーに含まれているさまざまな詩篇、マニフィカトと賛歌の交互のヴァースを演奏したかもしれない。 したがって、ModC(I)(454)は奇数番号のヴァースを含み、ModC(II)(455)は偶数番号のそれを含む。さらに、第2巻には、典礼的に、それぞれPalm SundayとGood Fridayのサービスに属するSt. MatthewとSt. J ohn Passionsの設定が含まれている。これらの巻は、BLのおよそ4倍の55×40 cmの、真のchoir books である。 ModCは、おそらくI475年以降に編纂されて書かれた。 受難曲に加えて、8I作があり、その4分の3以上は2、3声のための詩編であるか、またはfauxbourdonに設定されている。 2つの大きなグループの詩篇、ModC 1-35と49-8Iの間に、小さなグループの賛美歌ModC 36-43、magnificats ModC 44-47、およびtract ModC 48がある。 p42 詩篇の2番目のグループ49-8Iは、Tenebraeのためのものである(p51参照)。4つのマニフィカト44-47のうちの3つと同様、33の詩篇のうちの24はcanon a faulx bourdon を含んでいる。しかしそれは、奇数番号の節[つまりModC(I)]においてのみである。偶数番号の詩篇のヴァースを歌うグループは、聖マタイ受難曲においてのみa faulx bourdon の銘記がある2。 2 When G. Reese , Music in the Renaissance , 1954 , p. 165 , indicates that the Turbae of the St. John Passion are set in fauxbourdon, he apparently is referring only to the duos . Actually , none of these is inscribed A faulx bourdon in the manuscript itself. In the St. Matthew Passion , of the 17 phrases composed for two voices , only two are inscribed faulx bordon (sic 1) . 作品の冒頭で与えられたカノンがModC(II)の偶数節にも及ぶことを意図したものであるかどうかは明らかではない。賛歌のいずれにも、fauxbourdonの銘記はない。発展のこの段階では、fauxbourdon様式は主に、詩編唱のために使われたように見える。 fauxbourdonのスタイルは、ModCが編集された時についての論文を定式化した理論家、Guilielmus Monachus、Tinctoris、Adam von Fulda、Pseudo ChilestonおよびGaffuriusの指示に従う。冒頭の平行六度のつながりは、カデンツでオクターブとなる。このグループの理論家たちは、当時の(15世紀の終わり)のfauxbourdonの概念を説明していた。我々はその歴史全体を通して、理論家たちの声明を、fauxbourdonの実践について権威あるものとして受け入れる傾向があったが、それらはModCの詩篇において到達された作品のスタイルについてだけ権威があるように見える。 <FAUXOURDON AND DUOS IN SIXTHS> すべての(最初の)35の通常週用の詩篇は、作者不詳の3声のIn exitu Jsrael No. 5(15/226)を除いて、Tenebraeの詩とまったく同じスタイルで(faulx bourdon の銘記がないのを除いて)、2声で書かれている。 たとえそのような手順が特に必要とされないとしても、当然のことながら、これらの詩篇をfauxbourdon contratenor で実行することは可能である。それゆえ、我々は、それが可能であるという理由だけで、デュオに平行なcontratenor altus を追加することを期待できるだろうか?何人かの編集者は彼らのtranscriptionsでこれをしたが、しかし我々の意見ではこれは不当な手順である。 厳密な fauxbourdon の上声部が、平行四度でダブるという事実は、cantus と tenor の間で形成された協和音程を、六度とオクターブに制限する。したがって、フォーブルドンのための最も単純な作曲的工夫は、cantus と tenor の間に平行六度の鎖を導入することである。同様に、いくつかの単一の声部に伴う最も簡単な方法の1つは、2番目の声部を平行六度に追加することであった。 それゆえ、特殊な場合における更なるエヴィデンスが推論されることができるのでなければ、デュオが、fauxbourdonの銘記が欠けている音楽的テクスチャーに対して望まれていなかったと仮定する理由はない。 p43 その一例がTr88、394 Advenisti desiderabilis、Anonymousである。それはおそらく、TrentのGeorg Hack司教(1444年 - 1465年司教)を記念して作曲されたものである。オリジナルのテキストは、Trentへの特定の言及をするためにわずかに変更されているように見えるが、オリジナルの作品自体は、典型的には、地方的な産物であった。 cantus と tenorは平行六度でほぼ連続的に進行するので、記譜された contratenorが存在しないDTO VIIの編集者によってなされたように、fauxbourdonのcontratenor altus を追加しようという試みがある。 作曲家からは一定の音楽の賛辞が流されていたという事実を考えると、ある程度の量の音楽がかなり機械的に作られていたため、デュオがより適切であると思われる。 ある写本で作品にA faulx bourdonと刻まれていても、別の写本には刻まれていない場合、論理的には、その銘記のない設定がデュオとして歌われたことを期待されるかもしれない。 思い出していただきたいのは、fauxbourdonは最初から、デュオと密接に関係していたということである。 2つの作品の記譜に関する限り、2作品は、1つがA faulx bourdonの銘記を持っていたという事実意外は同一であった。実は、銘記は頻繁に欠けているので、意図的に省略されているのではないかと疑う。 謎canonが、常に演奏者によって正しく解釈されたかどうか、そしてそのような作品がどのくらいデュオとして演奏されたのか、ははっきりせず、fauxbourdonはそれによって、フォーブルドンはそれほど多くは失われていない。 15世紀第4四半世紀のTinctoris , Guilielmus Monachus or Gaffurius まで、どのような論文でも、fauxbourdonの正しい演奏が既述されていなかったので、それまでの演奏は口頭伝承に依存していたに違いない。それは、情報獲得には、本来的に、かなり不確定なことであった。 いずれにせよ、cantusに平行四度を追加することは、上声部を強調し、和声を豊かにするという目的を果たすことになる。fauxbourdonは、デュエットよりも充実した豊かなサウンドを持っているが、音楽的にはそれ以外の点では未分化であり、オルガンストップの追加に似ている。ある意味、完全音程のダブリングは、Dufayの同国人、ドビュッシーを予期している。彼はまた、音調の色彩のために、平行五度を使ったのである。 この様式にもっとも最も包括的な情報を与えた15世紀後半の理論家Guilielmus Monachusは、一貫してfauxbourdonとデュエットの様式を扱った。彼はそれを密接に関連した対としてgymel と呼んだ1。 p44 1しかしながら、我々は、Guilielmus Monachus によって不完全音程から形成された構造的なデュエットとして帰せられたという意味で、より多く、gymelという用語を使っている。これらはGuilielmus Monachusの時代の共通の構造的音程であったので、Guilielmus Monachusがこれが英国のスタイルであると述べているにもかかわらず、それらの使用が英国の影響を示すとは必ずしも言えない。gymeIの六度の厳格な連続は、後期のfauxbourdonのcantus と tenorの表現において同一である作品様式を生み出している。 これは例えば、fauxbourdon と gymelについての作曲と即興演奏の両方について彼が与えた以下のような説明書の中で見られるかもしれない。 ここで、英語の対位法の規則が始まる。それは、英国の理論家自身によれば、2つの手順を暗示している。 それらの間で一般的に最初のものは、faulx bordonと呼ばれている。 それは3つの声部、すなわちtenor、とcontratenor、sopranoで歌われる。gymel と呼ばれた2番目のメソッドは、2声部、すなわち、ソプラノとテノールで歌われる。 2番目の規則は、gymel が cantus firmus上に作曲されている場合、上記のfaulx bordon の規則を遵守しなければならないというものである。 3番目の規則は、 contratenor bassusは faulx bordon と gymelの両方で形成されることができ、これら2様式は、4声で歌われることもできるということである。 gymel の協和音程が、faulx bordonのスタイルのように六度か八度を提供するならば、gymelでcontratenor(bassus)を形成することもできる。前の規則で示されているように、後ろから3番目の三度か五度下とともに、三度か五度下のfaulx bordonのcontratenor(bassus)として進むことができる。 <BRIEF HISTORY OF DUOS IN SIXTHS> contratenor bassus とテノールの下三度と五度の交替公式に関する最後の声明に戻ってみよう。 しかし、まず最初に、ModCにおけるduosと fauxbourdon の歴史的関係を明らかにするために掘り下げる必要がある。その事実はよく知られており、その最終段階では、fauxbourdonは、詩篇唱チャントの特別性であった5。 faulx bourdon canonを使わずに、2つの声部に対して平行六度か八度で詩篇唱を設定するという伝統もある。ファルソ・ボルドーネのもう一人の直接の祖先は、あまりよく知られていない。 5 例えば、Gaforiusは、1496年に、六度和音のfauxbourdonが、詩編で使われていたという考えを定式化した。彼は、これらの考えを形式化し、ファルソボルドネの進化に関する説明を、音楽的機能よりも典礼的な機能においている。 特に、15世紀の終わりには、純粋なfauxbourdonが、MagnificatsとPsalmsを専門化し、その結果、ポリフォニックな詩篇唱とfauxbourdonは、ModCで同一になった。 fauxbourdonはしたがって、psalmodyのようなモノトーンのdeclamationや詩篇の単純な note-against-note 様式のpsalmsを意味することとなった。 ほとんどの場合、この様式は、必要に応じて存在したものであり、書き留められたものではない。それは、技術的に非常に単純なためである。 15世紀第4四半世紀の完全に発展した、ModC写本の成熟した形式の存在の前に、我々は、以下のように設定された、数少ない、記譜された詩編設定を見出だす。困難なTonus peregrinus , vide infra やMagnificatのより華やかな設定をのぞいて。 p45 この様式の発展は、すべての声部を容認し、そして響きの良い方法で規制する組織システムを提供するために、あらゆる声部におけるある種の音程の公式を遵守するcantus firmus として使われた詩篇唱における即興を含んでいたに違いない。 書かれた形においては、単純なデュエット様式の和声化した詩篇唱の伝統は、15世紀の第2四半期までさかのぼることができる。それゆえに、 fauxbourdon 自身としてのほぼ同時期での発展が明かである。 たとえば我々は、RatisbonのSt. Emmeram修道院の写本Emにおけるテキストのない白色記譜法での8つの詩編唱公式を見出す。TENORは、ユニゾンとその三度上で書かれているが、ほとんど装飾のない詩篇唱は、移調されていない cantus で示されている。cantus が1オクターブ高く移調されない限り、TENORは明らかにその上に不自然に横たわっていたままだった。もしも cantus (firmus)が1オクターブ上に移調されると、例12に示すように、テノールとともに、通常の六度が得られる。 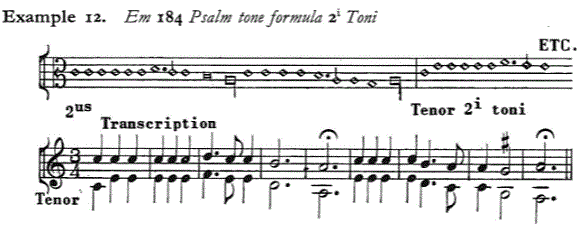 この提案された演奏方法は、cantus と tenor の通常の関係を保存し、そしてpsalm toneの設定方法を作り出す。それは後の出典、すなわちTr 90、Montecassino、 Bibl. Abbaz. MS 871 N (MC)、 ModC、そしてVer 759で再度見出される。 15世紀後半からのNeapolitan MS, MC では、 Sunday Vesper psalmsの設定 ,すなわち Dixit Dominus (presented as Example 13}) , Confitebor tibi , Beatus vir , Laudate Pueri and Laudate Dominus(folios 17-24) は、カデンツにおいて、cantus と tenor が六度で書かれている。 p46 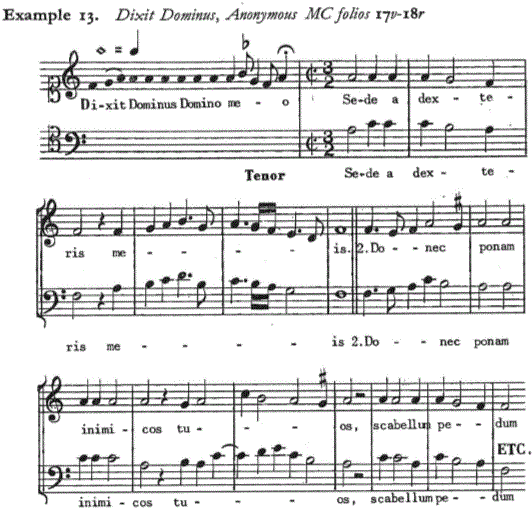 この様式は、Emの形式のように、機械的にfauxbourdonと同じであるが、基本的なcanonはない。 cantus firmus は上声部に含まれている。しかし、Emの公式とは異なり、テキストはすべてのヴァースのために下敷きにされている。 同様の手順がModCの最初のセクションでも行われている。 唯一の違いは、2つの聖歌隊の間の交替が、これらのデュオのパフォーマンスを向上させることである。 後のヴェロナ写本、Ver 759では、13の詩篇のうちの3つは、 cantus- tenor duoの六度を使っていない。それ以外の詩篇は、明示的にfaulx bordon を呼びかけるか、あるいは記譜された3、4声を示している。 Ver 759は、fauxbourdonを含むそれらの地域的なソースに専念するセクションでより詳細に議論されるであろう。しかし Neapolitan manuscript MC は、現時点で調査されねばならない。なぜなら、 A faulx bourdonと銘記された作品を含まないけれども、それが、スペイン人作曲家Pedro Oriolaによるfalso-bordoneスタイルの4声のための In exitu Israel (例14)の独自な設定を含むからである。 p47 この作品は、ギメルとフォーブルドンが4声で歌われる可能性があるというGuilielmus Monachusによる声明を明確に示している。 2声のための詩篇の場合のように、cantus firmus はExa.I4の上声部に含まれている。そして、cantus とtenor は、六度か八度の協和音程だけとなっている。しかしながら、さらに、contratenor bassus は、テノールの下で「三度か五度、最後から3番目と最後から2番目の音がそれぞれ三度と五度」で、Guilielmus Monachusが規定している通りに進行する。 その主な機能がハーモニーを増強することである contratenor altusは、cantusの真下に平行四度で追加されるのではなく、むしろテノールの三度か四度上を維持し、時折その声部を交差させる。この設定は、すでに発見された、最も初期の完全に記譜されたファルソボルドーネであるようだ。 Guilielmus Monachus(1480年頃)は、六度か八度でのcantus と tenor からの4声作品を作る際にOriolaが使用した方法を説明している。 六度かオクターブが、 fauxbourdon の外側の声部だったのか、それともデュオの一部だったのかは、あまり重要ではない。 Guilielmus Monachusに関する限り、六度かオクターブの構造上の使用のみが必要となる。 Faulxbordonのソプラノが(テノールと)六度かオクターブを形成する場合、テノールの三度か五度下で進む contratenor bassus を伴なう。最後から2番目は常に、テノールの五度下になる。これはソプラノと十度を形成する。そして最後から3番目の音は三度下となる。したがって、五度と三度の間で交互に切り替わり、最初と最後の音が低いオクターブまたはユニゾンを形成する。 fauxbordonのcontra(tenor ) altus は、最後から2番目において、テノールの上四度を取り、最後から3番目においてテノールの3度上を取る。テノールはこのように進んでいく。 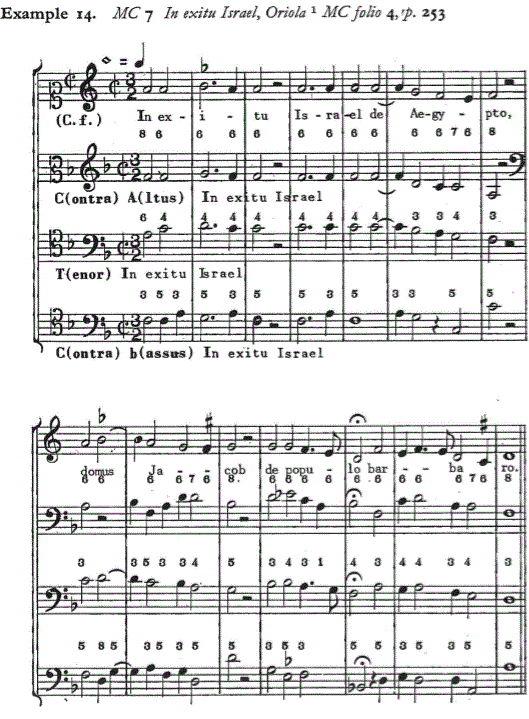 (15/226) p49 以下に、OriolaのIn exituの最初のフレーズの一連の音程の概略図を示す。これは、Guilielmus Monachusによって記述された公式の実際的な説明を与える。 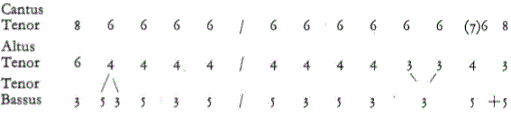 contratenor bassus は、第6小節の2つの連続三度を除いて、三度と五度の交代にほぼ隷属的に固執している。明らかに、Oriolaは、フレーズの終わりから2番目の五度へのパッセージを単純化して指し示すために、この時点で連続三度を書いた。これは実際には18 - 19世紀の和声の属和音―主和音カデンツ(ソド)をもたらした。 なお、contratenor bassusの最後の音符の跳躍に注意して欲しい。これは、contratenor bassusが、テノールの上五度までジャンプしている。あたかも、contratenor bassusがテノールとオクターブやユニゾンを形成するのではなく、contratenor altus et bassus となるようである。 Oriola's のcontratenor altus は、その bassusとしてのGuilielmus Monachusの公式とはあまりよく対応していない。指定されたように、ほとんどの音程が四度または三度を形成することは事実であるが、これらの音程は、規則的な方法で交互になることはない。altusは fauxbourdonでの平行altusと全く同じではない。 そのようなaltusは、唯一のcontratenorであることが意図されており、cantusとtenorとだけで一緒に演奏されたが、その一方で、この例のaltusは、ハーモニーを充実させるだけであり、そして、bassusとの連携ともに使用されている。 言い換えれば、平行altusは、3声のfauxbourdon の中にその場を持っているが、一方、ハーモニーを充実させるためのaltusは、4声のfauxbourdonで使用され、それは科学文献ではしばしばファルソボルドーネと呼ばれている。 我々は後に、OriolaのIn exituよりももう少し一貫性をもって、テノールの上を四度と三度で交互に繰り返す公式を利用するfauxbourdon とファルソボルドーネの作品に戻るだろう。 これらの公式は、 faulx bourdonの一連の音程のカノンに対する追加の解決を示している。 我々が導入した最も初期の解決法、すなわちcantusの下の平行四度の連続法、かなり以前から科学文献で知られていたが、追加的な形式の実際的使用は、これらのソースの音楽作品のtranscriptionや実演には敵良い鵜されなかった。 逆説的に言えば、より親しまれている平行altusよりも、contratenor bassus やハーモニーを充実させるためのaltusのより多くの記譜例がある。 このように、科学的な書法には、書かれた声部の様式的特徴と同様、書き言葉の文体的な特徴だけでなく、fauxbourdon contratenor の過度の単純化に満ちていることがわかる。 p50 六度のfauxbourdonあるいは gymelの、テノールへの規則に追加されるべきハーモニーを充実させるためのaltusとcontratenor bassusについてのGuilielmus Monachusの記述は、これらの声部の標準的な祖先を明らかにし、初期の平行altusに対するそれらの関係を明らかにしている。 bassus とハーモニーを充実させるためのaltusは真のfauxbourdon contratenoresである。たぶん、それらは代替のcontratenores がfauxbourdonのために提供された伝統から発展した。 固定された音程の連続のこのシステムは、カノンがその起源ではあるが、 supra librumの即興に、非常に適していた。適切なチャントを供給すると、cantusはGregorian tenor より六度上を歌い、bassusはテノールの下三度と五度で交互になっている。そして、ハーモニーを充実させるためのaltusは、bassusと共に、テノールの上三度か四度とシンクロしている。 多くのチャントの場合、その結果は、根音上の位置において非常に満足のいくハーモニゼーションを生み出している。例えば、チャントがフレーズの終わりで、通常の段階的な下降カデンツを持たない場合、結果はそれほど満足のいくものではない。 このように、快い音調を保証するための、記譜された、移調されていない詩編唱から十分なハーモニゼーションを生み出すためには、さらなる体系化が必要とされたように思われる。 幸いなことに、完全に記譜されたファルソボルドネの詩篇の多くは、supra librumに提示されるかもしれない機械的モデルとの非常に密接な関係を示している。そのような設定は、Oriolaの In exituのように、そうでなければ得ることができなかった即興のスタイルに関する情報を私たちに提供する。しかし、音程の連続公式の使用をさらに調査する前に、他の詩篇の設定を調べなければならない。 In Exituは、Oriola以外の作曲家によっても、しばしばポリフォニックに設定されていた。たとえば、ModBとFMにはそれぞれ、Binchoisによる設定の個別のバージョンが含まれている。 ModBは3声のための作品とfauxbourdon-like contratenor を配置しているが、FMはaltus も a faulx bourdon canonもなしにcantus -tenor duo のみを提示している。 In Exituは、Tr 90では3つの異なる方法でポリフォニックに設定されている。No.I059およびNo.1096の2作は、faulx bourdon の様式で平行六度を示すが、No.1096のみがカノンを含んでいる。 3番目の設定、No. 1095は、 fauxbourdon と 自由な3声を利用している。すべての設定を相互に比較してみると、後の写本ModCの基になっている組織的な考え方が少しだけわかる。これには、デュオ、fauxbourdon、および3声による詩編の設定も含まれている。 対照的に、ModC自体では、In exituは、自由な3声部で作曲されている。この設定では、cantus と tenor は主に六度に頼るが、それらはまた、多くの三度と五度を注入している。 Bassusは、Oriolaのln e xituの設定における公式のように、三度と五度を交互にはしない。実際、音程の連続に関しては、これはModCのすべてのpsalm設定の中で最も制限が少ない。fauxbourdon canon のない六度の2声のためのそれ以上の列挙された作品では、我々はまた、BL (N) 320 Magniftcat , Lymburgia and Ao 168 Magniftcat , Anonymous同様、Tr 90に含まれた多くのイントロイトの音符を取り上げることべきであろう。これらの典礼的なタイプはすべて、詩篇唱に密接に関連していることに気付かされるだろう。 p51 このevidenceに基づいて、単純な平行六度での朗読公式に基づいてチャントを実行する伝統は、一般的にfauxbourdonのそれと同じくらい古く、両方とも1430年頃に流行したと結論づけることができる。 したがって、ModCは、15世紀の終わり頃に、これらのデュエットとfauxbourdon を1つのコレクションにまとめた。 この時期から、2つの様式が融合して、科学文献ではファルソボルドーネと呼ばれるものになると思われる。 ModC中の作品をより詳細に調べることによって、我々は、変容の様々な段階を、ファルソボルドンに従うことができる。 <TENEBRAE PSALMS> この点に関しては、33のTenebrae詩篇が最も有益である。 これらの設定には、六度の2声(Guilielmus Monachusはこれをgymelと呼んでいたでしょう)のヴァースが含まれている。これは以前にトレースされた発展の流れを反映している。 以下の表は、ModCの2巻に従ったTenebrae詩篇で使用されている作曲技法の要約を示している。 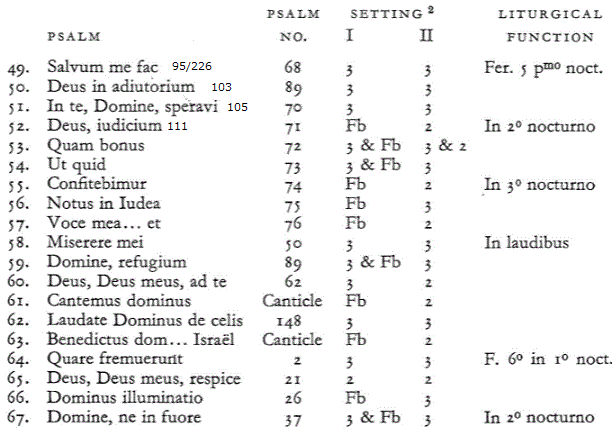 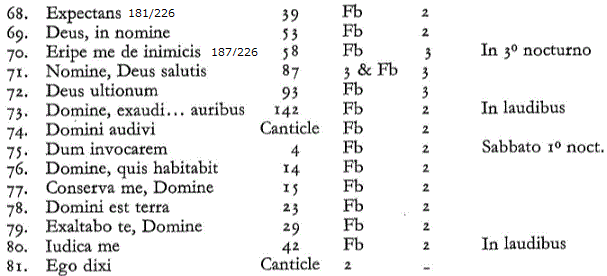 p52 6つの詩篇(No.49、50、51、58、62、および64)は、3声部のために書かれていて、No.65、および81の2作は、単にfauxbourdonのないデュオである。 9つの詩篇(53、54、56、59、66、67、70、71、72)は3声の書かれた声部のためのヴァースとfauxbourdonのヴァースを組み合わせており、1つ(No・60)は、3声の書かれた声部のためのヴァースとfauxbourdonを持たない2声のヴァースを組み合わせたものである。 残りの15の詩編の意図された演奏モードについてはいくらか疑問点がある。それらのヴァースにA faulx bourdonというラベルが付いていないにもかかわらず、第2聖歌隊が音楽の実演において、第1聖歌隊のfauxbourdonスタイルを続けていたと仮定すると、以下の15詩篇は、完全にfauxbourdon になるはずである(No. 52、55 、57、61、63、68、69、73、74、75、76、77、78、79および80)。第1コーラスの fauxbourdon と第2コーラスのデュオの間のコントラストは、第2コーラスによって歌われるような交互のヴァースの減少された設定をより好んでいる。 duoと fauxbourdon の設定は、すべて基本的に平行六度の範囲で動くが、3声作品では多かれ少なかれ、異なる公式が適用される。ソースを介して進むにつれて、公式はますます適用される。 もっとも自由な想定された設定は、ModCのNo.5のIn exitu において、見られる。 whereas by the time one has reached the sixty fourth of these psalms ,the cantus and tenor move almost exclusively in sixths (with octave cadences) and the bassus alternates thirds and fifths beneath the tenor , as has been exemplified in Oriola's setting of In exitu (Example I4). No. 73、Domine、exaudi(205/226)の最初は、その前の詩篇に続いて、この詩篇の3声部目は全部省略されており、cantusと tenor は全部、faubourdon canonと共に、六度(オクターブのカデンツを持つ)で書かれている。 ModCの作品のこうしたエントリー順が個々の作品の作曲順も表すのであれば、多くのヴァースの作曲家は明らかに、自分たちの仕事に飽き飽きしており、公式にどんどん落ち込んでいったようである。 p53 詩編唱自体の違いは、特定の詩編の設定の種類を選択する上で、重要な役割を果たしているようである。トーン4、5、7は、fauxbourdon または duo専用である。 追加的bassusが提供されるのは、トーン1、2(移調された)と8だけである。1 1 Tenebraeの詩篇は、第3、6トーンを利用していない。もちろんこれらはポリフォニー設定はされない。 例15は、 Notus in ludea (129/226)からのヴァース(詩編75編)であり、六度のデュエットスタイルとfauxbourdonの設定の両方を示している。 デュオとfauxbourdonの作曲技法の違いは銘記文字だけであるため、この1つの抜粋は両方に十分である。 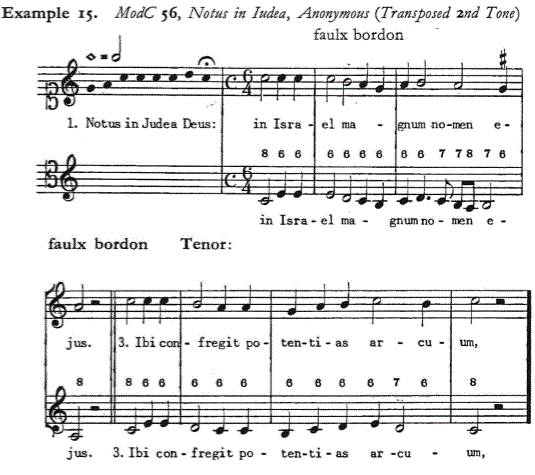 最上声部の中にcantus firmus を用いたnote-against-noteスタイルでの六度進行に気づくであろう。これは後期のフォーブルドンの典型である。 フレーズの終わりには、最終的なカデンツとしてオクターブにつながるほぼ常に7-6の繋留音が見出される。このパターンは、書かれた2声部が含まれるModC全体で使われる。初期のfalsobordoneスタイルでは、fauxbourdonの音程の連続公式を遵守するbassusが、この基本構造に追加されている。例16は、この追加を説明している。 p54 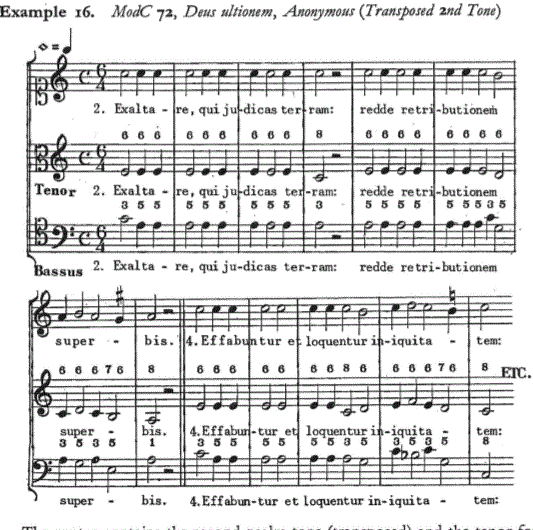 このcantusは第2psalm tone (転置された)を含み、テノールは例15と同じ方法で、cantusの下六度に形成される。さらに、機械的なcontratenor bassus が、テノールの五度と三度の交互で書かれている。 ModCの3声部設定のすべてが、それらの音程間のやりとりにおいてそれほど厳密であるとは限らないが、これは特に最初の数曲のTenebrae詩(No. 49-51)に当てはまる。 その組み合わせは、ModCの詩篇の過程でより機械的になる。 |