| p391 16世紀の音楽、特にイタリアのマドリガルにおける半音階の台頭は、学者たちの長期にわたる関心の的であった。長短の調性のエヴィデンスの探求において、ブルクハルト派において行われたルネサンス文化において現代音楽世界の兆候を期待するにおいて、調性的に強められた強められたシャープとフラットは、重要なエヴィデンスであった。 (16世紀半ばの)調性を破壊する半音階主義は、同時に、シュペングラー派が示したように、対位法的fabricでの崩壊の実証として使用することも、19世紀の半音階の負担下での調性の崩壊に類似していると見なすこともできる。 。サーガにおけるヒーローと悪役(デ・ローレやマレンツィオは常にヒーローと見なされていた、ジェズアルドは以前は悪役であったが、現在はアンチヒーローである可能性がある)が特定されているが、これは現代の学者によるだけではない。 Zarlinoが"cromatici"を嫌ったこと、対位法の規則を破った「moderni」へのArtusiの反対は、音楽史のあらゆる調査で説明されている。 19世紀との示唆的な類似点により、ある学者はArtusiとHanslickを比較するようになった。 これらの懸念や態度の多くは今では時代遅れに思える。旋法と調性は、もはや自己完結型のシステムとは見なされなくなっている。 seconda pratticaの台頭はもはや、古典的なポリフォニックシステムの破壊または完全な置き換えを目的としたものとは見られていない。 独自の異なる傾向の寛容な受け入れ、進化の進行の理論よりも循環的な変化の理論を好むことは、もちろん非常に時代遅れに見えるかもしれない。しかし、それはここで提案されているものとは異なる種類の議論の主題なのである。 これらのページでは、記述されている現象のより大きな音の重要性についての一般化を試みることなく、音楽の表面に見られる16世紀の半音階主義の側面について議論したいと思う。 p392 私が支持しようとする1つの一般的な結論は、この音楽におけるかなりの半音階主義は、公認の半音階主義者の間だけでなく、基本的に全音階の音楽を書いたり、Kroyerの分類を使った作曲家たちの作品における対斜(mi-faの衝突)を真に好むように思われる結果であるということである。 16世紀の半音階音楽とは何か? 半音階分野は彼らが疑いなく全音階的ポリフォニーと見なしたものにおいて存在した、ということを信じない同時代人に確信させたNicola Vicentの運命を思い出して、いくらかの注意を払ってこの質問に答えるべきである。 16世紀に一般に受け入れられていた回答に最も近いものは、意図的な半音階音楽は、大きいあるいは全音階的半音 (a-b♭ or, with musica ficta, c♯-d)に加えて、小さいあるいは半音階的半音(c-c♯あるいはb♭-b 5 調律と音律の厄介な問題は、ここでは扱わないが、考慮事項である。平均律は問題外である。 Vicentinoらにとって、c-d♭はmajor semitone (全音階音楽の移調に使用可能)で、c-c♯はminor semitoneあるいはフルの半音階的semitoneである。私はここで、全音階半音を大きいものとして、半音階的半音を小さいものとして、イントネーションに当てはめる(Zarlino、Le istitutioni Harmoniche [Venice、I558; facsm。、New York、I9651、Pt。III、Chap。I9を参照)。 ピタゴラスのイントネーションでは、2つが逆転し、limma あるいは small semitone は diatonic intervalに, apotome(ピタゴラスの音階の全音と半音の差をいう。これはまたクロマティック半音ともいう) あるいは large semitone はchromatic intervalとなる。 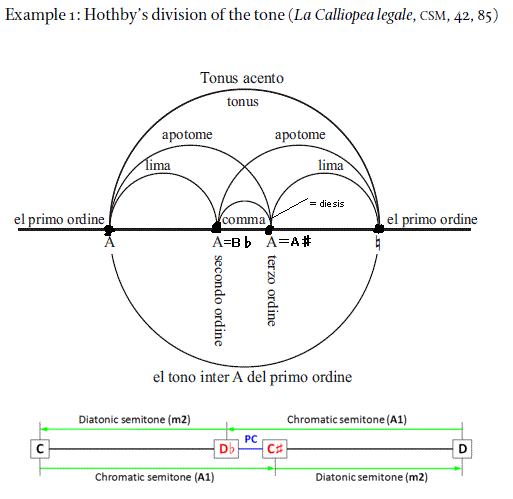 短三度のスキップの存在だけが半音階分野の混和剤であることを示していたVicentinoでさえも、彼がその分野に分野することを知りたがった音楽に直接半音的メロディの動きを入れることに注意を払っていた。このようにして、彼は古い時代の半音階的なテトラコードを利用した。 したがって、16世紀の半音階は、ある種の旋律的書法を意味していた。単に結果として(そしてイントネーションに対するかなりの困難を伴う)、 'ポリフォニックテクスチャ、または作品全体が半音階的になった。 p393 音楽のシャープやフラットを表す用語は通常使用されていなかったように見えず、直接の旋律的半音階はない。この説明の一部は、それでも耳に非常に色彩豊かで、少なくとも和声感覚のとれたカラフルさがある。彼らが16世紀の耳にどのように聞こえるかを正確に試みることなく、選択された旋法分野の移調されていない限界内で残された音楽とは異なる効果を生み出したと仮定することができる。 16世紀後半の音楽では、予期せぬ臨時記号が、空から落ちてきたという印象がある。with no preparation consequence しかし、ほぼすべての16世紀の半音階は、あるソノリティから別のソノリティへの動きで、時には個々の声の動きを大胆に計画していれば、規則正しく計画されてもいる。 16世紀の作曲家がメロディの半音階に頼ることなく色彩感をもたらしたいくつかの明確な和声進行がある。9 9 「和声進行」という用語は、ここでは、いくつかの声部で許容されるメロディーの動きによって生成される2つの連続したソノリティを意味する。 暗黙的ではあるが、調性との必要な接続はない。 実際、ルネサンスの作曲家が和音を書くことを学んだ teaching of discantは、主題として teaching of modeと一致することはめったになかった。 もちろん、所与の声部の中での半音階的inflectionは、メロディ書法の原則と情報に基づいた慣行に支配されていた。 16世紀の理論家たちは、当時の音楽における水平的要素と垂直的要素の要求の対立によって引き起こされる問題を認識していた。 まず1つは、バスでの五度または四度の動きの一連の進行で、以下のように、五度のサークルと我々が言い慣らしているものである(例1)。10 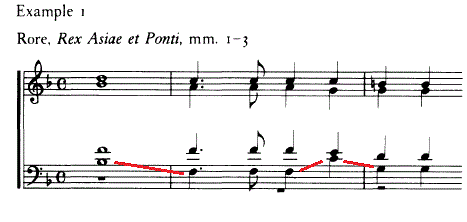 10 この作品の冒頭は、上に挙げたカテゴリーの実用的だが驚くべき例ではない。 進むにつれて、Rex Asiaeは五度のサークルの強迫観念的な使用で例外的になる(a♯からe♭まで)。 第63-89小節(Meier版)は、16世紀の音楽におけるこれらの進行の最も長く途切れない連続の1つである。 JosquinがこのデバイスをAbsalom fili mi11で使用して称賛したときから、それは時折のリソースとなった。16世紀半ばまでには一般的に使用されるようになり、世紀を通じて流行し続けた。 和音の各ペアでの明らかに音響的な”強さ”にもかかわらず、これは基本的には半音階的な工夫のように見え、しばしばほとんど恣意的に、作曲家が主たる音響的中心から離れることを許容した。 11 16世紀の音楽慣行での五度のサークルが果たす役割に最も興味を持っている学者は、もちろんEdward Lowinskyである。彼はこの進行においてmi-fa関係(mi contra fa)の回避を示すことに関心があった。 16世紀後半の音楽では、 このプロセスによって到達された新しいピッチレベルのつかの間の確立が(場合によってはハーモニックシーケンスの助けを借りて)本物であったことがわかる。 他の進行や省略なしでは、五度のサークルの使用は、もちろん、旋律的な半音階を要求をせず、対斜も生成しない。 次は、musica ficta、または旋法外のシャープとフラットを伴うことが多いもので、バスは全音または半音でアップダウンしている(例2)。(したがって、mi-fa関係(mi contra fa)が頻繁に生じている)。 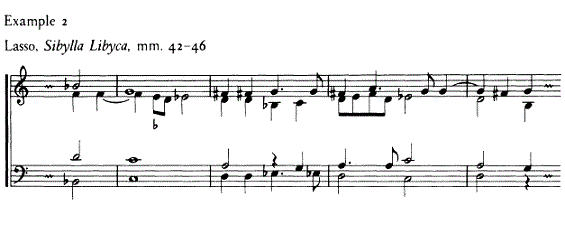 この進行におけるより高いバスの音符は、しばしば和声転回と呼ばれるものの下支えとなっている。これは、discant理論によってカバーされた現象であり、すべての和声パートの振る舞いが、どこにあっても議論される。そのメンバーの再配置の臨時記号が存在する和声的実体の特別な認識が、その理論の一部ではなかったにもかかわらず。 p395 16世紀のメロディ的半音階は、 small semitoneを使用して、こうした進行が要求されなかったにもかかわらず、それは、我々の感覚においては十分に半音階的であり、Zarlinoが”非和声的な関係”と呼んだものの多くを産生する。特により良い用語がない場合には、V-IV進行と呼ばれる。(例3参照)。  あるいは、半音階は、全音階的な段階的進行に適用された色彩的修飾をすることができる。(例4) 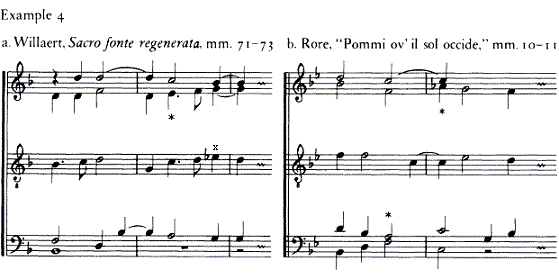 3つめは、staticなバスに対する度合いの変化で、和声的色彩が導入される別のの一般的な方法である。 これは多くの場合、あるフレーズの終わりから次のフレーズの始まりまでの間で発生することが多く(例5)、その点では、正しい対位法に対する多くの規則が中断されているように見える。13 13 フレーズの終わりにおける三度(にあたるところ)の(半音)上昇は、16世紀中ごろにはしばしば印刷譜において見られたが、それ以前の世紀ではめったになかった。それはすでに一般的慣行ではあったのであろうが。 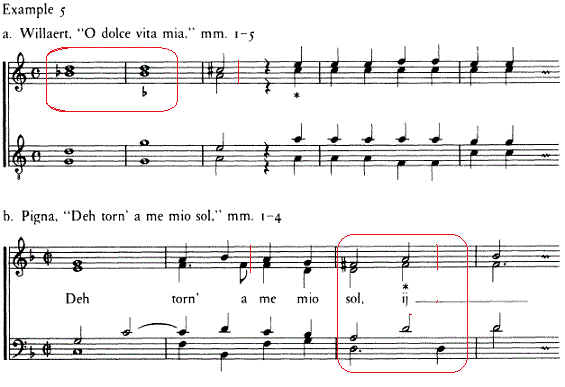 p396 こうした色合いの変化は、1つの声部の大きな跳躍の結果として、常にではないが、時にはフレーズの途中で発生することもある(例6)。 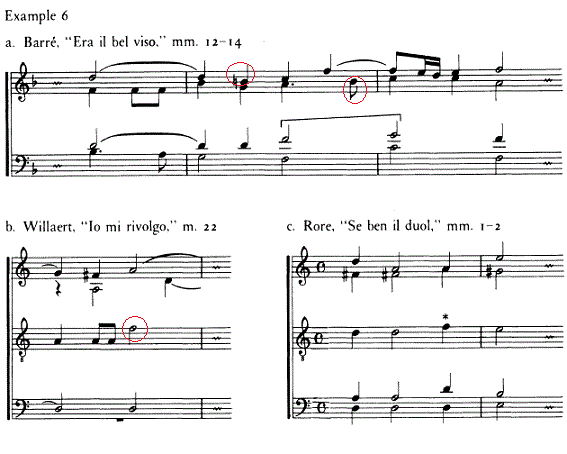 音の程度合いの交替は、半音階分野がwingに潜んでいるという疑いを生じさせることなく、同じ声部でさえ生じている(例7)。 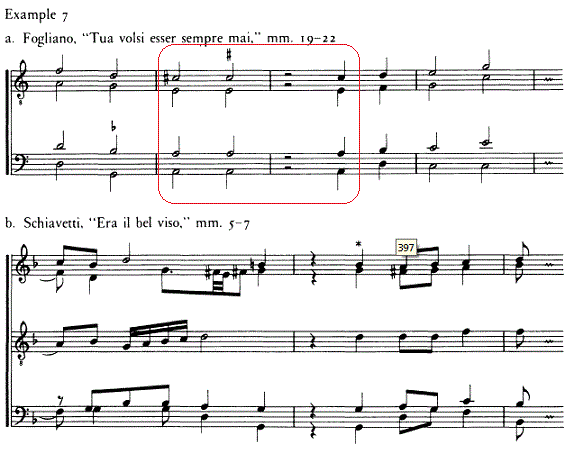 これらすべての例では可聴の対斜となるが、静的なバスの安定した影響は、その効果を弱めている。 4つめの進行のタイプは、旋法とはあまり関係のないものであるが、バスが長短三度で上下に移動する進行である(Exx。8-I I)。 これらの進行のすべてで、臨時記号の使用は、強く耳に響く対斜をどんどん産生するが、三度の微調整は、演奏に影響するかもしれない。  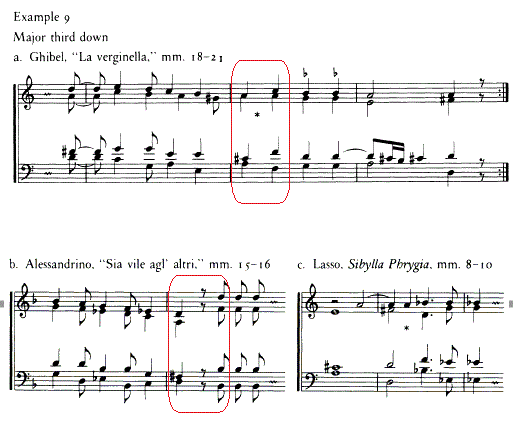 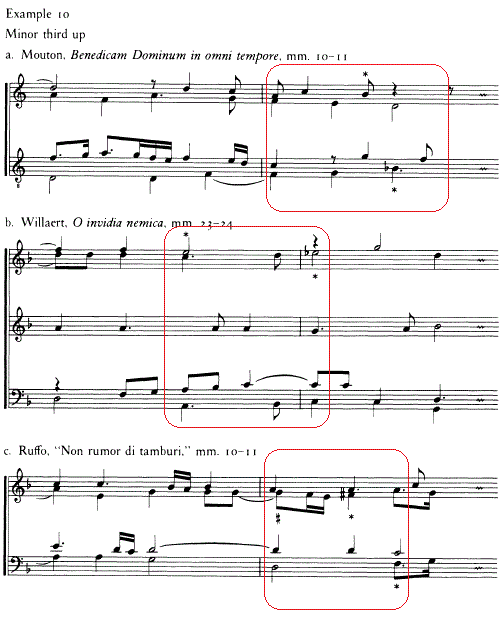 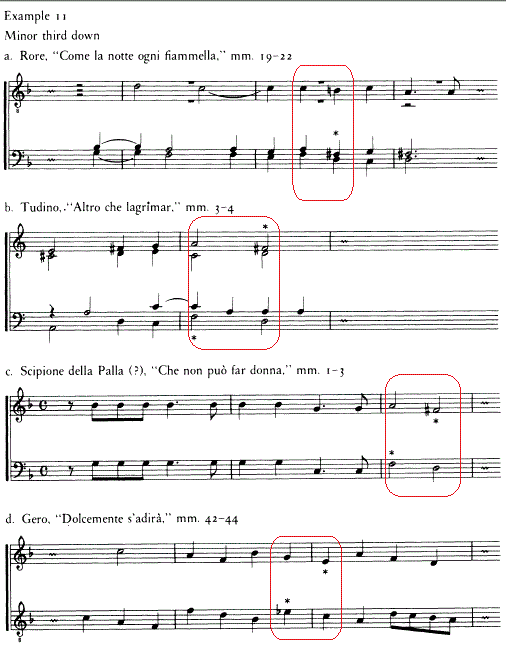 (外側同士の声部での)長三度(+オクターブ)の動きに伴う進行の例は、16世紀後半においては一般的であり、マレンツィオや彼の同時代人と関連している。(例12参照)。  16世紀の初めに使用された場合、ラッソのProphetiae Sibyllarum(上記の例8c)のオープニングが示すように、それらは意図的に自己意識的に半音階的になっている。単一の声部で旋律的半音階なしでのこの進行の使用は困難である。 p401 この進行で臨時記号を使用することは、単一の声部での旋律的半音階なしでは困難である。 一方、色彩的な短三度の進行は、すべてのパートにおける全音的なvoice leadingとともに、容易に書かれることができる。(これにより、おそらく対斜がさらに顕著になる)。 その頻繁な使用ははるかに早くから見られ、世紀半ばのマドリガルでは顕著なスタイル的なのアクセサリーになる。 (外側同士の声部での)長三度(+オクターブ)の動きは、多くのルネサンスのポリフォニーの特徴であるため、ハーモニーの教科書の言葉の「強力な」進行と見なされるべきである。 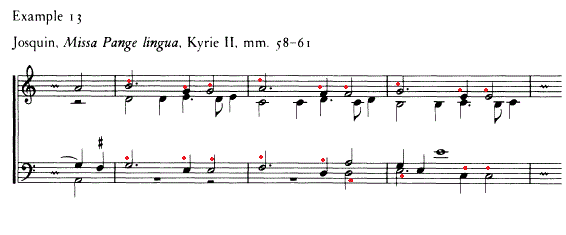 もしも例13における外側の声部の間でのすべての三度(+オクターブ)が半音階的変化を通して長調になった(cantusにおけるg♯、f♯。バスにおけるe♭)のであれば、ジョスカンは、すぐに(ラッススの)Prophetiae Sibyllarumにかわることができることだろうに。 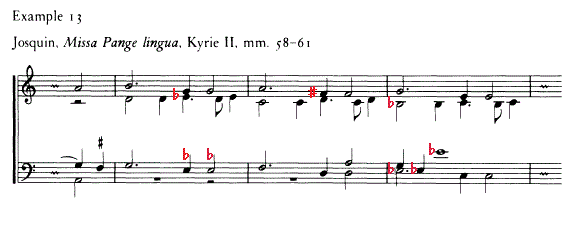 こうした極端に走るまでもなく、下降三度のつながりが、ジョスカンの様式においてさえも、musica fictaの問題を産生するであろうことがわかるだろう。(例14) しかし一般的には、多くの三度飛ばしを伴うバスラインの使用では、対斜を産生する必要はない。 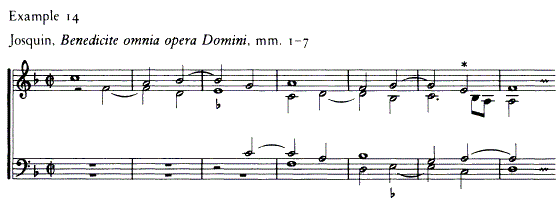 p402 こうした進行における対斜の意図的な使用は、フロットーラのレパートリーに現れ始め、フレーズを分離するための効果的な方法として機能している(例15)。 この音楽では、例16のように、テキストと音楽の両方が有名な即興演奏家Serafino Aquilanoに帰されるstrambotto( one of the oldest Italian verse forms, composed of a single stanza of either six or eight hendecasyllabic (11-syllable) lines)から、対斜が中途に現れることがある。   この作品の一般的なラフなテクスチャーは、対斜が偶然に、不注意に、または不完全な技術の結果であると考える人をリードする。 「正しい」使用法と呼ばれるものは、エキスパート技能者であるArcadeltの作品(Ex。17)で見ることができる。ここでは、介在する和音の存在によって、対斜が緩和されている。 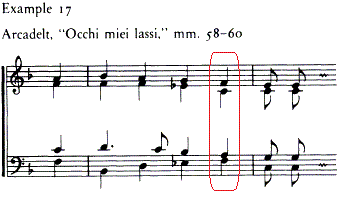 Arcadeltでさえ、介在するコードは単に暗示されるだけで(Ex。18)、完全に省かれてもいる(Ex。19)。 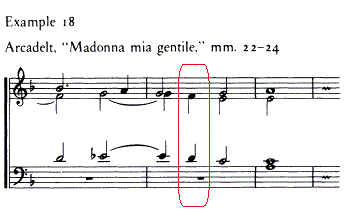 例19では、対斜を取り除くために、第4小節のカントゥスのeに編集者がフラットを与えている。 p403 だが、cantusのパートブックを手にした歌手は、誰もこの音符に♭をつけることはなかったことだろう。 私の主張では、この種の衝突は容認されただけでなく、16世紀の音楽家たちに好まれれていたのである。 確かに、そうした対斜は、我々の気が利かないラベリングを排除して、最高の作曲家の作品でも頻繁に生じているのである。  音調語彙の表現力のある可能性が16世紀の間に開発されたため、言葉の意味を強調する半音階の使用は、マドリガルの規則的な特徴になった。 Heliseo Ghibel は、 Ariostoの "Ben furo aventurosi i cavallieri,"の半音階設定を誇りに思っていた。それは、例20で見られる模倣の大胆な冒険の主題から始まる。 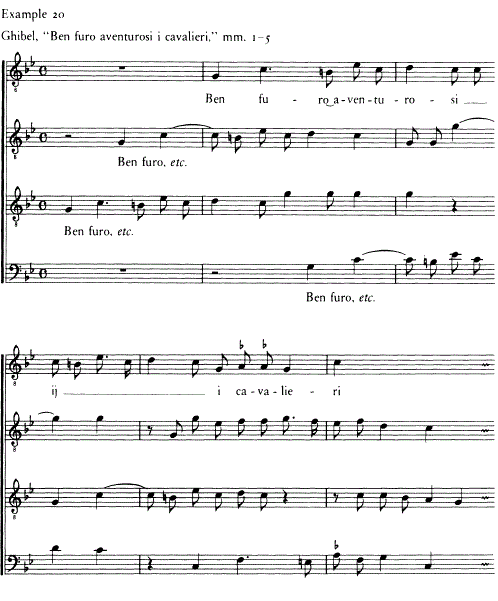 Cipriano de Rore's の表現豊かな半音階の使用の称賛は、彼が言葉の意味を強調するために対斜を選択した、と信じさせるものである。 彼は確かにそうしたことだったろう。しかし、Bernhard Meierは、ローレの対斜のすべてを慎重に見ようと試みた後、「対斜は必ずしもテキストで決定されるとは限らない」と判定した。 Roreの作品におけるテキスト的に中立な対斜の例は、 "fa super la."の明示的にマークされた観察からの結果として、 Meier によって試みられたEx.21で見ることができる。 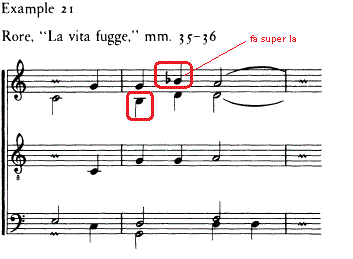 これは16世紀作曲家において真実のように見える点である。メロディーまたはハーモニーの転換は、効果的に言葉の歌詞づけをしている。音楽は歌詞の僕べであり、言い換えれば、day offとなる。 p405 作曲家らは、常に、表現のために半音階を使っているわけではない。そうであったときには、それらの語彙は、統一的ではなく、それは、世紀を経るにしたがって、変わっていく。 もしもアルカデルトの”Il bianco e dolce cigno"のフレーズ設定et io piangendoをヴェッキのそれ(アルカデルトの設定のパラフレーズ)と比べて見れば、アルカデルトのV-IV進行は、ヴェッキの直接の半音階よりもよりマイルドに、より古い流行で、劣らず効果的である。20 20 例22aにおいて、Albert Seayは、第8小節で、cntusに編集上、eを♭としているが、私は、表現上、あるいは技法上の理由で、不要だと思っている。第7小節の最後のcantusの音符に対してe 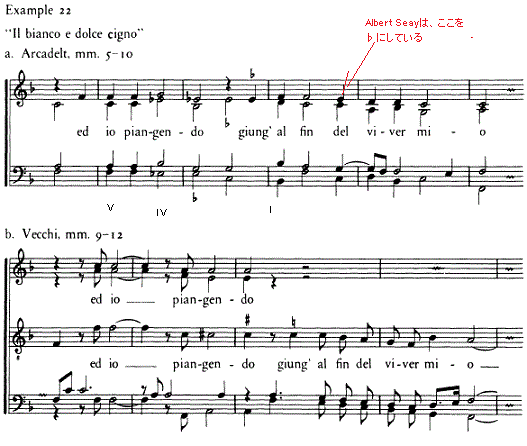 p406 どちらも、マレンツィオやモンテヴェルディがしたことと比べると(ジェスアルドとは言うまでもなく)、未熟である。これらの作曲家の使用法は、この論文の範囲を超えているが、ここで試されていることと同様の方法で研究できると思われる。 例として、1つまたは2つの点を簡単に説明できる。モンテヴェルディに好まれたデバイスである、多くの小節での繋留音を使った長きにわたる解決は、個々の声部が解決するような異なる割合によって形成された多くの対斜を生む結果となる。初期の音楽において、小規模なスケールの一種の拡大がクラッシュし、しばしば対斜の同種のものを生じる。 マレンツィオと彼の同時代人では、16世紀半ばの音楽で非常に強調されていた根音での和音の使用が変更され、第1転回での多くのソノリティが導入され(TUDAR MUSIC4 p65参照)、そのために、より優雅なバスラインが得られる。同時に、ここで記述された半音階進行の多くを取り入れていた。 アーカデルトと彼の同時代人に見られる時折の半音階的対斜は、次世代のマドリガリストの音楽においてより頻繁になる。この現象は特定の場所に限定されない。例えば、それはヴェネツィアの作曲家に特有のものではなく、アインシュタインが強調しているような、ヴェネツィアの色の愛の特別な証拠ではない21。 21 アインシュタインを公平に見れば、彼は、16世紀の和声の革新の関心を、「北イタリア、ことにヴェネツィア、Verona,ミラノの作曲家全体によるもの」としている。 ローマのAntonio Barre 、ミラノのPietro Taglia 、フィレンツェのStefano Rossetti はすべて、多くの例を提供している。私がここでデモンストレーションのために選んだ作曲家のHoste da Reggioは、ゴンザガ家の一員であり、マントヴァとその後のミラノで活動していた22。 Hoste da Reggio (c. 1520–1569)は、1550年代に人気のあった、デクラマシオン的でリズミカルにしなやかなmadrigale arioso様式を育成した。23 彼の音楽は、Roreのマドリガールのレベルではなく、この世代の他の偉大なマドリガリストであるRuffoのそれと同等である。しかし、それは有能に作られており、音色の驚きに満ちている。24 p407 上記で論じたような半音階的対斜は、1つまたは2つの中間和音を介して可聴相互関係を聞くことができる例を含めると、数え切れないほど多くある。以下は、直接的な対斜のいくつかの例である。 (1)例23a-c 同じバス上での三度の変化 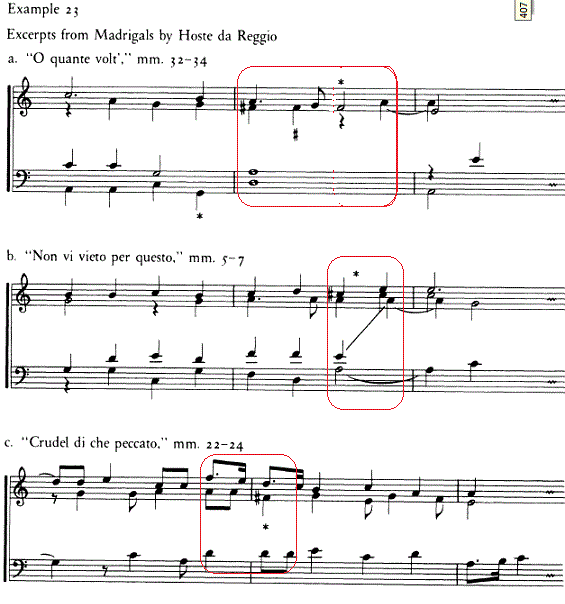 (2)ひとつ上の音へのバスの動き 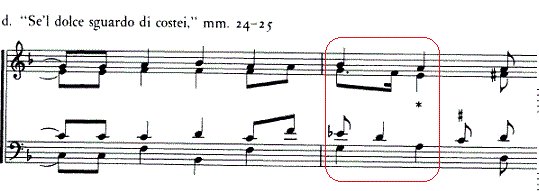 (3)下方の音へのバスの動き。ここでは最後のカデンツとなっている! 同じバス上で三度変更が続いて。 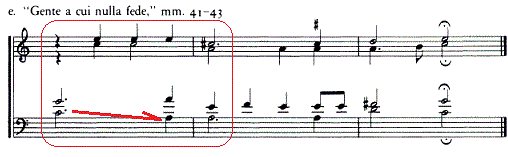 p408 (4)短三度上へのバスの動き 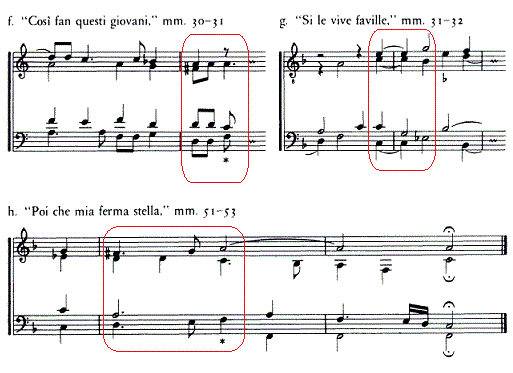 (5)長三度下へのバスの動き 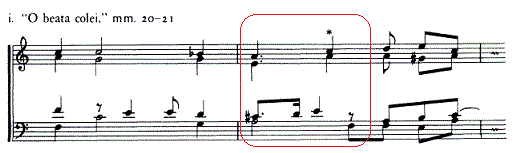 (6)短三度下へのバスの動き 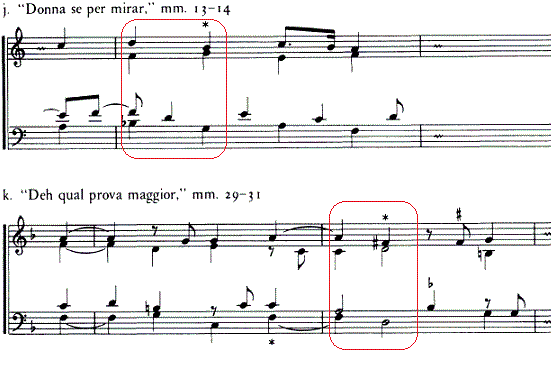 一般的な流れは、むしろ休符のないこれらのマドリガルの和声言語は、例23Lや典型的な終止である例23mにおいて説明される。 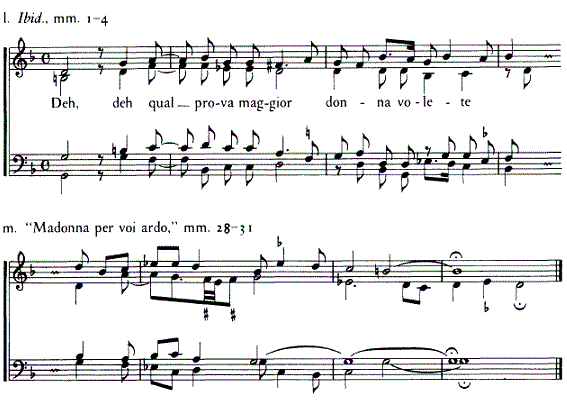 Hoste da Reggio (c. 1520–1569)は、表現上の目的のための半音階の価値を知っていたが(彼は、とある作品において、piu duraという言葉にa♭をつけていたが)、彼の作品からの例は、音画法の効果については使われていない。それらは作曲家の音の言葉の部分であり、それ自身が、そわそわとした実験的なイディオムなのである。 p410 いくつかのケースでは、対斜は直接的であるだけでなく、同時でもあり、文字通り解釈できるのか、それとも解釈すべきなのか疑問に思われることもある(Ex.24)。 「注意深い」臨時記号の理論では、これらのスポットを説明するようには思われない(あまりにひどい耳障りな音として響くから)。 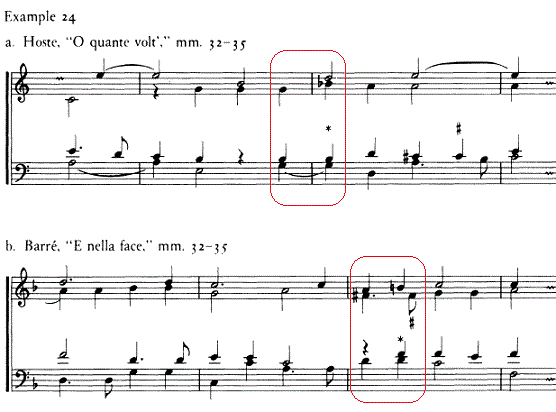 もしもこれらがミスではないのであれば、それらはさらに、この音楽の対斜の性質における注意深い耽溺のさらなる証拠となる。 私がHoste da Reggio (c. 1520–1569)の作品において見つけられなかった1つの進行は、長三度上がったバスの動き(での対斜)である。この和声進行では、その直接的なメロディ的半音階がほとんど不可避となる。対斜に対する彼の冒険的態度のすべてに対し、彼は、16世紀において半音階分野と呼ばれたものの使用を避けていたように思われる。 彼の同時代人は、こうした一歩を踏み出すことに、躊躇しなかった。チプリアノ・デ・ローレの祝祭的な半音階的実験は、この時代に行われ、そして、Nicola Vicentinoの理論に影響された作曲家らは、1550年代にmadrigali cromaticiと呼ばれたものを産生した。 p411 ラッススのProphetiae Sibyllarumは、半音階であることを明示する歌詞(訳注;この部分はラッスス自身による歌詞である)でもってラベル化された進行を伴って開始されており、そして、長三度のバスの動きが使われている(例8c)。 正当なやり方ポリフォニー書法としての半音階分野を擁護したとして知られているVicentinoは、彼の論文と、後のマドリガル作品の両者において、メロディ的半音階の例を提供した。28 .この音楽には、ダイアトニックなメロディーの動きによって生み出される対斜の例も含まれており、しばしばバスにおいて、短三度進行となっている。29 Vincentinoによる半音階分野の意図的な使用は、幾分は、避けられたかもしれない。もしも彼がそれを願ったのならば。例25aと25bとの比較で示されるような、和声パッセージの再スコア化がなされるならば。 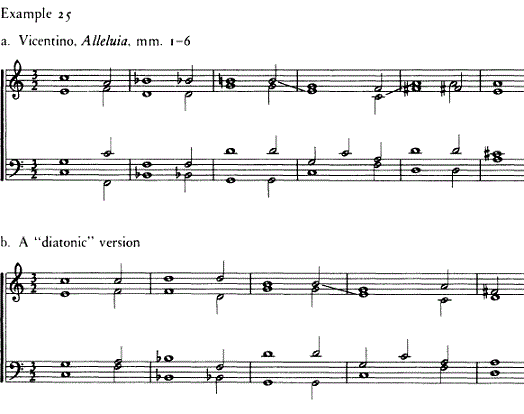 彼が完全に全音の音楽の"asprezza"(純粋さ)を保っているというよりも"participata e mista"(混合されたもの)として記述したこの音楽は、他の作曲家の作品に、自明的に導入された半音階分野、かつその小メロディ的な半音の必要性なしに、すでに存在していた。 これは、Vicentinoの寄与を最小化するのではなく、半音階の対斜の響きが、明らかに、古い分野を復活させることに興味のないように見える作曲家たちによってさえ、好まれたことを強調しているのである。 Vicentinoの理論の批評家は、新しい半音階について、軽蔑をしていた。Vicentinoの反対者であるGhiselin Danckertsは、軽蔑して、「今の時代において、全音階分野の音楽が、これらの新しい派手な作曲家の新しい書法の口実の下で、このような混乱に陥ったことを現代でどのように見出すか」 と書いた。 Zarlinoは、cromaticiに反論するために、かなりのスペースを割いた。そこにはVicentino は名前はなかったが、確かに(彼は)彼らのリーダーを意味していた。32 適切に調律された対位法は、半音階またはエンハーモニック分野のテノールの周りには書かれることはない、と最初に述べた(後の時点で、Zarlinoは、昔の人がこれらの分野で成功した理由は、最も単純な完全音程のみを使用してドローンバスまたは伴奏でメロディーを歌ったためだと言う)が、Zarlinoは、今の作曲家たちがこれらの分野において書いていることが実際的であることを、否定し続けている。なぜなら、彼らは、以前のリズムやテキスト的相応物なしで、特徴的なピッチ・音程を使用しているためである。 また、長短三度の出現も、テトラコードやエンハーモニーや半音階分野で分割された兆候はない。 これらの音階は、全音階の分野でも同様に、分割されていない。さもなければ、常に文字をスキップせずにアルファベットを順番に進むことを余儀なくされる場合、メロディーを書くことはできなくなる。 彼の時代に実際に起こっている音楽は、Zarlino が続けているように、それらは、半音階と全音階の混合物として見られる、♯や♭が豊富にある作品である、ということである。 このような使用法は、表現目的と音楽の移調のために価値があるが、半音階分野で作品全体を構成することへのこだわりは、醜さと不条理だけにつながる。 p413 対斜に関する彼の見解は別物である。平行音程について説明している章(III、29)で、彼は、平行長三度と六度は”和声的関係”がなく、後で説明することを約束し、そのために、避けるべきであることを指摘している。 これまでのところ、彼はステップワイズな動きを話してきたが、進行がスキップによるものである場合(例では長短三度によって進行する三度あるいは六度を示すで動く)、その進行は絶対的に禁止されている。次の章では、調和関係とその欠如について説明している。 作品のパートが声部の間で和声関係を持たないと言うとき、そのパートは増価または減価された音域、あるいはsemidiapenteや三全音などの音程によって分離されることを意味する。和声関係には、ピッチが離れた2つの同時音符だけが関係するわけではない。それはむしろ、協和音程を形成する2つの声部に含まれる4つの音符の間[Ex。 26] .で生じる。 例26の音符の対角線の関係は、対斜を示している。その中で、例26の最初の関係は、私たちの主題にとって最も重要である。 Zarlinoによれば、これらは単一の声部においてほど悪くはないが、2声書法では非常に重要であり、正確性が作曲家の目標である場合は避けるべきである。 多声構成では、これらの音程は、特にフーガまたは模倣的書法において、不可避であるかもしれない。 ただし、「欠陥」が発生した場合、臨時記号の結果としてではなく、選択した旋法内に留まる音楽でなければならない。 後者の例は、デリケートなフリギア旋法で、理論家によって与えられている(例27)。 したがって、例28のような一節に関するZarlinoの判断が想像されるかもしれない。 次の章では、Zarlinoは、”非和声的”関係は、多声作品において、あまり決定的なものではない、という、彼のadmissionを繰り返している。さらに、彼は、別の長三度によってではなく、その後に短三度が続く長三度を好んだことだろう。 p414 伝統的な対位法の教程は、2声書法で始まった。そして、16世紀には、duoの手ごろなliteratureがあったが、3声以上の多くのルネッサンスポリフォニーは、さまざまに組み合わされたduoから成っていた。 私が引用した例の大部分における対斜は、あたかも2声部のみであるかのように聴こえたが、Zaelinoは、これらを、不快な半音階に接するボーダーラインのケースとして見なしたと結論つけられている。 こうした理由のために、careは、Zarlinoの尊敬すべき教師であるWillaertの音楽からの引用を含むことは数少ない。 Hoste da Reggio (c. 1520–1569)のような冒険的実験家は、おそらく、Willaertの是認を得ることは、なかっただろう。 非和声的関係のZarlinoの論議は、1588年のTigriniのCompendioのような彼の作品の簡単な編纂には、現れていない。それはしかし、CeroneのElMelopeoにおいて忠実に再現されている。 ArtusiのL'Arte del comtrapontoは、繰り返すだけでなく、Zarlinoのポイントを詳しく説明している。パートがそれぞれsemitoneや短三度によって動くのであれば、反行によってユニゾンから長六度へとは行かないこと、あるいは、平行進行によって五度から六度には行かないこと、などが加えられている。(三度のスキップを使う)平行進行における長短六度は、poorである。そして、このスキップを使っている平行する長三度も等しく悪い。なぜなら、すべては、mi-faや非和声的関係を産生するからである。 ゆえに、ここで引用された16世紀のマドリガルからの例は、Artusiの是認を受けることはなかっただろう。モンテヴェルディの半音階に対する彼の非難は、ほとんど驚くに当たらない。 ティンクトーリス以来のルネッサンス期の理論家たちは、正しい作品芸術において、初心者に教唆する意味合いを持っていた彼らの規則違反に不満を抱いていた。 どの時代においても、落ち着きのない16世紀半ばが、言うまでもなく、第二作法のルーツとなったように、円熟した作曲家たちによるletterに従ったpreceptsであったと考える理由はない。 対斜における理論家の見方は、それゆえに、悪意的な重要性ではなかった。Zarlinoの詳細な観察は、常に、価値があるのである。 ここに現れるのは、書かれた臨時記号の使用を通して作られた対斜を受け入れ、一部の作曲家にとってはいくぶん誇張した好みさえあることである。ここに示した例が示すように、この半音階によって満足される旋律的な必要性―fa super laなど―はない。 このような臨時記号が、16世紀の音楽家が働いていた柔和な全音階的旋法のフレームワークにとって有益であると見なされたことは明らかである。ここで取り上げるレパートリーのジャンルは、時代が限られている。初期の音楽は、書かれた臨時記号の数は少ないが、この点で私が見なしたものよりは、確かに多く見られる。 intabulationや他の器楽音楽は、調査のための豊かな分野を提供する可能性がある。英国の音楽家たちが取った対斜に対するしばしば言及された喜びは、私が関係していた音楽のcorpusに追加されたことだろう。また、上記で引用したモテットの例は、マドリガルがこの種のことを起こしたジャンルではなかったことを示している。 一般的な観察として、16世紀半ばの理論と実践における旋律的半音階の導入は、対位法的fabricの表面下で静かに進行していた一般的な調性変化の兆候としての革命的な動きではなかった、といえるだろう。 また、アドバイスとして(少々微妙ですが、それでも心から)、この音楽の編集者に、少なくとも「正しい」編集上の臨時記号の導入によって、彼らの音楽の一部を奪わないように、彼らが出会うすべての関係を抑制しないことをお勧めしたい。 |