| Musica Ficta4 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| p19 CHAPTER II p21 現代の表記法との唯一の重要な違いは、「完全」long,breve、semibreveが、現代のように付点がついていないということである。 たとえば以下のような局面は― 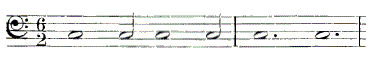 t tここでは、付点付きのsemibreves(ここでは全音符)は、付点なしのものとは区別されている。完全かそうでないかの見極めの回答は、内容にそって判断されねばならない。ちなみに、((現代譜での)局面は、(当時では)以下のように書かれていたことだろう。 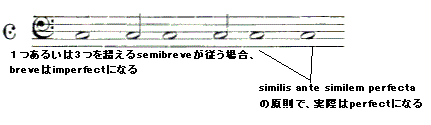 二分音符=minim p22 [3,2]に対するimerfectionの規則 1 別のbreveあるいはbreve休符が従う場合、breveはperfectとなる。similis ante similem perfecta 2 2,3のsemibreveが従う場合、breveはperfectになる。 3 1つあるいは3つを超えるsemibreveが従う場合、breveはimperfectになる。 http://machikun.la.coocan.jp/apel2.htm http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html http://maucamedus.net/franco/franco-ex01.html 音符や休符は、それゆえ、その内容に応じてある程度、音価において減価されることだろう。ただし、額面においては、その下の次の音符よりも音価が高いままである。 それゆえ、"tempus perfectum,prolatio major"では、通常、breveは9つのminimに等しく分割され、音価は7,6,5,4minimsに減価されるが、3minimsの音価とはならない。なぜなら、そうなると、1semibreveと等価になるからである。 ファクシミリと"Vince con lena" (p60)を比較すれば、第6小節のテノールで6拍に減価されたbreve、第7小節のテノールで5拍に減価されたbreve、そして第8小節の2つの上声部で4拍に減価されたbreveの例が見られるだろう。 ”similis ante similem non poteste imperfici"の規則は、計量記譜法の音楽をtrasncriptionするにおいて、一定の困難のある不合理な結果を導く。作曲家が以下のようなものを書きたいと思ったとする。 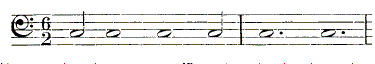 だがそのために↓のように書くことはできない。 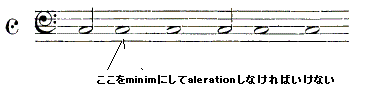 なぜなら、この正確な規則では、最初のsemibreveが2拍ではなく3拍になってしまうから。困難をまぬかれることができる唯一のやり方は、こうしたケースにおいては、ここをminimとして書いて、しかし演奏では2倍化すべきなのであり、この音価の2倍化のことをラテン語で”alteratio"と呼ぶ。それは、当時知られていた技能用語であった。 このような手段から生じると予想される混乱は、もしも音符が3拍子の2番目の拍に当たらず、次のより高い額面の音符にフォローされるのでなければ、音符は”altered"されない、という事実によってかなり軽減される。 p23 これらにはもともと、その使用の必要性が生じた状況があり、それは常に、限定的であった。"alteratio"の例は、p102の第3小節(treble),第4,7小節(コントラテノール)、そして第8小節(テノール)等で見られる。 <punctusについてhttp://machikun.la.coocan.jp/apel2.htm参照> 計量記譜法において、punctusは、以下の3種類で使われている。 ①punctum augmentationis(punctus additionis ) これは、近代の付点と同じであり、その通常音価にその半分を加えることである。それはむろん、”不完全”音符(2拍)に対してのみ適用され、”完全”音符には適用されない。 それを識別することの唯一の困難は、付点音符は必ずしも、より短い音価の1つによってフォローされるわけではない、ということである。なぜなら、タイでつながった音符は当時、なかったからである。 ゆえに、  は、15世紀では以下のように書かれたことだろう。 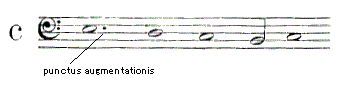 ②punctum perfectionis ”punctum augmentationis”と異なるのは、それが”完全”音符(すなわち、拍子記号にしたがって完全となる音符))に適用されることである。もしも付点がなければ、それらは、内容に応じて、不完全で表現される。 ③punctum divisionis これは、3拍子をその他から分けるために使われていて、計量記譜法をtrascriptionする最大の手助けとなるものである。ゆえに、以下のフレーズは  もしも規則が厳密に解釋されれば、2番目のminimがartelatioされて2倍化され、通常は以下のようになるが、  もしも2つのminimの間にpunctum divisionsが入れば、作曲者の意図通り、以下のようになる。 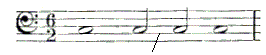 同様に、以下の厳密な解釈は  本来、規則によれば以下のようになるが、 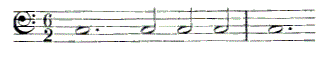 もしもpunctum divionisが最初のminimの後に入れば、3番目のminimが”alteratio"化され、以下のようになる。 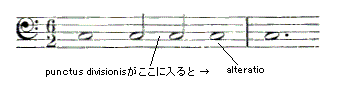 p27 CHAPTER III この初期の時代の音楽を概観すると、多くの粗野さと古風さが目につく。通り一遍の調査では、それを公にする有用性についてのいくつかの疑問を導くかもしれない。1400年~1440年の音楽の評価をするには、十分な素材がない。 p38 我々はもはや、これらの連続五度や三度を伴わない無数の三和音について、言うことはない。もしも我々がデュファイや彼の同時代人を評価しようとすれば、それらを寛容することを少なくとも学ばねばならない。 転回した三全音として使用されるような、不完全三和音が使われていることはほとんど期待できないが、まったくないわけではない。  上記は非常に興味深い。なぜならそれらは、musica fictaの適用の効果ではないからである。臨時記号は、オリジナルな写本において存在する。 和音の第2転回形は、一般的には、近代のものと考えられているが、しばしば生じている。あたかも不協和音のように、時には準備され、時には準備なく。 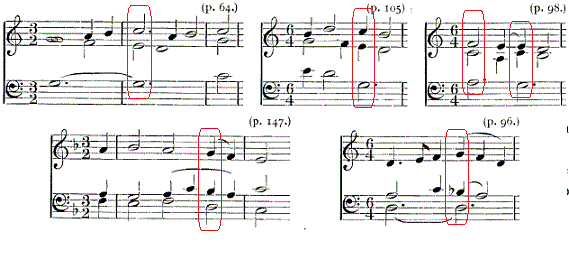 p39 ドミナント上の6/3和音(第一転回)は、ドミナント十三度の性質を取りながら、一般的な嗜好となっている。それぞれ準備されたりされなかったりしながら・・・ 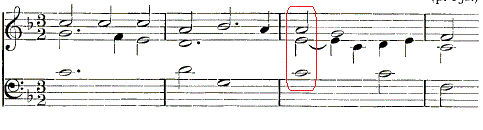 和声の真のドミナント的性格は、ときどき、よりマークされている。すなわち・・・  六度がバスにおいてあると、ドミナントの短二度が、時々それとともに聴かれる。  (略) p41 我々は、時々、主音の全音下の一般的和音の使用に出会う。すなわち、  七度のこの和音のバスは、不完全三和音を避けるために、♭化されていない。この進行は、地震のために好まれ、ほとんどその後2世紀半にわたって、教会音楽やマドリガルの作曲家らによってしばしば採用された。それは、英国の教会音楽においてさらに長く生き延び、いまだ続いている。それは時々顕著な効果を伴って使用されたが、そのために古くからのつながりが重要である。 この初期の時代のカデンツは、千差万別で、興味深い。これらの形式の大きなヴァラエティは、我々に考えさせる。我々が、この後の時代において、祖先からのヒントが得られるかどうかを。 我々のカデンツのストックは限られている。我々は、ドミナントからトニックへ、サブドミナントからトニックへと進む。 前者のケース(ドミナントからトニック)は、17世紀初期から一般的に使われるようになったが、それは他のすべての形式のリズムに取って代わることになった。17世紀においては、このカデンツを聞くだけで喜びが生まれたことは、明らかである。そのため、作曲家は一連の短い「periods」を順番にフレーム化した。聴き手にそれらのお気に入りの終止を提供するために。 これは、17世紀末や18世紀初頭に流行した作品の”scrappy"なパッチワーク様式を説明する。英国音楽は、この様式の採用で大いに苦しんだ。当時の教会音楽(アンセムやcanticls)は、しばしば、結びつきのないセンテンスのstringのみから構成される。我々にとって、統一性の欠如は退屈で悩ましいが、我々の先祖たちは、その正格終止の繰り返しにまったく満足していたのである。 p42 最終和音の三度が注意深く排除されていたことに注目されたい。かれらは、純粋な五度を聴く喜びが、三度のような新しい音程の導入によって傷つくことに耐えられなかったのである。最終カデンツにおけるこうした三度のomissionが、18世紀の初めに至るまでの英国教会音楽に慣習として残っていたことは、興味深い。 最終和声で三度を避けるためのしばしばスキップやジャンプが行われたことを考慮することは、驚くべきではない。以下に近代形式のものを示す。  以下は、そのスキップやジャンプの一般的形式である。 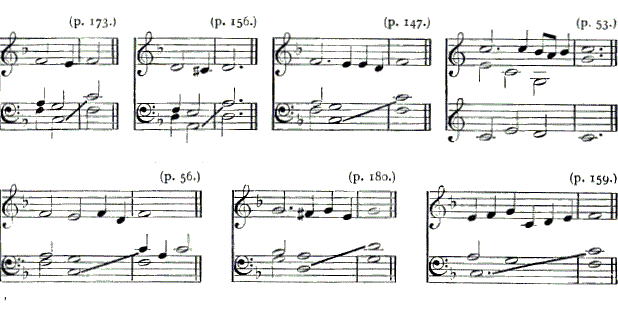 しかし、好ましいカデンツは、最低声部が、一般的にはテノールだが、最終音符に向かって二度低下する進行である。  p44 多くのケースで、下方のパートには1つの調号があるのに、上方の器楽あるいは声楽パートには調号がないという、興味深い事実に読者は気づくことだろう。この明らかな理由ははっきりしないが、以下のような説明ができよう。 純粋なプレインソングでは、よく知られているように、♭記号の導入は、一般に、旋法が移調されたことを示している。厳密にいえば、臨時記号ないということは、音楽が書かれたその旋法のままであることを意味している。なぜなら旋法は、natural scaleにおいて示されているからである(C fa utの自然なヘクサコードで示されるように)。 しかし、臨時記号の♭は、旋法が移調された折に、全音と半音の適切なつながりを維持するために必要となるが、♭は、要求されるがままにそれぞれの音符に対して書かれていた。こうしたやり方は、トラブルを避けるためとはいえ、非難された。 初期のポリフォニー作曲者らは、署名を使うにあたって、ことさらに言い訳が必要だったと考えていたものと想像する。彼らが祖先に”言い訳する”ための唯一の方法が、少なくとも1パートのみを、署名なしにしておくことだったのである。その他のパートは必要のままに署名を残した。 時代遅れのシステムの残存とそれに取って代わったより良いシステムとの共存が許容された事実は、愚かに見えるが、デュファイの時代の1世紀半後のマドリガル文学の精査は、調性のフル調号化のための”訂正”を考える必要はない、ことを示した。最後の導音が、どこにでも生じるような形で、付加されることによって。 1760年と1778年の間にDr.Boyceによって出版されたカテドラル音楽の標準的コレクションにおいて、Adurのアンセムは、2つの♯記号で書かれた。導音は、ことごとく臨時記号のマークによって示された。 私は、これが、デュファイが伝統的敬意のもとで、彼の作品の少なくとも1パートをそのままにしておいた、調号への同時期の反感から起こったと仮定することにはやぶさかではない。 |