| The Role of the Parisian Sequence in the Evolution of Notre-Dame Polyphony2 By Margot E. Fassler |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | |
| 前ページへ |
| <セクエンツィア「O Maria stella maris」の分析> 12世紀にパリで栄えたリズム的な詩の特定の様式によってパリのセクエンツィア作曲家に提供された多くの可能性は、例を見ることによって理解されよう。作品自体の中で、このレパートリーに見られる歌詞と音楽の密接な関係が考察される。44。 分析のために選択されたセクエンツィア「O Maria stella maris」は、間違いなく12世紀の前半に、おそらくノートルダム大聖堂の前任者、そして後にはAbbey of St. VictorのカノンになったAdamによって作られたものである。 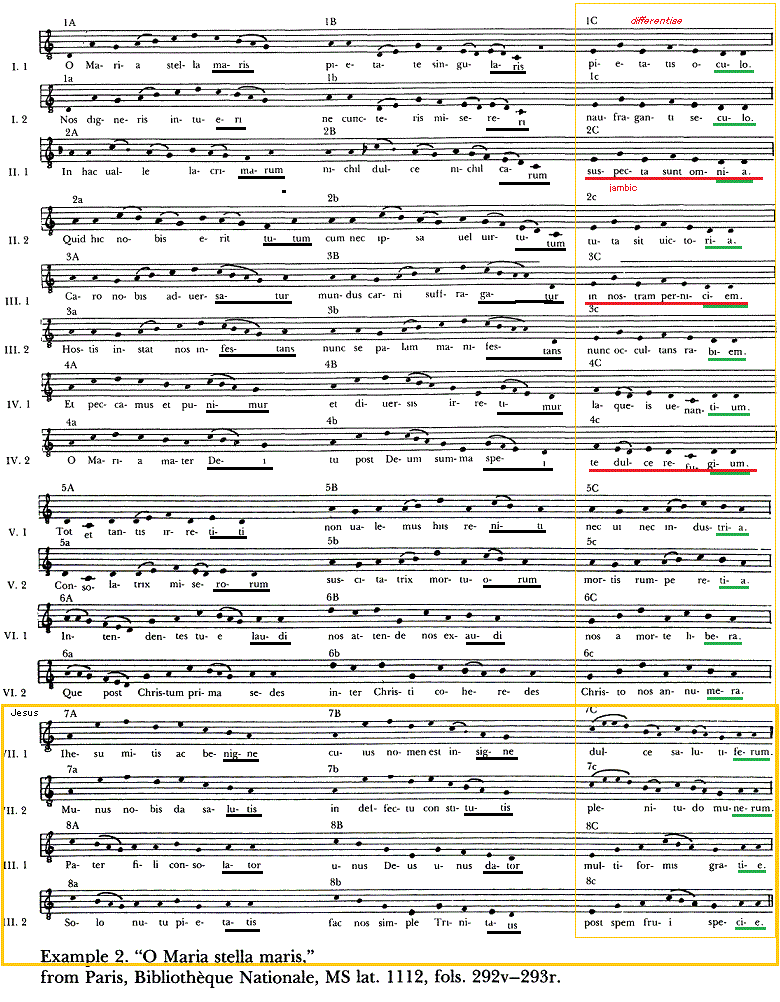 この作品は、古典的なパリのセクエンツィア様式の例である。それぞれの完全にバランスの取れたストロフは、2つの韻を踏む連句で構成されている。パリのセクエンツィアでは事実上常にそうであるように、個々のストローフィの押韻連句には同じ音楽が設定されている。したがって、各メロディーフレーズは2回使用される。45 45この手法は、初期のセクエンツィアに特徴的なペアのカプレット構造を保持しているような錯覚を引き起こした。 p361 「O Maria stella maris」は、John of Garland が「"spondaic with iambic variation."と呼んでいたものである46。バリエーション(John of Garlandによればdifferentiae)は、各ストローフィの第3,6行目(各c)に生じる。 バリエーション行は、8シラブルではなく7シラブルとなっている。詩全体は、7シラブルで定期的に発生する(バリエーション)行を除いて、執拗にトロカイックであるが、ライン全体にiambic castを与える試みも時折見られる47。 47 In strophes 2, 3, and 4, one finds the following exceptions to the trochaic pattern of word accent: Suspecta sunt omnia In nostram perniciem Te dulce refugium. セクエンツィアの歌詞は、有名な9世紀の賛美「Ave maris stella」のパラフレーズとなっている。そのセクエンツィアの音楽は、この賛歌のメロディーにバリエーションに伴ったテーマとなっている48。 歌詞と音楽の始めには、共通の目標がある。新しいイディオムを表現、伝達している。これは、すべての中世の賛歌の中で最も愛されているものの1つである。49 オープニングのメロディーユニットは賛美歌旋律からほぼ正確に借用されている。作曲家は、賛歌の2番目と3番目のフレーズを1つのフレーズに融合することにより、4フレーズの賛歌を3フレーズのメロディーに変えた。 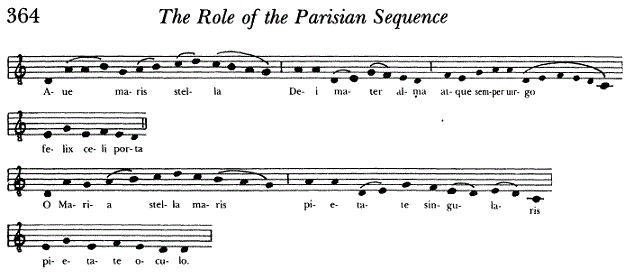 さらに、セクエンツィア作曲家が従ったこの賛歌の特定のバージョンは、明らかにパリでの使用のものでしあった50。 50 The Parisian version of "Ave maris stella" is taken from Paris, B.N. lat. 10482 作曲家によって作成されたバリエーションは、メロディーの最初のステートメントと密接に関連している場合も、非常に自由な場合もある。 この人気のあるシーケンスの作曲者、おそらく詩人のアダムは、他の方法でもメロディーを歌詞に結び付けている。音楽はドーリア旋法であり、このスケールの正格と変格の両方の領域とその音色システムを探っている51。 p364 歌詞の焦点は、最初の6つのストローフィの聖母マリアにある。最後の2つのストローフィは、イエスに注意を向けている。ここでも音楽が変わる。調性は劇的に上向きにシフトし、高音域に集中している。実際、「O Maria stella maris」のフレーズ7Aと7Bは、オープニングメロディーの大まかな移調となっている。音楽はマリアとイエスの同一性と違いの両方を強調し、後者により大きな栄光を与えている。 音楽は詩全体のテーマと構造を支持し、強調するだけではなく、また、その行とストローフィの構造を反映している。 3行のハーフストローフィごとに、最初の2行は韻を踏んでおり、アクセントパターンとシラブル数は同じである。各ハーフストローフィの3行目は、新しい韻を導入し、強弱強のカデンツを持っている。 音楽はこれと同じデザインで作曲されている。フレーズAとBは何らかの形で互いに平行している。ほとんどの場合、これらの関連するフレーズは類似した旋律の輪郭を持っているが(フレーズ3Aと3Bおよび4Aと4B)、異なるピッチレベルで類似した素材を含むこともある(フレーズ5Aと5B)。52 ただし、Cフレーズは通常、任意の行のAまたはB位置にあるフレーズのタイプとは異なっている53。 53 Cフレーズは、一種のルフランを形成するように、パリのセクエンツィアの特徴として、よく似通っている。パリのセクエンツィアには、韻を踏む、アクセントのあるカデンツを強調する、(レレやララのような))終止部分の繰り返しの音符群にはより低めの隣接音符が先行している、などの特長がある(ドレレ、ソララ)が、このセクエンツィアの作曲家は、賛歌の最後の行の旋律の動きに従おうとしただけで、このセクエンツィアでは、こうした規則は厳密には守られてはいない。 各メロディーユニットには、他のすべてのユニットとは一線を画す独自の特性がある。それは、特別な方法で元の曲に関連している。それでも、作品全体を通して、Aフレーズは最初のAフレーズの輪郭を反映するように設計されており、Bフレーズは、フレーズ1Bと同じように、下向きに急降下し続ける(以下のフレーズ2B、3B、4B、および8Bを参照されたい。)Cフレーズは単純なカデンツ公式である。もちろん、AフレーズとBフレーズは、セクエンツィアメロディーの最初のユニットを超えて賛歌旋律を継続しようとするため、互いに平行している。 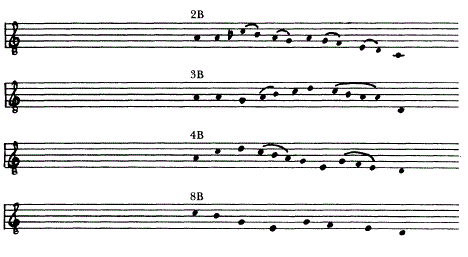 p365 しかし、連続するAフレーズとBフレーズが関連するメロディーのセクションは、多くのパリのセクエンツィアメロディーでは、一般的である54。Cフレーズは、ほとんどの場合、パリ風様式の、ある種のルフランとして機能している。 54 セクエンツィア全体を通して、AフレーズとBフレーズが類似するというこの傾向は、パリのレパートリーの他の多くの例に見られる。St. Victor修道院では、セクエンツィアレパートリーにおいて、一種のメロディ文法が開発されていた。このセクエンツィアはその原則の1つであった。このように、行内および作品全体におけるフレーズの位置は、後のSt. Victorのレパートリーにおいてさらに大きな意味を持つようになったのである。 この作品を見て、私は、パリのセクエンツィア作曲家らが音楽に対して設定したテキストの構造と音を強調する典型的な方法のいくつかを指摘した。しかし確かに、音楽はテキストを反映するように意図的に作成されているので、(そのために)詩の音を変形させ、形を変えるようにも設計されている。 リズム的なラテン語verseを読む時には、アクセントのパターンと韻を踏むリズムを強調する傾向があり、単調な歌唱効果を生み出す。このタイプの解釈は、中世の美学を裏切っいて、リズム的な詩が歌われていた。その音楽の最も偉大な作曲家ら(12世紀のパリ楽派)は、verseの単調な表現に逆らうようなメロディーを作成した。 パリの作曲家らは、アクセントのパターンや強くマークされたカデンツに違反することがよくある。彼らはしばしば、作品のいくつかの点においてのみ、そうした違反をするような詩と音楽の間に類似点を設定しているのである。彼らは執拗な、動きのある詩を保っているのだ。 セクエンツィア「O Mariastella maris」には、アクセントのずれの例がいくつかある。つまり、メロディーの形によって、テキストのアクセントが妨げられる場所の例である。 たとえば、最初のストローフィでは、賛美歌旋律から継承された、テキスト的に弱シラブルを強調する傾向が持続している。フレーズ1Aでは、テキスト的にはトロカイックであり、「a(ラ音)」までの跳躍により、行の2番目のシラブル「Maria」が最初のシラブルよりも音楽的に強くなる。 アクセントとictusが2番目のシラブルに当たる「Maria」の設定では、作曲家は弱い「g(ソ音)」(技法的にはドリア旋法の朗唱音である強いピッチ「a」(ラ音)を修飾する隣の音符)を供与している。 p366 アクセントが最初のシラブル(強-弱)にある「stella」の設定では、作曲家は「c(ド音)」から、旋法においてもっとも重要な音である、強力な「d(レ音)」(弱-強)としている。しかし、フレーズ1Bと1Cでは、テキストのアクセントを置換することなく、強調をしている。 フレーズ2Aでは、テキストの強くマークされた韻を踏むカデンツは、テキストのアクセントとはぶつかる音楽によって変形され、そうした設定によって隣接音を弱めることにより、アクセントのあるシラブルを弱めている。 ただし、フレーズ2Bでは、作曲家はこの変形を「修正」し、テキスト的カデンツと音楽的カデンツが完全に一致するように、メロディのカデンツを変更している。こうした頻繁な変位はパリのスタイルの一般的な特徴なのである55。 55 この議論で私が「強」と「弱」とラベル付けした音は、必ずしも12世紀の耳にはそのように聞こえたとは限らない、ということに異議を唱える人もいるかもしれない。しかし、旋法の終止音とその朗唱音がパリのセクエンツィア音楽に強力な極性を形成したという事実を否定することはできない。これらのピッチに対する弱い隣接音の概念は受け入れられよう。三和音の構造に関するパリのセクエンツィアレパートリーにもまた、否定しようがない強調があり、最終音または朗読音のいずれかに基づいて構築された三和音のメンバーであるこうしたピッチを際立たせる傾向がある。「三度のチェーン」とそれに関連する概念、D旋法とG旋法でのそれらの異なる動作原理の説明については、Leo Treitler、「The Aquitanian Repertories」、1:32-45を参照。 パリのセクエンツィア音楽は、ほとんどの場合、テキスト的アクセントを強調するように設計されているのだが、すべての曲でこの規則には多くの例外がある。こうした変位は、verseの強力なリズム的なグリッドを絶えず曲げている。 音節数、行の長さ、ストローフィの形、アクセントパターン、および韻のこのしっかりと構築されたグリッドは、パリのセクエンツィアとconductusの作曲者らを確実に制御および制限した。しかし、それはまた、彼らの芸術のための枠組みを提供した。それは、これまでこうした程度で、このような方法では存在したことがなかったものである。(訳注;古典派時代のソナタ形式のようなものかもしれない) たとえば、「O Maria stella maris」の作曲家は、いくつかの段階にもとづいて、彼の音楽を作り上げた(ここではその一部のみを説明する)。彼はバリエーションとともに主題を書いた。音楽はテキストとの密接な関係によって常に位置付けられているため、これは非常にうまく機能する。 AフレーズとBフレーズの微妙な違いは、各ハーフストローフィが作曲家にAフレーズとBフレーズを相互に関連付け、1Aと1Bの元の旋律の形に戻すためのテクニックを探求し続けるための新しい状況を提供するために、非常によい結果となる。 この微妙な変化は予測でき、それは喜ぶべきことである。たとえば、ストローフィ2から4では、AフレーズとBフレーズの始まりは同じだが、いずれの場合でも、Bフレーズは、関連するAフレーズとは異なる方法で終止している56。他の点では類似しているAフレーズとBフレーズの違いは、テキストが一定で不変の形状であることによって、浮き彫りになるのである。 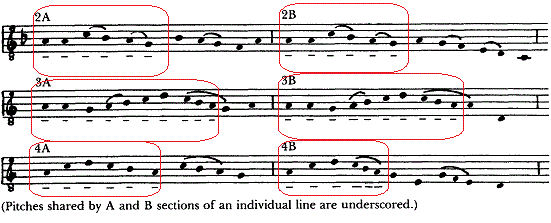 56「Musical Syntax」で、Treitlerは、パリのセクエンツィア音楽の分析で、 antecedent-consequent pairs やバール形式(AAB) の考えを、賢明に紹介した。 それを何と呼ぼうが、パリのセクエンツィア作曲家らは、類似したメロディーフレーズのペアを作成するというアイデアと、それらを関連させながらも非類似性を保つための探索手法を採用した。ただし、メロディーライン内およびセクエンツィアメロディー全体の形状内での各フレーズの位置が、同様に重要であった。 p367 作曲家はまた、古いパターンから新しいメロディアイデアをスピンオフし、それらを実行している。たとえば、リズムフレーズ4Cには、セクエンツィア音楽のストックカデンツ公式である4つの最終音符が含まれている。ストローフィ4を終止するためにそれらを残す代わりに、作曲家はそれらを拾い上げ、この短い動機をフレーズ5Aの始まりと(移調で)5Bにつなげている。57 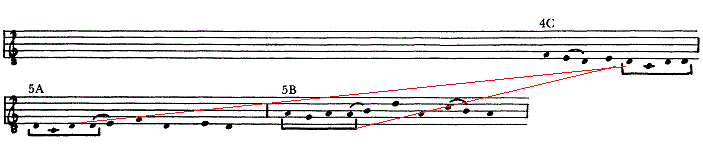 57 実は、メロディーユニット5が「O Maria stella maris」の作曲家によって最初に書かれたのかどうかを言うのは難しい。これと同じ旋律ユニットは、教会建立の祝日のためのパリのセクエンツィア「Quam dilecta tabernacula」においても見られる。しかし、「O Maria stella maris」の「Quam dilecta」からの借用の場合でも、「O Maria stella maris」の作曲家は、慣れ親しんだ動機を利用して独自の音楽的アイデアを開発したと考えられる。 12世紀のパリのセクエンツィア作曲家らは、音楽が展開される高度に構造化された状況のおかげで、フレーズ開発と相互作用の技術を、洗練された新しい高みに運ぶことができた。 最後の例は、「O Maria stella maris」の作曲家が、不撓にリズム的な詩の枠組みを、彼のメロディ的な創意工夫の箔としてどのように使用したかを示している。 「OMariastella maris」の降順メリスマ終結句1Aは、パリで使用されていた賛歌旋律とセクエンツィアメロディーの両方の特徴である。このフレーズの「g(ソ音)」で終わるカデンツは、(「a(ラ音)」まで戻る)"Ave maris stella"のパリ版から区別される。多くの地域では、この特定のフレーズのカデンツは、メリスマの後に「a(ラ音)」まで戻っている。 "O Maria stella maris" では、フレーズ1Bはそのまま、、「a(ラ音)」をピックアップしている。 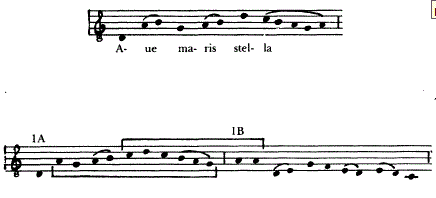 p368 フレーズ3Aでは、作曲家はフレーズの終わりで「a」に戻り、テキスト行がフレーズ1Aと1Bの間に生じた区切りを置き換えている。フレーズ3Bはフレーズ1Bと同じように始まっているが、フレーズ1Aと1Bによってもともと確立されていたテキストと音楽の関係は、フレーズ3Aの最後の「a(ラ音)」によって破られている。 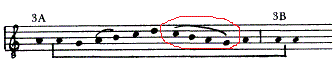 フレーズ4Aでは、カデンツフレーズは1Aと同じであるが、作曲家は、メリスマのグルーピングを変更している。 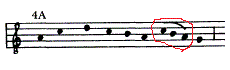 フレーズ6Aでは、フレーズが再度生じている。ここでは、作曲家はフレーズの最後に2つの「a」を使用し、フレーズ3Aのメロディックなバリエーションを反復するが、メリスマはさらに、行の冒頭の方から始まる。 。 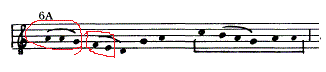 フレーズ8Aでは、フレーズ1Aは一種の逆行バージョンで生じる。おなじみのカデンツフレーズが最初に来る。行の始まりで繰り返された「a」の特徴がフレーズを終了している。 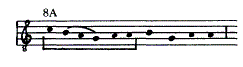 この微細なカデンツフレーズの発展は、テキストによって提供されるフレームワーク内で発生するため、特に効果的である。作曲家は、フレーズのリズム的な位置を簡単に破り、テキストによって提供される「小節線」全体にフレーズを横切らせてしまう可能性がある。セクエンツィアレパートリーで発展されたリズムパターンと旋律の形の間の絶え間ない相互作用は、ディスカントクラウスラと13世紀のモテットの芸術に不可欠になった。 <フィレンツェ写本への影響> この分析は、1つのレパートリーからの1つの作品だけであるが、すべてのパリのセクエンツィアに共通の思想を発展させている。ある種のパリのconductusもこれらの様式の特徴を共有している。フィレンツェ写本の第11冊子からのconductusは、その様式において、12世紀のセクエンツィアにいくぶん似ている。第10冊子からのconductusは、それほどではないが。58 58 F写本のこれら2つの冊子には、それぞれ非常に異なるタイプのconductusが含まれている。第10冊子の詩は、第11冊子の詩よりも長く、音楽はメリスマ的で精巧である。第10冊子には、風刺的で政治的な詩があり、他の写本と多くのconcordancesが見られる。対照的に、第11冊子のconductusは、ほとんどの場合、シラビックに設定されている。それらは、ほとんどの場合、ロンドー形式であるため、ルフランを持っている。他の写本との一致はほとんどなく、それらの作品は宗教的であり、典礼に使用する価値がある。 1 (f. 1-13): 6 four-part works and 9 three-part clausulae; 2 (f. 14-67): 26 organa, 5 clausulae, 1 organum, 1 clausula, 1 organum, all a 3 ; 3 (f. 65-98) : 32 organa from the magnus liber organi de antiphonario, 7 Benedicamus, 8 Domino clausulae, 4 Benedicamus and 3 more organa, all a 2 4 (f. 99 -146): 61 two-part organa from the magnus liber organi de graduali; 5 (f. 147-184): 462 two-part clausulae; 6 (f. 201-262): 59 three-part conductus and 2 four-part conductus-motets ; 7 (f. 263-380): 130 two-part conductus; 8 (f. 381-398): 26 three-part conductus-motets (25 in two-part score followed by the T + 1 in three-part score) ; 9 (f. 399-414) : 40 two-part and 3 three-part motets written in separate parts ; 10 (f. 415-462) : 83 monodic conductus; 11 (f. 463-476): 60 monodic Rondelli. As compared with W1, F often employs a breve shape instead of a long in unison passages, while the opening tuning-note is written as a double long instead of 2 unison longs. p369 セクエンツィアレパートリー(および、程度は少ないが、フィレンツェ写本のconductusレパートリー、特に第11冊子のレパートリー)では、このレパートリーにとって自然なように思われるデクラマシオンの自由のために、歌詞と音楽の間の微妙な関係が可能であると結論付けることができる。作品にモーダル拘束衣を付けると、歌詞と音楽の美しい相互作用が損なわれる59。 一方、アクセントは、歌詞と音楽の両方、および2つの芸術間の相互作用において非常に重要であった。リズムは、これらのレパートリーでは、一方ではictusまたは拍子子と、他方ではフレーズ構造(テクスチュアルおよびメロディック)の間の相互作用として定義されることになる。拍子子は作品全体の構造の根底にあるが、音楽はかなりの程度に、歌詞はある程度に、所与の作品のさまざまな場に似つかわしくないくらい自由がある。 3. THE PARISIAN SEQUENCE STYLE AND NOTRE-DAME POLYPHONY Sarah Fuller と Leo Treitlerの両者は、南フランスのリズム的な詩が、同じ地域のポリフォニックレパートリーに大きな影響を与えたことを実証した60。 そこにおいては、リズム的な詩とその音楽の美学とポリフォニックなレパートリーとの間の同様の相互作用がノートルダムで起こったと主張されてきた。 p370 12世紀の間に、パリのセクエンツィアと conductus の作曲家は、フレーズや並置された旋律のバリエーションを開発するための強力なリズム的なグリッドまたはフレームワークを持つことに慣れていった。 彼らは自分たちの芸術の力によってフレームワークを曲げたり形を変えたりすることに喜びを感じた。当然のこととして、彼らは彼らのメロディースキルを彼らのポリフォニーにもたらし、同時に、彼らの新しいメロディースタイルの開発を可能にしたおなじみのリズム的なフレームワークをポリフォニック作品に移す方法を見つけた。 私は、パリの作曲家が12世紀後半から13世紀初頭にこの移管を行うさまざまな方法を試し、パリのポリフォニーの最も初期の支配的な様式がこの音楽を「リズム的」にする試みをしていたことを提案したい。 At the close of her study of organum in early-medieval music treatises Sarah Fuller says; この研究はまた、西洋中世音楽理論では、ポリフォニック音楽の支配的な特徴としての韻律が出現するまで、協和音と不協和音の分類的かつ体系的な区別があいまいだったと主張しています。 オルガヌムの理論家が韻律とパターン化されたリズムにこだわるときだけ、彼らは協和音と不協和音の間の音の二分法も強調します。そしてこの順序では、韻律が最初で、協和音/不協和音が次になる。 John of Garlandの影響力のある定式化では、両者の相互作用は、ディスカントと呼ばれたmusica mensurabilisの一種において、最も明確に固定されています。ここでは、時系列の意味で、リズム的なパターンまたは拍子子が先行しています。それは、主に、the initial attackとその後のthe odd-numbered positions(私たちが計量的記譜の始まりとして転写するもの)の協和音を必要とする、協和音と不協和音の適切な配置を導く。相互作用は、オルガヌム種ではかなり異なります。ここで、John of Garlandが説明しているように、リズムと新しい韻律パターンは協和音の機能です。声部間の音の性質は、どの音価がlongで、どれがbreveかを決定する決定的な要因です。61 この一節は、organum purum とディスカントの2つの様式の重要な違いを示しており、これらの違いはポリフォニーの韻律構成に起因すると考えられる。私は、音楽の「リズム的なこと」と韻律構成は同じものではなく、リズム的に時系列の優先順位を割り当てる必要があることを提案したい。 パリでの新しいポリフォニック技法の発展を、モノフォニックレパートリーの馴染みのあるリズム構造をポリフォニックテクスチャに組み込むための着実な前進として見ることが有用である。 パリでのリズム的なテクニックの開発を詳しく説明することは依然として困難だが、パリの作曲家らが始めに、休符、短いフレーズ、および、私たちがセクエンツィア様式の印として見たフレーズ間の相互作用の種類を使用して、 organaのラインにリズム的な形を供与しようとした、と想像できる。 p371 以下の例は、レオナンの様式のorganum duplumからのものである。学者たちは、作品を転写する際の上声部の特定のリズムについて意見が分かれるであろうが、この音楽をどのように転写するかに関係なく、パリのセクエンツィアの4拍子子のラインを彷彿とさせる、多くの休符と多くの短く明確なフレーズが上声部にあることは明らかである。62 62この様式に共通する4拍子子のフレーズのいくつかの例とそのリズムの解釈については、Ernest Sanders、「Consonance and Rhythm in Organum」、Journal of the American Musicological Society 33(1980)、272-73を参照。サンダースのトランスクリプションが示すように、そのようなフレーズはしばしば第1モードに容易に分類される。しかし、初期のパリのソースからのorganaで見つかった音楽の多くは、そのようなきちんとしたフレーズのグループに分類されたり、モーダル転写に納得のいくものではありません。したがって、W1からのorganaのWilliam Waiteのトランスクリプションはモーダルであるが、多くの学者は現在、より自由なトランスクリプションが12世紀の慣習により忠実であると信じている。 より初期の華やかなorganaのラプソディックで非常にメリスマ的なスタイルがこの音楽の途中経過である。さらに、このポリフォニーでは、流れのリズムに重点が置かれ、協和音程への動きでそれを強くマークしている。さらに印象的なのは、フレーズのモチーフの展開である。 以下の例のように、小さなグループのフレーズが素材を共有し、メロディックなアイデアからの作業を含むことは一般的である。これは、1世紀にわたって、セクエンツィアメロディーの短く刈り込まれたされたフレーズで発展してきた手法である。レオニヌスは、この新しい様式の専門知識から、organaの最大の作者と呼ばれていたのだろう。 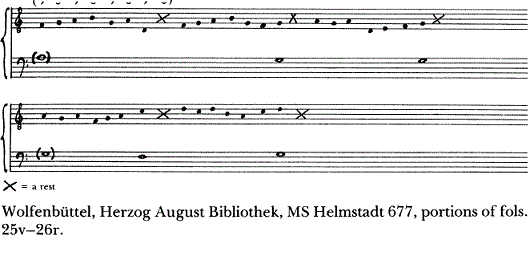 それにもかかわらず、ディスカントは、ポリフォニーを「リズム化」するプロセスがその究極の勝利を達成したスタイルであった。レオニヌスのスタイルのディスカントセクションには、非常に明確なフレーズが含まれている。これらのフレーズも、パリのリズム的な詩の大部分の行と同じように、4拍子子を持つのが一般的である。ペロティヌス世代の後期の音楽であるディスカントクラウスラは、リズム的なスタイルにさらに近づいている。 p372 ここでは、もともとリズム的な詩に触発されたフレームワークの音楽への翻訳を見つけることができる。それらのdiscant clausulae では、パリの作曲家らは、詩の実践からリズム的な流れだけでなく、詩のストローフィまたはクラウズラのリズム的な枠組み全体を引き継いだ。 もちろん、それはある芸術から別の芸術への移行で変化したが、リズム的な詩(または散文)のクラウスラの本質的な特徴の多くは、パリのディスカントのリズム的なクラウスラにまだ存在している。しかし、歌詞はありません。つまり、リズム的なフレームは、音符だけで存在するようになったのである。 フィレンツェ写本のdiscant clausulaから抜粋した以下の例では、セクエンツィア様式の2つの必須要素は、分離されており、個々の声部によって支配されている。流れを形作り、執拗なトロカイックな拍子子を提供するための歌詞はもはや存在しない。  代わりに、下声部、つまりテノールは、一貫してパターン化されたリズム的なフレーズでictusまたは拍子子を作っている。上声部は拍子子に合わせて動き、セクエンツィアの流れの自由度を制御することで、常に、まさに、それとテノールの間の和声関係を懸念しながら、モチーフの関係を発展させている。 John the Grammarian が説明したように、リズム的な詩を書く芸術と、discant clausulaを作る当代的芸術との間は、パラレルになっている。 John the Grammarianは詩のリズム的な枠組みを強化し、ictusや拍子に新たな優先順位を与えた。彼はまた、可能な限り韻律的な詩の観点から彼の作品を説明することを選んだ。彼の行は、iambic or trochaic(彼の用語では(spondaic)のいずれかであり、これらの韻律様シェーマを、単にカデンツに適用するのではなく、行全体に拡張したいと考えていた。 John of Garland the theoristや彼の同世代の若い文法家は、ディスカントを記述することに力を注いだ。彼は拍子子またはictusを協和音と不協和音に関連付け、これを行うために音楽の流れを構成するためのシステムを持っていた。彼の流れは規則的で、パターン化されており、リズム的なモードと呼ばれるロングとショートのシステムによって支配されている。 文法家と理論家の両者が、彼らのシステムに正確に適合しない流れを何と呼ぶかについては、長い説明を要する。どちらも、ディスカントの原則、つまり、緊密に組織化されたユニットを構築し、そのすべての要素で正確に計量化され、ictusまたは拍子の最優先の力によって支配されることに興味を持っていた。63 63 これらの2つの驚くほど独創的な形式の目標間の密接な類似性は、アイデンティティの問題を再び提起する。この問題は難しい問題であり、John the Grammarian の文法的な作品をある程度詳細に研究することをいとわない学者によってのみ取り組む必要があろう。 p373 リズムモードに戻ろう。作曲家がポリフォニック音楽に「リズム」をもたらしたとき、彼らは最初に新しい方法で彼らのラインを形作ろうとした。 12世紀の最初の4分の3では、リズムはおそらく音価とはまったく関係がなかった。ポリフォニーの作曲家(パリや他の場所でも)は、上声のラインを短くし、絶対的な明瞭さで、リズムを定義し始めた。 12世紀の後半には、レオニヌスのオルガヌムとディスカントの両方のパッセージがリズム的な詩のラインのように4拍子のフレーズを使用するようになり、上声のラインがより明確に表現されるようになった。 しかし、音楽は詩とは異なる。拍子またはictusのsharp blowは、それが大きくはないが、より長く見えるようにする強さを持っている。 「オンビート」の持続時間を長くするという考えは、おそらくゆっくりと、ポリフォニーをリズムで歌う伝統がすでに確立されて、初めて生まれた。最も初期のモードとしての第1モードの現在の理解は正確であるように思われる。リズム的な詩の強弱アクセントのパターンがロング-ショートに変わったことは、言うまでもない64 私たちの証拠は、完全に発達したリズムモードのシステムが、レオニヌスの時代のいくらか後に来なければならないという一般的に信じられている信念と一致するであろう。 モードに言及する最も初期の論文であるDiscantus positio vulgarisは、パリの13世紀半ばの主要なポリフォニックジャンルであるモテットの文脈でそうしていることを物語っています。ディスカントについての議論の中で、著者は長短の音符について論じていますが、モードについては言及していない65。 ディスカントクラウズラの様式が十分に確立されると、作曲家とスクライブは間違いなく音価のシステムを拡大し始めた。ディスカントの行に見られるように、2+1のグループ化を絶えず使用すると、必然的に3拍子の音符への発展となる。 代わって、こうした音符には、その使用を正当化するための説明とシステムの両方が必要になることだろう。リズムモードはそのようなシステムなのである。それらが発展すると、この研究で説明されたものとは非常に異なる新しい美学が、音楽の芸術を追い越し始めた66。 66 13世紀初頭の初期モテットのレパートリーは、新しいパリのポリフォニーの根底にある美的原則をある程度理解した今、新しい観点から見なければならない。最初期のモテットは、歌詞付きのディスカントクラウスラである。それらは作曲家にさらに別の課題を提示した。それは、リズム的な詩を、すでに独自のリズム的な形をした音楽に適応させることです。 p374 この研究は、パリのモノフォニックソースがパリのポリフォニーの研究に本質的に対応するものを提供すると主張してきた。これは、すべてのパリのレパートリーを、それらが作成された歴史的文脈に戻すことを願っている。また、2つのレパートリーを一緒に研究することで新しい知識を得ることができることも示している。これは、結局のところ、写本、典礼におけるそれらの存在の仕方にある。 研究の過程で、私は、詩と音楽という2つの芸術が、12世紀にダイナミックで新しい方法で統合されたと主張した。12世紀のリズム的な詩の影響下で育った母国語詩の偉大な新しい伝統は、ダンテとチョーサーに向かった。パリのポリフォニーの新しい音は、マショーとデュファイの音楽に向かった。 リズム的な詩と音楽は、パリのセクエンツィアのような12世紀のレパートリーで統合された後、13世紀に新たな独立を達成した。一方では、リズム的に複雑でありながら歌詞化されていないポリフォニーが生まれた。その一方で、歌われることを意図していないリズム的な詩がますます一般的になった67。 |