| p29 10. JOSQUIN EXAMPLE これらの考慮事項を念頭に置いて、ここでアルトなしで与えられたジョスカンのアヴェマリア(例2)からのパッセージを見てみたい。ソプラノ、テノール、バスの上昇シーケンス(4シラブル単位のCoe-le-sti-a、te-rre-stri-a、No-va re-plet lae-ti-ti-a)は、当時の対位法取り扱いの常套手段である。 Hothby、Aronらは、[完全] 五度と六度の交互のくさりにおける連続した対位法の2パートの例を提供または説明している(例3)。  例2は、ソプラノとバスがそれぞれ、どのようにテノールと関係しているかというものである。当時の音楽家は誰もが、第47小節において、テノールとバスの間で、同時に響くB-Fの五度は、決して完全音程ではないと考えていた。バスをB♭で歌うことによって、すでに響いているテノールのFに適合するだけでなく、F-Bの三全音もまた回避することができる。それは、同時的完全音程のより大きな利益を達成するのに役立つ場合にのみ許容される。 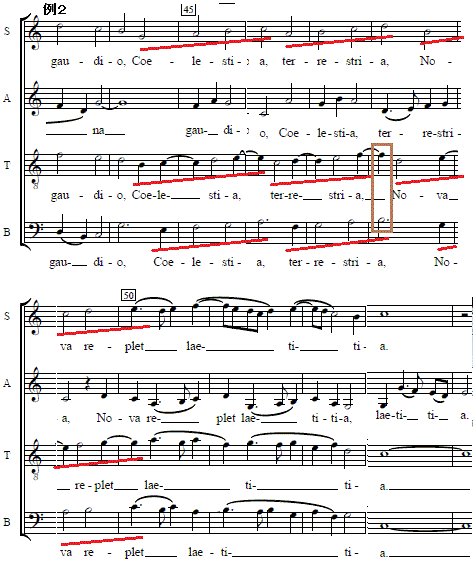 パッセージは、それらの間の優先順位に関係なく、両方の規則の満足度を示している。さらに、リズム的なオーバーラップで慎重に構成されている。(特にここの第47小節のソプラノのB)。不可避的な結果は、例4のように示される。 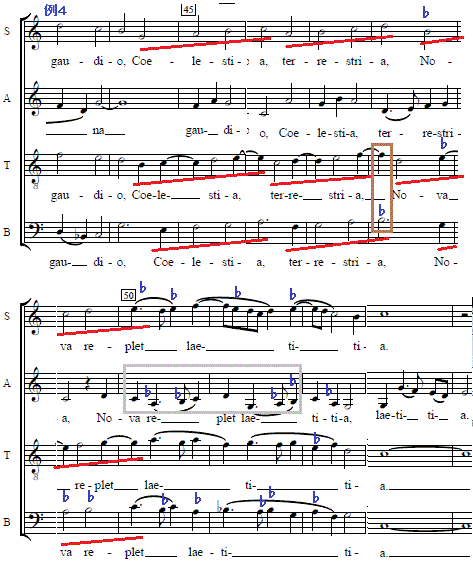 ソプラノが、そのパートだけによって要求されることのなかった何かをすることを強制されるのは、問題の存在とはほど遠く、見られた期待が、聞かれた同時性によって和らげられるときに起こるべきことである。 このパッセージの「従来の」白色音符の解釈においては逆に、バスは、自分のパートだけに直面して、彼がしたくないこと(三全音の概観)を演奏するように求められる。 Josquinのモテットは、上で引用した、三全音の忌避の明確なケースを記すのは愚かなことであるというTinctorisの言と同じ年代の日付であることが論じられてきた。テノールと減五度で歌い、メロディの三全音を作り出すようなバスパートのあらゆる歌い手は、二重のエラーを犯したことだろう。 p32 私は、この解決策は、テキストまたは音楽以外の重要性とは無関係に防御できると信じている。このようなパッセージは、同時代人たちによって、「行楽」として聞かれた程度は、テキストと音楽の関係に関する多くの大規模で重要な疑問と同様に、探求が行われていた47。 Josquinの Ave Mariaのパッセージが、ハ長調あるいは長調作品に対して場違いであり、その音調的安定性を乱すとか、あるいはその全音階主義を裏切るとか言うのは、問題を時代錯誤の用語観点から枠組みすることとなる。 さらに、写本に記入されている「臨時記号」を、本当の臨時記号として認識することで、記譜された記号とは独立して、音楽ケースを構築できる。 Ave Mariaのソースはごくわずか(の臨時記号)しか含んでいない。48 私の議論は、垂直的な完全性を達成するための強力な聴覚的イニシアチブを想定しているために、それは、こうした記号の存在や不在、そしてそれらを含む写本の信頼性によって触知された”偶然的”にぎないことなのである。 48 Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. MS 19は、第43,51小節において、疑いなく、バスはB♭をもっている。(Noblittがその日付を1470年代とした根拠となった)Munich, Bayerische Staatsbibliothek Mus. MS 3154 では、バスパートの♭記号はこのパッセージの間中、B♭記号を持っている。 London, Royal College of Music MS 1070 では、第47小節のバスのBの前に、B♭がある。 例4では、このパッセージの4つのパートすべてを、臨時記号を追加した現代の表記法で示している。 モテットは主にペアの模倣のさまざまな組み合わせや、最小限の4声書法から構成され、第40、94小節(3拍子)および143小節では、ホモフォニックに始まるパッセージが生じている。 これらの句読点的なパッセージはそれぞれ、作品内で、何らかの形で独自なものである。最初のものは、対位法規則の適用を示すためのlocus classicusとして役立っている。この連続したパッセージで、そしてこの作品のこの点で、例2と4とでの3パートにきちんと適合しているにもかかわらず、アルトパートは、テクスチャにそのまま加わった追加として判断される。.49 49 写本におけるアルトの臨時記号は以下である。後の時代のパートブック、Munich, Universititsbibliothek, MS 80 322-5 は、第47小節の括弧内に示されているB♭を記している。 この「fa」記号をそのまま遵守すると、その他のパートの基本的な対位法に大きな混乱をもたらす可能性がある。自分のパートだけを勉強していた演奏者は、この♭を歌っていたかもしれない(記譜されているかどうかにかかわらず、そしてそれを「fa super la」と呼ぶかどうかにかかわらず)。しかし、その前の(第45小節の)ソプラノでのBを聞けば、アルトはおそらくB p33 アルトの状態に関するこの見解に異議が唱えられたとしても、三全音よりも垂直の完全性の優先度を呼び起こすことにより、15世紀の基準の範囲内で、現在の解釈を守ることができる。 p34 以前に存在しなかった三全音を私が導入したことに反対するのは、記譜されたピッチと、ここで問題になった鍵盤楽器で定義された響きの間に相関があると仮定することであっただろう。 このジョスカンのAve Mariaの例では、3声部の対位法の”本質的な”作品が、その作曲と実現性の両方で優先され、アルトができるだけこれらに適合しようとしていた。この実現が出発点となる「規範」はない。声部の優先度に関係なく、これは、垂直的な完全音程と三全音との間の問題である。前者、完全音程が、優先度を持っている。 第50小節から51小節のアルトパートは、その後、JosquinのMass L'homme arme super vocesからAronが引用したパッセージ(例1)と音程的に同一になる。同様ではあるが同一ではない理由のために。 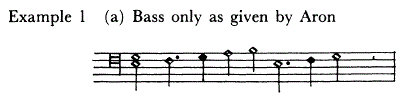 Chromatic Alteration in the Missa L 'homme arme of Pierre de la Rue: A Case Study in Performance Practice3 by William Geoffrey Kempsterp49 この例は、挑発的と見なされるかもしれない。私はJosquinに対し、Lowinskyがしたこととは大して変わらない響きがするものを実行した。 ジョスカンについて結果の表面的な類似性にもかかわらず、私の例の根底にある理由と、Lowinskyの隠れたの半音階的解決の私への部分的受け入れは、彼のものとは明らかに異なる。 Secret Chromatic Artの主な誤りは、それが半音階的ではないことである。したがって、それが隠れているべき理由はなかった。この解釈は、16世紀に知られていた標準によるメロディの進行において完全に全音階的なのである。 11. OBRECHT EXAMPLE Van Crevel は、ここで例6として与えられたオブレヒトのKyrie Libenter gloriabor からのパッセージを提示し、正確に順序付けを行うと、例6(b)でのような、F♭上の最終カデンツが得られることを指摘した。 しかし、彼が実際に出版したのは、6(a)のように、第93小節の最初の拍まではよかったが、”F p35 Lowinskyが言ったように、「van Crevelは、勇み足を恐れて、F♭での終止の可能性に固執しながらも、Fmajorでの終止の解決での妥協を提案した」。 私は、van Crevelの出版のヴァージョンが音楽的に受け入れられないという点において、Lowinskyに同意する。だがLowinskyは、Van Crevelの(言葉で示された)「スパイラル」バージョンも、「F♭」での終止も拒否し続けた。以下の理由で。 (1)F♭でKyrieを終了する歌手は、「FでGloriaを開始するというほぼ奇跡を達成しなければならない」(Fは、演奏の際にfrequencyが決定される) (2)「このような非常に早い時代に、伝統的な調和の概念からの極端な逸脱を正当化するような詩的、感情的、または図像的な自負心はない」。 (3)「C♭、F♭、およびB♭♭の使用が考えられるようになった1505年(オブレヒトの死の年)以前に、このような転調に対応する理論的対応物はない」 (4)Lowinskyによって提案され、van Crevelによって拒否された「隠れた半音階的」転調は、van CreveのObrechtの構築や歴史的称賛に対して、音楽的に優先している。 実際、van Crevel は、Fに”戻る”作品を作る際に、Lowinskyが反対した「非音楽的な」ねじれを避ける「F♭」での終止の可能性を認めてはいる。上記のように、Lowinskyは、Gloriaとのつながりの悪さのために、F♭への終止に反対しているが。 言い換えれば、Lowinskyは、厳密に音楽的ではない理由でスパイラルに反対している。そして彼は、確かに悪くはない和声学的なねじれの理由で、同じfreqencyに戻ることに反対する。 彼は第87〜89小節を受け入れ、その記譜法をタブラチューラのように扱っている。 例6(b)のように、このパッセージは必ずスパイラルでなければならない。 第87小節の記譜されたアルトのEbは、それなしでは何が起こるかを変えることなく、何が起こるべきかを確認する。 FまたはFbのどちらが第89-90小節で使用されるかどうかは、正確なsequenceのclaimがrecta音程関係のclaimに対してどのようにバランスされるかに依存している。 Lowinskyは、歌手たちがF♭でグロリアを開始しなければならないことには反対しているが、Kyrieの終わりの「F♭」がその楽章を調性的に一貫性のないものにすることには反対していない。 frequency安定性を放棄すると、それ(F♭でグロリアを開始しなければならないこと)に反対することはなくなる。 Gloriaは、そのポイント(ピタゴラス音律の半音分低く、さらに、comma調整のために開始点からわずかな周波数差が生じる)で「F」の音で開始し、独自のスパイラルを作成する。 p36 テノールとバスは厳格なカノン(フーガ)であり、繋留的な動機によって、導音を招く。音楽のコンテキストにより、テノールはsubsemitoneを使用できるが、バスは使用できない。こうして、同時に生じる完全五度の高い優先順位を尊重している。 superiusとaltusには、テノール/バスの繋留的な動機の最初の3つの音のみがある。これは、他の考慮事項が許す限り、subsemitoneである。 テノールにおけるように、superiusはsubsemitoneを取っていく。近代譜における最後の拍の部分(と次の小節の最初の拍)のように。ただし、アルトでは、この音は、常に五度高いsuperiusの入りと一致し、アルトがこれらのポイントで半音を取ると、減五度を生成することになる。 このアルトの選択(つまり、上声部間の弱拍でさえ、垂直方向の完全性を尊重し、または模倣動機で導音に引き上げる)は、異なった演奏によって、異なって解決される。ただし、バスはその導音への「引き上げ」することはできない。もしもそのようにすれば、テクスチャの下部で減五度を生成するだけでなく、あらゆる第2拍で(バスと)アルトとの減八度が生成してしまう。または、アルトがバスに対してオクターブとなるように調整すると、低声部間の減五度が生じてしまう。 こうしたケースは、どの点においても、垂直的な特定のsequence lapの維持に依存するのではなく、音楽のそれぞれの瞬間で、垂直完全性とカデンツのsubsemitonesの優先順位をいかにバランスさせるかについて、むしろ独立した決定に依存している。 さらに、一定のfrequencyに関与していなかった当時の歌手たちは、第87-8小節でそのconjuncteを適用しているため、何も起こらなかったように小節89-96を読むことができる。 これにより、第89-90小節でのバスとsuperiusのF♭が得られ、音部記号と調号によって示されるように、musica recta(または実際の旋法)に適切な音程関係が保持される。 「短三和音」は、このようなトランスクリプションを使用する現代の編集者には発生しにくいであろう。それは、個々の音符の”不必要な”余分なinflectionを含んでいるからである。 これがmusica fictaの扱いにとって、あるいはこの場合のように音部記号によって暗示された関係を再開することにとって重要でないことを示したいと思う。 なぜなら、現代の記譜法で必要なフラットは、ほとんどの場合、第88小節での変化の点以降、「fictive」ではないからである。例7のこのパッセージのほぼ白音での移調が示すように。 このバージョンは、現代の記譜法の読者が過度の記譜された臨時記号を抑制することなく、パッセージの音に関する偏見を試すことができるようにするために含まれており、第88小節以降はルネサンス歌手の思考プロセスに近いものを表している。 Musica fictaは、音でも記号でもなく、プロセスを示している。 例6の見苦しいフラットは、相対的なピッチ表記と絶対的なピッチ表記の違いによってのみ必要になる。 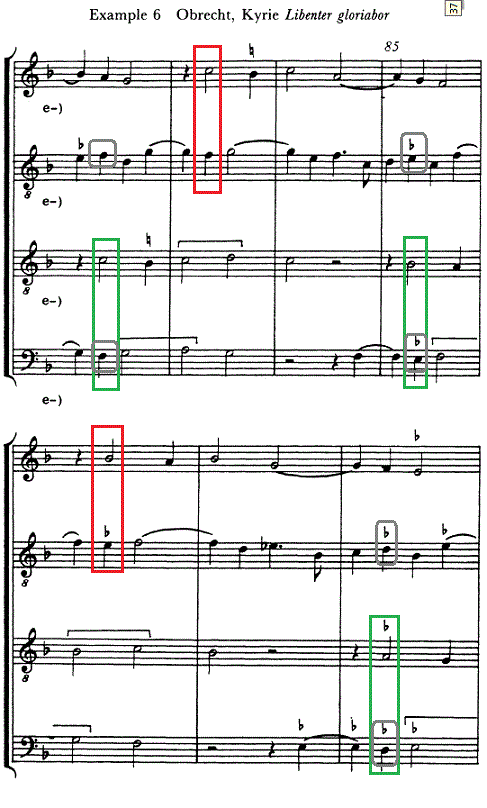 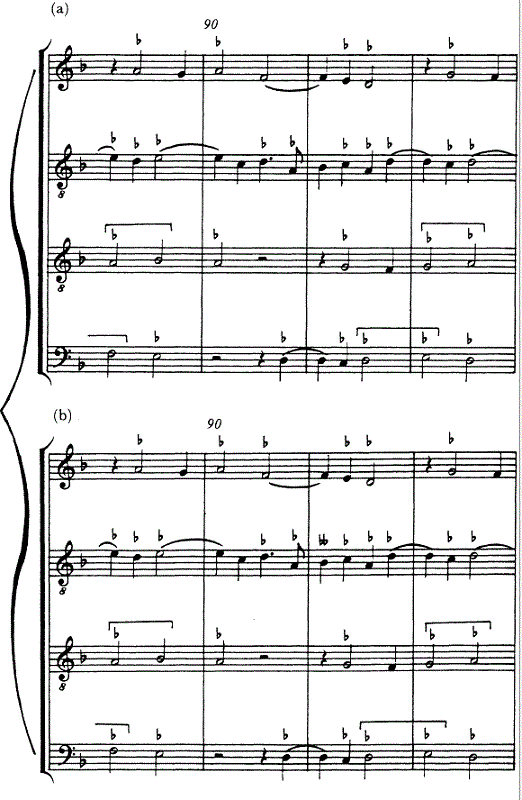 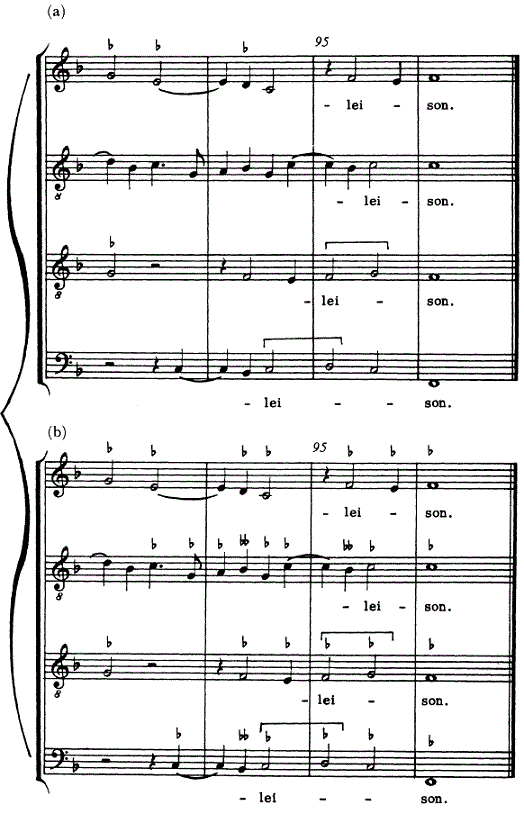 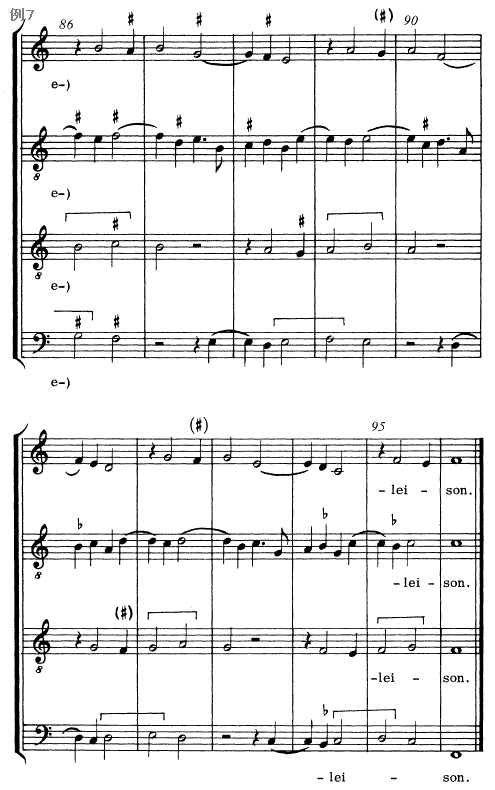 12. INTABULATIONS 声楽ポリフォニーのオルガンとリュートへのintabulation( 多声声楽曲を鍵盤楽器用に編曲したもの)は、演奏者に、アカペラのボーカルパフォーマンスには決して必要なかった、または必要なかった方法で、演奏に合わせてあらかじめ調整された楽器のどこに指を置くのか、そして、調整可能なフレット楽器を除いて、実際の音のピッチのレパートリーが最初にどこで確立されたか、を伝えている。54 キーボードタブ譜は、Apelによって、musica fictaの適用の主要な証拠として扱われたが、他の人は、時系列および地理的適用性を含むさまざまな根拠でこの証拠の有効性に疑問を呈している。 疑念は、タブラチュアの証言に基づいており、タブラチュアの内外での矛盾を根拠にしている。ほとんどのタブ譜の音符固有性にもかかわらず、いくつかの編集上の決定に対する明白な必要性が残っている。 p40 さまざまな種類のパフォーマンス練習、特に装飾と「臨時記号の使用」のためのタブ譜の証拠に見事な仕事が行われた。Howard Mayer Brownは、フレット楽器のタブ譜は、正確な”半音階的inflection"をするオルガンタブ譜よりも正確で一貫性を示すと主張した。「musica fictaの調査のための広く、未踏のレパートリー」'56。 彼は、リュート奏者の実践が、声楽の慣行に適用できると考え、Gafurius と Burtius の対位法の論文が、それらの教えが器楽と声楽の両方に適用されることができることを示していると信じている。57 しかし、 intabulationsはそれらのレパートリーの実際の音符の重要な情報源であるという非常に探求された見解を解釈する際に、アレンジメントとしてのtranscriptionsではないことを思い起こさなければならない。(ダールハウスが強調した点)。確かに、それらが最もしばしば妥協するクオリティは、正確に事前調整された有限のレパートリーに前もってコミットされなかった、声楽的に考えられたオリジナルの段階的な進行の異なる論理を招き、または強要さえする、対位法的なvoice-leading である。 現代の記譜法もタブ譜も、まったく異なる制約とオプションのセット、つまり聴覚的に決定された対位法的手順はあるがキーボードまたはモノコードのanchorageなしで歌手たちが扱うものが生成したものの唯一の、または最も正しい、または正確な表現さえも提供できない。 ここで提供される中世後期の声楽記譜の考え方は、原則として、シンボルが単一の所定のピッチを表すシステムとは明らかに異なっている。 ルネサンス期のintabulation作家らは、我々が編集者として出会い、そして、同様の臆病さで、そして特にこのための基礎で解決したような原則についての同じ衝突に出会った。(おそらく、2つのシステムが非常に大きな範囲で同様の結果をもたらすために、意識的な合理化なしで)。 p43 現代の記譜法は、16世紀の記譜法と同様に制限された、タブ譜の一種である。固定されたconnotationsを持つ現代の譜線記譜法のように、固定された鍵盤を持つキーボードは、声楽的記譜法の必要な補完である聴覚的に決定された対位法的思考に対する制限として機能した。 それは、 Prosdocimusの無限を有限にし、声楽に対して完全に表記する必要がない、できなかった、および表記すべきでないものを完全に表記した。リュートとキーボードのアレンジメントの多くは、対位法とmusica fictaの規則が要求する解決策に欠けている。なぜなら、それらのアレンジャーは、異なる目標にもかかわらず、現代の編集者が直面しているのと同じジレンマの角に引っかかったからである。つまり、理想的な音と、それぞれが動いている声部で考えられたオリジナルとは異なるように見える記譜法的なspellingの間の妥協点を見つけることである。 編集と記譜の両方のプロセスは書かれたものであるため、可聴なものを犠牲にしても目に見える異常を回避する解決策を奨励する。 現代の編集者が忠実に再現しようとする重要な違いと、ルネッサンス期のintabulatorがアレンジするための重要な違いで、両者は、表面的には似ているが根本的に異なる2つの記譜法システムの大きな重複を調整しようとしているが、実際には、概念の程度と潜在的な違いを覆い隠す実践と効果の重複の程度を保持する基本的な違いのある記譜システムである。 キーボードタブ譜は、現代の表記法と同じように、この議論に対してaccidentalなものである。私の主な目標は、初期のスタッフ表記が両方とも異なることを認識することを学ぶ必要がある理由を示すことである。 声楽と器楽の組み合わせの問題は、15世紀後半以降、理論家たちの幅広いexerciseであった。そして彼らは、ある種の妥協が必要であることを明らかにしている。実際それは、私がここでスケッチしようとした原理の衝突に理論家が気付いていたというほぼ唯一の証拠を提供する理論的証言なのである。 p44 Vincentinoは、オーガニストに対する、作品における移調の効果への時折の必要性に言及した。歌手の放浪が単に不注意だった場合、Vicentinoは確かに、オルガニストに移調を勧めるのではなく、イントネーションを改善するかオルガンに合わせるようにカウンセリングしていたことだろう。 固定された鍵盤を持つ楽器は、声楽的対位法から導かれた思考とは異なるやり方を生じさせた。そしてこれは、次第に、音楽的妥協を伴なっていった。 理論家たちは、器楽的のスキルとしてではなく、声楽としてより一貫して、対位法を提示しているが、現代の音楽家たちが演奏する際に聴覚的注意を喚起することは、非常に容易である。 (略) ますます多くの証拠が、14世紀から15世紀のアカペラ演奏は、世俗音楽においてさえ、これまで考えられていたよりも一般的だったかもしれないことを示唆している。したがって、声と楽器の組み合わせから生じる問題は、イントネーションにこだわりを持つ歌手のグループが器楽伴奏なしで歌うことを好むのと同じやり方で、そして同じ理由で、回避されたことだろう。 声楽と固定調律の楽器、キーボードなどと組み合わせは、器楽伴奏を持たない声部ができることのスタイルを常に窮屈にするであろう。 Fortuna, Ave Maria 、その他の多くの作品の Intabulations は、それゆえ、対位法やその他の”規則”から生じるものよりも”大胆な”版が少なく、この作品についての私の解釈やLowinskyのそれが16世紀までの音楽家たちには適用されなかった証拠にはならない。だがむしろ、異なるシステムで理解されているように、名目上の音と実際の音が分岐した時点で、 intabulators は、原則の衝突に直面した59。 59 13. TONAL COHERENCE ルネサンス音楽では、主に旋法理論を音楽の現実と調和させようとし、論拠よりも正確なピッチ内容の記譜法に関する強い仮定において、あらゆる時代の音楽を分析する際の「音調の一貫性」に対する我々の現代の最優先事項が反映されている。 初期の理論家たちは、少なくとも調整のくさびのエッジに明らかに依存する旋法のコンテキストを除いて、初期の音楽についてのほとんどの現代のアナリストたちによって意味された、長期的な音の一貫性の感覚を議論していない。60 p46 これらのレパートリーの旋法とfictaに関する現代の議論で繰り返される問題の1つは、ピッチを概念化するこのような2つの異なる方法が、キーボードの共通の基準に基づいて何らかの形で調整できるという仮定である。 musica rectaの音階の原理における構造と、理論的な構造としての旋法の音程構造の両者は、作品の一時的または残りのために、出発点から「出発」を作成するかもしれない調整の対象となった。 ロマン派の作品の分析は、音楽的現実としての拍子記号の抽象的なmeasureを反映しているかもしれないが、ルバートを考慮する必要はない。 16世紀の理論家の旋法分析は、表面的な現実性を考慮せずに、同様の抽象的な背景構造を反映している。 音階の程度を変えるのに、必ずしも旋法を変える必要はない。Obrecht のKyrieの終わりにある「戻ることのない」連続的なスパイラルは、ピッチのリタルダンドや、”戻り”のジョスカンを”戻った”ルバートに例えることができる。 キーボードのように、作品のオープニングの開始ピッチと暗示された間隔構造に固執するのは、当時の演奏のために一定のメトロノームの尺度を主張するのと同じように、当時は実に非音楽的でしたか? 私たちが慣れ親しんできた白音の二音論から逸脱した解釈は、それらとは異なるまたは特別なものでしたか?音を新しい方法で考えることに慣れるまで、これに答えるのは難しいです。私たちが継承した信仰を放棄することは言うまでもなく、全音と半音、直腸とフィクタの間に適用した従来の分割線なしで行うことに事前に調整されたホワイトノートスカラーのモーダル貞操で、不明確な点までささいな違反にさらされています。モーダル理論はある種の長期的な音のコヒーレンスを扱いますが、必ずしもピッチ安定性と同等であるとは限りません-私たちにとってその力を失った別の区別です。これは、長期的な音調の懸念がなかったことを意味するのではなく、私たちが期待することを学んだものとは異なる種類のものであったことを意味します63。 記譜された「ピッチ」は、音で実際の定義を受け取る前に、対位法的な文脈の音楽的現実を待っています。 14。 13. TONAL COHERENCE 「調性の一貫性」に対する私たちの現代の最優先事項は、あらゆる時代の音楽を分析する際において、反映されている。なぜなら、ルネサンス音楽は、主に旋法理論と音楽の現実を調和させようとしたため、そして、証拠が示すよりも、正確なピッチ内容の記譜上の処方についての強い仮定をしたために。 初期の理論家は、少なくとも調整のくさびの薄い端に明らかに依存している旋法のコンテキスト以外に、初期の音楽のほとんどの現代のアナリストが意味する感覚において、長期的な音の一貫性を議論しない。 Harold Powersの研究は、旋法の割り当てを、実現された対位法と効果的に限定された背景分析から、および旋法的「代表的な」作品のセットの事前構成的意図から断固として切り離した。 彼は本質的に、そのような仮定ではなかった作品の旋法分類を求める運動を信用していなかった。 実現されたカウンターポイントおよび効果的に限定された背景分析から、モーダル「代表的」作品のセットにおける事前構成的意図への割り当て。 彼は本質的に信用を失っている 実際の音楽からの例示にもかかわらず、グレアヌスの網羅的なモーダルは、公式のモーダル間隔構造を乱す必要はありません 14. CONCLUDING REMARKS 1つのoperationで、我々が慣習的にmusica fictaを「半音階的」、「inflection」、「変化」、「追加された臨時記号」などと定義した言葉の不適当な使い方を辞めることを期待するのが現実的でないのであれば、少なくとも私は、そのような使用により多くの自意識を注入したことを願っている。 両方向への偏見に対処した後、実際に対位法がどのように機能するかについての異なる見方と、現在尊敬されると考えられているよりも自由なmusica ficta への音楽的アプローチの両方に満足することを学ばなければならないと考えている。 視覚的なスコアコントロールの利便性を引き続き享受する場合は、初期の音楽では、少なくともそれが表す妥協の性質を認識し、それを異なる方法で読むことを学ぶ必要がある。 従来の現代的表記法では、選択肢または「travelling」ソリューションを具体化する簡単な方法はない。 これらのレパートリーを編集者または演奏家にスコアシフトするために、聴覚の現実に対応し、結果を実装する責任がある。これらは、JosquinおよびObrechtの例ではないため、個々のパートから識別できない。 このアプローチはすべての問題を解決することはできないが、表記法の性質を認め、規則間の優先順位を比較検討し、時には表記された臨時記号でも対位法の要点を置くことは、扱いにくいと考えられている場合に可能な解決策を提供する。 それは、inflectionとしての臨時記号の継続、長さ、キャンセルに関する議論をカットする。追加は最小限に抑えられるべきであるという推定を通じて、通常の意味の反転、または意図的に署名されていないcode notesの反転を要求する「注意」標識の識別を通じて。そして実際、記号は現代の対位法と同じように拘束力があるという仮定を通して。 絶対的周波数、ピッチ安定性、調性の一貫性、旋法的純度、「全音階的」優位性、「実際に書かれた音符」から逸脱する追加的臨時記号への抵抗、および ボーカルパフォーマンスへの処方箋としてのそうした音符のタブラチューラ的証拠について、反論を無効にする必要がある。 私はここで多くの問題を過度に単純化しなければならなかったが、いくつかの主要な音楽的事実を無視することにより、しかし、いくつかの主要な音楽的事実を無視することで、耐えられないように見える現代の楽譜の単なるグラフィックの不協和音を受け入れる前に、許容できない音程の聴覚的な不協和音を許容することになった。 |