| The Notation
of Polyphonic Music 4-1 900-1600 Apel |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世音楽のページへ | 次ページへ |
| 前ページへ |
| p155 D. PROPORTIO TRIPLA(3/1) tempus imperfectumのproportio triplaにおいて、C3は、既述のように、breveがperfect音符として読まれなければならない。言い換えると、semibreveは3つのグループとして読まれなければならない。 間違いを避けるために、proportio triplaは、すべてのproportionのように、少なくとも通常では、semibreveを基礎としており、breveではない。これは、基本的な方程式が、3S (proportion.)= 1S (integer valor)となり、 3B(proportion.)=1B (integer valor)ではない、ということである。 実際、これらの2通りの解釈は、必ずしも同一ではない。例 p156 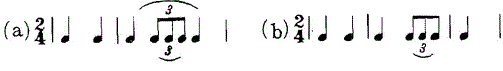 p156 (b)のみが正しい。この点の示唆的例は、ファクシミリ33(B)のTinctorisの作品に見出される。 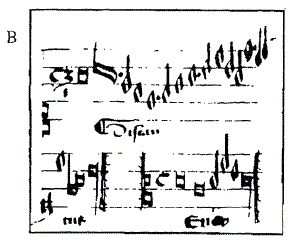 ここでは、テノールがbreveで始まっているので、discantにおいては、3つのbrevesによるこうした音符のそれぞれと対照されるかもしれない。しかし、結果は、下の(a)に示されているように、誤りである。正しい解釈は、テノールにおいて、それぞれ2つのbrevesがsemibrevesによって置き換えられることで、得られる。2つのbrevesは、下譜(b)で示されるように、それぞれdiscantの3つのsemibrevesに相当している。 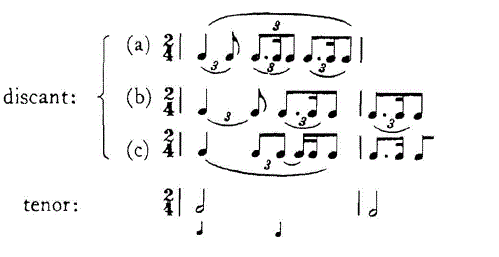 上譜(c)は、proportionのbreveがimperfectであると解釈されたとして、3B=1Bの関係をベースとして得られた別の解決の可能性を示している。この場合、この解釈は除外はできないが、意図されることもあり得ない。(この作品の第3小節を見よ)。 いずれにせよ、proportio triplaの一般原理とは、矛盾している。しかし、我々の時代の音楽においては、これらの原理の厳密な観察は期待され得ないが、proportio triplaが(imperfect) breveに言及するような、代替解釈の可能性に注意を払うことは望まれる。 p157 より明確な宣言が、minimaに関するproportio triplaの可能性に関してなされる。実際、以下のような例は、16世紀のソースには稀なものではない。 proportio triplaの一般原理に従えば、以下のtranscriptionは正しい。 しかしこれは、過度に早い音符の結果から集められたような意図されたリズムではない。実際、このケースのように、 tempus imperfectumのtriple proportionは、しばしば、記号 tempus perfectumのproportio tripla O3(9/8)は、すでに説明したように、 p158 E. OTHER PROPORTIONS <Proportio quadrupla(4/1)> Proportio quadruplaは、1:4の比での縮約を示す。これの記号は、 ここでtactusはlongに当たるために、このproportionはしばしば、alla longaと呼ばれる。Proportio quadruplaは常に、breve(tempus imperfectum)のimperfect計量記譜法を要求する。たとえtempus perfectum 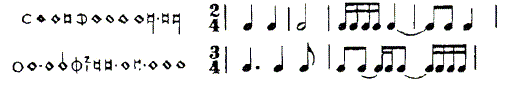 <proportio sesquialtera(3/2)> proportio sesquialtera(3/2)は、2:3の比での縮約を示す。triplaのように、常にbreveの、すなわち3つのsemibrevesのperfect計量記譜法を要求する。それぞれのグループは、integer valorの2つのsemibrevesのグループの音価に等しい。近代譜へのtranscriptionのために同じメソッドが、proportio triplaにおいて、以下のように適用される。 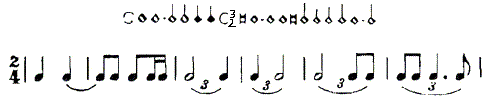 このproportionは、genus superpartiensの最初の例である。sesquialteraの基礎的な方程式、すなわち、2 S (int. val.) = 3 S(prop.)は、proportionにおけるternary group(tempus perfetum)に対してだけでなく、integer valorにおけるbinary group(tempus imperfectum)をも要求する。それゆえ、sesquialteraは、通常、tempus imperfectumと組み合わせられる。以下のように。 これは、純粋に仮想的意味合いである。これは、O3/2の使い方を排除することを意味しない。しかし、proportionが[3,2]におけるbinaryであるminimasへ適用されるケースでは、制限がある。 ファクシミリのEx.(C)は、その説明となっている。proportionの3つのminimasは、integer valorの2つに等しくなっている。第2段譜表の最初のその記号は、g-clefである。 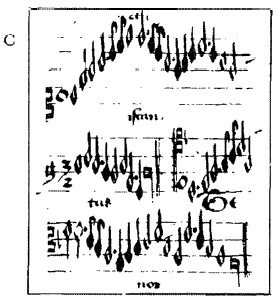 Tinctoris , Proportionale musices, MS Brussels , Bibl. Royale (ca . 1480) A: page 100; B: page102; C: page 104; D: p106; E: page 102 [2,2]において、sesquialteraは、coloration(hemiolia)として、同じことになっている。 容易にわかるように、 sesquialteraは、[3,3]で使われることはできない。 p159 p157で述べたように、sesquialtera はしばしば、記号3/2ではなく、通常、proportio triplaで要求される記号 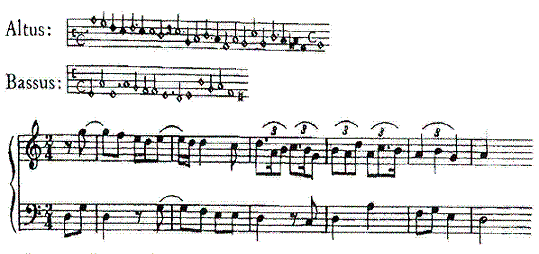 明らかに、形象 全体の作品が、tempus diminutum(alla breve p148参照)で描かれていれば、状況は幾分、単純になる。以下の例のように。(ジャヌカン La Guerre) 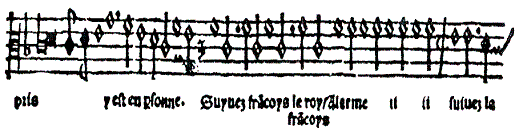 ここで、記号 proportio sesquialteraはしばしば、diminutio simplexと組み合わせて使われる。 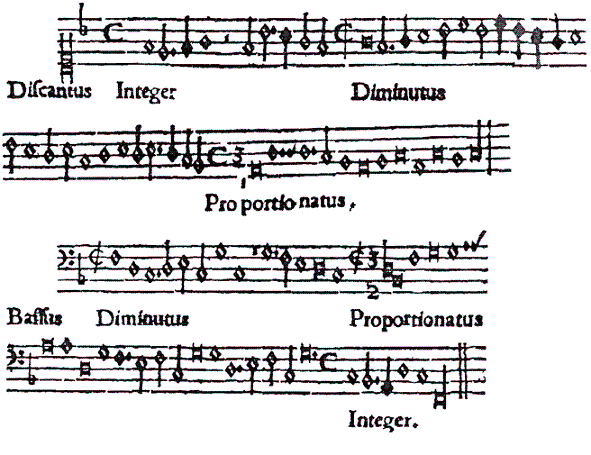 p160 < proportio quintupla,sesquitertia.> ここで取り上げられた以外のproportionは、白色記譜法の音楽文書においては、ほとんど出会うことはない。しかし、2つの例が、主題の提示を完成するために、精査されよう。以下は、GafuriusのPractica Musicaeからのproportio quintuplaの1例である。 p161 記号 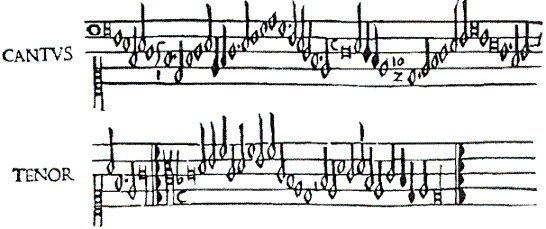  ファクシミリ33のDは、proportio sesquitertiaの説明をしている。それはしばしばepitrita(ギリシャ語)と呼ばれる。proportionにおけるセクションは、 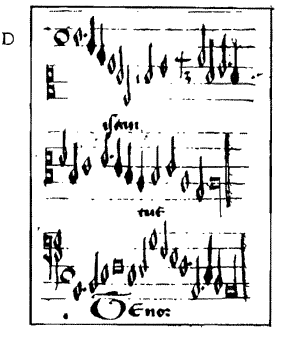 Tinctoris , Proportionale musices, MS Brussels , Bibl. Royale (ca . 1480) A: page 100; B: page102; C: page 104; D: p106; E: page 102 Successive Proportions 同じパートで複数のproportionsが連続して現れれば、その効果は、蓄積し、それぞれは、先行するproportionに言及し、integer valorにはそうしない。2つのproportionsの蓄積効果は、掛け算で示される。すなわち、 ファクシミリ33Eは、その例である。ここでは、最後のパッセージの記号 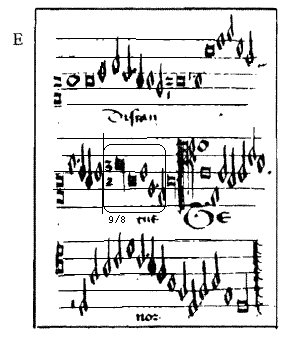 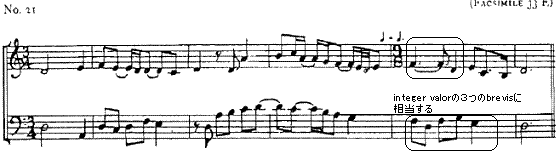 Tinctoris , Proportionale musices, MS Brussels , Bibl. Royale (ca . 1480) A: page 100; B: page102; C: page 104; D: p106; E: page 102 しばしば、作品においては、明らかなproportional signsだけでなく、規則的な計量記譜法のあらたな記号もまた生じる。蓄積原理は、概して、これらには適用されない。 たとえば、 p162 GafuriusのPractica Musicaeからの例は、この説明をしている。 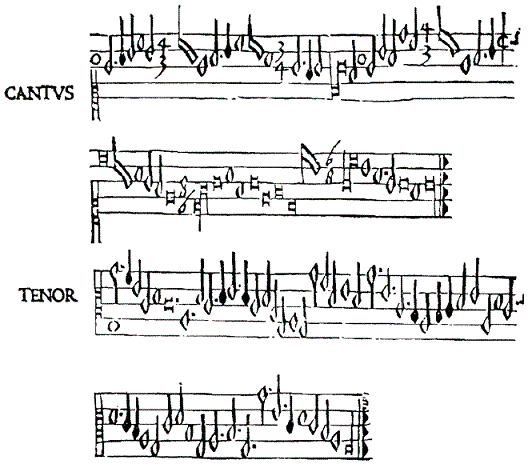 上譜のcantusでの記号についての蓄積の意味合いは以下のようである。 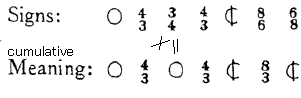 この例の特別な困難さは、いくつかのセクションでの不規則な長さにある。それは、必ずしも、テノールのtempus perfectum(3/4拍子)に適用されるわけではない。たとえば、3/4(実際再度tempus perfectumとなる)のもとでのセクションは、7つのsemibrevesを含み、すなわち、2つのフルの小節が求められる。それゆえ、以下のようなsesquitertia後のセクションは、小節の第2拍で始まり、終わる。上声部のtranscriptionは以下である。 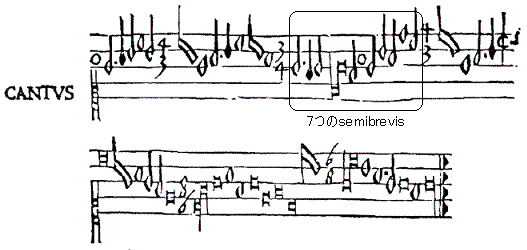 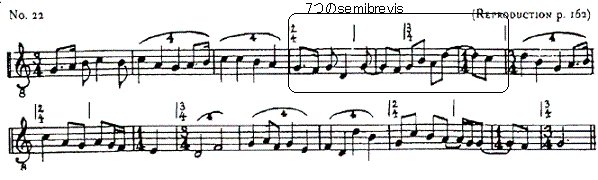 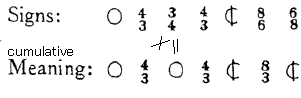 p163 F. AUGMENTATION proportionは、とりあえずはすべて縮約と考えられてきた。1/2や2/3のような(逆の)augmentationは極めてまれなproportion記号であり、それ以前の縮約のキャンセルのためにのみ使われた。 実際には、そのかなり頻繁な生成のために我々の注意に値する特別なタイプのaugmentationのみがそこにある。すなわちそれは、prolatio perfectaからの、より親しい記号によって示されたものである。以下のような原則が観察される。 prolatio perfectaにおいては、tactusはsemibreveによってではなく、minimaによって表される。 これは、記号 テノールの歌手は、prolatio perfectaの規則にしたがって相対的な音価を決定し、しかし、その他のパートの歌手がsemibreveとするのと同じところをminimaにすると、明らかに、結果は3倍の増大となる。prolatio perfectaは実際、tempus perfectumとなり、実際には円または半円で示されたtempus(imperfectumあるいはperfectum)は、modus(imperfectumあるいはperfectum)となる。 ファクシミリ34はこの実際を示す。ここで、テノールは、L'homme armeのメロディを含み、他のパートにおける○に対して、 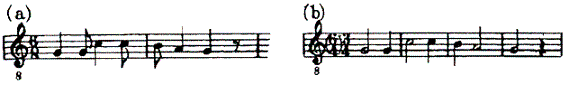 ファクシミリ34 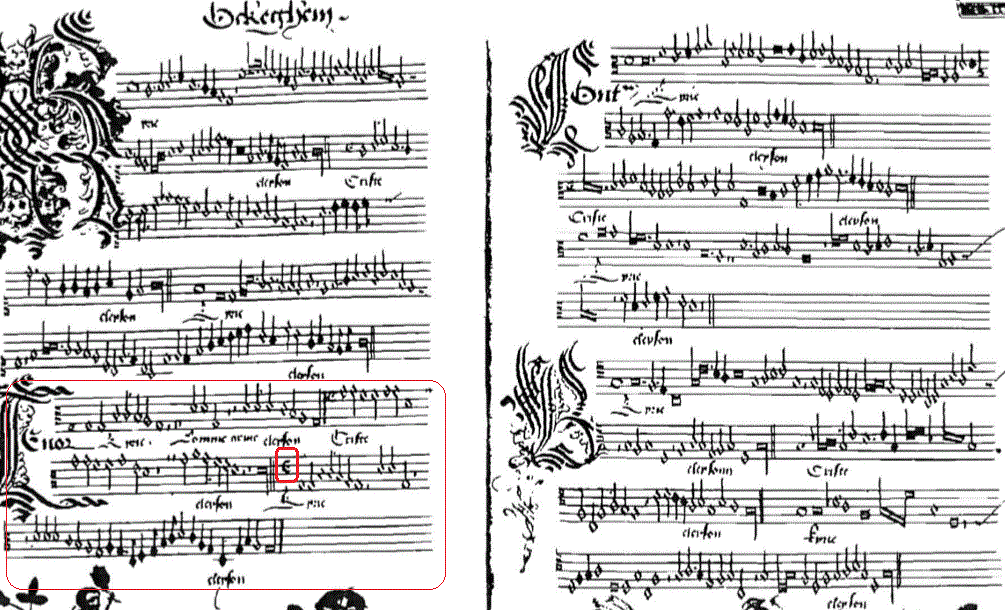 p164 Christeセクションにおいて、全パートはprolatio perfectaにて記譜されている。全体のセクションは、増大する音価、すなわち、6/4(あるいは3/4)であり、6/8ではない。同じ過程は、p138、ファクシミリ30で学習したこのミサ曲のEt resurrexitにも適用される。この作品において、reductionの通常のスケールは、十分な結果をもたらさないことに注意されたい。 結局、音符はあまりにも細かすぎて、我々のtranscriptionによるスピードでは歌うことができない。こうした失敗の理由は、今や明らかである。この作品において、minmaは拍を示し、それゆえ、八分音符ではなく、四分音符として校訂される。 こうした環境下では、ファクシミリ31,32にも同じ原理が適用されるかどうかという疑問が持ち上がるかもしれない。双方とも、prolatio perfectaである。しかし、すでに見たように、tempoの同じ考慮が、Et resurrexitとともに、増大の適用へのよき論議を構成している。 これは特に、作品No.31で明らかである。増大の原理は、それぞれ全体の3/4拍子に等しい音符の流れとともに始まる原因となっている。実際、こうした作品は、prolatio perfectaの規則には従わない。なぜなら、それらは、この原理がまだ確立していなかった、より初期の時代に属しているという単純な理由があるからである。以下の注目は、15世紀の間の「prolatio perfectaの歴史」をはっきりとさせる試みを示している。 Ramis de Pareiaは、1482年の彼のMusica Practicaにおいて、prolatio perfectaをsignum augentiaeとして述べた最初期の理論家であるが、この実践例はすでに、1400年頃の編集であるシャンティ写本中にみられている(ファクシミリ88参照)。しかしこれはむしろ、独立した例である。この時代の理論的な書法と同様、15世紀のより初期の音楽ソースは、明らかに、問題の解釈が、決して一般的あるいは普遍的に受け入れられていたわけではなかったことを示している。その他において、Tinctorisは、偉大な権威であるが、彼の著作Proportionale(およそ1475年)において、こうした事実を述べることはしていない。 しかしながら、記号 彼によれば、この計量記譜法についての3つの異なったリズム解釈は、彼の同時代人の間でも使われ、Ramisのそれに同意することがない。彼の遠まわしの説明への詳細な考慮に立ち入ることなく、4つの異なった解釈を示す以下のテーブルによる問題の説明のみで十分であろう。 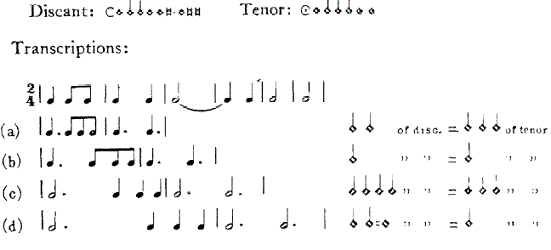 テノールのさまざまな実現化における小節の数の比較は、(c)は(a)の2倍であり、(d)は(b)の2倍であり、(d)は(a)の3倍であることを示している。 (d)は、上記の規則(3倍の増大)に求められ、(a),( b), (c)は、Thinctorisによって述べられていることである。無論、彼は(a)(彼は、discantとtenorにおけるminimaの関係に言及して、これをproportio sesquialteraとしている)には、(c)(minimaに関して、proportio subsesquitertiaとして)と同様、同意せず、(b)を唯一の正しい解決と考えている。 ある意味では、この解釈は、すべてのうちで、もっとも単純かつ賞嘆すべきものであるといえる。 これは、C(O)あるいは 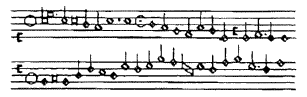 ここで、minimaは、○と もうひとつの同じ実践例は、デュファイのシャンソンBelle que vous楽譜である。そこでは、それぞれの声部において、異なった計量譜として記譜されている。 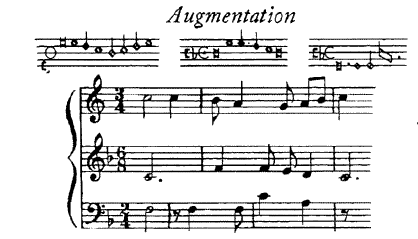 Belle, que vous ay ie mesfait 簡単にまとめると、15世紀前半(Dufay)には、prolatio perfectaは、prolatio imperfectaに対抗して置かれれば、minimaと同じ音価を示す。後の時期(オケゲム、ジョスカン)では、それは3倍の増価(M=S)を要求する。しかし、この後の時期では、prolatio perfectaの増価の重大さは、その記号と縮約の記号との組み合わせによって、チャラにされてしまう。次のように。 しかし、後の資料においてさえ、この問題での正解のなさは、認めなければならない。特に重要なのは、Seb..Heydenが、 以下は、この作品の最初である(全作品は、Mut,79参照)。パート全体に、minimaが続いている。 最初の部分(discantとaltus)は、2声部をカノンとしている。[2,2]である(記号C)discantは、ファ音で始まり、altusは、[3,2]で(記号○)、四度下で同時に始まる(subdiatessaronは、「完全四度下」の意)。次の部分(tenorとbassus)もまたカノンで、バスはテノールの完全四度下で始まる。このパートの最初に書かれている休符は有効で、テノールのためではない。実際、discantとaltusは一緒にスタートするが、バスのみは、4つのsemibreves分を隔ててスタートする。その場所は、signum congruentiaeによって、示される。 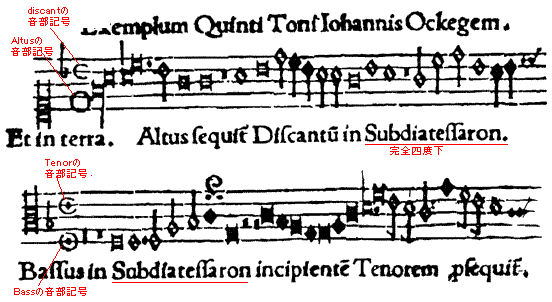 バスは、[3,3]であるために、最初のbreveの休符は、音価において、9minima分となる。そしてそれゆえ、transcriptionにおいては、9/8拍子すべてを占めることになる。しかし、この部分の続きは、tempus perfectumであるとは限らない。(すでに、最初のbreveは、その前のsemibreveの休符により、imperfectとなっている)。そのために、6/8拍子とするのが、9/8拍子よりも便利である。transcriptionの最初は、以下のようになる。 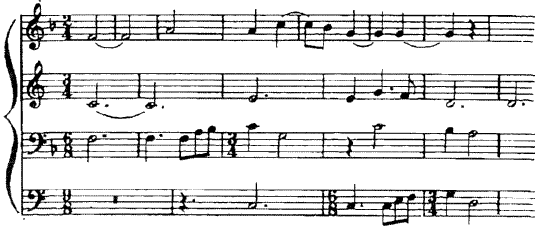 |