| Quid non ebrietas dissignat? Willaert’s didactic demonstration of Syntonic tuning |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
その前
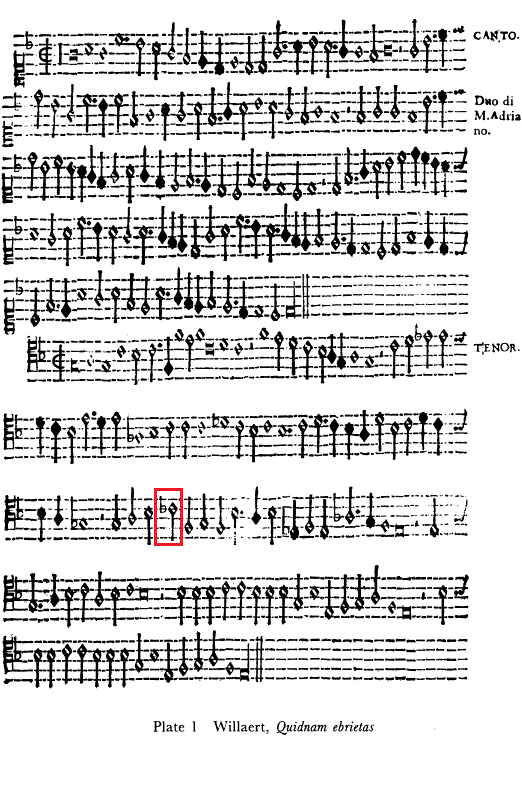 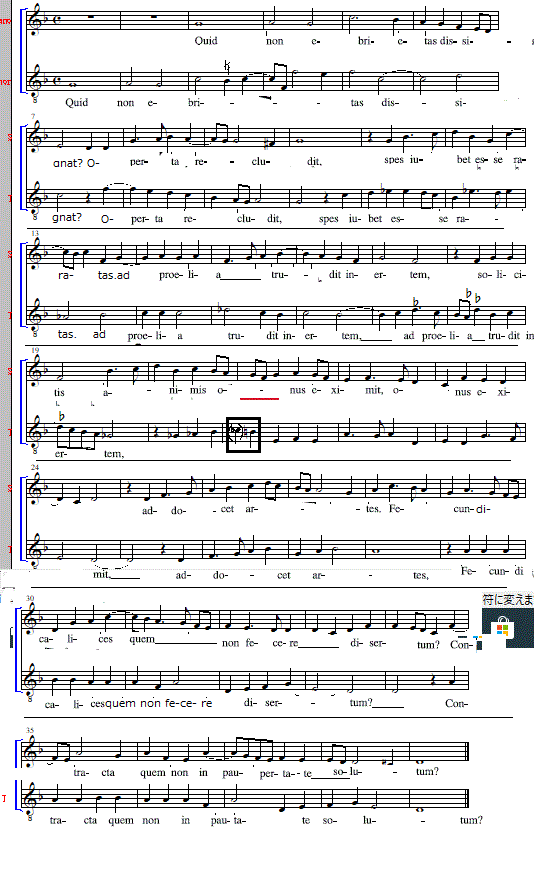 “Quid non ebrietas dissignat? Operta recludit, Spes iubet esse ratas, ad proelia trudit inertem, Sollicitis animis onus eximit, addocet artes, Fecundi calices quem non fecere disertum?” (Horace, Epistles I, V, 16–19) [飲酒によって達成できないことは何か?それは秘密を明らかにし、希望を実現し、非武装勢力の戦いを奨励し、 心配心から負担を取り除き、新しいスキルを教え、 誰にワインカップをより巧みに作っていないのか?] ホラティウスの書簡詩の上記の部分のウィラートの音楽的設定は、修辞的な質問から始まる。「飲酒によって達成できないことは何か?」レトリックは、(できないこととは対照的に)ワインカップを通して達成され得る肯定的な達成のリストを羅列する、残りの行によって再確認される。 最初に1524年にSpataroとAronによって、それから1600年にArtusiによって、そして最近ではLevitan、Lowinsky、Bentらによってこの作品が議論されて以来、問題は本質的に修辞的であるように見える。そして、なぜヴィラールトがこの作品を作曲したのか、そして彼は、何を示そうとしたのか? 彼の記譜法がどのように読まれ解釈されるべきかについての説明は進んでいるが、これらのいずれも、明確に認識された作曲上の目的に直接由来するものではない。 このように、この作品は、特定された好奇心を説明できる独自の客観的アジェンダを主張する創造物としてよりも、興味深い好奇心として見られてきた。 テキストで示唆されているように、「秘密を明らかにする」、「希望を実現する」、「心配している心から負担を取り除く」、「新しいスキルを教える」という構成が明らかになる。この論文は、分析と理論を通して、「なぜウィラートがこの作品を作ったのか」という問題が決して修辞的なものではなく、答えを必要とするものであると断言する。回答を提供する際に、論文は目的が達成された技術的手段を明らかにする。その目的とその技術的達成度を理解することで、ウィラートの作曲プロセスと彼のユニークなサウンドの世界をより広範囲に再評価することになる。 [1]ウィラートの世俗的なモテット “Quid non ebrietas dissignat?”についてのArtusiの議論が、彼の時代の劣等性(特に、モンテヴェルディのそれ)とは対照的に、彼が古い音楽の優れた美徳であると考えているものを称賛する論争を呼ぶ本で提供されたことは二重の皮肉である((1) 二重に皮肉なのは、この議論を通じてウィラートの作品がまったく保存されなかっただけでなく、その作品は(80年以上前に書かれたにもかかわらず)実際にArtusiが適切に理解するには高度すぎ、洗練されていた、ということである。 [2]作品を調べ、それが生み出したアイデアのいくつかを簡単にレビューする前に、その注目すべき特性の簡単な説明がなされる。 Artusiは、Cantus とTenorの2つのテキストのない声部のみを提供した。Aronは、これらが、彼が4声作品と判断したもののうちの2声部のみを形成していると考えた。(2) Lowinskyは、残存の印刷されたAltusno声部(テキスト付き)を出版し、彼が編纂中のバスに加えた3つの現存の3声の編纂を加えた。 テノール声部は、シミラレソドにフラットを連続して導入することにより、フラット世界に進行していく。ちょうど中心でC♭に達した後、 テノールのその後の音は、視覚的に表示されるよりも1度低いピッチで演奏する必要がある。 最終的にテノールは、Eとして見えて終止するようになる。Cantusのカデンツは、明確にDとなっているが。 図 初期の時代から現在までのすべての作家は、2つの音符が終止でのオクターブを形成しなければならないこと、そして、テノールの最後の音符どう見えようが、実際には、明確にDとして響くということにしっかり同意をしている。 したがって問題は、テノールの後半(C-flat以降の音符)をどのように解釋し、理解し、実行するかということである。 [3]必然的に、この見かけの主観性と不確実性が、異なる見解と解決策を引き起こした。Levitanは、 Artusiが、 Spataro は(不賛成ではあるが)C♭をB Lowinskyは、彼の版と作品の議論で、意図的な平均律での演奏という見方に同意した。一方、Bentはこの見方を否定し、作品をソルミゼーションとmusica fictaの慣行として見た。(5) 5. Margaret Bent, “Diatonic Ficta”, Early Music History 4 (1984), pages 16–20. 彼女の見方は、Dorothy Keiser(6) and Rob Wegman,(7) によって反映され、後者は、テノールがグイドの手のめぐりを完成させたことを証明しようとする分析を発表した。 前者も、当時の1492年のグローバルな就航に関連して作品を見ている。それにもかかわらず、意図された音の世界は平均律のそれであり、記譜の特異性とあいまいさはこれを反映しているように見えるという永続的な代替の見方がある。 [4]この論文では、次のことを主張する非常に異なる分析と理論的根拠を示す。 a)ヘキサコード理論とソルミゼーションとの想定される知的または因果関係は見当違いであり、実際に作品の不適切な理解と実現につながる。 b)平均律の推定は見当違いであり、作曲家の思考や期待とは無関係である。 c)「グローバルな周航」(または他の無関係な出来事)をほのめかすことによりモテットを構成する動機を植え付けようとする試みは不必要であり、ウィラートの作品を構成する本当の(そして実際に透明な)動機を理解していない d)テノールのメロディの後半の演奏に関する主観的な決定は完全に不要である。なぜなら、ウィラートは、実際には、彼が提示したすべての音符の正確なピッチ(分裂の値の範囲内で正確に)を、必要なメロディ音程とともに、明確に識別しているからである。 [5] Spataroがウィラールトの目的を理解できなかったことは、テノールの最後の音がカントゥスDとオクターブを形成できるという作曲家の明らかに誤った判断(Spataroが見たように)の非難において示されている。すなわち、Spataroは、EがE♭にフラット化されると、ピッチがmajor semitone下げられることを訴える。それがさらにフラット下げられると、ピッチはさらにmajor semitoneだけ押し下げられる。 2つのmajor semitones分だけ下げられたEの位置を彼のモノコードで測定した結果、Spataroは、ピタゴラスコンマによって、結果としてのピッチがDより低くなることを正しく観察することができた。(8) この観察結果は、Spataroが、Willaertの音楽的判断はピタゴラス的であった(またはそうであったに違いない)という仮定を立てていることを示している。 現在実証されているように、この仮定は部分的にのみ真実である。現実には、ウィラートの思考はC-flatに到るまでしか意図的にピタゴラス的ではないが、その後は意図的にプトレマイオス的になっている。 次の分析は、ピタゴラスのC-flatに到るようにテノールを構築するまさにその目的が、歌手に、独自の昔ながらの限定的なピタゴラスの枠組みの中で、プトレマイオスのテトラコードに特徴的純粋な長三度(5:4)と短三度(6:5)を達成する方法を教えることであることを示す。 プトレマイオス式の音程を作るのに使用されていない歌手がこれを達成するために、Willaertは、ピタゴラス式のmatrixを構成した。これにより、希望された5:4の長三度G-B(1コンマ分、Bより低い)は、BをC♭に置き換えることで達せられる。(BはCよりも minor semitone だけ低いはずであるが、C-flatはピッチにおいて、major semitone になる)。 C♭に続くテノールの音符は、F♭として歌われ、これは、Cと5:4の長三度を形成するコンマによって下げられたEの代わりになる。テノールのその後は、正確に、文字通りに記譜された全音、半音とともに進んでいくが、記譜されないmusica fictaによって、すべては♭化されている。 存在するすべてのフラットを読み取り、その結果はしかし、それぞれのmajor semitone によってピッチをさらにフラット化することにより、(Cantusに関して)この音程の狭小化がさらに拡張される。 したがって、ウィラートのテノールでは、「二重のficta」と呼ばれるものを使用する必要がある。最初のレイヤーは、書かれたフラットによって前半の記譜法において提供され、2番目のレイヤーは、まだ存在する前半のレイヤーに対して、後歌手によって2番目に追加される。ただし、記譜はない。フラットの最初のレイヤーは「書き込まれ」るが、2番目のレイヤーは単に「実行」される。 [6] Willaertの設計と実行を明確に理解することは、上記で提案したように、実際にヘキサコードベースの見方が想定されている場合は、妨げられる。 この推論が適用できない理由は簡単に説明できる。ヘキサコードは、中間のminor semitone (256:243)で区切られた4つの同一トーン(9:8)からのみ構築される。しかし、現在説明されているように、プトレマイオスのシントニックテトラコードは、サイズの異なる2つのトーン(9:8と10:9)だけでなく、単一のmajor semitone (16:15)も含んでいる。したがって、通常のヘキサコードでは、異なるサイズの音、または正しいサイズの半音(プトレマイオス用語)の認識と正確なピッチングの基礎を提供できない しかし、ヘキサコード評価が不適切であるより明白な理由は、ウィラートが望みのプトレマイオス協和音程を達成するための構造的手段としてテトラコードマトリックスのみを使用したという事実にある。この構造を簡単に説明し、例示することができる。 [7]ピタゴラスであろうとプトレマイオスであろうと、全音階のテトラコードは、上昇音程を含む4音のセルである。それらの性質は初期の理論家によって次のように定期的に記述されている。すなわち、2つの隣接するテトラコードが1オクターブを満たしたとき、それらは分離される(すなわち、それらは、オクターブE-eを埋める構成E-A / B-eのように、追加のトーンによって分離された)。しかし、2つのテトラコードが七度に留まる場合、それらはconjunctとなる(つまり、B-E / E-A、ここで、ヘプタコードB-Aは、同じ共通音Eを共有する2つの結合されたテトラコードで、synapheと呼ばれる)。テトラコードがconjunctであろうがdisjunctであろうが、結果のメロディーは全音となる。(9) [8]したがって、ウィラートのテノールはカントゥスと同じように全音階であるが、その構造は非常に異なっている。これは、例1に示すように、テノールの前半(カントゥスとは異なり)が全音のテトラコードをヘプタコード的に配置しているためである。 この例1ではまず、標準のテトラコードスケールが示され、テトラコードをconjunctされたHypatonとMeson(Eのsynaphe)を示し、それから、そのdisjunct(A-B)とSynemmenon(すなわちAでの「conjunct」 )のテトラコードとともに追加されたDiezeugmenon(すなわち「disjunct」)を、それぞれ示している。後者は1オクターブ(E-e)であり、前者は七度(E-d)である。 [9]2番目のシステムは、ウィラートが一連の7つのテトラコードを構築することで、Cフラットにどのように到達するかを示している。これにより、一連のオーバーラップペアが形成され、各ペアはヘプタコードにまたがり、連続するペアはそれぞれ連続してフラットを追加していく。それぞれ付け加わったフラットは、下の半音にある音符がsynapheとして機能することを表し、それぞれの新しい接続点(「coniuncta」)の結果の表明は1から6の数字で図に示される。 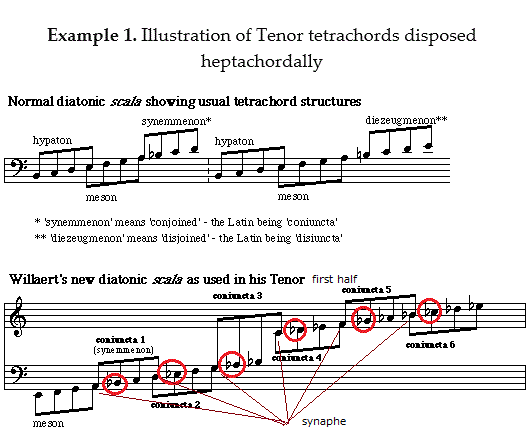 [10]したがって、新しいフラットのそれぞれの目的は、予想されるdisjunctaのポイントを新しいconjunctaのポイントに変換することとなる。 まず、disiuncta D-E(B♭を含むテトラコードマトリクスA‐D / E-A内)は、E-flatの出現によって新しいconiunctaに変換される(EからのヘプタコードではB♭を含み、AからのヘプタコードではE♭を含む、テトラコードA-D / D-Gのヘプタコードの配置を引き起こす) 。 このプロセスは、一連の新しいフラットが、新しい各 coniunctaによって作成されて累積されていく。これらの7つのテトラコードが標準的なピタゴラス音律で演奏されると、必然的に到達するC-flatは、B これは、ピタゴラスのB [11]以下の[19]-[21]に示すように、プトレマイオス(syntonic diatonic)スケールとピタゴラス(diatonic)スケールは、「クローズド」と呼ばれるものであり、完全に別個のエンティティである。 プトレマイオス(syntonic diatonic)スケールは、そのテトラコード音程を超特定の比率に制限することにより、より大きな協和音を実現している。これにより、major semitones(16:15)とlarger minor thirds (6:5)が生成される。 ピタゴラス(diatonic)スケールは、minor semitones (256:243)、narrower minor thirds (32:27)、および wider major thirds (81:64)を使用する。実際には、2つのシステムは、同一のテトラコード構造(同一の古典名が適用されている)を使用している間、異なる調律を提供する。すべてのテトラコードの外側の2つの音は、両方のシステムに共通のピッチを保持するが、内側のペアは異なる。 プトレマイオス(syntonic diatonic)スケールのテトラコードの内側の音は、ピタゴラス音階の対応する音よりも正確にシントニックコンマ(ピタゴラス音律に現れる長三度と純正な長三度との差。約21.51セント )分高く、この小さいが重要な違いは、ピタゴラス音律の三度と六度の(シントニック標準による)耳障りな音を排除する。それゆえ、完全音程の純度は、四度、五度、およびオクターブの純度と一致する。 しかし、”in-tuneness ”は、”完全協和音程であること”と同じではない。なぜなら、不協和音も(それらが意図的に不協和音であるとしても)調和(in tune)している必要があるからである。 したがって、syntonicistの”in-tuneness ”とピタゴラス音律(その理論家たちは、”色づいた不協和音として記述した三度と四度の不順さを認めて喜んでいる)のそれとの間には、葛藤が持ち上がる。 それゆえ、シントニックな配置をした作曲家は、ピタゴラス音律の訓練を受けた歌手でさえ、a)(ピタゴラス音律の標準ではなく、シントニック的に)純粋に調律が合っていることを歌うように強いられ、b)彼が喜びつづけることを願ったその斬新さと効果の両方を圧倒するような経験を見つけ、c)シントニック的校門のその瞬間から、望みの目標を達成するために慎重に指導された作品によって即座に報酬が与えられるように、注意深くデザインされた声楽音楽の説教的な作品を提供することを目指したのであろうか? [12]この論文の提案(タイトルで示されている)は、もちろん、これが実際にウィラートの明示的な目的であり、和声と音響分析がこの提案をサポートするために提供されることである。 一方で、一方(ピタゴラス)から他方(シントニック)への移行が単純で、不可避、不可逆的であるように、ウィラートが2つの外見上別々のチューニングシステムを調整できる技術的な方法を考慮する必要がある。 これらの条件下でのみ、作曲家は、演奏者がある慣行から別の慣行に必然的に移動するような厳密な制御を達成できた。 上記のように、C♭(以降、B この明確な交点は、作品の正確な中間点で達成され、テノールのフラット領域での動きの最終段階と、アプリケーションの新しく記譜されたフラットにおける最後の点が得られる。 Pythagorean C♭は、シントニック的に調律されたB ピタゴラス音律の歌手は、そのピッチを互いに対して慎重に配置することで、実際に(ウィラートのおかげだけで)シントニックして歌い始めた。これにより、ウィラートは、レオナルド・ダ・ヴィンチがVitruvian Man で円を正方形化したときにグラフィカルに試みたものと音響的に匹敵する何かを達成した。 ウィラートが正方形化した円は「調律円」であるが、レオナルドのエッセイのように重要ではないのは、正方形が完全に正確ではないからである。 Willaertの記譜のC♭は、実際には、その差が非常に小さい絶対的なピッチにおいて正確である(ピタゴラスコンマとシントニックコンマのわずかな差-約2セント)。(ピタゴラスコンマとシントニックコンマ参照) この小さな不一致は、例2に示されている。ここでの最初の同時性は、完全に受け入れられる純粋な長三度であるが、C♭がわずかに高くシントニックB 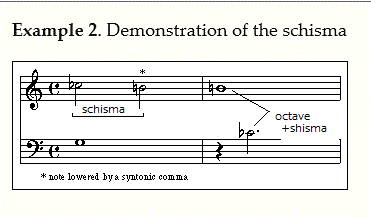 [13]したがって、ウィラートはコンマのinflectionを記す方法を考案した。シントニックコンマの変曲の正確な記譜法をグラフィカルに達成できないことは事実であるが、ウィラートはピタゴラスのコンマのinflectionの記譜法が確かに可能であることに気付i た。その違いはほとんど無視でき、控えめな認識でさえ、どんな歌手でもどんな時にも協和音程に達、本能的にそれを完全に同調させる可能性がある。 Willaertが行ったことは、純粋なピタゴラス音律の実行が実際に結果の和声をプトレマイオス音律となるようにメロディーマトリックスを構築することにより、彼に対抗して伝統的な歌手のピタゴラス主義を使用することであった。 この歌手は、おそらく人生で初めて、おそらく彼の正確なピタゴラスの音程が、彼がこれまでに達成したことのない純度の子音を生み出すことになったことを予想外に発見したことだろう。しかし、彼はこれが歌手としての彼自身の予想外の卓越性の結果であると仮定したのは愚かだったであろう。現実は、結果は作曲家のスキルと計画に完全に帰していたということなのである。 [14]例1で明らかにされたウィラートのテノールのテトラコード構造の理解は、彼の記譜法を理解するための真の鍵を提供する。フラットを追加する際に、新しいconjunctaの各テトラコードは、前のテトラコード(conjunctaされたもの)がまだ動作しているという推定によってのみ、そのステータスを取得する。 conjunctaの6番目のテトラコードが(C♭で)到るときには、前のすべてのテトラコードがまだ適用されいて、テトラコード構造が全体的に透明で、堅固なものであるという仮定が必要である。 このテトラコード行列を現代の記譜法で表現する際には、適用される慣習の違いを認識しなければならない。現代の記譜法では、新しいフラット自体の到着を知らせるだけでなく、古いフラットが引き続き存在することを再確認することで、フラットをグローバルに追加する必要がある。 たとえば、ヘ長調から変ロ長調に転調する場合、新しい調性は、Eにフラットを挿入するだけでなく、すでに存在しているB♭の継続使用していかなければならない。(16世紀の基準では、当然の反復使用であったが) したがって、「1フラット」の状況から「2フラット」の状況に移行していく。しかし、Bでの最初の繰り返しは単なる慣習の1つであり、これをキャンセルすることは示されていないため、音楽的には必要ない。したがって、例1を例3のように書き換えることができる。ここで、新しい記号は、新しいフラットを提示するだけでなく、以前の記号から既に想定されているフラットを再定義することもわかる。この修正は現代の慣習の1つであり、16世紀の基準ではまったく不要であるが。 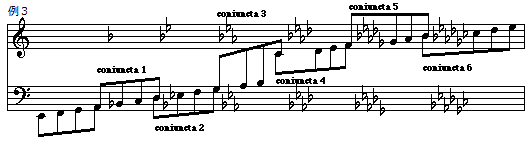 ただし、ウィラートのテナー記譜を現代の同等の記譜に変換する場合は、現代の慣習も考慮する必要がある。したがって、各新しいconjunctaテトラコードの到着は、新しいフラットだけでなく、すでに存在するフラットも示される記号の変更によって示される必要があり、これは例4aで見ることができる。 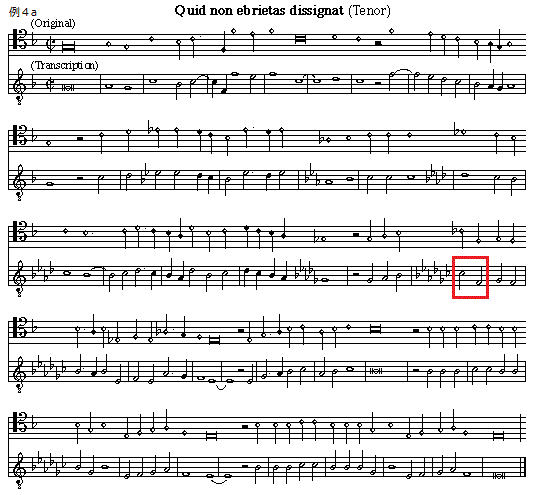 [15]この分析は、このテノールの以前の分析に挑戦する重要な観察結果を明らかにしている。何よりもまず、実際に記譜法で示されている最終音符がEナチュラルでなくEフラットであることを明確に示している。 したがって、さまざまな作家が「音程が1度低い」(全音または半音かどうかの不確実性を示す)音符の演奏を必要とする記譜法を説明すると、必要な音程の差は常に半音(全音では決してない)となる。これは、ウィラートが演奏の際に追加したと想定したfictaの第2層を追加するだけで実現できる(これが、必要な演奏ピッチよりも半音高くなるように記譜を残した理由なのである)。 必要な実際の演奏の方法は、例4bに示されている。示された編集上のフラットは、得られた6つのフラット記号によって示されているように、表示されているフラットにそのまま加えられていることに注意されたい。 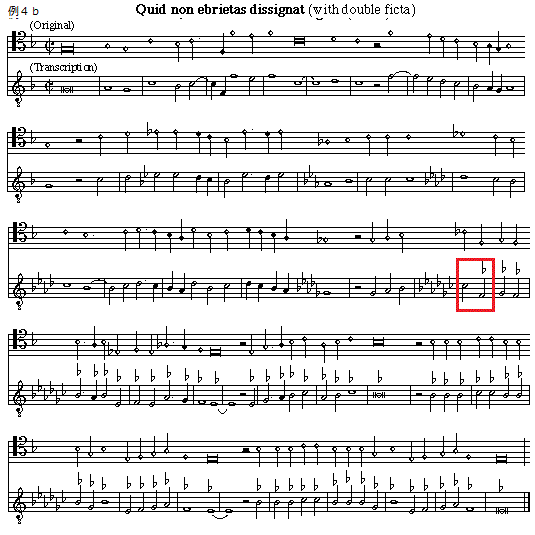 しかし、ウィラートの構造の美しさは、歌手がこの2番目のfictaレイヤーをどのように概念化する必要があるかについてまったく心配する必要がないことである。彼はC♭の次から完全五度分を降ろすだけで(書かれたFに最初の♭記号を適用する)、その後はすべて、そのままの状態でWillaertの記譜を読むだけでよいため、「戦闘に無防備」で完全に自信を持って冒険できる。 実際、彼は、(特に努力もせずに)残りのすべての音を半音低く移調するだけで、特定の音がどのように変化するか、または変化しないかについて個別に決定する必要はない。 しかし、ウィラートの特別な天才は、歌手がこれらの音を♭化するとき、歌手がピタゴラス音律のmajor semitoneの音価によって♭化するという推測にあり、それによって自動的に望ましいコンマのinflectionを提供する。 [16]だが、なぜウィラートは、最初のfictaの層に加えて、fictaの2番目の層を完全に記譜せず、それによってテノールの後半が、要求された歌唱ピッチよりも半音高く記譜されるようにしたのであろうか? そこには、Willaertが、 a) 唯一記譜された♭記号が(シミラレソドの)いちばん後のC♭である(訳注;Fには♭がついていないことに注意)こと、 b)歌手が必要とした響きよりも半音高く保つために、記譜されたピッチをそのまま残したという、明確な技術的理由がある。 記譜されたmusica fictaは、シャープであるかフラットであるかを問わず、トーンが離れている2つのmusica rectaの音符間にのみ存在できる。この原理に該当する最も離れたピッチの♭系列は、音符C♭(2つのrecta音符B♭とCの間に配置されている)である。(10) 10.同様に(この作品には関係ないが)、ficta表記法を適用できるチェーンの最も遠い♯系列のピッチは、2つのrecta音符AとBの間に生じるA♯である。 したがってヴィラールトが(臨時記号の)記譜をすることによって彼のfictaの要件を続けようとしたのであれば、彼は、F♭を作り出す必要があったことだろう。そしてそれからは、ダブルフラットで進行することになっただろう。 Tenor のC♭に続く「実行された」(唯一の)fictaの適用を呼び出す明確なシグナルは、(演奏のみで)完全に変更する必要がある減五度(C♭/ F)の視覚的降下である。この減五度は、ピタゴラス音律のmajor semitone で♭化されたF(F♭)を歌うことによって(実行のみで)完全五度に変更する必要がある。それにより、Willaertの目標である1コンマ分低くなったピッチEを達成することができる。(例4a、4b参照) 実行されたピッチ「F♭」のこのような使用は、CantusのGとの同時性が得られる。この場合、聴覚効果はピタゴラスコンマによって拡大された(複合的な)短三度である。 Willaertが、Syntonic音律への変換を主張していたという目的を達成したのは、この時点(前述のC♭によって既に知らされている)である。 |
