| Tonus Peregrinus: The History of a Psalm-tone and its use in Polyphonic
Music 4 Lundberg, Mattias. Chapter 5 The Rise of an Idiom: The Tonus Peregrinus in French Court Litergies of the Sixteenth Century |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
Psalmus 113 (114+115)
|
この章のグループ(5–10)では、 tonus peregrinus のポリフォニーへの適用について説明しています。 16世紀のtonus peregrinus には、フランスとフランドル地方の恩がうで扱われるのに十分な理由があります。すなわち、この地域の主要なポリフォニックtonus peregrinus 設定は、他の地域に先立つものであり、16世紀の西洋世界全体を通してのpsalmodyの作曲家に影響した、独自のイディオムを表しています。 フランスの典礼のいくつかの特別な状況は、この章で語られるが、ここでは特定の典礼の伝統についてのtonus peregrinusについて議論することは提案していません。 。 ここに含まれる作曲家の機動性やこれらの音楽の出版での幅広い普及のため、問題の詩篇モテットは、地理的にフランスとブルゴーニュに限定されていることを意味します。 しかし、それらはもともと、フランスの宮廷との関係で考え出されたものであり、この関係は、作品が別のグループとして議論されることを要求します。 詩篇の伝統のこの精力的なステージは、最も成功し、尊敬される当時活躍した作曲家、Josquin des Prez (c.1450–1521), Pierre de La Rue (c.1450–1518), Jean Mouton (c.1455–1522), Claudin de Sermisy (c.1490–1562) and Pierre Certon (?–1572)によって代表され、彼らすべて、今日の活動と仕事が頻繁である主要人物で、いわゆるフランドル楽派ポリフォニーに属していると見なされ、同じ地域での中世後期のデュファイ、オケゲム、バンショワの遺産の継続と考えられていた。 この作曲家グループは、これまで、主にfauxbourdonとfalsobordoneに限定されていた詩篇の音楽レパートリーを拡大し、通策タイプの詩篇モテットを含めた。 この達成の歴史的帰結は過大評価されることはほとんどありません。それは、そのような設定の長い規範の始まりです。 この章で説明する作品とは別に、those of Ludwig Senfl (c.1485–1542/3) in Switzerland and Bavaria, Martin Agricola (c.1485–1556) in Saxony, Jachet of Mantua (1483–1559) and Adrian Willaert (c.1490–1562) in Italian-speaking areasLudwig Senfl(c.1485–1542 / 3)の作品はすべて、フランドル楽派の自由詩篇モテットの影響を受けた。 ウィラートは Low Countriesで生まれましたが、彼の音楽については、イタリアの典礼に沿って論議されることだろう。なぜなら彼は、その環境で主に活躍していたためである。Giaches de Wert(1535–1596)の場合と同様に。 Settings of Psalm 113 p60 ピエール・セルトンによるIn exitu Israel の設定は、他のモテットとは一線を画しています。なぜならそれは、(当時までに)ほぼ汎ヨーロッパ的であったfalsobordoneの伝統に続いているからである。1
tonus peregrinusはテナーパートに厳密に限定されています。作品全体を通じて、スタイルのバリエーションは非常に小さく、声部間の機能の和声的変更または交換(どちらの機能も、そうでなければ、当時の”基本的な”falsobordone ではない)はない。 その適切で繊細な言葉の設定とその簡潔さにおいて、このIn exitu Israel は、セルトン自身のパリのシャンソンや彼の同時代人Pierre (Regnault) Sandrin (c.1490–c.1565).のそれによく似ている。 それは、当日の注目を集めそうな作品ではありませんが、実用的な機能は十分に発揮されました。 そのテキストのデクラマシオンの中で、西洋典礼におけるある種のヒューマニストの影響を示唆し、多くの点で、Certonの他の神聖な作品群のほとんどとはかなり異なります。 我々がもしも、彼のミサとモテットで示された対位法的書法を考えるのであれば、彼が自由なモテット様式でIn exitu Israel を設定しなかったという事実は、残念なことである。 <Jean MoutonのNos qui vivimus /In exitu Israel > tonus peregrinusに基づく自由な対位法でのいくつかのモテットは、一方では、、初期のフランドル楽派の巨匠から現存していた。 Johannes (Jean) MoutonのNos qui vivimus /In exitu Israel は、15世紀後半の大規模な作品です。2 ムートンは決して前向きな作曲家ではなく、スタイルも一定のままでした。そのため、彼の作品の年表を再構成することは非常に困難です。それにもかかわらず、この作品は、晩課のための音楽が彼に期待されていたであろうフランスの宮廷礼拝堂での彼の就任中に、1500年頃に作曲されたことがもっともらしいようです。3 1539年の出版時は、ムートンの死後、17年間経っていた。これは、この作曲家が受けた高い評価と、出版者の販売可能性の両方を示しています。 ムートンのモテットは、強烈であると最もよく表現されています。音価は、 double longae からdemisemiquaversまでの広範囲で、並外れた付点形の優勢がある。作曲家は、装飾と減価で、それから派生した旋律の断片をスピンアウトすることによって、明確で独特のtonus peregrinusをこのスタイルに同化します。 この良い例は、モテットのsecundaの3声部からなるテクスチャで見ることができます。(例5.1、bb。61–67)。 ここでは、tonus peregrinusは、いわば、対位法の表面の添え物となっている。すなわち、 terminatio はカデンツを支配せず、そのため、全体のtonus peregrinusのステートメントは、別の旋法に属しているような印象を与えている。 この明らかな「二重旋法性」は、フランドル楽派のポリフォニーでは比較的一般的な作曲上の工夫であるが、ムートンがここで示したほど簡単かつ効率的に使用されることはめったにありません。 p62 詩篇113のフランドル楽派の設定はすべて、表面上では詩篇の典礼機能に忠実であり続ける。なぜなら、tonus peregrinusのアンティフォンの1つが、修道院や世俗でのchoraliter」(会衆が斉唱で歌う)の慣行のように、作品の枠組みを作るからである。 ムートンの場合、アンティフォンは旋法的に、モテットに統合されている。模倣の短い一節では、アンティフォンは最も厳密に、詩篇の最初のverseの前のテノール(第1-6小節)に位置している。 下の3声部は、アンティフォンのメロディの最初の上昇だけですが、最高声部の装飾は、全体のアンティフォンを、少なくとも、ほのめかしています。ムートンの手順は、彼がアンティフォンと詩篇唱の間のつながりをどのように認識しているかを明らかにしています。 もしも私たちがNos qui vivimusの朗唱のテナーパート(装飾は置いておいて)とtonus peregrinus(bb。7–12)の最初のverseに従えば、我々は、tonus peregrinusの最初のsemiverseは、アンティフォンのメロディの続きとしてどのように機能しているのかを見ることができる。 この解決策は、最後の詩篇のverseの後にアンティフォン全体を歌わせながら、詩編の前にincipitを唱えるという、プレインソングの慣行と平行して実行されます。実用的な典礼に関する限り、アンティフォンはもちろんエンブレムや記章でもあります。 この記章は、以前のtonus peregrinus設定に対する音楽的見通しの別の変更を示している。すなわち、詩篇のテキストと詩篇唱を、初めて、その詳細を説明するのではなく、独自の方法でプレインソングの代わりに置き換える音楽作品の形で提示しています。 これは独特の印象を現代の読者または聴衆に残す。すなわち、典礼にそって使われるコンサート作品のそれのようなものである。これはもちろん、実際の音楽環境からは遠く離れているが。 実際、ムートンは、特に、広く普及している典礼の習慣を守りたかったようです。なぜなら、彼のモテットでは、アンティフォンがドクソロジー後に戻ったので、つまり詩編のテキスト自体を置き換えただけのBinchoisとOrihuelaよりもさらにポリフォニーの境界を拡大したのである。 ムートンは、典礼の伝統のこの側面の重要性にアタッチすると同時に、詩篇の詩句を明確に区別したいという正式な(そして伝統的に承認された聖書的な)願望など、以前は重要であった他の典礼的要因を、完全に無視します。 詩篇のverse構造を尊重する代わりに、ムートンの In exitu Israel は、Franco-Flemish の作曲家モテットに採用された形式的構造へのaspirationをtypfyする。 それは3つのセクションにキャストされますすなわち、最初のセクション(アンティフォン+第1-10節)は、tonus peregrinusの断片を使った、各パート均等なパート書法となっている。中央セクション(第11〜19節)は、3つの低いパートに設定され、自由なテーマにもとづいたカノンのようになっている。tonus peregrinusの冒頭で、round off sectionsがある。3番目のセクション(20〜26節)は、クライマックスであり、長くて明確な、virtuosoの華やかな対位法に関する詩篇全体の声明となっている。 3番目のセクションの例から引用すると、III pars bb. 14–27でそれを見ることができます。 middle parts in bb. 21–23の動機の繰り返しに注意してください。(テキストの繰り返しとは独立して使用されます)。 p63 間違いなくこれは、この種の tonus peregrinus の設定の中で最もintenseな例の1つであり、ムートンの同時代人のジョスカンや16世紀後半に有名になった規制された上品なヒューマニストの言葉の設定から想像できる限り遠く離れています。たとえば、同じ詩篇のCertonのad equales 設定に等しいです。 tonus peregrinus statement のゆっくりとした動きと、対照的な下声部のすばやい動きとを、pusillis cum maioribus: ‘the small [or lowly] together with the great [or mighty]’,という言葉の反映として解釈するように誘惑される読者は、cantus firmus と自由書法におけるこの速度の比率は、モテットのこのセクション全体で一貫していることに注意してください。 より適切な観察によって、、tonus peregrinus の扱いに関するsemi-verses の間の区別の欠如に関係がわかる。正確なmediatio cadence は、この華やかなスタイルの書法では望ましくないと考えられていたようです。 semi-verses は第24と25小節で効果的にありつぎになっており、そしてterminatioは、第2テナーの休符によって短くなります。 ここでも、finalis音符は、カデンツの根音としてではなく、ドミナントのカデンツの最後から2番目の音符として使われている。  <JosquinのIn exitu Israel > p64 ムートンの設定の「ゴシック主義」とは対照的に、ジョスカンによる現存しているIn exitu Israel は、より大きなバランスと穏やかさによって特徴付けられます(コントラストは誇張してはいけませんが、しかし、スタイルには確かに違いがあります)。 4 Bicinia とtricinia は巧みに点在しており、パート書法は音価と主題の関与の両方に関して驚くほどの平等を示しています。 言葉の設定は常に非難を上回っており、当時としては、16世紀を通じて北フランドル地方の作曲家による作品では比較的珍しかった韻律的な認識を示しています。 全体として、対照的なスタイルとムートンと交わったスタイルは、一度に1つずつ、はるかに構造化され制御された形式で表示されます。 たとえば、ムートンでひたすら見せびらかされている繰り返しは、ジョスカンの手によって、キーワードとなる2番目の部分のsimul acra gentium argentum et aurum: ‘they have made idols of silver and gold ’(例5.2、bb。74–86)で反映されている。5 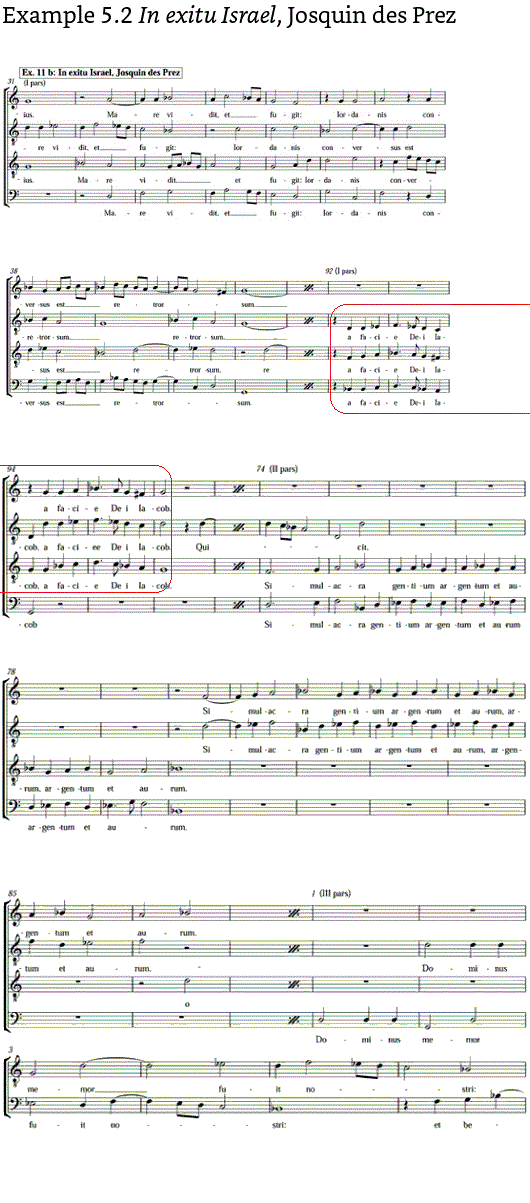 ここでの明確な言葉の設定の理想は、テキストの修辞的な反省と相容れませんが、それでも音楽は両方の原則の顕著な認識を示しています。 この事実は、南ヨーロッパへ旅行と任命の間中に、イタリア人文主義の思想から多大な影響を受けたJosquinと、かつてその長い人生の残りをパリの王室で雇われていたムートンとの間の影響力と野心の違いを非常に明確に示しています。 ムートンのモテットと比較して、ジョスカンは、音楽とoratoryの間の多くの知覚されたつながりを示しており、彼のモテットは、16世紀のコメンテーターがelegantiaと呼んだものの良い例です。6。 外見上、この理想は、以前はエレガンスとは正反対の修辞的な性質であるバーバリズムの例として認識されていた詩篇唱であったtonus peregrinusに基づいた作品で、このように大いに例証されているように見えます。 しかし、ジョスカンの設定の痕跡には、昔ながらのアプローチと北フランドル地方で培われた対位法のスタイルの両方が残っています。 p66 状況がそれを必要とするとき、彼は、例えば、3パートからなるテクスチャの下部声部で、オクターブ跳躍を使用して、これまで議論された音楽でのように、同じ gambit が使用されている中央声部の terminatio の最後の音符の五度上に到達します。 さらに、第1部の第92〜96小節は、Ockeghem and Binchois の世代の自由な対位法における共通の要素であった3部構成の平行fauxbourdon書法の例を示しています。ジョスカンの場合には、これは非常に「モダン」なやり方で使用されます。 その方法は、正確な繰り返しを必要とするが、ボーカルの範囲に合わせてパート書法を再編成する2つのサブ聖歌隊のオーバーラップです。 Josquinの設定における多くの異なるポリフォニックアプローチは、バリエーションのセットのほとんどの特徴を与えます。この多様なスタイルと構成技術の確固たる基盤は、常に完全な形でクライマックスのポイントに戻されるtonus peregrinus自体です。したがって、ほとんどの読者とリスナーは、ジョスカンの詩篇の設定では、詩篇唱を構造的なcantus firmusとして使用していないというJacquelyn Mattfeldの発言に同意する必要があります。 .7 一方、Mattfeldは、ジョスカンが詩篇テキストのverseの境界構造を無視していることを適切に指摘しているため、ジョスカンはcantus firmus のヴァリエーション技法の原則を無視するのではなく、cantus firmus 書法のoutward signs を回避していると言えます。 tonus peregrinusは、まさにこの作品の構造的基盤です。15世紀に一般的であったテノールのやり方ではなく、通作様式のそれであり、すべてのパートはカデンツ進行を均等に形成することに関与しているため、ムートンのIn exituモテットに見られるほどにはテノールに従属していません。 この主題の関与を可能にするために、モテットの最後のセクション(pt 3、bb。1–6)の冒頭にあるように、Josquinは、朗唱を五度下降跳躍によってbreak upし、tonus peregrinusを修正することがあります。 5回目。これがないと、カノン書法は和声的にあまりに静的になり過ぎてしまうことだろう。 <Claudin de SermisyのNos qui vivimus /In exitu Israel > フランコ-フランドル楽派のIn exitu Israel の一番最後の作品は、Claudin de Sermisyによる、すでに言及された作品である。8 セルミシは、パリのサントシャペルにあるセルトンの同僚で、後にそこにあるsous-maître となっている。 彼は詩篇の設定を、ジョスカンが行ったのと同じ程度に修辞的な考察に頼ることによって解釈することも、ムートンの設定での密で華々しい対位法を表すこともありません。 p67 多くの点で、セルジシの設定は、ムートンの時代と彼自身の継承の間にフランスの神聖な音楽に起こった一般的な変化を反映している。 例5.3から、ムートンの場合と同様に、Nos qui vivimusは多声的に「朗唱」されていることがわかりますが、厳密なステートメントは、テナーではなく最も高いパートに割り当てられています。 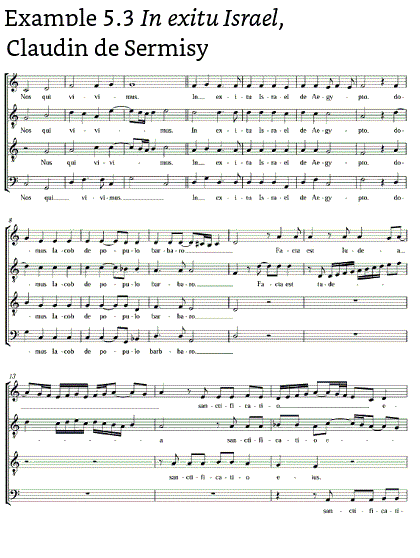 ムートンと同じように、セルミジは、tonus peregrinus最初のverseをありつぎのようにしたアンティフォンメロディーの半分だけを使っている。ファルスボルドンスタイルで設定している。 この手順はムートンの手順と非常によく似ており、当時の大部分の詩篇唱やとアンティフォンモテットとは非常に異なるため、両方の作曲家で独立して生じた可能性は低いと思われます。 2人の密接な専門的連携や、その結果としてセルミジがムートンの設定を知っていた可能性を考えると、この点でセルミシが故意にムートンに従ったした可能性があります。 セルミシは、ファルソルボルドンのverseを、対位法を丹精化するための前奏曲として使用します(例5.3、bb。4–11)。 それは象徴としての特徴を持っています。すなわち、tonus peregrinusのプレゼンテーションであり、そのフレーズは、減価や自由書法に対して、より長い音価で生じている。 ポリフォニックな詩編唱の機能を広げた作曲家の心の中で、tonus peregrinus は、詩篇やカンティクルの他のトーンとともに、falsobordoneのイディオムと密接に関連していた。 ここでセルミシは、falsobordone書法を、受け継がれた慣習のシンボルとしてだいたい使用していたようであり、ムートン様のメリスマスタイルの続く対位法(第11小節~)は、この冒頭との大きな対比となっています。 第18小節以降では、モチベーションの減価において、旋法の不一致の例があります。ここでは、厳密にドリア旋法(b faまたはmolleなし)タイプのメロディ素材と同じように模倣のポイントを書くためのテクニックが使用されているようです。 第21,22小節でのクローズエントリは、通常は問題が発生しない場所のような状況に似ています。 上声部の2声は、音声を支配する規則やtonus peregrinusの整合性に違反していないが、テナーパートの場合、望ましくないトリトーンのメロディック音程を許容するか、詩篇唱のトーンを変更するかの、解決すべき対立があります。 私たちの例が転記された印刷物では、後者のオプションが好まれているようです。このことはそう驚くようなことではない。なぜなら無数の同様の例が、音符の「性質」の変更は、それがその機能を保持している限り(ここではinflectionにかかわらず、bであること)、取るに足らない変更と見なされた、ということを示しているからである。 p68 ただし、この例で印象的であるのは、テノール部分で妥協が発生していることです。最も厳密なtonus peregrinusステートメントは、mediatioで終わりますが、他の声部は、より自由な活気のある書き方を続けます。 これは、その箇所にいくぶん奇妙な性格を与え、伝統的な正式な要件への一部の遵守とそのいくつかの重要な側面の違反の組み合わせのさらに別の例にしている。 (理論的には他の3つの声部に方向性を与えるべきであるまさにその声部のb p69 tonus peregrinusの基本的な特性についての知識は、プレインソングのb 一方、普及した形模倣では、その度合いの性質はより柔軟になる可能性があります。Ornithopharcusは、パートを歌う方法を知るために、歌手は、がよく歌えるう作品の詩篇唱を知る責任があると、している。9 これは、tonus peregrinus が変格声部に(アルトまたはバス)の移調で現れた場合、曲の旋法に合わせて修正する必要があります。つまり、 tenor and discantusの旋法です。 詩篇唱がいつ現れようと、自由なパート書法の旋法的な性格に関する限り、ジョスカンは、ムートンやセルミシのような作曲家よりも一貫して旋法的である。これは、彼のパッセージの多くが、移調されたドーリア旋法として機能している、という事実によるものだろう。ムートンやセルミシの作品は、bとb♭(tonus peregrinus では、有意に臨時記号として使われる)のあいまいさによって特徴づけられるのに対して。 我々は確かではない。Mouton and Sermisy あるいは彼らの出版者が、b これに加えて、ジョスカンは、詩篇唱の朗唱に対して、2つの旋法レベルを使用している。すなわち、”一般的な”形d-a(b♭flexaを含む)と移調された形g-d(e♭flexaを含む)。事実、移調されたレベルは、一般より頻繁に使われている。 (略) ムートンやセルミシとは異なり、ジョスカンは、我々の知識においては、フランス宮廷の恒久的な雇用をされてはいなかった。そこにはしかし、彼がイタリア半島での政治的激動の時代に、フランスに移動したことのいくつかの示唆がある。 1490年 と1505年に、 フランス王 Charles VIII とLouis XIIはイタリアを侵略し、いくつかの都市を支配した。 ルイは敗北し、power Josquin’s earlier patrons, the Milanese Sforza ducal dynastyからremoveした。 グラレアヌスは、個人的にフランス宮廷の音楽家を知っていた(ムートンら)が、ルイとジョスカンの詩篇モテットの1つとを結びつける逸話に関係している。14 この物語にsubstanceがある場合、ジョスカンは、1500年頃にフランスの宮廷音楽家と関わっていた可能性が高く、ムートンのIn exitu Israel を聞き、当時そこで彼自身の作曲を行っていた可能性があります。 状況証拠だけから明確な結論を導き出すことはできませんが、 In exitu Israel のこの後者の時系列は、エルバッハが当然と考えているものよりももっともらしいようです。 p71 その考察に、この作品の構造の例外を追加する場合があります。すなわち、Josquinのより有名な詩篇の設定の中で、このモテットほど包括的に詩篇唱を使用している他の楽曲はありません。15 Josquinに帰せられるIn exitu Israelは、tonus peregrinusだけでなく、antiphonも使用しています。エルバッハによって提案された年表は、ジョスカンが、今日では、2人の作曲家の中で少し古いと信じられていたという事実に基づいているようです。ムートンの初期の作品から結論付けたように、これはこの場合の適切な仮定ではありません。 両方の作曲家がsemi-versesについての異なるincipit形を持つtonus peregrinusバリアントを使用したことは非常に重要です。 私たちは前に、g上で2番目のsemi-verse を直接開始するバリアントが、両方のsemi-versesについてのa–b♭ incipitを持つバリアントと比較してまれであることを見出した。 これにより、semi-verses の間でより明確な旋法的な中断が生じます。Josquinによって十分に活用されたもので、Josquinはセクションをaベースとgベースのソノリティに分割します。厳密なcantus firmusが動作していない場合でも同様です。 このように、彼は旋法に関してparallelismus membrorum 構造を尊重し、それに依存しますが、モメンタムと大規模な形式のために、言われたように、彼は音楽のセクションが詩篇のverseの分割と一致することを許容することを慎重に避けている。 tonus peregrinus のまれな「直接」の2番目のsemi-verse の断片に基づくこの構造の例は、第36小節、例5.2、pt 1にある。すなわち、ここで最も高いパートは、Dに基づくヘクサコード内で機能しますが、その下のパートでは、すでに第34小節のG上のヘクサコードでの第2番目のsemi-verse を開始しています。 このステートメントが2番目のsemi- verseへの動機変化をもたらす場合、it is worked into the modal framework of the first recitation until the entrance of g in b 36 strikingly brings about a shift to a section based on the modal properties of the second recitation. それは、最初の朗唱の旋法的枠へ働きかける。第36小節での(一番高いパートでの)gの入りが著明に、第2朗唱の旋法固有性を基にしたセクションへのシフトをもたらすまで。 この旋法シフトは、その効果を直接のtonus peregrinusバリアントに負っている。このsemi-verse に共通のa-b♭-gのincipitがあると、変更は遅れたことだろう。 Josquinは、ここで議論されているtonus peregrinusの旋法シフトを、2番目の朗唱の入りから、実際にはparallelismus membrorumの中点に移動したと言えるかもしれません。これらの効果は、アルトの反復terminatio形式をもたらすので、外側声部の平行進行の典型的な基本構造によって強化されます(bb。38–41)。 p72 引用された例で見られる奇妙な追加的なflexaの度合いは、実際には、議論中の3つのモテットすべてで繰り返されるものです。3人の作曲家は、多かれ少なかれ一貫して、2番目の semi-verseで二重のflexaを使用し、2番目のincipitをa–b♭ [最初のflexa] / g–a-g [2番目のflexa] と表現します。 このtonus peregrinusバリアントは非常にまれであるため、ここに存在することで、ムートン、セルミシ、ジョスカンのIn exitu Israel のモテットが同じ典礼的文脈に属しているというさらなる証拠が得られるようです。 作曲家自身がその典礼に参加する頻度と、その中に tonus peregrinus がどのくらい頻繁に発生したかによって、さらに推測するかもしれない。 すなわち、このヴァリアントは、確かに典型的ではないので、セルミシは、もしもそれに慣れていない場合、(そしてパリのプレインソングのソースで過剰に表現されていないように思われる場合)、それはプレインソングに関する彼の知識からではなく、ジョスカンの作品から直接受け取ったかもしれません。 ここで説明する表現力豊かな音楽のgambit優位に立つための策,先手は、15世紀初期の設定からの詩篇設定の構成の変化を示しています。 変化はおそらく、14世紀から16世紀にかけて徐々に生じ、広くdevotio modernaと呼ばれることが多い、集団的および教義的な信仰から個人的および神秘的な信仰への一般的な移行に求められる可能性があります。ただし、この並行的な発展のみから確固たる結論を導き出さないように注意する必要があります。 それでも、我々が見た15世紀のIn exitu Israel 設定は、詩篇のテキストをポリフォニックに実装または実行することによって典礼の目的を果たしたという点で、「‘institutionalized’ 制度化」されたと考えられます。 16世紀のFranco-Flemish の設定は、作曲家によってテキストが解釈される点で、「‘individualized’ 個人化」されているため、典礼音楽家としての作曲家の機能に(おそらく偶然にも)、作品を受容するための追加のexegetical な結果を重ね合わせています。 私たちが見たように、この傾向はムートンの設定よりもジョスカンの設定の方がいくらか明白でしたが、セルトンの作品も、他のスタイルとは非常に異なり、15世紀のfauxbourdonの伝統に間接的に根ざしているとしても、より「現代的」に従うようです。 なぜならそれは、詩篇のテキストを何よりもまず詩として観察し(16世紀を通じてドイツ語圏で展開されたヒューマニズム的なオードの構成と比較すると、実り多いものになる可能性があります)、そして、注意深い言葉の設定が無論、一部のヒューマニストの間では、テキストの真の解釈のぜひ必要なもの sine qua non としてみなされたからである。 詩篇のテキストに関する個々の瞑想はOsthoffによって指摘されました。Osthoffは、それが、これらのテキストをムートン、ジョスキン、セルミシのそれのような、精巧なモテットの設定に対して人気があるようにした”個人的性格”であったという提案をした。16 詩篇113は、book of Psalmsのより個人主義的な詩のパターンとは多少異なることに注意されたい。なぜなら、それは、何よりもまず、 psalmist 自身ではなく、人々の集合的な感謝祭の詩だからです。 この事実は、現代の学者によって示唆されたいくつかの特別な政治的解釈のためにこの詩篇を選び出します。 |