| Tonus Peregrinus: The History of a Psalm-tone and its use in Polyphonic
Music 5 Lundberg, Mattias. Chapter 5 The Rise of an Idiom: The Tonus Peregrinus in French Court Litergies of the Sixteenth Century |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
Psalmus 113 (114+115)
|
The French kings as imitatio David regis - a political perspective on the French cort liturgy (略)
p74ジョスカンに関する彼の重要なモノグラフで、Helmuth Osthoffも同様の考えに達したようである。 彼はIn exitu Israel モテットの概念や本来の機能については詳しく説明しませんでしたが、他のジョスカンのpsalm motets、Memor esto verbi tui (Ps. 118) と canon-based De profundis (Ps. 129), について論議する過程で、 彼は次の結論を引き出したすなわち、「おそらく、ルイ[XII]が当時展開されていた詩篇の設定におけるジョスカンのイニシアチブに特別な関心を示し、現存するジョスカンの詩篇の中には、もともとルイを対象としたさらなる作品があったかもしれない。」20 特に興味深いのは、 Osthoff が、ムートンやセルミシの In exitu Israel 設定に直接関係することなく、この前提に到達したことです。 したがって、彼は間接的に、 Maceyによって議論されたimitatio Davidと、フランス王室との最も明白な関係を持たない特殊なIn exitu Israel とのつながりの可能性を提案している。 (ムートンとセルミシは、私たちが見てきたように、作品が考案された可能性が最も高かった当時、王室と直接つながっていた)。 ムートンがルイXIIの次女の誕生を祝うために自由なテキストを使ってモテットの冒頭のテキストとして、詩篇113のverseからのテキストNon nobis Domine, sed nomini tuoを使用したのは、詩篇113篇の特別な解釈から生じた「イスラエル」としてのフランス王国の神学的政治的概念のように見える別のジグソーピースになったのである。 私たちが入手できる情報では、フランス王室礼拝堂が、おそらく国家主義的および地政学的な動機から、詩篇113にいくつかの特別な重要性を帰したことを示しているようである。 これにより、ムートン、ジョスカン、セルミシの3つの大規模で精巧なモテットの作曲が刺激された。もちろん、提案は推測に過ぎないかもしれないが、これらの作品の起源について少しでも知りたい場合は推測が必要である。 この本のトピックについては、その起源は確かに非常に適切です。問題の作品はポリフォニックの伝統を始めたようであり、すぐにそのような神学的な意味合いを超えて、別の、より一般的には聖体主義的な性格を獲得しました。 A Huguenot setting of the tonus peregrinus 16世紀後半、ヨーロッパ中の作曲家が精巧なFranco-Flemish 詩篇モテットの影響を受けたため、tonus peregrinus はまったく異なる状況下でフランスで使用された。 ユグノーのヒューマニストであり作曲家であるClaude le Jeune (c.1530–1600)による多数の韻律詩篇では、詩篇113の詩的なtranslation-cum-paraphrase への6声のsyllabic homophony の詩篇唱セットが見つかった。 おそらくカトリックのJean Antoine de Baïfが書いたものだろう。 それはプロテスタント聖書の使用法に応じてそれぞれ114と115の番号が付けられた2つの設定で– Quand pour Egypte eloignerとNon、nonànousに分かれている(パラフレーズされたドキソロジーを含む)–Académiedepoésieet de musiqueから出版された。Le Jeuneはそれに、積極的に参加していたようです。 Le Jeune 、ブルボン王朝のアンリ4世の下でフランス宮廷に勤務し、元々はユグノーであった。 ヴァロワ朝の王のもとで書かれたこのタイプの In exitu Israel のモテットは、ルジューヌのキャリアのピーク時にはフランスで時代遅れになり、おそらく彼の作曲家の興味の範囲外にあった(彼の世俗的な音楽が彼から多くを学んだことを明らかにしたとしても)上記の作曲家)。 詩篇113の彼の musique mesurée の設定は、厳密に言えば典礼音楽である私たちのトピックに限っては、様式的にも文化的にも限定的なものである。Le Jeuneの詩篇の設定は、本質的にプライベートな領域のためのものであった。21 偶然にも、セルトン のIn exitu Israel setting は Le Jeuneに知られていた。これはカルヴァン派に沿ってのtonus peregrinusの採用のまれな例のように思われるが、これはまた、事実上、詩篇唱が西方教会のすべての主要なbrancheに属するポリフォニック音楽に採用されたことを意味している。 ここに登場するのは、カルヴァン派の神学者たちの間の伝統的なローマカトリック典礼の要素に対する一般的な疑いの背景に考えなければならない。また、当時のフランス王国のヒューマニスト作曲家や詩人たちの宗教的寛容を反映していることも。 Tonus peregrinus works with texts other than Psalm 113 16世紀初頭の詩篇146Lauda anima mea Dominumの4声設定は、ムートンとジョスカンの両方のモテットに似ています。22 この詩篇にtonus peregrinusを適用する理由は、この詩の帰属もそうであるように、明確ではありません。23 まず第一に、このモテットは、ゲルマン系のtonus peregrinusバリアントを全体的に採用している。これは、フランドルの作曲家によると思われる作品では予想外である。 Tim Steele は、1994年に発表された論文で、de La Rue の帰属に疑問を投げかけましたが、10年後、彼は考えを変えた。 p76 Steeleの後の意見は、より説得力があります。すなわち、モテットがドイツ語圏の作曲家による作品であった場合、他の3パートに対する(テノール)cantus firmus の明確な優位性と、オクターブでの模倣の蔓延が予想されます。(逆に、ここでは、さまざまな移調で記述されたtonus peregrinusが頻繁に見つかります)。 ランディーニ終止や、厳格な cantus firmus 書法などの少なさは、もしLauda anima mea Dominum がドイツの伝統に属していたとしたら、おそらく16世紀半ば以降の日付を考える必要があることを意味します。 1553年の印刷物でのその出現ということでは、それは不可能であるが。 ドイツ語の聖歌の方言の採用は、Habsburg–Burgundian の宮廷礼拝堂でのde La Rueの長期雇用で説明できます。そこでは、彼は、プレインソングのソースとポリフォニーの慣行の両面での北部ヨーロッパのレパートリーに濃厚に触れていた。彼自身の作品は、死後ドイツでの出版で広く流通し、彼は宮廷を広範囲に旅したが、フランス-フランドル派の彼の同時代人の多くとは異なり、 ローマ人が就任したことはないようである。 ローマ方言のtonus peregrinusが完全に支配的であったイタリア語またはスペイン語圏での任命はそれまではなかった。 したがって、この作品の帰属をde La Rueとすることに異議を唱える強い理由はないようです。Lauda anima mea Dominum の計量記譜法での朗唱は、テノールのcantus firmusの設定を約したが、実際には、その設定はJosquinの In exitu Israelによって提供されるような異なる技法のデモンストレーションではない場合でも、それよりもはるかに多様です。 表面上では、模倣のルーティンに従っているように見えるパッセージでは、伝統的なcantus firmus のやり方で、パートの1つが常に他のどのパートよりもある程度、tonus peregrinus に固執している。これは時折、テノール以外のパートにも適用されている。たとえば、第129-134小節のバスのように。(Example 5.4). 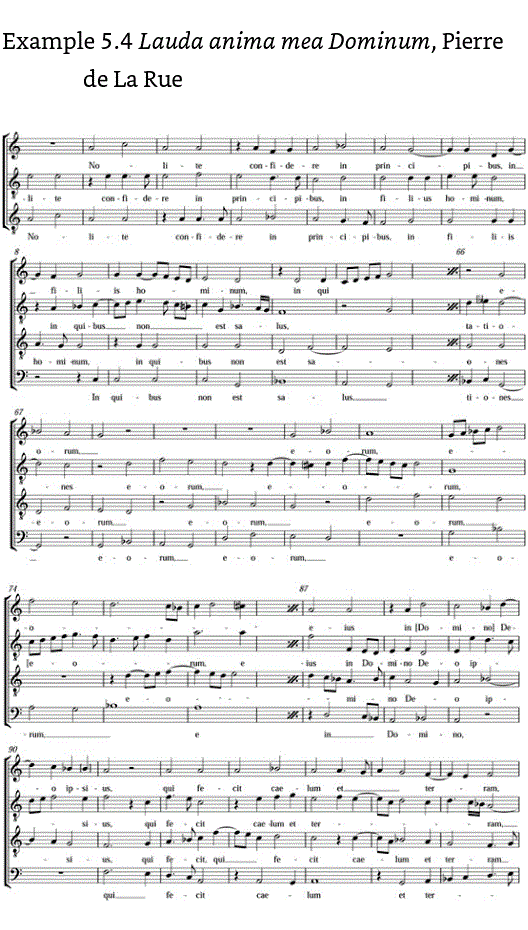 以前に議論されたモテットのそれらに似ているいくつかの bicinium パッセージが見つかりましたが、より高密度のテクスチャーに対する強い好みがあります。 tonus peregrinusの朗唱を引き立たせるために、3パートでいくつかの注目を集める準ホモフォニックな書法があります(bb。96–97)。 珍しいことに、作曲家は、トス・ペレグリヌスの terminatio 形に適用された模倣にこだわっている。そうでなければ詩篇唱のセクションは、その強いカデンツ的性質のために、 セクションをround offするためだけに最もよく使用される。第66–76小節は、この点に関する作曲家の対位法的技能を証明している。 tonus peregrinus に由来する断片の集中的な使用は、本当に驚くべきことである。terminatioはそのコンテキストから完全に動かされ、第66–76小節の集中的なstrettiの構成要素として使用される。 この例は、de La Rueの多くの同時代人とは異なり、彼が音楽のバランスを乱さない方法でこれらの企てを常に使用する方法を示している。この一節は、最高潮のカデンツに向かう勢いを重ねた書法への、ダイナミックなアプローチを示している。 p78 このクライマックスの感覚は、テクスチャー、ピッチ、ハーモニーのレベルで達成され、最後に(そして最も驚くべきことに)、第75および76小節のバスでの増価の特徴的な効果によって達成されます。 terminatio 形は、同じパート内の自由な移調で示されます。これは、様式的に進歩的な手順です。 作品におけるパート書法の平等性も、この初期の時代ではまれです。 この特徴は、他のパートと同等の条件で動作するバススパートで最も顕著に見られます。この側面については、16世紀の-leading規制に関する記事でより具体的に説明しました。25 Lauda anima mea Dominum には、音符の持続時間と和声のtonus peregrinusにおける朗唱ダイナミックスを保持する傾向があります。 時々、作曲家は、第32-37小節のカデンツの voice leading (そこではmediatioが2番目の朗唱に直接つながるか、または accentual elaboration (b. 145),から始まり、詩篇唱の第2semi-verse がunaccented tactus unitで開始されている)から生じるような動きに対する障害を最小限に抑えて、全体の詩篇唱を自由に動きまわらせたいと願う。 テクスチャを変更する多様な効果は、強いられたカデンツでその勢いを維持している。他の場合では、強力な終了効果を達成するために、一般的なtonus peregrinusカデンツが対照的に強調される(bb。89–91)。 これは、詩篇113の初期のパリの宮廷での設定と同じくらい洗練された、さまざまな対位法のスタイルである。Lauda anima mea Dominum は、戦略と実装の両方で印象的な作品である。 Pierre de La Rueの作曲でなかったとしたら、それは別の非常に有能な作曲家の作品でなければならない。そして、de La Rue が疑いなく称賛され人気のある人物であったとしても、 Montanus and Neuberは、故意かどうかにかかわらず、別の主要な作曲家の作品を誤解して、マーケティングの可能性を見落とした。 Philippe de Monte (c.1520–1603)による6声のMissa ad tonum peregrinum は、ヴロツワフのBiblioteka Uniwersyteckaが以前持っていたコレクションにリストされています。この原稿は1890年にエミールボーンによって言及されましたが、第二次世界大戦中にベルリンに移され、現在は失われているようです27。 de Monteの現存するミサの設定の価値と独創性、および通常のミサの枠内でのtonus peregrinusの採用の珍しい(唯一ではない)ケースを考えると、この作品の損失は、tonus peregrinusの全歴史の中で、最も残念なことの1つとして数えられる 。 de Monteのパロディに対する傾向に照らして、このミサ曲は、詩篇唱自体だけでなく、既存のtonus peregrinusモテットにも言及した可能性があります。 Conclusion ここで説明するすべての作品の遺産、特にムートンとジョスキンの詩篇113の設定の遺産は、次の章でいくつかの重要な作品を通じて追跡されます。 tonus peregrinusが、通作されたモテットのイディオムでうまく使用されたのは偶然ではありません。 cantus firmusモデルは、特定の典礼目的に関連する詩篇唱に非常によく適合しました。これらの作品は、その適切な祝祭的な機能で、 tonus peregrinus を自然に強調する自然な方法に対応しています。 この事実はまた、公式に認められた8つの詩篇唱とは少し別のところに、tonus peregrinusを設定しました。たとえば、それは、1564年にRoy and Ballard によって発行されたSermisyとCertonによるすべての(8つの)詩篇唱のMagnificat設定のコレクションには含まれていませんでした。28 このようなコレクションからの除外は、自然に、tonus peregrinusのモテットイディオムのアイデンティティを強化するのに役立ちました。 ジョスカンの cantus firmus テクニックを、その cantus firmus がシンボルとして使用された主にスピリチュアルなエクササイズであると説明した時に、Osthoffは、Franco-Flemishの In exitu Israel 設定で示されたある種の典礼の強調効果に、大きな洞察を示した。作品全体に対するシンボルの影響は、それを知覚することよりも重要です。29 16世紀初頭の過程で、Franco-Flemish composers は、象徴的なイディオムとして In exitu Israel モテットを確立した。 このイディオムが後の世代の手で広範囲な様式の変更を受けることになったとしても、それはtonus peregrinusの切れ目のない使用を通じてその象徴的な価値を保持していた。 16世紀後半に執筆した Zarlinoは、実際の音楽家らに認められた古くて由緒ある種として、さらなる議論なしに、彼の読者にtonus peregrinusの旋法特性を紹介することができたとき、彼は模範的な作品の知識を仮定した。その中においては、In exitu Israelの設定は確かに最優先であった。30 彼の声明は、豊富な転載と写本のコピーとともに、それらの歴史的および典礼的な重要性を証明している。 皮肉なことに、かなり具体的な政治的および文化的状況によってかなりの程度まで形作られた可能性のあるイディオム(フランスの法廷典礼)が、西方キリスト教世界全体に影響を与えるようになったのである。 その可能性は、文化的および芸術的概念が、私たちが期待する方法で普及することはめったになく、音楽では特に、作品とそれを支える元のアイデアの間には常に明確な分離があることを思い出させるだけである。 さらに、それは、 tonus peregrinus の典礼的および音楽的役割がどの程度これらの作品によって形成されているかを示している。 したがって、以降の章で取り上げる音楽は、その存在がここで説明する設定に大きく依存している。 |