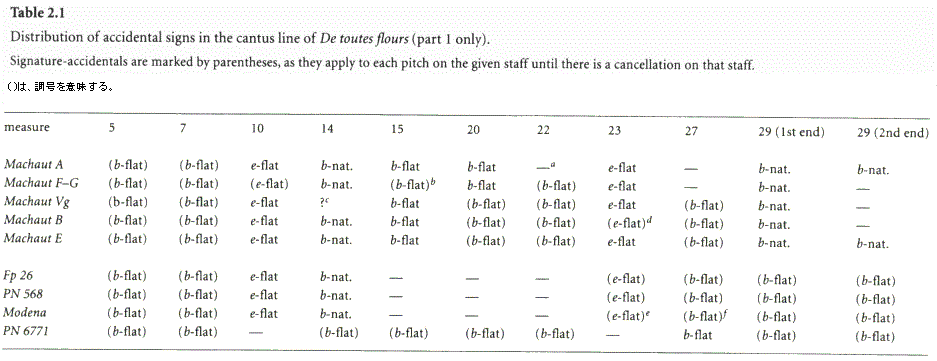| Chromatic beauty
in the late medieval chansons T.Brothers |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
| p108 Biaute qui toutes autres pere The Works of Guillaume Machaut バラードのスコア Biaute qui toutes autres pere(例2.8)は、3か所の結節点それぞれが、同じDを強調する異様なカデンツパターンで作られている。  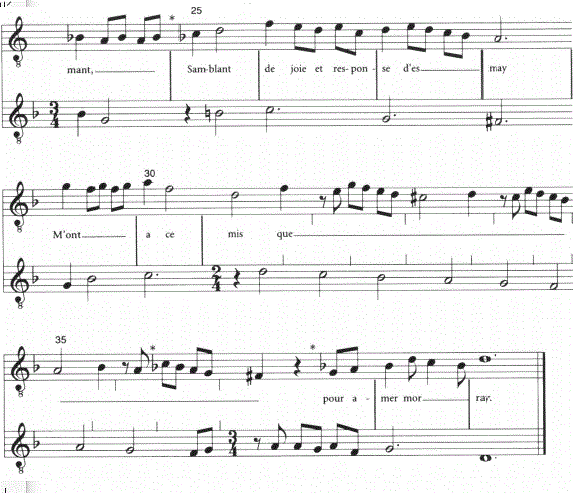 Biauté qui toutes autres pere by Guillaume de Machaut p110 マショーは、ouvertとclosを、互いに、ouvertには完全五度(D/a)、closや最終終止には完全オクターブ(D/d)のコントラストという微妙な手段でのみ、区別している。(1336年に、Petrus Frater dictus Palma Ociosaは、五度よりもoctaveが安定しているという、音程のヒエラルキーをコーディングした43)。 さらに、3つのカデンツは弱く、それぞれにおいて、テノールは跳躍で動き、cantusには導音がない。(Nes que on porroitのように) それは挑発的な組み合わせである。すなわち、マショーは、3つの主カデンツを、同じピッチにおいたこと。それはあたかも、彼が以前に行った、the sense of large-scale forward directionを否定するようなものである。 p111 Biaute qui toutes autres pereは、我々が、”終止より分析を始めよ”という、旋法理論の基本概念に従うのであれば、ほとんど意味をなさない44。 Dを強調する3か所の主カデンツ以外では、このソングでは、Gが一番重要なピッチとなっている。この作品は、結節点と、互いに対立するような内部の流れの計画との間で、矛盾したやり方で作られている。おそらくこれは、主カデンツの比較的な弱さを説明している。すなわち、矛盾した内容において、they seem not to conclude what has gone before. そして3回の繰り返しは、カデンツが内部の流れの主たるdiscourseとは立ち位置が異なるというideaを支持している。なぜならそうした繰り返しは、ouvertーclosパターンから期待されるthe sense of large-scale forward directionを否定することだからである。 Dは、ポリフォニーの流れを通して暗示された安定した目標よりも、セクションの終わりでの繰り返しにもとずく終止と関連している。 Gは、パート1において、メロディ、和声的イヴェントを通じて、メインピッチとして強調されている。冒頭のsonorityはG/dである。そして、最初の重要な到達点は、第7小節でのGである。第3小節のテノールのE♭は、下げられた導音を提供している。cantusにおいては、F♯がGへの到達を示す。45 第7小節が強い到達点をマークする感覚は、cantusが第9小節でdに駆け上がることで、確認される。そこでは、両声部は、最初のG/dを正確に作っており、その後の第9-16小節の雄大なメリスマへと滑り込んでいくのに適している。kのメリスマにおいて、テノールのシンコペーションは、リズムと和声において、着実な緊張を提供する。46 46 Carl Dahlhausは、以下のように第9小節のテノールの休符をはずせば、テノールのGとsuperiusのDが同時になり、cantusとtenorの間で協和音g形成される、としている。  p112 Gは再度、ここのところの不協和音、複数の計量記譜法のパッセージが第15小節のF♯を明らかにする、という事実によって強調される。そして第10小節の(cantusの高い)gはまた、最高音として、その位置が強調される。そしてそれが(第13小節の)aで下げ止まると、cantusは、ouvertとclosの終止の間の伝統的なステップワイズな関係(a-G)を予見しているように思える。 パート2は、C,B-flat,Cを強調したdigressionで始まる。こうした手順は、バラードとしては、だいたい一般的である。最後に、Gの重要性が、その他の構造的モーメントにおいて再確認される。すなわち、ルフランを宣言するのに使われるsonorityは、第28小節のF♯/aである。 パート1とパート2の最後音楽の繰り返しは、複計量記譜法のちょっとした改訂とclos終止の再声明をもたらす。 Biaute qui toutes autres pereは、単一の支配的ピッチにreduceすることができない。あいまいなデザインにおいて、臨時記号によって提供されたその指向的ヒエラルキー的示唆は、より重要になっている。さらに、F♯とE♭の役割は、たがいに、Dを覆うGを強調している。47 Biaute qui toutes autres pereは、マショーがバラードに特に関心があった比較的初期の作品である。おそらくは、絶え間ない、実験的な閃きは、ブレイクスルーを示している。 若きマショーは、複計量記譜法やシンコペーションリズムを通して、アルスノヴァのリズム的コンポーネントの統率を示した。そして、近接的applicationsの操作を通して、アルスノヴァの和声的言語の統率を示した。それは、通常ではない共同である。 トロヴェールのMS Oの研究において、音程の扱いやデザイン形成に対して、臨時記号の干渉がどのようにさまざまな可能性を差し出したのかを、我々は考察した。 p113 こうした技法は、アルスノヴァ和声的構文を通して、伝播された。75年後、デュファイは、Biaute qui toutes autres pereの概念に接して、その概念での仕事をした。 デュファイはそのバラード、Je me complains楽譜(p108)で、dを強調し、c♯がそのメインピッチであるという感覚を強めた。48. Je me complains piteusement - Dufay しかし、Je me complainsの3か所の主カデンツ(第7,10,28小節)は、”半カデンツ”を形成して、a/c♯で終わっている。伝統的なcantus-tenor フレームワークは、primus,secundus,tertiusとマークされた等しい音域へn嗜好において、放棄されている。伝統的なdiscantカデンツは不規則である。 通常ではないフォーマットへの応答においてのように、デュフィは、明らかに指向性の強い半カデンツであり、D上での強いsonorityを規則的に置いて、弱い到達点ではa/aaとなるこのプランを打ち出している。Biaute qui toutes autres pereにおけるように、注意深く置かれた臨時記号は、野心的な計画において、重要な役割を果たしている。 De toutes flours Guillaume de Machaut, B31 - De toutes flours (MS Vg) 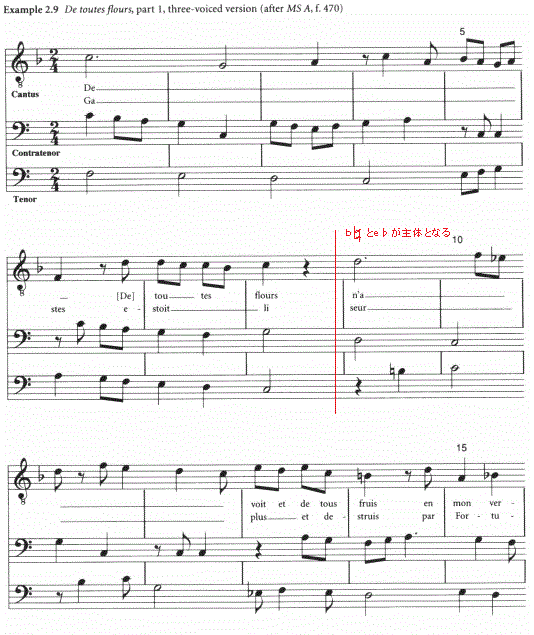 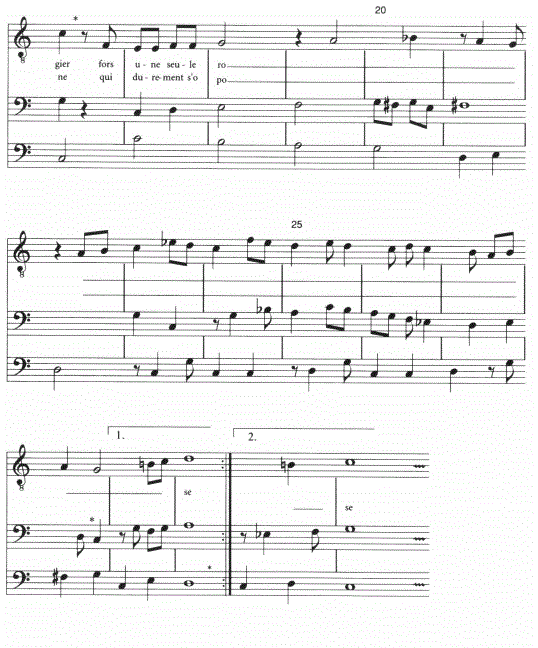 マショーのDe toutes flours(例2.9)は、近接したapplicationへの記譜しない慣習についての中心的問題を持っている。主に、音楽テキストは、おなじみの仮定と矛盾しているからである。 こうした過程をドロップして、我々は歌詞を、和声の基礎的なコンポーネントを操るマショーの関心のさらなるdisplayとして読むかもしれない。 ソングは、Fullerによって分析されてきた。和声に関するFullerの仕事は、臨時記号を解釈するための強い基礎を提供している。49 p116 ここで興味深いのは、第15小節でのb♭についてである。すなわちこれは、第14小節において、b スクライブの懐疑によって♭がつけられた可能性は理解できるが、Table2.1にあるように、主要ソースでは見られるが、二次ソースでは♭がついていない。当初のマショーの写本すべてがここが♭であり、その後の二次的資料では♭がない、ということは、まず、考えにくいのだ。 p117 同様のイヴェントは、後の作曲家らによる2つのソングでも生じている。SolageのLe Basil楽譜の弱いカデンツにおける、同じb♭の使用は、すでに、p31で述べた。De toutes floursとの類似は明らかである。 Solage - Le basile このイヴェントは、the sense of large-scale musical designsでも同様である。なぜならそれは、ポリフォニーが最初のしっかりと確立されたCから離れて流れる漸次の不安定さの一部を形成するからである。さらにCは、パート1のclos終止で戻る。そこには、Cと関連した安定性から、いくつかのinflectionsや和声的ターンと関連した不安定性へ、さらに再度Cと関連した安定への動きがある。 数年後、Johannes Cesarisは、彼のバラードBonte biaulteで、同じgestureを使っている。b♭を通したcへの動きは、その到着を弱める。(コントラテノールのeも、(盛期ルネッサンス期以降には頻繁に散られるようになったその)和声の”不完全性”によって、その働きに関与している)。(leading toneではなく)。あたかも、voice leadingの強化に対抗するかのように。 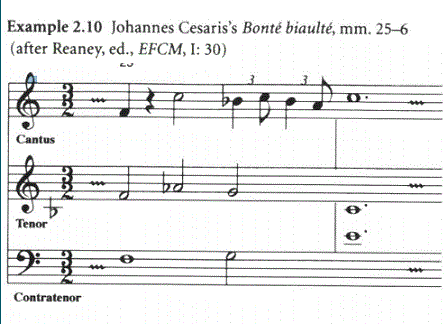 その暫定的な到達は、こうした位置でのカデンツによく合っている。なぜなら、このような(G―b♭のような)和音は、バラードのルフランの宣言に奉仕するから。(Biaute qui toutes autres pereの第28小節のF♯-aを想起させる。そこでもまた、こうした不完全協和音が同じ目的で使われている)。続くルフランは、作品に、主要音Eでの決定的な強力なカデンツをもたらすのである。 これらのテキスト3か所すべてが壊れていることはあり得ず、それらはあらゆるデザインにおけるツールとしての臨時記号の使用において、同じ関心を示している。訓練された歌手らは、非慣習的なカデンツの”訂正のしかた”を知っていたと考えるよりはむしろ、Fullerがそう考えたように、彼らはこうしたカデンツを書かれたように扱うことに長けていた、と考えるべきだろう。 上げられた導音は、理論家たちがすべて同意するように、到達度合いを強める。そうした上げられた導音がないと、到達度はより弱くなる。こうした技法によって、作曲家は、互いにヒエラルキー的に同じピッチでのさまざまな到達を区別する別のやり方をするようになる。音楽は常に2つのレベルで、さらには2つの相反する方法ですぐに機能する可能性を提供する。この技法で、作曲家は、前向きの動きを止めることなく、到達点をマークするようになる。 p118。 マショーのDe toutes floursでの下げられたb 私はDe toutes floursの写本の不安定性を説明するために、Lectio difficilior potior(特定の解釈で異なる写本が競合する場合、より珍しいものがよりオリジナルである可能性が高いこと)を提唱したい。 この原則は、臨時記号の研究においては、これまでほとんど適用されてこなかったが、特異的な解釈は、時代を超えて、慣習化されてきた、という想定をフォローする。52 Table2.1は、写本が次第に詳細化したことを示している。同表は、作品の不安定な性質が次第になくなっていくことを示している。基本ソースは、ソースにおける変異が非常に高い。2時ソースのうちのFP26,PN568,もでなA は、基本ソースで記譜されたinflectionのほとんどを保存している。それらは、第15-22小節のb♭は欠いているが。PN6771のスクライブは、千篇一律で、superius全体で、e♭はほとんど現れなくなる(表ではパート1のみ表されていないが、パート2でも同様)。もしも我々が、この版しか知らなければ、我々は、作曲者の概念んの本質的成分についての糸口がなかったことだろう。one can only wonder how many times that has actually happened throughout the surviving polyphonic corpus. 画像入る 煩わしいb♭は、ソングにおける分析の恰好の対称となる。cantusは、最初の音楽フレーズである第1-8小節では、cで始まり、終わる。最後は、反行で、不完全sonorityからC-G-cの完全sonorityで終わる。 b♭は、ほぼすべてのソースにおいて、支配的であるが、その到達点は比較的、弱い。第14小節で初めて、b そして、すでに見てきたように、第16小節でのカデンツにおいては、第8小節と同様、導音が欠けている。 p120 作曲家が、すべてのcへの到達を、同じような形では望んでいないという正当な理由があるだろう。最初のフレーズの間、いくつかのイヴェントは、ピッチの間での、いくつかの明らかなヒエラルキー的感覚を弱めている。 cantusはcで始まるが、それは、テノールではFで和声付けされている。そして、第6小節では、Fは再度強調され、cantusの最下音となる。cantusは、b♭を通したcから離れることで、このFに到達する。53 中世後期のソングではしばしば起こることだが、ピッチは動的かつ予測不可能に編成され、ある種の旋法や調性の”中に”こうしたフレーズや作品をラベル化するミスリードの原因となる。 フレーズ2は、第、9,14小節でのb この変化は、和声的緊張を産生するばかりでなく、作品を正確にFから遠ざけることになる。b Biaute qui toutes autres pereがパート1の最後で、流麗なメリスマをもたらしたように、De toutes floursにおいても、cantusは、第20,22小節でのb♭を通して、メリスマとなる。 (略) p121 マショーは、デザインの広範囲な感覚とともに、臨時記号の使用におけるニュアンスを統合する能力を示した。56 Sarah Fullerのこの時代の観点は、彼女を重要な仮説に導いている。それは、アルスノヴァのポリフォニーの表現の中心に和声を置く、ということである。 作曲技法のイシュー指向の歴史は、14世紀の作曲家の第一の任務が、新しいリズムの実践によって前へと強制される新たな和声的資源を支配・発展させることであったということを示唆している。(ON SONORITY IN FOURTEENTH-CENTURY POLYPHONY: SOME PRELIMINARY REFLECTIONS Sarah Fuller p38) 補足的な見解は、作曲家らが、ポリフォニー音楽の中心的な部分となった和声構文の固有の柔軟性を利用する方法を発見したことであろう。これらの努力は、しばしばアンソロジーを形作った伝播の経路を通して踏みにじられたことだろう。 その踏みにじりは、De toutes floursの伝播で明らかである。そこには、疑念的な問題もある。分析が一般的な調性とのアナロジーによって過度に条件付けられている場合、14世紀の和声的構文のニュアンスや柔軟性は、どちらもわからなくなってしまうことだろう。 p122 このように分析して、我々は、causa pulcritudinisへの近接したapplicationを追い回すことになるかもしれない。The application Is used here but not there.now with this formula now with that one. ガイドは作曲家のデザインのセンス、すなわち、彼の美的感覚である。discursive メロディーのサービスにおいて inflectionsを使用する線形モデルは、ポリフォニーに移すことができよう。 Further notes on style and transmission (略) 垂直の三全音はたとえば、Rose,lis(例2.11)からのもっとも愛らしき断片のひとつをマークする。D/b 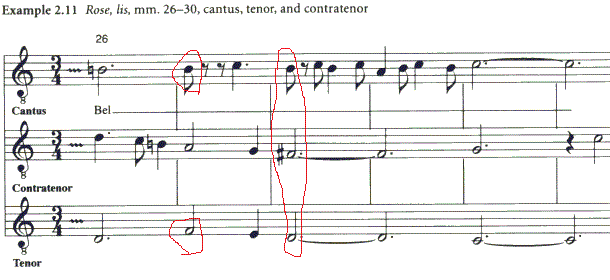 p123 マショーは、困難な跳躍をも使う。Amours me fait desirerの冒頭は、Gからc♯への跳躍で始まる。Je sui aussiでは、同じ三全音が、バラードのスタンザのパート1と2の間のブレイクとして機能している。Ne penses pasのルフランでは、cantusは、完全ロングで、f♯からcへと進行する。61 演奏実践の想定された慣行として、直接的三全音を好む作曲家による作品への間接的三全音に対しての記述を適用することには、確かに慎重であらねばならない。62 第1章の一般原則が、ここで強く適用される。すなわち、作曲家は、プレインチャントに合った音程の礼儀正しさの標準に歩調を合わせるというよりも、それに対抗しようとする。マショーの作品で粗く描かれた輪郭を均すための、記譜されていないinflectionsの適用についての演奏実践は、こうした慣行にはまったく入り込まず、むしろ逆行する。すなわち、劇的フレアを伴う困難な跳躍を強調するような演奏実践を、容易にイメージすることができる。 Honte,paour,doubtanceの最初のフレーズは、4番目のシラブル-ourで詩的caesuraを強調するようにデザインされた近接したinflectionへのdisplaced-オクターブ(fis-g)での解決を特徴としている。その近接したinflectionは、いる。(例2.12) プレインチャントと関連したメロディの礼儀正しさから判断して、マショーは、エレガントな作曲家ではあり得なかった。 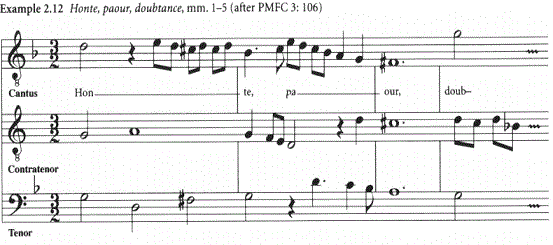 楽譜(No.25) Guillaume de Machaut - Honte, paour, doubtance p124 Summa musice(c.1200)の著者は、九度の跳躍を”いななく象”と記述しているが、マショーのcantus行のような異国情緒的産物を表す”憎むべき不協和音”を容認はしていなかった。63 歴史的内容への証明を欠いていることによる過度の単純化があるかもしれないが、独立した表現力のあるアイデンティティを生み出す機会を生かす作曲家としてマショーをイメージすることは、魅力的である。 Honte,paour,doubtanceは、♭と♯の顕著な隣接を示している。それは、マショーが時折使った技法である。64 パート1では、cantusは、e♭とc♯の双方を歌う。、dへのalternativeな近接したinflectionとして。 パート2では、傑出したe♭は、おなじように傑出したe Rose,lis、De toutes flours、En amer a douce vie, De petit poは、それぞれb 他方、これらのソングのどれもが、cantusにおいて、f♯を持っていない。私は、このinflectionの回避が、特定の臨時記号を互いに混ぜるのを嫌がるのと関係することには、疑問を持っている。 p125 C作品のべつのグループにおいては、cantusでf♯が使われ、e♭は回避されている。65 これら2つのグループのソングに当てはまるいくつかの一般化を提案することが可能である。 f♯を使うがe♭は使わないcantus行においては、下降するメロディの流れのより強い感覚がある。高い♯は、gを二次的ピッチとして強調し、この効果は、低い方へと解決される高い緊張感覚を強化する。 特により初期のソングにおいては、メロディを構成するこのやり方は、強力である。後期のソングでは、同じ技法はより限局的になるが、inflectionの効果はそこにある。 e♭を使う4つのC作品(Rose,lis、De toutes flours、En amer a douce vie, De petit po)は、メロディの方向は、よりバランスがとられ、下降進行の解決の原型に縛られることがない。 これらには2つの傾向がある。高いf♯は、フレーズのピークを強化し、終止からのその距離を強調している。e♭は、ほぼ到達しつつある終止への進行を妨害する。(略) p128 マショーは、Pas de tor en thies paisのcantusにおいて、作品を不安定なポリフォニーの流れに導くような、一連のinflectionsを置いている。すなわち、c♯には、f♯とb♭が続いている。 バラードのパート2では、cantusは、さらに、同じinflectionがある。さまざまな臨時記号が、2つ以上のピッチの支配を明らかにしている。71 テキストの問題が際立っている。おそらくは、たとえば、第14小節のcantusのf♯がつけられるべきか、ということは大きな問題ではない。(第33小節においても同様)。 ここで我々は、それが使用される上で結論がもたらされるまで、inflectionが和声の論理を保持し、かつ、行が解決のピッチgから離れて下降するように自動的になくなるのか、という可能性には、惑わされるに違いない。おそらく、これらの2つのinflectionは非常に短いので、問題にはならない。 一方、最後のカデンツ(例2.13)は、非常に重要であると思われる。4つの主要なソースにおいてそれがinflectionされていないという事実は、注意を要する。 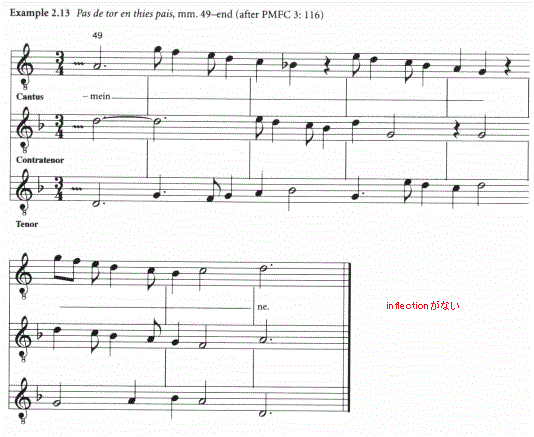 楽譜(No.30) Pas de tor en thies pais - ballade 第44小節のc♯がカデンツを通じて保持されると、軽々しく論じることはできない。臨時記号がこれほど長く複雑なパッセージを支配するのであれば、なぜこうした臨時記号が、ソングの他の場所では、一貫して、繰り返し記述されているのであろうか? 4つのソースにはすべて、第4,15,37,39上のc♯がつけられており、第11,30、39小節ではf♯がつけられている。 なぜなら、そこでは自動的に、臨時記号は必要とされない、ということは、誰の目にも明らかであったのでとのことで、スクライブは、最後のinflectionを記譜する必要はない、と割り切っていたのか?72 p129 状況は、”musica fictaの問題”ともなる。(短八度を回避するという)必要性の規則によれば、第55小節テノールb♭は、cantusでのb♭を誘発する。(実際、すべてのソースにおいて、わずか数小節前に、テノールにはb♭の調号が存在する)。 b♭とc♯がひとつ前の小節に適用されれば、cantusは、増二度とならねばならない。それは、このイディオムでは受け入れられはするかもしれないが、一般的なことではない。演奏者らが、彼ら自身によってこうした矛盾した状況を解決することが期待されていとイメージすることは、困難である。 同じ作品においてすでに明白に素直なinflectionsが記譜されているのに、なぜこのような矛盾した状況が、演奏者に委ねられようとされていたのか? この問題を解決するためには、演奏者は、対位法理論の2つの概念に沿ったいくつかのパートからの記譜されたエヴィデンスをバランスしなければならないだろう。演奏者は、増二度の問題に考え込まざるを得なかったことだろう。演奏者らがこれに応えられた証拠はない。論文も応えていない。 p130 DやGで終止するかなりのソングが、終止カデンツに対する近接した臨時記号を欠いていることは、重要かもしれない74。 数少ないケースでは、終止に至るまで影響するようなより早期のinflectionを認めている。75 その他の場合、導音は、非常に短い音符である。 一方、作曲家が、あえてそれを望まずに、最終カデンツでの臨時記号を記譜しなかった可能性もある。作曲家は、inflectionされない響きを望んでいたのかもしれず、それは、作品に特殊なアイデンティティを提供したことだろう。私は当然、それは旋法へのアイデンティティだと考える。 マショーの詩の直前、パリ人の無名者の1375年に、ポリフォニーソングにおける旋法を分析している。 たとえば、モテット、バラードのようなソングについては、それらの音や旋法の判断についてを明らかにしなければならない。それゆえ、motets,ballades,rondeaux,virelaisのようなソングについての音や旋法のそれぞれの終止に関して、判断をしてみよう。 まず第1に、re,sol B quadratum,la naturalis ,sol,la B mollisで終わるタイプのそれぞれのソングは、第1,2トーンとなる。mi,la B quadratumで終わるタイプのそれぞれのソングは、第3,4トーンとなる。fa natural,fa,ut B mollisで終わるタイプのそれぞれのソングは、第5,6トーンとなる。sol,ut naturalis あるいはfa,あるいはut B qadratumで終わるソングは、第7,8トーンとなる。76 p131 この見方は、ポリフォニーや世俗的モノフォニーに対する旋法の重大性について、75年前のグロケオの注目とは異なっている。さらに、100年後、1475年にティンクトーリスは、それ以前よりもより確信を持って、ポリフォニーの分析の議論を好んでいる。 ティンクトーリスのアプローチ(第4章)は、旋法の”種”の定義とあきらかに結びついている。すなわち、それぞれの旋法は、四度、五度、八度のスカラーモジュールの組み合わせとして定義される。これらのモジュールは、半音と全音ステップの繋がりにおいて、互いに異なっている。 この種の概念をマショーのソングの分析にに当てはめることはポイントがずれている。なぜなら、作曲家が好んだinflectionは、理論をベースとしたモジュールを混乱させているからである。 パリの無名者は、四度、五度、八度の種については何も言わず、彼がこのように旋法について考えていたと信じる理由はない。彼の簡単な声明は、終止音やそのあたりの音程についてを強調している。これは、旋法へのより伝統的なアプローチであり、通常、音域について論議すれば足りている。 |