| Chromatic beauty
in the late medieval chansons T.Brothers |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| p1 Introduction:musicaficta,causa pulchritudinis false musicは、2つの理由から発明された。ひとつは必要のために、そしてもうひとつは必要のために、そしてもうひとつはメロディ自身における美のために。・・・美のためのとは、cantus coronatusにおいて宣言される。 Anonymous2,Tractus de Discantu(c1300) Musica fictaは、中世には多くの名前を持っている。Anonymous2の上記のパッセージにおいて以外の論文では、同じ概念が、musica ficta,synemmenon,conjincta,musica colorataとして定義されている。 これらは、伝統的なグイド音階には含まれていない音程に対する用語であり、13世紀までに確立され、中世後期に十分に発達して文書化されたものである。 p2 グイドの手以外のピッチは、invented ,hooked onなどと分類される。”musica ficta”という用語のinvention感覚はそれゆえ、臨時記号の近代的概念とはまったく無関係である。むしろピッチは書かれた音階に属さないがゆえに、innventedとなるのである。 この現象には、正確な定義がある。なぜならそれは、閉じた理論システムとの関係において考えられているからである。4 4 Karol Bergerは、この定義を拡張し、それは、グイドの音階以外のピッチだけでなく、不規則なソルミゼーションも含む、としている。feigned ステップは、同じ場に見出された真のステップからはピッチにおいて異なっている。feignedであるステップのために必要であるすべては、そのシラブルはfeignedとなる。(Musica Ficta p13) 通常、こうした現象についての中世後期の記述は、抽象的なピッチセットを超えて一歩を踏み出す。彼らが、staff notationやmonochordを通して、実用的な提示を参照するときに。 Petrus frater dictus Palma ociosa(1336): false musicaは、グイドの手には見出されないものであり、プレインチャントの理論によっている。さらに一般的に、false musicは、soft b あるいはsquare bが通常ではない場に置かれることである、と妥当に定義される。 Walter of Odington(jI. 1298-1316): これらの変化しうるbやb♭は、モノコードにおいて、適当な度合いで呼ばれるが、別の変化しうる音はfalse musicと呼ばれる。それらは、不協和音であるためではなく、モノコードの一定位置からは外れているがゆえに。そしてそうした音は、昔はなかったのである。 p3 中世の終わりに、ティンクトーリスは、彼の音楽用語辞典で、以下のように言う。 coniunctaとは、イレギュラーな場にあるround bあるいはsquare bの場所である。 上記のAnonymous 2の簡単な声明の価値は、musica fictaの”美のための使用”に言及している。これは、音楽分析への潜在的な半音階の重要性を示す。 理論家は、musica fictaの使用のための2つの理由を提供している。最初に、”必要のために”は、しばしば13世紀から16世紀の論文では記述されている。 そのタイトルのように、Tractatus de Discantuは、主に、ポリフォニーを作るための基礎的技法を扱っている。そしてそれは、この内容において、必要な規則を提唱している。 Musica fictaは、、五度、四度、オクターブを適合させるために必要とされる。それらを完全音程にするために。 たとえば、b 理論家らがしばしば言うように、もしもグイドの音階での伝統的なピッチに制限されていれば、適当な垂直的sonorityを形成することは不可能であることだろう。 必要性の規則についてのAnonymous 2の報告は、彼が提供したその他の理由と同様、ルーチンである。なぜなら、musica fictaを使うことは稀だからである。そしてこの理由のために、その声明は、簡素であいまいではあるが、正確である。 必要性の規則は、それ自身、美と関係もしていると論じられる。なぜなら、適度に秩序付けられたポリフォニーは、まったく美しいからである。しかし、この時点でのcantus coronatusの導入によって、理論家は、ポリフォニーからは離れるように見える。 p4 少なくとも、(美と必要性の)組み合わせは、相補的関係を暗示する。そしてそれは対立の感覚ももたらすだろう。(略) false musicにとっては、”cantus coronatus"に対しては、じれったい言及のみがある。必要と美の間の区別において、理論家がmusica fictaの使用において2つの異なった思考をするのであれば、その時彼は、ポリフォニーをモノフォニーに対抗して設定することだろう。モノフォニーは、”cantus coronatus"によって示される。 垂直的音程の計量へ密接な注意を払う音楽理論の体系化において、必要性のルールを根拠付けるのは簡単であるが、モノフォニーにとっては、しかし、そうした根拠付けは、それほど簡単ではない。 モノフォニーにおいては、musica fictaはより明らかに旋法性やヘクサコード構成や、ピッチの直線的構成に触れる基本的な理論構築を侵害する。モノフォニーにおけるmusica fictaの適用が簡単に理論統合できないのであれば、美にたいするポテンシャルを単純に認めることよりもより妥当なやり方があるだろうか? ”cantus coronatus"は、中世後期においては、いくつかの意味合いがあり、Anonymous 2に限定するのは困難である。時折この用語は優勝歌を意味するが、こうした使い方は、あまり適合はしない。すなわち、musica fictaによってソングへの賞が与えられたら、その時我々は、我々が見出す以上のより多くの臨時記号を見出すことになっただろう。 別の使い方においては、”cantus coronatus"は、王権の含意を持つが、それは、Anonimous 2が、貴族的作曲家は特に半音階を好む傾向がある、と言うこととは異なったものとなろう。10 Anonymous 2に妥当な言及は、彼を理解する助けとなる。Johannes de Grocheioは、”cantus coronatus”を、より広く論じ、そしてGrocheioがこの用語をひとつのジャンルの定義として用いたことはまず間違いない11. lOhn StevensとChriStopher Pageは独立に、この分野を、今日のgrand chanson courtoisである、と特定した。12 GrocheioとAnonymous2を並べれば、後者では、音階からのオプショナルな偏移が時折、このレパートリーで使われている、と言えよう。 この解釈は、必要と美の間の区別に光を当てることで、意味あるものとなる。すなわち、musica fictaの異なった様式に注目するために、洗練されたモノフォニーに対して洗練されたポリフォニーを設定することが自然なことになろう。 p6 私たちの利益のために、理論家は定量化可能な現象を中心としたdiscourseの旋法から抜け出す。我々は、パッセージを、フランスシャンションにおいて長い時を経てきた13世紀の現象認識と見なすことだろう。monophonicでもpolyphonicでも、双方は、理論的に定量化された目的のために、inflectionのオプショナルな使い方をしている。 Au renovel 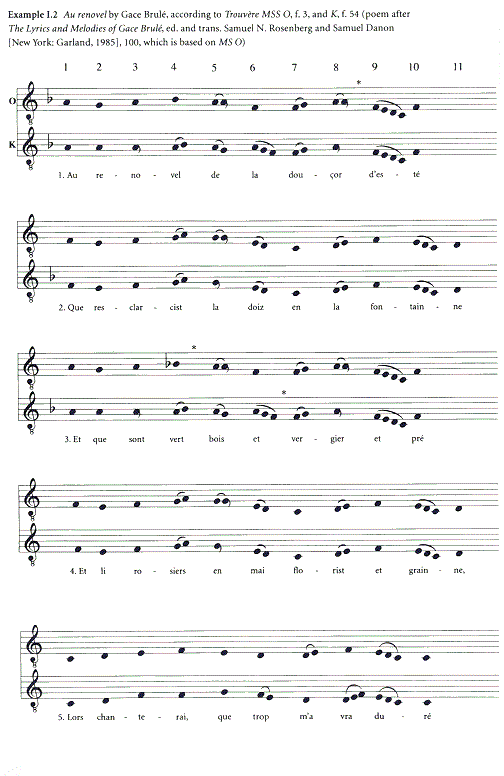 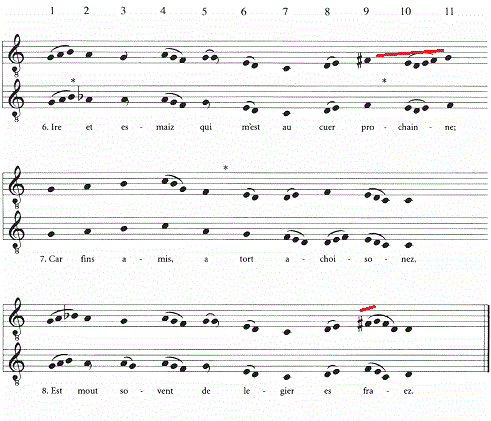 frons(フェーズ1-4)では、MS OはMS Kと変わらないが、caudaになって、フェーズ5でも同じであるが、フェーズ6になると、F♯が導入される。F♯はG上のカデンツを導き、こうしたカデンツは、この写本(MS O)のみであることが重要である。これに符号するMS Kはこのフレーズの最後はFとなっている。digressionは、カデンツでの多様性において、興味深さを示している。 MS Oに符号するMS Kは、D,C,F上のカデンツを特徴としている。そしてこの計画に対して、MS Oの改訂者は、(フェーズ6で最後を)Gとしている。明らかに、F♯は、散漫なカデンツを強調するために導入されているのである。 p9 MS Oのフェーズ7では、メイングループとの合意に戻るが、スタンザの最終フレーズでは、別の重要な改訂が行われている。すなわち、F♯が復活し、カデンツはGでは終わらないが、カデンツの1つ前のシラブルのネウマ的装飾の一部分となっている。 この版では、他の版と同様、Dが、聴き手がソングに投影するヒエラルキーにおいて主要なピッチとなっている。しかし、F♯を介した予想外の遅い流れは、このヒエラルキーを弱体化させる。 F フェーズ6のF♯は、カデンツの論理に従う。その離れた位置から、容易に、以下の理論概念を引き出せる。”それはカデンツでの導音を導く”。 このような声明は当時は存在しないが、cantus coronatusへのAnonymous 2の言及は、トロヴェールソングでのmusica fictaへの唯一の言及となる。こうした見方への唯一の方法は、実践的な証拠からの推論である。 しかし、すでに見たように、そのレパートリーは実践の点において、ほとんど一定していない。現れるのは、多くの場合、いくらかのカデンツで、いくらかの音でinflectionされるのみである。 ”カデンツでの導音を導く”の概念が当時の理論家によって記述されていても、写本の証拠は、統一には程遠く、選択的適用を好んでいる。MS Oにおける最初のF♯は、G上のカデンツを実際に強調するが、このカデンツはその他の写本ではそうではないが、MS Oの場合はinflectionされていることは、重要であろう。 フェーズ8のF♯は、完全にオプショナルである。すでに論じたように、it makes an unsettling contribution to the design. 我々は、13世紀のモテットのようなapplicationは見出せないが、MS Oに保存されたハイスタイルの曲には、一貫したスタイルの編集を提案するのに十分な数がある。 それゆえ、写本の証拠は、理論家がポリフォニーアプリをモノフォニーアプリと比べ、そして、理論的に成分化されたアプリを、その唯一の正当性が美であるアプリと比べたという、Anonimous 2の解釈を支持している。 p11 Chromaticism as digression(逸脱としての半音階) (略) Anonimous 2は、理論的に定量的な目的を持たないinflectionを使用することについて、正当性としての多様性を認識することとして、最も中立的に解釈していることだろう。我々は、より決定的な解釈的な戦略の方向に、彼をわずかに押すかもしれない。 musica fictaの定義は、すでに見たように、正確である。すなわち、それは、グイドのヘクサコード音階(それはまた”全音階フィールド”としても記述される)に属さないすべてのピッチの問題である。 それゆえ、inflectionは、こうした全音階フィールドからのdigressionあるいは偏移と見なされるだろう。そして、音階が合理的創造であると考えるならば、旋法と相互依存する補完的なもの、musica fictaは、不合理な現象として見なされる。 我々は、この点からの可能な影響を、それの資格とそれからつながる理解の色合いをふるいにかけて、考慮する必要がある。 中世を通して、音楽は、数と秩序の連関からくるその理論的厳密さのおかげで、その他の芸術からの嫉妬であった。 p12 理論家たちが、musica fictaを、基本理論外に存在する現象として定義していたことが不幸であったことは、確かである。 本質的なdiscourseは、彼らが音階を再定義することによって、現象を理論に取り入れようと努力していることを示している。 ある点から判断して、このdiscourseは成功はしていない。すなわち、ルネッサンスは、常に正確に定義されたmusica fictaの概念を継承した。 この本の特徴的なソングの多くで、musica fictaは、なにか特殊なものとして使われている。これは特に、対斜が顕著な場合、当てはまることだろう。 それゆえに、作曲的慣行は、ある程度、理論的概念を支持する。すなわち、musica fictaは、理論的に、全音階秩序の混乱として見出される。確かに、それは常にあるケースではないが。我々はそれを一枚岩の現象としては、扱わない。 たとえば、臨時記号は、全音階秩序を移調するために使われることもある。トロヴェールの歌が、musica fictaを使って、同じ音域パターンで、2つの異なったピッチレベルで記譜されていたことを見出すのは、珍しいことではない。 もちろん、inflectionは、不合理な混乱のストロークではなく、むしろ合理的な秩序である他の種類の利用もある。 しかし、より基本的な点は、musica fictaが、世俗ソングの作曲家に利用可能であったとしても、それはピッチフィールドの”正常な”特徴とはならなかったことである。 この時代のシャンソンの多数派は、その控えめな使用である。ほとんどの使用がなかった。全音階フィールドの典型的な使用は、半音階フィールドの非典型的使用が目立っていた内容を形成していた。 さらに、musica fictaの特別なステータスは、全音階が主であるプレインチャントには一般的にこれがほとんど見られないことで、確証される。16 この実践的状況は、ヘクサコード音階の教育的役割から確定される。学識ある音楽家らは、全音階フィールドが、初期訓練のメインパートであることを知っていた。歌手が適切な音程の折衝で節を指さすだけで応答できる程度に、それを内面化しながら。 グイド音階内部のものと外部のものとのピッチの二分法は、文化に深く根ざしていた。 このmusica fictaの概念を当時の思考に対する逸脱と関連付けるための1つの方法は、レトリックを伴う類似によるものである。レトリックは、標準的なデヴァイス、あるいはcoloresであった。.Geoffrey of Vinsaufは、verbal discourseを拡大する6番目の手段として,逸脱を挙げている。 p13 discourse の線をさらに伸ばす必要がある場合は、問題の範囲外に出て、少し後退し、ペンを他のことに捧げます 13世紀の間、レトリックと音楽の類似は普通あった。そのために、このパッセージと、全音階ピッチからのオプショナルな隔たりとして定義されているAnonymous 2の”美的使用”との関係は不適当ではない。18 「逸脱しているが、帰り道を失うほどではない」というdictumは、レトリックよりも音楽においてより容易に可能である。Au renovelについてのMS Oの編集は、その臨時記号が、多様で意外な領域を通して作品をリードし、良いイラストレーションとなる。 Johannes de Grocheioは、世俗ソングとポリフォニー(cantum civilem et mensuratum)が旋法システムによって支配されることはない、と示唆している。この立ち位置は、musica fictaの美的使用としての理解については、重要である。19 p14 我々はすでに、GrocheioとAnonymous2における、”cantus coronatus"という用語についての、同様の使用を記述した。 p15 musica fictaと旋法の間の関係については、(少なくとも)3通りのあり方が考えられる。 ①musica fictaは、旋法の移調の一因となる。 ②musica fictaは、二次的レベルであり、旋法には何らの影響も及ぼさない。 ③musica fictaは、旋法からの離脱を示す。 ②の、臨時記号が二次的位置にあるという見方は、私の意見において、説得力を持って拒否されている。21 私は③の方向を取りたい。なぜならそのために、我々には、彼らが、世俗ソングとポリフォニーが旋法システムによって支配されることはないことや、半音階が美のソースである、ということを暗示した時に。GrocheioとAnonymous2の暫定的なサポートを主張する目的があるからである。(略) Au renovelのF♯は、ピッチフィールドを混乱させ、最終カデンツの強さを損なった。旋法の概念は、通常、統一されたピッチフィールドと単一ピッチの優位性の両方のレベルの制御を主張するために使用される。 そして、もしも旋法が合理的な構築であるならば、損なわれた旋法は、不合理な行動ということになる。 De plus en plus ポリフォニーシャンソンの時代においての、Anonymous 2のmuica fictaの”美的な使用”の、唯一の遠き残照が残存している。それは、およそ1世紀後、Philippotus de Caserta(c、1400):に着せられた論文において、である。 ボエチウスは、2つの理由のために、musica ficta を発明した、すんわち、必要のために、そして、メロディにおける美のために。我々は、必要性の理由を持っている。それは、すべての場において、協和音を持つことができないからである。美の理由はしかし、cantilenaにおいて明示されている。 p16 Anonymous 2の”cantus coronatus”(l400年までには一般的な意味合いを持たなかったであろうが)は、中立な”cantilena"を生じている。その代替は、その言及がジャンルに関連する我々の想定を弱めるものではない。このパッセージのもっとも単純な分析は、それがシャンソンにおいてオプショナルに、musica fictaの使用の伝統を認めている、ということである。 De plus en plus(例1.3)は、若干inflectionされており、半音階的伝統に従っている。 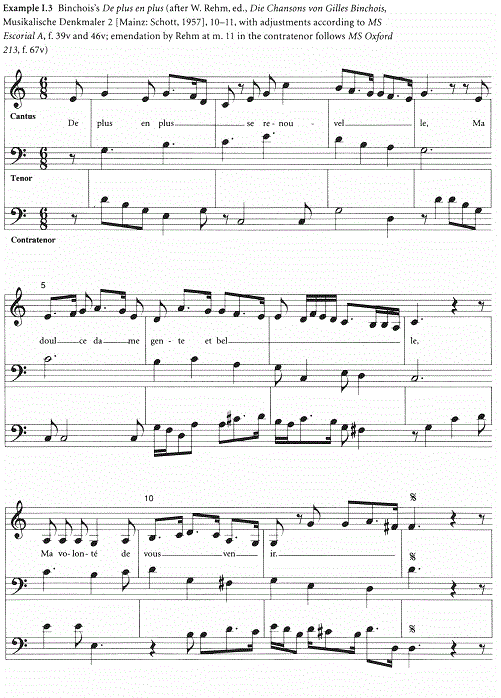 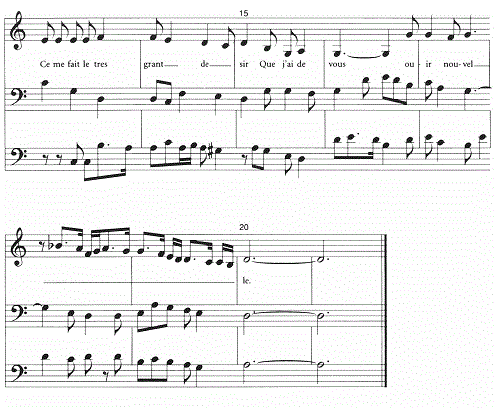 第11小節のcanntusの♯は、ソングの中間にあり、ある種の優位性を示している。ソングがロンドー形式の完全な繰り返しで演奏されれば、この点から最初への戻りが起こるだろう。 ポリフォニーシャンソンのcanntusをテクスチャーを支配するメロディとみなせば、そのinflectionsは重要性を持つ。潜在的に、tenorやcontratenorよりも。 cantusは、そのメロディ的なエレガンスにおいて、歌詞投影の主たる負荷を担っている。こうした点において、それは、トロヴェールの抒情詩メロディの伝統に由来していると言える。 De plus en plusのcantusの優雅さは、遠く離れた女性への渇望をうたう詩にフィットしている。 しかしバンショワは、多くの優雅なメロディを書いたが、この有名な歌の成功は、そしたものだけでは説明できない。メロディの優雅さと並行して、f♯が小粒だが重要な貢献をしている、なぞのデザインがある。 cantusは、今日、我々が第1-2小節のアルペジオ的Cmajor三和音として認めている外観となっている。このジェスチャーの透明さは、作品全体のデザインにおける重要なコンポーネントである。 アルペジオ機能は、モットーとして機能し、ソングの音楽的アイデンティティを直接確立している。その地位は、おそらく、言葉によるアイデンティティを提供する詩的なモットー「De plus en plus」に類似している。23 p17 疑いなく、Cは最初のフレーズではもっとも重要なピッチであり、それは、第4小節で、gでの”開放された”終止となる。 フレーズ2は、第5小節のtenorとcontratenorに支えられ、原調に戻る。そして、バンショワがフレーズ2をcで終えると(第8小節)、彼が最初の2つのフレーズから単一のユニットを作成するために、終止の基本原則をどのように使用したかを見ることができる。15世紀初期のその他のソングも、同様のアルペジオのような始まりとなっている。(略) p19 De plus en plusについてもっとも顕著は点では、それが、最初に、ある音を強く強調していることである。バンショワのルフランの後半が、伝統のように、Cに戻るのであれば、作品は素直なものである。ArnoldのNe me vueilliesのように。しかし、De plus en plusは、驚くべきことに、Dで終止している。 Gは、フレーズ3,4で強調されている。それについては、CとDの間の移調のピッチとして考えることが可能である。 最後のカデンツが第15小節のDでのカデンツによって準備されているのは確かであるが、にもかかわらず、それが安全に聞こえるやり方での予見は困難である。 ソングがルーティンにCで終わっているのなら、あまり面白みはなかったことだろう。そして、中間点にf♯がなければ、やはり面白くなかっただろう。 常に、inflectionsは、より大きなcontextに頼った、、多かれ少なかれ、重要である詳細を表している。 De plus en plusは、2つの15世紀のソースで伝播されている。MS Escorial Aは、例1.3にある臨時記号すべてを持っている。それらは、しかし、MS Oxford213 ではすべてなくなっている。 なぜf♯がcantusから脱落したのかを想像するのは、容易である。ロンドー形式の記述に従って、この中間点からソングの始めに戻る時に、f♯は少し遅れて、gへと解決される。それは、三和音の(下の)ピークである。 和声的には、その解決はイレギュラーであるが、バンショワにとっては、通常でないことはない。cantusがf♯から音楽的ルフランの第2部へと移る時にはしかし、inflectionはすべてを解決はしない。 現在の編集者は、cantusは第13,4小節ではf inflectionは、音楽的ルフランを効果的に、二分する要因となっている。ルフランの最初の方は安定し、予想できる感じであるが、あとの方は、不安定で予想ができないようになっている。25 p20 中間点の♯を取り去ることは、両部分の間の移行をスムーズにする。削除は簡単だが、バンショワの”難しい”解釈のちょっとしたことに重要である。 当時の音楽理論は、こうしたイヴェントの理解には役に立たない。旋法理論は、はじめの三和音的モットーの詳細を理解する助けにならない。そして、安定から不安定への動きの過程を明らかにすることもない。26 移調されたヘクサコードの理論は、中間のf♯の理解に役に立たない。このケースでは、これらの伝統的な理論は、空疎なままである。それらは作品を理解するための戦略に道を開かない。 我々は、伝統的な理論を捨て去ざるを得ず、緩やかで柔軟な音楽構文を認めている。そうした音楽構文は、特異なinflectionや特異なデザインに適合している。 実際、これは、後期中世の音楽におけるメロディ的そして和声的デザインを作る一般点となるかもしれない。すなわちそこには、システマティックな構文を探す傾向にある場であるかもしれない。 Au renovelとDe plus en plusの両者の書かれた記録は、臨時記号の伝播における不安定性を示している。両者では、それは異なってはいるが。(略) Au renovelとDe plus en plusの両者ともに、inflectionsを実践するための記譜されない伝統が、変異として説明されていたと信じられる理由は存在しない。 ”書かれた臨時記号に対する明らかに何気ない態度は、演奏者に備忘録を実践させるという文脈でのみ意味がある”という主張があるが、そうした主張は、上記2ケースには当てはまらない。そして両ケースは、1275-1450年頃のシャンソンの伝統から外れてはいない。 |