| Subtilitas in the tonal language of Fumeux fume Peter M. Lefferts |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| 楽譜 シャンティ写本 60/82(59r) p176 14世紀後半のフランスのレパートリーには、創意工夫と繊細さを特徴とする音楽が含まれており、その参照用語は完全に芸術自体に由来している。 当時最も有名なフランスのシャンソンの1つである、ソラージュのロンドーFumeux fumeには、多種多様な芸術や巧妙で大胆な音楽テクニックが含まれている。 しかし、音楽のars subtiliorのよく知られた特徴である表記法とリズミカルな言語の贅沢とは対照的に、Fumeux fumeの最も顕著な特徴は、臨時記号の増殖とそれらが示す奇妙な音の振る舞いである。F、C、G、D、A、E、Bに加えて、表記されているピッチには、B♭、E♭、A♭、D♭、G♭、F#、C#、G#.が含まれる。1 1.臨時記号の範囲は、このシャンソンが作られた音律システムについての憶測を即座に引き起こす。音符は、F#=G♭、C#=D♭、G#=A♭となるピタゴラス音律の16のうち15を構成している。D#(= E)またはC♭(= B)などのような音符が特定されていないため、ウルフの五度と呼ばれる五度の位置は、未定のままである。これは、BとF#=G♭(D#の場合)またはEとB(B =C♭の場合)のいずれかの五度となったことだろう。 これらのウルフの五度はどちらもcantus と tenorの間に書かれているのではなく、B-Eの四度は第9小節と31小節の cantus と contratenor の間で生じ、B-F#の五度は第5小節のcantus と contratenorの間で生じている。 これらの臨時記号は、Fumeux fumeの実質的にすべての編集上の問題の原因であり、その音言語においてどのようなsubtilitasがそこにあるのかを、明確に評価するために存在する。この論文では、その特異性の防御とともに、(例1として)新しい版で紹介する。必然的に、そのような版は、ソースのあいまいさを解消するバージョンを構成する。 ピッチに関する作曲家の意図のほとんどは、既存の情報源の証拠から認識および復元できるという推定を明確に受け入れています。 問題は、musica fictaの扱いにくいものではなく、musica rectaの解決し得るものものです。 Fumeux fume はその唯一のソースである有名なシャンティー写本からの注意深いtranscriptionsを提示する出版物で見ることができる。2 p177 どちらも臨時記号の解釈に完全に対処していないため、これらのどちらも演奏者に推奨することはできません。いくつかの点で、両方ともソースのエディションですがしかし、作品の版ではありません。 Fumeux fume の場合、選択できた他の多くの例よりも強力な編集者の必要性が明確ですが、実証された原則は一般的なものです。 編集者は、介入が必要な場合に情報に基づいた選択を行うために、彼の知性と音楽的洞察を積極的に使用する必要があります。 彼は、ソース、音楽、そして現代の理論についての知識と経験をできるだけ多く考慮して、それらを作成する必要があります。 ここでのように、1つのソースのみが関係している場合でも、選択を行う必要があるという事実を回避することはできません。 p178 確かに、「単なる」 transcription またはdiplomatic ファクシミリは、これがその主要な意図ではない場合でも、いくつかのあいまいさを解決する必要があります。 しかし、14世紀後半のポリフォニーでは、単に原典版をきれいに読むことを目的とした一種の「原典版」を意図した現代記譜法の学術版は受け入れられません。 コンセプトとして、このシャンソンのような作品では、演奏者が演奏可能な作品を制作するために印刷されたテキストを修正した経験があると想像されても、「原典版」は考えられません。 Fumeux fumeは、transcriptionを確立することと、エディションを作成することの両方の難しさを示している。transcriptionの最初の行為でさえ、単なる機械的な作業ではなく、編集者が多くの問題の解決に直面しなければならない作業である。なぜなら、シャンティ写本は、譜線上の臨時記号の位置に関するスクライブの不一致で有名だから。 編集上の決定はすぐに行われよう。つまり、これはA♭またはB♭、EまたはD♭か? 転写のプロセスと想定される最終産生物との間で、これらの選択のために、いくつかの相互作用が即座に開始される。 予想によって;これらの選択を行うために、編集者は、最終産物がどのようなものであると想像するか、言い換えれば、作曲家が意図したものについて、柔軟ではあるがいくつかの概念を保持する必要がある。 これらの選択を一時的に解決し、編纂者はいくつかの決定がなされた中間点(ApelとGreeneの出版版のようなもの)に到達するが、編集タスクは完了したとは見なされない。 次に、それらの臨時記号に関して、編纂者は、臨時記号が譜線に入れられた時点から、それが意味するヘクサコードシステムが次の臨時記号によって上書きされるまで有効であると仮定して、中世の歌手のようにfictaを操作する必要がある。 4 この場合、これらの臨時記号の完全なヘクサコードの意味を追跡することは、歌手にとって厳しい実践であり、現代の編集者が直面する確かに主要なタスクである。 この点で、彼はソースと彼のtranscriptionの両方の視覚的イメージを超越しなければならない。そして、このプロセスのメロディとハーモニックの両方の結果に常に注意を払わねばならない。 Fumeux fumeのいくつかの重要なポイントで問題が発生する。その選択は、通常は、厄介な旋律または和声の音程のために単に公理的であるだけでなくだけでなく、いくつかの調性デザインの実行における一貫性の欠如のためになされねばならない。 編集者は、あいまいな臨時記号の意図された位置に関する決定を修正することを余儀なくされる可能性があり、おそらく、臨時記号のソースを完全に受け入れることを拒否するかソースでキャンセルされない継続的な効果を無効にするか、実際に臨時記号を追加している。 (略) シャンソンの最も印象的で記憶に残る瞬間は、各半分に見られるリズミカルに活発な下降する旋律と和声的連続であり、特に第16-21小節の3拍子と第28-35小節の2拍子である。 前者は、同じリズムミカルなモチーフが各声で6回出現し、和声を埋める役割に忠実なカウンターテノールはメロディ的に多様であり、テノールは、1小節(拍)半後にcantusのメロデ的な厳密さに合致している。 構造的なcantus and tenor声部でさえ、全音と半音が正確に繰り返されることはない。 p179 実際、それは、短音階で厳密に調和された、全音階の下降音階G-F-E♭-D♭-C-B♭の精緻化で構成されている。 これは例2aで明確に示されている。例2aは、breveで書かれたcantustenorフレームワークの骨格を示している。 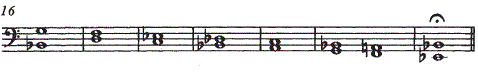 第28〜35小節の連続は別の種類のもので、4小節のフレーズの2つのステートメントがあり、2番目のステートメントは最初のそれよりも五度低い。 フレーズは、cantus and tenorでは正確に移調され(34〜35小節のテノールでのオクターブ転位を除く)、コントラテノールは、例によってリズム的であるが、メロディー的に厳密ではない。 各フレーズは、cantus内の2つの2小節単位で構成され、音の内容は類似しているが同一ではない。減四度(全半半音と半全半)にまたがり、テノールの和声が異なっている。 いずれの場合も、2小節ユニットはリズムパターンを明確に表現し、その後サイドステップ化される(長三度→五度、長六度→オクターブ)。 この連続部位の縮小系を例2bに示す。 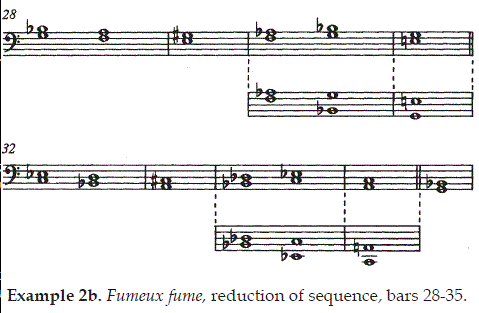 14世紀後半のシャンソンレパートリーの唯一の比較可能なパッセージは、匿名のバラードLemont Aonのsecunda parsにある連続パッセージである。(その縮小形が例3で示される)。5 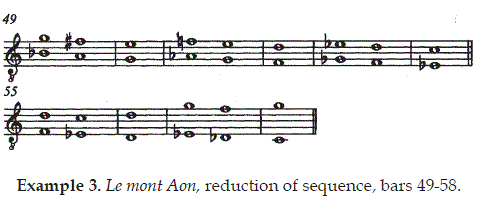 2番目のシーケンスの第29〜30小節と第33〜34小節では、歌手は、G#とA♭の間およびC#とD♭の間でmiからfaに変化して同じ音の高さを歌わなければならないヘクサコード間の♯のdisjunctionに直面する。 これは、音色の内容とシーケンスの厳密さの最も劇的な結果であり、cantusは、第31〜32小節のE 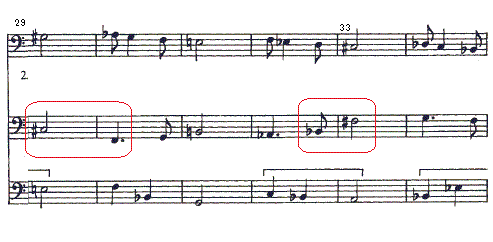 第18小節のcantusで指定されたE♭は、前の小節のG♭の調性から突然離れるが、第16〜21小節のシーケンスの歌手にはそれほど混乱することはない。 この解釈では、cantus and tenorの間(第19小節と20小節)とcantus and contratenorの間(17小節)で2つの減五度が残されている。 ただし、すべては弱拍で生じている。  2番目のシーケンス(28〜35小節)の降順スカラー素材の本質は、最初のシーケンス(16〜21小節)の本質と同じである。したがって、それは変形され、リズム的に圧縮されたバリエーションと見なすことができる。 一般的な調性的素材は、その最初の、そしてもっとも凝縮された外観を、第6〜7小節の短いシーケンスで表示し、第10〜12小節分で延長されるために、Fでのカデンツ解決が遅れる(第8〜9小節で始め利、第14小節で終わる)。 このスカラー素材は和声的三度、メロディ的目標のB♭とともに、F上の終止音である一般的な調性とは対照的に使用される。 この点で、ロンドーの内側のカデンツ(第22-23小節))がcantusでのgrave音域のB♭(テノールがE♭で下支えしている)という事実は、最も重要である。このカデンツは、2次的な調性の目標としてのcantusの終止音の五度下の使用に対するシャンソン全体のレパートリーにおいて、特徴的である6。 6.二次的なカデンツの目標とは、具体的には、バラードまたはヴィルレーのouvert-closペアのouvert、バラードのpre-refrainカデンツ、およびrondeauの内部カデンツを意味する。この内容において、F終止音を持つロンドーは、通常、三度上のAのcantus 終止音、またはその半音下のEのいずれかでカデンツとなる。 この機能の目新しさは確かにSolageの存在理由であり、その重要性がリスナーにはわからなかったとしても、当時の歌手にとってそのポイントは失われなかっただろう。 p180 シーケンス、およびそれらが導入する音域は、このシャンソンのフレーズまたはピリオドを定義する大規模なジェスチャーの設定の一部である。それぞれが音符のメロディ的延長と見なすことができ、その後にシーケンスとカデンツへの開放が続く。 このように理解すると、それらは、最初に第1〜6小節がcantusのGの周りをメロディ的にホバリングし、次に第6〜7小節のシーケンスが続く。次に、第8〜16小節のcantusがFの周りをホバリングし、第16〜21小節のシーケンスと第22小節のB♭のカデンツに続く。第3に、第24〜28小節のcantusがCの周りをホバリングし、続いて第28〜35小節のシーケンスと、サイドステップのカデンツのチェーンが続く。最後に、第35〜39小節(およびA〜C〜Eの響き)の保持的なgrave音域のAが、第39〜41小節の昇順(F、A、Cに上昇する半音)およびF上の最後のカデンツへと向かう。7 7.これらのジェスチャーは、パルスレベルでの攻撃の頻度によってリズム的に強調され、たとえば第8〜13小節の計量の変化、およびすべてのピリオドまたはフレーズが含まれる一般的な2拍子によって計量も明確になる。 最初の3小節後に、all periods or phrases は、すぐに適応する。 2つの印象的な類似点により、これらのジェスチャーがさらに明確になる。prima parsでは、第1〜3小節のcantus and tenorの正確な輪郭が、第14〜16小節で想起される。これは、わずかな変化だけで、一全音分低くなっている。secunda parsでは、上昇する2拍子の連結符の出現において、そしてC上のメロディの強調において、特に、12度下のテノールのFで和声付けされた第24〜32小節と第39〜45小節の間に平行関係が認められる。 2つの主要なシーケンスは、別の優美さ、つまりFumeux fumeの和声言語の一貫性と異常な密度も強調している。これは、六度とオクターブよりも三度と五度にはるかに依存している通常ではないような確固としたcantus-tenorフレームワークの探求に起因している。 コントラテノールは、和声の埋め草である面が多いが、8/5よりも頻繁に5/3や6/3を形成している。;時々それはcantus とtenorの上になり(第10–11、19、21–22、33–36小節のように)、ユニゾンや奇妙な飛躍となるようなことはめったになかった。 したがって、テクスチャはかなり厚く、不完全協和音に満ちている。Cantus と tenor はしばしばオクターブではなく五度のカデンツになり(第6、23、27、41小節のように)、長六度→オクターブカデンツの回避、またはそうした不規則な解決は、secunda parsの主要なシーケンスだけでなく、他の場所にもある(第9〜10、13〜14、25〜26、43〜44小節のように。第2〜3小節でも意図されている可能性がある)。 注目に値する他の珍しい特徴には、第7小節でのcantus と tenorの間の音域の交換、および第12〜14小節でのtenor と contratenorの間の役割の交換が含まれる。 当時の歌手に関する限り、しかし、Fumeux fume の珍しい音色の特徴の中で最も印象的なのは、それが記されているピッチレベルであり、非常にまれにしか遭遇しないgrave Fのcantus終止音や Gamma-utの下のFよりオクターブ下のテノールの終止音がある8。 8. 14世紀後半から15世紀初頭にかけての世俗歌のレパートリーでは、変格のcantusメロディとオクターブカデンツを備えた低いF終止音は、3つの例でしか知られていない。Fumeux fume以外では、それらは、Matteo da Perugia’の ballata Giada rete d’amor とThomas Fabriの rondeau Die mey so lieflic wol ghebloitである。 これらはすべて、ポリフォニーの音階での下向きの移調と見なすことができよう。これは、通常は1オクターブ高く表記されていた可能性がある。一方、cantus声部のために利用可能なスペースの下部で、非常に低い終止音が考案され、採用された別の方法がある。 たとえば、マショーのシャンソンでは、F上の終止音は、grave 音域にのみ見られ(acuteではなく)、正格メロディーとユニゾンの終止カデンツにのみ関連付けられている。 それは、42のポリフォニーのバラードの1つ(12番)にのみ使用され、ロンドーは使用されていないが、33のヴィルレーのうちの11において使用されている。4つはポリフォニー(24、29、30、32番)で、7つはモノフォニー(2、6、8、12、15、22、33番)である。 後のフランスのレパートリーでは、grave音域のGは明らかに、低い終止音を扱うこれらの方法の領域にあり、どちらの役割も引き受けることができる。 アペルのFrench Secular Compositionsでは、grave音域のG終止音を持つ6つのシャンソンが正格cantusを持つ。(バラード No.29、53、114、137、149、159;ヴィルレー No.14、およびロンドー No.248)、さらに8つのシャンソンには変格cantusがある(バラード No.23、108、111、119;ロンドー No .67、238、249、284)。 ここでそれらは正格記譜法のためにリザーブされた。ポリフォニー設定の最後のカデンツが cantus and tenor でユニゾンで終わるメロディーとともに。 しかし、この表記についての説得力のある音楽的な理由はない。 。 3声の音域は、通常であり(1オクターブ強)、終止音(tenor and contratenor が正格であるのに対し、cantusは変格)と全体の音域(オクターブとFからCまでの五度、およびその上下の音)に関する配置も同様である。 同様に重要なのは、遠方の臨時記号の急増は別として、シャンソンが特定の音色の特徴を共有するおなじみのクラスの曲に属していると認識されるようなパート書法である。すなわち、終止音の上は長三度であり、四度上の2つの形式とcantusの終止音の下の音符との音符の間には頻繁な音色のゆらぎがある。 Fumeux fume では、このゆらぎは、acute音域のBとB♭の間、およびgrave音域のEとE♭の間で生じる。 歌手は、♭領域に二重に移調された場合はB♭、♭領域に単独で移調された場合はF(通常は1オクターブ高い)、移調されていない場合はC、または♯領域に移調された場合はGのいずれかに記された同様の音色の特徴に精通している9。 9Signature-systems and tonal types in the fourteenth-century French chanson参照 すべてのボーカルのパフォーマンスでは、これらすべてをほぼ同じレベルとする。つまり、通常、ほぼ2オクターブの全範囲にまたがるシャンソンポリフォニーを規定したところである。 |