A New Theory of Chromaticism from the Late Sixteenth to the Early Eighteenth
Century2
|
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
その前
| p277 Juxtaposed diatonicism Juxtaposed diatonicism はおそらく識別するのが最も難しいタイプの半音階主義である。なぜなら、その使用は半音階的半音から独立していることが多く、その識別はしばしば主観的な判断に依存するためである。必須的および非必須的な半音階主義の例とは異なり、16世紀や17世紀の音楽理論においては、ほとんどまたはまったく根拠がない。 例10は、有名なラッソのProphetiae Sibyllarumからのプロローグの最初の9小節からの縮小である。作品は、ナチュラルシステムで始まる。ラッソは、第3小節において、4♯システムを並置している。 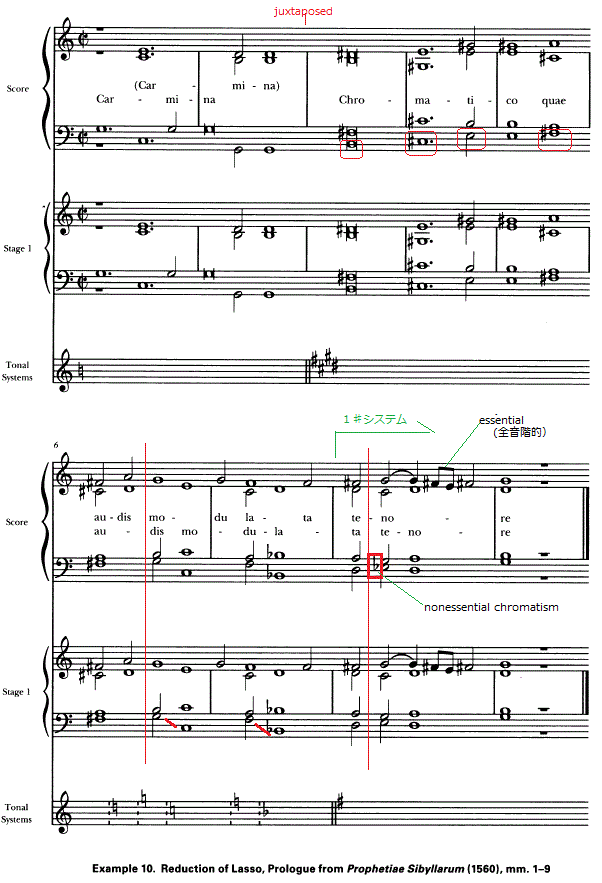 このシステムは、第6小節の2番目の和音まで有効である。そのD p278 パッセージには削除するべきタイプA(文脈上正しくないソノリティを修正するための変更)の変更が含まれていないため、ここではステージ2は削減から除外されている。 たとえcantusの最後の2つのF♯が次のGへの直接の進行を作成するにしても、それらは半音階的変化ではなく全音階のトーンなのである。なぜなら、1♯システムがこの進行を支配しているからである。実際、パッセージ全体で唯一の非必須的変更は、第8小節のバスにおけるE 例10はまた、選好された全音階主義やより大きな簡素さの原則が適用される。第3小節における変ロ長調のソノリティは、新たな、4♯システムの案内役となる。選好された全音階主義の原則に従って。 この原則がなければ、次の4つのソノリティを、基になる全音階的ソノリティの半音階的変化として、ナチュラルシステムに何らかの形で統合することを余儀なくされる。ただし、B、C♯、E、F♯上のLassoの三和音は、直前に来ていたト長調との関係に対して半音階となっているが、相互に関連しては半音階的ではない。 実際、例11のようにパッセージ全体が移調された場合、冒頭は半音階的であるが、第3-5小節は全音階的であるのが明らかである。 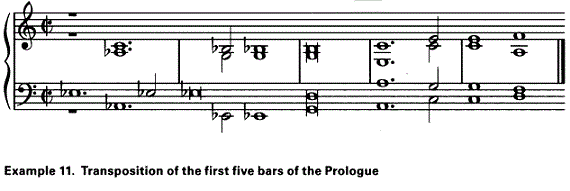 これは、ラッソの半音階主義が、単一の全音階的基礎ではなく、むしろ2つの異質の全音階的パッセージの並んだ配置からなっていることを示唆している。この例や他の例のような隣に配置された全音階主義の利点は、それが、ソノリティやシステムの間の機能的な階層を作り出そうとすることなく、多くのソノリティが同じ全音階的システムに属していると言う事実を強調することである。 第3小節の変ロ長調がB-minorの三和音の基礎となる変化であり、D♯が、evadeされたカデンツのマナーで、次のソノリティへの直接の動きを生じようとしていることが論じられるかもしれない。これは、例12で示された全音階的縮小を導いたことだろう。 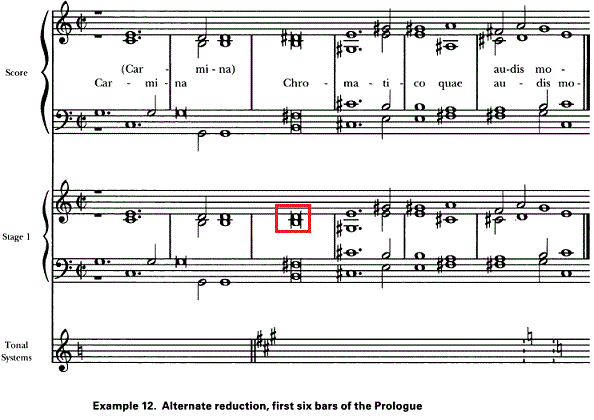 ここでは、関連する並置が、1シャープシステムと3シャープシステム間の第3小節において生じているが、この解釈は、そのパッセージにその半音階的響きを供与するその瞬間、すなわち、ト長調からロ長調の和音への変化を無視している。(選好された全音階主義の原則は、グループの最初のソノリティが全音階的である調性システムを好んだことを思い起こせよ)。 例10はそれゆえ、多くのより単純な解釈であり、音楽についてのリスナーの経験により密接に対応するものである。 p280 例10についての最後のポイント。第1-2小節での4つのピッチクラスの存在は、これらの小節がナチュラルシステムか1♯システムかを意味する。私は、音階にF♯の欠如によって、ナチュラルシステムとしてこれらを解釈した。 この状況は原則として、その包含を正当化するほど頻繁には発生しないが、縮小は、全音階的としてのmusica rectaの音階に属するトーンの広がりを好むことを示す。 Distinguishing juxtaposed diatonicism from nonessential chromaticism. 並置された全音階主義の決定的な特徴の1つは、2つの互換性のない調性システムの場であることである。 (たとえば仮に)例13のようにLassoのプロローグが続いた場合には、ソプラノのD♯は、単純にタイプBの非必須的な変更であり、根拠とする(例12の)1シャープシステムで明らかなように、削除されることができる。 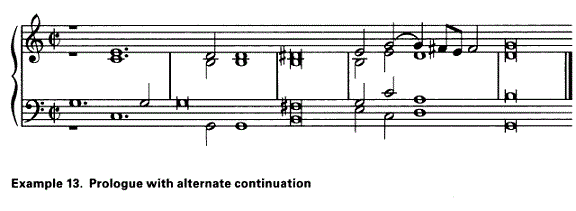 そうではなく、D♯とそれに対応するロ長調が全音階になるシステムの継続によって、並置された全音階主義が作成される。 例10で与えられた解釈は、第4-6小節の和音が第1-2小節の和音と関連する半音階的なものであるが、それらが互いには全音階的であることを認識している。 プロローグの第6〜7小節には、半音階的五度サイクルが含まれることに注意されたい。それは、作曲家達、ことにラッススがこの時代に導入した半音階主義のもっとも一般的なやり方である。(JAMES HAAR False Relations and Chromaticism in Sixteenth-Century Musicp393参照)。 そのような進行を分析するさまざまな方法は、ほとんどの例がそのような進行の前または後にあるため、並置された全音階主義の概念に大きく影響する。 p281 多くの場合、並置には、元のシステムに戻る下降五度サークルが続く。KlausHübler(1976)は、Prophetiae Sibyllarumの分析で、一貫したSprung、あるいは離れた和声への跳躍として、ラッソの半音階主義をこの方法で説明した。 あるいは、「行き過ぎ」て、元のシステムを離れてしまった下降五度サークルには、元のシステムに戻るための並置が続く。以下は、この理論がどのようにそのような進行を説明するかを説明する。 例14として示された Claudio Monteverdiの良く知られたcanzonetta Zéfiro, tornaの第113-28小節を考えてみたい。 このパッセージは、1シャープシステム内の一連の非必須的な半音階的変化として解釈することができる。こうした解釈では、第114-16小節での半音階的に変化したトーンや平行パッセージは、次のソノリティに向けられた動きを作成するタイプBの変更として見ることができる。 それにも関わらず、縮小は、この流れが、並置された全音階主義の真の例であることを示している。違いはコンテキストにある。抜粋の4小節目は、実際に、これまで作品を支配していた1♯システムに属するソノリティに戻る。しかし、第113小節以後、1♯システムにもっぱら属する音はない(∵第113-15小節にはF音はない)。もしも仮にパッセージが例15のように進めば、イ長調やホ長調のソノリティは、レトロスペクティブに見れば、半音階的変化として受け取られたことだろう。 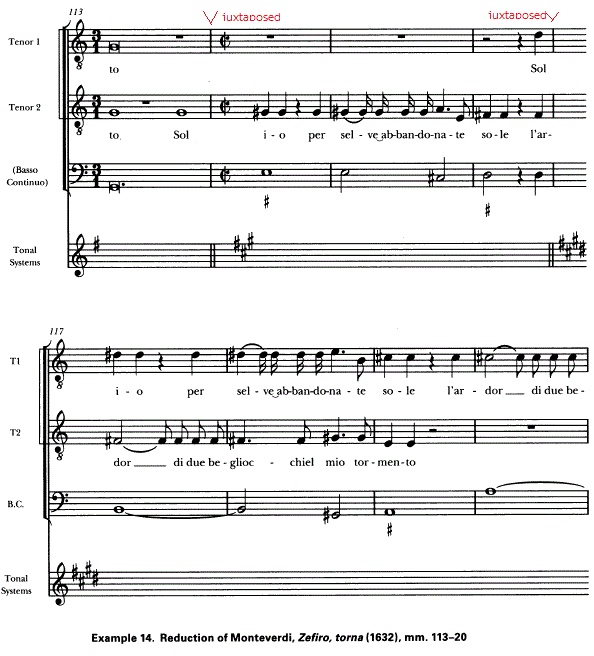 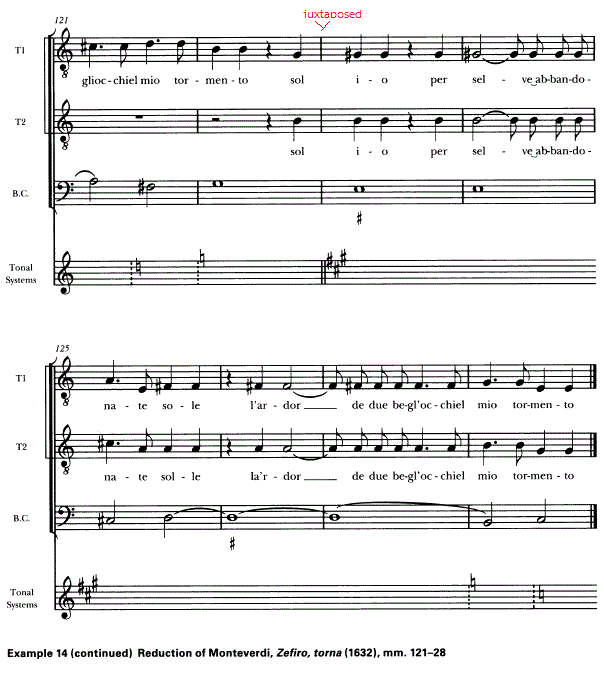 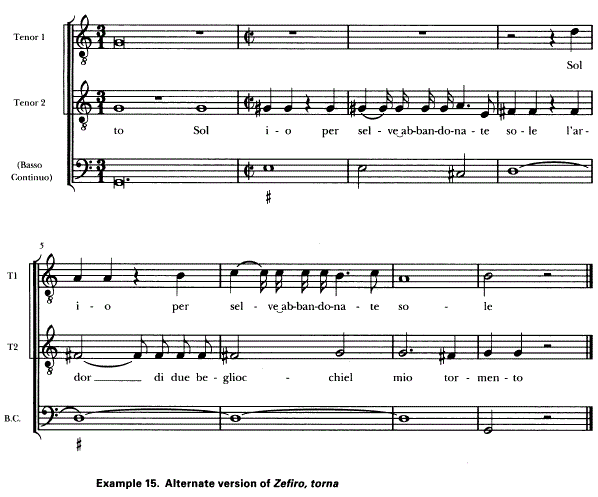 モンテベルディは、1シャープシステムに戻らないだけでなく、4シャープシステムに2つ目の並置を導入する。この当時では、連続する五度サイクル進行は、1シャープシステムに戻っているが、モンテベルディは、第117小節がレトロスペクティブに、半音階的変化のつながりとしてよりも、新しい調性システムへの動きとして受け取られた新しいシステムで十分な時間を費やしている。27 27 例14は、HüblerのSprüngeの概念を、五度のサークルの動きが続いた、離れたハーモニーに適用する最適な場に思える。 人は、Sprüngeの観点からMonteverdiの半音階主義を記述するのが適切かどうか疑問に思うかもしれない。 Sprungのアイデアは、この例の第113-14、116-17、および122-23小節で並置について正確に記述することだろう。 Hüblerの概念は、このようなパッセージの全体像を提供していない。 特に、基礎となる調性システムとSprüngeとの関係の問題を扱っていない。 Sprüngeは、単一の半音階的トーンのように、同じ理由、あるいは同じ目的に常に役立つわけではない。 この理論は、半音階的並置が非必須的な半音階主義として認識されるか、まったく新しいシステムへの移行として認識されるかを決定する際に、ある程度の主観性を考慮しなければならない。 p282 ハーモニー以外の要因は、パッセージの聴取に影響を与える可能性がある。例14での、拍子の変更とダンスのようなキャラクターからレチタティーヴォへの変更は、並置された全音階主義の感覚を強化している。28 それにもかかわらず、前述の例から、我々は、並置された全音階主義の例を他のタイプの半音階主義から分離するのに役立ついくつかの基準を誘導することができる。 第1に、潜在的な並置に続いて、作曲家が、オリジナルなシステムにおいて全音階的であったが、新しいシステムではそうではなかったであろうシステムを導入する場合、リスナーはシステムの変化を知覚する可能性がはるかに低くなる。このようなソノリティはおそらく、新しいシステムでは半音階的には響かず、元の調性システムの名残となるだろう。それまでの半音階的イヴェントが非必須的変化であったことに対抗して。 第2に、リスナーが異なった調性システムへの変化を自覚するであろう可能性は、そうしたシステムに属し、かつ、以前のものにはそうではないソノリティの数や持続とともに増加している。 p284 Juxtaposed diatonicism arising from nonessential chromaticism 例16は、ヘンリー・パーセルのGloria Patriからの第20-26小節で、もともと非本質的であった半音階的トーンが、どのように、新しい調性システムへの並置に影響を及ぼすかを示している。 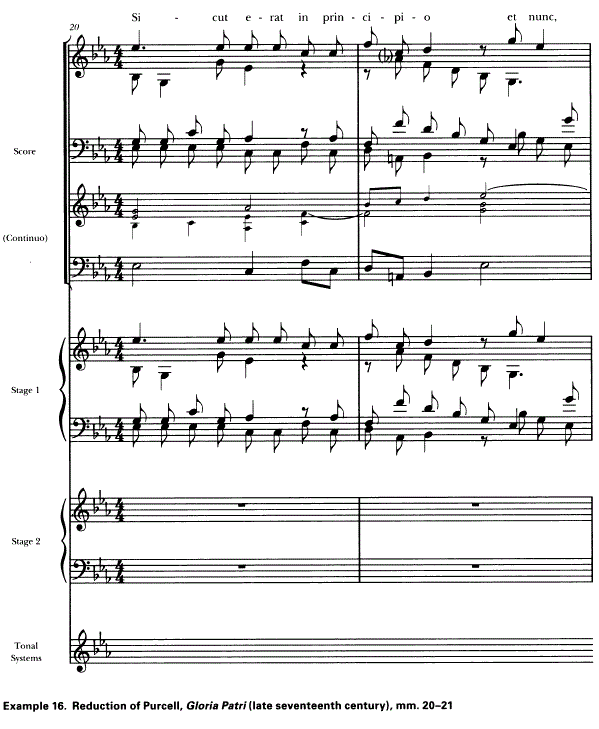 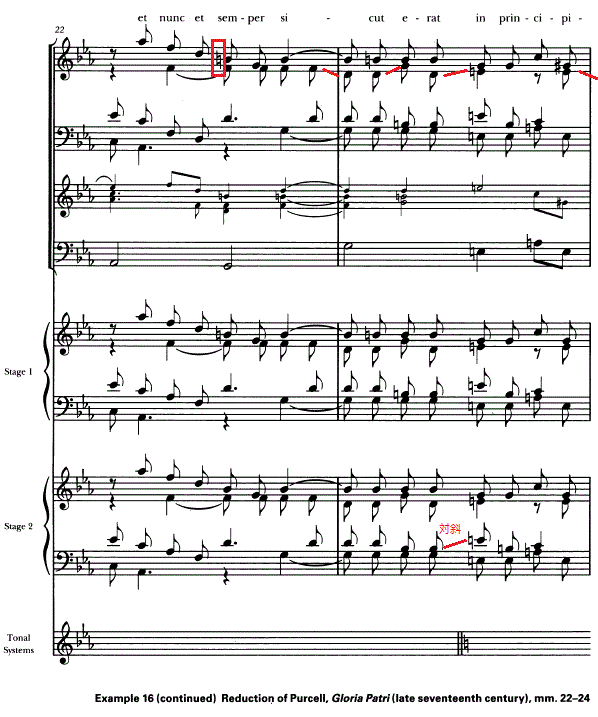 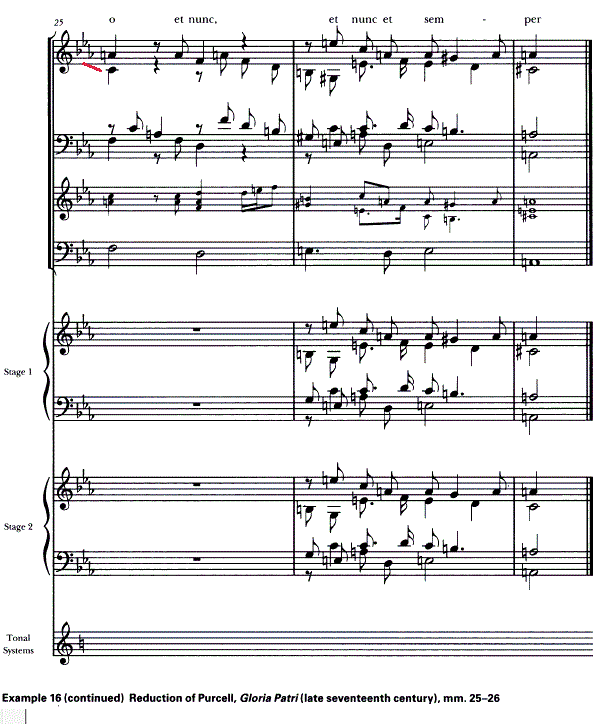 パーセルの署名が示すように、パッセージは、作品の大部分を占める3♭システムで始まる。このシステムにおいては、第22小節のソプラノのB 第22小節からは、期待されるような何らの解決もない。Fは、7度和声であり、解決の前にDへ次にGへと跳躍し、そしてそれが解決すると、それはE♭ではなく、E 続く和音は、ホ長調ソノリティとの関係で全音階的であり、縮小を示しながら、3♭とナチュラルシステムとの並置を形成している。B p285 縮小は、第23小節におけるB♭からE p286 Suspended diatonicism(支配的な調性システムを決定することが不可能な任意のパッセージで構成されるもの) pretonal的音楽は常に、全音階的特徴を持っている。いくつかの例においては、パッセージへの決定的に支配的な調性システムには達することができないのであるが。suspended diatonicismにアプローチする状況は稀である。このセクションは、特定された数少ないタイプや基準を調べることつる。 Suspended diatonicism arising from simultaneous chromatic tones Suspended diatonicism は、同じシステムに属することができない、同時に、いくつかのトーンを使用することで作られる。例17は、Bernardo StoraceのPassagagliからの第49-53小節を示している。 p287 これは、はっきりしたパッセージでのsuspended diatonicismの非常に簡素な瞬間である。ナチュラルシステムがそれゆえ支配し、グラウンドバスのA-G-F-Eパターンで強化されている。このシステム内で、第50小節の第2拍でのソノリティは、説明がしやすい。すなわち、B♭とG♯は、双方とも、TypeB的変更である。 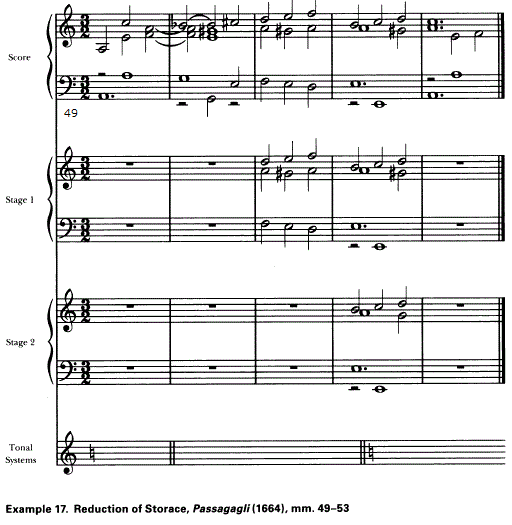 p288 だが、和音の顕著な不協和音は―それは減三度、減五度、増八度を含み、次の和音へは増二度に上がる―リスナーに対して、リアルタイムで全音階的トーンから半音階的トーンを区別させることを極端に困難にしている。そしてそれゆえ、音楽がいくつかの異なった調性システムのひとつであり続けることができるような状況を作り出している。31 たとえば、3シャープシステムに変更して、例18のようにパッセージを進めることができる。 31このソノリティは、François-JosephFétis(1879)が全音階を説明するために使用したソノリティに類似している。ソノリティは、どのキーにも明確に属しておらず、したがって実質的にすべてのキーに解決できる。 この場合、システム間の並置の瞬間はなく、ナチュラルシステムのパッセージだけであり、あいまいなソノリティ―suspended diatonicismの瞬間―とシャープシステム維持が続く。 それが始まったのと同じシステムでのパッセージの継続は、suspended diatonicismの瞬間を変えることはない。 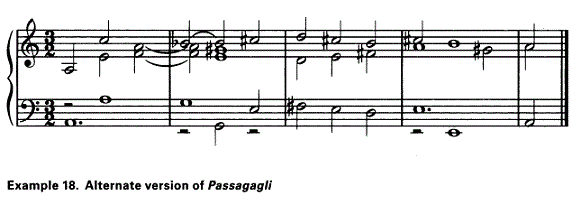 p289 Suspended diatonicism arising from consecutive semitones 最も頻回なsuspended diatonicismの例は、複数の声部に連続する半音が蓄積する場合に発生し、それにより、全音階的および半音階的半音の間の識別をあいまいにし、単一の調性システムの識別を不可能にする。 並置されたダイアトニックと同様に、中断されたダイアトニックの認識は、コンテキストに大きく依存している。例19は、Barbara StrozziによるCuore che reprime alle lingua di manifestare il nome della sua cara であるが、両方の声部に連続した半音が含まれているが、中断されたダイアトニックの例ではない。 第175-77小節のバス進行は、完全五度の間ですべて半音階進行となっているが、先行するパッセージがナチュラルシステムによってのみ支配されているため、全音階的トーンと半音階的のトーンを可聴的に区別する。 したがって、D♯,C♯,B♭は、タイプBの変化であり、バスでのタイプBの変化として認識されているため、第176小節のソプラノもまた同様に認識される。ナチュラルシステムのA上のカデンツ第178-79小節は、続く小節のバスの半音階的トーンをタイプBの変更として文脈化し、バスを半音階的とし、それらはソプラノを半音階的とする。 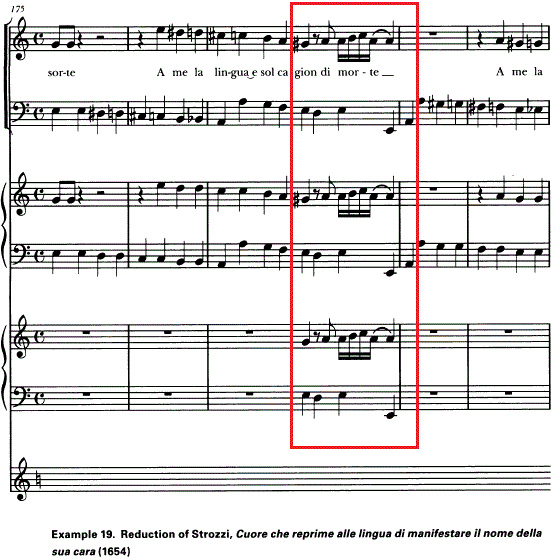 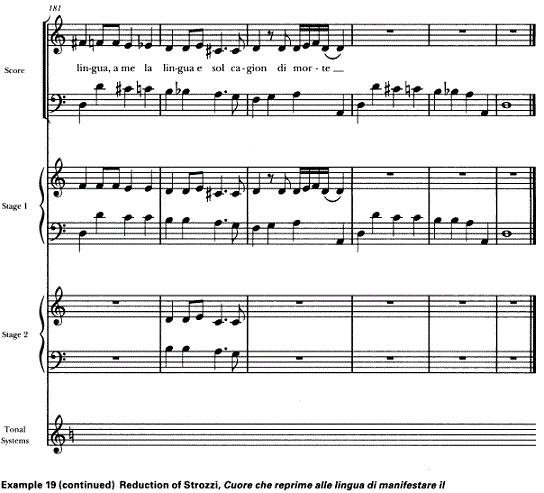 一方、例20では、suspended diatonicismが発生する。なぜなら、単一の調性システムを確立するのに十分な音がないためである。例はClaudio de MonteforteによるFantasie ex D の最初の10小節の縮小である。 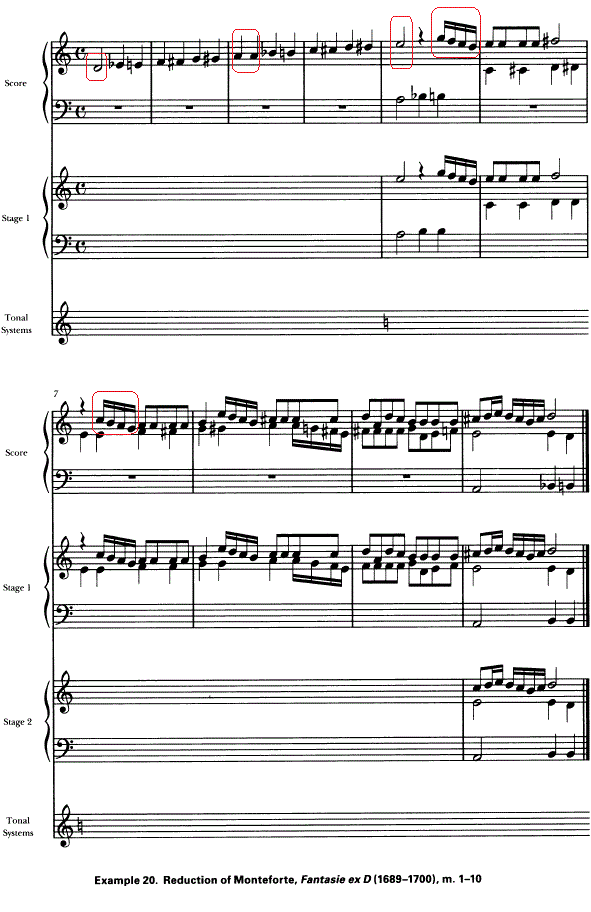 最初の4小節については、縮小のステージ1および2は省略されている。これは、suspended diatonicismの性質が、全音階的トーンと半音階的トーンの区別ができないためである。このような状況では、さまざまな種類の半音階的トーンを区別することはできない。代わりに、スコアの下の単一の譜表は、第5小節になって初めて調号が出現する。 最初の4小節では、トーンDとAのみが全音階的として知覚できる。これは、それぞれが他のトーンの2倍の音価を持っているためである。 Dが作品を開始し、Aが最初の重要なメトリック到着点である。 したがって、リスナーはこれらのトーンを全音階的、あるいは少なくともその他よりも安定しているとして知覚するとよい。しかし、2つの全音階的トーンは、調性システムから構成されているのではない。 p290 確かに、リスナーはおそらくDを終止音として、そして、Aをその五度として認識するであろうが、それが必ずしもその他のトーンのステータスを決定するとは限らない。特に、F 32 F しかしながら第5小節までに、全音階的内容はよりはっきりする。すなわちE 35 この作品は、例9のように、D終止音での作品における調性システムの決定の困難さを浮き彫りにしている。 p291 E 第7小節で、B B 繰り返しとなるが、例19と例20の違いは内容である。例19のバスは、例20の冒頭主題のほぼ正確な反転となっている。それは、suspended diatonicismを示さない。モンテフォルテの例20では、半音階的変化がそれ自体際立っているコンテキストは確立されていないが、ストロッツィの例19では、いくつかのリズムがナチュラルシステムを強く確立している。 さらに、ストロッツィの作品例19の第179-82小節では、五度のステップダウンでのアクセントを伴って、バスは1オクターブを半音階で埋める(音域の変更はあるが)。これは作品の最終版である。 p295 これは、ストロッツィのパッセージに、九度の音程(レーオクターブ上のミ)を満たすモンテフォルテのそれよりも強い半音階的コンテキストを供与している。 suspended diatonicismのさらに顕著な例は、例21の Michelangelo RossiのToccata VII 第69-87小節に生じている。第74小節の冒頭では、すべての声部における半音階的半音の付加や、はっきりとしたカデンツの欠如、あるいはそれらについての期待さえ、支配的システムを見分けることは不可能になる。34 34 この例は、1つの♭記号があるにもかかわらず、ナチュラルシステムにおいて始まっていることに注意。 この単一の識別可能な調性システムの欠落は、ここで説明された他のすべての半音階的現象と中suspended diatonicismとを区別する主な特徴である。 p296 たとえば、例10のLassoのプロローグの最初の9小節をもう一度考えてみよう。第6-7小節では、調性システムが各ソノリティで変化し、4♯システムで始まり、1♭システムで終わることを示している。これは、調性システムが非常に急速に変化し、パッセージが始まったシステムからはるかに離れたシステム上で停止するため、suspended diatonicismの例として見ることができた。 しかし、ラッソのパッセージとMichelangelo Rossiのプロローグとの決定的な違いは、(ラッソにおいては)プロローグにおいて音楽が、第5-7小節におけるソノリティを停止させ、その点における支配的な全音階的システムが明らかになったであろう、ということである。 一方、Michelangelo Rossiのパッセージは、音楽が第74小節から81小節までのソノリティを止めることができたとしたら、そのソノリティが短三度三和音であろうが長三度三和音であろうが、件の和音についての調性システムまたはその状態(ダイアトニックまたはクロマティック)を決定するのに十分な明確なコンテキストがなかったことだろう。 ダイアトニックではないとしても、特定のトーンをより安定したものとして際立たせる特徴がある。半音階的上昇と下降のほとんどは、GからDまたはDからAの音程を満たしている。どちらもナチュラルシステムまたは1フラットシステム内の重要な音程である。 例21では、第72小節のソプラノの上昇、第73-75小節のバスの上昇、そして第77小節でのソプラノの上昇の始まりに注意していただきたい。.さらに、パッセージ内のすべての4分音符と繰り返される8分音符のほとんどは、1フラットシステムに属し、多くは半音階的上昇または下降の目標として際立っている。(ことに第74小節におけるソプラノのA 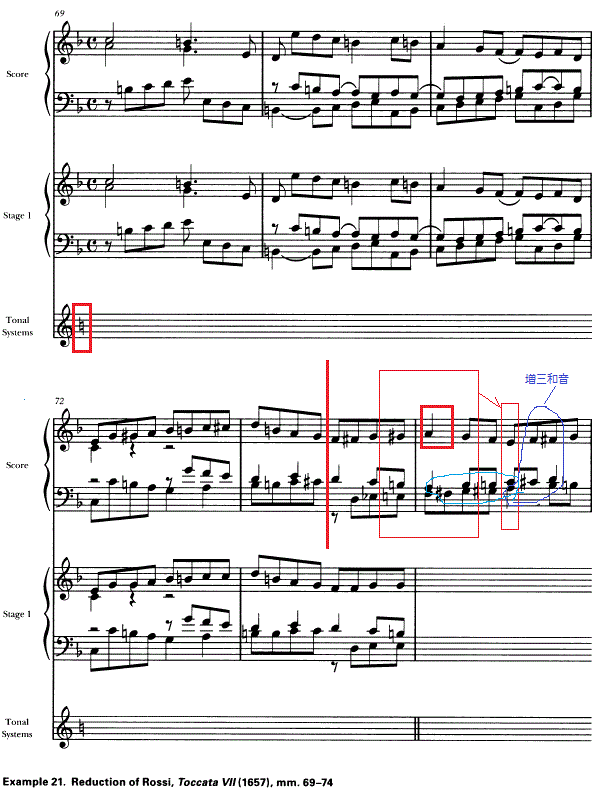 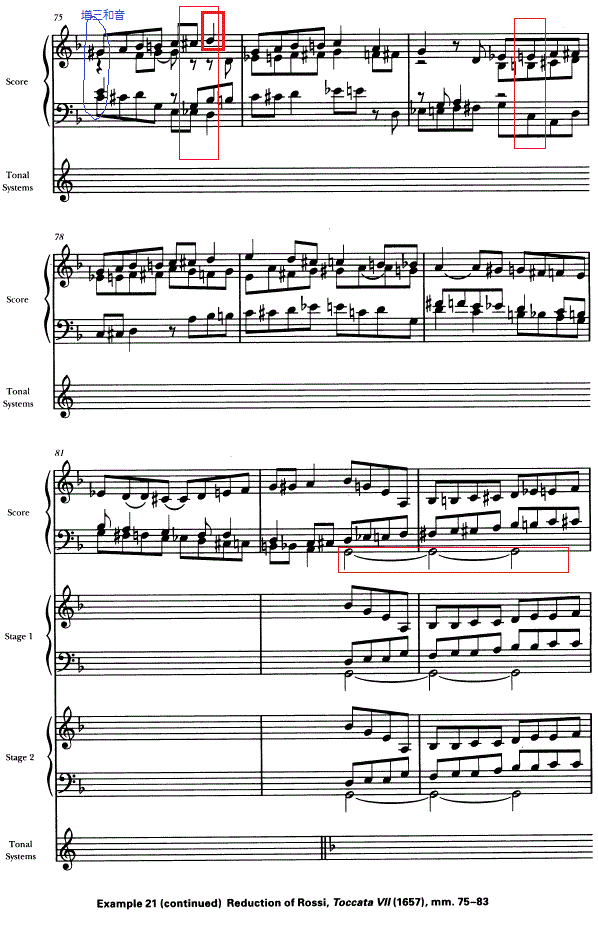 ある種の進行は、カデンツとして解釈される場合もある。EメジャーからFメジャー(mm.73-74)への動きは、Aマイナーへと回避されたカデンツとして解釈できる。第75小節では、ソプラノとバスは、増六度E♭‐C♯35からオクターブのDへと強制的に進行する。Dマイナーへの実際のカデンツは、B♭への中間声部の動きによって回避されるのだが。 最後に、第79‐80小節の進行は、Dメジャーへの変格タイプのカデンツと見なすことができよう。 35 この増六度は、実際には2つの相反する効果がある。一方では、全音階的トーンとしてのDの状態を強直するDoctaveへの進行を強める。他方では、E♭‐C♯が同じ調性システムに属することができないという事実により、全音階主義の感覚を不安定化させる。 それにもかかわらず、全体として、このパッセージは、suspended diatonicismの例である。すべての潜在的なカデンツのうち、強白に該当するものはほとんどない。そして大部分は回避され、調性システムを決定する能力が低下している。 複数の声部で連続していくつかの半音階的トーンを使用すると、あいまいなソノリティと進行が生じる状況が多くある。Michelangelo Rossiがこれらの状況を作り出す最も一般的な方法の1つは、2つの音声を平行な動きで連続した半音で動かすことにより、同じ音程サイズを維持することである36。 36 Strozziも例19でこの手法を使用したが、上記の理由により、調性システムは明確であった。 このタイプの動きによって作成されたトーンの複合体は、少なくとも3番目の連続したインターバルまでは、単一のトーンシステムに属することはできない。 第73小節の中央から第80小節のほぼすべての音楽には、少なくとも2つの声部間には、このタイプの動きが含まれている。 第73小節の第3拍の後半では、ソプラノとバスは、D-F♯からF-Aに平行長三度で上昇する。(バスが半音ずつ上に移動し続けるという事実は、第74小節のダウンビート(第3拍)での回避カデンツの感覚を不安定にする主な要因である)。 p297 第74小節のダウンビート直後から、バスとミドルボイスが、第3拍の前半まで続けて、平行短三度の進行を始める。この時点で、すべての中で最も音調を不安定にするイベントが発生する。第74小節の第3拍から第4拍への連続する増三和音は、第75小節のダウンビートで別の増三和音につながっていく。 .増三和音は、あいまいなソノリティである。 1つの増三和音は、単一の調性システムに属することはできず、そして、それらのうちの2つは、全音階主義の感覚を完全に否定する。第 76、77、および78小節において、ミドルボイスとソプラノが完全四度で動き、第77小節第3拍の後半のソノリティC-B-Eの作成し、そのソノリティは、tonalあるいはpretonal音楽のvoice-leadingの原則で説明することは困難である。 例21のパッセージには、ソプラノまたはバスの標準的なvoice-leadingパターン(下降五度パターンなど)のいずれにも従わないソノリティの多くの連続も含まれている。 互いに、どんな種類の機能的関係にも存在していない。 第77小節の第3拍から始まり、第78小節のダウンビートに続く和音の連続を考えてみよう。 これは、予測可能な一連の予想を作成する一連のソノリティではない。 なぜならそれは連続的ではなく、同じ方法で継続するという期待すら作成しないからである。 第82小節のバスGへの到着まで、安定したトーンと不安定なトーンを区別することは困難であり、したがって、支配的システムに属するトーンをそれらのトーンの半音階的変化から区別することは困難である。 Conclusion 16世紀の音楽に関して、James Haar は次のように書いている。「音楽のシャープやフラットを表す用語は通常使用されていなかったように見えず、直接の旋律的半音階はない。この説明の一部は、それでも耳に非常に色彩豊かで、少なくとも和声感覚のとれたカラフルさがある。」(1977、False Relations and Chromaticism in Sixteenth-Century Music By JAMES HAARp393)。 この記事は、この現象に対処することを目的としていた。この理論は、Haar が思ったように、「クロマティック」が初期の音楽家たちにとって多くの異なる意味を持っていたが、そのすべてが同時代または現代の理論のいずれかによって説明されたわけではない。 それはまた、ソノリティが常にどちらかであるとは限らないことを示すことにより、diatonic と chromatic の区別を曖昧にするのにも役立つ。むしろそこには、半音階的トーンの陰がある。そのいくつかのトーンは、他のトーンよりもはるかに深いレベルの構造に存在している。表面上の表現的デバイスを表すものもあれば、全音階的collectionsへの基本的なシフトを表すものもある。 ここで紹介する方法論は、そうすることでこれらのタイプのトーンを区別するための具体的な基準を分析することを目的とし、理論家が異なる半音階的現象を知覚する方法を議論できる語彙を提供する。 p298 Appendix B;Further discussion of the terms essential and nonessential 多くの学者は、これらの用語の私の使用と、それらを適用する方法の両方に間違いなく例外を取ります。 以下の議論は、私がそれらを使用することを提案する特定の方法にいくらかの光を当てます。 明らかに、この用語は Johann Kirnbergerから採用されましたが、それは彼の用語と何らかの関係があると解釈されるべきであることを意味するものではありません。 むしろ、それらは文字通りできるだけ取られるべきです:「必須でない」半音階的変更は、作品のスタイルを考えると不必要であるか、異なる文脈でそうなる可能性があり、「必須的な」半音階的の変化は、文脈に関係なく必要なものです。 この記事の以前のバージョンの読者は、これらの用語の使用に起因する可能性のある多くの問題を指摘し、これらの最も重要な3つに対処します。 第1の、そしておそらく最も重要なのは、カデンツの導音を作成するのに役立つ臨時記号は、まったく半音階的と呼ばれるべきでないという異論である。 Margaret Bent は"Diatonic Ficta" などで、この観点について十分に詳しく説明しており、この点に関する私の立場を明確にする必要がある。私は、これらの臨時記号が生じる進行が、多くの場合、完全に全音階であることを否定はしない。それらは全体的に、拡張した全音階内で理解され、ソルミゼーションされることができる。しかし、私はこうした臨時記号は半音階的であり、ある意味、現代のそれに近く、それらの使用から生じる音程が、支配的な調性システムの外側にあると考えている。(p260の私の定義を参照)37 37 こうした見方は実際、16世紀後半の多くの理論家らに一貫していた。 この論文では、明示的に別段の指示がない限り、支配的な調性システムの継続を耳が期待する、基本的な仮定に注意していただきたい。したがって、半音階的に変化したカデンツの導音が、全音階的あるいは半音階的なメロディの継続を生じるかどうかは、与えられた文字の名前の形とは異なるものとしてマークされる。38 38 Berger (2004, 45-46) makes a similar これは現代の音楽家らが使用する「半音階的」という用語の意味であり、私がここで使用するものである。実際、これらのトーンを説明するために「半音階的」を使用する際に、Bentや他の人から強い異議を予想しているが、同じ学者が私の結論に同意することを想像することしかできない。つまり、そのようなトーンが音楽表面から減少すると、それらを含むパッセージはもっぱら全音階的であることが明らかにされる。 2番目の異論は、カデンツの導音とピカルディの三度は、たとえ私の定義によれば合法的に半音階的と呼ぶことができるとしても、特に16世紀においては、ほとんど「非必須」ではないということに対してである。 ここでは私は、これらのトーンの使用が何らかの形でオプションであったことを暗示するつもりはないが、音楽は原則として、これらのトーンなしで同じトーンシステムで継続することができる。カデンツの導音とピカルディの三度はスタイルの点では必須であるかもしれないが、それらを引き起こす状況はそうではない。 説明するために、私は、Pietro AronのAggiunta to theTscanello in musicaの2つの例を借用したい。 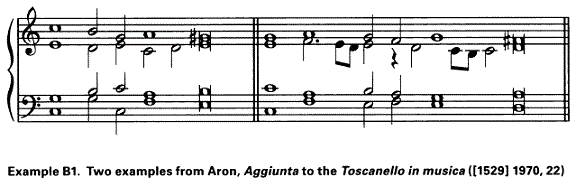 Aronの例は、作曲家が臨時記号を演奏者の裁量に任せるのではなく、記譜すべきであるという、ある種の状況を説明することを目的としている。ただし、Picardyの三度を「非必須」と呼ぶ私の理由もわかりやすく示している。 右側に示す例の最初のソノリティは、左側に示す例の3番目のソノリティを置き換えることを目的としている。 Aronのポイントは、作曲家が例B1の左側にあるソプラノのG♯を記譜するべきだということである。なぜなら、音楽が右側のように続いた場合、Gは変更されずに残るほうがよいからである。 このようなG♯を非必須と呼ぶ私の理由も同様である。もちろん、左の例のピカルディ三度はスタイルの「必須な」側面であるが、音楽がたまたま終わったという事実はない。音楽が右側のように続いた場合、G♯は必要ではないし、実際、追加するのは正しくない。 したがって、左側のピカルディの三度のG♯は、別の音楽コンテキストがそれを不必要にする可能性がある限り、非必須なのである。おなじみの「inganno」カデンツ(偽終止)を含む、カデンツ的導音の同様の状況を簡単に想像できることだろう。 最後に、この理論は、スコアにおいて作曲家によって含まれた臨時記号と、musica fictaの適当な適用によって暗示されたそれとの区別をしない、ということ。ここで私は、musica fictaの適当な適用から由来している臨時記号は、作曲家が特に記譜したものと同じくらい、音楽テキストの一部である(l70ffを参照)という、Berger(2004 )に同意をする。 p302 事実、例B1では、この点も示している。 右側の進行では、Aronは、アルトにおけるカデンツでのC♯を示していない。あたかも、彼の時代の演奏家がこれを当然のように含めて演奏していたかのように。 したがって、このパッセージの分析では、アルトの声部を、記譜されたC♯が含まれているかのように扱わなければならない。 これを半音階ピッチとして考えれば、上記の理由により、私の分析では、音楽の表面になくても、それを”必須的”であると考えられようか。したがって、私の分析では、暗黙的ではあるが必要な臨時記号は、記譜された臨時記号と同等のものとして扱う。 |