Hearing Counterpoint Within Chromaticism: Analyzing Harmonic Relationships in Lassus’s Prophetiae SibyllarumTimothy K. Chenette |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
その前
Lassus - Prophetiae Sibyllarum 楽譜 [1.1] Orlandus LassusのサイクルProphetiae Sibyllarum(1550年代)は、現代の聞き手にとっては馴染みがあり、そして不安をもたらすものである。(2) それは、明らかなトライアドを使用しているが、その根音の範囲が非常に広いため、最初の調性のシンボルとしてそれらを聞くことは困難である。 作品の(プロローグの)歌詞に応じた3つのカデンツは、第8旋法である(3)が、その臨時記号は、全音階オクターブに基づく旋法の選定を複雑にする。 (3)Rothは、このような旋法的な視点について詳しく説明している。プロローグの全体的な旋法は第8旋法である。その最初と最後の和声はG上にあり、主たる内部のカデンツはC上にあり、終止音と属音はHypermixolydian modeと関連している。低音部記号は調号を持たず、Gの終止音の構成はまた、第8旋法を表すためのルネサンスのポリフォニーで使用される音色タイプにも対応している。 オープニングフレーズの個々のメロディーラインは厄介で、しばしば大きな飛躍を通して平行五度や八度を避けているが、同時にそれらの中で協調感、そしておそらく進行さえも聞かざるを得ない。 この奇妙なプロローグ、およびProphetiae Sibyllarum 全体の基礎となる原則は、何であろうか? この半音階をどのように理解できようか?さまざまな場所でさまざまなテクニックが使用されているのか?それとも、サイクルは一貫して奇妙な音楽の長い洗浄を表しているのであろうか? 最後に、わきに置いて論じるであろう一見必要だと思われる質問であるが、どの調性/旋法/ダイアトニックシステムが「入っている」のであろうか。 [1.2]これらの課題に対処するために、最初に発表された、Prophetiae Sibyllarum の分析のいくつかは極端な位置を占め、ランダム性または絶対順序のいずれかを強調した。(4) プロローグのオープニングについて説明した後、Edward Lowinsky は次のように宣言した。「 第7小節のF major 和音から、F major, B-flat major, D major 、 E-flat majorへとスイッチされていく。違いはほとんどないだろう」と。そして彼は、その見かけのランダム性を “triadic atonality” (( 1961、39)と呼んだ。 10年後、対照的に、William Mitchell は Lowinsky を、「横に拡がるメロディや幅広い構造的音価」が “G major, minor, or Mixolydian”を明確に確立できることを示すSchenkerianのスケッチで反論した。 LowinskyとMitchellは基本的な方法で意見が一致しなかったが、どちらも作品の全音階標準(ここでは調性)との関係を調べた。これは後の学者にとっても焦点となった。 (略) Analytical Distinctions and Tools [3.1]このセクションでは、表面レベルの現象に焦点を当てたソノリティ間の関係を分類する2つの方法を発展させたい。 最初に、16世紀後半の複数の理論家によって共有されている規則について述べたい。つまり連続するソノリティのトーン間の非和声(半音進行や三全音)関係の禁止である。 第2に、特にどっしりとした半音階音楽でさえ、全音階システムが、いくつかのソノリティのスパンにわたる関係を理解するのにどのように役立つかを提案したい。 これらの2つの視点は多くの点で重複しているが、他の点では矛盾している。それらの関係は、最終的な分析で検討したい。 [3.2]連続するソノリティ間の関係を分類するのに役立つ技術的な違いの1つは、Gioseffo ZarlinoがLe istitutioniharmoniche(1558)で説明した、和声と非和声の関係である。 作品のパートが、それらの声部の間で和声関係を持たないと言うとき、パートは、増価または減価したdiapason[オクターブ]、またはsemidiapente [減五度]または三全音[増四度]等の音程で分離されることを意味する。和声関係とは、単に、ピッチにおいて離れた2つの同時の音符を含むのではない。 むしろ、2つの協和音程を形成する2つの声部に含まれる4つの音符の間で生じている。 私は、「和声関係」と「非和声関係」を使用して、そのような進行自体(「X–Yは和声/非和声関係」である)と、Zarlinoがここで行うように、そのような進行が持つ品質(「X –Yには、和声/非和声関係を持つ)の両方を参照したい。 [3.3]後のLe Istitutioni harmonicheでは、Zarlinoは、全音階システムに減五度と三全音を臨時記号で修正すべきだと明示的に述べている。 半音階ステップを使用することにより、すでに示したように、 我々は、tritone, semidiapenteおよび同時歌唱から生じる類似の音程などのような全音階における貧困な関係を逃れ、良い和声を達成することだろう。 半音階がなければ、多くの厳しい和声とぎこちないメロディが聞かれる。 貧弱な関係は全音階ステップのみで回避できるが、特に、必要に応じてハーモニーを変えることを求めているときに、そうするのはかなり難しいであろう。 上記の手順を使用すると、モードがより甘く滑らかになります(Zarlino 1976 [1558]、281)。(16) 特に和声を変えるために、そうすべきである場合、そうするのはかなり難しいであろう。 上記の手順を使用すると、モードがより甘く滑らかになることだろう(Zarlino 1976 [1558]、281)。(16) [3.4] Zarlinoの非和声関係の禁止は、2声の対位法のみを扱う論文の一部に由来していうが、より大きなテクスチャ内からのピッチの任意のペアを同様に選択できる。 事実上、所与のソノリティの音符と次のソノリティの音符の間で、三全音と減五度(訳注;音程的には両者は同じ)が禁止される。 3.5]テキストで要求される場合、ほとんどの音楽関係を容認することで有名なVicentinoでさえ、ソノリティ間の関係を改善するには臨時記号がしばしば必要であることに同意する。 ただし、Zarlinoの定式化にはいくつかの重要な違いがあります。 まず、彼はガイドラインを規則ではなくアドバイスとして表現している。 第2に、おそらくより重要なこととして、彼はそれを否定的ではなく肯定的に言う。つまり、非和声関係を禁止するのではなく、代わりに奇妙な音の前でそれ和声関係を使用して歌いやすくすることを提案する。 協和音程を助けるために、短調を長調にしたり、その逆のためには、そして完全五度を作るためには、 「これらのinflectionが耳に奇妙に聴こえないようにするためには、作曲家は、♭または ]3.6] VicentinoとZarlinoの証言から判断すると、和声関係(特に完全四度あるいは完全五度)の継承は、非和声関係のあるものとは、(作曲家が意図して)何らかの点で、異なって聴こえるものと仮定することができる。特に、非和声関係は、何らかの形で、より粗く、より厄介で、またはさらに困難であるとみなされるべきであると想定されることだろう。 一方、和声関係はよりスムーズに聞こえるであろう。 [3.7] Zarlinoは、このルールは多くのパートを含む作品では従うことは不可能かもしれないと認めているが(67)、Zarlino自身の作品や音楽例の多くは確かにそれを無視しているように見え、また原則に明らかに従っているポリフォニー作品もある。 例1は、ZarlinoのモテットPater noster/Ave Maria.の始まりの現代譜である。 この作品は、E 例1 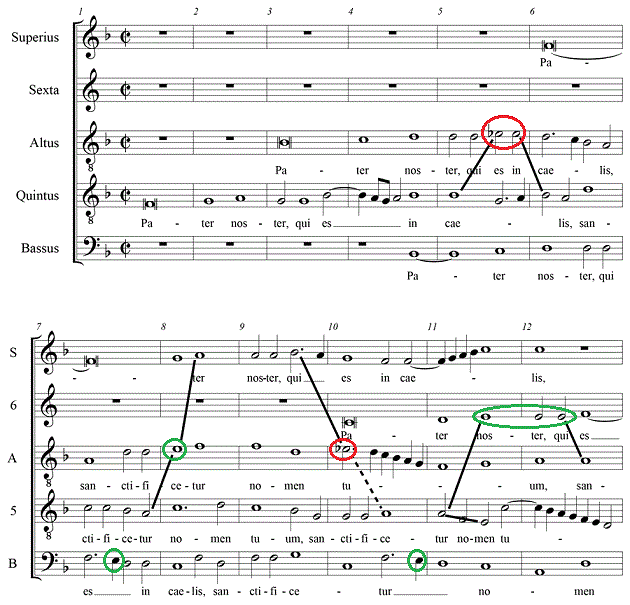 このスケールステップのほぼすべての出現は、B♭またはA 例1の連続した線は、E♭とE [3.8]それらが全音階的境界を越えるという事実にもかかわらず、連続するソノリティ間のそのような「対位法的に滑らかな」関係を好むことは、私の分析にとって重要である。しかし、次の2つの注意事項がある。 最初に、Zarlinoは、私に関するようには、この考えを取らない。第2に、ラッススが作曲したときにこの「規則」を念頭に置いていた可能性は低い。 Zarlinoがここで説明しているのは、全音階系の境界を超えても(またはそのためでも)対位法がスムーズに聞こえる方法なのである。 [3.9]私の2番目の分析の焦点は、結局、全音階の関係である。 16世紀の音楽家たちが彼らのリスニングと作曲に全音階的バイアスをもたらさなかったとは考えにくい。記譜システムは本質的に全音階であり、ほとんどの理論家は(ある程度、Vicentinoでさえ)全音階の関係を記述することへのバイアスを示し、多くの当時の作品は臨時記号なしでほぼ完全に書かれた。 しかし、高度に半音階的な音楽では、全音階との境界の位置を特定するのが困難な場合が多く、「基礎となる」全音階システムが個々のソノリティや多くの臨時記号の進行と有意義な関係を維持するのが難しい場合がある。 [3.10]その代わりに、連続するソノリティ間の潜在的な全音階的関係を説明したい。 隣接する2つのソノリティが全音階システムを共有する場合、それらを「ダイアトニックに関連する」と呼ぶ。20 ソノリティの文字列が全音階システムを共有する場合、私はそれらを「全体としてダイアトニックに関連する」と見なす。 パッセージ全体は全音階システムを共有していないが、パッセージ内の特定の一定数の連続するソノリティの特定のサブグループはダイアトニックに関連しているため、より大きなパッセージは「X-ソノリティグループでダイアトニックに関連する」と考えます。 Xはサブグループの長さである(例2、ラッススのプロローグから)。(21) 例2 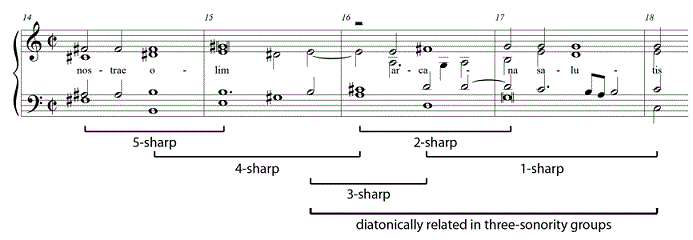 [3.11]これらの要素、すなわち連続したソノリティ間の和声および非和声関係と全音的関係に注目することは、もちろん、16世紀の音楽家が与えられたパッセージをどのように聞いたかを明確に伝えることはできない。 それにもかかわらず、彼らは私たちに表面レベルの関係を理解するための出発点を与えることができ、意図されるかもしれない特定の感情的または修辞的な性質を提案することができる。 非和声関係は「粗い」ように聞こえ、和声関係は「滑らか」に見えるだろう。また、ダイアトニックに関係しない音のペアは、おそらく驚くほどに響くことだろう。 高い全音階的関連性を持つ一連のソノリティが、耳障りではないように聞こえるように。 Analysis I: Prologue [4.1] The text of the Prologue is as follows:(22) Carmina chromatico quae audis modulata tenore, Haec sunt illa quibus nostrae olim arcana salutis Bis senae intrepido cecinerunt ore Sibyllae. あなたが聞くこれらの歌は半音階的的に動き、 シビルの12人の口は遠い昔に、 私たちの救いの過去の謎を大胆に歌った 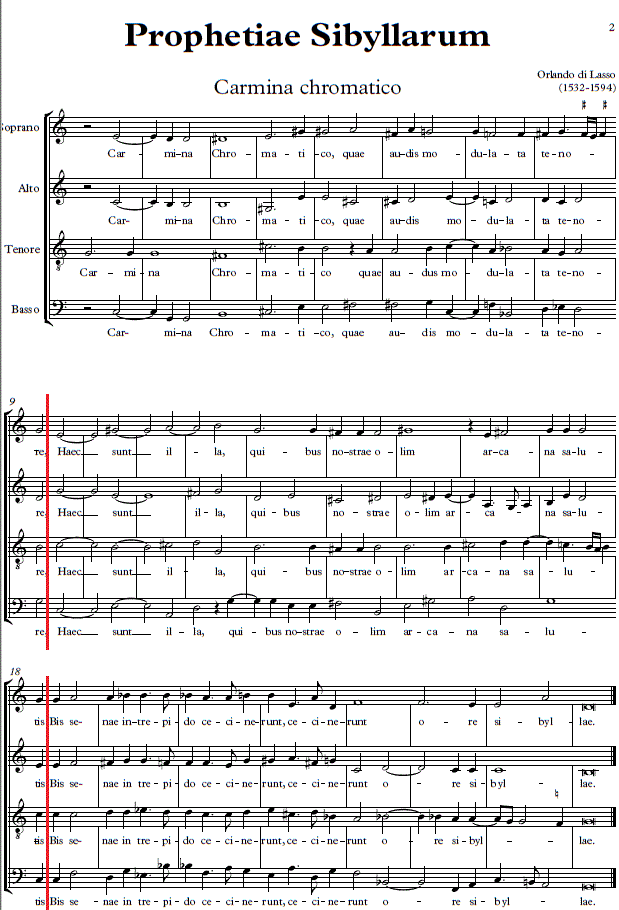 [4.2]ラッススの対位法的優先順位を理解するために、プロローグからシビュラの預言へのパッセージを同じパッセージの、仮想の全音階バージョンと比較することは有益である。例3aは、プロローグのフレーズ「Haec sunt illa」(第9〜12小節)であり、2つの譜表の検査を容易にするために提示されている。 例3a 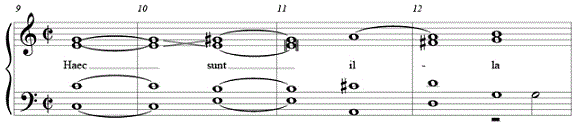 例3bは、臨時記号を削除した同じパッセージである。作曲家が全音階の純度にもっと関心を持っていた場合に普及していたはずのバージョンである。 例3b 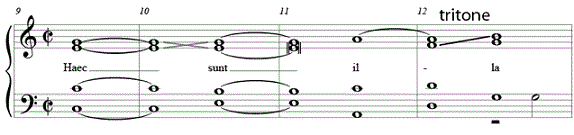 [4.3]例3bのソノリティとそれらの関係は、2つの主な問題とともに、上記のルールに従ってほぼすべて対位法的である。 第1に、このサイクルはバス上の長三度(+オクターブ)を明確に選好していることを示している。第2に、最後から2番目のソノリティのF [4.4]例3cのように、この非和声関係に対する1つの可能な「修正」は、Bにフラットを追加することである。 例3c 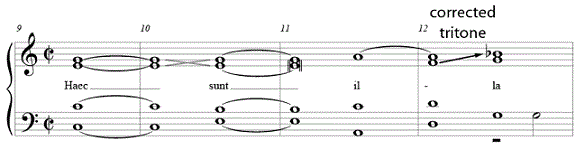 しかし、これは、バス上の長三度に対するラッサスの明確な選好に違反している。 さらに、このパッセージのテキストは完全な制限条項で構成され、その後に作品内の唯一のバスの休符が続く。これは、最終的なソノリティで長三度を必要とするほどの強いアーティキュレーションである。「 作曲家が作曲の途中で協和音程で休息する必要がある場合、短三度よりも長三度で止めるのが、比べものにならないほど良い」(Vicentino 1996 [1555]、253)。 [4.5]代わりに、おそらくFに♯を追加する必要がある。しかし、これは、例3dのように、非和声関係の連鎖反応を引き起こす。すなわち、第12小節の弱拍に転写されたF♯は、三全音を避けるために、前のソノリティでC♯を必要とする。 それは、その前にソノリティでG♯を必要とする。つまり、最初のソノリティでG♯が必要になってしまうのだ。 同じソノリティで、テノールとバスのC♯が必要になる。 Zarlinoの和声関係への関心によると、例3dは「対位法的には滑らか」に聞こえる可能性があるが、記譜上、16世紀のポリフォニーに通常期待されるものをはるかに超えている。 この例は、第10小節のG 例3d  [4.6]実際、この対斜は、多くの臨時記号の使用にもかかわらず、書かれたものとして、ラッススの音楽の唯一の対位法違反である。対斜は、プロローグの冒頭(第2-3小節)での同様の上昇する半音階のハーフステップを明確に思い起こさせ、その工夫が、この特定の部分を象徴することを示唆している。 対斜の後、パッセージの残りの部分は、(バスは)我々が下降五度進行と呼ぶもので構成され、第12小節の終わりに(バスが)休符となる。(25) [4.7]したがって、この一節は、ほとんど「良い」対位法の例である。第10小節の対斜を除き、連続するソノリティはすべて和声的関係を持っている。さらに、Lassusは一般に、Vicentinoの以下のアドバイスに従うことで、臨時記号を歌いやすくなった。 「これらのinflectionが耳に奇妙に聴こえないようにするためには、作曲家は、フラットまたはナチュラルでピッチを鳴らす前に、前の音の五度または四度に対応する音符をその上または下に書くことをお勧めする。」(Vicentino 1996 [1555]、252)。 重要なことだが、下降五度の進行は、全体としてダイアトニックに関連しているわけではないが、3つのソノリティグループではダイアトニックに関連している(26)。Significantly, though the descending-fifths progression is not diatonically related as a whole, it is diatonically related in three-sonority groups.( 26. Adams(2009)は、このパッセージ(下降五度の進行)を「間接的な半音階」の例と考えている。つまり、半音階は、単独で考えられた場合には、連続する2つのソノリティは必ずしも半音を必要とするわけではない、という事実によって実現される。 「下降する五度」の進行は、Haar(1977、393-94)が以前に指摘した事実である、ダイアトニックシステムの長い音域と良好なソノリティとソノリティの関係の顕著な連合における間接的な半音階に完全に適した媒体なのである。 Adams A New Theory of Chromaticism from the Late Sixteenth to the Early Eighteenth Century.” JAMES HAAR False Relations and Chromaticism in Sixteenth-Century Musicp393 つまり、バスの音符E、A、およびDの上のソノリティは、3つの♯を持つダイアトニックを共有でき、バスの音符A、D、およびGは、2つの♯を持つダイアトニックを共有できる。これらすべての要因(非和声関係の欠如、四度、五度を伴う臨時記号の先行、および進行中の高度の全音階の関連性)は、このパッセージが比較的スムーズに聞こえることを示唆している。 [4.8]最後に、(すでにラッススによって)書かれている音楽(例3a)を例3bにおける純粋に全音階バージョンと比較することは有益である。例3bは、カデンツにおいては、非和声的関係となっており、例3aは、フレーズの冒頭に非和声的な関係があり、スムーズな対位法でカデンツにつながっている。 例3bでは、バス上の短三度(+オクターブ)が支配的であり、例3aでは、長三度(+オクターブ)が支配的である。結論としてはだから、書かれている音楽よりも例3bを好む理由はない。実際、後者は、長三度の選好のためと、対位法的な違反がフレーズの終わりよりもフレーズの始まりにより適しているかもしれないので、さらに良いかもしれない。 Vicentinoでは、「適切なタイミングで開始し、音程またはモードのピッチと位置に向かって徐々に確実に移動することにより、最終パートにエレガントに近づくことを条件に」別の旋法の導入を許容する。(付録1およびVicentino 1996 [1555]、246を参照) )。 [4.9]「quibus nostrae olim arcana salutis」(例4で転写された第13〜18小節)は、同様のパターンに従う。すなわち、非和声的な関係の後に、下降五度進行が続く。 27 27.Hübler(1976)は、このパターンを「Sprüng」(本質的に半音階的な三度の関係)として説明し、その後に五度の下降が続く。 Hüblerは、これを明確に対位法の慣行に関連付けていない。 ただし、フレーズはわずかに変更されている。 非和声的な関係は第10小節の対斜とは異なる。ここでは、第13小節の終わりと第14小節の始まりのソノリティ間に、三全音と減五度の存在がある。(バスの)下降五度進行は、はるかに長く、より複雑であり、第17小節の前置装飾が含まれている。(28) 28.具体的には、第15小節の終わりには、Amajorの三和音の前に、G♯minorとEmajorの第一転回(G♯-C-E)が、時代錯誤的に挿入されている。現代のリスナーには、小節の最初のソノリティの転回とし最終的なソノリティを聞き、その間にD♯が入っているように聞こえる。 16世紀の理論家は、理論上共有された根音ではなく、単一の低音ピッチに5/3や6/3のソノリティを関連づける傾向があった。 例4 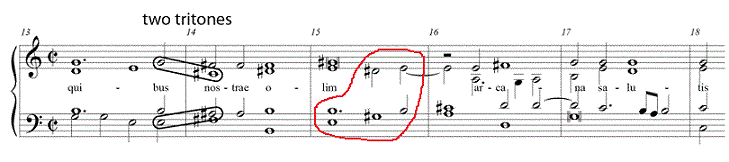 [4.10]プロローグの3行のテキストの2番目(Haec sunt illa quibus nostrae olim arcana salutis)を設定するこれら2つの中間サブフレーズ(例3aおよび4)の一貫性は、残りの部分に目を向ける際の正式な期待に影響を与える。 そして対位法と全音階主義との関係を理解するために。 対位法の規則を破る進行には新しい驚くべき臨時記号が必要であるが、下降五度の連鎖がそうであり、下降五度の連鎖は、Zarlinoの良い対位法の規則に従う。 このように、これらのフレーズは奇妙かもしれないが、それらの特定の性格は、臨時記号のランダムな使用からではなく、むしろ対位法違反の慎重な組み合わせとそれに続く優れた対位法から来ている。 判明したように、最初のフレーズは同様のモデルに従うが、フレーズの先頭の対位法的違反は、テキストから派生しているのである。 [4.12]プロローグの最初のフレーズの議論は、多くの理論的文献が取り上げているが、やはり、それは大部分が滑らかな対位法から成り立っている(例5を参照)。 ここで、主要な対位法違反は、トップ声部の第2-3小節間のD-D♯の半音階である。 多くの当時の理論家は、“chromatico.”などといったカラフルな言葉のもとで、この不規則性を明らかに許容している。(29) 29.しぶしぶながら、Zarlinoは言う。「作曲家は、理由もなく、旋法に不自然なステップで作曲を開始する必要があることがある。diesis (♯) and molle (♭)記号が、最初、中間、終わりのどこにでも見られるようなやり方で、半音階と全音階ステップを混ぜ合わせる。作品がそうしたことを要求した場合、そのようなことは容認できるが、作曲家は、作品の言葉またはその他の特徴によってそれらに強制されない限り、できる限りそれらを控えるように注意される」(Zarlino 1976 [1558] 、175)。 「反対に、作曲家の唯一の義務は、言葉を活かすことであり、和声ととも、情熱を表現することである-厳しさ、甘さ、陽気、悲しみ、など。 これが、その効果に応じて、すべての悪い跳躍とすべての貧しい協和音程が言葉を設定するために使用される理由である。」(Vicentino 1996 [1555]、150)。 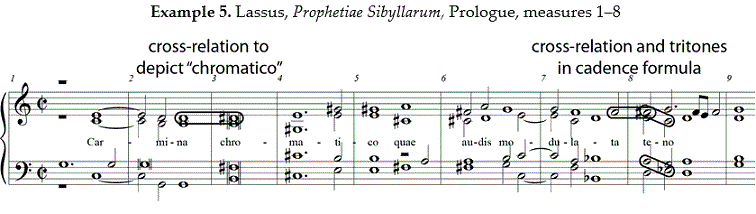 この時点から、第8小節のカデンツ公式まで、それぞれの2つのソノリティグループがダイアトニックに関連しており、いくつかの声部において、ほぼすべての臨時記号の前に、完全四度あるいは五度の音符が先行している。 実際、第3-5小節は全体として全音階であり、第6〜7小節では五度の下降が続く。(30) 30. Adams(2006)は、第1〜5小節を“juxtaposed diatonicism”:の例としている。すなわち、第1〜2小節は、ハ長調系でダイアトニック、第3〜5小節は4つのシャープシステムでダイアトニックであるが、第2小節の終わり、第3小節の初めのソノリティは、単一の全音階システムと共存できないのである。Adams A New Theory of Chromaticism from the Late Sixteenth to the Early Eighteenth Century.” [4.13] 第3小節のD♯の衝撃は非常に注目されているが、それは作品の特に驚くべき2つの部分の1つである。(31)このD♯は、作品が非常に色彩的であり、次の2つのサブフレーズの根底にある対位法違反を引き起こすことを宣言している。 次に、最後のフレーズ(例6)は、前のフレーズで設定された期待をはるかに超えて移動している。作品の最初の部分は、対位法違反に続いて、ダイアトニックに関連するサブグループとのスムーズな対比が続くフレーズを特徴としているが、最終フレーズは、新しいレベルの半音階の対位法を達成している。 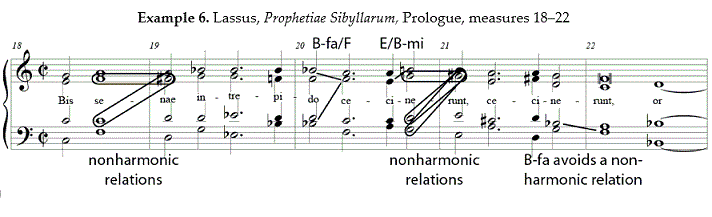 [4.14]第20小節は、B しかし、meansが前のフレーズで使用されたものと類似しており、ソノリティ間の和声関係を尊重している場合、ここでのピッチ変化の速度はこの進行をより衝撃的なものにする。But if the means are similar to those used in previous phrases, respecting harmonic relations between sonorities, the speed of pitch change here renders this progression more shocking. [4.15]さらに奇妙なのは、第19小節19と21小節への同一の声部誘導動作である。それぞれにおいて、転写されたダウンビートのアルトの音を(半音)上げると、前のソノリティとは、三全音と半音階ハーフステップの両方が生じる。上げられた各音は、(テノールとの間で)ソノリティの長三度(ラッススの好み)を表現するが、特に加速されたハーモニックリズム内では、驚くべき計算もされている。どちらも付随する言葉(「senae」/「six」および「cecinerunt」/「sang」)を表すようには明らかに設計されていないが、この行の別のどこかで示された、Sibyllsの大胆不敵な口(“intrepido ore”) に適した特定の野生性を示唆している。 [4.16]他のフレーズと同様に、このフレーズは、第21小節の最初のソノリティで始まる五度下降の流れで終了するように見える。実際、この流れはそれに先行するものと似ているが、非常に速く、(第21)小節の最終的なソノリティは、一音低くなって、バスとともに、(第22小節で)別のソノリティが突然続いている。 Indeed, this chain is similar to those that precede it, but it is significantly faster, and the final sonority of the measure is suddenly followed by another sonority with a bass only a step below. さらに、ラッススは、第22小節の最初のソノリティにおいて、長三度を考慮していたと考えられる。そのため、第21小節の最終ソノリティは、BとFの間の非和声関係を避けるために(テノールとバスは)短三度を持たなければならない。したがって、前述のフレーズとは対照的に、この下降五度の進行は、第22小節の最初のソノリティに対して、ほぼ平行に動く短三度のソノリティで終わる。 この“glitch”は、最後の瞬間でさえ、おそらくこのフレーズに適切なものであろう。最初の2つのセクションを慎重に違反した後、テキストがSibyllsの大胆不敵な、または勇敢な口を語るときの対位法の新たな衝撃的な性質は、最後のフレーズに興奮感を与える。 [4.17]ある意味で、このプロローグの「対位法的」解釈は、以前の学者らの洞察の多くを再生成した。私が「非和声関係」と呼ぶものと、特に五度下降進行との間に種類の違いがあるという考えは新しいものではない。しかし、このアプローチはいくつかの要素を追加する。 まず第1に、それは現代の分析における歴史的概念「和声関係」と「非和声関係」の潜在的な分析的使用を提案する、ということ。第2に、さらにより重要なのは、表記法ではなく聴覚効果に重点を置くことにより、表面レベルのソノリティとソノリティの関係により大きな焦点を当てることができることである。 それは、臨時記号の導入にもかかわらず、下降五度の流れが、滑らかな対位法と見なされる理由を説明し、ZarlinoまたはVicentinoにはどの進行が耳障りになったかを示す。そうすることで、このアプローチは、すべての全音階変化と臨時記号が等しいわけではないことを示している。プロローグの最後のフレーズは、その前のとは種類、文脈、量が異なっている。 Conclusion [7.1]Prophetiae Sibyllarum は、疑う余地なく驚くべき作品であり、ダイアトニックと対位法の当時の規範に挑戦している。 この論文では、このような音楽の分析に集中できる2つの要素を提案した。すなわち、隣接した音響間の非和声的関係と全音階的関係である。 他のトピックスも分析に有望だと思われる。すなわちこれらには、音程の感情的な使用、(47)カノンなどの厳密な対位法の効果、全音階系間を移動する対位法の使用、および voice-leadingの一貫したパターンを可能にするソノリティ関係(特にシーケンス)が含まれる。 ピッチの中心とそれに付随する全音階システムを説明するためのさまざまなツールがあるが、全音階的機能と局所的対位法関係に関連して臨時記号を理解すると、作品設計とその聴覚効果をより完全に理解できる。 |