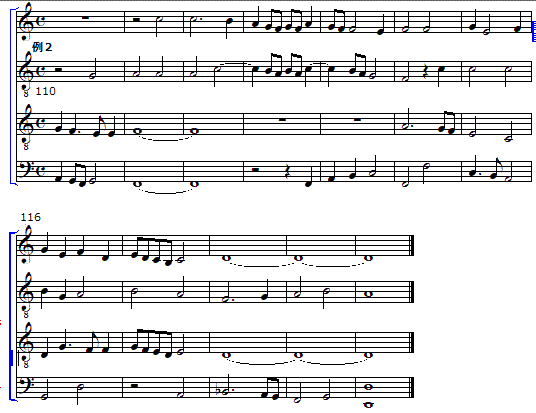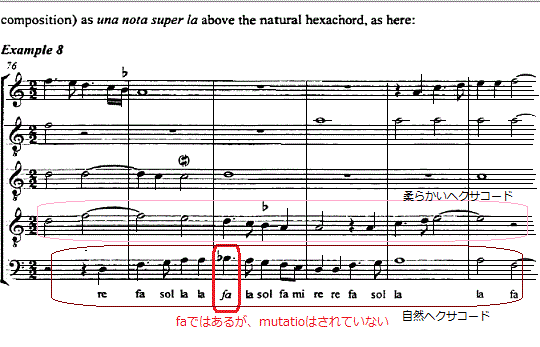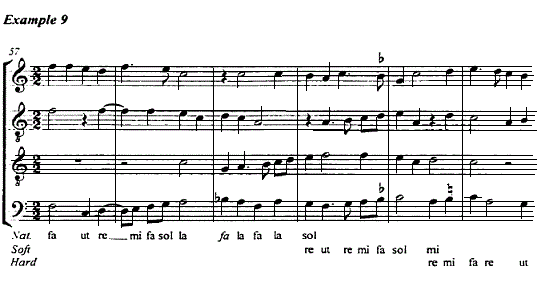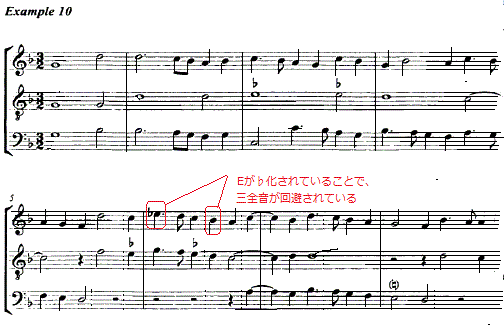CHAPTER 3
Hexachordal choices
p21
柔らかいヘキサコードの使用は常にオプションとして考慮されるべきであるため、ヘキサコードシステムの適用は、「音階」の焦点のある種の柔軟性を意味する。このヘキサコードが他の2つよりも使用頻度が低いことを示唆するものは何もない。
自分のパートことを調べるルネッサンス歌手の位置に身を置こうとすると、柔らかいヘクサコードの使用を示唆する視覚的な手がかりは、容易にイメージされる。
歌手たちは自然に、与えられたパッセージを自分たちで解決しようとしたことだろう。可能であれば、特に理由がない限り、不必要に多数のmutatioを避けて。
間違いなくそのような視覚的な手がかりや、彼らが音楽を解釈するやり方や一定の繰り返しによって染み込んでいる(ソルミゼーションプロセス自体と同様の方法で)。
記名のないパートを仮定すると、これらの中で最も重要なものは次のとおりであり、追加する必要はあるが、この音楽を解釈いる現代の歌手にも有効である。
I. FとB(三全音分離れている)の両方が近接して含まれているパッセージ。
2. 最低音がFであるパッセージ
p22
3. Fの直下から、あるいはFをキーと上昇または下降するパッセージ、またはキーとしての和声音としてFを含むパッセージ 3
3 この最後の点は、自然のヘクサコードに続く柔らかいヘクサコードとともに、自然なヘキサコードの順序が、段階的なやり方で上昇するもっともロジカルなやり方であった事実に由来している。もしも特にF ut が、G sol re. やA la mi.でのように、自然のヘクサコードから柔らかいヘクサコードへと容易にmutatioされる調性記号として、フレーズに含まれている場合には。
これらのポイントのうち最初の2つは、Missa Torrs les regretsの最後のAgnusからの以下において、詳しく説明されている。まず、変更前は以下のようである。
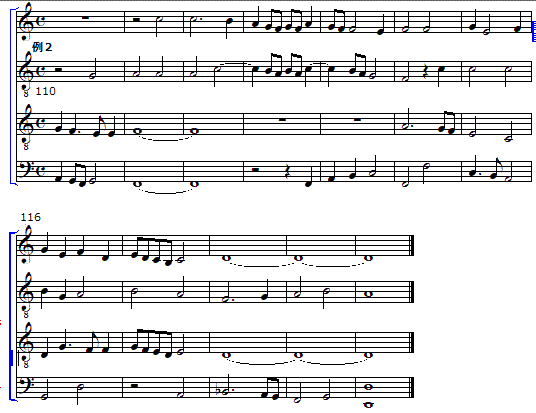
21" Andreas Ornithoparchus and John Dowland, A Compendium of Musical
Practice (New York: Dover
Publications, 1973), 135. (Note the spelling here is fiom Dowland's 1609
translation).
Allaire. Carvell and Bergerらによって、この慣習のより初期の言及が論議されてきた。22。
22 Allaire, Theory of Hexachords, 46. Bmce Carvell, "Notes on Una nota supra In. In Music from the Middle
Ages through the Twentieth Century: Essays in Honour of Gwynn McPeek, ed.
Carmelo Cornberiati and Matthew Steel (New York: Gordon and Breach Science
Publishers, I988), 93-1 11.Berger, Musica Ficta, 77-79
一見認識もコメントも受けていないように思われる1つの参考文献は、14世紀後半の理論家のJohannes Hollandriniのものであり、そのチャントを正確に表現する方法に関するアドバイスはまったく同じ問題に関係している。
我々がどのようにb音を歌うに当たり気をつけねばならないこと。第1,2旋法で歌うときは、高いc音に到達することはないが、b音を歌うようにはなるだろう。すなわち、b音に達しないで歌う時はいつでも、高いc音やそれ以上に達することはなく、b音でmutatioするのみである。
しかし、c音に達する時、そしてより高い音でmutatioを必要とする時には、常に ♯でmutatioしなければならない。そしてその時には、b音の性質を受け入れ、 ♯でmutatioしなければならない。そしてその時には、b音の性質を受け入れ、 ♯の性質を残すことになる。 ♯の性質を残すことになる。
p33
したがって、この長期にわたる概念が広く知られ受け入れられたことは疑う余地がほとんどなく、実質的に、多くの作品に、その適用性の例が多数ある。「メロディーまたはハーモニーをよりエレガントにする」ために三全音を避けるべきか、それとも単にソルミゼーションの節約性を高めるために貢献するためか。
一般的慣行においては、この規則は、次のように、自然なヘキサコードの上のuna nota super laとしてB♭(調号のない作品で)の導入に影響している。
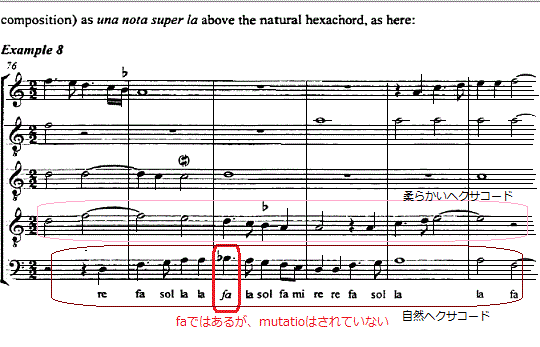
この例は、Credo of the Missa Ave Mariaからのものであるが、第78小節のbassusにおいて、自然ヘクサコードの音域のひとつ上にまで一時的に上がっており、そこは、ソースにおいては、fa super la であるB♭の記名がなされている。これは、bassus全体が同じヘクサコードでソルミゼーションされることとなっており、mutatioなしで達成されたB♭のfaとしての記号である。
上記の例8では、これが本当に柔らかいヘキサコードへのmutatioではなく、fa super laの場合であるかどうかについて混乱は考えられない。それは、bassusの音域が、alteration後に、柔らかいヘクサコードの領域より下にまで降りているからである。25
25 その他のパート(テノール)におけるB♭はしかし、fa super laよりは、柔らかいヘクサコードの選択を示している。<ではなく、柔らかいヘクサコードへのmutatioを示している。
p34
他の多くの場合、fa super laの概念と柔らかいヘキサコードへのmutatioとの密接な親族関係は、以下の例9のように、柔らかいヘキサコードへのmutatioを遅らせるかまたは予知するだけで、fa super laの進行は、しばしば見受けられる(同じ作品のKyrieから)。
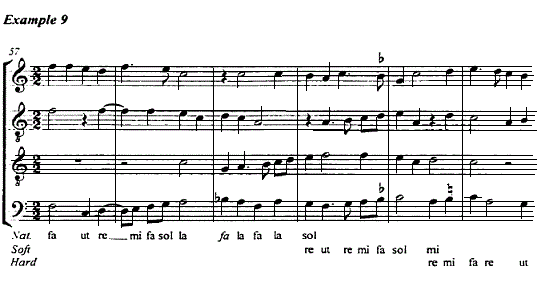
1つの♭の調号を持つ作品では、E♭は柔らかいヘキサコードではrectaになる。E♭は、Fからの自然なヘキサコードの上のfa super laとしてのalterationとなる。次の例10では、Missa Puer natus est nobisのSanctusの冒頭を示しているが、discantusの第6小節のE♭は、主なソースで実際に記名されている。
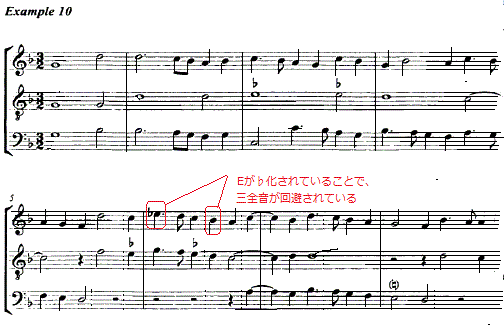
上記の例では、contratenorの唯一の可能なヘキサコードの選択は、冒頭でのFからの自然なヘキサコードである。第5小節までの最初のフレーズの全体は、fa super laの使用により、このヘキサコードにおいて歌うことができる。
まったく同じことが、discantus(実際、第6小節ではE♭は記名されている)にも言えるので、作曲家のこれらの両方のパートの意図は明らかである。
上記の例10では、fa super laは、2つの異なる理由で使われている。 そのうちの2番目の理由は、第6小節で記名されているE♭であり、それは、同じ小節内に現れれているメロディ上の三全音を避けるために、役立っていることである。26
26 1つのヘクサコード内では、メロディ上の三全音が生じることはないが、ヘクサコードがfa super laの使用によって拡大すると、miと(拡張された)faの間のメロディ上の三全音の可能性が実際のこととなる。この例では、E♭とA、あるいはE とB♭の間での三全音が不可避である。 とB♭の間での三全音が不可避である。
ただし、第3小節のcontratenorでのE♭は、旋律的三全音の修正には使われていない。なぜなら、(contratenorの)このフレーズにはB bはないから。この問題に関するBergerのやや横柄な発言に照らしてこれを考えてみよう。
要するに、16世紀には無分別に「fa super la」のルールを適用する多くの人がいるが、知識のある音楽家は、このルールは単なる三全音禁止からのスピンオフであると考えている。 16世紀の音楽を編集または実行するときに、三全音禁止のルールを独立に適用するかどうかは、その時代の最も賢明な音楽的意見に従うか、むしろ洗練されていないがかなり一般的な慣習であると思われるものを模倣するかどうかによって異なる。37
37 Berger, Musica Ficta, 78-9.
p36
fa super laの慣習が、旋律的三全音を和らげるために最も頻繁に使用されることは事実だと思われるが、上記の例はこれが常にそうではないことを明確に示している。
確かに、この問題に取り組む際の洗練度の欠如を主張しても仕方がない。私は、この規則の適用が、三全音を伴わないパッセージに関連する可能性はあると思う。ヘキサコード順を超える半音階の拡張が示されている特定の旋律構成を認識する経験のみが、その評価が可能である時に、信頼できるガイドとして機能する。そのタスクは、ケースバイケースでアプローチされるべきであろう。
|