| The Motets of Antoine Busnois BY EDWARD H. SPARKS |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p216 最近の本で、Heinrich Besseler は、フランドル様式の基礎は、すでに、15世紀半ば以前から準備ができていたという結論に達している。 彼は、この当時の、音楽の発展の連続性を強調し、Kiesewetterの3つのフランドル楽派のカテゴリを是認する説明をしている。神聖な音楽の分野では、少なくとも、彼は、初期のブルゴーニュ派と後期フランドル派の間の区別をしない傾向にあった2。 2 Besselerは、ヤン・ファン・エイクの作品がフランドル絵画の始まりを示すように、デュファイがフランドルの音楽の始まりを示すと述べている。彼は「ブルゴーニュ派」という用語を、公爵宮廷のシャンソン芸術に適していると考えている。様々な理由から、しかし、「ブルゴーニュ楽派」「フランドル楽派」という用語等は、この論文でも使われている。 I460年代と70年代の音楽の研究は、連続的な発展の概念を完全に支持している。そして、長年ブルゴーニュの宮廷で働いていたビュノワのモテットは、それに対する明らかな論拠を与えている。 これらは決して、新しい音楽傾向のすべてがオケゲムからやってきたわけではないことを示している。逆に、 Dufay (Busnois, Faugues, Regis) に続く世代のブルゴーニュ派は、若い世代のスタイルに不可欠な部分になった新しいリソースの開発に非常に活発であった。Obrecht, de la Rue, Josquinの作品の様々な本質的な特徴を考慮して彼らの作品を受容することが、絶対に必要なのである。 ビュノワの生涯については、ほとんど情報がないが、彼はCharles the Bold of Burgundy の音楽家であったことが知られている。そして、I460年代のと700年代に約20年間、ブルゴーニュの宮廷にいた。彼の名前は1481年以降、宮廷記録からは消えた。1492年にブルージュで死亡した。1474年のデュファイの死後、約20年後、1495年のオケゲムの死の数年前であった。 保存された作品の数から判断すると、ビュノワは、モテットやミサ曲の作曲家としてよりも、はるかに世俗曲のそれであった。シャンソンははるかに他のカテゴリでの作品数を上回るので、これは、現代の出版に反映されている。その結果、私達の彼についての概念は、テノールモテットやミサ曲の楽章よりもむしろ、主に世俗的な作品を基礎に置いている。 p217 ①hydraulis, ②Anima mea liquefacta est--Stirps Jesse, ③Regina caeli (II), ④Anthoni usque liminaの4つのモテットが、出版されている。 これら4点の作品のうち、2点はビュノワのスタイルの特殊性の指標として特に有用ではない。 Anima mea liquefacta est は、様式的に、もっとも初期のモテットであり、初期の作品である。In hydraulis (楽譜)も後期の作品とは考えられず、そのテキストから、1467年以前に書かれたに違いない。 出版されていない作品は、①Victimae paschali laudes, ②もう1作のRegina caeli, ③Conditor alme siderum, そして 2つの小品-Alleluia, verbum caro factum est とNoel,noelである。 モテットのための中心的な資料は、Codex 5557 of the Bibliotheque royale de Belgique at Brusselsである。それは、In hydraulis とConditor alme siderum以外のここでご紹介したすべての作品を含んでいる。 この写本は、Charles van den Borrenによって簡素に記述され、詳細は、 Sylvia W.Kenneyによって記述されている。 それは非常に注意深く書かれており、チャペルでの実際の使用を意図していた。そのレパートリーは、ミサ曲、マニフィカト、モテットで構成されており、およそ1450年から75年に作られた。 作曲家は、Dufay, Regis, Ockeghem, Busnois, そして2人の英国人Walter Frye 、Richard Cockxである.。 ビュノワのモテットが、作品の構造を明らかにするにつれて、尋常でない痛みを持つような、彼らに非常に近しい人物を示しているような証拠がある。16 この人物は、作曲者本人である可能性が非常に高い。 16 例えば、 cantus firmus は、必要に応じて、テキストに言及されることが通例であったが、こうした場合は、メロディ全体を担う声部の下に通常、置かれた。先行するstatementやmigrationのようなこうした繊細なpointsは、示されなかった。 しかし、Anima mea liquefacta estにおいては、ソプラノによる部分的なcantus firmusのstatementは、適当な音符のもとでのrespond Stirps Jesseのシラブルを書くことで示されている。これらのシラブルは、実際のテキストが通常のように、譜線の下にあるのに対して、譜線の上に書かれている。 同じことは、Regina caeli (I)でも行われている。チャントのシラブルは、cantus firmsのmigrationを示すために、1つの声部から別の声部へと動いている。これらは、作品構造についての不安への顕著な例である。 同様のケースは、Anthoni usque liminaでも見られる。ここでは、こうした痛みは、それを見逃すことができないとしても、作曲者の名前を示して受け取られている。(最初と最後の言葉のシラブルは、赤インクで書かれている。すなわち、"Anthoni usque . . . omniBus Noys."となっている。 p218 モテットは、時代の完全特徴ではない多くの足跡を示す。例えば、Noel, noelと Verbum caro factum estの2作は、その概念において、著しく和声的である。直線的水平的観点は、通例よりもはるかに大きく、垂直に従属する。 他の作品のどれもがこのような単純な、和声スタイルで書かれていないが、ハーモニーは、全体的に固定的である。そこには、完全な三和音の優位性があり、そして、和声から和声への動きは一般的にはっきりとしているが、そのような場所でさえ、個々の旋律の流れは、非常に華やかである。 クリアな和声的基礎は、ブルゴーニュの伝統においては通底していないわけではないが、ビュノワの和声は、より早期の作曲家たちよりも、豊かなものとなっている。 これは、内声がより活発なことによる。さらにいくぶん、低い音域で。そして、不協和音の自由な使用、特に、三全音や短七度の響きなど。 例1は、しばしば鋭い不協和音となる2声を示している。こうしたクラッシュは、デュファイの成熟した4声書法ではまれである。 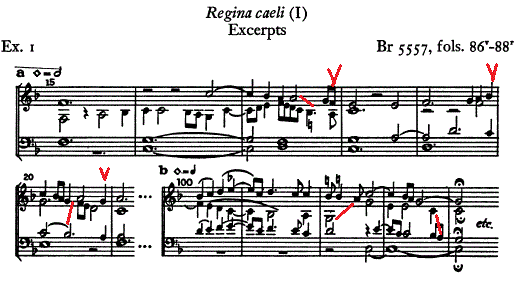 確かに、彼の様式の和声の透明性は、主にちょうどそのような組み合わせの控えめな回避によって維持されている。これらの不協和音はしかし、根本的なハーモニーに関連して説明することができるという意味で、すべて和声的には「正しい」。この点でビュノワは、単純に、15世紀の前半において、不協和音に関連して基本的な協和音程としての三和音を受け入れたより初期のブルゴーニュ派の実践を、単純に、さらに発展させている。18 18 和声音へのステップによって解決されない声部のリズム変位に起因するような不協和音は、ビュノワには極めてまれなことである。Anima mea liquefacta estのコントラテノールの第115小節にその例がある。不協和音であるdが、gに四度跳躍している。こうしたシンコペーションによる不協和音は、14世紀後半の説く直であるが、15世紀の第2四半世紀には、それほど使われなくなった。これらはむしろ、デュファイやビュノワよりもオケゲムにおいてしばしば見られる。 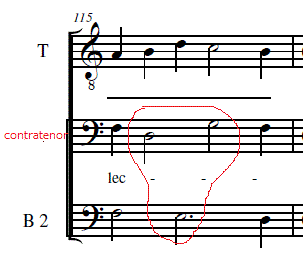 カデンツについては、ビュノワは、彼の時代の多く使われた偽終止形式 (V→VI, V→IV, etc)には従っているが、しばしばより古い終止公式が保たれている。 加えて彼は、しばしば、カデンツを拡張している。通常は2つだけの和音(VII6→IまたはV→I)上にカデンツを形成するデュファイとは対照的に、ビュノワは、カデンツを繰り返すことによって、あるいは偽終止的なカデンツをつなげる書法によって、全体のフレーズを構築し、意識的にそれを遅らすことにより、カデンツを強調している。 以下の3作のモテット(EXX。2-4)の最後のフレーズは、彼の作品において、純粋な和声効果の重要性を示すのに役立っている。 Regina caeli(I)においては、第112小節のフルカデンツには、ソプラノのメロディが2回、終止音の前で偽終止的和音となる丹精な拡張が続いている。強調された完全なカデンツが聞かれる。 Noel, noelの単純な様式は、和声をとりわけはっきりさせる。同音の初期の導入(第21小節)は、終止の前の4小節の強いカデンツをもたらす。最後の小節は、単に確認し、それを強調するだけである。 p220 同様に、 Victimae paschali laudes においては、フルカデンツは、終止前の数小節にわたって現れる。そして、V→I進行の丹精なカデンツ表現が続いている。 第111小節より114小節において、1声部が増えており、それは、和音の根音を作るためのみの目的でつけられている。bassistenorが上声部と模倣のpointを作っている。(Noel, noelのmusica fictaの問題に注意。ここのバスのミ音は明らかに♭化されるべきである。trebleにおいては同じミ音はナチュラルであるが。訳注;要はここは”対斜”となる)。 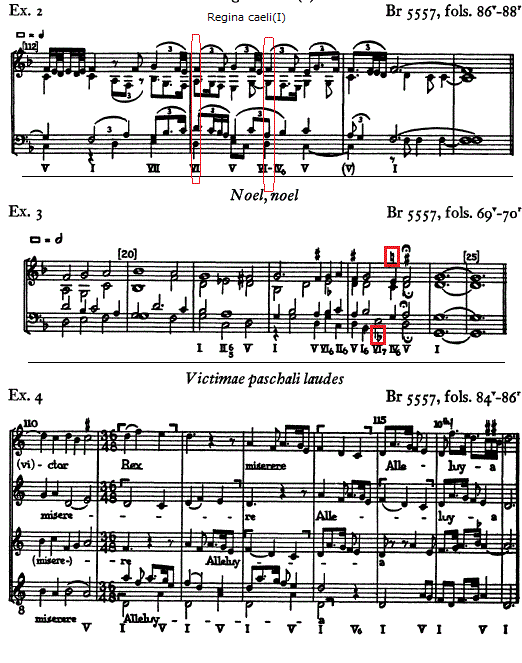 表現としてのカデンツの強調、一般的なクリアな和声作成、そしてむしろ自由な不協和音の使用は、ブルゴーニュ様式の伝統に沿わないわけではない。それらは、決定的な進化は遂げてはいるけれども。 これらの和声の足跡が、フランドル学派の父、オケゲムから由来していないことはあきらかである。それらが直接、より若いフランドルの作曲家であるオブレヒトを示すことは、明確である。 一方で、ビュノワの旋律スタイルは、ほとんどブルゴーニュ様式と呼ばれることができない。むしろ、それはオケゲム寄りである。これは、彼のメロディがフランドルの巨匠のそれと間違えられることではなく、それらが、オケゲムがそうしたような同じ一般的な点においては、バンショワやデュファイの伝統的な様式とは異なっている、ということである。これらの違いは、多くの作家によってすでに議論されており、詳細を繰り返す必要はない。M. F. Bukofzer, Studies in Medieval and Renaissance Music (New York, 1950), pp. 272-292. ただし、ブルゴーニュ音楽では通常、3拍子であり、ヘミオラを頻繁に使用したリズムは流麗であるが、基本的な拍子が一般的であると強調されている。否定的に述べると、シンコペーションの連鎖や拍の細分化から始まる連続するリズムパターンなど、拍の単位(通常はsemi-breve)をかなり不明瞭にするリズム的なデバイスを避ける傾向がある。 このようなパターンは、拍の後半から開始される場合があるが、Ex.5(最低声部mm。71-72)の場合のように、第2四半分または第4四半分から開始されることはほとんどない。 例5 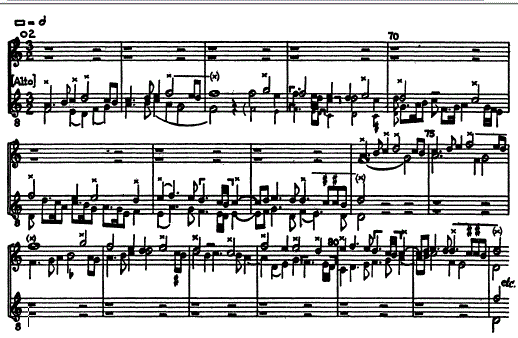 一般に、これらのstatementは、デュファイの後期のミサ曲でさえ当てはまる。Ockeghemの神聖な作品のリズムパターンは、もっと複雑である、拍のより小さな下位区分が常に使用されている。アクセントの配置は非常に一般的である。ラインはしばしば「オフビート」でクライマックスに達する。すべての声部は、1つのタクトから次のタクトに持ちこたえる。その結果、表向きの拍の単位であるsemibreveは、ブルゴーニュ音楽のように聞こえないということになる。 波乱に欠けるような、おそらく初期のビュノワの作品では、拍の単位としてsemibreveを感じることができるという事実が、ブルゴーニュ様式への一定の類似性を付与する。 これは、特に4声のモテットIn Hydraulis楽譜)、および3声のAnima mea liquefacta est--Stirps Jesseに当てはまる。 ただし、メロディラインは複雑ではないが、リズミカルな落ち着きのなさや旋律的な角ばりは、デュファイやRegisのバランスの取れたエレガントなメロディ様式とはかけ離れている。その他の作品は、オケゲムで見られるものを上回るようなシンコペーションされたリズムパターンであふれている。 p221 この例(Victimae pascbali laudes Second Part)では、最も低い声部は、数小節進んだ後、非常に増大する速度(m.70 ff。)で突然爆発している。 コントラストをさらに強調するために、アクセントは、拍の2番目と4番目にシフトされている。この派手な書法ほどに古いブルゴーニュ派の音楽精神からかけ離れたものは、想像し得ない。 モテットが全体として、とらえられると、声部はその性質において、合理的に類似していることがわかる。すなわち、対位法は均一になる傾向にある。 しかしビュノワは、対位法(で各声部が)が等しくなる華麗な声部の使用においてオケゲムと比較されるかもしれないが、ビュノワは全く異なる芸術的効果を目指している。 Ockeghemは、声部の一定の動きを適度に一定に保つ傾向があり、音楽素材の極端な一貫性と継続性を目指した。 Busnoisは、特徴的に、警告なし示され、数小節以上は維持されないような驚くべき動きの変化をもたらす。 ビュノワが、、動きの速さだけでなく、リズム的な複雑さを行うことによって、リスナーの注意を引き付けるように設計されたディテールの素晴らしい効果に非常に興味を持っていたことは、明らかである。このようにリズムの効果に没頭する中で、ビュノワは、15世紀の最後の四半期を通じて持続し、最高の作家の作品の特徴であるスタイルの側面を予測した。 ビュノワの輝かしい効果への愛は、彼の書法の別の観点からより明確に現れる。非常に多くの場合、自由に流れるメロディーラインは、繰り返されるパターンで構成されたメロディラインのために放棄されている。 こうしたパターンは、単にリズム音型を繰り返したものかもしれないが、通常はメロディー音型も繰り返す。 p222 それらはいつもお互いに従うわけではないが、フレーズを通してばら撒かれ、あるいは、はっきりと連続している。 これらは通常、複数のパートで厳密に模倣して示され、声部間の強いクロスリズムを生成するようにエントリが配置されている。 Anima mea liquefacta est--Stirps JesseおよびIn hydraulisにおいて、そうした作品は初期のものであるが、この種のパッセージは通常、デュオおよびフレーズの途中で発生し、一時的な多様性、または作品の過程での興味深い偶然性がそこにはある。 より進んだ他の作品では、これらのパッセージの影響は、すべての声部でパターンを集中的に使用することにより、大幅に増加している。 Victimae paschali laudisの最後のフレーズ(Ex。4)が実例となる。 パターンは簡潔で鋭く輪郭づけられることに注意したい。 それらは単純な調和的進行を暗示しており、オスティナートの全効果を付与している。 さらに重要なのは、このタイプの最も印象的なパッセージは、最後のカデンツまたは最後のカデンツの直前のパッセージのために取っておかれているということである。 この位置では、それらは作品全体の興味深い出来事以上のものになり、全体の形に関連する重要な機能を達成する。 一方では、この種のパッセージは、デュファイのスタイルの重要な部分を構成せず、オケゲムのスタイルの重要な特徴ではないことは明らかである。他方、、最終カデンツでのパターン化されたメロディラインまたはクライマックスのパッセージの使用には、オリジナルなものはなく、当時は誰もがそれらを使用していた。 ただし、カデンツは通常、速度の増加だけで強調され、むしろ穏やかな効果があります。ビュノワは、パターン化されたメロディラインを使用する頻度もあるが、主に音楽のクライマックスを構築する上でその有用性を最大限に実現したために、同時代人よりも際立っている。 彼は、より若い人たちによってさらに完全に発展させる可能性を探求することにおいて、彼の仲間の作曲家よりもさらに進んでいる。これらの短い一節は、JosquinのMissa Gaudeamus のクレドの終わりやMissa Hercules dux FerrariaeのSanctusのような広範かつ圧倒的に素晴らしい楽章の初期の先駆者である。 ビュノワはモテットにおいて、模倣をかなり活用しているが、一般的に彼は同時代人がそうであるように、非模倣的な対位法をも書いている。前述のストレットとRegina caeli (II)のカノンのcantus firmus を除き、これらの作品の模倣的なパッセージは、新しい実践を示していない。 たとえば、Regina caeli(I)とIn hydraulisの第2部の導入デュエットの模倣、またはAnthoni usque liminaの導入トリオを終止する3声の短い模倣パッセージでさえ、本質的に新しいものを構成していない。そのような扱いは、世紀の初めまでさかのぼったモテットにまで見られる。 模倣のpointは、フル声部と同じくらいにはある。さらに、比較的控えめなシャンソンや歌のモテットでは、多くの、またはすべてのフレーズの先頭で模倣的なエントリが使用される可能性があるため、定期的に繰り返される模倣pointは見い出されない。 モテットでは、模倣が基本的な構造的手段と見なされるほど十分に系統的に使用されることはない。確かに、構成的要因としての用途はあるが、その重要な機能の1つは、さまざまなモチーフ的な工夫を共有しているが、単に対位法に興味と多様性を与えることである。 この時期以降、ミサ曲とモテットで、模倣の実際量が着実に増加しているにもかかわらず、非体系的な使用におけるこの特質は、15世紀を通じて証拠として残っている。 ほとんどの作品の構造的基盤は cantus firmusである。 2つの例外があり、それは、比較的シンプルで音符に反したスタイルの短い作品であり、note-against-note styleのNoel, noel と、自由に作曲されたAlleluia, verbum caro factum estである。 作品のうちの5作は、グレゴリオ聖歌のメロディーを使用している。 Conditor alme siderum は、ソプラノでわずかに装飾された賛歌のメロディーを使っている。 この作品は明らかに、メンスーラの特定の特徴を説明するために書かれたものである。 すべての声部で異なるメンスーラが同時に使用され、個々の声部内でメンスーラが時々変更されている。 記譜法のこうした側面に重点を置いているにもかかわらず、和声は、ビュノワの書法の充実した特長となっている。 Anima mea liquefacta est--Stirps Jesseは、Tenor motetの非常に単純な例で、4声あるいはそれ以上ではなく、3声だけで書かれている。 Antoine busnois: Anima mea liquefacta est 楽譜 テノールは、respond Stirps Jesseのメロディーを使っている。 サイレントである間、ソプラノによるcantus firmus の通常の先行するstatementがある。最初のところと、作品のほぼ中央(mm。87-IO6)である。 このように、作品は2つのセクションに分類されるが、形式的に行われるような、フルカデンツで分割されているわけではなく、通常の”二重線”によってなされる。つまり、最初のセクションは、ロンドーの最初のセクションのように、セミカデンツで、フル三和音で(c#を伴うイ長調、コントラテノールにsignum congruentiaeがある)終止する(第86小節)。 真のバスの欠如と、テノールの上下の和声の埋め草としてのコントラテノールの扱いにより、この作品は他のモテットよりも幾分古風に見える。 Regina caeli(II)(楽譜)は、2つの最低声部による五度のカノンのcantus firmus statementに基づいている。 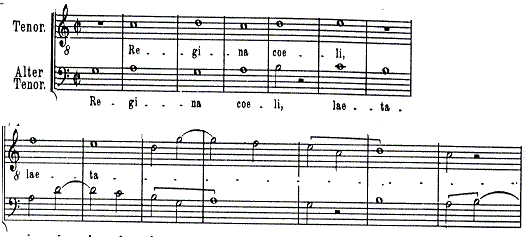 これは、当時の対位法に対する関心が高まっていることを示す多くの作品の1つである。(こうしたもののうちでもっとも極端なのがFauguesのL'Homme arme' Mass であり、これは全体的にカノンとなっており、借用素材に基づいている)。 このモテットは、デュオやトリオの機会を供与するためのテノール部分の長い休符がないために、Fauguesのミサ曲よりも、通常のテノール構造としては、かけ離れている。 作品はカノン声部で始まり、ほどなく、非常に短い時間で3声分のcantus firmusを形成する、簡単な模倣パッセージとなるsuperiusに結びついていく。 カノン自体はかなり粗っぽいものである。それは、長さが1〜8小節の短いフレーズに分割され、模倣の音価は、1.5から3.5まで変化している。それ以外の場合、模倣は、間隔とリズムに関して正確である。 p224 カノンは、作品全体のアーキテクチャに注目して管理されている。最初は7小節の間、連続的に維持される。その後、cantus firmusを担う声部の片方または両方が常に参加している、一連の変化するカルテット、トリオ、およびデュエットが続いている。 これらに続いて、最も低い2つの声部のカノンデュエットが、最後のセクションにやってくる。それは、作品の音響的クライマックスである。このセクションでは4つすべての声部を使用しているため、最も低い2つの声部は、連続したカノンで18小節半の長さで演奏する必要がある。 これを達成するために、作曲家は、cantus firmus由来ではないフレーズを導入するが、彼はそれをカノン的に扱うため、ガイド的原理はそのまま残されている。 Busnoisは、テノールモテットの中音域にあるテノールにcantus firmusを持ってこない。 Regina caeli (I) において、彼はそれを最も低いパートに持ってきており、Victimae paschaliではaltoのパートに持ってきている。 このように、借用した素材担う声部の位置を変えることにより、ビュノワはデュファイの慣行から離れ、オケゲムや他の若い作曲家の慣行に従っていっている。 一方、Busnoisは、ブルゴーニュ派がそうであったように、cantus firmusを非常に規則的に使っている。 「規則的なstatement」とは、いったん開始されると、cantus firmusの全体が最初から最後まで規則正しい順序で引用されることを意味する。 つまり、作品の途中で放棄されたり、オケゲムで見られるような引用における折り返しや、その他の気まぐれで予測不可能な用法があったりはしないのである。 オケゲムに対するビュノワの敬意は、In hydraulisのテキストにおいてよく知られているが、それのさらなる証拠は、オケゲムのSalve regina に類似するモテットRegina caeli(I)にも見られる。 それぞれの作品では、①cantus firmusは最低声部で見出される。それぞれの冒頭のデュオは、通常通りに、借用したメロディーを先行提示している。さらに、②両方のデュオには、cantus firmus の終止音が出現する前に、精巧で自由なセクションがある。 Ockeghemの場合、こうしたことは驚くことではない。しかし、ビュノワでは、デュオへ導入されるmigrationによって状況はより複雑になる。そこでは、全体のパッセージは彼にとっては通常と異なっており、cantus firmusの提示は通常通り、かなり簡素なのである。 最後に、③両方の作品では、下から2番目に低い声部に、バスのエントリの短い模倣のstatementが存在する。これら3つの点での類似性は偶然ではない。それらが意識的な模倣の例であることに疑いの余地はほとんどない。なぜなら、Busnoisは彼の作品をより精巧にするために苦しみ、彼のモテットはOckeghemのそれをモデルにしているからである。 p225 また、ビュノワのVictimae paschali laudes とOckeghemのAlma redemptoris materの間では、両方のcantus firmusがアルトにあることで、一定の関係がある。両方の作品の音域も高くはなく、それぞれの一番上の声部はC音部記号ではなくG音部記号で書かれている。 しかし、オケゲムの作品ではcantus firmusは終始、1つの声部が担うが、ビュノワのフレーズでは、アルトが沈黙しているときには他の声部でそれが出現するために、外部的な類似性はここで終わる。 言い換えれば、ビュノワはテノールモテットの通常の形に近いということである。 Victimae paschaliの第2部の冒頭では、アルトによる一連のメロディーのフレーズのstatementがソプラノによって音ごとに繰り返されている(例5、mm。66-74および74-82)。 正確な繰り返しの同様の例は、第1部分の冒頭にあるデュオにも見出される(ただし、声部の順序は多少異なる)。これらの正確な繰り返しは取るに足りないことかもしれないが、以前の慣行の矛盾を表しているため、かなり重要である。 反復がオリジナルのメロディ自体に存在しているか、作品においてcantus firmusをレイアウトするやり方によってもたらされたかにかかわらず、cantus firmus素材の反復(の2回目)では、装飾がなされるのが慣習であった。 たとえば、デュファイのテノールモテットAve regina caelorum の冒頭では、同じチャントのフレーズが連続して4回、それぞれわずかに異なる形で繰り返されている。数多くの作品において、我々は、繰り返しの効果を見えなくするために、そして、作曲家の空想の無限の流れの連続的に展開するメロディーの印象を生み出すために、積極的な努力がなされたと結論付けなければならない。 Victimae paschaliからのこうした短いパッセージには、当時の音楽に現れる明確な構造的関係を作成したいという紛れもない欲求の例の1つがある。 In HydraulisおよびAnthoni usque liminaは借用されてはいないが、特にこれらの作品の足場として機能するように考案されたTenorsに基づいている。このようなテノールは、ジョスカンの世代の間で非常に人気があったタイプの初期の例である。 これらを構成するメロディは、多くの場合、テキストのシラブルから選ばれたもの(Ut Phoebe radiis)27、人の名前がついたもの(Hercules dux Ferrariae)、または作曲家の空想にふさわしい他のソースから選択された。ステファンは、In Hydraulisのテノールの音符は、言及されている音楽の音程と一致するように選択されたことを示唆している。四度、五度、およびオクターブという具合に。28 27 このメソッドは、非常に複雑なプロセスの一部としてOckeghemでも使用されており、それによってモテットUt heremitaのテノールが導出されている。 28 テノールの音符はd-c-d、休符、a-g-a、休符、d-c-d等である。2番目のステートメントは1番目よりも五度高く、3番目は2番目より四度高く、1番目より1オクターブ高くなる。 Anthoni usque limina のテノールは、音符dの繰り返しのみで構成されている。ベルをたたくか、ベルを模して歌っている。ボーアは、鐘は聖アンソニーの伝統的な属性の1つであることを指摘している。 p226 これらのテノールのそれぞれは、厳格なリズミカルなスキームに従ってレイアウトされている。この手順は、当時では、ミサ曲においてよりも、モテットにおいて、よりまれである。30 30 Anthoni usque liminaのテノールの音符のリズム配置は、教典碑文によって示されているが、その意味は非常に曖昧であるため、いくつかの異なる解釈が提供されている(Van den Borren、Atudes、p。239ff; Stephan、op。cit。 、p。22; Boer、op。cit。、音楽付録)。 多くの場合、試行錯誤の過程で、テノールの音を他の声部に合わせると、適切な解決策に到達することができる。教典碑文を使用してテノールを解決する代わりに、テノールを使用して教典碑文(の問題点)を解決するのである。ただし、この作品では、ハーモニーの大部分はDマイナー、Bbメジャー、Gマイナーであるため、テノールのdは実質的にどこにでも収まる。 主題が非常に問題を抱えていることは疑いの余地はないが、さまざまな理由から、ボーアの解決策には完全に納得できない。1つには、ハーモニーは、パート1の第42小節で、非常に不安定になる、ということ、もう1つは、テノールがパート1の第2小節とパート2の第1小節で入るために、導入のパッセージがないことである。 これはテノールモテットではあり得ないことではないが、珍しいことである。この作品では、バス "Barripsaltes"が入る前に、パート1にbreves9個分、、パート2に18個分のbrevesの導入のトリオの明らかな証拠があるため、それは特に疑わしいようである。 (パート1のメンスーラはO、パート2のメンスーラはO2である。) 最も深刻な問題は、テノールと作品全体のアウトラインとの関係である。モテットは驚くほど対称的で、パート1は54個のbrevesとlongaから成り、パート2は、1O8 のbreveとlongaから成っている。 このような作品では、出発点はテノールであり、全体の対称的な比は、テノールの対称的なレイアウトの結果となる。提案された解決では、パート1に27回、パート2に31回のベルストロークが出現する。(Stephan、op。cit。、pp。22-23も参照。) これらの数は、作品の比とは無関係である。 テノールは、別の点では、作品に対しては非対称である。なぜならテノールは、パート1では2番目のbreveで始まり、最後のロンガを逃すからである。 パート2では、最初のbreveで始まり、最後のロンガとなる。 Anthoni, usque limina Orbis terrarumque maris, Et ultra, qui vocitaris Providencia divina, Quia demonum agmina Superasti viriliter: Audi cetum nunc omina Psalentem tua dulciter. Et ne post hoc exlium(2分37秒) Nos igneus urat Pluto, Hunc ab orci chorum luto Eruens, fer auxilium: Porrigat refrigerium Artubus gracie moys, Ut per verbi misterium Fiat in omnibus noys. Anthony, calles to the limits of the earth and sea and even further, by God's provision, since you have defeated demonic attacks with manly bravery, hear the choir singin your deeds with sweet song. Save this choir, with your help, from the cesspool of hell, so that, after this vale of tears, Satan's fire scorches us not. https://www.allmusic.com/composition/anthoni-usque-limina-motet-for-4-voices-mc0002404627 The first fourteen lines weave a tapestry of images taken from various chants and spoken collects for liturgies of the Feast of St. Anthony, while the last two lines (from the text "Ut per verbi mysterium," set in imitation) seem to bring the piece into the context of a Mass celebration by evoking the present mystery of the Incarnate Word. Unconventionally, its vocal scoring shifts over the course of the motet:: for the opening moments of both sections only, a third high voice appears by "Gymel" notation, and then vanishes.After these trios, which are marked by a quite pervasive imitative style, the actual third voice, a low voice labeled "Barripsaltes" enters. As is the case in his Rondeau A que ville, the use of a made-up voice-name may serve as another "signature," combining the first text capital "A" with this capital "B." "Anthonius Busnoys" the literate provides one more clever puzzle in the motet-a canonic derivation of the true fourth voice, the tenor. The half Latin, half bastardized Greek inscription at the bottom of the manuscript page contains cryptic instructions as well as two images, a bell and a Tau-shaped crutch, or cross, both symbols of St. Anthony. But the canon seems to indicate as well that the tenor voice should, instead of singing, sound a bell at regular intervals over the course of the motet. The bell (or vocal imitation of a bell) adds tonal luster and harmonic stability, as well as effecting a kind of ritual invocation, perhaps even linking Anthoni usque once again to the ritual bell tolling at the central moment in the Mass, the Elevation of the Host. BusnoisのL'Homme arme Massは、cantus firmusの扱いに対する彼の態度をさらに特徴づけている。 彼は、シャンソン・テノールを、オケゲム、デュファイ、レジス、またはキャロンよりもはるかに文字通りに引用している。 それの繰り返しは、増価、移調、反転によって変化する。 Mass O crux lignumのcantus firmusの扱いも単純で素直である。 与えられたメロディーを文字通り引用し、それを操作することに興味があることで、彼は同時代の人たちとは少し離れた場所にいる。彼は全体として、借用した素材をより自由で空想的な方法で述べることを好む。 この点でも、彼はオブレヒトに似ている。オブレヒトは、与えられた素材をそのまま慣用的に引用し、あらゆる種類の操作を行っている。 <まとめ> ビュノワのモテットは、いわゆるフランドル楽派の父オケゲムの特徴ではない多くの様式的足跡を残しているが、それは、この楽派の若い仲間の書法の重要な特徴なのである。 オケゲムには、満足のいくような先例ではない若い世代の様式の要素がたくさんあるが、これらの先例は、ビュノワの作品では非常に明確である。 さらに、ビュノワの同時代人の多く(レジス、フォーゲ、キャロンなど)は、彼と同じことをしているが、それほど鮮明な効果はない。 それゆえ、ブルゴーニュ楽派が終わり、フランドル楽派に置き換わったと結論付けるのは、単純すぎる解釈であるように思われる。 地域差の存在を否定することなく、一般的に音楽スタイルの広範かつ継続的な発展があったようである。 ブルゴーニュ派とフランドル派の両方が、ジョスカンと彼の世代の作品で最高潮に達した新しい発展に貢献した。 |