| "PSEUDO-AUGMENTATION" IN THE MANUSCRIPT BOLOGNA, CIVICO MUSEO
BIBLIOGRAFICO MUSICALE, Q 15 (BL)*3 BOBBY WAYNE COX |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 | St.マーシャル楽派へ |
| Leoninのページへ | ノートルダム楽派(conductus)のページへ |
ペロタン(Viderunt Omnes) |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ | まうかめ堂さんのページへ |
| substitute clausulaのページへ | 中世楽のページへ | 前ページへ |
| 次ページへ |
その前
| p436 混合計量記譜法が、少なくともある程度は、作曲家以外の人の工夫であったという主張をさらに裏付けるために、記譜がsigunaturesを偽るような2つのモテットを精査して、我々はQ
15以外の写本に見られるいくつかのpseudo-augmentation の作品を見て回ってから、また Q 15 に戻ろう。(略)
p439 この研究で考慮されるべき作品の最後のグループは、計量記譜法レベルの混合を含んでいない。このグループはむしろ、Q 15の中のいくつかの作品が、tempusレベルでの記譜法であったが、 prolatioレベルで作曲家によって考え出された可能性があることを示している。 後で、筆記者か他の仲介者のどちらかによって、これらの作品はその時より新しい、よりファッショナブルなtempus記譜法に変換された。このような見解は、イタリアの音楽に関して知られている事実によって最もよく支持される。しかしそのようなことが起こったことを実証するフランスの音楽における明白な例がある。 その記譜の手書きによる扱いは、Trecentoの最後の頃、イタリアの音楽で実践され、Quattrocentoの初期の頃はよく知られてるようになった。 Kurt von Fischerは、brevis記譜法で写本に見つかった作品が、longa記譜法で別の写本にあった事例を指摘している。 Fischerによると、その目的は記譜法をアップトゥーデイトすることである。 この問題は、Eugene Fellin によって最近議論された。彼は90のunicaではないマドリガルとカッツィアをリスト化し、特にそれぞれが保存されている記譜法のタイプを示している。Fellinはさらに、フランスの記譜法からイタリアの記譜法における誤りや癖に基づいて、いくつかのunicaを選び出している。 p440 作品の記譜法があるシステムから別のシステムに移すできることが明らかであれば、作品のすべての声部が同じフランス語またはイタリア語のシステム内で一段階進められることを知っても驚くにあたらないはずである。フランスの記譜法では、prolatioはtempusになり、tempusはmodusになり、音部記号 そのような変換の1つの有名な例は、BorletのHe、tres doulz roussignolである。 このvirelaiは、2つの異なるレベルの記譜法で現存しているが、どのバージョンにもsiginituresはない。 PR106は3声で、GR 16 2では4声である。それぞれ記譜法はprolatioレベルである。Ch 89とStr 53では、記譜法はtempusレベルで、Ch 89は4声だが、Str 53にはcantusIのフラグメントしか含まれていない。 フラグメントはしかし、diminutionemごとにラベルかされている。 ある作品が、2つの記譜バージョンで存続するのであれば、He、tres doulz roussignolのように、どちらか一方のバージョンが「扱いにくいもの」であっても、書き換えが行われたことは明らかである。 一方、tempusのバージョンのみが現存する場合、 もともとprolatio perfectaの作品がより高いレベルで再記譜されることを心から受け入れることにいくらかの抵抗があるだろうが、そのような美容形成を受けたことの第一候補であるQ 15には、2つのモテットがある。 <Excelsa civitas Vincencia Feragut> 写本(608/697) FeragutのExcelsa civitas Vincencia、BL 271は、これまでの議論の対象であった。Ox 3としても保存されており、両方の資料でモテットは、tempus音価になっている(図20signaturesは、Oxも同様)。 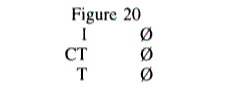 ただし、2つのバージョンには違いがある。Oxでは、1433年5月7日にVicenzaの司教に選ばれたFrancesco Malipieroを称えているが一方、Q 15では、Malipieroの前身であるPietro Emiliani讃えることを意図している。 Petrum Emilianumという名前はテキストの一部であったが、Francescum Malipetroは別の手によって置き換えられた。 p441 Feragutのモテットを取り巻く論争は、すべての声部に 他の作家は、1433年を作曲の年としてリスト化した彼に同意しているが、ほとんどの歴史家は、ExcelsaがEmilianiを称えるために1409年に最初に作曲されてそれからMalipieroを称えるために1433年に2度目に使われたというAndre Pirroの提案に従っている。 Excelsaの作曲年が1409年だった場合、シグネチャ 私はそうは思わない。 すでに示されてきたように、 (1)このスラッシュの使用は、1420年代にのみ発生したように思われ、それ以前に作曲されたいくつかの作品に遡及的に適用されたが、私が判断できる限り、体系的な方法では適用されなかった。 (2)Excelsaの低い声部の記譜パターンは、 独特の記譜法についての説明は、次のようになる。 Excelsa のcantus声部は、もともと これもまた以前に論議したことだが、反対に、 contratenor and tenor が p442 OxとQ 15の筆記者が個別に、そして自分自身で、Excelsaをtempusレベルに再記譜しようとしたことは述べられず、示されていないが、エヴィデンスは、これがFeragutのオリジナルではないことを示している。 <Aurea flamigeri、BL Romanus> 写本(521/697) Q 15の筆記者がおそらく、時折、 作品は4声で、すべてが それから手順は繰り返される。すなわち、cantus Iは 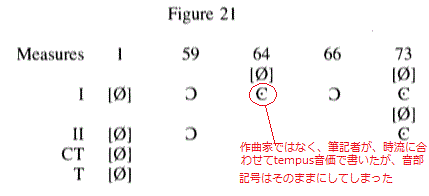 Q 15の筆記者がこれらの疑わしい改訂のいくつかに責任があるかもしれないという考えを強化するモテットを、ここで最後に引用したい。 RuttisのPrevalet simplicitas、BL 261、118もまた、Ox 305として現れている。この1セクションのモテットには多数のフラグ付きのsemiminimがあるが、Q 15とOxの筆記者はtempus imperfectum cum prolatio perfecta 帰属と記譜法の点で、15世紀初頭のより信頼できる写本の1つとしてQ 15が名高いにもかかわらず、筆記者は、やはり時代の人であった。 彼が生きていた時代は、音楽が周囲の状況に合うように仕立てられた時代であった。 おそらく、私が論じたいくつかの作品の中のtempus記譜法は本物のものであるが、そのいくつかが作曲家以外の誰かの貢献であることは疑いようがない。 それが筆記者であるのか、別の人物であるのか、私は言うことができない。 Tempusは、Ducalis sedeslStirps Mocinico(図11)のように作品全体であっても、Balsamus et munda(図3)のように短い部分だけであっても、声部において、prolatioに簡単に置き換えられる。 prolatioがtempus記譜に置き換えられていた期間(おそらくこれは10年から15年の期間を超えない)、混合メンスーラを使用するのはかなり論理的に思えたかもしれない。 ars subtiliorの厳しさとリズム的な複雑さの中で訓練されたならば、音楽家たちは、 pseudo-augmentationの理論的根拠に順応するのにほとんど問題はなかっただろう。 しかし、その記譜法を作曲家が書いたものの本物の複写として受け入れようとすれば、おそらく論理を少しだけ押し付けすぎることになる。 その中には、これまで考えられていたよりも「偽」に見えるものもある。 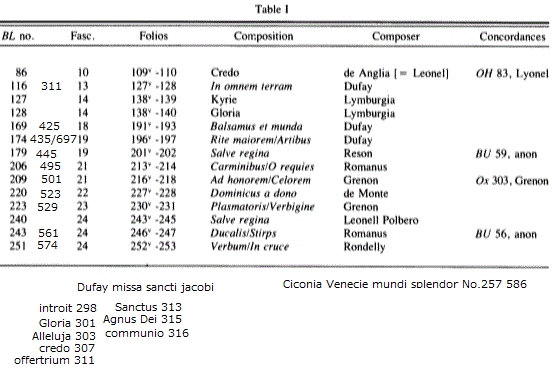 |