| Tonus Peregrinus: The History of a Psalm-tone and its use in Polyphonic
Music1 Lundberg, Mattias. Chapter 2 Historical Background of the Tonus Peregrinus in Monophonic Practice |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
Psalmus 113 (114+115)
| General definitions of psalmodic structure p7 西方教会の典礼におけるtonus peregrinusの使用を調べて議論するには、詩篇のいくつかの定義を確立する必要がある。 そのために、例として、通常の詩篇唱の1つと、その後、例として、tonus peregrinusのarchetypal form を使用する。 一般的な用語が決定された場合にのみ、tonus peregrinus の個別のバリアントの議論を開始できる。 これは主に典礼および理論的なソースから選ばれた特徴的な例を使用して行われ、次に同様の解釈を持つ他のソースを参照して行われる。 まさにその用語tonusは、modern mind.を混乱させる可能性がある。 この命名法の理由は、詩篇唱が通常、1つのrecitation noteで構成されるためである。 これはtonus peregrinusには当てはまらないため、別の詩篇唱Vがより典型的な例として役立つ(例2.1)。 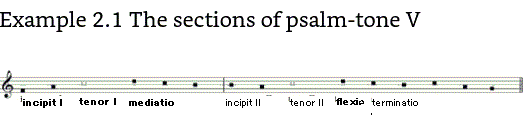 詩篇のテキストの大部分が引用されているピッチはcである。したがって、これはラテン語の理論ではtenor, dominant 、repercussa、と呼ばれ、ドイツ語ではtubaと呼ばれる。 詩篇唱の声明の中で、テノールは(この例では)2回発生している。例では、分割は、最初のsemi-verseと2番目のsemi-verseの間の小節線でマークされている。テノールは、装飾のいくつかの要素が追加されたモノトーンのdeclamation の名残を表している。 これらの最初の部分は、最初の semi-verseのテノールに至る2つの音符によって形成される。この形式は、initium、inchoatio、intonatio、またはincipitと呼ばれる。最初の朗唱はmediante, medium, mediatioまたはelevatioとしてまとめられ、次に小終止が続く。 2番目の朗唱は、同様に incipitから始まる。それは、mediatioよりも重要な構造的機能を持つ、finitioまたはfinalisの用語で終了する。1 最初のsemi-verse では、テノールはflexio (flectio) または flexaの影響を受ける可能性がある。すなわち短いinflectionであり,この例ではdのピッチで示されている。それは主に、より長い詩篇のverseに使用され、主に最初のsemi-verseに使用された。 p8 ここでは、最初の incipit、最初のtenor、flexa、mediatio、2番目のincipit、2番目のtenor、およびterminatioという用語が、同等のものではなく使用されている。その理由は、それらが音楽理論の歴史を通じて最も一般的に使用されている用語であるだけでなく、同じラテン語の用語の伝統に準拠しているため、しばしば一緒に見い出されるからである。用語は必ずしも、ここで提示されている文法的形式で示されているわけではない。 初期の詩篇唱理論では、それらは、能動または受動的で動詞としてよく使用されている。以下のようなステートメントは、しばしば記譜において詩篇唱を補足するものとして示される。Primus tonus sic incipit、et sic flectitur、et sic mediatur、atque sic finitur。「「私がこのように始める詩篇唱は、このようにinflectionされ、このように半分に分割されますが、このように終了します。」2 8つの通常の詩篇唱のそれぞれは、3つの異なる目的で使用される3つの異なる基本形式で示される。すなわち・・・ (1)詩篇、 (2)canticles -特に、Magnificat、Nunc dimittis(Lk。2:29–32)、Benedictus (Lk 1:68–79)とBenedicite– (3)introitus psalm verses。 さらに、Matinsのオープニングでは、invitatory, the singing of Psalm 94 (Venite exultemus Domino)を歌う特別なトーンがある。これらは通常3部形式であり、それらのいくつかは朗唱の変化を含んでいる。 典礼の聖務日課の詩篇では、通常のminores形式の詩篇唱が使用されたが、canticlesはしばしばpsalmi maioresと呼ばれ、よりメロディー的に精巧な(たまに旋律的にさえ異なる)異形に詠唱された.3 Introitus psalmody は、celebrant and the ministers が教会に入った後、祭壇に近づく時に、ミサにおいて始まる。それは通常、そのアンティフォンを伴う詩篇の断片にすぎない。また、ミサでintroitus psalmody に使用される詩篇唱の形式はより複雑だが、tonus peregrinus はこの目的には使用されないため、ここでは詳しく説明しない。 次の章では、聖務日課での詩篇とカンティクルの両方でのtonus peregrinusの使い方について説明したい。ここでは、tonus peregrinusがカンティクルで使用するように処方されている場合、他の8つの詩篇唱とは異なり、特別なmaioris形式はないことを説明するにとどめる。例2.2は、確立された用語に沿ったtonus peregrinusの原型である。 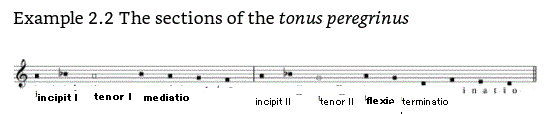 p9 同じ出典の中で、詩篇I〜VIIIには、 differentiae と呼ばれるterminatioの形のいくつかの異形の形式(しばしばvarietates あるいは divisionesとも呼ばれる)が供与されている。 これらは、詩篇唱とそのアンティフォンとの間に滑らかなつながりを生み出す機能を持っていた。この本の中心となる時代を通じて、主流的慣行は、詩篇唱で朗読された詩篇のテキストをアンティフォンで構成することであった。 さまざまなdifferentiae によって、歌手は、分類が難しい詩篇唱とアンティフォンから生じる不適切な音程の跳躍を回避できた。 tonus peregrinusは、ほぼすべて1つのタイプのアンティフォン的メロディーと関連していたため、differentiae の音域に対する根拠はなかった。代わりに、詩篇唱は常にdで終わる。 他の8つの詩篇唱とのtonus peregrinusのもう1つの大きな相違点–これは実際に最も顕著な特徴–は、2つのsemi-versesのそれぞれに異なるtenorがあることである。詩篇唱のこの珍しい特徴については、後で詳しく説明したい。 The forms and variants of the tonus peregrinus tonus peregrinus は、いくつかの点で他の詩篇唱より統一されていた。そうであっても、いくつかのソースは注目に値する差異を示し、時折、その逸脱は、その機能の理解に非常に顕著な違いを明らかにしている。 私たちの最初期のソースに先だって、チャントのメロディーは口承で伝えられ、おそらく現存しないソースからも伝えられた。民族音楽学からモデルを借りて、近年、初期の西洋音楽における口承の伝統に関する重要かつ画期的な研究が行われてきた。 この「新しい楽派」の学者らは、グレゴリオ聖歌の伝統が何百年もの間、表記なしで生き残ってきたという事実に注意を引いた。したがって、我々は「原型的な」チャントの形に関する結論に達することに注意が必要である。 Peter Jeffery は尋ねた。「我々が持っている最も古くに書かれたメロディーが、その modes and the neumesの導入前に「純粋な」口承の一部ではなかった改訂である可能性はあるのか?」4 1つの答えは、確かなことではないが、歌うことの頻度に基づくメロディーの伝達には、慣例の階層があるはずである、ということである。したがって、早期の詩篇唱の解釈は、付随するアンティフォンの解釈よりも信頼性が高く、詩篇I〜VIIIの解釈は、おそらく、 tonus peregrinusの解釈よりも信頼性が高くなければならない。こうした不整合で検証された仮説は、 tonus peregrinusの初期の発生で述べられた。a hypothesis that is validated by the inconsistency mentioned above in early occurrences of the tonus peregrinus. それでも、 tonus peregrinus はポリフォニーの自然な要素であった時期は、ほとんど変化がなかった。そして最も初期の表記は、実際、詩篇唱よりもアンチフォンに関してより詳細である(これは、詩篇唱に対して、より強く口承を支持している)。したがって、詩篇唱の異形の調査は、年代順ではなく地理学によって導かれるべきなのである。 tonus peregrinusの2つの主要なタイプがソースにある。1つはa-b♭-aで始まり、もう1つはa-c-aで始まる。後者は、北ヨーロッパでの優位性のために、ゲルマン方言として、前者はローマ方言として知られている。 p10 北ヨーロッパのソースにおけるゲルマン方言のincipitは著しく明確である。まれな反対の例が遠方の地域で見つかり、巡回学者によって「エリア外」でコピーされた可能性がある。 出典または作者の出所がわかっている場合、地中海、アルプス、イギリスの地域で Roman incipit が使用され、北部東部のすべての地域でGermanic incipit が広がっていたという基準にはほとんど例外がないことがわかる。 Jacobus of Liége (c.1260–after 1330)のSpeculum musicae は、ローマ、ゲルマン両方の方言の例を含む数少ない資料の1つである。5 <German dialect> Germanic incipit は、グレゴリオ聖歌の北ヨーロッパのソースにおいて、増大する音程への一般的な傾向の一面にすぎないようである。6 基本的なGermanic tonus peregrinus の公式には、いくつかのサブタイプがある。 最も一般的な形式では、最初のincipit にcがあり、2番目のincipitにaがある(例2.3を参照)。7 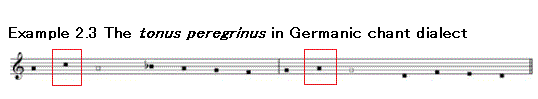 最初のsemi-verse のb♭のmediatioは、Roman incipitの名残を表す可能性がある。その場合、 Germanic intonation は、個別の伝統を表すのではなく、論理的にはローマの発展形になる。 もう1つのGermanic dialect は、両方のsemi-verses で同じincipitを持っている(例2.4)。 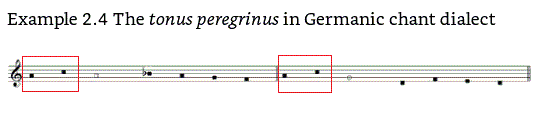 ちなみに、これは後にルター派典礼のマニフィカトの規範となった。 後述するように、それがterminatioにおいて2回、四度下降するという事実は、それを動機づけの発展の完全な手段にした。 これらの2つのバリアントに加えて、2番目のsemi-verse incipitのないバージョンもある(例2.5)。8 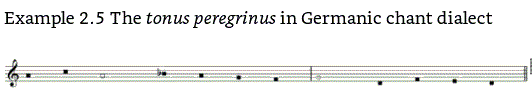 p11 <Roman dialect> ローマのtonus peregrinus dialect は、半音のincipitが特徴である。この形は、2番目の semi-verse でも繰り返される(例2.6)。9 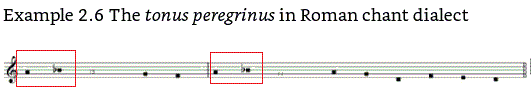 他の場合には、2番目のsemi-verse のincipitは、最初のtenorのrepercussionであり、旋法的な移調で最初のincipitを再現している(例2.7)。 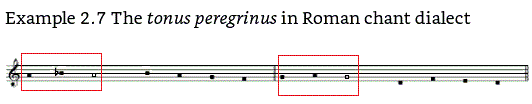 後者のバリアントは、おそらく semi-verses のより大きな旋法としての分離のために、ポリフォニック設定で従来型になった。これは、16世紀の作曲家にアピールしたようである。10 このようなバリアントでは、2番目のtenorに重点が置かれている。 、別々のsemi-versesの朗唱度合いについての曖昧さはない。ただし、2番目のsemi-verse とそのtenorが、不一致の可能性に関する議論の対象であった。 いくつかの初期のローマのヴァリアントは、実際にはtonus peregrinusが2つではなく1つの朗唱音符に基づいていたという考えを示している。 Commemoratio brevis(c.900)の作者は、詩篇の2番目のsemi-verse を、a上で朗唱している(例2.8)。 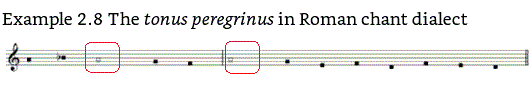 最初の千年紀の終わりに、このタイプの朗唱が実際にありふれたものだったとすれば、一部の理論家がtonus peregrinus を通常の詩篇唱のヴァリアントと見なしたことは驚くに値しない。11 しかし、本当のプロセスが逆であった可能性を排除することはできない。すなわち、tonus peregrinus が別の詩篇唱の単なるdifferentiaであるという考えは、Commemoratio brevis の著者に、通常のシステムに準拠するため、詩篇唱を変更するように導いた可能性がある。 p12 incipitの形に偏位が見られることがある。 最も一般的なものは、実際には最初のsemi-verseの別のバリアントではなく、むしろ、最初のincipitのinflectionした言い直しで(a-g-a)あり、tonus peregrinus を2つではなく3つに分割している(例2.9)。 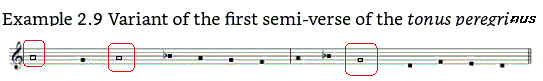 Hieronymus of Moravia は詩篇113番第15節に、3分割構成のヴァリアントを見出している。 Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt, non clamabunt in gutture suo: ‘They have hands but cannot grasp, they have feet but cannot walk, they cannot cry from their throats.’12 理論家がこのverseに詩篇の最初の詩の一般的なRoman variant に加えて三部構成のtonus peregrinusパターンを与えるという事実は、 flexaによって最初のテノールを、2つのセクションに分割する確立された慣行を示唆している。 例2.11.に示されているように、通常のMediatio形のないバリアントも見受けられる。 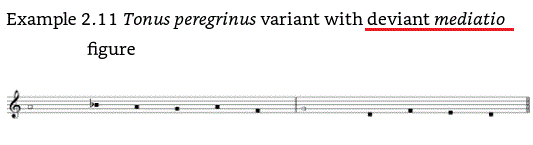 IncipitもFlexaもないバージョンは、イベリアのソースで主流となっている。 Diego del Puertoの Portus musice、, Juan Bermudoの El libro llamado declaración de instrumentos musicales, the Intonarium Toletanum and the Breve instruc[c]ión de canto llano、すべてのバリエーションは、明白な3つの音符の冒頭のsemi-verseで構成されている(例2.13)。 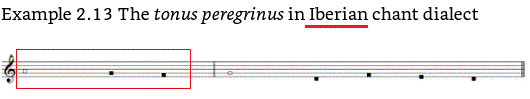 p13 その後、Escuela musica según la práctica moderna (1724) of Pablo Nassarre (c.1655–c.1730) and the Arte de canto-llano (1778) of Ignacio Ramoneda (c.1730–1781), などのスペインのソースは続いて、 この慣習を支持している。 後の章で見るように、このバリエーションはヨーロッパのこの特定の地域のポリフォニーにも採用された。 このフォームは「イベリアバリアント」と呼ばれている。 2番目のincipitは、例2.10のように供与される稀なものである。通常のflexaのようなincipitを置き換えるdは、より一般的なtonus peregrinusバリアントからの最も広範囲にわたる偏位を示している。 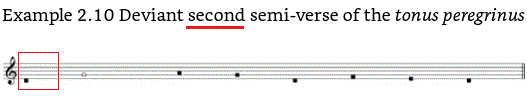 このバージョンは、その冒頭に関連して、例2.4のバージョンと同様に詩篇調の終了に関連していると想定する必要がある。dは構造的に terminatio 形までたどることができる。なぜなら、通常の詩篇唱見られるflexaの変異の豊富さは、しばしばそれらの基本的な形の特徴に関連しているからである。 この特殊なincipitの変異は、ポリフォニック設定ではほとんど見られない。 Nicolaus Capuanus(fl。c.1415)は、2番目のテノールに、f–g–a形を介して到達する第2のincipitを持つ版を供与している。15 同様に、これは構造的にすでに詩篇唱(mediatio)のピッチに関連しているが、このincipitの結果は、Ladislaus of Zalka (15世紀後半)の結果とはかなり異なっている。これは、最初のincipit から2番目のテノールへのconjunct 遷移を生成するためである。 p14 英国の島々でのセイラム典礼での使用で特に一般的なもう1つの別の第2semi-verseは、terminatio公式にfを含んでいる(例2.12)。16 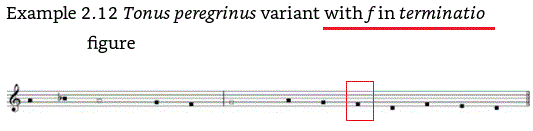 この音符は、他の場所では第2semi-verseにおいて四度下降するその線形特性の多くを導出する詩篇唱の輪郭を弱めている。 Commemoratio brevisでのterminatioは、さらなる代案を導入している。(例2.8)。そこにあるeは、tonus peregrinus の形状を大幅に変更しているだけでなく、第2semi-verseに、西方の詩編では典型的でない構成を供与している。 訓練を受けていない歌手が、詩篇の詩の最後の音節をこの非常に長いterminatioに合わせるのは困難だったに違いない。 我々はこれで、典礼と理論のテキストだけでなく、初期のポリフォニーのレパートリーで最も頻繁に発生するtonus peregrinusのバリアントについても説明した。これらの例から明らかなように、tonus peregrinusのほとんどの主要な変化は、第1semi-verseで起こっている。 さまざまなdifferentiaeに関しては、これらは、詩篇唱I〜VIIIに通常採用されているものほど浩瀚ではない。この事実は、tonus peregrinus と規則的に関連したアンティフォンの統一性が、 differentiae を不必要にしたことを示しているのかもしれない。 実際、differentiaという用語は、別々のtonus peregrinus エンディングの研究では、誤解を招くものとなっている。これは、これらの構造における通常のterminatio d–f–e–dから逸脱することはめったになく、他の詩篇唱のdifferentiaeと同じ種類の機能を果たしていないためである。これは確かに、詩篇唱が累計的には非常に限られたアンティフォンのレパートリーで使用されていたという事実によるものであった。 Other recitation formulas with more than one reciting note tonus peregrinus は、複数の朗唱ピッチを構成する唯一の朗唱公式ではなかった。たとえそれが、毎日の典礼におけるシングルピッチの朗唱の正常性からの最も一般的で広範な逸脱であったとしても。 tonus peregrinus 以外の場合では、単一音程からの逸脱はresponsorial psalmody,で最も頻繁に見られた。主たる歌手は、別の歌手で歌われたversesに応唱し、あるいは、詩篇やcanticles以外のテキストで応唱した。 これらの他の朗唱公式が、tonus peregrinus のように、詩篇の応唱的歌唱に使用されなかった理由を説明する私たちの試みでは、仮説に頼らなければならない。 最も明白なのは、詩篇および他の二部形式のparallelismus membrorum (テキストの複合構造と補完的追加、またはあまり一般的ではないが、テーゼとアンチテーゼ)を表現する場合に、すなわち、相互言い換えとして機能する2つの類似したsemi-versesのバランスが、朗唱ピッチの変更によって乱された時に、おそらく2つの音程のコントラストが望ましくなかった可能性があることである。 p15 初期の音楽理論では、単一音程から逸脱した詩篇唱がグループとして議論されることが多く、2人のフランク人作家が、(単一音程から逸脱した詩篇唱が)応唱の歌唱には不適切である可能性がある問題に対応した。 一人は、non finiuntur ita ut inchoant: ‘ 誰もが始めたように終了しない'と主張し、もうひとりは quia per omnia ab orbita in sui canore versiculi segregatur, huiusce toni,「この詩篇唱は、すべての詩篇の歌唱の共通の流れから semi-verse で区切られているため、他の詩篇から除外された。」と主張した。17 この仮説は、主に既存の、問題のあるアンティフォンのおかげで、tonus peregrinus が詩篇においてその地位を得たという初期の示唆に間接的に依存している。これは、第7章でさらに説明されている。補足的な仮説では、複数の朗唱音程が主に応唱的詩篇で発生した理由は、主に,説教的なのではなく、伝統的な音楽慣習に関係しているためとされている。 「呼びかけ」と「応答」の対比は、西方キリスト教世界の初期に広く培われ、その後、応唱的な詩篇の遺物として生き残った可能性がある。18 nothaeからはおそらく区別された、または8つの通常の詩篇に関連して逸脱した2つの朗唱音程を持つ1つの詩篇公式は、Sarum典礼での詩編113 (In exitu Israel)のメロディーである。以下で説明するように、この詩篇は特にtonus peregrinusに関連付けられていた。 したがって、典礼の文脈だけでなく、tonus peregrinusについておそらく何かを教えてくれる可能性があるので、詩編113 (In exitu Israel)の代替の公式も参照する必要がある。 例2.8と2.9のtonus peregrinusバリアントと同様に、この公式は、一見すると、tripartiteに見える。 3番目のフレーズはAlleluiaで、このメロディが復活日と次の週の特別な機能を担っている。 これは、ここではアンティフォンの代わりに機能し、各verseの後に追加されているという事実は古さを示唆している。すなわちおそらく古い応唱詩篇との関係(各verseは詩篇唱のように応唱的に扱われていたが)である。 Sarum use Directorium sacerdotum(1487)とProcessionale(1502)が出版された頃には、詩篇の各verse後のアンティフォンを繰り返す慣習が、少なくとも数百年にわたって一般的であった。21 このメロディーは英国のソースだけでなく、西フランスに由来するものにも見られる。Guy Oury は、このメロディーとそれに基づく詩編全体がフランスで生まれ、その後ノルマンディーを経由してイギリス諸島に広まったと示唆している22。 我々は、詩篇で使用された複数の朗唱を持ついくつかの旋律パターンを見てきた。ミサの文脈の中で、さらに、複数の朗唱を持つその他のいくつかの旋律パターンがあり、これはtonus peregrinus や invitatory psalm-tones とは異なり、詩篇とカンティクル以外のテキストに使用されていた。 これらのうち最もよく知られているのは、おそらくPrefatio(Sanctusの直前にある聖体拝領の祈りの最初の部分)の一般的なトーンの1つである。23 p16 このような朗唱公式の性質と機能は、ここではその変化がテキスト解釈のpunctuationを表現することを目的としているため、 tonus peregrinus とはかなり異なることに注意することが大事である。 したがって、これらのチャントとtonus peregrinus は、音楽の発達や典礼の実践に関してほとんど共通点がなく、ここではtonus peregrinus が西方教会の典礼において音楽的に異例であったことを示すためにのみ言及されている。 Falconer はtonus peregrinusがしばしば8つの詩篇の1つのdifferentiaとして分類されたので、 それらがMozarabic やAmbrosian典礼のカデンツパターンに似ているために、これらの詩篇唱の他のdifferentiaeは、同じように元々不規則な詩篇唱に属していた可能性があることを取り上げた。.24 Ruth Steinerは、同様に、その一部は不規則であり(特に彼女が「トーンS」と呼ぶ詩篇唱)、 tonus peregrinusを想起させるシングルピッチから逸脱した詩篇唱に注目している。そしてAtkinson は、詩篇唱I〜VIIIと似た起源を持つと彼が信じているparapteresのために、4つの詩篇唱をカタログ化した。ただし、これらは厳密にinvitatory tones のままであり、1200年以降もそうであるようには見えない。 The liturgical context of the tonus peregrinus 西洋のポリフォニーが登場する前のtonus peregrinusの名前、記述、典礼機能は、その起源の歴史学と同様に、他の場所で取り上げられている(19世紀と20世紀の学者の間で大きな意見の相違があった問題) )25 p17 ここで言うことは、用語tonus peregrinusの起源は不明瞭であるということだけで十分である。それが詩篇唱の音楽的固有性( (a ‘wandering’ or ‘migrant’ character), )に関係し、詩篇113のテキストに関係し、特別な復活日の晩課の行列で使用と関係していたことを示唆して。 tonus peregrinusのポリフォニック設定と西洋音楽理論におけるその役割を説明する前に、その典礼機能の簡単な説明が役立つであろう。 すでに何度か言及されているtonus peregrinusの最も一般的な適用は、詩篇113への使用である。これは、最も一般的であるだけでなく、その機能の中で最も古いものでもある。 問題のこの詩篇113は主日の晩課にふさわしいものであり、この文脈において、本書に記載されている音楽の多くが演奏されている。それはほとんど独占的にメロディ族のアンティフォンと結びついていて、最も一般的なのは、詩篇113のverseから由来するNos qui vivimusである。 この詩篇唱の次に多い使用は、ドイツ語のMagnificat(Meine Seele erhebt den Herren)で、ルター派の典礼の伝統に特異的なものである。これは、詩篇67篇にあるように、 感謝の祈りBenedictionに対する会衆の反応としてのtonus peregrinusの適用にも当てはまる。 詩篇113篇、晩課、ドイツ語のMagnificatといった3つの典礼機能と同様に、我々がtonus peregrinusを基礎にしたポリフォニー作品を論じるような、より一般的ではない数多くの使用を思い浮かべる。 |