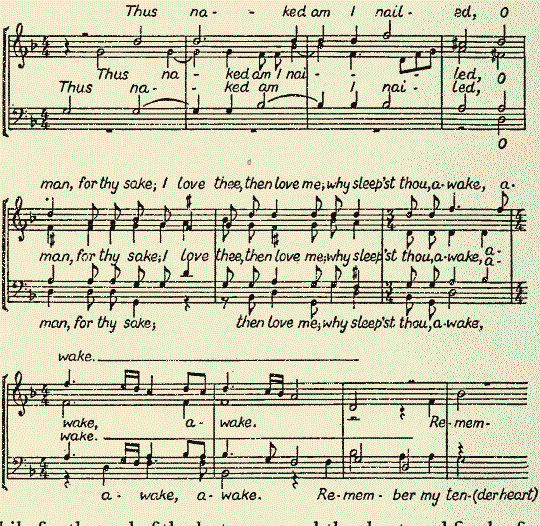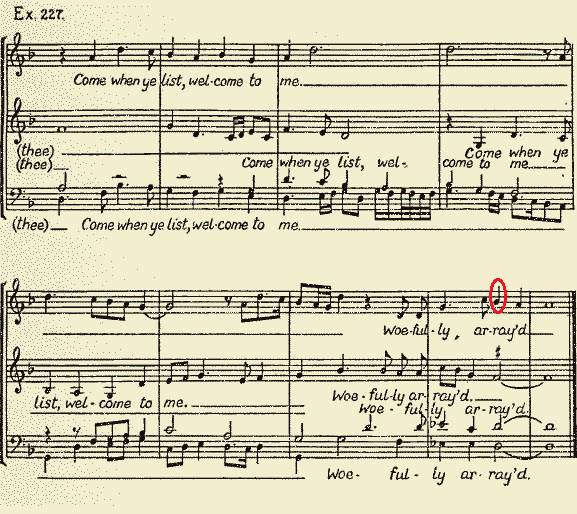| MUSIC IN MEDIEVAL BRITAIN 11 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | まうかめ堂さんのページへ |
| 初期多声音楽 | |
| St.マーシャル楽派へ | |
| ペロタン(Viderunt Omnes) | MUSIC in THE MDIEVAL BRITAIN10へ戻る |
| 中世音楽のページへ |
| VII OTHER RITUAL FORMS; THE CAROL Apostles' Creed and Lord's Prayer Eton_Choirbook Lambeth_Choirbook Gyffard partbooks Fayrfax Manuscript p413 ここに加えられた儀式項目の2つの独自のポリフォニー設定には、Robert Wylkynsonによる使徒信経がある。それは、 Eton choirbookの最後のページにある。そしてGyffard part-booksには、Philip van Wilder の主の祈りがある。後者は、1554年にアントワープで出版された Tylman Susato's fourth book of Ecclesiasticae Cantiones quatuor vocumにも印刷してある。それは、3つのtrebleとテノールのための模倣様式の設定である。それは、Pater nosterのチャントは使用していない。 Wylkynsonの作品は、実際、興味深い。使徒信経は、聖歌隊が出席した時には、終課で毎日唱えられており、そしてこの設定は、レントの終課のために書かれた。なぜならそれは、Lentの第1週の月曜日のマニフィカトへのアンティフォンであるJesus autem transiensの第1フレーズからなるcantus firmusに基づいている。 p414 チャントのこのフレーズに対しては、Credo in Deumのテキストとともに、rotaのやり方で連続して12のパートが追加され、各セクションには、伝統的にそれを供給したと言われた使徒の名前が記されていた。 歌われるときの効果は、Jesus autem transiens というフレーズが真に「中を通って」通過し、最後に残る(例219参照)。 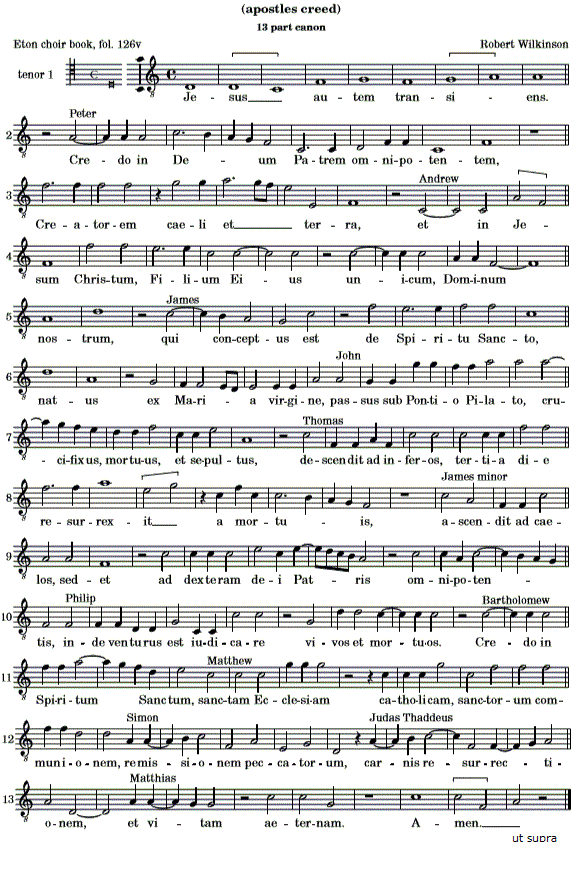 Canon for 13 voices: "Jesus autem transiens, Credo in Deum" (Robert Wylkynson, 15th century) Benedicamus Benedicamusの多声の設定は中世後期では珍しいものであった。1例を除いてすべてはPepys manuscriptに19例存在し、William Hawte Knyghtの2作とJ. Nesbetによる1作を除けば、作者不詳である。 いくつかの作品においては、上声部はBenedicamus chantsを使っている。この時代はカノンは稀な技法であり、そうした設定の1つは、大陸の「トランペット」パートの慣用句で書かれ,その後はオルガンポイントとなるテノールの上に2つのカノンがあるものである1。 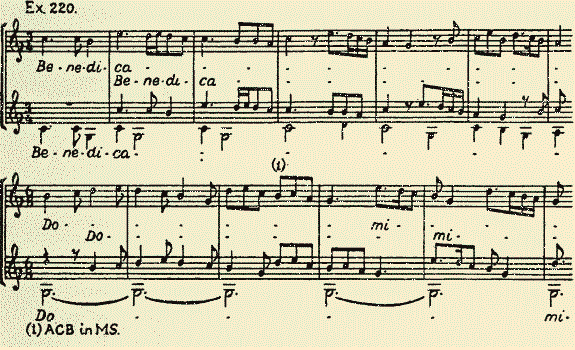 Hawteの作のひとつは、三つ組の偽カノンの形をとる (see Ex. 221) 2。 Nesbetのそれは、 Easter AlleluiaとともにBenedicamusのin perenni のメロディを扱っている。cantus-firmus様式の冒頭と自由な装飾のパッセージを伴う終止を持つ3 (see Ex. 222) 。 1 Cambridge, Magdalene College, Pepys MS. 1236, fos. 124.V-125. 2 Ibid., fo. 127. 3 Ibid., fo. 126V. 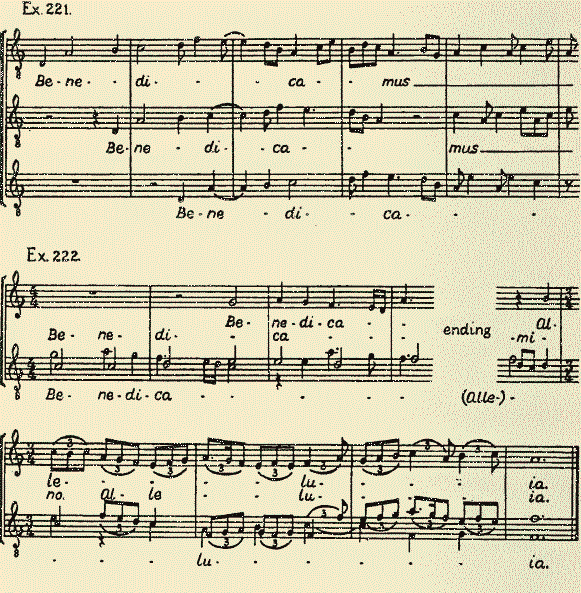 p416 Carol 13世紀と14世紀の礼拝規定書の時代の後、Benedicamus substitute の使用に関する直接の情報はない。 14世紀後半の conductus の消滅と同時の随意アンティフォンの登場は、Benedicamusの祝祭用代替としてのconductusの代わりをしたことを示唆しているかもしれないが、 institutions の実践とantiphonsのテキストの性質は、これが随意antiphonの主な機能ではなかったことを明らかにしている。 一方、conductusが使われなくなった時代に現れた分野である、ポリフォニーキャロルの言葉は、15世紀の神聖なキャロルが、conductusから、Benedicamus substitute の役割を引き継いだようにしている。 キャロルは「いくつかの主題を持ち、統一されたスタンザで作曲され、burdenを与えられた歌」として定義されていたが、burdenは各verseの始めと終わりに歌われた。いくつかのケースでは、verseは繰り返される行で終わり,自己完結的な burdenとは区別されたルフランを要求する。 |