| Peter Urquhart CROSS-RELATIONS BY FRANCO-FLEMISH COMPOSERS AFTER JOSQUIN 1 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
| p4 I. THE OPENING OF ERGONE CONTICUIT これらのリマークに焦点を当てるために、冒頭でcross-relationを示唆しているように見える作品を考えてみたい。唯一のソースでJohannes Lupi ヨに帰せられたモテットErgone conticuitは、四度の跳躍を組み込んだ冒頭動機を使用している。 (例1)6  答声部、カウンターテノール、バスでは、動機のピッチレベルでは、第5,13小節で、四度の跳躍において、E♭が要求される。 どちらの声部でも、線形の観点から、最初のEをfaとして歌う(E♭とする、B♭上のヘクサコード)必要性に疑いの余地はほとんどない。和声的内容もまた、第5、13小節において、この解釈をサポートする。 バスでは、E♭の使用は、明示的な臨時記号の存在によって確認される。これは、絶対に必要というわけではないが、役立つ記号である。 パッセージの難しさが明らかになるのは、これらの答声部の2番目と3番目のE(コントラテノール第7、8小節)である。メロディの流れの観点からは、EのinflectionをE ただし、和声の観点からは、カウンターテノールとバスででのE♭の使用から、強いcross-relationが発生する。それは編纂者が取り除くのに大変な努力を要するものである。 第8小節において、コントラテノールのE♭は、superiusのE♭に直接隣接することとなる。superius Eはフラットになる可能性があるが、その解決策はさらに問題を引き起こす。 メロディの流れの観点からは、E♭はsuperiusでは歓迎されず、E p7 したがって、編集者はおそらく、第7小節に戻り、コントラテノールのE♭をE バスでも同様の問題が発生する。 バスのE♭がメロディの流れへの理由で許容されるか、あるいは、テノールとの cross-relationにもかかわらず、第15,6、小節でバスのE♭がE その選択は明らかに、問題のないハーモニーを伴う面倒なメロディの流れか、単純なメロディの流れを持つ不自然な和声との間を揺れ動く。 これら2つの可能性のどちらかを選択するためのコンテキストは、Ergone conticuitと本質的に同じ冒頭を持つニコラ・ゴンベールによるいくつかのモテットを検討することで、供給される。 例2は、これらの冒頭の驚くほど類似した性質を示している。さらに、ほとんどの場合、動機はピッチレベルで配置され、まったく同じ音程内容を示している。 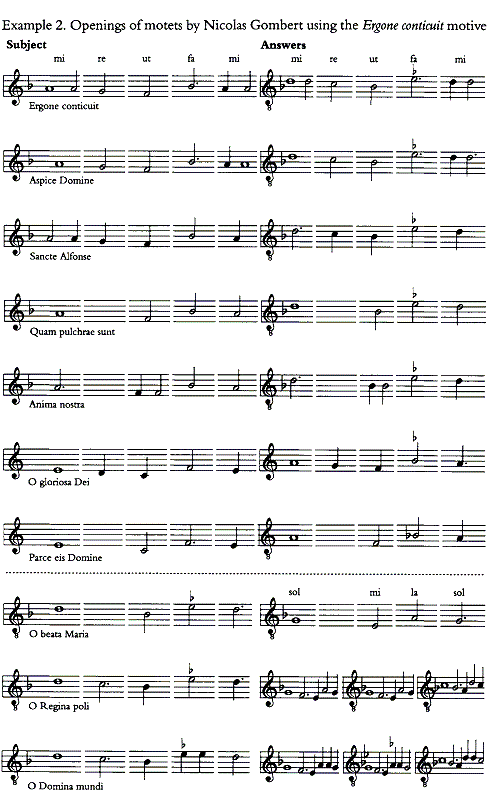 p8 例2でリスト化された7つのモテットにおいて、主題と応答の両方の動機はすべて mi re ut fa mi, あるいは la sol fa fa laのバリエーションであり、ソルミゼーションは、1つのヘキサコードが使われるか、あるいは、トップの音に対するfictaの拡大(fa super la)を伴ったヘクサコードかに拠っている。 いずれにせよ、主題と応答のピッチ内容、特にfaとなるトップピッチのinflectionは同じままに残されている。もちろん、Ergone conticuitの和声の複雑さの原因となるのはその上部のfaピッチであり、これと同じ和声感は、リストされているすべてのGombertのモテットに見られる。 例3は、Aspice Domineの冒頭である。ここでは、同じソルミゼーションが「Ergoneの動機」の主題と応答の形式に適用されている。 この作品では、cross-relationの問題はない。Gombertが、直接の競合を回避するために、結果的にE♭とE 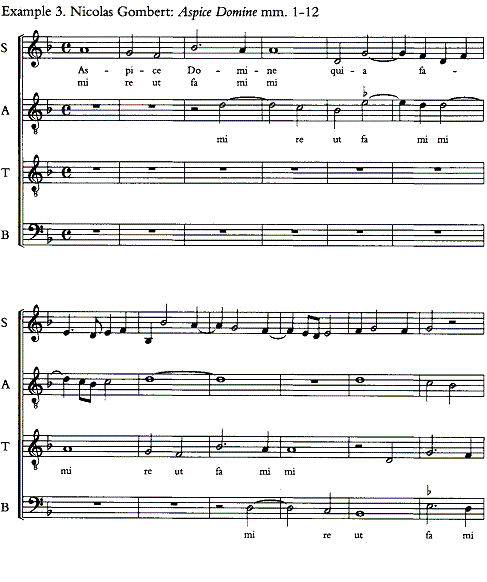 p9 Ergoneの動機を持つ別のゴンベールのモテットの例は、♭記号を持たない O gloriosa Deigenitrix (Example 4)である。その動機は、調号で暗示された全音階外の♭の使用と、主題の同じソルミゼーションを要求し、そのように応答しているが、ゴンベールは、動機のトップピッチが要因となる mi/fa のクラッシュを避けることには、ほとんど考慮していない。♭faと 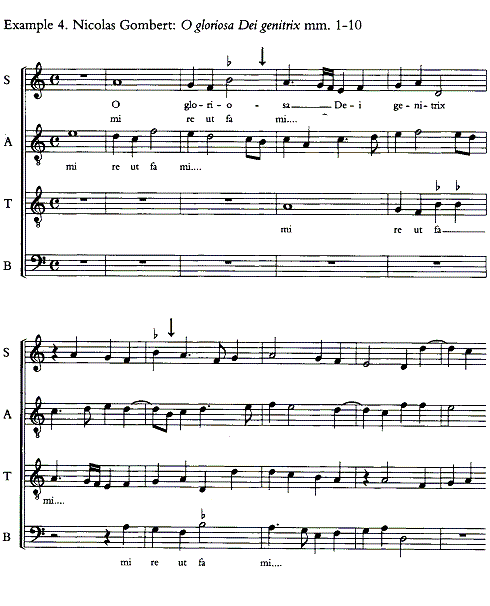 例2のモテット類の冒頭動機の間の類似性は注目すべきであり、すべての主題は移調されて同じピッチにあることは興味深く、そのために、主題と応答におけるBとEfaとmiの形成の間の和声的緊張が、ほとんどすべての場合に調査される。 ゴンベールが動機を他のピッチレベルに置いていたら、この緊張は存在しなかったであろうし、同じソルミゼーションが必ずしも主題と応答の両方に適用されなかったであろう。 p10 ピッチレベルは、動機の旋律的輪郭(特に四度の跳躍)がB♭またはFの柔らかいヘキサコードでのfaの使用を強制するように選択されたように見える。 柔らかいヘキサコードでのfaの使用を示唆する別の動機は、16世紀後半のjingle 'una nota super la、semper est canendum fa’.として示唆された、自然なヘキサコードでlaの上に隣接するものを使用することであったろう。9 Gombert は、この上部の隣接する音符の特徴を備え、Ergoneの冒頭動機と非常によく似た冒頭動機を利用している(例5)。10 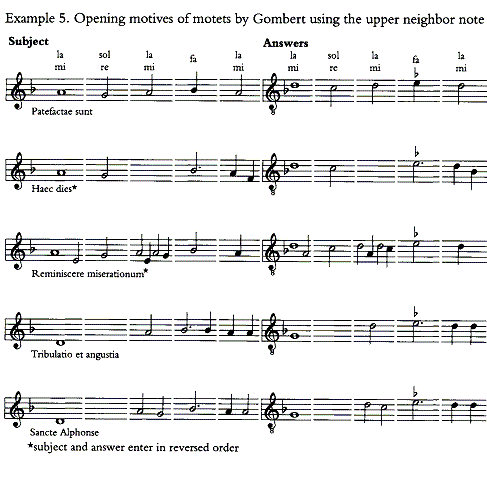 例5のこれらの5つのモテットの冒頭では、F-hexachordのmi fa mi、またはC-hexachordとF-hexachordの両方のla fa la(∵fa super la)が、五度(または四度上)の間隔で同じソルミゼーションによって応答されている。時には、 Patefactae suntに見られるようなE♭ / E 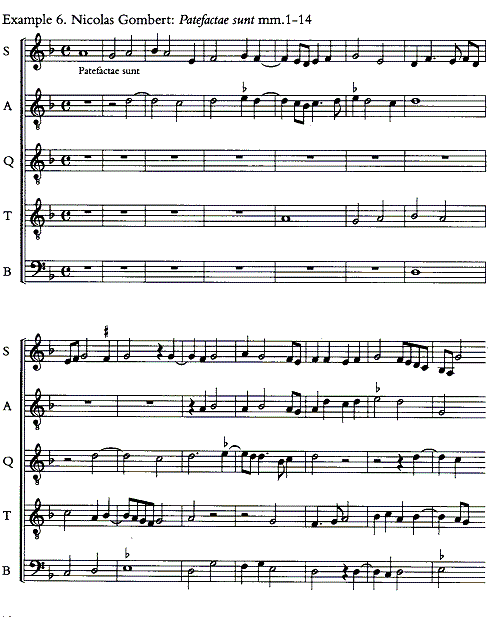 p11 例2の点線より下部にリスト化されているErgone動機を使用する3つのモテットは、他のモテットのソルミゼーションの可能性についての一般化に挑戦しているように見える。 3つすべてが全音階の模倣を使用している。つまり、調号によって暗示される全音階のコレクション内にとどまっているものとして、模倣は音程のナンバーに関しては正確だが、性質は正確ではない。 3つのモテットには、明らかな臨時記号のないE♭を必要とする冒頭主題がある。対照的に、点線より上部にある7つのモテットは、応答に表記されていない臨時記号(B♭)のみを使用している。 O Reginapoliと0 Domina mundiの冒頭は、特に標準とは異なるように見える。冒頭は通常よりもやや洗練されており、入りは2つではなく3つのピッチレベルになっている。さらに、O Domina mundiは、模倣パターンがさらに複雑化する partial signatureを持っている。 しかし、ソースを調査したところ、両方のモテットが並行した例外的なケースであることが判明した。これは、我々が以前見た冒頭での模倣の正確な音程内容に対する同じ詳細な懸念を示している。 O Regina poli(例7)は、DとG上でのaltus と superius の入りと、五度下のGとCに移調された bass and tenorの入りで構成されている。 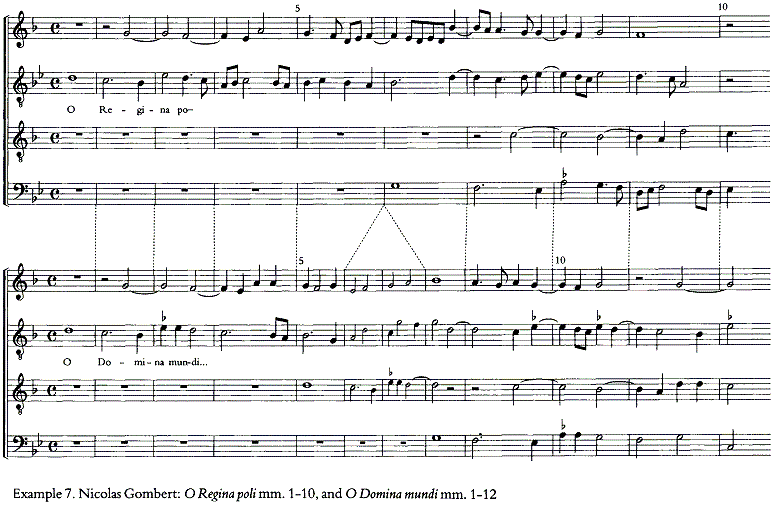 superiusとaltus、tenor とbass iの間の模倣は確実に全音階であり、2組の声部は正確である-ソルミゼーションに関しては、superius = tenorとaltus = bass- の驚くべき結果として、G上のsuperiusの入りとG上のバスの入りは大きく異なることとなる。 O Regina poliの冒頭のこの解釈は、Opera Omnia版でも、Scotto(1539)またはGardane(1541)の版でも明らかではない。 ただし、以前の出版物(Moderne、153210)が存在し、{♭2♭、♭、2♭}のa partial signatureが生じ、 C, F, B♭, E♭上の4つの異なるヘキサコードの通常ではない使用が可能になる。 ScottoとGardaneによる後の版で見つかった一貫した1♭調号は、誤解を招く単純化であることが判明したのである。11 <正確な模倣と全音階的な模倣> O Regina poliの冒頭に関するこの説明は、O Domina mundiのほぼ同一な冒頭計画によって確認されている。その作品は、ScottoとGardaneの版に続いてOpera Omniaに登場している。そこでは、[♭♭♭2♭]となっている。 ここでも冒頭は、全音階の模倣における一対の声部として解釈されることだろう。そこでは、五度下で正確に模倣されている(例7下段)。 ここでの第5小節の(O Regina poliにはない余計な)テノールの入りは、より複雑化させるが、O Regina poliとの比較での、この作品でのテノール声部の入りは、第9小節で生じている。そこでは、バス声部を(正確にではなく)全音階的に模倣している。 O Regina poliにおけるように、 O Domina mundiのtenor/bassの入りは、superius / altusの入り五度下を正確に模倣している。12 O Regina poliとO Domina mundiの冒頭における全音的に模倣されたペアの正確な模倣は、前に検討した正確に模倣された冒頭に見られるよりも単純な全音階ピッチのパレットを使用することにはならない。実際には、反対が正しい。 これらの2つのモテットで、ゴンベールは半音階的対斜関係の使用を極端に拡大し、E♭をE p13 それでも、2つの冒頭の終わりで発生するわずかなクラッシュを除いて、同時の対斜は、両作品を通して、慎重に回避されている。後で見るように、これらのわずかな和声のクラッシュの位置でさえ、意図的であった可能性が高い13。 作曲家がモテットの冒頭で正確な模倣を使用する傾向は、当時の理論家によって言及されていた。 特にZarlino(1558)は明確な説明を提供しており、正確な模倣のことを彼はfugaと呼び、対照的に、全音階の模倣模倣のことを、imitatinoneと呼んだ。音程のナンバーは同じままだが、性質は異なっていた。14 Zarlinoの用語は、モテットの冒頭の自由な模倣同様、canonsにも言及している。 legata (strict) と sciolta (free) は、fuga と imitationに相当している。 Aaron (1516 and 1545), Ramos (1482), Tinctoris (1475),らによるより早期の論文においては、fugaは、ソルミゼーションの用語において論じられた。fugaであるためには、同一のソルミゼーションが必要で、 canonic (legata) あるいは単に fugal opening (sciolta)と呼ばれた。15 Zarlinoの時代(1517年 - 1590年)までには、四度、あるいは五度のfugaの例は皆無だったが、代わりに、不完全音程でのimitationeとinversion canonsがあった。 Zarlinoの定義はまた、fugaと結びついていたソルミゼーション言語は不要となっていた。それはおそらく、彼の時代には、ソルミゼーションが、三つのヘクサコードをもはや均等には扱わなくなったためである。 Tinctorisたちによって記述された15世紀の3つのヘクサコードソルミゼーションのもとで、四度、五度として拡張されたfugaは、同じソルミゼーションを使うことを可能にした。2つのヘクサコードシステムのもとでは、もはや異なった調号の使用は、this was no longer true without the use of different signatures. ゴンベールが彼の作品に対して特殊なソルミゼーションを考えたことは確かではなく、彼が3つのヘクサコードソルミゼーションをさらに使っていたことも考えられ得る。彼のモテットは一般的に、冒頭での正確な模倣を好んでいる。それらは、3つのヘクサコードを使うことによってのみ初めて、同一のソルミゼーションが可能となったのである。 Gombertの同時代人によるモテットの冒頭では、正確な模倣の傾向は著しく異なる。 Adrian Willaert やJachet da Mantuaは、正確な模倣の維持には関心を示さなかった。;実際の模倣によるモテットの冒頭の約半分は正確な模倣であり、半分は全音階的模倣である。 一方、Gombert,は、4声、5声の彼のモテットで、約3対の1比率で全音階的模倣よりも正確な模倣を採っていた。Pierre de Manchicourt は、彼の4声のモテットにおいて、正確な模倣をする傾向がさらに強いことを示している。 表1では、1539年の5つのコレクションで出版された4声のモテットの冒頭のタイプを比較している。最初の印刷されたモテットコレクションは、単一の作曲家のものである。16 Willaert とJachetは、全音階的模倣を正確な模倣と同様に採っており、GombertまたはManchicourtのどちらよりも多くの音の模倣と非フーガの冒頭を書いている。17 17 少なくとも3つのピッチで模倣が維持されていない模倣エントリは、フーガ以外の冒頭部としてグループ化されている。ほとんどのフーガの冒頭部は約5〜7回模倣する。バロック時代のフーガの標準的な用語は、これらのフーガの冒頭部の記述として使われた。 調性的な模倣では、interval numberは、バロック期のフーガのように、通常はfinalとconfinalを強調することによって、旋法の特徴的な種の輪郭を描くように調整されていた。 実際の模倣では、 interval number は厳密に維持される。実際の模倣は、正確性と全音階性の2つのカテゴリに分類できる。上記のように、正確な模倣は正確な音程を維持するが、全音階的な模倣は、一般的に、調号で決められたピッチの全音階コレクション内にとどまるように、音程の性質を調整している。 明らかに、16世紀における「調号」の正確な意味合いとアクセス可能なピッチのパレットとの関係は基本的な疑問が残されている。 北フランドル楽派の作曲家ゴンベールとイタリア的フランドル楽派の Willaert やJachetとの間のフーガ様式の違いは、、彼らが使ったソルミゼーションの違いに関係していると思われる。 p14 Johannes Lupi がこの提案された二分法のどこに当てはまるかは定かではない。 Lupiのモテットのほとんどは、ゴンベールのモテットに見られる程度の正確なソルミゼーションをサポートしていないようである。ただし、Ergoneの動機または upper neighbor note motiveを使用する作品は例外で、すべて正確な模倣を受け入れている。18 ほとんどの冒頭部では、対位法によって自動的に作成されるようなmi / faの衝突を回避するための注意がなされている。 Sancta Dei genitrixの冒頭(例8)はあまり注意を要しない。編集者のボニー・ブラックバーンは、第5小節でのニアミスは許容されようが、第10小節のバスでの平行パッセージに必要なE♭を追加することは控えている。結果として生じるsuperiusとの同時衝突を避けるために。  例2や例5で概説されている関連する模倣冒頭部に関連する内容で、上記で説明したように、Ergone conticuitの対斜が豊富な解決は、もはやとても奇妙には見えない。 ある種の作曲家たちは、おそらく、四度や五度のfugaeのために同じソルミゼーションを使用することに関連して、正確な模倣に関心を示している。 これらの音程での正確な模倣では、使用する調号に応じて、 B♭と B Ergone conticuitでの模倣は、どのようにそのような対斜が発展したかのいくらか拡張された例の、典型的なものである。確かに、例2のすべてのモテットに見られるような動機とピッチレベルのまさにその形式は、対斜の発展の目的のために設計されているようである。 これらの観察を考えると、「musica ficta」の土壌における対斜を修正または回避する現代の編集者の傾向は、メロディの一貫性を損なうだけでなく、対位法の意図された和声目的をあいまいにすることになる。 |