| Manuscript Accidentals:Ficta in Focus 1350-1450 Andrew Hughes その1 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 次ページへ |
その前
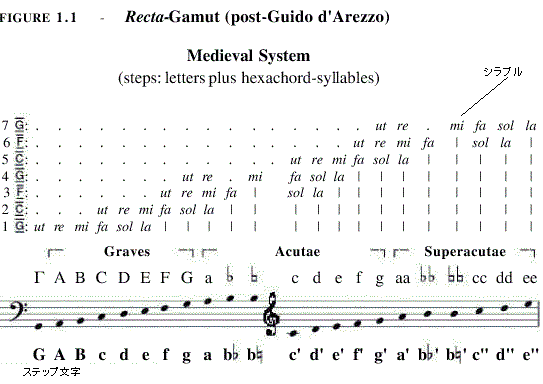 中世の演奏のための写本は、musica fictaについて理論家が言うことと音楽内容とを一致させるために必要な臨時記号を完全に備えていることは、ほとんどない。 演奏に関係のない仮定的な技法のみに言及していたという論文等の思考は、理論家の必要要件を除いて、拒否する必要がある。なぜなら、写本自体に、満足できる結果を得るために必要なすべての臨時記号がほとんどつけられていないためである。 したがって、通常は、さらなる半音が付け加えられなければならない。参考文献に記載されている項目で、どんな臨時記号が、どこでつけられなければならないかという問題が注目されている。 p19 9 Semitones. Ugolinoによって使われた中世の標準的な調律においては、音は、広い半音と狭い半音という、不均等な音程で分割されていた。すなわち狭い半音は、miとfa、eとf, b 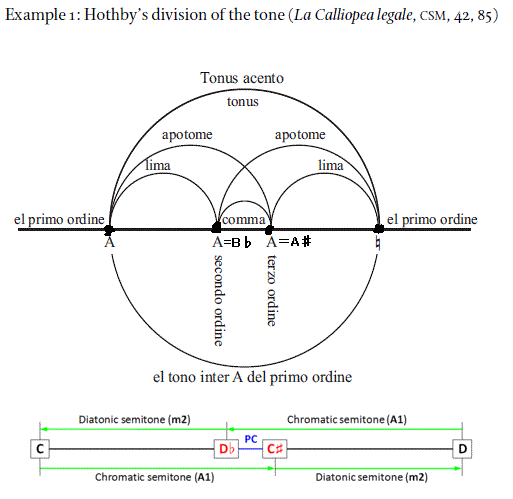 A1=augmented unison m2=minor second apotome=major semitone limma=minor semitone Perfection. 音程は、広い半音の追加によってのみ、完全となる。それゆえ、不完全五度は、上の音を♯化するか、下の音を♭化することで完全化される。 この変化は、musica fictaの第一の要求であり、目的である。すなわち、協和音は、完全でなければならない。音響的にも美的にも哲学的にも。 Coloration. 哲学的には、完全協和音のすぐ前の音程は、可能な限り、ほとんど完全でなければならない。したがって、必要に応じてそれらを半音で拡大または縮小することにより、それらは、当時の語彙が許す限り、音楽的に完全協和音に近づける必要がある。 こうした過程は、完全性とは呼ばれない。なぜなら、協和音自身のみが完璧に完全となるからである。Ugolinoらはしばしば、ここではperfectioという用語を用いているが、より完全な感覚においては、ほぼ完全である、ということである。 こうした音程の完全性に言及する代わりに、理論家たちは時々、それらはcolouredされている、という。実践は完全性そのものほど義務的ではないようである。 perfectioという用語の意味合いにおけるあいまいさは、おそらく、”不完全協和音”の2通りの解釈の間の混乱にある。 1つには、それは、五度や八度のような増、減の”完全”協和音を意味している。他方では、それは、14,5世紀において、協和音でも不協和音ないもの、すなわち、三度や六度を完全により近づけることをも意味している。これらはまた、”不完全協和音”でもある。したがって、perfectioの意味合いは、通常、その内容から明らかにされねばならない。 (略) p29 12 Ugolino of Orvieto;Declaratio musice discipline About Music Ficta 1-5 すべての音符とそれらによって生成された協和音と不協和程音が示されている。そして、対位法がプレインソングのソルミゼーションのordinemに従うために、ときには、完全協和音は、rectaのソルミゼーションシラブルの発音では産生されず、固有の対位法には適さない不完全協和音が生ずることになる。 このような不完全協和音を完全化するために、理論家たちは、musica fictaと呼ばれたある種の音楽を、進化させた。musica fictaと呼ばれたのは、それ自身の権利(すなわち、それ自体がrecta)を持たない、想像上の位置に配置されたためである。それは、不完全協和音や不協和音をうめるために使用されている。 前者が生じる場合はどこでも、musica fictaは非常に義務的で(permaxime necessaria)あり、それが義務的である場合には、何らかの協和音の不完全性が見つかる。 6-9&13-18 musica rectaによってソルミゼーションされた垂直の五度B-Fは、不完全協和音である。なぜなら、miとfaの音程は、広い半音ではなく、極端な不協和(三全音)となるからである。(例1a)。 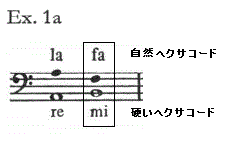 この場合、広い半音を五度の上の方の音(superiori)に付け加えねばならない。それは、ヘクサコードによるmusica fictaを通してもたらされることになる。そのヘクサコードの初めのutは、D上に置かれる。すなわち、そのfaはG上となり、そしてそのmiはF♯上となり、このF♯が、下のmiとともに、完全五度を構成することとなる。  p30 10-12 このような例は、musica fictaの必要性を示している。そのvocisの義務付けられた場所は、musica rectaには存在しない。協和音を完全化するために、そして、その例から我々がわかることは、それは、絶対に必要な場においてのみ使われる(necessitate cogente penitus)、ということである。 19-26 同じように、musica fictaは、やわらかいヘクサコードにおいて上声部がB♭となる時や、別の声部が五度あるいはオクターブ下でmusica recta miで歌う時にも、使われる。その時には不完全五度、あるいは八度が産生されている。 双方のケースで、recta miの代わりにmusica ficta faとなっている。すなわち、五度の場合、そのヘクサコードはB♭上のutとなっており、八度の場合、そのヘクサコードは、Γの下のF上のutとなっている。 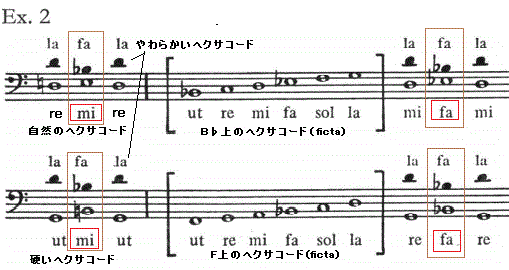 27-28 五度、八度などで、協和音の1つのパートが別のパートと不完全協和となるところでは、musica fictaを使うことが適当である。前出の例から、広い半音が、完全性を形成するために、下の音符(inferiori)に加えられている。 29-33 musica fictaを示す記号は♭であり、それに対してはシラブルfaが当てられ、 p31 34-39 fictaの理由は2つある。すなわち、①不完全協和音を甘美な和声とするために(つまり、それらを完璧に完全にするため)、そしてまた、②不協和音の音程を完全にするために、それを色付けするためである。 第1の理由は、学識ある人にとっては当然のことであるが、♭や 第2の理由は、すべての不完全なものが完全性に到達しようとするように、あらゆる不完全協和音あるいは不協和音が可能な限り、完全性へとアプローチすべきことで、変更された分だけ完全に近づく。 それゆえ、♭や 不協和音である長短の音程双方があるために、そして、完全性となるために、長は短となり、短は長となる。そして、長短の音程の間の相違は、b♭とb 40-46 ここでは、♭と 例3aにおいては、 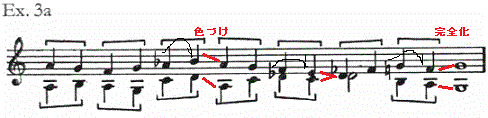 六度は、直近の協和音、完全性(次の完全八度)に適切に持っていくことを表現するために、長六度になっているのである。 この例では、最初の♭は、不協和音を完全にするのではなく、それを色づけするために置かれているのである(p31冒頭の②に相当)。そして、re-miを、半音を使ってmi-faとしている(例2参照)。六度は短六度となり、そのサイズと位置において、直近の完全(すなわちAのオクターブ)に可能な限り持っていっている。(全音ではなく)半音が完全(八度)へと近づいていくことで、六度からの完全化がより容易になっているのである。♭はそれゆえ、六度を色づけするのであり、それを完全化するのではない。♭は、続く完全(八度)へと六度を接近させるためにあるのだ。 p32 例3aの2番目の♭は、同じ理由で置かれている。そのために、c-eの三度は、続くユニゾンdへと接近する半音となる。同じことは、例3bの上声部の最初の♭においても当てはまる。 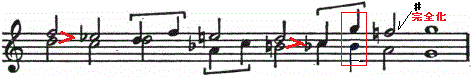 47-51 例3bの上声部の最初の ①ステップf-eを半音とすることで、 ②結果としては、より甘美な和音となること。 上声部の最後の 例3bの下声部の 52-58. 協和音の完全化、不協和の色づけ、甘美な和音の産生は、musica ficta を必要とすることが理解される。それは、musica rectaそれ自体には存在しない場所に配置されるためである。(略) 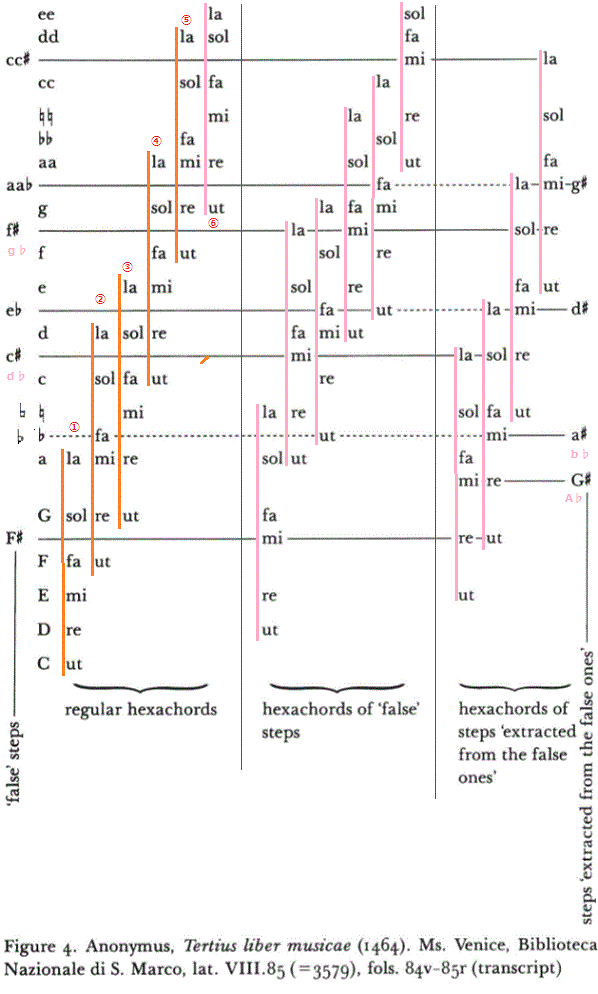 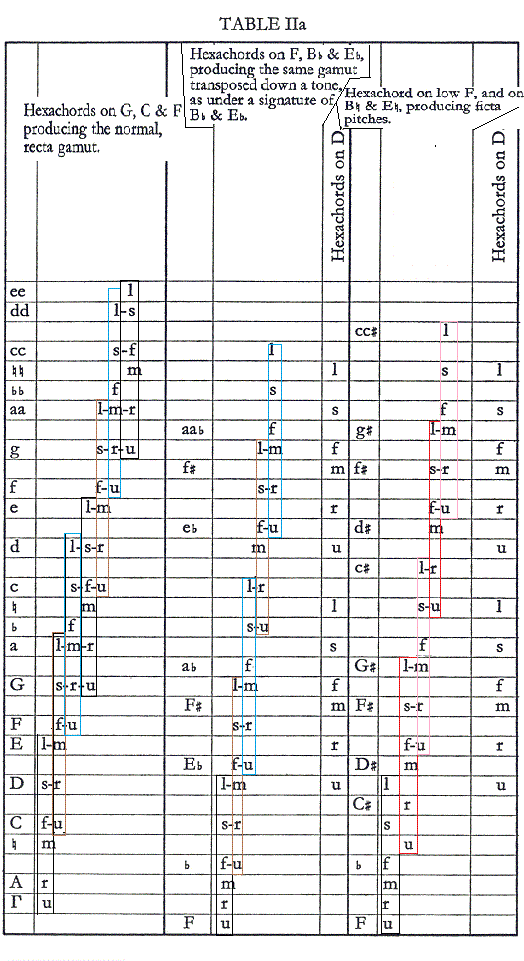 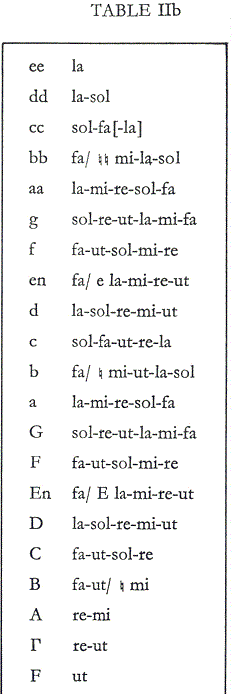 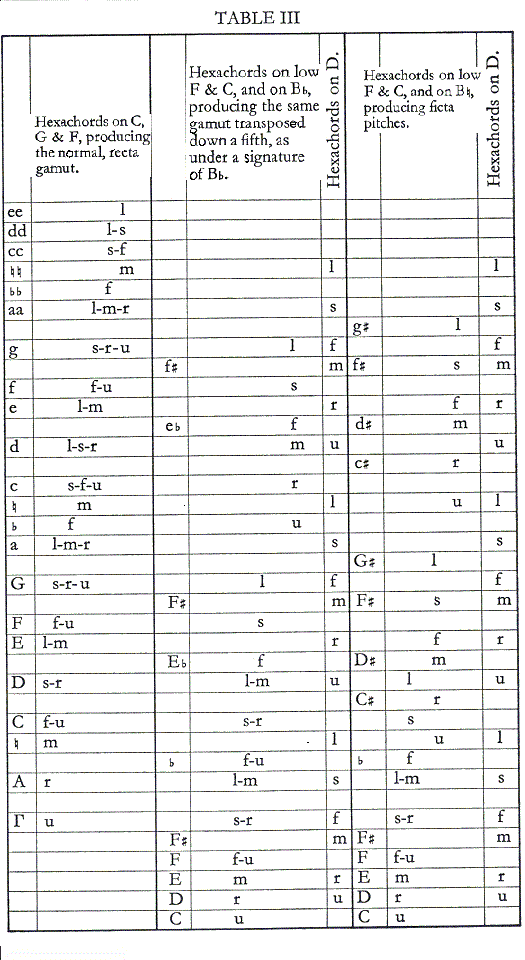 59-65 しかし、rectaであれfictaであれ、完全性であれ色づけであれ、歌手らは古い時代の真実を無視している。彼らはこうしたmusica fictaの確かな知識を持っていて、♭と これらの記号は、音程の色づけが甘美な和音を産生するものとして、発明された。(それは、長音程が短音程になった時に、あるいは短音程が超音程になる時に生じた)。そして、不完全協和音がより広く、かつ完全になるために発明された。 p33 より甘美な和音は、次のように示される。すなわち、B-mi →A reではなく、B♭-fa →A-miとなることで。なぜなら、上記の対位法の規則に基づいて、それがつづくユニオンにより完全化される場合、三度は短三度になるべきだからである。全音mi-reの代わりに、♭を置いて狭い半音fa-miにすることで短となるのである。 それゆえに、長三度は、広い半音の控除によって短三度となる。すなわち言い変えれば、二全音(長三度 ditonus)は、短三度(semiditonus)となって、甘美な和音を作るのである。 上記の規則によれば、対位法における協和音と不協和音は、完全、長であるべきで、不完全あるいは短であるべきではないので、不完全なものが生じるときには、それらは、すでに言及した記号のひとつによって、変えられなければならない。 たとえば、この次の六度は、c-fa→ d-sol(硬いヘクサコード)ではなく、c♯-mi→d-fa(A上のfictaのヘクサコード)となるべきで、広い半音が加わることによって、完全に導かれることになる。 p37 66-67 このように、当時は、cとしてのrecta faを 上声部のc-faからd-solへの上昇では、全音での引き上げをするが、faのところにmiを置く場合には、 それゆえ、それが狭い半音の上昇となるのは、miからfaへは常に狭い半音の上昇であるためであり、recta fa上のcのピッチは、recta fa(c)からficta mi(c♯)へと、広い半音で引き上げられることになる。 なぜなら、c-fa→ d-solが全音であれば、ficta mi(c♯)→d faは狭い半音となり、そのとき、recta fa(c)からficta mi(c♯)へは、広い半音となる必要があるだろうから。こうして、短六度は長六度になる。 68-74 こうしたことから、c上のficta このficta hexachordによるこのE-cは、長六度であり、完全へと導かれる。musica fictaによって置き換えられた半音を通して、長六度は広い半音によって短六度から変化する。 75-79 同じような六度はD-bにも生じる。つまり、♭-faであれば六度は短であり、 80 こうしたことから、musica fictaは、必要性と、修飾・審美性に対して、案出された、と言えよう。 そしてfictaのために、cがc♯となり、a上のficta hexacordを持つことが、長六度のための十分条件となる。 Commentary Gravesにおいては、B♭はmusica rectaには入っていない。そして、Ugolinoは、通常はこれより上の音域(Acutae)を選択しており、音程をF♯で訂正している。 Acutae以上の音域においては、rectaB♭が可能となっており、それによって五度を完全化することができる。すなわちこの場合、写本の臨時記号 p38 29-33(略) 40-46 Ugolinoは、例3aの3番目の♭には何ら触れていない。それはf♭で、現代のシステムにおいては、無意味かつ不要である。中世のシステムにおいてそれは、e( 47-51 Ugolinoは、協和音(ソのオクターブ)の直前ではないこの六度が長六度でなければならない理由を、述べていない。 彼はまた、例3bのテノールの最初の♭にも言及していない。すなわちこれは、二重な不運である。なぜなら、その存在理由が、中世システムにおいてさえ、はっきりしないからである。ヘクサコードを変える必要性もない。なぜなら、b この場合、bは自動的に 52-58 ficta hexachordsのいくつかのutがfa上に配置されているか、recta systemのあいまいなBのmi上に配置されているか、つまり、B♭かB Only the hexachord beginmngon D, common to bothTables, is not affbcted by this ambiguity. それぞれの表は、ficta を rectaシラブルを分け、、①中央の列では、utに対してはrectaシステムのfaを選び、②右の列では、utに対しては(rectaシステムの)mi(recta)を選ぶという、2通りの選択肢を示している。 両解釈の存在には、意図がある。もしもfictaの音符を使うことが目的であるなら、すなわちそれが♯であるなら、右の列がその働きをすることになる。 しかし、表2,3での(各列の)ピッチの結果は同一であり、2つのダイアグラムがある必然性はない。 2つの表がfictaの音符ではなく、fictaのヘクサコードを示すことや、fictaの音符が産生される場を示すことは、考えられよう。すなわち、2つの表のうちでは、それぞれは、gravesでのFとC上のrectaヘクサコードがダブっており、それぞれがD上の(fictaの)ヘクサコードを持っているが、前者はその他にB上とA上の(fictaの)ヘクサコードを持っているのに対して、後者はB上の(fictaの)ヘクサコードのみを持っている。 ピッチではなくヘクサコードを示すこれらの目的はおそらく、表3でのEとA上のヘクサコードの欠損を示している。それは、右の列の解釈と関連する。 p39 一方、fictaシステムがどのように完成されたのかを示すのであれば(それは、B♭のみとB♭&E♭で産生されたもので、recta音階とは五度ないし全音分ズレてだぶっている)、中間の列の解釈と関連する。 中間の列と関連した後者の解釈は、そのシンメトリーをひっくり返すようなD上のヘクサコードの確固たる存在で、いくぶん弱められている。なぜならそれは、音階での支持された移調で産生されていないからである。 表2bにあるような、En-faとE-la-mi-re-utのはっきりした分離は、移調されていない音階のB-fa/B-miの曖昧さを、確かに反映している。そして、ピッチの同じ区別が存在していることだろう。 同表における、B-fa-utとB-miの間の別のはっきりした分離は、En-♭-faとE- E-♭-faはそれゆえ、右ではなく、中間列のコラムを確信させる。それからE-la-mi-re-utはE- たとえば、C-utでは、Gはsolとなり、 Ugolinoが、モノコードのficta音符の単なる産出を超えた段階に行き着き、通常のシステムと並行して、それらを合理的に構成しようとしていたことは明らかである。 80 音符aに基づいて構築されたヘクサコードの強調はおそらく、この特殊な位置が、前に示した両表から省略されていることによる。 Ugolino はまた、E上のhexachordの省略についても言及しているが、表1は、E |