| THE FUNCTION OF CONFLICTING SIGNATURES IN EARLY POLYPHONIC MUSIC2 By EDWARD E. LOWINSKY |
| 音楽エッセイのページへ戻る | 初期多声音楽 |
| Leoninのページへ | 中世楽のページへ |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | ペロタン Clausulaのページ |
| substitute clausulaのページへ | 前ページへ |
| p246 これまでのところ、主にフランス、イタリア、ブルゴーニュの音楽におけるconflicting signaturesの使用について検討してきた。オールドホール写本を調査すると、この慣行がいかに堅固で統一されているかが明らかになる。 p247 この写本は、conflicting signaturesを持つ作品を、少なくとも46作含んでいる。 圧倒的多数では、その目的は、カデンツの種類によって説明される。 それは、これらの作品の1つであるダメットのグロリアで使用されているものを引用し、それらの外観の頻度を示すだけで十分な場合であろう。 最初のカデンツはリディア旋法で、11回使用される(例27a)。 2番目は移調されたドリア旋法で、13回発生している(例27b)。 3番目は移調されたリディア旋法で、3回発生している(例27c)。 最後は移調されたフリギア旋法であり、一度だけ使用されている(例27d)。 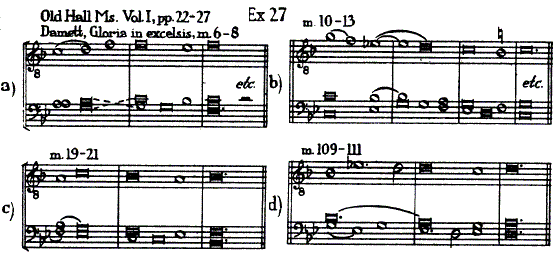 写本9v 1つの♭署名のみを持っているsuperiusにおいてEフラットが頻繁に出現することは、多調性の問題がないことを示している。このパートには、4つのEフラットが書き込まれ、32がmusica fictaによって暗示されているが、26のEナチュラルがある。個々のパートの他のパートへの相互の同化が継続的に行われている。これは、共通の「調性」への傾向に由来する。作品には TyppによるSanctusでの♭ 似たような状況は、匿名のAgnus Dei (第III巻、p。106)でも見られる。ここでは オールドホール写本の作品のtrebleのBナチュラルは、C上のカデンツに対してだけでなく、G上のハーフカデンツも使用されている。それは、オールドホールスタイルの特徴である。 ダメットは例28のようにハーフカデンツを使用している。 Pycardは、6声部のグロリアにおいて、例29で示されるような優雅な形式における別のカデンツに対して、しばしば、B p248 こうした和音の組み合わせから、1450年以前に書かれた、Pycardのスタイル全体から明らかになることがある。 もしもオールドホール写本の音楽が”保守的で退廃的でさえ”あると非難されたならば、Damettの作品や特にPycardのそれの和声的観点は、厳しい審判の目から逃れたに違いない。 Pycardの2つのGlorias (Vol. I, pp.84-103)の生き生きとした上声部のリズム的ヴァイタリティと低声部の長く保たれた和声には、驚くべきソノリティがある。 OH音楽の最後の”layer”の作品の詳細な調査と比較は、それが1430-50年の間に作曲されたことを確証させることになった。OH写本に現れる作曲家に関したウィンザーの記録はほとんどなく、推定するしかない。 J.Pycardは1461年の記録がある。R.Cherburyは1455年にチャプレンだった。Damettは、ウィンザーで1430-36年に、N.Sturgeonは1442-52年にcanonであった。一方、John Aleynは、1362-73年にcanonであったが、彼のGloriaは(p7)非常にプリミティブなfauxbourdon様式で書かれ、こうしたデータと合っている。 OH写本において、ダンスタブルの作品がほぼないことが、以上のような証拠に疑念をつける可能性があるとは私は思わない。 唯一のダンスタブルの作品には、彼の名前は欠落している。(その他のソースからの記載でそれがわかるのである)。このようなコレクションの機能は、非常に実用的なものであった。 p249 OHの音楽は、ウィンザーチャペルでの礼拝での使用のために書かれ、編纂された。その作曲家らは、実際、王室礼拝堂のメンバーであった。さらに、ダンスタブルはイギリスに住んでいなかった。 (略) p250 これまでに調べた出典の中で、我々の原則に従って説明のつかない conflicting signatures がある作品の割合は無視できる。 Copenhagen Chansonnier は、かなり多くの例外はあるが、最初のソースである。conflicting signaturesを持つ18作品のうち、5個は実際にはこのようなconflicting signaturesの必要がない。 これにより、Jeppesenが、彼のconflicting signatures についての理論をこの写本に基づいて、それらがスクライブの側の杜撰さの印でしかないと結論付けた理由が理解できるようになる。 Jeppesenは、Copenhagen Chansonnierは、15世紀後半のすべての写本と同様に、非常に不注意に書かれていることに気付いた。これが、比較的多数の例外の原因となる場合がある。それはまた、メソッドのポイントに私たちを導く。表記法の問題を説明する試みでは、均質であり、表記法の注意と正確さによってそれ自体を区別するソースを調べることをお勧めする。さらに、いくつかの異なるソースを調べることにより、1つの特定のソースの特異性から一般原則を推測することを避けることができる。最後に、すべてのルールに例外が存在することは当然のことと考えるべきである しかし、 Copenhagen Chansonnierでも、conflicting signatures を持つ18のシャンソンのうち13が、伝統的のパターンに適合するか、新しいパターンを作成している。 このシャンソニエは、Binchois and Dufayの世代に続くBusnois-Ockeghem の世代の作品を表している。 すでに説明したカデンツパターンに加えて、新しくて大胆なパターンが見つかることは不思議ではない。 調査されたソースの中で、Copenhagen Chansonnierは、偽終止のカデンツを時折使った最初のものであることが見出されたことは不思議ではない。 例30a-bのような(偽終止)パターンは、なぜドリア旋法または移調されたドリア旋法で書かれたシャンソンの最も低い声部がそれぞれ1つまたは2つのフラットの署名を必要とするかの理由となるだろう。 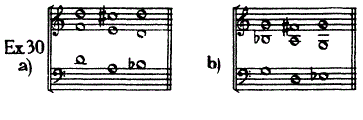 偽終止ゆえに♭が最低声部で1つ余分に必要になる p251 もう1つの新しい大胆なパターンは、1つの声部で2つの導音(ひとつは上から、もうひとつは下から。すなわち、B♭→A、G♯→A)を使用する半音階clausulaである(Clausulaは、ここでは、カデンツで生じるメロディ公式を示すために使われる)。 Jeppesenは、和音のカデンツ公式の性質と、署名の変化するパターンに対する影響を認識していない。彼は半音階的clausulaも同様に誤解し、調号によって明らかに要求されているにもかかわらず、B-flatを排除してしまっている。 例 31は、半音階clausulaと偽終止カデンツを組み合わせたものである。 通常ではない署名♭ Copenhagen Chansonnierは、象徴的な発想にその起源を持つconflicting signatures が使われた作品を含む最初のソースである。このことは、No.17のような特殊な作品で明らかになる。ここでは、第15小節において、署名は 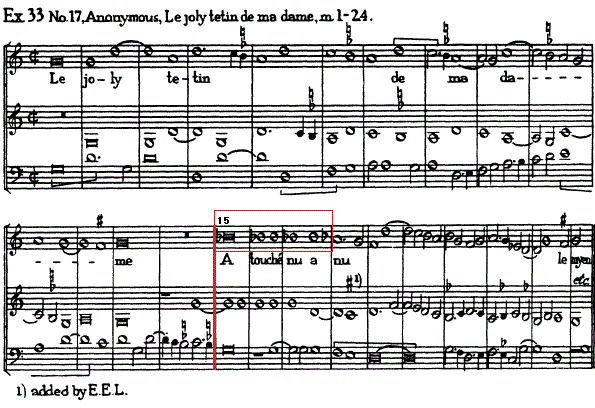 15世紀の音楽の記譜法をよく知る人たちは、5つの連続するB(第15-7小節)に対する3つの♭の使用や続く1つの♭署名の使用が非常に奇妙であると認めるだろう。なぜ、署名は単純に、すぐに導入されなかったのか? 匿名の作曲家は、大胆な歌詞に対する大胆な音楽設定をしている。彼は、B♭を耳から同様、ヴィジュアルの意味合いとして使い、場面を現す親密さを高めている。テキストは以下のようである。 Le joly tetin de ma dame A touche nu a nu le myen 当時の用語では、B Jeppesenがシャンソンの最初の14小節に追加したフラットはすべて間違っている。作曲家は、これらの小節をhexachordum durumに入れたいと考えた。 hexachordum molleで作曲された(第15小節以下の)次のセクションは、「a touche nu a nu le myen」という単語の柔らかさと甘さを表現することであった。 p253 その象徴的な意図を明確にするために、作曲家はフラットの蓄積を利用した。彼の意図的な手段の選択に気づくためには、2つのセクションの和声設定を比較するだけでよい。 hexachordum durumで書かれた最初のセクションでは、作曲家は、(第3音のない)オクターブと五度の和音を頻繁に使用して、空疎で厳しい和音効果を生成しようとしている。 hexachordum molleで記述された2番目のセクションでは、作曲家は、三度や六度、そして三和音を使用して、官能的な美しさの完全でソフトなサウンドを生成している。 このセクションの最後のカデンツは、空疎なオクターブとなっている。同じように目立つのは、最初のセクションの単調で反復的な性質とは対照的な、hexachordum molleセクションのメロディーの特徴的な性質である。 もちろん、最初のセクションがそう設定されているのは、テキストの冒頭が要求したからではなく、作曲家が、特に説明したい単語を含む、甘美な2番目のセクションの対比としてそのような設定を必要としたためである。ここでも、以前の研究で行ったように、臨時記号の問題に取り組むとき、細部を理解するためには全体をよく理解しなければならないことがわかる。 テキストが特に感情的になるポイントで曲の途中で署名が変わる他の例がある。 匿名の作曲家によるOstez la moy de mon Oreille (No. 21)では、3つの声部のいずれにも署名がない。 しかし、第50小節以降では、superiusは(歌詞に応じて)Bフラットになる。 Mon tout, mon souvenir, m'amyeにおいては、superiusは署名なしで始まり、その間テノールとコントラテノールはそれぞれB♭を持っている。第12小節において、歌詞は続く。Ayez regard au panant(悔い改めに憐れみを)。superiusはここからB♭署名を持つようになる30。 30 16世紀の作曲家は、長短調だけでなく、苦しみと喜びの象徴としてもまた、♯と♭記号を使った。こうしたMon tout, mon souvenir, m'amyeのような作品において、我々は、16世紀のB♭の象徴的な伝統の先行を見るかもしれない。 p254 p257 イタリアのlaudi の和声様式は、移調の有無に関わりなく、装飾されたり拡張されたように純粋に、ミクソリディア旋法のカデンツをよく好んでいる。作曲家は、B♭-C-G-CカデンツにおけるB-flatとGの間の三度の関係(例19)の魅力を発見し、そして彼らは、これらの2つの和音を分離して、B♭とB スクライブの怠惰が、ここでもまた、conflicting signatures の理由となっている。 バスでのBの欠如または希少性も原因として再現される。したがって、Dammonisでは、1つのフラットをsuperius、alto、およびtenorに配置しているが、No。67、70、および83のバスにはいずれも配置がない。 なぜなら、Nos. 67ではバスには2つのBしかなく、他の2曲にはBはないからである。 匿名の作曲家によるO tempo giocundissimo は、テノールのみに2つの♭があり、その他にはまったく♭がないという、珍しい構成となっている。その理由は、非常に特殊かつ魅力的な和声概念にある。テノールは2回移調されたドリア旋法であり、ソプラノのはイオニア旋法にあり、バスはイオニア旋法とミクソリディア旋法の間を動き、コントラテノールはメロディアスな一貫性のないものとなっている 。 結果は、最初の8小節が示すように、長短調のユニークで大胆な混合となっている。 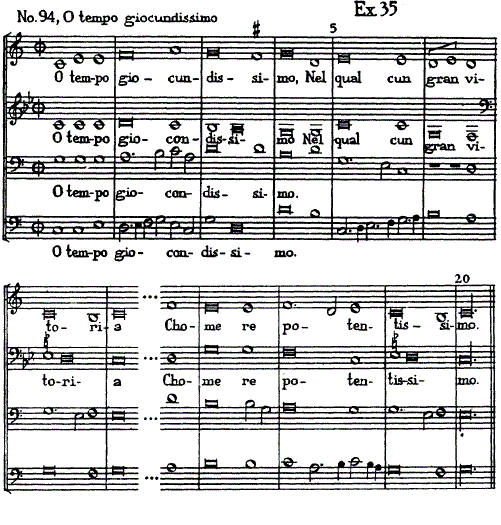 p258 イタリアのlaudiからのいくつかの例は、リズム、メロディ、ハーモニー、そしてフォーマルな構造における明瞭さとシンプルさへのイタリアの傾向を示している。 イタリアの側でのconflicting signatures の使用に対する急速に減少する関心は、明確さを求めるのと同じ欲求から来ている。conflicting signaturesは明らかに、明確さの欠如と不安定さを作っていると見なされた。 イタリアの音楽的感覚は均一な調性に向かう傾向があり、この傾向は、統一された署名を著しく好むことで、その論理的正当性を見出している。 イタリアの実用音楽が示すことは、イタリアの理論によって確認されている。 Pietro Aronは、1523年の Aggiunta del Toscanelloで、Aggiunta del Toscanelloから取られた以下の言葉で、conflicting signatures の慣行を非難している。 p259 私は、ポリフォニー作品において、深い考えもなく、1つの声部(大抵は最低声部であるが)だけにB♭を置くことには反対する。このようなlicenseは禁じられ、許容されない、と言おう。それは、真の音楽家には考えられもしないことなのだ。 Aronは、conflicting signaturesを拒否した理由を2つ挙げている。 1つ目は、同一の旋律の進行のソルミゼーションにおける不整合である。 署名のない高い声部がGからD、DからB、またはBからGに移動する場合、ソルミゼーションはそれぞれsol re、sol mi、またはmi utです。 シグネチャにBフラットがあり、バスが同じトーンを持っている場合、ソルミゼーションはre la、la fa、fa reとなる。 Aronの2番目の理由は、オクターブやダブルオクターブの不一致(B♭-b すべての他の声部にも♭署名を使用すること、そして、すべてのメロディ進行や協和音程は、まっさらで、調和的となるだろう。そこでは最初のいくつかは不協和音程となる。 同一の旋律の進行の異なるソルミゼーションへの彼の異議を、完全に重要視すべきである。 彼は、(ソルミゼーションが)異なる原因となるconflicting signaturesに反対しているが、この種の表記法から始まる、またはむしろそのような表記法に帰する、調性の統一の概念を示さない一種の思考にも反対している。 「調性の欠如」は「多調性」の別の用語ではない。 多調性は、さまざまな声部のさまざまな調性の競合によって生成される。 しかしここでは、競合は全体としてポリフォニック作品の本体にまで及んでいる。 すべての声部が等しく影響を受ける。 p260 Aronは、調性と表記法の処理に合理的な方法を適用するようにした。 明らかに彼のアイデアは、最初にイタリアで、それから西洋世界の残りの地域で勝利した。イタリアの調性と音楽記譜の合理化の台頭は、conflicting signaturesと3世紀以上にわたって揺るがなかった旋法の衰退の原因となった。 |