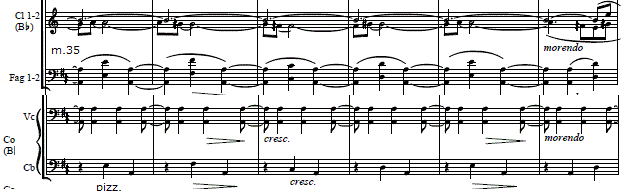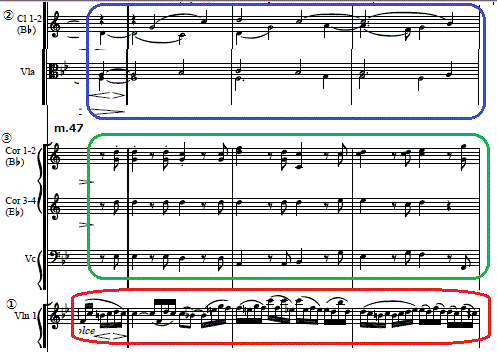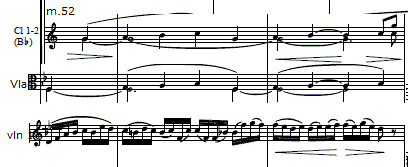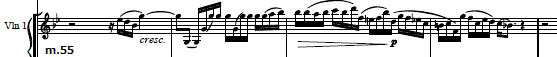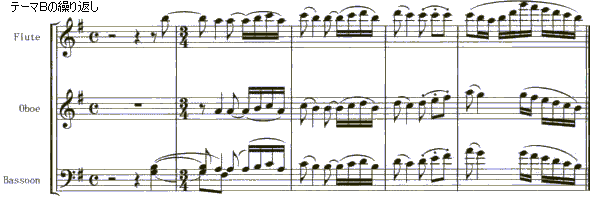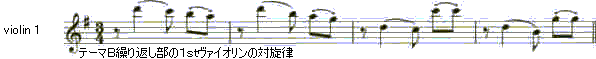<第九第三楽章の思い出>
ベートーベンの第九とはもう25年の付き合いである。なんかこの第九とはウマが合って18歳の時から飽きもせず聴いている。大学に入った時に\750で買った全音のミニチュアスコアをまだ持っている。ひとりでこのオンボロスコアを眺めながら頭の中で自分なりの演奏を楽しむ暗い青春を送ってきた。19歳の時に生まれて初めてとある女性とデートをしたつもりが実はそうではなかったときは(要するにすぐフラれた)つかの間の誤解の上での青春を過ごした証しとして第九の第三楽章をよく聞いていた。だから今でもこの第三楽章を聴くとあのときのつかのまの誤解の青春を思い出す。
だからというわけでもないが第九の中では第三楽章が一番好きである。第九は好きだけどこの第三楽章は聴いていると眠くなるという人がいるが、もったいない話である。私はこの第三楽章からは何かベートーベンの妖気というか執念のようなものを感じるのだが。そしてベートーベンはどうしてこんな音楽を書いたものかと思う。ここでやや煩瑣になるがこの第三楽章の全体構造を見てみたい。
<全体の構造>
そもそも交響曲とは、通常は第2楽章はゆっくりしたリズムになるのが普通であった。ベートーベンも第7交響曲まではセオリー通り書いていた。ところが第8になると、事実上、緩徐楽章がなくなってしまい、ついにこの第九においては、第2,3楽章が逆転してしまい、第2楽章にスケルツォが来て、この第3楽章が緩徐楽章となる。第九の場合、最終楽章が爆発的な出だしなために、こうした逆転は理にかなっていると言えよう。
さてこの第3楽章は、最終楽章と同様、壮大な変奏曲となっている。変奏曲が2曲続くにもかかわらず、その性格が全く異なるために、まったく飽きが来ないのはさすが、と言えようか。
さて、第三楽章の構造は、以下のようになっている。
テーマAの提示(~第24小節) B♭
テーマBの提示(第25小節~第42小節) Ddur
テーマAの第1変奏(第43小節~第64小節) B♭
テーマBの繰り返し(第65小節~第82小節) Gdur
テーマAの第2変奏(第63小節~第98小節) E♭
テーマAの第3変奏(第99小節~第120小節) B♭
最後のファンファーレ(第121小節~)
<導入部→最初の主題>
まずはクラリネットとファゴットによる導入である。pで入り、途中がふくらむ。(下譜)それに呼応して弦がヘ長調の和声を出す。チェロが途中F→Gesと変化して和音が一次的に減七になるのを聴き逃してはならない。特にファゴットのシ♭ラソファという動きは今後折りに触れて出てくるので大変重要である。

そしてヘ長調から本来の変ロ長調となり、弦によるこの曲のメインテーマ(テーマAとする)が美しい弦の和声と共に入ってくる。(下譜)
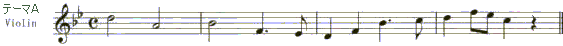
コントラバスがないことに注目!。またメロディーも弦楽器にしては高くなく、つまりこれは四部合唱を構成する人声の範囲である。そのためかこの部分は非常に親しみやすい感じがする。
このメインテーマは途中断続的に入ってくるクラリネット、ファゴット、ホルンによりとぎれるが、これら管楽器はメインテーマを引き継ぐように入るので音楽はずっと連続的に流麗に流れていくのである。
そしてホルンが と入ってくる第15小節からがクライマックスである。ここよりメロディラインは人声の範囲を超え、高くシ♭まで上昇する。そして他の弦楽器群はここより急に単純な8分音符の刻みとなり、ホルンと共に純粋に伴奏に徹するようになるのである。 と入ってくる第15小節からがクライマックスである。ここよりメロディラインは人声の範囲を超え、高くシ♭まで上昇する。そして他の弦楽器群はここより急に単純な8分音符の刻みとなり、ホルンと共に純粋に伴奏に徹するようになるのである。
さて第19小節になって初めてコントラバスが入る。この効果は絶大で、ここで曲全体が引き締まる。その直前からのティンパニの も聴きのがせない。ティンパニは曲全体を包み込むような性質があるのでこのpで入るティンパニもまた効果的である。ここで曲がいったん引き締まったあとは主としてクラリネットがメロディを吹いていく。第15~18小節における弦によるメロディがクラリネットにより繰り返されるのである。その間今度はファゴットとホルンは単純な8拍子を刻み、弦は装飾音を伴った時計の振り子のようなリズムを刻む。 も聴きのがせない。ティンパニは曲全体を包み込むような性質があるのでこのpで入るティンパニもまた効果的である。ここで曲がいったん引き締まったあとは主としてクラリネットがメロディを吹いていく。第15~18小節における弦によるメロディがクラリネットにより繰り返されるのである。その間今度はファゴットとホルンは単純な8拍子を刻み、弦は装飾音を伴った時計の振り子のようなリズムを刻む。

こうした装飾の仕方はベートーベンとしては珍しいのではないか。私の知っている限りでは類似例としてはおそらく「アテネの廃墟」の中のトルコ行進曲くらいのものだろうと思う。こうしてメインテーマの提示が終わり、曲はヘ長調の属七からニ長調へと移っていく。
<テーマBの提示>
ニ長調に転調したところで新たなテーマ(テーマBとする)が出る。(下譜)

これは2ndヴァイオリンとヴィオラという珍しい組み合わせである。ヴァイオリンだけではメロディラインが低いために埋もれてしまうし、かといってチェロを使ったのでは今度は目立ちすぎである、とのことでその中間の組み合わせであるこの2つの楽器を使用したのであろう。これで適度にメロディラインが目立つこととなった。
ベートーベンの頭の中にはあらゆる楽器の組み合わせが鳴るようになっていたのだろう。作曲というとたいていの人はピアノを使ってするものと思われるだろうが実は作曲というのは頭の中でするものである。私のようなへっぽこでも一応は頭の中で作曲するのだからベートーベンがピアノがなければ作曲ができなかったとは考えにくい。
それにオーケストレーションなどは頭の中で鳴らすしかない。チャイコフスキーなどもたとえば「悲愴交響曲」を作曲した時などは頭の中で作曲して感動のあまり泣いたらしいが、ベートーベンやスメタナが耳が聴こえないでも作曲できたのも頭の中で作曲をしていたおかげである。
このテーマBにはさまざまな楽器が絡み付いて彩りを加えている。たとえば、2回目の繰り返しでは、第33小節よりオーボエが付随してくる。第35-40小節では、フルートとオーボエが交互に2ndヴァイオリンとヴィオラの旋律を強化している。
チェロとコントラバスも分離されているので(これもベートーベンの時代としては珍しいことだろう)バスの音色は乾いた響きがする。チェロは、第1クラリネットとともにずっと事実上のオルガンポイントとなっている。バスにあたるパートは、ピッチカートのコントラバスとオクターブにわたるファゴットとともに、なんと3octaveにもわたる構造になっている。したがって演奏の際には、ここはかなり抑えめにした方がよいだろう(特にファゴットは)。
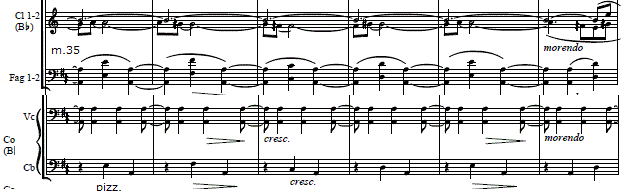
このテーマの提示が終わると調性は一時変ロ長調となり(この転調も非常に感動的である)ヘ長調の七の和音を経て、最初のテーマの変奏が始まる。
<テーマAの第1変奏>
この第一変奏(下譜)はメインテーマを16分音符に分解して行われる。そして最初の部分のアウトラインをクラリネットが受け持つことによって聴衆が何気なく聴いていても「ああ、最初のメロディの変奏だな」とわかるようになっている。チェロと2ndヴァイオリンはピチカートとなり、ホルンと共に曲の基礎部分を作っている。

すなわちここの変奏部分は、おおざっぱにいって、以下の3構成からなっている。
①1stヴァイオリンの変奏
②クラリネットとヴィオラを中心とする本来のメロディライン
③ホルン、ピッチカートのチェロによるバスライン+伴奏
下譜は①~③でスコアを再構成した1例である。
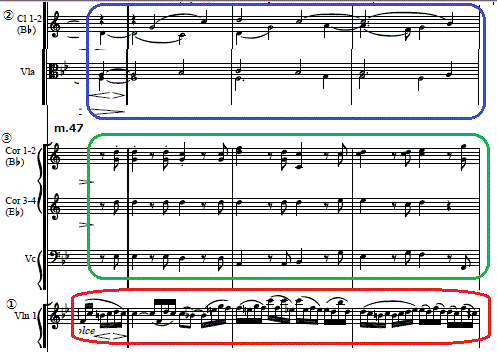
注目すべきはヴィオラである。ヴィオラは2パートに別れてクラリネットとペアを組み、低い音域ながら大変重要な対旋律を奏でているのである。
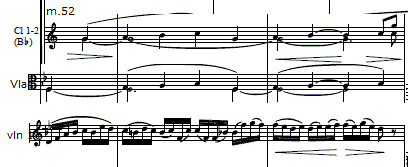
ここは第九の第三楽章の中でも私が特に好きな部分で、例のつかの間の誤解による青春のときも特にここのところはスコアとにらめっこしながら耳をすませて聴いていたものである。ここに私はベートーベンの妖気を感じるのである。言葉で表現するのはむずかしいが、スコアからなにか妖気が立ってくるような気配がする。
ベートーベンはなぜにヴィオラパートを2パートに分けてまでここの部分をかくも念入りに書いたのだろうか。ヴィオラにしか出せない何かを表現したかったのだろうと思う。そしてほぼ一オクターブ上をクラリネットが吹くことによって、とかく埋もれがちになるこの大切なヴィオラパートを保護しているのではないかと思う。つまりクラリネットの方が音域的にはめだつのだがベートーベンが本当に大事にしたかったのはヴィオラの方ではないかと思うのである。
第55小節ではホルンがテーマAに対してのところの がここの第一変奏のところでは がここの第一変奏のところでは と変化し、また第56小節では1stヴァイオリンが一時開放弦の低いソの音まで落ちるのが印象的である。 と変化し、また第56小節では1stヴァイオリンが一時開放弦の低いソの音まで落ちるのが印象的である。
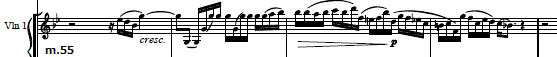
<テーマBの繰り返し>
その後はテーマAの提示部分と同じになり(ここの部分はこの第三楽章のうち唯一不満が残る点である。もう一工夫してもらってこのあたりも少し変奏してくれていればといつも思うのだが)先ほどはニ長調へと移っていったが、今度はニ長調からさらにト長調となって先ほどニ長調で出たテーマBが今度はト長調となって繰り返されることになる。(下譜)
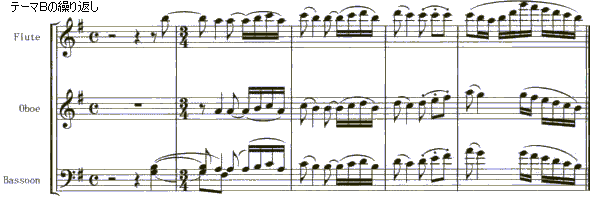
メロディラインを奏する楽器は今度はフルート、オーボエ、ファゴットの三点セットとなる。この三つの楽器の組み合わせは生硬な音が出るのが特徴で、ベートーベンもよく使っている手慣れた組み合わせである。
ホルンはさきほどチェロが奏していたオルガンポイントとなっている。木管楽器にメロディを回したおかげで弦楽器は対旋律に専念することができることとなった。バスラインは今度はチェロとコントラバスは一緒になりニ長調の時とは異なる潤いのあるバスとなっている。途中でコントラバスのみが裏切ってピッチカートになってしまうために今度は実質的にチェロが最低ラインを受け持つことになる。開放弦であるレの音をうまく使ってコントラバスが欠けたチェロのみの時のバスラインの独特のきしむような響きを出している。このあたり、ニ長調のところのコントラバスのみの乾いた響きとしっかり比較して微妙な響きの違いを聴き分けてあげたいものである。でないとこうした細かい工夫をしているベートーベンに申し訳ない。
コントラバスとヴィオラ、2ndヴァイオリンがピッチカートになったところ(第73小節)で1stヴァイオリンがすばらしく美しい対旋律を奏で始めるところも注目に値する。(下譜)
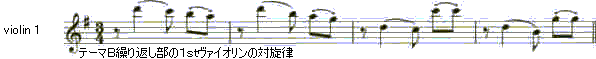
この対旋律は非常に目立つのでボーっとして聴いていてもすぐに耳に入ってくる。このあたり、舞踏を思わせるような雰囲気である。木管楽器のメロディラインはここよりフルートとオーボエ、そして1stファゴットと2ndファゴットがそれぞれ3度の和音を形成し、ホルンはここよりオルガンポイントから なものに変化している。 なものに変化している。
そして曲は今度は非常に印象的な変ホ長調となり、変ロ長調属七を経て本格的に変ホ長調の曲となっていよいよこの第三楽章のうちの特異な幻想的世界へと入っていく。
|