| �I�@�́@����̈�Âւ̒� �@�@�@�@�@�@�\�u���ł��f�܂��傤�ȁv�̑n�� |
| TOP�y�[�W�� �n���Ẫy�[�W�� �I�͂��̂Q�y�[�W�� �O�y�[�W�� |
���̂P�G�u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t����낤�I �����̈�Â̌��_�G���V�� �@������t�ƂȂ����̂͂R�R�A�����̐l�����X�N���x��Ă����B������w�o�ϊw���𑲋Ƃ��A���̌�A���͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����R��暌��A�m�u�t�A�������Ȃǂƕ��Q�������ƁA�����w�i�������ȑ�w�j��w���ɂ���Ƃ������Ƃ������������ē��w�����̂��Q�V�̂Ƃ��B������w�̊w������A�S���̃n���Z���a�×{����K�₳���Ă������������Ƃ����������ŁA��t���u���ĂT�N��̂��Ƃł������B�����ĂU�N�ԁA�ҕ����āi�H�j�����A��t�ƂȂ邱�Ƃ��ł����B �@�x�炫�l���A�ł����������K�^�ɂ���t�ɂ����Ă����������̂�����A�����ł����̂��ߐl�̂��߂ɓ������Ǝv���A�����Đl�̖����~�����߂Ɉ�ԑ�Ȑf�ÉȂ͋~�}�Ɩ����Ȃ��Ǝv���A�܂��͂��̓�̉Ȃ̃g���[�j���O�����B���̌�͕č��^ER���������a�@�Ō��C���A�S�Ȃɂ킽���ĕ����ʂ蓪�̂Ă��瑫�̂ܐ�܂Őf�邱�Ƃ̂ł����t���߂������B �@�P�X�X�U�i�����W�j�N�A��t�ƂȂ�قڂR�N���߂������_�ŁA�������Ď����������V���ɂ��閯�Ԃ̕a�@�ɕ��C���A�T�N�Ԃ������ʼn߂������B �@���V���͖k�܂Q�W�x�Ɉʒu����A�����ŗL���Ȉ��M�т̓��ł���B�������A��Q������l�̐l������������傫�ȓ��ł���Ȃ���A�����a�@�͂Ȃ������B���̂��߁A�������C�����a�@�i�x�b�h����P�X�X���j�����̍ŏI�a�@�Ƃ��Ă̖�����S���Ă����B �@���̕a�@�ł͊O������ȁA�O�Ȃƕ����Ă��Ȃ������B�����f�Ñ̐��Ƃ��āA�ꊇ���ĊO�����҂�f�Ă����B�i�ꕔ���P�Ȃ���j�@���ׂł����ɂł����ɂł����ł�����ł��P�l�̐搶�̐f�@�ōςނ̂ŁA���҂���̗����͂悩�����悤�ł���B�s��̕a�@�Ȃ�A�Ȃ��Ƃɍׂ����O����������A���͉��ȁA���̎��͉��ȂƂ����悤�ɁA���邮���āA�u�R���ԑ҂��v�ɂȂ��Ă��܂��̂�����B �@�������C���������A��t�͐��l�������Ȃ������B�e��t�͈ꉞ�O�Ȃ̐搶�A���Ȃ̐搶�A�����Ȃ̐搶�ȂǂƂ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă͂������A���������ƂɊO�Ȉオ���Ȃ̊��҂���̎厡��ɂ��Ȃ�A���Ȉ�⏬���Ȉオ��p�̏���i���ɂ͏p�҂��I�j�����Ă����B�܂��t�͐��ɂƂ��ꂸ�A��{�I�ɊO���Ŏ������f�����҂���͂ǂ�ȕa�C�ł��낤�Ƃ��̎厡��ɂȂ�A�Ƃ����̐��������̂ł���B�ނ���t���m�A�R���T���e�[�V������c�_�͂��Ă������A�ꍇ�ɂ���Ă͎厡�オ�r���ŕς�邱�Ƃ����������A��ǂ͑�����ǂł���A�݂�Ȃŋ��͂��đS�Ȃ̊��҂����f��A�Ƃ����ł������B �����ł����Ȃ��Ă����@�� �@����ɁA�����̉@���̈�t�Ƃ��Ẵ��p�[�g���[�̍L���ɂ͋������B�O�Ȉ�ł���Ȃ���A�]�O�ȁA�Y�w�l�ȁA���`�O�ȁc�c���̎�p�ł����Ă����i�̂͂���������҂��������������炵�����j�B �@�ǂ����Ĉ�l�ł���ȍL�͈͂Ȑf�Â����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�����܂ł��Ȃ��Ƃ��A�����ł͂�����x�܂ł̐f�ÂɂƂǂ߂Ă����āA���Ƃ͖����������ɁA���n�̕a�@�ɔ����Ȃ�A�Љ��悢�̂ł͂Ȃ����A���C�����A���͂����v�������̂��B �@����ł���Ƃ��A���͂���ȋ^����@���ɂԂ��Ă݂��B�@���̘b�͂����ނˎ��̂悤�Ȃ��̂������B �\�\�����͓������A������������������A�ً}�̏d�NJ��҂��ȒP�ɂ͓��n�ɂ͉^�ׂȂ����ȁB���n�̕a�@�֏Љ��������Č��������ĂȁA���҂����Ƒ��̂��ƍl������A���������đ�ςȂ�B���ɂ͋���ɂ�Ȃ��Ƃ����o�Ă���B�����ǁA�a�@�̍̎Z���l����A�S�Ȃ̈�t���ق��킯�ɂ͂�����B������A�����Ȃ���Έ�ŁA�ł��邾���̐f�Â��ł���悤�ɂȂ��Ă����Ȃ���Ȃ�����B���ꂪ���҂���̂��߂ł������Ȃ����ȁB������\��N�O�ɂ��̕a�@���ł���ȑO�A������p�ɂɊ��҂��������܂Ŕ�������Ă����B�����炱�̕a�@���ł����Ƃ��A�Ƃɂ������҂���ً̋}�������ł��邾�����Ȃ����悤�ƍl������\�\ �@���̌�A�����ł̐����������Ȃ�ɂ�A��������ɉ@���̍l���������ł���悤�ɂȂ����B �������̐�����͋߂��̑����f�È� �@���āA���������ɕ��C���Ăقڈ�N���o�߂����P�X�X�V�i�����X�j�N�P���́A����y�j���̌ߌ�̂��ƁA�܂��ɂ������������f�Â̎����ƂȂ�悤�Ȋ��҂��~�}��������Ă����B �@�T�Q�Βj���B���������ł��āA�ӎ��s���̏d�́B�������������N�����Ă����BCT�����̌��ʁA�f�f�͋}���d���O����B�]�̂܂��̍d���Ƃ����d�����̊O���Ɍ��t�����܂�����ԂŁA�ً}��p�����Ȃ���قڂP�O�O�����S���鎾���ł���B �Ƃ��낪�����ɂ��A���̓��͉@���A���@�����s�݂������B �@�@���Ȃ炷���Ɏ�p�����邾�낤�A���͂����v�����B�����̓��Ȃ̈�t�Ƒ��k���A���ǁA���O���������Ă��Ă͎��ԓI�ɊԂɂ���Ȃ��A�����Ŏ�p������ׂ����A�Ƃ������_�ɒB�����B�Ƒ��ɂ́u���ɂ͔]�O�Ȑ��オ���܂���B�������A���O���������Ă��Ă͎�p���n�܂�܂ʼn����Ԃ��������Ă��܂��̂ŁA���̕ۏ��ł��܂���B�O�Ȉ�ł��鎄���������܂��B���̕����A���҂�������m���͍����Ǝv���܂��v�Ƃ����|�����b�����āA�������B �@��p�͂��܂��������B���҂���͂��̌�A���̌��ǂ��c�����ƂȂ��A�����ɑމ@���邱�Ƃ��ł����B���Ƃł��ً̋}��p�̂��Ƃ��@���ɕ�����ƁA�u�悭������A�撣�����ȁv�Ƃ��J�߂̌��t�������������B �@���̏ǗႩ��A���͑����f�Â̑����g�ɂ��݂ė��������B�ʏ�Ȃ�A���̊��҂���͎��q���ɍq��@������v�����A���n�̕a�@�֑����Ă������낤�Ǝv���B�������O�q�̂悤�ɁA���q���ɔ�����v�����A���ۂɎ�p���n�܂�܂łɂ́A���̐��x�ł͉����Ԃ��������Ă��܂��̂ł���B�������Ŏ�p�����Ȃ��ł��̊��҂������n�ɔ������Ă�����A�����炭���̓r���Ŕ]�w���j�A���N�����A���S���Ă������낤�B �@���́u�o�����v�́A���̌�̎��̈�t�����̌��_�ƂȂ����B�~�}���҂̏ꍇ�A�u�����̐�����͋߂��̑����f�È�v�ł���A���̕������҂���̂��߂ɂȂ�A�Ɗm�M�����B�i�������A���������ً}��v����~�}���҂̎�p����O�̈�t���s�Ȃ��Ƃ����̂́A��͂藣���̂悤�Ȋ��҂���ً̋}�������ނ��������Ƃ���Ɍ�����ł��낤�B�~�}�Ԃŏ��Ȃ��Ƃ��P���Ԉȓ��ɑ�a�@�֔����ł�����ł́A�������������͑����ʂ�������Ǝv���j �@���̈�t�Ƃ��ẴL�����A�̂����A�����ȏオ�����ł̂��̂ł���B���������Ăǂ����Ă��A���Ȃ���t�Ŋ��҂�����ǂ��f�邩�A�Ƃ������ϓ_�����Â����邱�ƂɂȂ�B �@��t�̏��Ȃ������̐f�Âɂ������đ�Ȃ��Ƃ́A���҂���𑍍��I�ɐf��Ƃ������Ƃł���B���ɂ�������Ă͂����Ȃ��B���Ȉゾ���珬���͐f�Ȃ��A�O�Ȃ͂��Ȃ��A�ł͍ς܂Ȃ��̂��B���ǁA�����ɂ���ƈ�t�̐��ȂǂƂ������̂͂����������Ȃ̂���A�Ƃ����C�����Ă���B �@ ���ł��j�[�Y�̍����f�ÉȁA����́u���ł��f�܂��傤�ȁv �@�������Ĉ�t�ƂȂ��ď\���N�A�����ł̈�Â𒆐S�Ƃ��āA�Y�w�l�ȁA�O�ȁA���`�O�ȂƓn������Ă����B�܂������̉ȈȊO�̊��҂�����A����܂ő����f�Ă����B���̂悤�Ɏ��͊Ԍ��͍L���̂ł����A�c�O�Ȃ��炻�ꂼ��̉Ȃ̃X�y�V�����X�g�ɂ͂�����̕���ł��A���̐��I�\�͂ł͂��Ȃ�Ȃ��B���������Ӗ��ł͒��r���[�Ȉ�t�ł���B �@�������A�S�Ȃ𑍍����Đf��_�ł͒N�ɕ�����Ƃ��v��Ȃ�����������B�悭���҂���u�搶�͂����ȉȂ̊��҂����f�Ă���݂��������ǁA���͉��ȂȂ̂ł����v�ƕ�����邱�Ƃ����邪�A����Ȏ��ɂ́u���[��A���ł��f�邩�燀���ł��f�܂��傤�ȇ��ł����ˁv�ȂǂƓ����邱�Ƃɂ��Ă���B �@���݁A���{�ɂ͖�Q�T���l�̈�t�i��Î{�݂ɏ]�����Ă����t�F�Q�O�O�Q�N�u��t�E���Ȉ�t�E��t�����̊T���v�̒������ʂ��j������B�����炭���̂قƂ�ǂ̈�t���A�u���́����Ȃ����ł��v�Ƃ���������̉Ȃ̕W�Ԃ����Ă��邱�Ƃ��낤�B �@������������ł͂��邪�A�ł݂͂Ȃ���́A���A�Љ�̒��ň�ԃj�[�Y�̂���̂́i��Ԑl�C������A�Ƃ����킯�ł͂���܂���j���Ȃ̈�t���Ǝv���邩�B �@���͂��ꂪ�A�N���W�Ԃ͂��Ă��Ȃ��u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t�Ȃ̂ł���B���ɋ~�}��Â̏ꍇ�A��Ԗ��ɗ��̂͂��́h�ȁh�̈�t�B �@�~�}���҂͂����������Ȃɑ�����a�C�Ȃ̂����킩��Ȃ����Ƃ��������̂ł���B�˔��I�ȕa�C��P�K�ł́A��������ł��邩�킩��Ȃ��B�����ȂƂ����T�O���Ƃ肠����������͂����A����Ă������҂�����_��ɐf�@����K�v������̂��B �ȑO�A�d�q�^�~�}�a�@�Ɍ��C��Ƃ��ċΖ����Ă����Ƃ��A����Ȃ��Ƃ��������B �@���銳�҂��f�������āA�~�}��������Ă����B����f�����Ȃ�A��t�̕��ł͕��ʂ͈݂��\��w��������ɏo���̌�������ƍl����B�����炻�����˂�������������Ă����B �@�Ƃ��낪�A���̂Ƃ��ꏏ�ɂ������̎w����͔]�O�Ȃ̈�t�������B������̂��Ƃ͂قƂ�lj�������Ȃ��B�ނ͎��ɋ��B �u����CT���B��I�v �u���A�ł��f���̊��҂���ł���v �u�f���ł��A���̕a�C����N���邱�Ƃ�����A���Ƃ��Δ]���o���Ȃ��Ƃ����Ɉݒ�ᇂƂ��ł���̂́A���O�����Ēm���Ă��邾��v�Ƃ̂��ƂŁA���̊��҂���͓f���œ����Ă����̂ɁA�Ȃ�Ɠ��̕a�C���܂��^���Ă��܂����̂ł���B �@CT�����ŁA���ɂ͉����ُ킪�Ȃ������B���ǁA������O�Ȃ̎w����ɑ��k���A�݂̓������������s�Ȃ����Ƃ���A�݊������������B�f���̌����́A�c�O�Ȃ���i�s�����݊�����̏o���������̂ł���B �@ �t�ɁA����Ȃ��Ƃ��������B �@��͂茌��f�������҂��~�}��������Ă����B�������A���x�͓f���Ƃ������͍����ۂ��������ʓf���������B��������C�ɂȂ����̂́A���҂���̈ӎ��������낤�Ƃ��Ă������Ƃ������B �@���̂Ƃ��̎��̎w����͏�����O�Ȃ���Ƃ����t�ł����B�w����͎��Ɍ������B �u�����Ǐo������A�Ƃ肠�����݂̓����������A����Ă݂悤�v �@�����������ŁA�������Ɉ݂���̏o���͂���܂����B�������A�ӎ��������������Ƃɋ^������������́A���̈�t�ɏ�\���܂����B �@�u���̈ݒ�ᇂ͔]���o������̓I�Ȃ��́i�]���o���ɂ��X�g���X�ɂ���ċN������́j�ł͂Ȃ��ł��傤���B����CT���B���Ă݂܂��v ���ʂ͂�͂�]���o���������B �@���̂悤�ɁA��t�Ƃ����̂͂Ȃ܂����ӕ��삪����ƁA�ǂ����Ă��������犳�҂����f�悤�Ƃ��Ă��܂����́B���̂��߁A�v�������Ȃ���f�����Ă��܂����Ƃ�����B���ɋ~�}��Â̏ꍇ�A�����Ŋ��҂����f���t�͂Ȃ܂����ȂǂȂ������A�������ċq�ϓI�Ȋ�ŁA���҂���̑S�̑��𑨂��邱�Ƃ��ł���̂ł���B �@�~�}�O���Ŗ��ɗ��̂̓x�e�����̐�����A���܂��܂ȉȂ����[�e�[�g���C���Ă����O�`�l�N�ڂ��炢�̎Ⴂ��t�ł���B�ނ�͂܂�����قǐ����ɂ߂Ă��Ȃ��̂ŁA���R�Ȕ��z�Őf�Â��ł��邩��B����������t���������u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈���ł͂Ȃ����A�Ǝ��͏���Ɏv���Ă���B �@����̐��������Ȃ����������u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t�������A���͈�Ԃ̃j�[�Y�̂����t�Ȃ̂ł���B�����Ă��������j�[�Y�͉����~�}��ÂɌ��炸�A�ǂ�Ȑf�Õ���ł��A�ǂ�Ȓn��ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B ���Ȃ����A�c���D�R�g�[�Ȃ̂��H �@�Q�O�O�R�i�����P�T�j�N�A�u�c���D�R�g�[�f�Ï��v�Ƃ����e���r�ԑg�����f����A�傫�Ȕ������ĂB�����ŁA��������l�ő劈��A���̊O�ȂɌ��炸�K�v�ł���ΎY�w�l�Ȃ�]�O�Ȃ̎�p�܂ōs�Ȃ��A�܂��Ɂu���ł��f�܂��傤�ȁv�̌����̂悤�Ȉ�t�c���D�R�g�[�𒆐S�Ƃ��鈤�Ɗ����̕���ł������B ���̔ԑg�͂Ȃ�����قǃq�b�g�����̂��낤�B �@���҂���͐���̐f�@����苁�߂�悤�ɂȂ��Ă���A��t�̐�含����苁�߂�悤�ɂȂ��Ă���A�ƌ����Ă���B����Ȃ̂ɁA�Ȃ��������������Ƃ͐����̈�t�ł���c���D�R�g�[�Ɏ����҂͎䂫����ꂽ�̂��낤���B �@�����̐g�̂̂��ׂĂ�f�Ă�����t�A�Q�S���ԁA�e�g�ɂȂ��Ă�����ƑΉ����Ă�����t�A�Ƒ����a�C���������Ă��A�قƂ�ǂ̐f�Â��s�Ȃ��Ă�����t�A��ɂ����Ȃ��d�NJ��҂͂��݂₩�ɃX�[�p�[����ɏЉ�Ă�����t�i�������A���ł����ׂĎ����ōs�Ȃ��Ă��܂��u�u���b�N�E�W���b�N�v�Ƃ͈قȂ錻���I�ȂƂ���j�A�c���D�R�g�[�͂���炷�ׂĂɂ��Ă͂܂��t�ł������B �@���̂悤�ȁu���ł��f�܂��傤�ȁv�I��t�����A���͈�ʂ̕��͋��߂Ă���̂ł͂Ȃ����B�����������ݓI��]���u�c���D�R�g�[�f�Ï��v�̐l�C�̔閧�ł͂Ȃ������̂��A�Ə���Ɏv���Ă���B �@�c���D�R�g�[�������u���ł��f�܂��傤�ȁv�I��t�̗��O�^�ł���B�����āA����������t����l�ł������Ă����i�c���D�R�g�[���݂̂��Ƃ܂ł���Ă��������Ƃ͌���Ȃ����ǁj�A�����Ă���������t�ɂ��`�[����Â����W���Ă����Γ��{�̈�ÁA�Ȃ����~�}��Â͂ƂĂ��悭�Ȃ��Ă����͂��ł���B���炢�܂킵�Ȃ����͂����Ȃ��B�����Z���^�[�a�@�Ȃɍs���Ȃ��Ă��A�߂��́u���ł��f�܂��傤�ȁv�`�[������������Ɛf�Ă����A����Ȉ�Âł���B �@�c�O�Ȃ��炵�����A���{���l���Ă����Ð���͂��������l���Ƃ͐����̕����Ɍ������Ă���B �����ׂĂ̎����ɑΉ��ł����t�� �@���݂̓��{�̕a�@�̕a���́u�}�����a���v�Ɓu�×{�^�a���v�̓��ނɑ傫���������Ă���B�}�����a���͎�ɂ��ꂼ��̐��Ȃ̈�t���f�Ă��邪�A�×{�^�a����f�Ă���͎̂�ɓ��Ȃ́A����������Ă��͔N�z�̈�t�ł���B �@����Ȃ���A����������t�ɇ���Ç��͊��҂ł��Ȃ��B���Ƃ��A���҂��}�ς������ɋC�Ǔ��}�ǂ����ł��Ȃ��ł��낤�i���̕������b�����A�a���ŐS�x��~�ɂȂ������҂���ɁA����V��t���C�Ǔ��}�ǂ������A�u�e���v�`�[�N�������Ă����v�Ƌ���ŁA�Ō�t���������R�Ƃ��������ł���B����ȃN�X���A���ł͂Ƃ����Ɏg���Ă��Ȃ�����ˁj�B �@�×{�^�a���Ȃ炽�����Ĉ�Â��K�v�Ȃ�����A�V��t�ł��������낤�A�Ƃ̔��z���炱�������ɂȂ��Ă���悤�ł���B��Ғ��Ԃł��A�u�����A�������́h�V�l�a�@�h������A����������搶�ł������v�Ȃ�Č����Ă��邩��ˁB �@���{�̈�ẤA�V�l�ɃJ�l�������Ă���悤�ŁA���͂���Ȏ蔲�������Ă���̂��B���������̈�t��u���Ă��������ŁA�ǂ�Ȉ�Â��ł��邩�Ȃǂ͂܂�ŔO���ɂȂ��B��҂����u���Ă�������Ő��Ԃ͂��܂����邾�낤�A�Ƃ������z�ł���B�������A�×{�^�a���������Â͂���Ȃ��A�Ƃ������z�͑傫�Ȃ܂������ł���B �@�×{�^�a���ɓ��@���Ă��銳�҂���͂��N���䂦�A���낢��ȕa�C�������N�����B�x�b�h����]�|���ĉ�������邱�Ƃ���������イ�B�����ꂾ���Ă悭�ł���B���������V�l�́A���͋~�}���҂̗\���R�Ȃ̂ł���B��������ȁA���`�O�ȁA�畆�Ȃ𒆐S�ɁA���ɂ͕w�l�Ȃ܂Ŋ֗^���Ă���Ƃ����A���ł�����A�܂��Ɂu�a�C�̃R���r�j�v�ł���B �@���������j�[�Y�ɓ��Ȃ̘V��t���Ή��ł���͂����Ȃ��B�܂��Ɂu��҂͂���Lj�҂͂��炸�v�̏�ԂȂ̂��B �@����Ȃ�o���o���̐����u���Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ邪�A������_���B����͐l�Ԃ̓���̑����a�C�����̐f�ÑΏۂƂ��邩��A��͂�×{�^�a���̂��܂��܂ȃj�[�Y�ɂ͉������Ȃ��B���̐�含�����ɂ́A�����悤�ȕa�C�̐l���W�܂��Ă�����łȂ���Ȃ�Ȃ�����ł���B �@�������u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t�͗×{�^�a���̂悤�ȁA�a�C�̃R���r�j�I�Ȋ��ɂ͂����Ă��ł���B�����u���ł��f��v�̂�����B����������t���P�l����A�����炭�P�O�O�l��Q�O�O�l�̗×{�^�a���ł��A��������Ƃ������҂���̊Ǘ����ł���͂��ł���B������W�߂���P�O�l�͈�҂��K�v�Ȋ��ł��A�u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t�Ȃ�P�l�Ȃ����Q�l���炢�ŏ\���Ȃ̂ł���B �@���͈ȑO�A���_�ȕa�@�ɔ��Έ�t�Ƃ��ċΖ��������Ƃ�����B�a�����Q�T�O���̂��Ȃ�傫�ȕa�@���������A�����̉@�����ق������Ă����̂��u���_�ȈȊO�̂��ׂĂ�f�Ă�����t�v�ł������B �@���_�ȕa�@�Ƃ͂����A���@���҂͂�͂�V�l�������A���ȁA�O�ȁA���`�O�ȁA��A��ȂƂ������e�Ȃɂ܂����鎾��������Ă���l�������B �@���������������ׂĂ��Ǘ��ł����t���@���͋��߂Ă����B����ɂ����Ă��Ȃ̂��A���̎��������B �@�������e�Ȃ��ꂼ��̈�t�����낦�悤�Ƃ���A���l���̈�t��K�v�Ƃ��Ă��܂��B����ɂ͂��������a�@�̏ꍇ�A�厡��͊�{�I�ɐ��_�Ȉゾ����A�ǂ����Ă����@���҂̐g�̎����S�̂��Ǘ��ł����t���K�v�ƂȂ��Ă���̂ł���B �@�Z�����ԂŁA�������T���̔��Ƃ����`�ł̂���`�������ł��Ȃ��������A�u���ł��f�܂��傤�ȁv�����̂��鎄�́A�Ō�t�Ɋe���҂̖��_�����ڂ��Ă��炢�A�W���I�ɊǗ������܂����B�݂낤�i�݂ɒ��ډh�{�𑗂�`���[�u�����邱�Ɓj�̑��݁A�O���B���E�̑��K���Ȃǂ̊��҂���̊Ǘ��A�ݓ������A�G�R�[�����₶�傤���n��n���̊Ǘ��A���̂ق��ł�����ő���̂��Ƃ��s�Ȃ����B�����炭�e�Ȃ̈�t���l���̎d���͍s�Ȃ�������ł���B �@���������u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t�͂܂��A���ɗ����E�ւ��n�A���邢�͂����܂ł����Ȃ��Ƃ���Éߑa�n�ɂ����āA���ȈЗ͂�����B���������n��ł͐l�����x�����Ȃ����߂ɁA�l�����W�n��̂悤�Ɋe�Ȃ̈�t�����낦�邱�Ƃ�����ł���A��l�̈�t�������̐f�ÉȂ��J�o�[������������ɂ��ēs�����悢����ł���B ����t���������Ă���̂Ɉ�t�s���Ƃ͉�����H ���{�̈�t���͑��������Ă���B 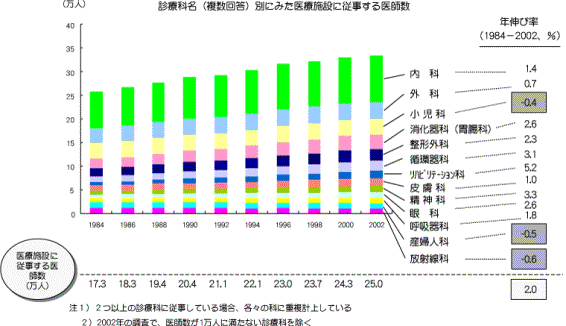 http://www.kosonippon.org/prj/med/think/hito/hito1.html������ �����F�����J���ȑ�b���[���v��u�����P�S�N��t�E���Ȉ�t�E��t�����v���쐬 �@�������A��t�s���͂��������ɉ������Ȃ��B����ǂ��납�[���ɂȂ����B���ɉߑa�n�Ȃǂł͂������҂������Ă��A�����ς��t������Ă��Ȃ��B����͂ǂ����ĂȂ̂��B �@�悭������̂��A��t���s��ȂǂɏW�����Ă���A�Q�O�O�S�N�x����̐V������t���C���x�Łu��t�͂����v���s�Ȃ��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B�������A���R�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B�u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t�����Ȃ��A���ꂱ���������Ƃ��傫�Ȉ�t�s���̗��R�Ȃ̂��Ǝ��͎v���B �@���ꌧ�̂��闣���̌����a�@�ł͖��N�A��t�s���ɔY�܂���Ă���B�����䂦�̈�t�s���ƌ�������͂����Ȃ̂����A���͂��̕a�@�̈�t�s���̖{���̌����͕ʂ̂Ƃ���ɂ���B �@���̕a�@�͕a�����T�O���A��t�̒�����T���ƂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A���̕a�@�͂T���̈�t��������Ă��Ă���t�s���A�ƌ����Ă���B �@�Ȃ����B�W�҂̘b�ł́u�T���̈�t�ł͑���Ȃ��B�P�S�C�T���̈�t���K�v�ł���B�e�Ȃ̐f�Ñ̐����[�������邽�߂ɂ͂��̂��炢�̈�t������v�Ƃ̂��Ƃł���B�T�O���̕a�@�ɂP�S�C�T���̈�ҁI�@��t�P�l������̓��@���҂��R�C�S�l�B�s��̕a�@�����āA����Ȃ��������ȕa�@�͂Ȃ��B�ǂ����A�����Șb�B �@�ł́A�Ȃ�����ȂȂ����̂˂�������Ĉ�t�s���Ȃǂƌ����Ă���̂��B�����Ɉ�t�̐�含�������ł���B�l���̏��Ȃ������Ȃ̂ɁA�e�Ȃ̐����S�����낦�悤�Ƃ��邩��A��t�s���Ɋׂ�̂ł���B�܂���t�s���Ƃ����̂́A��t�̐�ΐ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�e�Ȑ��オ����Ȃ��A�Ƃ��������Ȃ̂ł���B �@�ł͂��̗����Ɂu���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t���O�l����Ă�����A�ǂ����B���_�A��҂��l�ԁA���ꂼ��ɓ��ӕs���ӂ͂��邪�A�R�l�����͂��ĕ����Ȃ��J�o�[���邱�ƂɂȂ邾�낤�B���Y�����Đ��핪�Ȃ�f�邵�A�����Ȉ�łȂ��Ă������̐f�Â͂�������f��B�O�Ȃ��A���`�O�Ȃ��A�]�O�Ȃ��A������x�܂ł̎�p�Ȃ�\�ł���B��l����p�ɓ����āA�c��̈�l���O���ƕa����f��̂ł���B�����͂R���ɂP��ł�����Ƒ�ς�����ǁA���̌o�����猾���A�l���P���l�ȉ��̋K�̗͂����Ȃ�A�s�\�ł͂Ȃ��B�����ĐS�؍[�ǂ�A���������o���Ȃǂ̂悤�ȋً}���̂���d�NJ��҂݂̂��w��������������̂ł���B �@�ł����ł���B�O�l�ŁB�������l���]��B�ł���A���ƂP�l�����悤�ȁu���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t������A���]�T�B �@�܂�A��t�s���Ƃ����͈̂�t�̐�ΓI�l�����s�����Ă���̂ł͂Ȃ��A��t�P�l�ЂƂ�̎���͈͂��������āA���ʓI�ɑ����̈�t��K�v�Ƃ��Ă���Ƃ����̂ɂ����Ȃ��̂ł���B�u���ł��f�܂��傤�ȁv�̈�t��������A��t�s���ȂA�����ǂ���ɉ�������A�Ǝ��͎v���Ă���B �@�����������Ƃ͓s��ł͂Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ����A�l�������Ȃ��A�O�E�Ɗu�₳��Ă��闣���ɂ���Ƃ悭�����Ă���̂ł���B TOP�y�[�W�� �n���Ẫy�[�W�� �I�͂��̂Q�� �O�y�[�W�� |