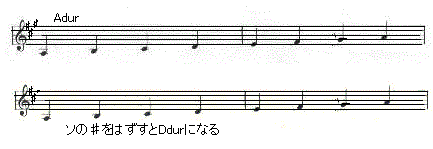|
教会旋法のページでご覧頂いたように、現代の長調、短調はもともと教会旋法より抽出されてきたものだった。その中で、長調が比較的早く音階として固定したのに対し、短調はなかなか一つの音階に定着しなかった。今でも楽典には短調には自然短音階、和声的短音階、旋律的短音階の三種類が書かれている。つまり短音階というのは、今日でもかなりあいまいなままなのだ。これはなぜだろうか。
最大の理由は導音の問題であると思う。長音階の場合は、音階の7音と8音の間が半音となるので、導音を作るにあたって問題はなかった。ところが短音階の場合、それは全音となるのである。そのために短調の楽曲の場合、導音を作るためにはどうしても第7音を半音上げざるを得なくなる。これすなわちこれは和声的短音階である。
しかし、この和声的短音階をピアノで弾いてみるとどうも流れが不自然である。それは、第7音を半音上げてしまったために、第6音と第7音の間が結果的に短3度と同じになってしまったから。そのために、それなら第6音も半音上げてしまおう、というわけで旋律的短音階ができた。これは旋律的といわれるだけあってさすがになめらかに聞こえるが、音階の後半は結局長音階と同じである。長音階との違いは第3音が半音高いか低いかだけとなる。但し、この旋律的短音階は、下りは自然短音階と同じになる。下りの場合、導音を作る必要はないからである。



このように現代でもあいまいさが残る短音階であるため、バッハの時代には短音階はまだまだ鬼っ子的存在であった。ピカルディ終止などというものが残っていたのもこうした理由からである。短調で楽曲を終わらせることに対し、バッハの時代の人たちはまだまだ抵抗があったのである。
こうした短調の不安定さはマタイ(に限らないが) の短調の曲の変位記号の数に現れている。前ページで書かれているように、現代の記譜法にくらべ、♭記号が一つ足りないのである。この現代とちがう慣習もまた短音階の不安定さに由来している。
短音階では第6音と第7音が鬼門であることはさきほど述べた。この2音が曲の状況に応じて半音あがったり下がったりするのである。これは短音階の宿命ともいえる。
たとえばDmollの曲を考えてみる。この調の場合、シが♭になる訳だが、短調のこととて、つねにフラットされるとは限らない。ナチュラルのシの場合も多いのである。もしこのシがナチュラルであるとすれば、これは結局Amollの曲と変わらなくなる。ならば調号の♭は必要なく、ト音記号のとなりに書く必要はないではないか、ということになる。つまり短調の曲の場合、短音階の第6音がナチュラルになるのを前提として記譜がされていたわけである。第6音をナチュラルさせると和声学の法則により、フラットはひとつ減ることになるからである。
この記譜法は一般的だったのはバッハまでだったのであろう。古典派に入ると次第に短調も認知されるようになり(それでもモーツァルトなどは短調の曲はほとんど書いていない)♭をひとつ減らして記譜する慣習もなくなっていった。
さて、最後に実際の譜例を見てみたい。下譜はマタイの26番の通奏低音からとったものである。下譜からわかるように、この曲の通奏低音は第2小節では自然短音階、第2小節から第3小節は旋律的短音階、第10小節では和声的短音階になっていることがわかる。


P.S
●元来、臨時記号の使用は控えめだった
ところで、臨時記号がひとつ少なめのつけられたのは、長調においても見られた。たとえば、1760年と1778年の間に、英国のDr.Boyceによって出版されたカテドラル音楽の標準的コレクションにおいて、本来3つの♯が使われるはずのAdurのアンセムが、2つの♯記号で書かれていた。導音は、ことごとく臨時記号のマークによって示されたのである。こうした不便を忍んででも、譜表全体での臨時記号の表記は”嫌われていた”のである。(EARLY BODLEIAN MUSIC DUFAY参照)
元来、臨時記号は、ふたつの目的のために使われはじめた。すなわち、causa necessitatis(必要性のために;たとえば三全音の忌避のために)と causa pulchritudinis(美しさのために;たとえば導音導入のために)である。(TUDAR MUSIC6 p164参照) そして、近代和声学が確立するバロック期以前には、それは元来、必要悪的な側面があった。
そのために、その記譜を必要最小限に留め(譜表全体に効かせる場合と、個々の音符につける場合とがある)、ある程度以上は、musica fictaとして、演奏者の手に委ねた。(現代での楽譜再構成ではだから、いつもこれが問題になる)。
ことに、譜表全体への臨時記号の記譜は、必要最小限が徹底していた。そのために、各声部で♭記号の数が異なるという、近代和声学ではあり得ないことが、まかり通っていた。(THE FUNCTION OF CONFLICTING SIGNATURES IN EARLY POLYPHONIC MUSIC2 By EDWARD
E.LOWINSKY参照)
臨時記号への忌避は、このように臨時記号発声とともにあり、したがって、15世紀前半のデュファイの時代においてすでに、それはあった。
16世紀になると、臨時記号のいわゆる”連鎖反応(三全音の回避のために、つぎつぎと♭をつけていかざるを得なくなること)が問題になり、こうした側面もまた、臨時記号忌避の要因になったといえよう。(Musica Ficta6P121 参照)
以上のように、臨時記号は、すでに完全に調性音楽が確立した18世紀においてなお、近代譜のようには書かれなかった。
また短調では、旋律的短音階を作るために第六音の半音上げが必要となり、結果的に♭が減ることになったが、長調の場合、もともと導音を記譜化する習慣がなかった(musica
fictaとして処理された)ために、♯がひとつ減ることになった。(たとえば、Adurの場合、ソが導音化されてソ♯となるが、その♯を省略すると、近代和声学では、♯2つのDdurと同じ♯数となる)。
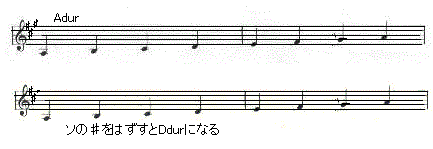
|