| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC1 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | |
| Leoninのページへ | |
| ペロタン(Alleluja Nativitas) | 中世音楽のページへ |
| substitute clausulaのページへ | Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC2へ |
| Studies in MEDIEVAL and RENAISSANCE MUSIC1 ex.3 |
| Two Forteenth-Century Motets on St. Edmund East Angliaの王、英国人殉教者St. Edmund(d.868)の祝日は、1013年の英国の典礼で導入された。そして、その年以来、彼の死である11月20日に、特別な礼拝が歌われることになった。 彼の名誉のために作曲された音楽には、plainchant作品とポリフォニックの作品が含まれており、この2つの興味深い組み合わせが、本章の主題である。 Bodleian図書館のMS E Museo 7には、14世紀初頭の2つのモテットが含まれている。1つは3声のDeus tuorum militum-De Flore martyrum-Ave Rex gentis 、もう1つは4声であるAve miles-Ave rex patrone-Ave Rexである。 本章の最後に両者の譜が書かれている(http://machikun.la.coocan.jp/bukofzerex3.htm)。 その断片はもともとBury St. Edmundの修道士に属していたため、St. Edmundに捧げられたのは驚くことではない。 モテット同士の典礼的なつながりは、同じフォリオ上で直接的に連続して書かれていて、外部的に示されている。 p18 さらに、テノールのincipitsは、その声部が同じプレインソングを使用していることを示唆している。テノールのメロディーの比較は、それらが実際に同じであることを示している。しかし、同じなのは最初の部分のみで、その後、別になっている。それらは同じチャントを使っているのだろうか? この質問に答えるためには、プレインソングのソースを決定することが不可欠である。バチカンの参考書類は、私たちを見捨てている。それらはそのタイトルのチャントをリスト化していないので。回答のためには、Sarum useに関する典礼書に目を向ける必要がある。この場合は多くのものと同様、、それらは、中世の英国音楽の研究に欠かせないことを証明している。 Worcester Antiphonal と Antiphonale Sarisburienseの両方が、聖エドモンドにあるAve rex gentis Anglorum という名のAnthiphonを記録している。現在見られるように、両方とも、テノールのソースである。 私が慎重にチャントをコピーしたとき、私は,メロディーとテキストがおなじみのringを持っていることに気付いた。 Ave rex gentis Anglorumは、音楽においても、テキストでも、Marian antiphon Ave regina caelorum、mater regisとよく似ている。モテットのテノールと最もよく一致するAve rexのWorcesterバージョンは、Edmundian形式とMarian形式のテキスト両方で以下のようである(例1)。 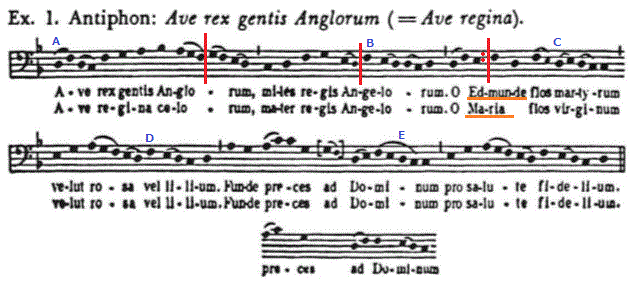 Antiphonale Sarisburienseの版は、いくつかの点で異なっている。それは、かぎカッコで表示されている。 p19 歌詞preces ad Dominumの部分の変異は、15世紀の簡略版を代表している。 Sarum Processionalsに見られるように。 Marian antiphonのバチカンのメロディーは、Sarumのバージョンとまったく一致していないが、ここに記す必要はない。 印刷物に簡単にアクセスできるためである。すべての既知のバージョンのantiphonの基本的な音楽的同意は、テキストの類似性同様、明白である。 実際に、最初の行の数語だけが異なる。 改定は、可能な限り、文字の変更でなされた。rex gentisはreginaに対応し、miles は materになっている。 残りの部分は言葉も同じである。 2つのantiphonのプロトタイプはどちらであろうか?Marian形式だけが有名になったので、これが元のものでなければならないと考えるのは当然である。しかし、ソースが不完全であるために、この仮説に疑問を投げかけられている。Edmundianの形を記録している2つのSarumのantiphonalは、13世紀のみに属している。 Chevalierによれば、Marianの最も初期の出典は、 14世紀からであるが、W1写本の第11番冊子の2声設定は、それが少なくとも13世紀の後半に存在したことを証明している。Marian形式は、15世紀に処女マリアの強められた崇拝と顕著に上昇し、その時さかんにポリフォニーに設定された。 15世紀と16世紀のSarum の行列は、マリアン形式のみを伝えている。この時期には人気があって他のものをはるかに上回っていた。 しかしながら。Edmundの形式は1531年のSarum Breviaryにも記録されている14。それは15世紀の英語のキャロルにはburdenとして現れる15。したがって、15世紀と16世紀にはまだ忘れられていなかった。 14 同じソースは、こちらでは、St.Albanに対して改作されたアンティフォンの4番目の変異が含まれている。テキストはAve prothomartyr Anglorumで始まり、正確にEdmundの形式が続く。 15 Greene, The Early English Carols , Carol No. 312. See also p. lxxxiv. p20 適切な文書の欠如は決定的な結論を導かないが、antiphonの英語起源は、少なくとも可能性があるものとみななければならない。それはもともとSt. Edmundの名誉を込めて作られたもので、より一般的なMarianの使用に後で適応し、Marianの形で大陸に導入されたのかかもしれない。この提案は、間接的に、後者のテキストが俗語とラテン語が混じったキャロルによって完全に借用されているという事実によって支持されている。16 16 Greene , op. cit . , Ixxxv . The Marian formはまた記録されていないトロープスFunde virgo(OS fol.13)とともに、英語作品に、現れる さらに、Ave regina の初期のポリフォニック設定の大部分は、英国の作曲家に由来している。チャントの言葉は完全に発達した韻を示しているため、12世紀以前ということは、あり得ない。議論されている2つのモテットについては、優先順位の問題は重要ではない。Edmundの形がプロトタイプであることが証明されれば、それらの根底にあるプレインチャントでさえも英語になるであろう。 これら2つの作品は、1300年前後のイングランドで流行した、いわゆる "Petronian"または "Fauvel"記譜法で記譜されている。これは、breveを分ける短い音符の数を示す点によって特徴付けられる。この表記は、上の声部における厳密なモードパターンのbreakdownと、より小さな単位のbreveの分割と同じペースで発達した、より微妙で多様なリズムへの転換を示す。 4声部のAve milesは、2または3のsemibreveに分割することができないので、リズムの観点においては、保守的なモテットということになる。 Deus tuorumでは細分は5,6にもなり、急速なcoloraturaとparlandoを交互に必要としする。しかし、両方のモテットでは、モード・リズムの潮流はそれにもかかわらず、4声作品ではまだ知覚可能であり、より強くそうである。 和声的には、モテットはモテット書法において、英国の六度のコードスタイルが徐々に侵入している。 13世紀の和声スタイルを特徴づける各perfectionの初めの逆進行と協和音程の重視は、ここでは三度または六度を導入する傾向や逆進行同様の平行進行や、並行3/6和音で弱められている。これらは、ゴシック様式の音楽の目的と効果的にバランスを取って、フランにおいてイギリスよりも普及していた音域、色彩、そして特にリズムを使って声部を差別化した。blending intervalと、まったくの響きの音色への感受性を持つ英国の作曲家たちは、和声や「ハーモニック」エフェクトと呼ばれるものに忠実に従っていた。彼らはPetronian様式のリズム改革からは完全に離れていたが。 p21 <Deus tuorum militum イソリズムの嚆矢> このpointはDeus tuorum militumにはっきりと現れており、3声のすべてのテキストで聖エドモンドを呼名している。 triplumの言葉は、今日の典礼の中で殉教者を記念して歌われる、よく知られている賛歌「Deus tuorum militum」をパラフレーズしている。 賛歌のメロディーはモテットでは使われていないが、テキストとの関係は非常に近く、次のパッセージからもわかるように、同じ思考の言い回しである。 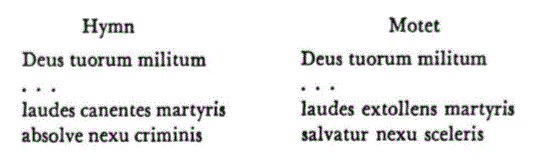 音楽を調べる前に、Fauvel記譜法では、semibreveのリズム解釈は確実ではなく、推測の問題であることを理解する必要がある。4声のモテットとして、3/4拍子で写譜されがちであり、これは音楽のリズムペースを強化することになる。2〜3のsemibreveのグループは、単純な2拍子グループと3拍子として、それぞれ同等に読むことができる。音楽を9/8拍子にする2つのグループの不均等な解釈が、ここで採用されている。なぜなら、5〜6のsemibreveの分割は、リズムの差を知覚するに十分なほどゆっくりすることを求められるからである。写本においては、4つ以上のグループの単純なsemibreveは、それらをminimに変えるcaudaに向けてマークされる。それらが描かれているあやふやなやり方から判断して、 caudaeはおそらく、ars nova記譜法に照らして、記譜法を改訂するための後の追加である。 p22 リズムの視点から見ると、motetusの De floreは最も”近代的”な部分である。 この声部だけが、breve の3分割を越えて、いくつかの活発なparlandoなパッセージを含んでいる。つまり、第14小節において。triplumは、より規則的なペースで控えめに動く。 最も遅い声部は当然のテノールであり、longs and brevesにて進む。第6小節を除いて。それは六度の和音の他の声部と共に動く。 テノールのリズムとプレインチャントの取り扱いには、さらなるコメントが必要である。何よりも、この声部は、最初のイソリズム構造が注目に値する。他の声部ではこれは見られない。プレインチャントの最初の2つのフレーズのみは、モテットの旋律的な基盤として機能する。それらは十分に忠実に提示されている。カデンツでわずかなメロディ展開がなされている。テキストは、写本中には不完全であり、チャントに対応して括弧で囲まれて記入されている。作曲家は、メロディーをそれぞれ7つの小節の3つのイソリズムパターンに分けている。校訂では、赤線によって示されている。最初の方の連結符は、各タレアで非常に厳密に繰り返され、最後のタレアの最後の小節のみがリズム的には正確ではないことが分かる。テノールは繰り返されている。コロルは写本では、明示的に要求されていない。 上声部は、タレアの規則性を完全に無視しているが、モテットの第2部分を構成するコロルがある程度見られる。これは、第2部分の音楽が第1部分の自由に変化したバージョンとして、明瞭に聞こえる。 ほとんどのperfectionの冒頭では、声部の位置の逆転のために余裕があれば、それぞれの進行はお互いにかなりよく一致している。さらに、第1部分の最後のタレアは、すべての声部で最後にほとんど文字通り再現されている。そのため、この形式は巧みに丸く削って滑らかにされている。 13世紀のモテットでは頻繁に起こることはないが。 その初期のisorhythmic構造と明瞭な形式では、確かに、Deus tuommはRoman de Fauvelの特定のモテットに類似している。(isorhythmicパターンがテノールに限定されている)。そして、厳密なイソリズム構造の登場を予見している。このモテットのコロルは単純な繰り返しである。そこには、diminution や augmentationは存在しない。それでも、1世紀後の完全なイソリズム原理は、すでに確立されていた。 p23 <Ave miles> 4声のAve milesは、大陸モデルに依存することが少なく、より典型的な英語の作曲テクニックを表示している。 BesselerとReeseのモテットについての議論では、すでに声部交換の役割について言及してきている。これは、英国の中世音楽で他のどの国よりも頻繁に出会うさまざまな繰り返しの奇妙なデバイスである。声部の取り扱いは、実際には、作曲の支配的な構造原理を表し、借用されたプレインチャントに関して、非常に特異的かつ高度に複雑さをもたらす。 モテットは、歌詞のついたantiphonの言葉をパラフレーズするポリフォニー的なトロープスに分類される。後者はおそらく典礼では、モテットによって置き換えられていたかもしれない。上声部は、antiphonだけでなく、同時にBenedicamus Dominoへもトロープスを形成するので、そのテキストは二重トロープスとみなされる。写本にはいくつかの トロープスモテットが含まれ、14世紀の英国の音楽では、音楽的トロープスである現存のいくつかのソースのうちの唯一のものである。。テキストのパラフレーズによる声部の相互同化は、声部の交換、すべての声部の中での同様の動き、Deus tuorumよりもはっきりとここで発音される三度や六度の和音などを融合することによって、音楽的に強化される。リズムの分化の欠如は、統一声部の印象をより強く普及させる。休符ととhocketにおける特定の部分だけが多様性の要素をもたらす。 Ave milesは、polytextual double motetの外観を持っているが、実際には言葉の連続したセットが1つしかない。交互にrecite あるいは vocalizeする2声の上に(2声が)広がっている。melisma的セクションと不変的テキストを含むセクションは、常に内部交換と一致し、したがって、音楽構造を明確にする。 テキストを持つ最上声部のあらゆるセクションは、初めて音楽を明言し、その間、下の声部は相互に模倣した新しいテキストの音楽を繰り返す。一対の上声部は、同様のテノールのペアにおいて、pendantを持っている。 p24 重要なのは、テノールの上の声部は、contratenorとは呼ばれず、 tenor secundusであることである。両声部の音楽は本質的に同じであるため、これは論理的な定義である。これらの構造部門はもちろん、上声部のものと並んでいる。モテット全体は5つの主要部分に分かれており、それぞれが交換で繰り返され、最後の5小節のコーダ(F)は、交換や繰り返しはない。小節の数によって示される各セクションの長さを持つ概略図は、以下のようである。 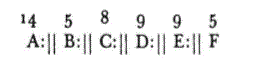 ここでの記譜法では、主要な部分は太い棒線で示され、かっこの上に縦のダッシュで繰り返し部分が示されている。 繰り返しは、声部のの取引によって影響され、音色の変化をもたらす。 声部交換は、非常に厳格になっている。それによって、筆記者の誤りを訂正することができる。 わずかな偏差は、音声が位置を切り替える点でのみ現れ、滑らかな移行のために、いくつかの音符が変更される可能性がある。 さらに、パートAの最後には不規則性がある。最初のセクションの14小節分は、声部交換の小節と同じ数だけ正確に回答されるが、冒頭に戻る15番目の重複する小節が続く。 残りは規則的で慣習的に進んでいく。 これすべては、テノールの声部のペアではないので、それほどの注目はない。声部交換のあるモテットでは、テノールは、上の声部の往復を許容ように作曲されなければならず、2つの下の声部があれば、それ自身の音楽のセクションの声部交換も可能にする必要がある。 こうした特殊条件は、テノールが特別に作曲されている場合に、最もよく満たされる。この種の殆どの作品では、実際にそうである。しかし、テノールがプレインチャントから借用された場合、繰り返しはやむを得ないものとなる。 p25 このような特別な事例は、モンペリエMS中の英国起源の2つのモテットBalaam inquit ,と Huic ut placuit."によって例示されるかもしれない。ここではテノールは、セクエンツィアEpiphaniam Dominoからのセクションを提示し、それは唯一の支持声部であるため、上の声部の声部交換に対応して、一貫して、繰り返されている。versicleのメロディーは全体は、毎回修正され、そのために、内部構造はそのまま残っている。 Balaam inquitの始めには、声部交換がテノールのメロディを進めていく短いセクションがある。しかし、versicleの最初の2つのフレーズがメロディ的に同一であるという理由だけで、これは可能となる。このモテットとモンペリエのモテットとの本質的な違いは、それらのテノールは、相互模倣に参加していないということである。 Ave miles では、状況はより複雑で、その理由から、はるかに興味深いものである。アンティフォンAve rex は、(Deus tuorum militumと異なり)完全に引き継がれているが、それが継続的に提示されてから繰り返されると、セクションが過度に長くなってしまう。 一方、チャントは、それ自体に対する対位声部として使用することはできない。他には何の代替もなく、メロディーをセクションに分け、それぞれに独立した対位声部を供与し、それらを声部交換で繰り返す。これが、まさに作曲家が行ったことである。 結果として、プレインソングのセクションは、声部が切り替わるときはいつも、自由に作曲されたセクション、すなわちもともとプレインソングへの対位声部であったものと交代しなければならない。その一方で、他の声部は(対位声部として)、プレインソングを再掲する。 下図において、その切り替えは前後に矢で示されている。ローマ数字で対位声部を示し、文字でチャントのセクションを示してある。 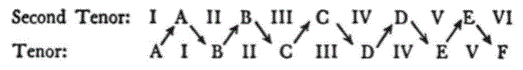 Motet Ave miles celestis このダイアグラムは、antiphonで始まり、終わり(A-E)までそれを担うテノールが、補間されたセクション(I―V)によって規則的な間隔で中断されることを明確にしている。 全体は、借用されたものと新しい素材の奇妙な組み合わせである。 p26 これらの内挿法は、Deus tuorum militumのテノールが、Ave mileのテノールと同じチャントを使うもかかわらず、初めだけに一致する理由のパズルに対する解決策である。 これらは、さらに、リズム的扱いが異なる。 (Deus tuorum militumにおける)反復的なイソリズムのパターンの代わりに、Ave miles では、非常に自由で想像力豊かなリズムを見いだす。この自由なリズムは、いわゆる「プレインチャントリズム」とは対照的に、自由に作曲された計量的メロディの性格をテノールに供与する。 おそらく内挿についての最も注目すべき点は、それらがチャントを分けるやり方である。細分がメロディのフレーズと一致することを期待することは妥当であろう。したがって、借用された、そして新しい素材は、自己含有型ユニットとして並置される。 しかし、ここで私たちは完全な失望を経験する。作曲家は一貫して自然なcaesuraeを無視し、(Ave mileにおいては)チャントを恣意的に5つのセクションに分け、いずれの場合も、フレーズ分割に跨っている。この取り決めがかなり慎重だったのは、音楽の内部的な証拠に含意されるだけでなく、テキストの分配において、外部的にも表現されていることである。 筆記者は、言葉を完全に整えてではなく、単に、プレインソングが未確認のままである限り、それ自体は理解できない手がかりをもってテノールを供給した。我々の、失われた言葉へのtranscriptionではその部分の旋律に従って括弧内に単語が挿入されている。 テノールは一般的に、プレインチャントに近接し、写本中の手がかりの位置によって強調されていることが分かる。 一見すると、それらは無作為に分配されているように見えるが、より精密な調査では、メロディーが要求するところに正確に現れることが明らかになっている。transcriptionは,写本にある状態で正確に、糸口を再生している。シラブルad[Dominum]を除いて。[Dominum]は写本では遅すぎてやってくる。それは、パートEの1つ前の小節にある。 テノールとチャントの合意は、他の場所よりもこのパッセージでは満足できるものではないので、作曲家は若干異なる変形をしたものと見なすことができる。他の糸口の全ての手がかりの正確な位置は、筆記者が、プレインソングからのテノールの導出を認識していることを証明している。 チャントのセクションは、それ自体が任意であるが、プレインソングへのスイッチバックが1小節早いパートEを除いて、交替で規則的に進行する。 取引する声部間の接続は、チャントに属さない1つか2つの音符の内挿によって行われる。パートEの最後の切り替えの後、プレインソングはそのコースを走る。そして、繰り返しのないコーダ部分Fは、自由に作曲されていると仮定できる。 p27 しかし、筆記者はEvovaeをテノールに追加することに注意したが、この小さなセクションでさえ正しく指定されたプレインソングであることが判明した。これは、第1詩編唱のseculorum amen 定式のdifferentiaeの1つである。 この定式が実際にモテットの不可欠な部分を形成することは非常に興味深い。 上記の分析から、モテットは、cantus firmusの扱いと声部交換という、奇妙な組み合わせを表している。2つの技法は通常は相互に排他的と見なされるものなのであるから。両者とも、一貫して適用されているが、最終的な分析では、それらは平等には扱われていない。明らかに、声部交換は、cantus firmusに勝っている。プレインソンをよく知っている人でも、実際の演奏でそれをフォローすることはできない。 メロディーの輪郭は、4つの要因によって削除されなければ、あいまいである。 これらのうちの第1は、自由に作曲された対位法と交替するセクションへのチャントの分割である。それぞれのセクションは、その他のテノールで一度に再演されるのはもちろん、声部交換の結果であるが、繰り返しによってメロディーの連続性が損なわれたる。 第2の要因は、分割の任意の性質である。セクションは、論理的な場所以外のところでは途切れて、聞き手がそれを認識する前に無意識のうちに自由な音楽に行く。 第3には、2つのテノールの間での声の交差を頻繁な使用が、異なる音色で始まると、そのパートを区別することが困難になることである。どちらも、長時間のうちで最も低い響きのパートではないと言える。それらが一貫して1つの音域を保持するならば、この難しさは取り除かれる。 最後に、両方の声部に数多くの休符があること。例えば、パートBの冒頭などのように、時折顕著なhocket効果がある。 チャントは明確に、一つの声部で表現されているが、それはhocketによって、チャントとは異なる新しいメロディに移される。これは、以下の抜粋(例2)で見ることができる。ここでは、チャントは、2声部の不連続な音調を、実際の耳がそれを知覚する単一行に結びつけるパッセージの実際の効果と比べられている。 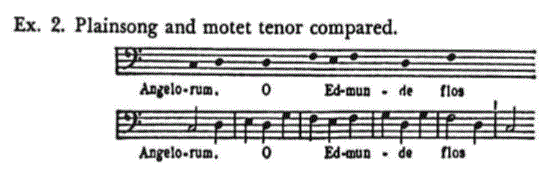 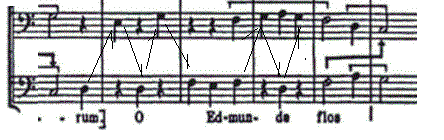 p28 hocketとは別に、cantus firmusの休符は、さらに行の混乱を招く。なぜなら、それらが対位法を押し付けるところはどこでも、チャントの連続として、うっかり受け入れられてしまうからである。cantus firmusの行は、それゆえ、声部交換のセクションによってだけでなく、テノールが休止している間の音符の響き方によるセクションの”内部において”によっても分裂することになる。 このような観察は、それが聞こえ、作曲家が努力をしていた継続的な存在としてのチャントの提示ではないことは疑いの余地がない。借用されたメロディの音調は、単なるテノールをぶら下げるペグではなく、またはその構造の単なる生の素材ではない。明らかに、チャントは、聞き手によって知覚されることはできない。こうした環境は、作品の不足として批判されるべきではない。構造的な声部がはっきりと知覚されるべきであることを要求するためには、中世音楽作品に対して近代的基準を強いることが必要であり、そしてそれは、方法において深刻なミスをするだろう。 モテットは、外的な視点によるとよらずに聞き取れるようには作られていない。テノールの構造を難なく伝えることができる人は1人しかいないせん。そのパートを担う歌手である。hocketを鳴らすために、声部の交差や休符は邪魔にならない。 音楽は、ある種の中世絵画のような「内面的視点」を前提としており、「観客」ではなく、参加者にしか見えない。それは、歌手の音楽に耳を傾ける音楽である。外部の視点に向けた唯一の譲歩は、統一の象徴であるが、その一方でテノールが目立たないようにする楽器の音と弦楽器の質感を融合させたものである。 モテットの構造的特徴は、今日知られている限り、独特ではないにしても非常に面白い。同様の作曲例については、相互交換を伴う作品の全レパートリーを、同じ例で再調査すべきである。声部の取引は、それ自体が具体的で可聴なデバイスで、Ave milesは、奇妙な抽象的なcantus-firmusの取り扱いが重ねられている。この作品の構造的合理性は、一見すると全く異なるように見えるイソリズム原理のそれと比較される。 しかし、後者(イソリズム)の工夫は、前者(cantus-firmus)がメロディに対して行うことをリズムに適用する。その機械的な分割と非典礼的な繰り返しによって、チャントはほとんどそのアイデンティティを失い、機械的ではない、構造的ではないにしても、合理的なものになる。 p29 中世の作曲家にとっては、それなしでは聞くことができないという問題はない。彼にとっては、「聞こえた旋律は甘いが、聞こえないものはより甘い」というのは確かに真実である。主なポイントは、音楽の中にチャントが存在することである。チャントは、人間の心がその合理的な芸術を立てることができる神聖な土地を提供する。 |