| モーツァルトの天才の秘密その1 ―ハイドンセット第一番K387第四楽章にみるポリフォニーとホモフォニーの結合― |
| TOPへ 音楽エッセイのページへ モーツァルトの天才の秘密その2へ進む |
楽譜へのリンク(第四楽章はP30~) モーツァルトは1781年にハイドンが発表したいわゆる「ロシア四重奏曲」に刺激を受けて後、6曲の新作の弦楽四重奏曲を作曲し、ハイドンに捧げた。今日いわゆる「ハイドンセット」と称せられているものである。これらのうちでも特にその第一番ト長調K387の第四楽章はモーツァルトが真の天才であったことを示すエキスのような存在である。私事で恐縮であるが、かつて大学生の頃、この一連のハイドンセットを聴き、特にこのK387の第四楽章が特に印象に残ったのをよく覚えている。その後この曲の和声学的な分析を試みるにつれて、この曲がモーツァルトの途方もない天才を如実に示すものであることがわかった。 一般にモーツァルトの曲というのは比較的耳に入りやすい(おそらくモーツァルトとしてはあまりたいして深く考えずに作った)ものが世間によく流布しており、明るい肩のこらない曲を作った作曲家としての印象が強いが、実はそれはモーツァルトの一面しかみていない。もしモーツァルトがそうした肩のこらない曲ばかりしか作らなかったとしたら彼の名は現在のように音楽史に燦然と輝く存在とはならなかったであろう。それではモーツァルトがモーツァルトである所以は何か。前人未到のホモフォニーとポリフォニーの結合、半音階の多用、といった音楽上の革新を行った作品を晩年に書いたからである。 こうした晩年の作品の理解なくしてモーツァルトを評することは、たとえば「虞美人草」や「坊ちゃん」だけ読んで「明暗」を読まないで夏目漱石を評するようなものである。 無論モーツァルトの音楽をそんなに堅苦しく考える必要もなく、わかりやすい曲だけを聴いているのもそれはそれでよいと思うのであるが、たとえば漱石を読んでいけば「虞美人草」や「坊ちゃん」などだけでは物足りなくなってもっといろいろな作品を読みたくなるように、モーツァルトの音楽の場合もやはり耳にやさしい曲ばかりでは飽きてくる。そしてモーツァルトとはなぜ天才なのか、ということを知りたくなってくるのである。そのモーツァルトの天才を凝縮したのがこの曲なのである。 この曲は通例どおり、ソナタ形式で書かれているが、まず大雑把に見れば次のようになる。 提示部 第1小節~第124小節 展開部 第125小節~第174小節 再現部 第175小節~第267小節 締結部 第268小節~最後 前述の如く、この曲の特徴は提示部と再現部で第一主題、第二主題共にポリフォニックな主題→ホモフォニックな主題という結合が見られることである。これはたとえばジュピター交響曲などでも見られるモーツァルト晩年の特徴であり、またこれほど露骨に相異なる音楽形式をごく自然に結びつけた作曲家はモーツァルトの前にも後にもいない、という点においてまさにモーツァルト的といってよい。こうした芸当はモーツァルトの天才があってはじめて可能となったのであった。モーツァルトの天才を具現する曲といってもよいだろう。 次に各論的にこの曲を見ていきたい。 まず第一主題。譜①のごとくフーガによるポリフォニックな構成で始まる。この音型はいわゆる「ジュピター音型」(譜②)と似ている。ジュピター音型というのはモーツァルトがジュピター交響曲の第四楽章の第一主題として使用した音型で、モーツァルトは彼のミサ曲などでもこの音型をしばしば使用している。(K192のクレドやK257大クレドミサのサンクトゥスなど)この音型はもとをたどればグレゴリオ聖歌のHymn「Lucis creator」の冒頭に見出され(下記ネウマ譜参照)モーツァルト以外にパレストリーナやブラームスなども使用しているとのことである。(The Complete Mozart; p213参照)   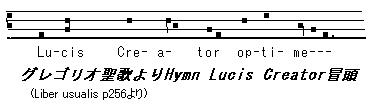 こうしたポリフォニックな状態が続いたあと、第17小節後半より突然古典派特有のホモフォニックな和声が響いてくる。(譜③)  |
| TOPへ 音楽エッセイのページへ モーツァルトの天才の秘密その2へ進む |