| チャイコフスキーの和声と無調音楽 |
| TOPへ 音楽エッセイのページへ 「チャイコフスキーの甘美な旋律について」へ戻る |
前ページではチャイコフスキーの甘美さの秘密をさぐってみた。このページではチャイコフスキーの使用した和声法の面白さと20世紀の無調音楽にもつながる彼独自の無調的オーケストレーションについて見ていきたいと思う。 チャイコフスキーの活動時期はだいたい19世紀後半で、15世紀後半以降営々と築き上げられ、ベートーベンにより完成された近代和声が爛熟期を迎えていた頃である。そうした時期にあってチャイコフスキーはあえて完成された和声学にメスを入れていった。 ひとことでいえばそれは古典的和声の”くずし”である。チャイコフスキーは一部の曲を古典的和声を少しくずしながら作曲をしていった。つまりベートーベンを典型例とする古典的和声を楷書であるとするならば、チャイコフスキーの和声はいくぶん行書的であるといえる。チャイコフスキーは行書的音楽を書くことによって20世紀の無調音楽への足がかりを作ったといえる。(ちなみにこれを草書までくずしてしまったのがシェーンベルクの十二音音楽であり、その後は文字そのものが判読不能となって今日に至っている)ほぼ同時代を生きたブラームスがベートーベン的和声の範疇から離れなかったのとそれは対照的である。 それではどこがどう行書的なのかを具体例で見ていきたい。まずは有名なピアノ協奏曲第一番の第一楽章の終わりの部分。ここの部分のチェロバスはB♭→E→B♭→Eと動いていく。(下のMIDI参照)つまり減5音程で動くのだ。したがって和音はB♭minor→G♭上の七へと変わっていく。 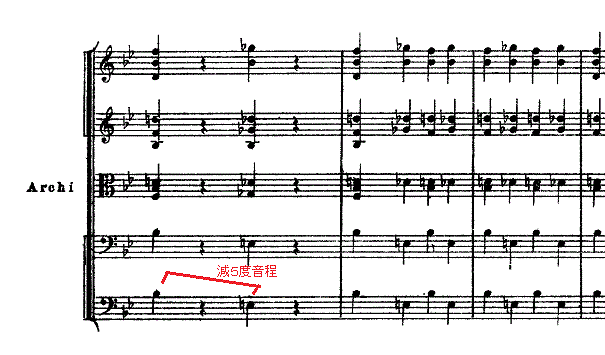 ピアノ協奏曲第一番第一楽章第650小節〜(ピアノソロは省略) チェロバスをTuttiでわざと不安定な減5音程で動かすことなど、ベートーベン的古典派的和声では考えられなかった。ベートーベン的発想ではチェロバスの部分はB♭→E♭と動くか、あるいはB♭→Fと動くかのどちらかしか考えられないからである。 しかるにチャイコフスキーはFとE♭の中間のEを用いた。これによりチェロバスは非常に不安定な三全音を上下することになり、聴衆に何ともいえない不思議な魔法をかけてしまうのである。 以上のようなことはオーケストラでチェロバスを弾いている人にとっては自明のことであろうが、チャイコフスキーのオーケストラ曲のチェロバスラインはこのようにかなり独特なところがある。そのためにこうしたチェロバスを基礎に作り上げられる和音もまた古典的和声のワクにはまらない独特なものとなるのである。チャイコフスキーの音楽はちょっと聴いただけでは気が付かないが、よく見るとそこには新しい時代の音楽への息吹が感じられるのである。 さらに一歩進んで、チャイコフスキーの音楽にはほとんど無調と思えるように書かれているところも見受けられる。オーケストラの各楽器が緊密に連携し合って有機的に結合し、あたかも一つの楽器のようになってはっきりした調性を感じさせないままに進んでいくところである。 例として前述のヴァイオリン協奏曲のTuttiのその後のところ(第141小節〜第160小節)を挙げてみたい。 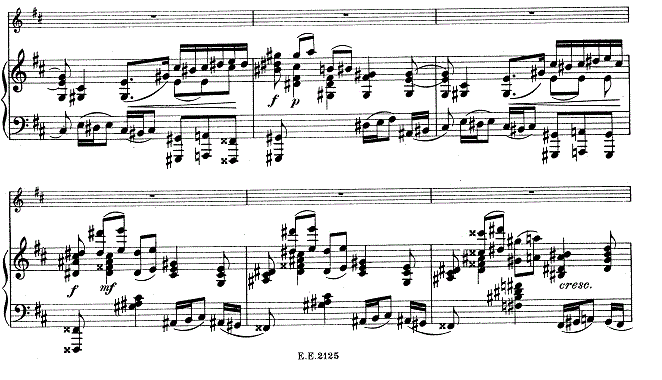 ヴァイオリン協奏曲第一楽章第141〜169小節 こういったところを聴いているといったいこの曲は何調なのか、と思ってしまう。もはやチャイコフスキーは調性の概念を打ち破り、ひたすら内なる声にしたがって書きたいものを書き始めた感じがする。それはほぼ同時代のワーグナーのトリスタン和声と相通ずるものがある。 さらに次の「1812年」の第119小節以降ところのはどうであろうか。この部分は金管楽器でフランス国家の「ラ・マルセイエーズ」が旋律として入っているのであるが、ここではそれを取り除いてある。そうするとこの部分の調性はまったくわからなくなる。まるで現代曲を聴いているようだ。つまりここでは無調の海の上に「ラ・マルセイエーズ」の旋律が浮いているのである。(「ラ・マルセイエーズ」に付随する和音が本来はあるのであるが、それが意識的に消されている) 「ラ・マルセイエーズ」旋律を省略した「1812年」の第119小節〜 「ラ・マルセイエーズ」旋律が入った「1812年」の第119小節〜 チャイコフスキーの音楽は一般に「白鳥の湖」や「胡桃割り人形」など、古典的和声に則って書かれたわかりやすい曲に人気がある。オーケストラを巧妙に自在にあやつる技術を持っていた彼は状況に応じて曲を書き分けることができた。 バレエ音楽では聴衆は音楽を聴きに来るのではない。バレエを見に来るのだ。したがって難解で複雑な音楽はいらない。単純でわかりやすく、なおかつバレエが映える音楽が必要だ。(それでもバレエなしで音楽だけ聴いてもすばらしいのはさすがにチャイコフスキーである) それに対してチャイコフスキーが新たな挑戦として書いたのがおそらく上記で紹介したような行書的和声と無調的パッセージである。彼の才能は耳にわかりやすい巧妙なオーケストレーションだけでは満足できず、次の時代のステップとなる新たなる試みをも模索していたのである。 |
| TOPへ 音楽エッセイのページへ 「チャイコフスキーの甘美な旋律について」へ戻る |