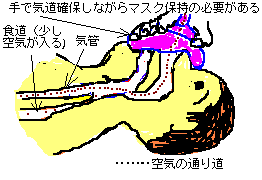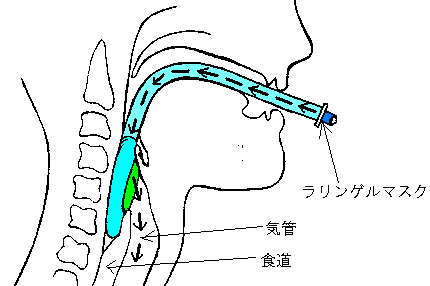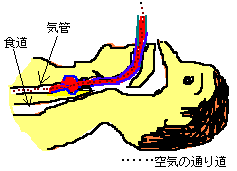| TOPページへ 地域医療のページへ 第四章その3へ 前ページへ |
||||||
その2;救急救命士が生まれてから さて日本においては、前述の如く救急隊員は医療行為はほとんど何もできなかったが、1991(平成3)年より救急救命士制度が発足し、制度的には確かに一歩前進した。日本はフランスのドクターカー方式ではなく、アメリカのパラメディック方式を取り入れたわけである。(ただし、ヘリコプターを使った搬送に関しては、日本ではむしろフランス式のドクター同乗が主流になってきている。いわゆるドクターヘリである)。 しかし仏作って魂入れず、というのは、まさにこのことをいうのであろう。この制度はいかにも日本的な妥協の産物で、あまりに不完全なものと言わざるを得ないものであったのだ。 当時、救急救命士の資格でできる医療行為は血管確保と除細動、そしてラリンゲルマスク(あるいはコンビニチューブやEGTA)と呼ばれる器具を使用した気道確保の3点であった。そして、いずれも〝医師の指示において〟という制限条項があった。一方、気道確保に一番有効である気管内挿管と、薬剤の使用は認められなかった。 ではここで、当時救急救命士が行えるようになった医療行為について一つひとつ見ていき、その問題点を考えてみよう。 ●あまり意味のない血管確保 救急救命士は、現場で血管確保ができるようになった。(血管確保とは、要するに点滴をすること)。しかし、薬剤を使用することは認められなかった。 救急の場合の血管確保というのは、たいていは薬剤を投与するために行なっている。救急患者に飲み薬は飲ませられないし、効果発言も遅いから、点滴ルートから薬剤を入れるのである。したがって、薬剤を使用できない血管確保はほとんど意味がないことになる。 利点といえば、せいぜい出血性ショックの患者さんなど、大量の輸液を必要とする患者さんに多少は効果があるかないかという程度のものであろう。出血性ショックの患者さんの場合、とにかく迅速な大量の輸液が必要となるからだ。 しかし、外にどんどん出血しているケースなら、とにかく出血部位をおさえておけばたいていの場合、とりあえずはそれで止血することは可能だし、体内に出血している場合は、現場で血管確保をして大量輸液をすることは有効だが、現場でその診断を行なうこと自体、困難である。 せいぜい食道静脈瘤破裂などで、現場で大量の血を吐いている患者さんくらいになら有効かも、といったところだろうか(しかし、これも現場で食道静脈瘤破裂の診断をするのは無理なことだ)。 そもそもこういった出血性ショックの患者さんは、だいたいは血管が虚脱している。そのため、血管確保は非常にむずかしい場合が多く、現場で血管確保のために徒らに時間を費やすよりも、とにかく早く病院に運んでしまった方が良い、ということになりがちである。 余談だが、こういった出血性ショックの患者さんの場合、ドクターカー方式ならば有用性があるといえる(ただし、そのメリットは現場が病院からはるか遠く離れているような場合にかぎられるが)。 医師が現場に行って、エコー検査などで血胸や腹腔内大量出血などの診断がつけられれば、すぐに現場で輸液、場合によっては輸血を始めることができ、また開胸心臓マッサージを行なうことも可能で、多少は救命率向上に効果があると思われるからである。 ●必要な時間に行なえない除細動 次に除細動。これぞ、まさに救急救命士制度の眼目みたいなもの。しかし、2003(平成15)年までは、この除細動も〝医師の指示〟が必要だった。 現場で救急救命士が心電図モニターをみて、「あ、心室細動だ、除細動が必要だ」と判断しても、除細動をすることができなかった。そのため、貴重な数分間が浪費され、助けられるはずの命が助けられない、といった問題も多くあった。 助ける手段があり、その技術はあっても、目の前でじっと医師の指示が来るまでひたすら待つしかない、というきわめておかしな状況に救急救命士は置かれていたのだ。 私がかつて勤めていたある大学の救急部では、この「医師の指示」のために心電図電送システムがあった。救急車から電送されてくる心電図がモニターに映し出され、当番の医師がそれを見て「心室細動を行なってください」という指示を救急救命士に出すのである。 ずいぶんと大掛かりな装置であったが、実際に救急救命士から心室細動の指示が求められる機会はあまりなく、ほとんど遊んでいる状態であった。救急救命士が自身の判断で心室細動をできるようにすれば、こんな大掛かりな装置はいらないのに、法律の不備のために、ずいぶんと無駄なことをしているものだなあ、とよく思ったものだ。 心電図を電送してから医師の指示を待って、と、その間、貴重な数分間はあっという間にたってしまう。おかしな法律のために、患者さんのせっかくの救命の機会を失ってしまう――これではいったい何のための救急救命士制度なんだ、という思いでいっぱいだった。 その後、この除細動装置は簡素なものが開発され、2004(平成16)年からは一般の人にも使えるようになっている。救急救命士さえ医師の指示がなければできなかった医療行為が、器械が簡素化されたとはいえ、一般の人が医師の指示もなく(器械の指示にしたがって)「医療行為」ができるようになったことに、隔世の感を感じる。 ●本当は怖~いラリンゲルマスク ラリンゲルマスクというのは、主に麻酔科の医師が使用しており、気管内挿管をするほどでもない、短時間ですむ手術の患者用に補助的に用いられていた簡便な気道確保用の器具である。 ↓ラリンゲルマスク  http://www.chinagauze.com/instruments/laryngeal%20mask%20airway.htmより ところが何と気管内挿管が認められない代わりに、このラリンゲルマスクの使用が、救急救命士に許可されたのである! 救急救命士法が施行させる以前、救急隊員に許されていた気道確保は、マスクを用いたいわゆる「マスク換気」だけであった。(下図参照) 気道確保その1;マスク換気
この方法は実はラリンゲルマスクの挿入よりも熟練を要するのであるが、特別な器具なしで気道確保ができるために、従前より救急隊員には認められていた。 ラリンゲルマスクの場合、気管内挿管のように喉頭展開(のどのところに管を挿入して、声門を確認すること)をする必要がなく、盲目的にのどに挿入をすれば、そのまま気道確保ができるような構造になっている。マスクを盲目的に挿入すると、食道をふさぎ、下図で示したように、空気は自然に気管に入るようになる。(下図参照) 気道確保その2;ラリンゲルマスクによる気道確保
そのために特別な技術がいらずに気道確保ができる、というものである。 しかし、そのぶん信頼性も少ない。要するにすぐに抜けたり、ずれたりすることがあるのだ。私も何回かこの器具を使用したことがあるが、あまり信頼性が高くないので、すぐに使用するのをやめてしまった。 まして救急搬送では、ゆれる救急車内で使用するのである。搬送途中で抜けたり、ずれたり、といった危険性は当然あるのではないだろうか。 きちんと気管内挿管をしていてさえ、ゆれる救急車内では挿入したチューブがはずれてしまうことがときどきあるのだ。私もいままで救急車搬送に同乗した際、何回か途中で救急車を止めてもらって、挿管をやりなおしたことがある。 ラリンゲルマスクの欠点はさらにある。気管内に管を挿入していないので、窒息患者には有効でなく、また患者が嘔吐した場合はかえって危険を伴う、という点である。 気道にもちや玩具などの異物があったり喘息発作などで、気道自体が狭くなっていたりして窒息状態になっている患者の場合、単に空気を送り込む道を作っただけでは状態が改善しない。これだけでは、空気が気道から肺へと入っていかないのである。どうしても気管そのものに直接管を挿入して、気道確保を行なう必要があるのだ。 前図を見ていただければおわかりのように、ラリンゲルマスクは食道にふたをすることにより気道確保を行なうので、気管に直接管が入らない。したがって、窒息した患者さんのような気道そのものに問題のある人にはこのマスクは無力なのである。 さらに、患者さんが嘔吐をした場合は、吐物の出口をラリンゲルマスクがふさぐ形となってしまうので、かえって吐物による窒息を助長することになる。 つまりラリンゲルマスクというのは、従来のマスク換気による気道確保に比べて利点がないどころか、嘔吐が激しい時などはかえってマスク換気よりも都合が悪いわけで、これをもって救急救命士にあらたなる医療行為が認められた、と喧伝することはまったくもってナンセンスなのです。なまじこんな危ない気道確保をするよりは、「頭部後屈おとがい挙上」で気道確保する従来のマスク換気法の方が、よほど安全なのである! 気道確保その3;気管内挿管法
●ラリンゲルマスクの使用が認められたのは日本的妥協の産物! 要するに、このラリンゲルマスクを救急救命士に使用可としたことこそが、まさに日本における法の妥協の産物なのである。救急救命士法ができ、いかにも救急救命士がいろいろな医療行為をできるようになったと国民に見せかけていたが、実際にはその手足をがんじがらめに縛っていたのだ。 実は、はじめて救急救命士制度を作るにあたって、救急救命士に気管内挿管を許可するか否かが、医療界で論争になった。賛成の医師も多数いましたが、医師会をはじめ一部の医師は、救急救命士に気管内挿管をさせることに強く反対した。そうした綱引きの結果、それでは中間をとってラリンゲルマスクなら救急救命士でも扱えるようにしましょう、ということになったわけ。これならみんなが納得するだろうということで。要するに玉虫色の決着であり、医療の世界も政治の世界などと変わらないのである。 しかし議論に参加したえらい先生方は、おそらくラリンゲルマスクを扱った経験も、救急車同乗をした経験もお持ちではないのではないだろうか。現場を知っていれば、救急車でラリンゲルマスクを使う、などという発想が出るわけがないから。 救急救命士制度発足当時、救急救命士がラリンゲルマスクを使用することが、プレホスピタルケアの革命であるかのように言われた。しかし、以上の理由から、私にはどうしてもこれがまやかしであるようにしか思えなかった。当時、私はまだ医学生だったが、その後、医師となって、さまざまな救急の経験を積むにつれ、ますます強くそう思うようになった。 なぜ救急救命士はこのようなかえって危険な道具を使わされていたのだろうか。それで日本のプレホスピタルケアが大幅に前進しただって? 冗談ではないよ。このような妥協の産物をあてがわれた救急救命士こそ、いい迷惑だったであろう。 こうして妥協をした結果、起こるべくして起きたのが次にご紹介する〝事件〟である。 |
||||||
| TOPページへ 地域医療のページへ 第四章その3へ 前ページへ |