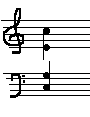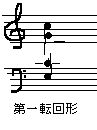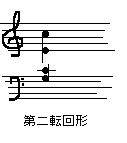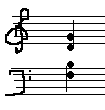|
和音というのは基本的に3つの音で構成される。(ドミソです)しかし、和声は通常4声である。したがって、3つの音のうちの最低どれか一つが重複されることになる。なぜ和音は3つの音なのに、和声となると4声となるのか。
これは安定性の問題である。もし和声が3声であれば、常に三和音を出していなければどの和音か分らなくなる。たとえば各パートの行き掛かり上、ドとミしか出せないとするとその和音はドミソなのかラドミなのか判然としない。これではきゅうくつだ、という訳で4声が標準となったわけである。(これにはデュファイの功績が大きい。詳細はデュファイその1以降のページ参照のこと)つまり”遊び”が必要なのである。仕事でもあんまりぎりぎりの人数でやってるとうっかり休みもとれないではないか。人生は和音である(和音と人生のページ参照)というのが私の信条であるから、人生も和音も同じなのである。
さて4声のうち、特に和声の一番下の部分にあたるバスは和音を決めるのに重要な役割を果たす。和音はたとえばドミソを例にとると、下から根音、導音、属音と呼ばれるが、この3つのうちどれをバスにおいて和音の重複をするかにより、和音の転回が生まれることになる。
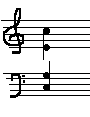 |
まず、左譜。これは転回なしである。つまり和音の根音が重複されている。これはもっとも基本的な形である。何と言っても根っこの音が根っこにあるんだからね、安定している。あらゆる音楽の基本はこの形であるからあえて例を出すまでもないだろう。
|
ここでバスとテノールが完全5度を作っていることに注目したい。バスとテノールは和声の基礎であるから、音響学的に安定していることが望ましい。そのために安定した完全8度ないし5度でバスとテノールを組み合わせることが和声学においては基本となるのである。反対にソプラノやアルトの領域で完全5度をやるとなんとなく空疎な感じになり、あんまりやらない方がよい、ということになっている。
ただし何事にも例外があり、例えば男性合唱などではあえて低い音域において3度、2度などが出てくるわけであるが,これはわざとこの濁りを楽しむわけである。混声合唱が清酒とすれば男性合唱は濁り酒といえようか。またベートーベンのピアノソナタなどではわざと低い音域に音を密集させて独特のベートーベンらしさを醸し出している。(こういった例は彼以前のハイドンやモーツァルトにはほとんど見られない)。
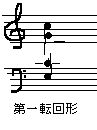 |
次が第一転回形である。(左譜参照)これは二番目の導音が根音に来ている。つまり一回ひっくりかえるから第一転回である。この和音の特徴は非常に不安定なことである。そもそも導音というのはその名の如く、他の音へと導く音としてでてきたシロモノで、もともとの教会旋法にはなかった音である。旋律の行き掛かり上必要となって出てきた、歴史の新しい音である。これがなんか知らないうちに和音の真中に収まって和音を決める重要な音になっちゃったのである。 |
たとえばドミソではミが導音であるが、ミがミ♭になるとCdurからCmollへと和音が変化する。言ってみれば必要に応じて作ったある製品がひょんなきっかけでまったく別の用途に使われて他の製品の心臓部になったというようなものだろう。バイアグラはもともとは血管拡張剤として開発されたものだが、ひょんなことからインポに効果があることがわかり、今やインポの人にはなくてはならないものになったのと同じである。
さて、なぜか和声の話をしていたつもりがインポの話になってしまったが、とにかくもともとなかったような音を根っこに据えてすわりがよいはずはない。したがって私はこれを「一本足で立った状態」と表現している。
しかしこの第一転回形の不安定さはさまざまな楽曲に応用されている。別記で述べたように、レシタティーボの冒頭和声におけるこの第一転回形の使用はそのひとつの応用例である。大規模な使用例としてはまたもやベートーベンであるが(私が好きな作曲家だからどうしても御登場願う機会が多くなる)チョー有名な第九の第4楽章の第30小節以下の部分がある。ここでは第一転回形が何小節もえんえん続く。この間聴衆は不安定な状態を余儀なくされ、早くなんとか解決(安定した和音へ移行すること)してくれと思っている。ここがベートーベンのねらい目なのだ。
実はこれは第九の第一楽章冒頭への回答なのだ。周知の如く、この冒頭の和声には導音がない。(それに二短調の曲なのにイ短調で始まっている)つまりラとミの音しかないから聴衆はラドミなのかラド#ミなのかわからないままえんえんと待たされることになる。ここでベートーベンは聴衆にナゾを投げかけているのだ。そしてその回答が第4楽章のこの部分の第一転回形なのである。チェロバスの一本のDisの音がその回答なのだ。肝心のその回答がこうしたきわめて不安定な和声となるところがベートーベンらしいではないか。
ここでベートーベンのこの二箇所を聴き比べてみたいと思う。
「第九」第一楽章冒頭;導音がなく不安定
「第九」第四楽章第30小節〜;第一転回形で前者が解決されている
話がずれたが、とにかく第一転回形というのは不安定な和声ということである。
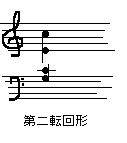 |
次が第二転回形。今度はもう一回和音をひっくり返して属音が根音にくる。(左譜)第二転回形が活躍するのはなんと言っても古典派時代のコンチェルトである。再現部が終わりに近づき、クライマックスに達したところでカデンツァが入る。その直前の和音がまさにこの第二転回形である。名人芸が終わった後は属和音→主和音となって曲は終わる。 |
この例としてハイドンのチェロ協奏曲第一楽章のカデンツァの部分を挙げてみよう。
第二転回の例(ハイドン チェロ協奏曲ニ長調第一楽章第179小節〜)
マタイではイエスのお言葉のおしまいの定型の完全4度下がるところの和音が第二転回形である。第二転回形は私は「両足を拡げてイスにすわって開き直った状態」と表現している。
次は第三転回形。これは七の和音にのみ現れる。和音が4つないと第三転回はできないよね。3つじゃあ、三回ひっくり返したらもとにもどってしまうから。
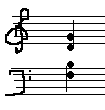
第三転回形 |
第三転回は左譜のごときであるが、この特徴は曲の一時停止にはピッタリであること。とりあえずこの転回で終止させると曲を止めることができる。だから私はこの第三転回は「ブレーキを踏んでクルマを一時停止させた状態」と表現している。
|
これをうまく使ったのはヘンデルである。彼は曲をこの第三転回形で一旦終止し、再度カデンツを出して本格的に終止させる、というのを得意としたらしい。有名な「メサイア」にこの例を多数見出すことができる。たとえば「メサイア」最後のAmen Chorusの最後の直前第155小節のところなどである。
第三転回の例(ヘンデル「メサイア」Amen
Chorus第153〜5小節)
もう一つのうまい使用例はバッハのヨハネ受難曲で使用されるパターンである。ヨハネでは最初からユダが登場するが、エヴァンゲリストが「ユダ!」と言うと伴奏和音は決まってこの属七の第三転回形となっている。 |