|
デュファイ総論
デュファイは中世とルネッサンスを結ぶ作曲家として有名である。彼が生を受けた14世紀末~15世紀初頭はマショー以来発展していた中世ポリフォニー音楽が爛熟期を迎えていた。いわゆるArs Subtilior(より繊細なる芸術)と言われているものである。技巧を駆使し、20世紀以降の現代音楽もまっつぁおの複雑なリズムが支配していた。
こうした状況の中でデュファイは爛熟した中世末期の音楽を整理し、次のルネッサンス時代への足がかりを作った。しかし無から有は生まれない。デュファイは新らたなる創造をするためにArs Subtiliorにはないまったく別の音楽を吸収した。すなわちそれがダンスタブルを中心とする英国の音楽とトレチェント・イタリアの音楽、そしてチコニアの音楽である。(下図)
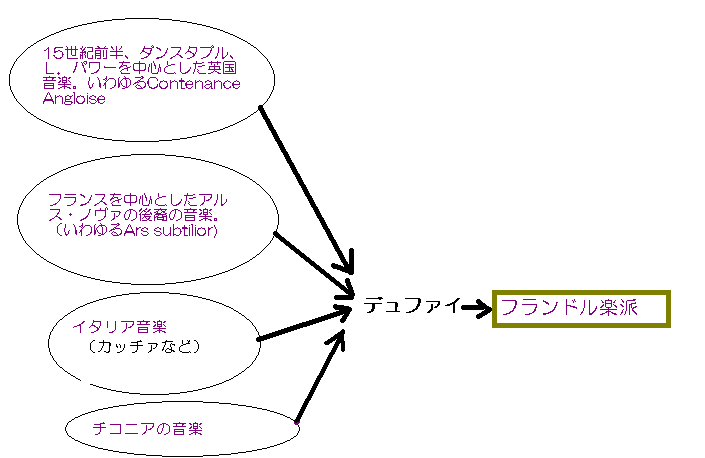
デュファイはArs
Novaの音楽を整理し、そこに英国で発達していた3度や6度の和音、イタリアのトレチェントで発展していた旋律の流麗さを融合させた。またイタリアとフランスで活躍したチコニアの模倣書法や低音処理の方法などを取り入れた。
要するにデュファイは15世紀半ば頃までに成立していたヨーロッパのありとあらゆる音楽要素を綜合し、次のルネッサンス時代の音楽への道を切り開いたのである。まさに皆川達夫先生も述べているように、それは3世紀後の大バッハの業績にも匹敵するものといえよう。
ただデュファイはバッハよりもさらにすごいところがある。すなわち大バッハはそれまでのヨーロッパ中の音楽をその頭脳で溶解させ、バロック音楽を完膚なきまでのレベルにまで達せしめたが、次の時代の音楽(古典派音楽)を創造するまでには至らなかった。それに対してデュファイは彼以前ならびに彼と同時代の音楽を綜合させたばかりでなく、次のルネッサンス時代の音楽の雛型のようなものまで作ってしまったのである。但しそれはデュファイとバッハという天才の程度の差ではなく時代の差であるといえる。バッハの時代、彼がいかに大天才といえどその脳の襞に吸収すべき情報量は3世紀前のデュファイの頃とは雲泥の差があった。デュファイがほぼ一人で成し遂げた音楽改革をバッハは彼とその後継者(そこには息子たちも含まれる)とで分業して成し遂げた、といえよう。(但しバッハは結果的に一人でバロックの総仕上げを成し遂げたが、デュファイの場合は同時代人もまたかなり音楽の革命に参加しており、複数の作曲家の代表としての役割といえる)
また、デュファイをモンテヴェルディに模することもできよう。(その場合、バッハはジョスカン・デ・プレかパレストリーナに相当することになりますね)モンテヴェルディは17世紀初頭の音楽界の激変を巧みに見抜き、それまで進めていたルネッサンス的書法(第一作法)を捨てて、まったく新しいバロック書法(第二作法)を試み、17世紀以降の音楽の決定的変化の礎を築いた。デュファイもまた彼一人の作法の変化がヨーロッパ音楽全体の変化につながったのである。
中世を終わらせた巨人
以上のように、デュファイはその生涯における作風の変化により音楽の世界を中世からルネッサンスへと旋回させた巨人といえる。その後の音楽史において、デュファイのように個人の作風の変化により前時代の音楽にピリオドを打ち、新しい時代を切り開く役割をした作曲家は前述のモンテヴェルディとベートーベン、ワーグナーくらいのものなのではないだろうか。(ベートーベンは初期の作品ではそれまでに発展していた古典派音楽を十分に咀嚼した程度のものであったが、交響曲、ピアノソナタ、弦楽四重奏曲等における後期の作品では独自の世界を切り開き、西洋音楽の進歩に大きく貢献した。またワーグナーは初期にはそれまでに発展していたオペラと同様な発想にもとずく作品を書いたが後期には独自の楽劇を作り上げ、また「トリスタンとイゾルデ」に見られる無限旋律がその後の無調音楽の萌芽となった)
デュファイの具体的功績
デュファイの具体的功績は以下のようなものである。
①それまで三声が主体であった作曲法を四声主体に変えた。(特にミサ曲において)
②フォーブルドンの使用。
③ミサ曲において一つのテーマ(Cantus
firmus)でミサの各章を統一する形態(循環ミサ)を確立した。
④ミサ曲において各章をほぼ同一の形式(冒頭動機)で開始する形態を確立した。
①に関して。もともと多声音楽はグレゴリオ聖歌を定旋律としてこれに細かい音符がからんでゆく、という形で発展してきた。そんな中で三声の音楽が主流となっていったのはやはりキリスト教の三位一体思想を意識してのことであると思う。さらにまたあまりにたくさんの声部が定旋律にからんでゆくと当時の最大の売りであった複雑なリズムが不明瞭になる、といったこともあったのかもしれない。
ところがデュファイはこうした多声音楽にもう一つの定旋律ともいうべきもの(当時はContora Tenor
と称された)を書き加えた。彼がなぜこうしたことを行ったのかは私が調べた範囲ではよくわからないが、とにかくこれは結果的には画期的なことであった。(無論のデュファイのモテトゥスには三声のものも多いが)
ところで人間、二人で仕事をする時は同じことを二人ではやらないものである。大抵はそれぞれ自分の得意とするものに特化し、分業をするようになる。二つとなった定旋律もそうであった。定旋律は二つあっても意味がない。一般的には二つの旋律を人間の耳で同時に聞き分けるのは使用楽器を代えるなどしない限り不可能である。したがってデュファイは二つの定旋律を一つは本来の定旋律として、そしてもう一つには近代和声学でいうBassの役割を持たせたのであった。
すなわちこの二番目の旋律は曲の一番下のパートを担当し、次第に明確化してきた和音の根音を主として担当するようになった。こうすると曲のすわりがよいことがわかってきたからである。
結局デュファイは四声を主体とした作品を書くことにより自然と和声の役割を発見し、三和音が常に響きわたる次のフランドル楽派(=ルネッサンス音楽)への橋渡しを行ったのである。但しデュファイの曲は後期のものでもまだ和音の第三音が抜けていることがほとんどであり、耳で一聴しただけでもまだまだフランドル楽派の音楽とは異質であることは容易にわかる。特にランディーニ終止は後半期の作品でも頻繁に使用している。(しかしランディーニ終止とならぶ中世の代表的終止形である二重導音終止はデュファイの後半の作品ではほとんど見られなくなる)
②に関して。フォーブルドンとは近代和声学に即していえば三和音の第一転回形の和声を延々と続けていくやり方(真ん中の音は譜面には書かれないことが多い)で、3度と6度への執着の強かった英国からの影響といわれている。(特にデュファイよりやや先駆けて活躍していたダンスタブルの影響が強い。いわゆるContenance Angloise”イギリスの装い”)
それまでのArs
Subtiliorの音楽では多声で作曲されるに際し、、もっぱらリズム、旋律を中心とした各パートの横の関係が重視されていた。しかしフォーブルドンの輸入はデュファイらに和声というものを強く意識させる結果となった。鍵盤楽器などを使った和声学を最初に習うことが多いわれわれからはこうしたことはむしろ逆ではないかと奇異に見えることであるが(当時は平均律の概念がなかったため;平均律が確立したのはバッハ以降)、当時としては各パートの縦の関係よりはとにかく複雑きわまりないリズムを駆使することに重点がおかれ、はっきいって途中で各パートの音がぶつかろうが何だろうがあまり気にしていなかったのである。
しかしデュファイはダンスタブルの音楽などを通して多声音楽の縦の関係の重要さに気づいた。これがさらに①におけるBassの発見と相俟って作曲をする際に各パートの縦の関係をも十分気にかけるようになった。これがさらに係留音を始めとする各声部の合理的処理に結びつき、多声音楽はより洗練されたものとなっていったのである。反面、前時代の複雑なリズムはこうした声部の合理的処理とは相容れないものとなり、廃れていった。(14世紀にArs
Novaとして一世を風靡したイソリズムも15世紀前半には廃れていた。デュファイも初期の作品ではイソリズムを使用しているが、後期のそれではほとんど影をひそめている。)
③に関して
cantus
firmusを使用してミサ曲全体を統一しよう、という傾向は英国で顕著であった。有名なライオネル・パワーのMissa Alma
Redemptorisは最古の循環ミサとして有名で、この作品ではグレゴリオ聖歌の旋律がまったく修飾を受けることなくTenorパートで流されている。
こうした英国におけるミサ曲作りの新たな試みがデュファイに受け継がれ、何曲かの循環ミサが書かれている。なお、ミサ曲全体を同一モチーフを使って統一しようという試みは英国だけでなくブルゴーニュ楽派の先駆けであるチコニアなども行っている。チコニアの楽譜は私はまったく所有していないので具体的なことはよく知らないが、特にGloriaとCredoを統一して作っていたとのことである。
(尚、チコニアの書法にはBassラインにおいてある程度、和音の根音を取っていく傾向が見られ、後のデュファイの書法の先駆けとなるものである。たとえば、gloriaの楽譜のtenor(実質的なBass)パートを見ると、このパートが和音の根音をかなり取っていることがわかる。楽譜参照)。 デュファイを大バッハにたとえると、チコニアの存在はバロック音楽初期の発展に貢献したモンテヴェルディのようなものだろうか)
④に関して
冒頭動機の統一性もまたチコニア、ランタンらの作品で見られるとのことである。(楽譜がないので確認できないんだけど。)③、④のような作曲法でミサ曲全体を統一する、というのはその後ルネッサンス期における”はやり”となる。ジョスカン・デプレ、パレストリーナ、オケゲムらルネッサンス期の著名な作曲家は皆全体が統一されたミサ曲を多数書いており、ミサ曲は百花繚乱の時代を迎える。デュファイはこうしてルネッサンス時代のミサ曲の隆盛の基礎を作ったといえよう。
役立つリンク集
・デュファイの時代背景に関しては のサイトがわかりやすいです。 のサイトがわかりやすいです。
・デュファイの生涯に関してはフランドル楽派の作曲家たちがわかりやすいです。
・Ars Subutiliorに関してはArs Subulitiorがわかりやすいです。
・デュファイの作品全体に関してはギョーム・デュファイ簡易作品表がよく整理されています。
・ドミナントの発見
|