| TOPページへ 地域医療のページへ 第二章その1へ 前ページへ |
|
●千差万別の患者がやってくるアメリカのER テレビ番組「ER」をご存知の方は多いと思う。アメリカのER(Emergency Roomの略で、直訳すれば「救急救命室」となります)を舞台にしたドラマで、ベイトン先生やカーター君やなど、いろんなキャラクターの医師が登場して、なかなか面白い番組である。この番組を見ていると、アメリカに行かなくても何となくアメリカの救急医療の雰囲気がよくわかってくる。 では日本にもあんな形で救急を行なっているところがあるのだろうか。実はほとんどありません。 日本の救命救急センター方式とアメリカのER方式とは根本的に異なるのである。日本の救命救急センターでは三次救急の重症患者しか診ないが、ER方式では、一次から三次までのあらゆる救急患者を診る。日本のように、救急患者を分別しない。そしてそのほとんどは家庭医からの紹介患者や直接、病院に搬送された患者さんである。無論、診断も何もついていない状態だし、まず血管確保、酸素投与といった段階から診断、治療が始まる。 さらに、基本的にER方式には日本での病院間搬送という概念がない。一つの施設で一次から三次までの救急患者を扱うために、一つの病院で診療が完結し、患者さんを他の病院に搬送する必要がないからだ。 実際、あの番組をご覧になるとおわかりかと思うが、一方で超重症患者の処置をしているかと思えば、一方では傷の縫合などの軽症患者の処置をやっている。つまりERはなんでもありの救急の坩堝のような世界だ(下図参照)。 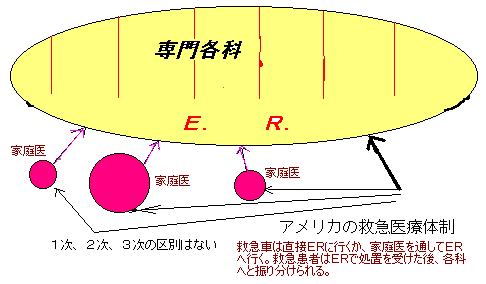 アメリカでは、救急患者はERのような大組織で引き受けられ、そこで救急処置をされた後、各科へと引き継がれていく。たとえば多発外傷患者が来れば応急処置後、外傷チームへと引き継がれる。そしてこのERは、ベテランの医師というよりは、レジデントと呼ばれる若い医師や高学年の医学生が主体となって運営されている(アメリカの医学生は日本のそれと異なり、かなりの医療行為を許されている。「ER」を見ていても、医学生が現場の第一線として気管内挿管などのトレーニングを受けているのがわかる。日本の場合は医師法上の制約があり、ほとんどが見学にとどまっている) ●ER方式では「たらいまわし」は絶対にありえない さてしかし、日本においても少しずつですが、最近はアメリカ型のERを持つ病院が増えてきているようである。一次〜三次と、救急患者を分別することは、病院には都合がよくとも、患者さんにはやはり不利益が大きいということが認識されてきたからだと思う。 ここで私が研修を受けたT病院について少し語らせていただきたいと思う。その病院は600床の大病院で、当時の日本ではめずらしく、ER型の救急医療を行なっていた。年間の受入れ救急車台数が約5〜6000台、さらに夜間・休日の外来だけで、年間1万人以上の一般受診者(救急車で来ない患者さん)がいた。ER型だから、一次〜三次の区別なく、すべての救急患者を引き受けていた。まさにのべつくまなく救急車が殺到、夜中の1〜2時頃まで外来は患者でごったがえしていた。 そこでの主力は研修医だった。そう、まさにテレビ番組「ER」の世界だ。救急車搬入、外来受診を問わず、研修医自らがトリアージ(受診患者の重症度を決めること)を行ない、自らの力量で診断・治療できる患者は自らの判断で行ない、その力量を超える患者に関しては、院内に当直している上級医にコンサルトをする、という形で診療が行なわれていた。 このやり方は研修医、上級医双方にメリットがあった。研修医にとってはある程度の責任をもたされ、しんどかったけれど、やりがいのある仕事だった。また上級医にとっては、一次救急患者で夜中に呼ばれなくてもいいので、かなり楽ができたようである。 このER型救急は住民や救急隊にも非常に評判がよい制度だった。絶対に断られることがないのだから、救急隊はとにかくT病院に搬送すればいい、という安心感があった。また、地域住民からすれば、いつ何時病気やケガをしても「とにかくT病院に行けば、必ず診てもらえる」という安心感もあった。したがって、〝救急患者のたらいまわし〟などということは絶対にありえなかったのだ。 ●燃え尽きてしまうER医師の苦悩 さて、いいことずくめにみえるER型の救急医療だが、無論、問題点もある。それは医師のトレーニングの問題である。 ER型の救急医療の場合、通常、若手医師をたばねる存在として何人かのER専属の医師がいるのが普通である。しかし、こうした医師たちは救急に関する幅広いトレーニングを受けることはできますが、初期治療のみしか関与できないことが多いのだ。 腹痛の患者が来たとする。ER専属医が最初に患者を診察して、どうやら急性虫垂炎(いわゆるモーチョー)であろう、と診断する。しかしERの医師が関与するのはここまで。診断がついて、あとは外科へ回され、そこで必要であれば手術を受けることになる。たとえERの医師にその能力があったとしても、手術をしたり、その後、その患者さんの管理をすることはない。特にER専属ではない研修途上の医師だったら、自分で執刀して腕を磨きたいと思うのが普通であろうが、患者は外科に回ってしまうので、その機会もなくなってしまう。 また、ERでは専属ベッドを持っていたとしても、そこに入院するのは他科が取らない患者ばかりとなる。必然的に、全身打撲のような、特に治療をしなくとも寝かせておけば自然に治る患者か、植物状態や脳死患者のように、残念ながら回復の見込みのない患者ということになる。つまり、医療をもってせずとも助かる患者か、医療の力ではどうにもならない患者かのどちらかがERのベッドに横たわっている、ということだ。 その中間の、まさに医療の力によって救命し、社会復帰ができるか、というクリティカルな患者はERのベッドには残らない。こうした中間領域でのERに特有の患者といえば、せいぜい薬物中毒患者くらいのものだろう。 こうしたことが続くと、医師は救急をずっと続けようという気が起こらなくなる。最初は救急に燃えてER専属となった医師も、次第に情熱を失ってくる。まさにバーンアウト。 アメリカの事情はよくわからないんが、以上のような理由があるために、とにかく日本の救急医療では、医師がそこで長く救急をやろう、というインセンティブを維持していくのは非常に困難なのだ。やる気がある優秀な医師ほど、それは顕著に現れる。 優秀な医師ほど、自分が初期診断をつけた患者なら、最後まできちんと自分の力で診てあげたい、と思うのではないだろうか。そのためにこそ、医師はきびしいトレーニングもいとわないのだから。 医師の研修医時代はきびしいもの。ボロぞうきんのようにこき使われ、患者さんのために私生活も犠牲になる。新しい研修制度で、最近はだいぶ変わってきているようだが、研修医の辞書に労働基準法という文字はないのである。それは将来、患者さんを自分の力できちんと最後まで診ていく能力を身につけるため、という大義名分があるからこそ。だから頑張れる。 しかし、こうした研修医のような生活が延々続き、いつまでも初期診療のみしかタッチできない状態が続けば、いつかその医師は燃え尽きてしまうだろう。 ●将来、救命救急センターはICU化する!? 日本においても、今後はER型の救急医療体制がメインになっていくであろう(すでに東京都では、石原慎太郎知事が都立病院でそのような構想を打ち出している)。従来の一次・二次・三次と救急患者を分割する救急医療体制よりは、ER型の方が明らかに地域住民のためになるからだ。患者さんのためというよりは医療者側に向いていた日本の救命救急センター方式と、患者さんや国民の側を向いている北米式のER型救急を比べてみれば、後者の方がよいに決まっている。 今後は従来の救命救急センターとは全く異なる体制の、すなわちER方式の大規模な救急外来が各地にできてくると思う。そして従来の三次救急専門の救命救急センターはICU化していくだろう。入院した重症患者を診ていくことを主体とする三次救急はICUと変わらないから。 三次救急の救命救急センターでは主に術後や慢性期の重症患者などを診る場となり、救急はもはや取らなくなるだろう。そして救急患者を一次・二次・三次と分ける慣習もなくなっていくだろう。トリアージはもはや現場で救急隊員が行なうのではなく、病院内で医師により行なわれる。病院内で行なわれるから、もしもそのトリアージに間違いがあっても(この間違いは永遠になくならなりません!)、すぐに対処できる。 ●ER型救急病院が増えると無意味な病院間搬送はなくなる 新しいER型の救急医療施設が日本で確実に増えていけば、やってくる救急車はすべて受け付け、よほど特殊な疾患を除けば、すべて同一病院で治療が受けられるようになる。したがって患者の病院間の転送というのは必要がなくなり、患者さんの安全性も高まるはずだ。従来の分別方式では、やたら病院間の転送が増え、その間に亡くなる人も少なくなかったから。 病院間搬送の弊害を指摘している医学論文はほとんど見当たらないが、最近、毎日新聞でこの弊害を指摘している記事があった。 2006(平成18)年3月19日付の記事によると、2003(平成15)年に全国で救急搬送された患者さんは457万人、そのうちいったん病院に収容されてから他病院へと搬送された患者さんはその1割強の47万人、そしてその約4分の1が重症患者であったとのことである。「年間十万人以上の重症者が最初に運ばれた病院では治療を受けられなかった可能性がある」(同新聞記事より)わけで、こうした重症患者は日本型救急システムのために、状態が悪いままにさらに本来必要もない救急車に乗せられているのである。 考えてみれば、より高次の医療機関への転送を必要とするような重症患者が、救急車という、まあよくゆれてそこでは何らきちんとした医療行為もできないような空間に押し込められて一定の時間を過ごす、というのはどうみても危険だし、バカげている。 最初の病院への搬送はしょうがないとしても、「うちでは手におえませんから○○救命救急センターに搬送します」と言われた場合のムダな搬送、無謀な搬送がなされなければ助かった患者さんというのも、これまで大勢いたはずだ。さらに、前述した「免罪符搬送」なるものは貴重な救急車の無駄遣いとしか思えない。 このような事情を知らない患者さんやその家族こそがとばっちりを受けている。「○○救命救急センターへ搬送されれば助かる」と思っている、または、「○○救命救急センターへ搬送しなければ助からない」と思っている家族が、実に何と多くいることだろうか。 「○○救命救急センターにまで運ばれて助からなかったのなら、仕方がない」と思ってしまうのだ。まさに知らぬが仏。本当は運ばれたことそのものが患者さんに大きな負担となっていたのに。 こうした無意味な、有害な救急搬送はなくさなければならない。そのためにも、ER型の救急施設の整備が必要となってくる。そこでは直接、運ばれた患者を最初から最後まで責任を持って診るわけだから、逃げ道がない。 従来型の救急体制であれば、搬送する側は「うちでは手におえない」という逃げ道があった。また搬送される側は「こんなひどい状態で送られても、助からない」という逃げ道もあった。 ER型救急ではそれが、ない。まさに施設のマンパワー、能力が問われることになる。これは地域住民にとっては大変好ましいことだろう。前述のT病院の実状が、まさにそれを如実に示しているといえる。 ●ER型救急を担う総合診療医の育成を! しかし前述のように、ER型の救急施設では、そこに努める医師のインセンティブの問題がある。むろん従来型の救命救急センター方式でも同じ問題はあるのだが、救命救急センターではICU的な病棟管理がメインなので、「ICUの専門医」というハクがつく。また、一次・二次救急担当者は「片手間救急」だから「しゃーないや、オレの本業は別にある」という逃げ道がある。 しかし、ER型救急では「自分はしょせん〝救急屋〟だ」などと自己卑下に陥る可能性がある。日本では、ER型救急をやっている医師は今のところあまり高く評価されていないから。 この問題は簡単には解決しないと思う。縦割りで行なってきた日本の医療社会には欧米のような外傷専門医というような概念もないし、特に大きな病院では各科のなわばり争いがいろいろめんどうくさい。 では、ER型救急を日本でも普及させるにはどうしたらよいか。 そのためには、ゼネラルに何でも診れる「総合診療医」の多数の育成が前提となる。臨床医の7〜8割が総合診療医であるべきである、というのが私の持論である。こうした医師が増え、ERだけで主要な診療が完結するようになれば、救急医療に興味を持てる医師も増えるはずだ。 本当に専門的治療が必要な患者というのは実は少なくて、多くはゼネラルな総合診療医でその診療は可能なのだ。専門にとらわれない、幅広い初期診療に精通したER専属医がどんどん増えて、さらにその守備範囲を広げていくのが、ER型救急の普及には必須である。この「総合診療医」に関しては後ほどに詳しくご説明したい。 ●ER型救急は医療過疎地域も応用できる こうしたER型救急は、基本的にはある程度以上の人口密度のある地域でなければ機能しない。ER型救急として、一つの医療機関で一次〜三次にわたる救急患者を診断から治療まで完結させるには、多大なマンパワーを必要とし、そういった大きな医療機関をいくつか作るにはやはり人口密集地であることが必要となってくる。それでも、人口百万人に一つという救命救急センターの設置よりは、多くのER型施設を作ることは可能だと思っているが。 ところで、病院間搬送を前提としないで一ヶ所の病院で診断・治療を完結させようというER型救急の発想は、離島・へき地のような医療過疎地での救急医療にも敷衍させていくことができる。人口密集地でなければできないER型救急がなぜ過疎地にも適しているのか。 離島・僻地では、患者の搬送が容易でない。家族の経済的負担などを考えても、できれば現地で医療が完結する方が望ましい。そのために、ER型救急の発想で、守備範囲の広い総合診療医を現地に置き、そこでありとあらゆる患者を診て、できる限り患者搬送をしないようにするのである。 これまで、こうした医療過疎地域での医療は、都市部の病院へ患者さんを搬送することを前提としてきた。医療過疎地で少ない医師が孤軍奮闘するよりは、さっさと大きな病院に患者を搬送してしまえ、という発想である。 現在は、こうした考えが医療関係者のみならず、地域住民にまで浸透しきっている。せっかく地域に診療所があってもほとんどそこが利用されず、交通機関を利用して、いきなり遠く離れた大病院を受診してしまう人が多いのが現状である。離島でさえ、多くの患者さんが高い船賃や航空料金を払ってでも、いきなり内地の病院を受診している。 私は、地域の診療所でも装備を重装備として、医療過疎地でもできるだけ医療が現地で完結できるような体制を作っていくべきではないかと思っている。地域の人たちも、わざわざ手間ひまとカネをかけて遠くの大病院まで出かけるより、近くの診療所で診療が完結できる方がよいと思っているのではないか。 そのためにこそ大切なのが、ER型救急的発想と頭のてっぺんから足のつまさきまできちんと診ることができる総合診療医の養成である。両者はクルマの両輪で、ER的発想でこそ総合診療医が養成されるし、優秀な総合診療医がいてこそ、ER型救急は可能なのである。 ERで養成された総合診療医がそこでくすぶっていないで、どんどん地域に出て、その持てる能力をいかんなく発揮できる環境が整えられれば、日本の地域医療はずいぶんと改善されるはずである。 |
| TOPページへ 地域医療のページへ 第二章その1へ 前ページへ |