| TOPページへ 地域医療のページへ 第一章その3へ 前ページへ |
|
●「一次救急」「二次救急」「三次救急」 日本では救急患者の診断、治療にあたり、便宜上、救急患者を一次救急・二次救急・三次救急と分けることになった。 一次救急患者は、簡単な怪我、風邪など入院の必要もない軽傷患者。二次救急患者は、肺炎や脳炎、消化管穿孔など手術を要したり入院を要するが、すぐに生命には別状はない、ある程度の重症患者。そして三次救急患者は、全身状態がきわめて不良で、すぐに緊急の治療をしないと生命の危険がある患者である。(下図参照) 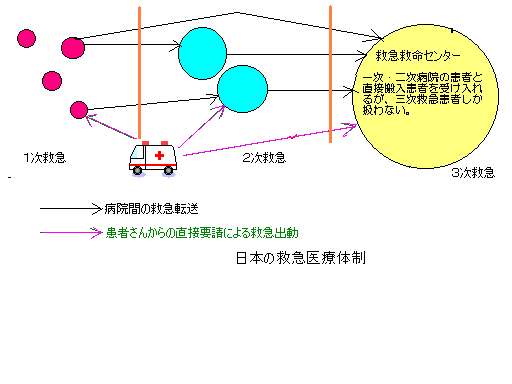 発足当初から救命救急センターでは、三次救急患者のみを取り扱うことになっていた。二次救急患者までならば、これまで通りの各科縦割りの医療体制でも十分対処できるであろう、と考えられたからである。そして、一次・二次救急病院では、搬送されてきた患者が自らでは治療が困難であると判定された患者は、救命救急センターに「病院間搬送」をすることになっている。 救命救急センターでは、最重症患者は直接救急車を受けることもむろんあるが、一次・二次救急病院から搬送されてきた患者を扱うことがメインである。特に「高度救命救急センター」と称せられる特別な三次救急施設では、扱う対象はほとんどが他の病院から搬送されてきた患者となっている。 日本の救急医療体制の特徴は、このように救命救急センターが三次救急、すなわち最重症患者の治療のみに特化したことである。これがあとから述べる北米などで行なわれているER方式との最大の違いだ。 ●救急患者の判定の困難さ ここでまず問題となったのが、この一次・二次・三次救急患者の判定である。 この判定は誰がどのように行なっているのだろうか。日本の場合、フランスのようなドクターカー(ドクターカーに関しては後述)はないので、結局、現場に駆けつけた救急隊員が自らの経験にもとづいて、その判定を行なっている。 しかし、この判定が困難な場合が少なくない。特に、軽傷だと思ったのが、実は重症であった(一次救急と思われたのが、実際は二次・三次救急であった)という場合が問題となる。 2006(平成18)年3月22日の「毎日新聞」の記事によると、「救急車で慶応大病院に運ばれた重症患者のうち、救急隊が重症と判断していた患者さんは約2割しかいない」とのことである。そのほか8割の患者さんは、軽症・中等症として運ばれ、結果的に重症であったわけだ。三次救急対象と判断されずに一次・二次救急病院に運ばれている重症患者は相当数いる、という恐ろしい事実が浮かんでくる。 日本の場合、医療機関が最初から救急患者を分別して扱っているので、どうしても最初に患者に接する救急救命士がその重積を担わざるを得ない状況なのである。 ●軽症とみなされた患者が数時間後には死亡するケースもある! ここで、私が経験した極端なケースを二例ご紹介したい。当初、軽症とみられていたのが、結果的には心肺停止にいたった重症だったケースである。 交通事故でハンドルに胸を強打したAさん。はじめは胸部打撲だけで、少し胸が痛い、という以外、大きな症状はなかったようだ。目立った外傷もなかった。そのために、現場で警察官から事情聴取を受けていたほどである。 ところがその胸の痛みが一時間ほど続いた後、Aさんは突然、意識がなくなり、あっというまに現場で心肺停止状態となってしまった。そして病院に救急搬送されてきた。 着院後、すぐに心肺蘇生を開始。外来での超音波検査により、左胸に大量の出血がある血胸という状態であることがわかったため、心臓マッサージを開胸心臓マッサージ(胸のところを十数センチ切り開き、心臓を直接触ってマッサージすること)に切り替えた。しかし結局、患者さんは出血性ショックで死亡した。 この患者さんの場合、受傷直後にはまだ胸部大動脈が皮一枚でつながっていたのである。しかし、ある程度時間がたって、急にそこが破綻し、胸の中に大出血を起こしてしまった。 こうした患者さんはどうしても最初は一次救急として処理されてしまいがちである。たまたま警察官が現場で一時間も事情聴取をしていたために、三次救急患者であることが判明したのである。事故後、すぐに搬送されていれば、救急隊員はこの患者さんを一次救急対象と判断してい)たことであろう。 次に、同じく交通事故で胸を強打して運ばれてきたBさんのケース。BさんもAさんと同じように、最初は胸部打撲とのことで一次救急患者として搬送されてきた。レントゲン写真でも特に異常はなく、目立った外傷もなかった。 主治医は念のため、Bさんを入院させた。ところがその夜、Bさんの容態は急変したのである。 入院後も不穏状態(興奮して暴れまわる状態)であったBさんは、その日の深夜、突然、心肺停止となった。Aさんと同じく、やはり大動脈損傷があり、皮一枚でつながっていたのが、夜中に破綻したのだ。皮一枚で大動脈の壁がつながっている場合、レントゲンを撮っても異常が見つからないことも多く、入院時には主治医もBさんの身体の中で起こっていた異常に気づかなかったのだ。 Bさんは主治医の懸命な蘇生処置にも関わらず、助からなかった。後から思えば、異様な不穏状態が大動脈破綻の前兆であったと思われるが、医師でもまさかBさんが本当は三次救急患者であるとは判定できなかったのだ。 このように、救急度の判定というのは医師が行なっても難しいものなのである。まして救急隊の方に、そこまでの判断を現場で求めるというのは大変難しいことであると言えよう。推測だが、このような判定の誤りによる手遅れというケースは、おそらく全国的に相当数あるだろうと思う。 一次・二次・三次と救急患者を分けて治療する日本の救急システムはこのようにトリアージ(患者さんの重症度の判定)の大きな問題を抱えているのであるが、ほかにもまだいろいろな問題が残されている。 ●不必要・無意味な救命救急センターへの搬送も! 救急搬送には、一般の人からの通報による、現場から病院への搬送と、病院間の搬送の二種類がある。先ほどは前者、すなわち現場からの搬送の問題についてのことであったが、次に後者の、すなわち病院間の搬送の問題について考えてみたい。 実はこの病院間搬送には、不要な搬送、無意味な強いられた搬送というものがたくさんある。本来なら一次・二次救急段階の病院でも十分対処できるはずの患者さんでも、救命救急センターへと病院間搬送される傾向があるのだ。 私自身は純粋な三次救命救急センターでの勤務経験はないが、搬送する側(一次・二次病院側)の経験からすると、なぜこれくらいの症例をあえて搬送しなければならないのか、と思うことはしょっちゅうあった。それほど重度ではない脳内出血、子宮外妊娠、卵巣茎捻転、子どもの急性虫垂炎(いわゆるモーチョー)、気管支喘息重責発作、熱性けいれん、それほどひどくない熱傷など、明らかに二次救急病院で管理ができる患者さんがどんどん近郊の救命救急センターへと搬送されていった。 これはなまじっか各地域に救命救急センターができたために、起こることである。たとえ不必要ではあってもあえて病院間搬送をせざるを得ない状況になっているためで、その結果、地域の病院がかえって救命救急センターに頼ってしまい、一定水準以上の医療が行なわなくなってしまっている(もしくは行なうにも行なえない)。 ●「免罪符搬送」という問題点 また逆に、一次・二次の救急段階で、すでに救命は絶望的な状況にありながらも、地域に救命救急センターがある以上は無意味を承知で搬送する、ということもある。 たとえば異常分娩で救命が困難な状態となり、残念ながらどこに搬送しても助からないのがわかっている妊婦さんを、あえて救命救急センターに搬送しているケース。妊婦死亡の統計を見ると、志望場所が○○救命救急センターなどといった、第三次救急救命機関となっていることが多い。 また、一次、二次の救急病院で心肺停止となった患者が、無意味とわかっていながらも、あえて近隣の救命救急センターへ搬送される、ということもよくある話だ。 これはおそらく搬送を依頼する側の医療機関が、搬送自体を免罪符にしている面もあるのだろうと思う。救命のための搬送ではなく、自己免責のための搬送である。「こちらでは処置ができませんので、○○救命救急センターに搬送しました。そこで助からなければしょうがありません」と家族に言い訳するために無駄な搬送を行なう。こういう無駄な搬送を「免罪符搬送」と名づけてもよいと思う。 ただし、こうした搬送は家族に強いられて、という側面もある。「だめでもともと」とわかっていても救命救急センターへの搬送を望む家族も多く、そうした家族の意向を無視することはできないから。 ●「一次・二次救急」と「三次救急」の決定的な違い 以上のように日本の救急体制は、一次・二次・三次と分別され、それらの医療機関をつなぐものとして病院間搬送というものがあるが、実は一次・二次救急と三次救急とでは決定的な違いがある。 前述したとおり、一次・二次救急の場合、主として一般の方からの直接の救急搬送を受けつける。当然、患者さんは何も診断はついておらず、まっさらな状態である。 そのために、一次・二次医療機関が通常まず行なわねばならないことは、できるだけ正しい診断をつけることである。こうした医療機関は中小企業のようなもので、マンパワーも少なく、限られた医療設備やスタッフの中ではたしてこの患者はいかなる病気かということを、まず一生懸命に考える。そして診断がついて治療の段階となってから、自院で治療するか、三次救急の医療機関へ搬送するかを決断する。 つまり、一次・二次救急の場合、診断からはじまって治療までしなければいけないことのバラエティーが多く、こうした医療機関の医師には診断から治療までの幅広い能力が要求されるのである。 ところが三次救急の場合、一次・二次医療機関からの病院間搬送患者を取り扱うことが多いので、たいていの場合、すでに診断(疑診も含めて)はついている。あとは治療の手順に従い、豊富なマンパワーを駆使して困難な治療を開始する。 たとえば心肺停止患者が救命救急センターに搬送されてきた場合、まずするべきことは決まっている。そして蘇生に成功した場合には、それぞれの基礎疾患に応じた治療を開始する、ということになる。 このように、一次・二次救急と三次救急とは質の面で異なるのだ。前者は外来に来たまっさらな患者さんを対象とするが、後者は主としてすでに診断のついた重症患者の病棟管理といった側面が強く出てくる。必然的に、三次救急は救急というよりは、むしろICU管理というイメージに近くなる。 後者(三次)の場合はしたがってやることがある程度パターン化しているが、前者(一次・二次)の場合はまさに千差万別の患者が来るわけだから、両者に対するアプローチは根本的に異なるものになる。 ●医療側の都合により作られた日本の救急医療システム もともと、救急患者を一次・二次・三次と分けるこの日本式のやり方は、さまざまな重症度の患者が医療現場に混じってしまうと現場が混乱するため、それを避けるために取られてきたものである。 たとえば、心肺停止状態の人の治療を行なっている時に、同時にやってきた子どもの軽症の熱発患者を診るのは非常に効率が悪いもの。だから前者と後者は診る病院を分けよう、という発想から生まれた。 つまり日本的なこの救急患者の分別は、たとえが悪いかもしれないが、ゴミの分別のようなものである。 ゴミは再利用目的のために分別収集される。もしも何もかも一緒くたに出されたら、再利用できるものもできなくなるだろう。ゴミの分別はゴミを出す一般住民のためではなく、行政の都合のいいように考えられた方法である。 これと同じように、救急患者の分別も実は患者さんのためではなく、患者さんを診断・治療する病院にとって都合のいいように考えられた方法なのだ。 したがって、この日本的方法は医療機関からみた効率という点では大変よいものなのだが、実は上記のようなたくさんの問題点を抱えており、患者さんやその家族にとっては必ずしも都合のよいものではない。 こうした問題点をなくしていくにはどうしたらよいのだろうか。次に、日本とは異なった救急医療体制をとっている、北米のER方式を見てみよう。 |
| TOPページへ 地域医療のページへ 第一章その3へ 前ページへ |