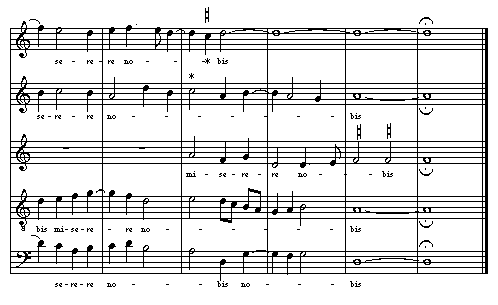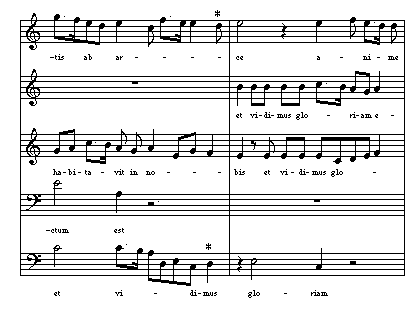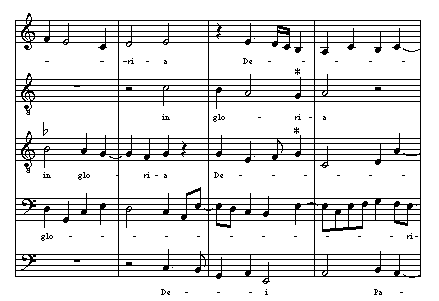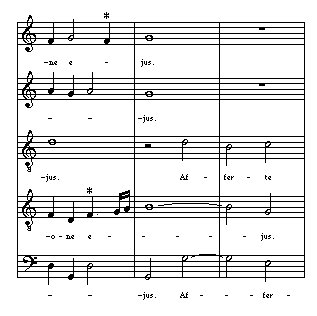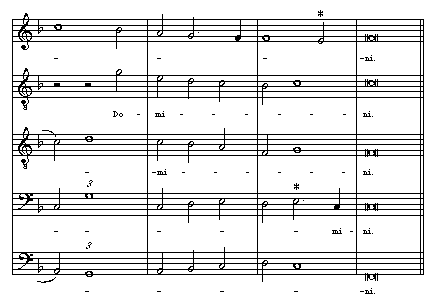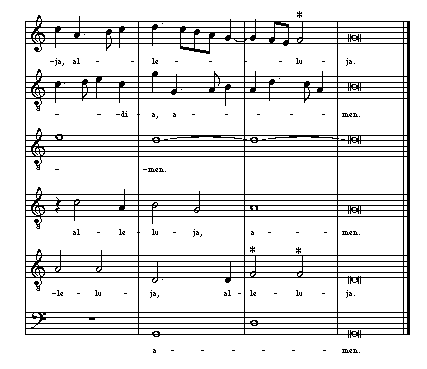<Doubling the subtonic > 音楽エッセイのページへ戻る 声楽作品における特有な半音変化についてへ戻る ”音の近接”に関する古典的学説へ進む 対斜における問題点へ進む
ex.: Clemens non Papa, Missa "Panis quem ego dabo", Agnus Dei
上譜のカデンツにおいては、最上声部と上から二番目の声部との両者がそれぞれ導音を形成している。前者は通常のカデンツ形成でD-C♯−Dとなっており、後者はD−B−Cというカデンツを形成し、譜例における3番目の小節の第2拍が短二度でぶつかっているのである。(c-c♯ 訳注;この譜例においては短二度であるが) はルネッサンス時代の音楽背景では考えられないことであるとした。そして引き続き、1550年頃までのフランドル楽派の音楽においては、あらゆる導音が排除されているということを主張した。
数年後、LowinskyはこのCauchieの不完全八度に関する提案を受け入れたが、しかしあとの過激な結論(訳注;フランドル楽派においてはあらゆる導音が排除されているということ) に関しては否定した。Lowinskyの意見によれば、導音の排除は例外的なものであり、決してすべて排除をしているわけではない、という。(上譜のような) ただDoubled subtonic を避けるためにのみなされるのであり、その他のあらゆるカデンツは半音変化(訳注;つまり導音を形成するということ) を必要とするという。終止は半音ステップによって行われるものだからである。他方より最近の研究では、半音上げられた導音の体系的な使用を是とし、また対斜をも容認する傾向にある。これは主としてティンクトリスやコレアの意見にも近いものである。
この対斜に関する複雑な問題を論じる前に、まずDoubled subtonic の歴史についてより詳しく見ていきたい。<”Doubled subtonic”の起源> Doubled subtonic は、まずフリギア終止において15世紀後半に現れる。以下の例では導音を半音上げる問題は発生しない。それはフリギア終止ではないからである。したがってここでは不完全八度の危険性も問題とならない。O admirabile commercium (訳注;対斜が同じ箇所で起こり、結果的に短二度や不完全八度といった不協和音を作り上げること) を引き起こす可能性のある終止形を使った最初の作曲家であった。
Jean Ockeghem (c1420-1497), Missa "Fors seulement",
Gloria 訳注;上から二番目の声部の*は♯がついて歌われたと思われる
オケゲムの後の世代のフランドル楽派の作曲家たち(オブレヒト、イザーク、ジョスカンからクレキヨン、クレメンス・ノン・パパ、ゴンベール、セルミジ、Manchicourtにいたるまで)にとって、こうしたやり方は一般的になった。そしてこうした終止形を使用しない作曲家はほとんどいなかった。(訳注;多声であればあるほど、終止において同時的な対斜による不協和音が起こっても耳で聴いてわかりにくくなるためにその問題点もはっきりしなくなる)
<統計学的考察> 統計学的考察により声部数とDoubled subtonic との関連性が明らかになる。以下のようなジョスカン、イザーク、クレメンス、ゴンベールの作品から1000の終止形を選んだ調査結果はDoubled subtonic が5声の作品においてしばしば出現し(ほぼ30%)、6声の作品においては通常のカデンツを上回りさえもする、という事実を明らかにした。Table
1
Number of voices Normal cadences Doubled subtonic Errors
3 voices
60 (98.3%)
0 (0%)
1 (1.6%)
4 voices
320 (98.7%)
4 (1.2%)
0 (0%)
5 voices
124 (71.2%)
50 (28.7%)
0 (0%)
6 voices
35 (38.4%)
56 (61.5%)
0 (0%)
Total
539 (82.9%)
110 (16.9%)
1 (0.1%)
Doubled subtonic の頻度は音楽のジャンル(宗教曲か世俗曲か)とは無関係であることがわかる。(下表参照)Table
2
Genre Normal cadences Doubled subtonic Total
Secular
32 (60.3%)
21 (39.6%)
53
Sacred
127 (59.9%)
85 (40.1%)
212
以上の結果は格別に興味深い。なぜならばLowinskyの意見とは正反対だからである。彼の意見によれば、Doubled subtonic は、旋法的な終止(訳注;半音化した導音を使用せず、全音同士で終止をすること) を強調したり、作った曲に色合いを与えるために、作曲家によって”意識的に”使われるという。もしそうであるならば、旋法的終止はグレゴリオ聖歌の荘厳さと簡素さの精神と密接に関連しているために、特に宗教音楽との関連が深いと考えるのは妥当なことと思われるが、すでに見たように、統計的アプローチなこうした見方を否定している。(訳注;たとえばイオニア旋法、リディア旋法のような長音階では音階の最後SiDo、MiFaは必ず半音となる)。 したがってこうしたケースにおいては、七度のダブリングが不完全八度となることはあり得ない。(訳注;イオニア、リディア旋法では旋法内の音ですべての導音を作ることができるので、終止においては♯や♭などの臨時記号を必要とせず、したがって導音が二重化してもカデンツにおいて臨時記号付きの音とナチュラルな音がぶつかり合うことはない。但し後で述べられているようにこの両旋法においてもF−Eや、B−Cで短二度でぶつかる可能性もある)
Table 3
a) Cadences with five actual voices:
Final Normal cadences Doubled subtonic
g
74 (71.1%)
30 (28.8%)
f
34 (87.1%)
5 (12.8%)
Total
108 (75.5%)
35 (24.4%)
b) Cadences with six actual voices:
Final Normal cadences Doubled subtonic
g
17 (34.6%)
32 (65.3%)
f
12 (50%)
12 (50%)
Total
29 (39.7%)
44 (60.2%)
この表の結果では、我々の期待は見事に裏切られている。すなわち導音のダブリングは、Gの終止において、若干多くなっているのである。(訳注;上記の推論からすればFで終止するリディア旋法の方が導音の二重化には無頓着でいられそうに思えるが、結果は逆ということ)。 つまり不完全八度のリスクは、作曲家をして、七度のダブリングを禁じさせない。(訳注;たとえばG−F−Gといった進行が導音化によってG−F♯―Gとなること) は以下で論じられるレパートリーにおいては適用されないということである。多くの例で、導音はカデンツにおいては必ずしもダブらないし、さらにまた下譜のように、他の声部が鳴っている間に一つの声部が半音下降して不協和音を形成することもある。
ex.: Josquin Desprez, motet Cantate Domino canticum
novum
major second (or ninth): f-g. But if the cadence were in f, this second (or ninth)
would be a minor one (e-f), which is much more dissonant:Gで終る特別なケースでは、上記の例のように、”長”二度(ないしは九度)すなわちF−G間の一過性の不協和音が出現する。しかしもしもカデンツがFで終るのであればその場合、この二度は下譜にあるように、E−Fという、より不協和音的な短二度となる。
ex.: Heinrich Isaac, Missa de Beata Virgine (I),
Sanctus
Thus, contrary to our initial supposition, doubling the subtonic entails
harmonic consequences which are more noticeable for cadences in f than
in g. This could be the reason why composers are seen to be more cautious
about the former than the latter.それゆえに我々の当初の仮定に反して、導音のダブリングは、Gでの終止よりはFでの終止において、より顕著なとなる。(訳注;音楽形式的にはFでの終止の方が導音の二重化を作りやすいことになるが、技術的にはむしろGでの終止の方が作りやすいということ) <イタリア> (訳注;イタリアは14世紀にはいわゆる”トレチェント”という早咲きのポリフォニーが発達していたが、15世紀になるとその主導権をブルゴーニュ楽派やフランドル楽派の作曲家たちに奪われていた) Doubled subtonic のテクニックにしたがっていた。
ex.: Adrian Willaert, Verbum bonum et suave (published
1519)
訳注;最上声部の*は♯がついて歌われたと思われる しかしながら後になって、こうした特徴はほぼ同時代に出現した導音を記譜する習慣と相俟って、彼らのレパートリーから排除されるようになった。こうした変化は当時のイタリアの理論的研究における隣接原理(訳注;隣接した臨時記号をどのように扱うかという問題で、前ページにその解説があります) の復活にも通じるのである。<フランスとフランドル> Dialogue a Sept parties "においてはもはやこうした古いフランドル楽派のテクニックは用いておらず、すでに多くの記譜された導音の臨時記号を用いている。それゆえ、こうした技術のフランドル楽派への移行期はおよそ1560年頃と思われる。Doubled subtonic の欠如)も認められる。Dialogue ”の中のterminus ante quem と一致する。Doubled subtonic を避ける方向にむかっている。ヤコブ・レニャールのSacrae aliquot cantiones (1575)や、1578年にアントワープのプランタンで出版されたGeorge de la Heleのミサ曲などはPaschal
de l'EstocartのOctonaires de la Vanite du Monde (1582)と同様、まさにこの流れの中にある。Doubled subtonic はもはや見出されない。さらにl'EstocartのOctonaires(これは増六度の例を多く含んだ、和声学的見地からは驚くべき大胆さをもった作品である)における1ケースを除いては不完全八度も認められない。音楽エッセイのページへ戻る 声楽作品における特有な半音変化についてへ戻る ”音の近接”に関する古典的学説へ進む 対斜における問題点へ進む