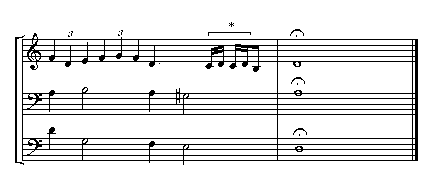
訳注;mi contora faを避けるために、アスタリスク部分は当然、♯をつけて演奏されたであろう
対斜における問題点
音楽エッセイの頁へ戻る
Doubling the subtonicへ戻る
二重化された導音の歴史を概説したあとで、われわれは同時的対斜(=不完全八度。訳注;対斜が譜面上同じ場所で起こるためにクラッシュすること。通常対斜といえば同一小節上で起こるものを指す)の問題について考えていきたいと思う。当時の音楽言語における使われ方を鑑みると、以下の3つの観点からそれは考えうる。
①声楽作品の研究
②理論家の意見
③器楽曲のタブラチュア譜からの証明
①声楽作品
すでに見てきたように、導音の臨時記号の記譜は16世紀の最初の半世紀におけるフランドル楽派のポリフォニーにおいては行われていなかった。特殊な不完全八度がこの時期の作品のカデンツには現れなかったのはそのためである。
事情は1530~40年頃には♯の臨時記号が増えてきたイタリアではいくぶん異なっていたが、実際にはやはりこの時代の資料においても記譜された不完全八度に伴う二重化された導音の例を見出すのは不可能である。仮に同時的な対斜がこの時代の音楽に特徴的なものであったならば、コピイストや出版者もおそらくこうした導音を多少は記譜していたのではないだろうか。
1560~70年頃のフランドル楽派の音楽はすでに半音変化の記譜を行っていた。こうしたやり方に対する少数の例外がG.リースによって観察されている。すなわち、J.ヴェトの作品においてである。しかしこれは決定的なものではない。このケースにおいては、対斜はヴェトの存命当時(1564年)に出版された声楽パートには見出されず、彼の死の15年後に出版された器楽用編曲において認められる。
他方、同時的な不完全八度の記譜はバードやタリスといった16世紀後半の有名な英国の作曲家の作品においても見出される。しかしこうした作品の研究は困難な問題を伴っている。
②理論家の考え
中世からルネッサンスにかけての多くの理論的著作においては完全八度音程内におけるMi contra Faの有名な禁則(訳注;Fa-Si間の三全音のこと。ソルミゼーションの読み替えでMiはsiとなるために、こう言われる。一番下の図を参照のこと)が述べられている。この禁則は不完全八度の音程内においても同様な感じで減五度として振舞う。
しかし上声部同士で作られたⅡ-Ⅰカデンツにより発生した減五度がルネッサンス期の音楽においてはかなり普遍的なものであったことはよく知られている事実である。(訳注;たとえば下譜の二重導音において上声部の*のドが♯を付されないままだと中声部のG♯とで減4度が発生する)
ex.: Buxheimer Orgelbuch, Vierhundert Jare
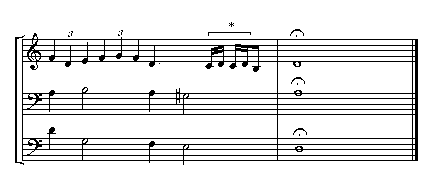
それゆえ、Mi contra Faの禁則は例外があって当たり前という前提で存在していたということが理解される。これは不完全八度や減五度においても同様である。しかし理論家たちはこうした不協和音の性質についてより詳細な考えを打ち出し、おのおのの不協和音の違いを明確にしようとした。
・二重化された導音を含む特殊なカデンツにおいて不完全八度を禁ずる理論書
(?) Ramos de Pareia (1482)
Francisco Tovar (1510)
Nicola Vicentino (1555)
Vincentio Lusitano (1558)
・不完全八度は禁ずるが減五度の使用は可とする理論書
Juan Bermudo (1555)
Tomas de Santa Maria (1565)
・不完全八度は減五度よりも耳障りであると主張する理論書
Johannes Tinctoris (1477)
・不完全八度は音楽に聴きなれた聴衆のみならず、一般人にも耐えがたいものであるとする理論書
Pietro Aaron (1529)
Ghiselin Danckerts (around 1550)
これまでに述べられたティンクトーリス、ラモスの二人の初期の理論家(Tinctoris, 1477, and Ramos, 1482)は確かに注目に値する。なぜなら彼ら両者ともがあらゆる完全協和音程(すなわちオクターブ(完全八度)に加えて完全五度をも含んだ)においてMi contra Faを禁じているからである。(ティンクトーリスはまた不完全八度に加え、減五度をも含む例を示している。これに対してラモスはユニゾンについて言及し、さらに完全協和音程をもそこに含めて考えている)
さらにティンクトーリスは、ほとんどの作曲家たちはこうした禁則にも関わらず、禁じられたタイプの不協和音を用いている、と言う。この意見はdoubled
subtonicを伴うカデンツの特殊な場合としての不完全八度の示唆ないしは正当化と考えるべきである。
ティンクトリスの著作が現れた頃までにはdoubled subtonicはまだ非常にまれなものであった。前頁にも書いたように、オケゲム(1420頃-1497)がこうした状況を最初に作り出したのであるが、しかしそれはその後に続く世代のフランドル楽派(オブレヒト、ジョスカン、イザークなど)の作曲家たち以前の世代ではいまだに一般的ではなかった。ラ・リュー(1460頃-1518)やコンペール(1445-1518)といった当時の有力な作曲家でさえ、こうしたテクニックに気付いてはいなかったのである。
したがってティンクトーリスがdoubled subtonicを伴うカデンツで現れる不完全八度の存在をほのめかしていることはもっともなこととはいえない。
以後、この稿ではティンクトーリスの時代の作曲家による減五度の使用を援護するにとどめよう。しかしそのあいまいさはティンクトーリスが偽の五度や偽の八度といったものを拒否し、こうした概念をきちんとl区別しなかったために起こったものである。
<まとめ>
15世紀後半~16世紀の理論的論証は不完全八度をカデンツを構成する要素としては認めなかった。こうした状況は16世紀後半~17世紀以前までは特に大きな変化はなかった。(T.モーリーは1597年に不協和音程カデンツを認めない、と主張したThomas Morley, 1597, who attests the dissonant
cadence without approving of it Tudor Music p165参照)
③タブラチュア譜
器楽のタブラチュア譜もまたこのことに関して有用な情報を提供する。それらは以下の三つのカテゴリーに分類される。
①減五度をそのカデンツに含んではいるが不完全八度はほとんど使用していないもの
②非常に短いフレーズのみに不完全八度を使用するが、カデンツでは使用しないもの
③カデンツを含むより長いフレーズにおいても不完全八度を使用するもの
③はこの研究に関して非常に興味深いものとなっている。このカテゴリーに入るクリーバーのタブラチュア譜には持続する不完全八度の四つの例が示されている。また同じくバクファークのそれは9例ある。しかしそれらすべては同じ作品においてあらわれる。そしてそれらはピートンによるフランドル楽派の作曲家たちの作品の器楽編曲である。
こうした特殊なケースにおいて、イタリアのリュートタブラチュア譜の記譜法は音符の正確な長さをあらわすことができない。そのために対斜が連続的に交叉して現れているのか同時に現れているのかは確かめようがない。
それゆえ、明らかに不完全八度の使用をしているFridolin Sicher やDiego Pisadorのような作曲家の間ではとりわけ上記のような叙述が必要となる。特にPisdorの場合はその評価が難しい。彼はおそらくアマチュア音楽家であり、理論家Bermudoによってその不器用な器楽編曲(それはまたプロ歌手からもからかわれた)をからかわれた酷評された人物である。
Sicherに関しては、彼のタブラチュア譜は不完全である。とにかく彼らの仕事はその当時の器楽曲全体の代表とみなすことはできない。
ルネッサンス時代のタブラチュア譜の作曲家の大部分は彼ら自身による同時的な偽オクターブの扱いに関しては慎重である。もしも偽オクターブが(特にDoubling
the subtonicにおいて)フランドル楽派の声楽ポリフォニーにおいて通常使用される音程であったならば、同時代の器楽曲においてももっと自由な作風のものが増えていたであろう。{訳注;偽オクターブ(false octave)という語はおそらくimperfect octaveと同義だと思われます}
English music
垂直の対斜(訳注;English cadenceのこと)は英国においては16世紀後半より以前には見出すことができず、もっとも初期のその例は1575年のバードとタリスのCantiones quae ab argumento sacrae vocanturに見られるものである。
ex.: T. Tallis, When Jesus went into Simon the Pharisee's house
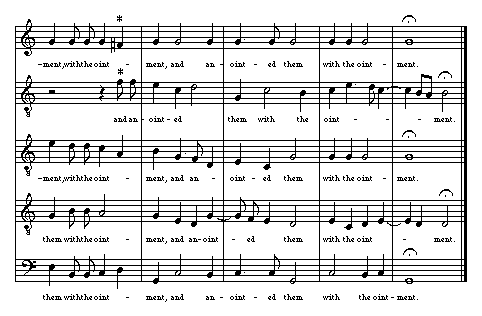
しかしおそくとも1575年までには,doubled subtonicはすでに完全に大陸からはなくなっており、上に引用したタリスの曲と同様な例は英国のみに見出される特殊なケースなのである。
この例よりもさらに初期のものを見つけ出すことは興味深いことであるが、しかしここではこうした作品の違った問題を取り上げなければならない。すなわち1575年以前の、主として世紀半ばの宗教的闘争により逸失したりしたみじめな作品の保管状態についてである。
16世紀の初頭までに、英国のポリフォニー音楽の主なソース(イートン・クワイヤーブックやカイユス・クワイヤーブックなど)は大陸のそれとはその形式においてまったく異なった作品群となっていた。
同時代のフランドル楽派やイタリア楽派の典型的なカデンツ定式、すなわち六度からオクターブへの進行、半音上げられた導音による上声部進行などは、英国のレパートリーには欠けていた。たとえそれらが英国音楽に見出されたとしても、(大陸で発達した)近接した音同士の原則(すなわち導音)が使われていることはなく、、むしろ稀なケースながら大陸の基準に反するようなことさえあった。
ex.: Richard Davy, Stabat mater dolorosa (Eton Choirbook)
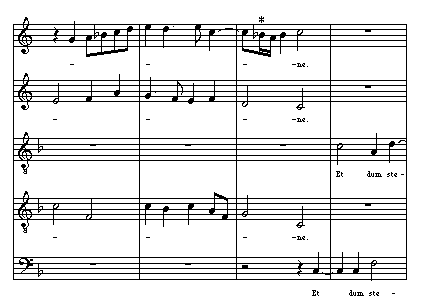
[See HARRISON, F. Ll. (ed.), The Eton Choirbook, London, Stainer and Bell, 3 vol., 1956-61 (=Musica Britannica X-XII), vol. 2, p. 89/140.]

https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/5/56/IMSLP282756-PMLP458640-eton_parte_4.pdf 17/37
こうした例は同時代のBuchnerのようなドイツのオルガンタブラチュア譜のパッセージを思い起こさせる。
つまり近接した音同士の処理の原則は15世紀末~16世紀にかけての英国のレパートリーにとってはあまり重要な要素ではなかったのである。しかし1530年代からは何人かの英国の作曲家たちは大陸の作曲家らによってすでになじみになっていたカデンツ定式を使いはじめた。
そうした作曲家としてはたとえばタヴァーナー、タイ、シェパードらがいる。しかし上記の近接原理がすでにこの時代に使用されていたのかどうかを知ることは困難である。なぜなら16世紀中ごろに書かれた作品群はよりあとの時代の写本を通して受け継がれてきたが、そうした版では作曲家自身の時代よりもより新しい時代の概念が含まれてしまっているからである。
しかしながらこうした状況下での作品の知識であるにせよ、こうした後の世代の眼を通った写本(それは臨時記号の問題も含む)が私たちに16世紀の音楽を伝えてくれているのである。(See CHADD, D. (ed.), John Sheppard: I, Responsorial music, London,
Stainer and Bell, 1977 (=Early English Church Music 17), p. x.)
だが少ないながらも今日の研究において特に重要性を持つ当時の写本も残ってはいる。
Forrest-Heyther partbooks: early 1530s.
Henrican partbooks: around 1539-41.
British Library, Ms. Roy.Add. 74-7: around 1547.
Gyffard partbooks: between around 1540 and 1580, but mainly 1553-58.
こうしたケースにおいては、半音変化はより後の写譜屋によって付け加えられ、オリジナル版の状況を見つけ出すのは不可能ではないにせよ、きわめて困難である。
こうした16世紀半ばの作品においては同時的な対斜はかなり見出すことができるが、それらのいくぶんかはまだ検討中の問題である。
ex.: Thomas Tallis, Benedictus (Roy.Add. 74-7)
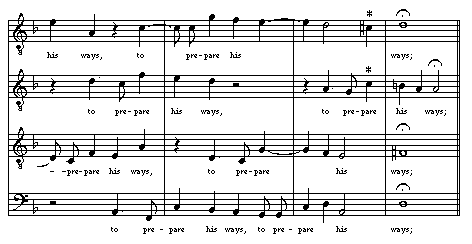
しかしその大部分はわれわれの研究課題に貢献する可能性は少ない。多くはまったく非合理的であり、それらが作曲家の意図に忠実であることは期待できない。
ex.: Christopher Tye, Alleluya. Per te Dei genetrix (Gyffard Partbooks)
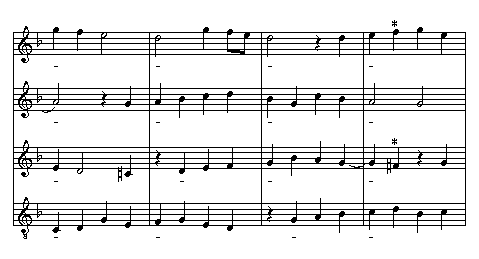
こうした問題はすでにオリジナル版を再建しようと試みた専門家たちによってすでに強調されている。
結局バードやタリス、モーリーらによってその典型例が示された不協和音カデンツが出現した正確な年代ははっきりとしない。少なくとも1530年よりあとであることは確かであるが。
もしも対斜が16世紀半ばからのイギリス音楽で見出されると考えるならば、こうした不協和音は、すでにフランドルやイタリアの音楽家たちが入り込んだ多様な状況に合致することになる。不完全なオクターブは、訓練を受けていない耳にさえも耐えがたいものであると言った上記のAaronやDanckertsらの主張を再読する必要があるだろう。
言い換えれば、英国音楽の場合、大陸の音楽のカデンツにおける偽オクターブの導入を正当化するのには不十分なのである。
<結語>
不完全八度は、あきらかに16世紀当時のフランドル楽派の音楽には認められない。そして七度のダブリ(訳注=導音の二重化)は、導音のない旋法的カデンツを許容させる結果となる。(訳注;doubled subtonicがあると、どちらかが半音変化になるために音がぶつかり不完全八度になる。ぶつからないためには結局導音化しないでもとの旋法的な動きをしていればよいということ)
しかしこの旋法的カデンツの許容が、doubled subtonicを持つカデンツのみに適用されるのか、あるいはすべてのカデンツに適用されるかについては次の二つの説が考えうる。
1導音の二重化は旋法的カデンツを強いるために作曲家によって意識的に用いられたテクニックである。結果的には、その他のカデンツにおいては近接導音の原則(Lowinskyの仮説。訳注;導音の排除はただdoubled subtonicに対してのみなされるべきであり、その他のあらゆるカデンツは半音変化を必要とするというもの。前頁参照のこと)が適用されるべきである。
2あらゆるカデンツは旋法的のままにされておくべきである。二重化された導音は本来旋法的であるべき導音の問題が目に見える状態となったものであるにすぎない。
前者の説においては、カデンツの旋法的形式は、その切り詰めた、あるいはほとんど禁欲的な、しかし壮大な色彩により、宗教音楽的なものとして優先的に保たれていくべきであると考える。
三声、四声、五声あるいはそれ以上の声部の作品においては明らかな相違はないが、すでに見たように統計的研究が明らかにこの論争の決着をつけてくれるであろう。
後者の説においてはより詳細に考察されるべきである。よく知られている事実ではあるが、ルネッサンス音楽のカデンツの大多数は以下に示すようなパターンである。
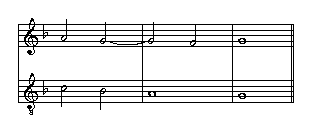
一つの声部が入ってきても他の声部は変化せずにそのまま残るために、カデンツの流れは急には変化できない。(訳注;係留音が形成されるため)この基本パターンは以下の2つの方法で解釈されうる。すなわちa.導音を取らずに厳密に旋法的に流れるか、あるいはb.導音を取って進んでいくか、である。後者では結局古典的和声法と同様な結果となる。
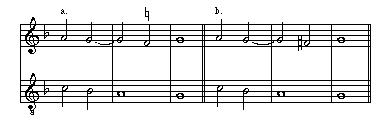
もしも作曲家が後者の解釈を取れば、導音の扱い方について非常に注意を向けねばならない。もしもその導音がk重なれば、対斜が発生する。他方またこのケースでは導音を重ね、旋律の跳躍やアルペジオ、速いパッセージなどに利用することもできる。こうしたことは1560年頃のオケゲムやジョスカンの時代のフランドル楽派の作曲家たちによってすでになされている。
もしdoubled subtonicが四声からせいぜい六声の曲のみに使われているに過ぎないとするのであれば、それは和音の真ん中の導音を重ねることが三声から四声しか対旋律のない曲では実際的ではない、という理由による。
このあとの説は以下の如く発展形させられる。
1この説は二重化した導音が声部数と関係があることを証明する。
2この説は二重化した導音が宗教曲か世俗曲かには関係ないということを証明する。
3フランドル楽派のレパートリーは近接導音の原則の適用により生ずる和声上の問題を忌避する傾向にある。
4、5省略(訳者)
6この説はティンクトーリスやグラレアヌスの理論的労作によって、あるいは第一旋法、第四旋法、あまつさえいろいろな旋法(オケゲム)といったタイトルでの同時代人の銘打ちによって明らかにされたように、教会旋法の刷新を体験していた時代のより一般的な描写に適合する。それはアペルが言ったように、ミュージカルサウンドや音楽風味のまさにその概念における一般的な変化にも一致する。
ブルゴーニュ楽派(デュファイ)と初期フランドル楽派(オケゲム、オブレヒト)との間の違いは簡潔に以下のように特徴づけられる。三声部書法から四声部書法へ、比較的高い音域から低い音域へ、器楽的透明性の中世的響きから声楽的ア・カペラ的響きへ、フォーブルドンから三和音へ、飾られた和音スタイルあるいは旋律-伴奏関係からすべての声部が熟成した真のポリフォニックスタイルへ、貴族的繊細さ洗練さから経験ないのりと神秘的表現へ。
<訳者付録>
| Γ | A | B | C | D | E | F | G | a | b♭ | b | c | d | e | f | g | aa | bb♭ | bb | cc | dd | ee | |
| 硬 | ut | re | mi | fa | sol | la | ||||||||||||||||
| 自然 | ut | re | mi | fa | sol | la | ||||||||||||||||
| 柔 | ut | re | mi | fa | sol | la | ||||||||||||||||
| 硬 | ut | re | mi | fa | sol | la | ||||||||||||||||
| 自然 | ut | re | mi | fa | sol | la | ||||||||||||||||
| 柔 | ut | re | mi | fa | sol | la | ||||||||||||||||
| 硬 | ut | re | mi | fa | sol | la |
上記のソルミゼーションの図はhttp://www.geocities.jp/gammautalamire/index2.htmlよりお借りいたしました。
音楽エッセイの頁へ戻る
Doubled the subtonicへ戻る