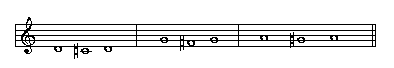
音楽エッセイのページへ戻る
Doubling the subtonicのページに戻る
The "classical" doctrine of attraction
私がこれを「古典的」と呼ぶのはそれが昔の権威ある学者たちから繰り返し提案されてきた事柄だからである。そしてそれは現在の音楽学者にとってもまた通用することがらである。
カデンツにおける導音の必要性は中世やルネッサンスの理論家達によって二つの異なった方法で説明されてきた。一つは旋律的な事柄であり、もう一つは同時間隔(協和音の連続)において集中している事柄である。(訳注;わかりづらい表現であるが、あとを読めばわかるように要するに旋律から見ていくか、和音から見ていくかということである)まずは両者の理論的な簡略化されたモデルを検討していきたい。
1.旋律的定式
d-c-d, g-f-g or a-g-aのような旋律の流れにおいて、全音として記譜されるが、実際には特にカデンツにおいては真ん中の音が半音上げられて歌われる。(下譜参照)
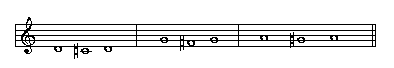
さらにやや少ない場合であるが、下譜のように記譜上はやはり全音であるが、実際には最後から二番目の音が半音上げて歌われることもある。
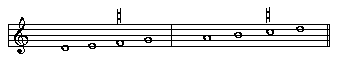
2 和声的定式
もしもカデンツの最後の直前の和音が六度の場合、各パートは反行進行し、オクターブで解決される。この場合六度は長六度となる。必要な場合は記譜された臨時記号が使われる。(下譜参照)
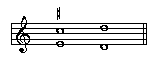
三度や十度、あるいは十二度においては五度への拡大される。(下譜参照)
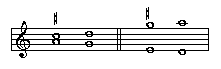
他方、短六度は下譜のように五度で解決される。この場合、動くのは上声部のみである。
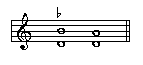
短三度の場合はユニゾンとして解決される。そして短十度の場合はオクターブでの解決となる。
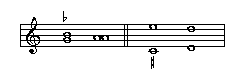
こうした規則は中世後期からルネッサンス期の理論書においてはたびたび出現する。しかしそれらの言い回しは必ずしも完全で歯切れの良いものではない。そして多くの理論家たちは主題をすべてこのようにはアプローチしてはいない。なかにはこうした「古典的」規則に明白に違反していることさえある。それではここからは世紀ごとのこうした全体的な変化を見ていきたいと思う。
13世紀
このテーマにかんするもっとも初期の資料は13世紀後半に現れる。(ガルガンディアのDe musica mensurabili positio.がその例) 著者はオリジナルな述語に絶えず論及する。それはしばしば現代の研究者にとっては理解しがたいものである。
著者はc-d-e-f-gと上昇する音型の接合規則と同様、g-f-gと進行する補助音の役割を含んだ旋律進行の規則について言及している。加えて、彼はこうした規則は主としてグレゴリオ聖歌に適用され、協和音に応じるためにポリフォニーにおいては必ずしも妥当しない、とはっきり述べている。
14世紀
この時代のもっとも有名な二人の理論家、すなわちW.オディントンとヴィトリは隣接した臨時記号の観点からムジカ・フィクタにアプローチはしていない。同じことはJehan
des Mursにもいえる。
有名なAd sciendum artem discantus(そこにはそれまでの時代までに基礎付けられた隣接原理の完全な論述が含まれている)はもはやMursの作とは考えられていない(
Ulrich Michels (1970) や Klaus-Jurgen Sachs (1974)によればこれはもっと新しく、15世紀の著述であるという)
もう一つの理論書Quilibet affectans(これはMurs作と言われている)においては例外を多く含んだ隣接原理の簡単な和声的アプローチからの論述があるのみである。
しかしながらこのテーマに関しては三人の興味深い14世紀の理論家がいる。Marchetto da Padova, Pseudo-Tunstede、パリ理論書の無名人の三人である。
Marchetto da Padova
マルシェットのLucidarium (between 1309 and 1318)は和声を論述した最初の理論書である。(しかしこれはむしろ「古典的」なやり方とは異なった内容である)
彼は、真の半音階はc−c♯であると考えたために、c♯からdへのステップは一全音の1/5に過ぎないと主張した。これは彼が主張した説のうちでも最も驚くべき事柄である。
ex.: Marchetto da Padova, Lucidarium II (between 1309 and 1318), cap. VI
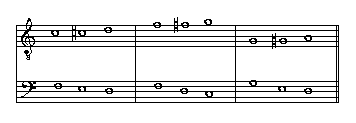
Quatuor principalia
Quatuor principalia(かつてこの書の著者はTunstedeと考えられていたが、その十分な根拠はない)の著者の考えはより変わっている。この書は四つの独立した理論書から成るが、それぞれはいくぶん異なった説を取っている。第三巻と第四巻のみが隣接原理を取り上げているが、それぞれは別の方針で書かれており、整合性がない。
第四巻は和声学的論述を含んでいるが未完であり、あまり興味も引かない。これに対して第三巻は高い独創性があり、グレゴリオ聖歌を扱って隣接原理の旋律的定式に言及している。(しかしながらその内容はただ単にそうしたことを否定しているだけであるが)
Capitulum LVI. Quod intervalla vocum perfecte pronuntienturより
ソルミネーションの一つ一つの音節に応じた間隔は正確に歌われるべきであるが、その上に言いたいのは半音が全音の代わりに歌われるべきではないし、その逆もしかりであるということである。この点に関し、最近の人々は誤解をしている。レからファを通ってソへ上がるとき、たいていの人々はファとソの間に半音を置かない。
さらに、ソファソあるいはレドレと歌われるとき、人々は全音ではなく半音上げて(たとえばソファ♯ソという具合に)歌う。そこで人々は全音階の元を混乱させ、グレゴリオ聖歌を破壊することになる。もしあなたがなぜ人々が全音の代わりに半音で歌うのかと尋ねれば十分な権威と理由を持って彼らはこう答えるだろう。すなわち高い地位にある人々がチャペルでそのように歌っているのだ、と。
彼らはさらに言うだろう。こうした歌手たちはやみくものそうして歌っているわけではない。なぜなら彼らは非常にすぐれた歌い手だから。彼らは他人の足あとでミスリードされ、結局彼らすべてが誤った方向へと進んでいるのだ。
この著者は近接した臨時記号(すでに譜で紹介した補助音や上昇音型における旋律定式)の紹介に抵抗しただけでなく、彼の時代や国における音楽活動に対して興味深い情報を提供したのである。貴族の教会に対して、大陸芸術の実践の影響のもとで、彼は13世紀の理想をかたくなに守っている本来の英国の伝統を際立たせたのである。英国固有の14世紀のレパートリーにおいて、記譜された近接した臨時記号は稀なことだったからである。
以上のことは結局次のようにまとめられる。すなわち14世紀の保守的傾向にあった英国では近接した臨時記号そのものを否定していたのである、と。
パリ理論書
パリ理論書の無名人にとっては、記譜されない近接した臨時記号の存在を証明することがまず第一であったと思われる。しかしそれに相当する年代は不明であり、だいたい14世紀後半と類推するしかない。
音楽エッセイのページへ戻る
Doubling the subtonicのページに戻る