| 「メサイア」―モーツァルト版とプラウト版の比較研究(各論)その4 |
| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その3へ戻る その5へ進む |
●Glory to God in the Highest <モーツァルト版>+フルート、オーボエ、ファゴット、、ホルン、トランペット、ティンパニ ↑ヘンデル原典glory to God この曲の原曲においては、トランペットが大活躍をする。しかし、残念ながら、モーツァルトの時代には、そうしたオーケストレーションは、時代遅れになっていた。バロック期のトランペットの名人芸は忘れられてしまい、トランペットはこの時代、ティンパニと共に、オクターブや完全5度を中心とした単純な音型を吹いて、オーケストラにアクセントをつけるだけの存在に成り下がってしまっていた。 当然、モーツァルトは時代に応じた編曲を行なった。すなわち、ヘンデルのパートはばっさりと切り落とし、古典派時代のトランペット奏法へ切り替えた。  この良し悪しに関しては、今日からでは評価できない。モーツァルトはトランペットの用法をこのようにしか書きようがなかったわけなのだから。したがって、モーツァルト版で演奏する場合、ヘンデルのトランペット奏法は捨てざるを得ないのであり、それがいやなら、モーツァルト版は諦めるか、プラウト版を使うしかない。 <プラウト版>+フルート、オーボエ、ファゴット、、ホルン、トランペット、トロンボーン、ティンパニ 14分33秒〜 プラウトは序文で、モーツァルトがこの曲のトランペットを変更してしまったのでそれを元に戻した、と書いているが、これは時代背景を考えれば、当然のことである。プラウトの生きた20世紀初頭、すでにトランペット技術は復活しており、バロック音楽自体が復活していた。したがってプラウトがモーツァルトを引き継ぐはずはなく、序文の文章は当然のことと言える。 さらにモーツァルト版とプラウト版、との違いは、and peace on earthの部分の取り扱いである。モーツァルトはこの部分をフォルテとし、ティンパニとトランペット、ホルンを使用し、その後を木管楽器+ホルンの合奏としている。プラウトはこの扱いを、余分なものがあるとして、付加するのはホルンのみとしている。 ●Rejoice greatly o daoughter of Zion <ヘンデル版> <モーツァルト版>+2声のヴァイオリン、ヴィオラ 原曲は、ヴァイオリン2声+ソプラノ+チェロバスの4声であるが、ヴァイオリンは途中の一部を除いて実質的には1声なので、実質的にはトリオソナタ形式である。モーツァルトはこの実質トリオソナタの上に、ヴァイオリン2声とヴィオラを置いている。 新たに置かれた2声のヴァイオリンは、基本的にもともとのヴァイオリンパートと同じ旋律を弾いているが、通奏低音のみの部分にくると、この付加ヴァイオリンが、ヴィオラとともに、活躍を始める。すなわち、本来ならばオルガンやチェンバロで埋められていた和声を3声の弦楽が代わりに弾いているのである。こうした処置により、いかにもバロック音楽的な部分は、より古典派音楽(具体的に言えば、弦楽四重奏曲のような)に近づくことになる。 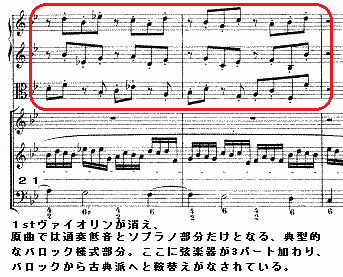 ヴィオラは最初こそ通奏低音と同じ旋律をなぞっているが、中途よりしばしば独自の旋律を弾くようになる。(通奏低音と一緒になることもある) よく聴いていないとわからないのだが、よく聴くと、うまいこと中声部を埋めていることがわかる。 <プラウト版>+ヴィオラ、クラリネット、ファゴット 16分52秒〜 モーツァルト版とかなり異なっている。実際プラウトは序文の中で、この曲について、”Thie is one of the least satisfactory numbers of Mozart' score”とまで言っている。さらに続けて、”a considerable part of the movement being left in two-part haromony only"と言っている。要するに、モーツァルトがあえてトリオソナタに近くしておいたことが気に入らないらしい。 では何が気に入らないのかというと、モーツァルトが原曲をあまりいじらずに(前曲とは正反対!)おいたことがいかん、と言っている。そして自分は全面的に伴奏を厚くしたの、と言っている。 ということでプラウトのスコアを見てみると、なるほど、モーツァルト版とはまったく違う。まず目に付く(耳に響く?)のが、最初から始まるクラリネットとファゴットの伴奏だ。本来快活なリズムであるこの曲に、べったりと全音符が張り付いている。全体にスラーが多く、いくら和音を埋めるとはいえ、まったくこの曲の軽快なリズムとは相反する伴奏である。  なぜにプラウトはこのような奇っ怪な伴奏をつけたのか。そもそもその精神は、前曲と正反対ではないか。 おそらくは、プラウトはこの曲の通奏低音に伴う楽器はオルガンがよいのではないか、と考えたのだろう。もっともそれなら、わざわざ木管楽器群にしなくても、オルガンそのものでもよかったのではないか、と思うが。 しかし、この曲はやはり和声はオルガンではなく、チェンバロで埋められるべきであろう。ソロの快活なリズムと、やや鈍重なオルガンのリズムは合わない。やはり、チェンバロがよい。 したがってやはりこの部分の朗々とした木管楽器は蛇足である。 前曲「glory to God」においては、プラウトはモーツァルトの書いた木管楽器群を消し去った。また、pastraleにおいてもやはり同様のことをしている。にもかかわらず、この曲に関しては、逆に無駄な木管楽器群をつけ加えている。 ヴィオラに関しては、基本的に、モーツァルトのものを踏襲しているが、モーツァルト版にて通奏低音と一緒になる部分では、あえて独自の主張をしている。要するに、常に”three parts”となっているのだ。 結局、モーツァルトがpastralをいじくりすぎたように、プラウトはrejoiceをいじくりすぎた。モーツァルトは偉大な作曲家だから、いじりすぎてもあまり後世の人から文句も言われないが、プラウトは作曲家としては二流だったから、いじくりすぎるとボロクソに言われるのだ。 ●His Yoke is easy <モーツァルト版>+オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン この曲は、And He shall purifyとFor unto us a chile bornに続いて、合唱がソロカルテットとtuttiに分かれているが、前2曲と異なり、明確なリトルネルロ形式は取っていない。Tuttiは最後に申し訳程度に現れるだけである。 この曲は、前曲とは正反対に、通奏低音に伴う鍵盤楽器はチェンバロよりはオルガンがふさわしい。おそらくヘンデルは、弦楽器群が休止している部分は、かなり積極的にオルガンの即興演奏をしたのだと思う。 モーツァルトは、そうしたヘンデルの意を汲んで、弦楽が抜けている部分を中心に、管楽器によってオルガンの代替を試みている。また、管楽器の合いの手の役割も受け持たせている。 それにしてもこの曲は、他の曲と比較して、全体的に薄化粧である。したがってこの曲の編曲の目的は、バロック形式の音楽を強制的に古典派に仕立てなおすというよりは、バロック形式をあえて残すようにモーツァルトは考えたように思う。無論、ホルンパートの使い方などは古典派そのものであるが、あくまでも主目的は木管楽器によるオルガンの代替である。 さてしかし、この曲においても、オーボエ問題が立ちはだかる。すなわち、「for unto us a child bornのごとく、ヘンデルの後期の版ではこの曲ではソプラノに合わせてオーボエが使用され、それがきわめて効果的なのであるが、モーツァルト版ではそれができない、ということである。ヘンデルの原典版に近い演奏でも、バロックオーボエが入っている現状では、この問題は看過できないものである。YouTubeなどでも、モーツァルト版メサイアが、原典版と比較して圧倒的に少ないのは、こうした問題のせいでもあるのだろう。 <プラウト版>+フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、オルガン プラウトは、この曲に付けられたモーツァルトの木管楽器群はヘンデルの雰囲気にはふさわしくない、と判断したようで、すべて取り去ってしまって、新たに書き直している。 プラウトの場合はむろんオルガンが使えたので、モーツァルト版と単純な比較はできないが、木管楽器はオルガンの代替といった目的がより明快になっている。たとえば第7小節までの通奏低音のみの部分は、オルガンがない場合のみ管楽器を使え、と書いてある。 ただ、プラウトは通奏低音の和声の穴埋めは基本的にはチェンバロを考えていたのか、オルガンの使用部分は以外と少ない。基本的には、tutti部分のみにしかその指示がない。またtutti部分は木管楽器もおおむね合唱をなぞって出現しており、プラウトはこの曲の持つリトルネッロ的要素を強調したのかったのかもしれない。 |
| トップページへ戻る 音楽エッセイのページへ戻る その3へ戻る その5へ進む |