| R.Maunder Mozart's
Requiem3 |
| 音楽エッセイのページへ戻る | R.Maunder Mozart's Requiem2へ戻る |
| R.Maunder Mozart's Requiem4へ進む |
| 8 Mozart's Models for the
Requiem 前章では、モーツァルトが、Agnus Dei in th e Requiemのモデルとして、彼の以前のミサ曲、ことに Agnus Dei of K 192, Gloria of K 220,Agnus Dei of K 275を使用したことが明らかになった。確かに、モーツァルトは、自分自身の始まりのために、しばしば他の音楽の刺激を必要とした。 。 Dentは、1907年に、モーツァルトが知っていたと思われるレクイエムの初期の設定について、記述した。そして特に、unfinished Requiem in C minor by Florian Gassmann (1729-74)について注目した。それは、Mozart's ‘Requiem aeternam'へのモデルを明らかに供給している。 ‘Requiem aeternam dona eis Domine'と 'et lu x perpetua lu cea t eis'.の冒頭の言葉の2つの設定には驚くべき類似点がある。Gassmannの版をEx. 8.1に示す。 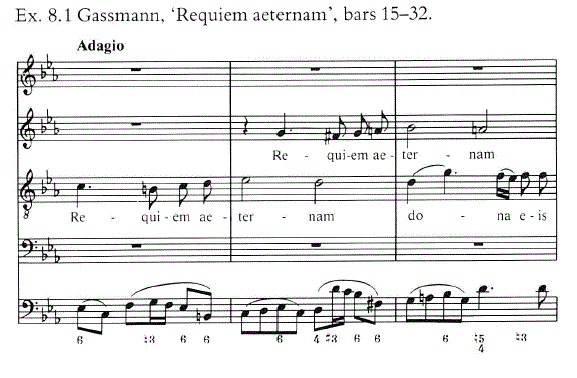 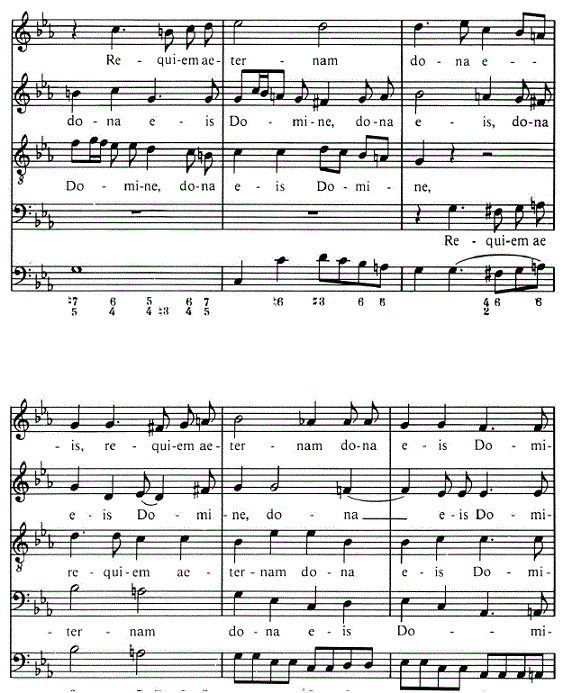 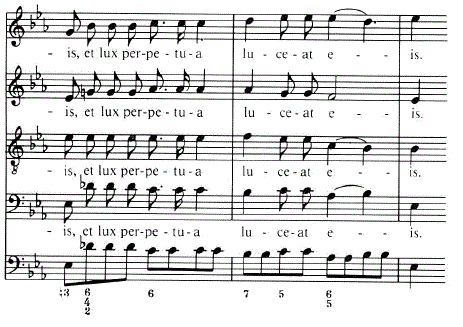 2つのレクイエムでのその他の楽章、特に共通のメロディ素材は明らかではないが、デザイン上は密接に関連している。Gassmann's‘Confutatis'は、その構造だけでなく、その力強い声楽の冒頭フレーズや、対照的な‘voca me cum benedictis'の設定においても、モーツァルトのそれに非常によく似ている(モーツァルトの‘Confutatisにおいてのように、こうした対照的なセクションは、異なった調性で再現されている)。see Ex. 8.2. 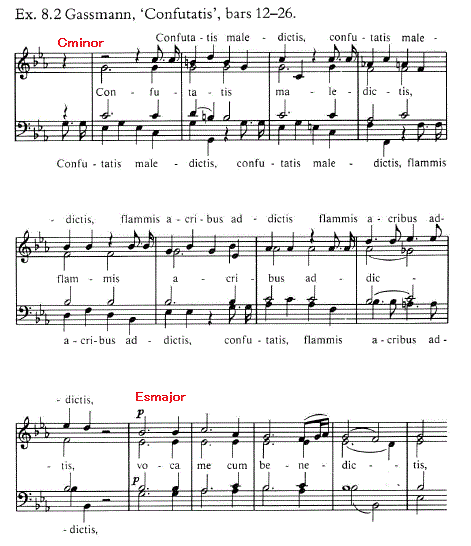 Nowak(1965年)、Abertに従い、その他の作品とのいくつかの類似性を指摘していた。たとえば、Mozart' s K yrieと Handel のメサイアのchorus ‘And with his stripes' との関係など。おそらく、モーツァルトが自分自身で、K339 やK222のような1780年代のほとんど同じフーガの主題を使ったことが、より重要だったのである。 モーツァルトは以前、Requiem aeternam'のメインテーマを以前使ったことがある。それは、Misericoridias Dominiの主たる主題である。 Nowakはまた、Michael Haydn's Requiem in C minorの'Requiem aeternam' 中の‘ Te decet hymnus'への注意を向けている。ハイドンの設定は、プレインソング(Tonus Peregrinus))のメロディの最初のフレーズを使っている。seeEx. 8.5 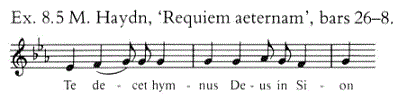 ハイドンがこのテーマを、自分のBenedictus (Ex. 8.6)にリンクさせたことは興味深い。さらに、もっとも最初のモーツァルト自身の先例は、すでにAbertが指摘していように、それはcantus firmus in Betulia liberata (1771)として使われている。seeEx. 8.7  ハイドンの'Requiem aeternam'は、その他の点においても、モーツァルトのそれとよく似ている。声部の最初の入りは、テーマは異なっているが、効果の点では同様であり、特に伴奏のリズムはそうである。さらに、ハイドンの‘et lux perpetua'の設定は、Gassmann'sのそれよりも、モーツァルトのそれに似ている。 ハイドンのセクエンツィアは、彼はそれを一連のものとして作曲したが、ほとんど単一のテーマの楽章は、モーツァルトのより量感的な取り扱いとは似ていない。しかし、‘Domine ]esu',においては、類似性が顕著である。‘Rex gloriae' (Ex. 8.10)や‘et de profundo lacu' (Ex. 8.11)や‘de oreleonis' (Ex. 8.12)のハイドンの設定は、特にコメントをするまでもなく、モーツァルトのそれへの類似性が十分にある。エネルギッシュな‘ne absorbeat eas tartarus’やそれに続く‘ne cadant in obscurum',は、異なったフーガ主題ではあるが、明らかに、モーツァルトのそれと同じ効果を目指している。 さらに、ハイドンの'Quam olim Abrahae'のフーガの主題は、モーツァルトのそれと異なることはない。彼の'Cums anctis’もまた、似たイメージを持つ。 <Biber Requiemとの類似性> 楽譜へのリンク 意外にも、モーツァルトが、Heinrich Biber(1644ー1704)のF minorのレクイエムを知っていた可能性は非常に高いようである。これは17世紀の終わり頃に書かれた曲で、明らかに、ザルツブルグ大聖堂で演奏されるためのものであり、モーツァルトの時代にも時折演奏される機会があった。 Biber's と モーツァルトの設定は、単なる偶然の一致のようには思えない。Biber's‘Quam olim Abrahae’のフーガ (Ex. 8.16)は、モーツァルトの'Requiem aeternam'と同様の主題を持っている。 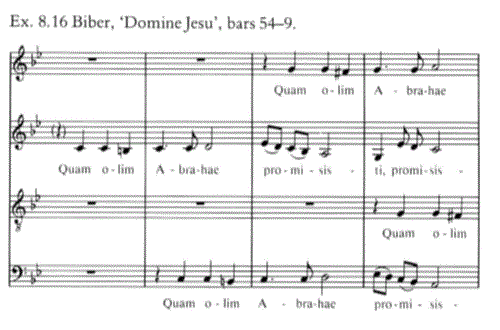 ここは確かにモツレクとよく似ている ‘ne cadant' in the ‘Domine Jesuは、特に同様である。モーツァルトの第29-30小節は、ビーバーの版と比較される(Ex. 8.17).。 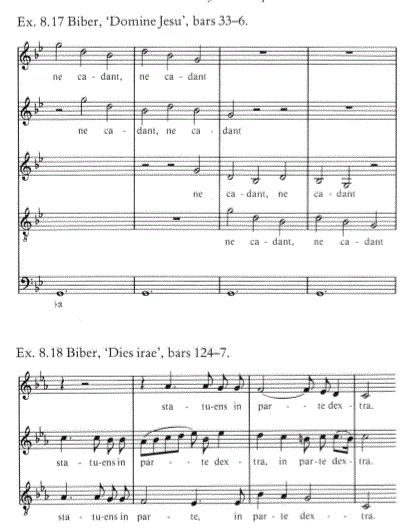 Biberの(Ex 8.18)に、Recordare'の'parte dextra'におけるモーツァルト像の先覚者を見出すことは楽しみであるかもしれない。しかし、 Biberの Oro supplex et acclinis' は、明確に、モーツァルトのそれと同じような和声効果を目的としているものと思われる (Ex. 8.19)。 おそらく、もっとも注目すべきことは、’Lacrymosa '(Ex. 8.20)とモーツァルトのAmenスケッチの主題とBiberの設定との類似性である。その類似性は、モーツァルトの最初の版(Ex. 8.21)でよりはっきりしている。彼はのちに、(Ex. 8.22)に変えた。(モーツァルトのAmenの主題は、むろん、、‘Requiem aeternam'のメインテーマの鏡像であり、ビーバーのレクイエムにおいては、この鏡像版は、‘ Quam olim Abrahae'において、別のやり方で以前生じている)。  最後に、‘Oro supplex et acclinis'への別の先例があるのを見てみたい。これは、モーツァルト自身のReina coeli (Ex. 8.23 K 276 , bars 68-76)である。これは、まったく注目すべきである。すなわち、おそらく、レクイエムの12年前に、モーツァルトはほとんど同じやり方において、非常に似た言葉を扱ったのである。オーケストラの伴奏に対してさえ、彼はレクイエムの不完全なスコアに記していたのである。持続する木管楽器が、最初の小節で静かに声楽と一緒に入ってくることに、非常に注目したい。ジュスマイヤーがモーツァルトのオーケストレーションを、レクイエムで相当する部分で誤解したために、彼は、コーラスの入りの前に、木管楽器の余分なものを加えてしまった。 9 Some Notes on Mozart's Orcheration (前略) こうした点をサポートするにおいてふかんぜんな自筆譜をクラリネット協奏曲K622と比較することは非常に有用である。モーツァルトはあきらかに、ソロやバスパートは何も変えていない。そこでは、初期のはんがすでに彼の頭の中では完全に出来上がっていたことを強く示唆している。なぜなら、彼が、より後の部分を書くまでに、オーケストレーションについて考えていなければ、存在するパートへの重大な変更は行わなかったであろうから。 むろん、'Requiem aeternam'はいくつかの点で、もっともベストなソースではあるg、それ自身では、のちの楽章におけるオーケストラに持ち上がってくるあらゆる問題を解決するには不十分である。どうあれ、それは、 その他の作品から推論される原理がレクイエムに適用されるもっともベストなチェックを供給する。こうした理由から、'Requiem aeternam'の詳細な分析は第10章へと延期される。 モーツァルトのスコアを少し見れば、オーケストレーションはしばしば、ハーモニーから自然に持ち上がってくることがわかる。モーツァルトは非常に注意深く、ハーモニーがつねに完全であることを確認している。そして、こうした原理はしばしば、内声の数や形式を固定する。 たとえば、標準的カデンツであるV7‐Iにおいて、両者の和声を完全にするためには、”5つの”声部が通常、必要となる。これでは、ヴィオラは2分割されねばならず、エキストラな木管楽器がなければならない。通常それはファゴットである。なぜなら、内声にはもっともこれが適当だからである。こうした付加されたファゴットパートは、K621の 'Se all impero' に生じる (Ex. 9.2)。いかにパ―トの数の突然の増加が避けられているかが理解されよう。ファゴットは、最後の4小節でバスト二重になっている。しかし、しばしば、属七が、5音、稀には、3音がないことがある。その進行は、ドミナント上で、7/5 6/4 5/3となる。同じ原理は、弦のアルペジオパターンが非常に注意深くフィットされなければならないことを意味する。たとえば、Ex. 9.3のように。 その他の基本的な和声規則は、いくつかの和音のレイアウトを決定する。モーツァルトははっきり、もしも斜進行ではなく、あるいは、金管楽器において不可避でなければ、同一の楽器のペアの間での五度の響きは好んではいない(場合によっては四度)。 ゆえに、木管楽器のペアはほとんど常に、五度や四度は避けられ、一般的な6/4 5/3カデンツにおいて、第2ヴァイオリンやヴィオラパートは交差し、そのために、ヴァイオリンは互いに6度で動くことができる。Ex. 9.4のように。  ヴァイオリンパート間の五度や四度を避けるために、第2ヴァイオリンとヴィオラの交差は別のところでもまた生じている。 減七和音においては、モーツァルトは決してより高いオクターブへバスを二重にしない。もしもこれが金管楽器上において、絶対的に不可避でないのであれば。‘Donner, Blitz,Sturm ' chord at bar 807 of the Act II Finale of K 620は、20パートのフルオーケストラでのレイアウトであるが、バスの音符(B♭)は、チェロバス、ティンパニ、バストロンボーン、第2ホルンにも使われている。しかし、第1トランペットを除いた高音楽器にはない。 この和音では、弦、金管、ティンパニのみで使われており、木管楽器ではそうではない。 ‘Ah che tumulto orrendo l' section ofthe Act I Finale of K 621 もまた、だいたいこのようにレイアウトされている。 いくつかの雑多なハーモニーポイントは以下のようである。 ①不協和音の経過音は、七度和音(時に九度)の形式で分類されるが、しばしば全音階的な半音のクラッシュがり、通常、動いているヴィオラパートと関係する。 Exx. 9.5 and 9.6 bars 7-12 of the‘Recordare' 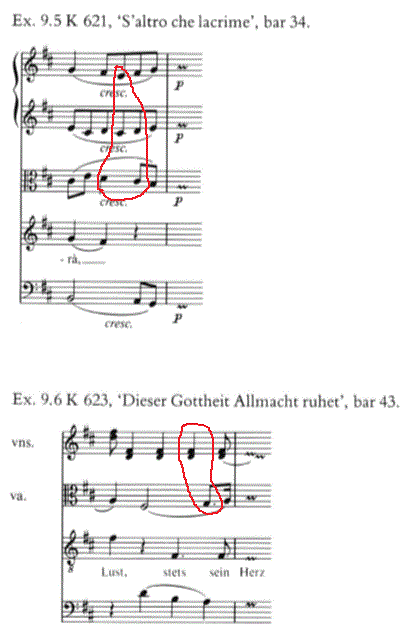 ②ソロパートの.Appoggiaturasは、ときどき、伴奏のリズムを出し抜くような解決をすることがある Exx. 9.7 and 9.8.。しかし、たとえば小節の第1拍を省略することによって、あるいは属七の第3音を省略することによって、こうしたクラッシュを避けられよう。 (Ex. 9.9) ,(Ex9.10) 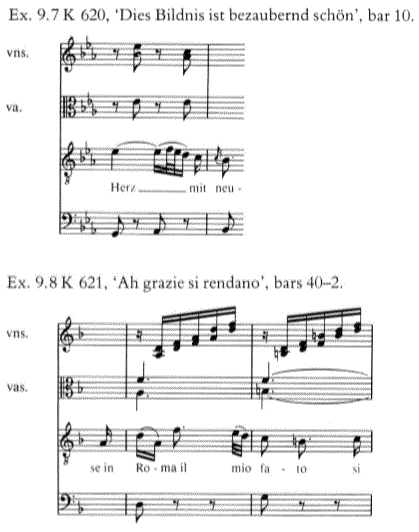   ③オーケストラパートは自由にユニゾンあるいはオクターブであり、ヴィオラとバス、あるいは、弦と木管楽器間の”普通の”連続八度は受け入れられる。 (Ex. 9.11).  一方、連続五度は実際、非常に稀である。特に、四度の連続は、別ののオクターブと二重になることはできない。これは、 ' Laut verkunde unsre Freude' in K 623 の第2、第10小節 ( Ex. 9.12)における異なったヴィオラパートを説明する。もしも第10小節のヴィオラがオクターブで第2テノールとダブリングされていれば、それらは、第1テノールと連続五度となっていることがわかるであろう。 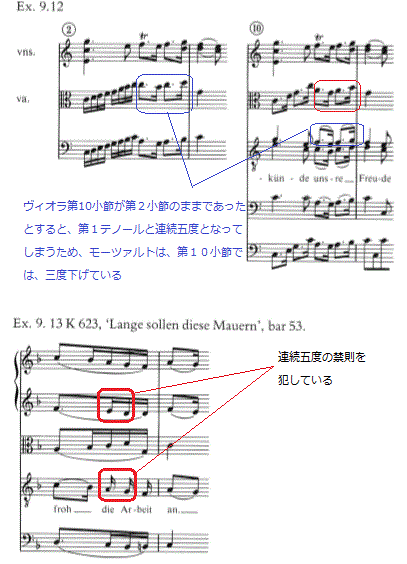 だがモーツァルトはしばしば”ソロ”テノールパートにおいて、この禁則を犯していることが認められている。彼はおそらく、その音高よりもオクターブ上と見なしていた Ex. 9.13 。厳密に言えば、ここでは、第2ヴァイオリンは、ソロテノールと連続五度となっているのである。'Requiem aeternam'の第20小節の第2ヴァイオリンと第1ファゴット間の五度も、同様に説明できることでだろう(下譜9。 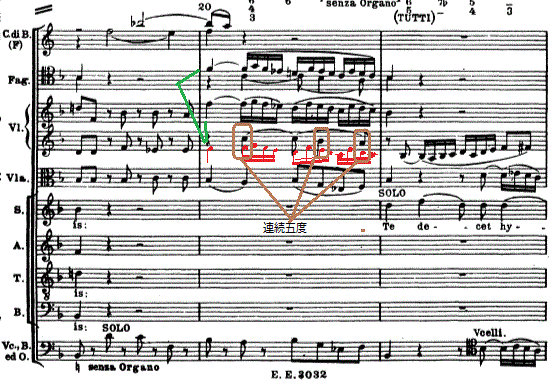 ④ドイツの六は、しばしば、第2ヴァイオリンの動きの中で認められる。ドミナント上の三和音に続く場合、バスとドイツの六との間の連続五度を避けるためには、イタリアの六に代えられなければならない。 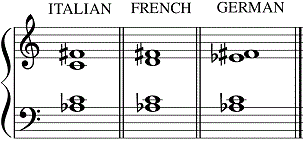  ⑤モーツァルトの”対斜”は、和声学のテキストで推奨されているものとは異なっている。彼は、全体的に半音階的に変えられた音符を、”それぞれ異なった”パートにばらまくことを好んだように見える。もしも音程変化が目立たなければ (Ex.9.15) 。しかし、こうした音程変化は、もしも半音変化した音符が、減七和音となるのであれば。明らかに不要である(Ex.9.16)。 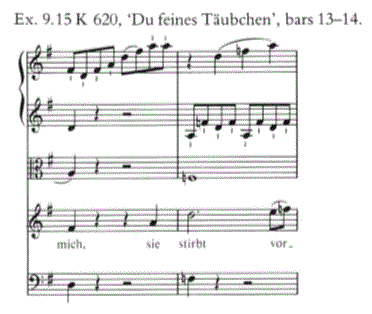 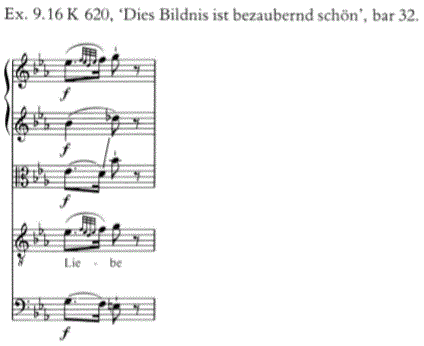 オーケストラ書法におけるモーツァルトのその他の非和声的原理は、特に注目すべき価値がある。弦楽器はしばしば、標準的伴奏パターン(たとえば、 'Requiem aeternam'の最初など)を取り、そのわおんはより性的ではあるが、決して機械的ではない。 それぞれのパターンは、自身の独特のバスリズムを持ち、バスの変化はその時、全体的パタンの基礎となる(こうした見方は、特に 'Tuba mirum'の補筆において手助けになる)。 弦楽器は決して常に4声ではなく、素早いフォルテパッセージにおいては、通常、2パートだけになることもある。  ヴィオラはバースとダブルになることもあり、ユニゾンでもオクターブでのそれは起きる。一方、和音を完全にするために、数音符程度では、ヴィオラの2分割が行われる必要性も出てくる。第2ヴァイオリンの分割は稀である。こうしたヴィオラの分割書法は、低いオクターブでの三度や六度でのダブリングのために使われるものとは別に考えられるべきである(Ex.9.17)。 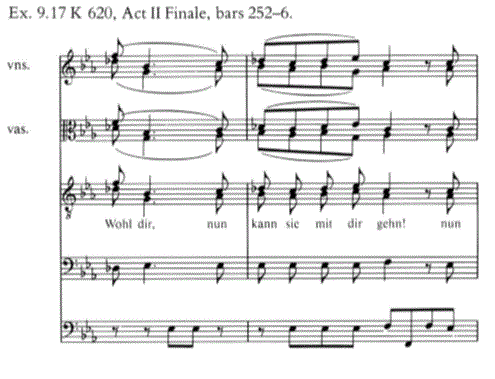 ヴィオラの分割はまた、長い保続音のためにも使われる(Ex.9.8)。こうした保続音はそれほどしばしば分割されることはなく、どういった場合でも、小節のほぼ最初では不適当である。 最大4つのパートのヴァイオリン和音(ダブルストッピング)が一般的であるが、モーツァルトは常に、ボウイングの戻りのための十分な時間を用意している。2つのヴァイオリンパートは、互いに、同じ和音であり、あるいは、よりしばしば、”ありつぎ”になっている。そのために、ヴァイオリンはその和音の一番上または二つの音符を保持したままになり、和音は完全である(Ex.9.18)。 事実、モーツァルトは、一番上の音符にのみ、和音を期待したように見える。もしも記譜が明示的にその反対を明記しない限り(Ex.9.19)。  ヴィオラはほとんど、2音以上で和音形成に関与しない。そしてチェロは決して和音形成をしない。モーツァルトの弦楽器書法の重要な原理は、それは木管楽器にもある程度当てはまることではあるが、合唱の伴奏であり、それらを単になぞる面においても、声楽と弦楽パートの間で、多くのリズムやメロディの微妙な変化があることである。特に、弦楽器は、自身の特性のレイアウトを持っている。一例が、Ex. 9.20に見られる  モーツアルトの木管楽器のレイアウトの数少ない原則はすでに記述した。しかし、弦楽器と異なり、木管楽器の和音は必ずしも完全ではなく、五度やバスのミスもある(たとえば、高音域のファゴットに見られる)。 それは一般的に、三度のペアで起こり、オクターブでの三度の二重のペアではしばしば起こる(そうした場合、七度和音や導音ではより自由に二重になる。木管楽器の”ありつぎ”は非常に稀である。(Ex.9.21)のように、特殊な効果を発揮するために使われることはあるが。 モーツァルトの通常のフルの木管楽器のオーケストレーションの過程では、それぞれのペアの第2パート(バセットホルン)を下のパート(ファゴット)の第1パートとユニゾンにしている。(Ex.9.22)  しかし、金管楽器は時々、Ex. 9.23 のように、木管楽器と”ありつぎ”にされる。あるいは、Ex. 9.24のように、より稀ではあるが、金管楽器同士でも。 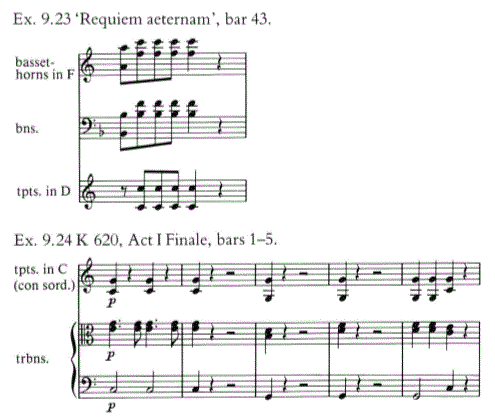 木管楽器においては、弦楽器のためのような標準的な伴奏パターンはあまり多くないが、一般的なカデンツのパターンはほぼ常に、持続和音の2小節を持っている。Ex. 9.25 こうしたカデンツが、繋留音や解決の連続を通してアプローチされれば、これらはまた、木管楽器によって持続される傾向にある。Ex. 9.26 別の同様のところでは、持続的な木管楽器が使われ、クライマックスや特殊なハーモニーの場所を強化するために、1、2小節が加えられるかもしれない。Ex. 9.27 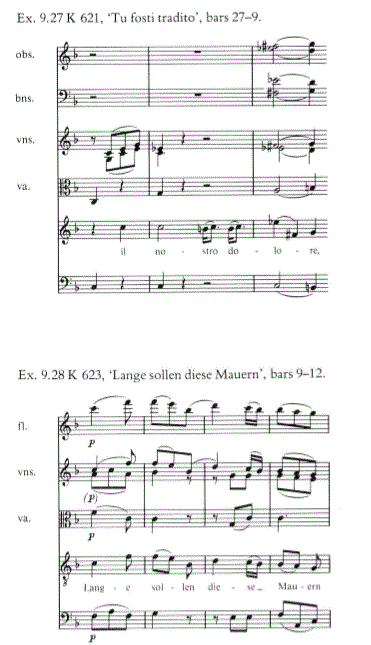 木管楽器は、しばしば、長い状態で、ソロヴォイスとダブる形で使われる。特に、声楽が弦によるユニゾンでダブられる場合に(ソロテノールは、1オクターブ上の響きとしてカウントされる)。Ex. 9.28 一方、声楽は、いくつかの木管楽器で、数小節程度で、オクターブでダブられる。こうした”多重ダブリング”は、明らかに、構造的な目的を持って現れる。なぜなら、それは、通常、セクションの終わりにのみ生じるからである。Ex. 9.29のように。 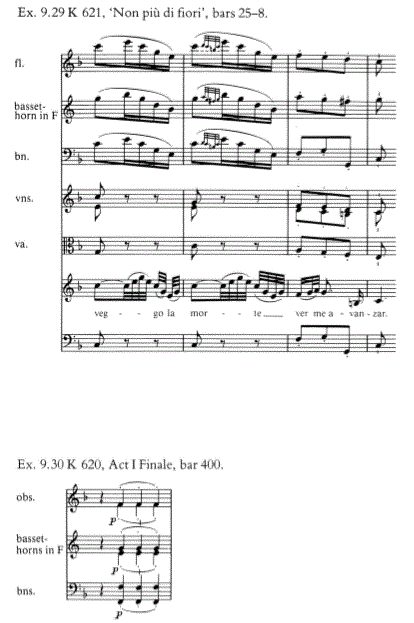 その他、木管楽器やティンパニについてのいくつかの雑多の点を述べたい。 ①バセットホルンは、はきはきと動くことができない。そのために、他の楽器がリズムのポイントを作らなければならない。Ex. 9.29 実に、K620において、バセットホルンは。ほとんど自身が聴かれることはないことに注目すべきである。しかし、その混合的性質はほとんど独自なものとして使われる。 ②ファゴットはしばしば、ヴィオラとダブって使われる。むろん、その他の内声をも形成する。ほとんど例外なく、コントラバスがない時のチェロのサポートとして使われる。 ③トランペットはほとんどメロディ的には使われない。それが可能であったとしても。実に、トランペットが持続的に使われることは稀である。時々ピアノでそのように使われることを除いて。そのために、その他の楽器が二分音符であるのに、往々にして、四分音符や四分休符となる。 ④トロンボーンは、コーラスのサポートで使われる(18世紀のオーストリアの教会音楽の伝統)が、その他の楽器と異なり、コーラスを正確になぞる。通常こうしたパートは書き出されることはなく、単に、’trombone colla pate'などと書かれることが多い。 だがしばしば、独立したパートにもなる。たとえば、 bars 143-5 and 149-51 of the Act 1 Finale of K 620 など。そして、K427ハ短調ミサでも。これは、ソロヴォイスと一緒の時に使われ、バストロンボーンは通常、下の方にいる。 ⑤ティンパニは必ずしもトランペットに付随しているわけではなく、両者は、特殊な効果のために、あるいは、トランペットだけが和音を形成するために、分離して使われることもある。Rollは稀であり、一般的にリズムは非常にシンプルに保たれている。 最後に、モーツァルトのフルオーケストラ書法についていくつかを記したい。高い音と低い音の木管楽器の間のギャップを伴う和声は受容され、そうしたギャップは、しばしば、”ありつぎ”のダブルストップによる弦楽器によって埋められる。Ex. 9.35のように。 反復の扱いはさまざまである。フルの再現部は正確であるが、いくつかの小節のみが繰り返される場合、特に、ディナミックの変化がある場合、モーツァルトは通常、楽器を代える。決して機械的ではない。モーツァルトは明らかに、それぞれのパートのそれぞれの音符を考え、そのために、ベストな効果を作るために、常に、”明らかな”テクスチャーの繊細な改変をしている。オーケストラが合唱をダブらせている例は記述した。しかし、その他の例もある。 非常に示唆的な例は、K623「フリーメーソンのためのカンタータ「我らの喜びを高らかに告げよ」 の冒頭のTuttiである。そこでは、第1,2ヴァイオリンは最初の5小節はユニゾンで、第2、3小節の3つの音符を除いて、そこでは第3小節のスタートから、4パートの弦楽器の和声を多様化している。  時々、モーツァルトはほとんど知覚不能に、ひとつのテクスチャーから別のものへと移している。あるいは、楽器を代えている。まるでマジックのように。そうした好例は、K621にみられる。たとえば、ほとんど知覚不能な、第2ヴァイオリンに対するヴィオラの代替がある。あるいは、極端な伴奏のテクスチャーの漸進的なmetamorphosisなど。 |