| R.Maunder Mozart's
Requiem�Q |
| ���y�G�b�Z�C�̃y�[�W�֖߂� | R.Maunder Mozart's Requiem�֖߂� |
| R.Maunder Mozart's Requiem�R�i�� |
| 6�@The
Benedictu�� bars 1-18 ��28-50�ɂ��Ă̐^��ɂ��Ă�Handke�̏ڍׂȃP�[�X�́A���l���̃��C�^�[�Ɏ����ꂽ�BBlume��Marguerre�̂悤�ȋ^���[�����̑��̃��C�^�[�������BEinstain�����A�S�̂Ƃ��āABenedictus�ɂ����āA�W���X�}�C���[�����炩�ɁA���[�c�@���g�̎ʖ{���̂U�Ȃ����W���߂̌`���̒��́A���[�c�@���g�̈Ӑ}�������Ă���Ƃ����W���X�}�C���[���g�̎咣������Ă���BHussey�́ABenedictus�̂��ׂĂ͐^�̃W���X�}�C���[�����̂ł���Ɣ��f�����A�Ǝ咣���Ă���B���̊y�͂͂���䂦�A�\�Ȍ��蒍�ӂ������ăA�i���[�[���Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@Handke�́A�ނ̋c�_���A��1-3���߂̃e�[�}���A�ȑO��Benedictus�ݒ�ɂ����āA���[�c�@���g�ɂ���Ďg��ꂽ���̂Ɨގ����Ă��邱�Ƃ���n�߂�B�ŏ��̔����́A'Lacrymosa'�̑�R���߂̃\�v���m�ɗR�����A���Y���ɂ����āAK194 �̂���Ɠ���ł���A�Ƃ���(Ex. 6.1).�BK259 �ɂ����Ă����l�̃��Y��������A����͘Z�x�̒�����Ă���(Ex. 6.2)�B ����ɁA�e�[�}�̌㔼�́A���Ƃ��AK167�ɂ����đ����Ⴊ����(Ex. 6.3)�BHandke�́A���[�c�@���g�̎�ɂȂ�A�����A�ӎ����́A�i���I�ߒ�������A�Ƃ���B����10�N�ȏ�̌�A���N�C�G���ɂ�����Benedictus�̃e�[�}�Ƃ��Č��������BHandke�̏ꍇ�́A�����炭�A�ނ��ߑ�]�������_�ɏ]���������̂ł���B �@�@�e�[�}�̍ŏ��̂T�̉��́A�ŏ���Lach�ɂ���Ďw�E���ꂽ�悤�ɁA�ނ̒�qBarbara Ployer�̂��߂̗��K���Ƀ��[�c�@���g���������T�̉��Ɠ���ł���(Ex. 6.4)�B �A�@�e�[�}�̌㔼�́AK337��Sanctus�̃t���[�Y�ɔ��ɂ悭���Ă���B(Ex. 6. 5)�@����́AK337�́eOsanna'�̑�14���߂ōēx�g���Ă���B����́h�c��e�B�g�̎��߁h�̑�2���t�B�i�[���ł��o������B (Ex. 6.6) �C�� �@�䂦�ɁA�e�[�}�A�����đ�2-3���߂̑Έʖ@�́A���[�c�@���g���������f�Ђ̏W�܂�ł���BHandke���M���Ă���悤�ɁA����̓��[�c�@���g�̃}�C���h����i�������̂ł��낤���H���邢�͂���́A���[�c�@���g���������邽�߂̃W���X�}�C���[�̎��݂Ȃ̂��H�ēx�A1-3���߂ׂĂ݂悤�B���̂��т́A���[�c�@���g�̒��Ґ��Ɂh����h�؋��������A���������߂ɁB �@�ŏ��̋^�킵���_�́A��P���@�C�I�������A���j�]���܂��̓I�N�^�[�u�Ńo�Z�b�g�z�������d�ɂ��邩�ǂ����A�ł���i�eNon piu di fiori'�̖`���Ɣ�ׂĂ݂悤�B�����ł́A��ɁA�I�N�^�[�u�œ�d������Ă���j�B 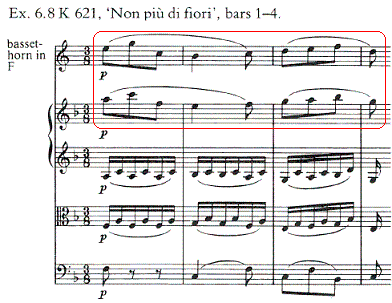 ���̂ނ���s��p�ȃI�N�^�[�u�ւ̕ω��́A��P���@�C�I�������W���X�}�C���[�ɂ���ĕt�����ꂽ���Ƃ��������Ă���B���ɁA���B�I���́A��Q���߂̍ŏ��̂Q�̔��������̃e�[�}�ƂƂ��ɁA�A�����x���`�����Ă���B���[�c�@���g�̋K���ɂ��A����̓o�Z�b�g�z�����ɂ����āA���������邱�Ƃł�save����Ȃ��B ���������A�����x�́A�ʔ������ƂɁA���[�c�@���g�́u���y�̏�k�v�ɂ����Č�����̂Ɠ���ł���(Ex. 6�B9�j �BBenedictus�̑�1-2���߂̃��B�I���p�[�g�͐������Ȃ��B 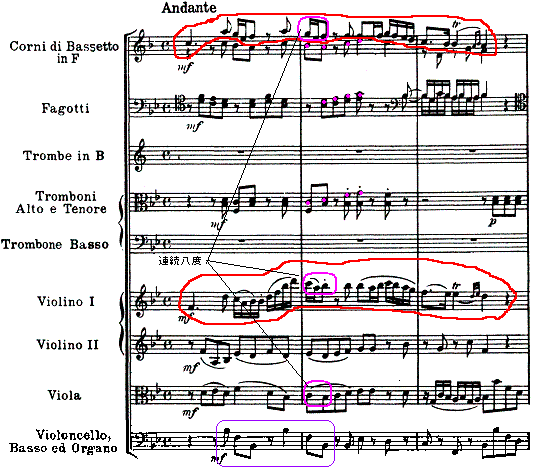 �@����䂦�A��2-3���߂̃e�[�}�ƑΈʖ@�̑啔���́A�������B�������A��R���߂̑�P���̘a���͉������肳�ꂽ�̂��H�@�o�X�̃h������������A�a����7/4�ƂȂ�B������Ex. 6.7�́A�l�x����������邱�Ƃ������Ă���iBenedictus����3���߂ɂ����ẮA�t�ɁA���̎l�x�̓o�X�Ƃ̘A���l�x���o�R���ăA�v���[�`����Ă���j�Bbut Ex. 6.7 shows that the fourth should have been prepared (in bar 3 of the Benedictus �C on the contrary �C this fourth is�@approached via consecutive fourths with the bass�I). �h���ł͂Ȃ��A�o�X�ɑ��蓾��̂́A�����ł��낤�B���̂��߂ɁA��P�o�Z�b�g�z�����̃t�@���Ƃ̊W�͘Z�x�ƂȂ�A�s�p�ӂȎl�x�ł͂Ȃ��Ȃ�B���������̂Ƃ��A�q�����ꂽ�t�@�S�b�g�̃V��́A�o�X�Ƃ̊Ԃł́A���肦�������Ȃ��Z��x�ƂȂ�A2�Ԗڂ�16�������̃\���͖��Ӗ��ƂȂ�B ��R���ߑ�P���̗B��̉\�Șa���́A�o�X�̃������ ��R���߂�����̉��ɓK���ł���ׂ����Ƃ��A�W���X�}�C���[�ɂ���ē������ꂽ���Ƃ́A�^�킴��Ȃ��B�ނ́A�������ɈႢ�Ȃ��B�Έʖ@���K�v�Ƃ��ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���̕K�v�Ȕ\�͂��Ȃ����Ƃ��B�W���X�}�C���[�́A�o�X�ƃI�[�P�X�g���̂��߂�Alleluia�́A�ނ̋U�Έʖ@�̗ޗ�ł���B�����ł́A�ނ��A�q���Ƃ��̉����̘A�������������ʂ�n�������ł��낤�����Ɋ�]�������Ă����悤�Ɍ�����B �@�e�[�}���c���Ă���B���̏I�~�͋^�킵��������B�Ȃ��Ȃ炻��́A3���߂��ƂŁA�eDomini'�Ƃ������t�ɓK���悤�ɁA��A�ς����Ă��邩��ł���BEx. 6.11�@����͂����ŏ��̃t���[�Y�݂̂��c���Ă���B���[�c�@���g����������������Ƃ͂��܂�݂蓾�Ȃ��B�W���X�}�C���[���ABarbara Ployer's seven -year -old exercise book���R�s�[�����悤�Ɍ����邱�Ƃ́A�����ꏭ�Ȃ���A���蓾��B�����ŁA�ނ��P���ɂ��̃e�[�}�����R�l���t�������ǂ������^�����R�͂Ȃ��B�ނ́A�����炭�A�eNon piu di fiori'��͕킵�悤�Ƃ����̂ł���A����ɑ�2-3���߂ɁA����I���͋C�𖡂키���߂ɁA�t�@�S�b�g�p�[�g���������̂ł���B �@��4-6���߂́A�{���I�ɁA��1-3���߂̌J��Ԃ��ł���B���t�ɍ����悤�ɂ��邽�߂ɁA�e�[�}�̍Ō�ŏ����ȕύX�������Ă��邪�B�����āA�o�X����ς���Ă���B���������o�X�̕ύX�̌��ʂƂ��āA��P���@�C�I�����ƃ��B�I���̊Ԃ̘A���I�N�^�[�u�́A��ΓI�ɖ��炩�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B �@Handke�̏ꍇ�A��7-9�̃\�v���m�̃t���[�Y�́Athird �C fourth �Cfifth �C sixth �C and seventh�̉����̘A������b�Ƃ��Ă���B�ނ͌����BEx.6.12�̗ގ��ɑ���u���[�c�@���g�̌���̓���ȓ����ł���f�ƁB��������҂͘A������㏸�ł͂Ȃ��A�L���x������A���I�Ȃ��̂ł���A���ڂȗގ��ł͂Ȃ��B 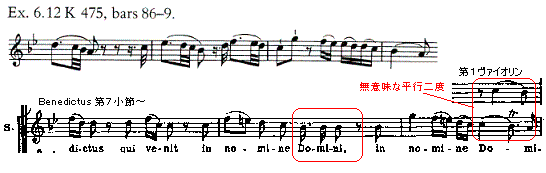 ����ɁA��W���߂ɂ�����eDomine'�Ƃ������t�̃��Y���͎��s�ł���A�ȑO�̔ނ̃~�T�Ȃɂ�����Benedictus�ɂ��Ẵ��[�c�@���g�̐ݒ�ɐ旧���ƂȂ������B �eDomine'�Ƃ������t�̃t���[�Y���ŏ��ɁA�l�������V��Ƃ��ď����ꂽ���̂悤�Ɍ�����B���t�́A���Ƃ���t���������āA�ׂ��������ƂȂ����B����䂦�AHandke�̊m�M�I�_�c��������Ă����A��7-9���߂ɂ́A���t�̂Ȃ��X�P�b�`�݂̂����݂������Ƃ��낤�i�I�[�P�X�g���p�[�g�́A�����炩�ɂ܂������I�ł���B �@��10-11���߂́A�a���I�ɕs�K���ł���B�����́A�g�j�b�N�ƃh�~�i���g�̌J��Ԃ������ł���B����Ɉ������Ƃɂ́A�����͘a���I�ɂقƂ�Ǖs���S�ł���i���Ƃ��A��10���߂������̂Q�Ԗڂł́A��O���̂Ȃ��ܓx��l�x�ƂȂ��Ă���j�B�����������߂́A���Njł���A���[�c�@���g���g�̂����������@�̈����Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��j�Bsee Ex. 6.13 �@Handke�́A��12-13���߂̃A���y�W�I�̃��`�[�t���AK525��Romanze�ɂ��̓��e���ގ����Ă��邱�Ƃ��ώ@���Ă���B�ނ́A���̃t���[�Y�́AK194��Sanctus�ɂ����l�̂��Ƃ��N�����Ă�����t���������B�������A�Έʖ@�͎��s�ł��邽�߂ɁA���[�c�@���g���g����Ȏ҂ł���Ƃ͌����Ȃ��B��12���ߑ�Q���̃\�v���m�ƃo�X�̉B���ܓx�̌�A���`�[�t�̂��ꂼ���statement�́A�������A�O�x�̃X�L�b�v�ɂ��ЂƂ̃p�[�g�̊y�͂ɂ���ĕs�K���ɐU����ꂽ�A�����x�ŏI�~����i�����j�B���������A���́A�A���g�ƃo�X�̊ԂɋN����i��12���߂̍Ō�̔�����13�����̍ŏ��̔��ցj�A�\�v���m�ƃo�X�̊Ԃł��N����i��13���߂̍Ō�̔������14���߂̑�P���ցj�B����䂦���炩�ɁA�����������߂́A�����ɃW���X�}�C���[�̂��̂ł���B�@ 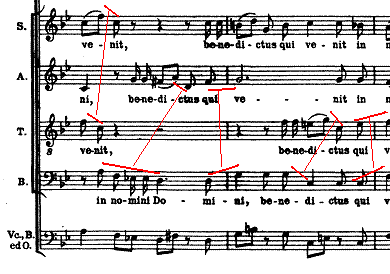 �@��14���߂̎O�x�Ԋu�̔����K�㏸�́AHandke���w�E����悤�ɁAK525��Romanze�ł̓��l�̃X�P�[���Ɏ��Ă���B���̏㏸�����K�́A�O�x�͂Ȃ����AK257�ɂē������t�œ��l�̕���������B 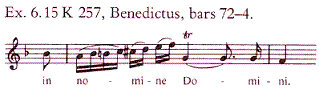 Handke�͖��炩�ɁA��14���ߌ㔼�� 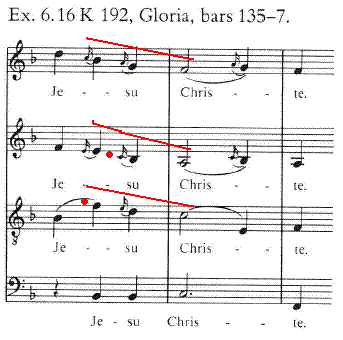 ��14���߂Ƃ���ɑ��������42���߂̊Ԃɂ́A�����[���s��v������B�����Ƃ����ڂ��ׂ��́A��14���߂̃e�m�[���̃~���ƁA��42���߂̃��ł���B�������A�����ɂ͉��x���̖���������B���Ƃ��A��14���߂ɂ����铯���V���u���ł̌J��Ԃ���郉�����̂���� 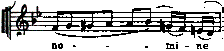 �́A��42���߂ł� �́A��42���߂ł��@��15-18���߂́A�꒮����ƁA���[�c�@���g���ɒ�������B��16���߂̑���̎g�����́A�eDomine Jesu' �̑�38���߂�[�c�@���g��Ave verum corpus(Ex. 6. 17)���v���N��������B�������A�A���g�ƃe�m�[���ɂ�����o�߉��̌��ʂ́A������9/7�̘a���ɑ��āA���ɔ��[��9/4�a�����Y�����Ă���B 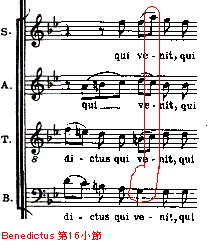 �@ ���ڂɂ͂��̌�A��17���߂ɂ����āA ��17-8���߂̃\�v���m�̍Ō�̃t���[�Y �@��1-18���߂ɂ��Ă̂܂Ƃ߂Ƃ��ẮA���[�c�@���g�̃X�P�b�`�����݂����\���̂���B��̏ꏊ�́A��1-3���߁A��7-9���߁A��14���߂ł���B���������ꂼ��̏ꏊ�ł́A������^���ׂ��\���ȗ��R������B�䂦�ɁA�X�P�b�`�̑��݂����蓾��\���ȏ؋�������킯�ł͂Ȃ��B ������ɂ���A���������f�Ђ�N���������̂��́A�قƂ�ǖ��ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̂悤�ȏ��Ȃ��f�ނ���S�̂̊y�͂��Č����邱�Ƃ́A�s�\������ł���B �@�y�͂̎c��́A�Ȍ��ɏq�ׂ���B���ԕ��A��18-27���߂́AHandke�ɂ���Ăł����A�W���X�}�C���[�̍�ł���ƍl����ꂽ�B���̊Ԃ̃t�H���e�B�V���̃p�b�Z�[�W�́A���炩�ɁA�eRequiem aeternam'�̑�43-4�����iEt lux perpetua�h�h�h�h�[�V���[)�̊W�ߓI�Ȃ��̂ł��邪�A���̊y�͂���͔r�������ׂ��ł���B�����āA�W���X�}�C���[�ɁA�ނ�Ave verum corpus�̒��Ԃ��X�t�H���c�@���h�̋��ǘa�������������l�̖����o�����������B ��21-2���߂́A���ɒ����̂Ȃ����Ӗ��ȂƂ�Ƃ߂��Ȃ������ƂȂ��Ă���B�����āA���r���[�Ȓ���������5���߂������Ă���B�������A�W���X�}�C���[����23-6���߂ɂ����āA�eRequiem aeternam'�̑�15-17���߁iEt lux perpetua�������t�@�[�~���[)������Ĉ��p������ԂɂȂ��Ă���B��25-6���߂̃\�v���m�Ƃ���Ƃ̊Ԃ��B�����x�����ڑ����B���ܓx���āB �@��27���߂́AMarguerre�̔�]���V���g���E�X�̃����c�ł�葊����������悤�ɁA�Č������B����́AMarguerre�ɂ��������A�A����̃��[�c�@���g����Ă��悤�ȃp�[�g�̌����ł���B�������A�p�[�g�̌����ɂ���āA�P���ɁA�W���X�}�C���[�����[�c�@���g�ɕς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����āA�Č����ł̑�4-9���߂ɂ�����\�v���m�ƃA���g�́A�e�m�[���ƃo�X�ւ̓]���́A�V�˂̂Ђ�߂��͂قƂ�ǕK�v�Ƃ��Ȃ��B ����ɁA��32-3���߂ł̕σz�����ւ̓]���́A���ˑR�ł���i�V�����g�j�b�N�́A��32���߂ł̃X�^�[�g��\�z���Ă���j�B��33-4���߂́A��10-11���߂̂悤�ɋ����ł���B��35-7���߂́A��12-13���߂ɑ������邪�A�����ł͖͕�I�ł�����̂������A������ł́A�����I�ȃo�X���C���ƂȂ��Ă���I ��38���߂̑�P���ł̂֒����ւ̓]���́A�s�����ł���B�Ȃ��Ȃ�A����́A�]���ɂ͌��������������ł���B����͑�10-11���߂̕ʂ̌J��Ԃ��ł���i�V���ȃ~�X�Ƃ��āA��39�C40���߂̑�P���͑�O���̂Ȃ��ܓx�ł���j�B��41���߂ɂ́A��12-13�̍Č����Ƃ��Ă̎��݂�����B �A�����x�͑��ς�炸���݂��邪�A 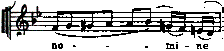 ��14���� ��42���� �e�m�[���̃���������āA�����āi���R�ɁH�j��S���̃A���g�̃V���appoggiatura�̏ȗ��������āB�����́A��15-18���߂̍Č����ƂȂ邪�A���̓x�́A��������x�͏ȗ�����Ă���B�����āA�e�m�[���ƃo�X�̊Ԃ̘A���ܓx�́A�B�����x�Œu���������Ă���B ��46-7���߂́A�v�͑ދ��ł���A���Y���I�ɂ���肪����B�Ȃ��Ȃ�A�����́A��18���߂���R���̑���ɁA��50���߂���P�����ŏI�J�f���c�Ƃ��邩��ł���B ����ɁA��48-50���߂́A��17-18���߂ɑ������邪�A���炽�Ȃ������̃~�X�e�C�N������B��48���߂̃\�v���m�ƃe�m�[���̊Ԃ̉B�����x�A��48���߂̑�R���̕s���S�Șa���ł���B ��48-9���߂̃\�v���m�����ہA��13-4���߂̃o�X�̌J��Ԃ��ł��邱�Ƃ́A��Ȉ�v�ł���B 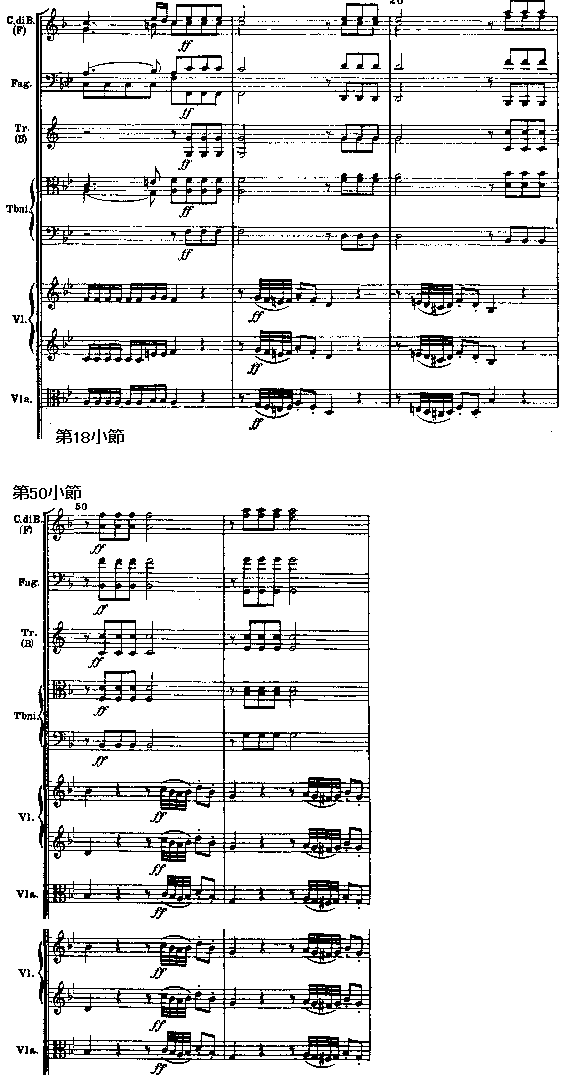 �Ō�ɁA��19-21���߂̃I�[�P�X�g���̃t�H���e�B�V�����J��Ԃ���A���ߐ��Ɖ��y�͂܂�����Ă��邪�A����́A�`���I�ȃJ�f���c�����ɏ]���Ă���B �@����䂦�ɁA18-53���߂ɂ́A�V���Ȑ^�̑f�ނ̑��݂͏ؖ�����Ă��炸�A���_�͍ŏ���18���߂̌�Ɏc����Ă���ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ킿�AHandke�̋c�_�������\��������ꏊ�́A��1-3���߁A7-9���߁A�����Ă����炭��14���߂ł���B�������AHandkeno�P�[�X�́A�ア���ʂ�����A�m�M���Ȃ��B�����ABenedictus�S�̂ɂ킽���āA������ 'Lacrymosa'�ASanctus �C �eOsanna'�̊����Ɋւ��āA���̂悤�ȁA���[�c�@���g�ɂ����Ă͓��R�̂��Ƃł�����Ղ͑��݂��Ȃ��B�����āA���̂悤�ȃe�N�j�J���ȕs���S���̐M���������\��������A���[�c�@���g�����̂悤�ȕn���ȉ��y�Ɋւ���Ă������Ƃ��m�M���������R��m�邱�Ƃ́A�s�\�ł���B 6�@The Agnus�@Dei �e�N�j�J���Ȕ\�͂̒��ړI�ȃe�X�g�́A'Lacrymosa'�̕⊮�ASanctus�A 'Osanna'�ABenedictu�͂قƂ���������킵�����̂ł��邱�Ƃ������Ă���B�������A���e�̌��@�ɂ����āAAgnus Dei���{���ł���Ƃ����m�M��������i�͂Ȃ��B�������Ȃ���A�����̃��[�c�@���g�̃~�T�ȂƂ̔�r�AAgnus Dei�̌`���̕��́ARequiem�̎c��̕����Ƃ̊W�́A���Ȃ��Ƃ��ASussmayr�������炭���̊y�͂��AMozart�̃X�P�b�`�A�����炭��Constanze�ɂ���Ĕނɗ^����ꂽ���̂��x�[�X�Ƃ��Ă������Ƃ������Ă���B �@�����̍�Ƃ́A'Requiem aeternam'�̃X�^�[�g�̃e�[�}���\������ŏ��̂X���߂ɂ�����o�X���A�h�~�i���g�܂ŏ㏸���邱�Ƃ��ώ@���Ă���B�i��7.1�j  ���ہA���̃e�[�}�̃��N�C�G���ɂ�����g�p�́ARequiem aeternam'�̂��Ƃő�������B���Ƃ��A�eDies irae'�̍ŏ��̂U�����AAmen�t�[�K�̃X�P�b�`�i�����ł��邪�j�����̗�ł���B���������ώ@�́A���_�A�ŏ��̂X���߂͐^�Ƀ��[�c�@���g��ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă���B�������̂��̑��̏ꏊ�ŁA�W���X�}�C���[�́A�����̊y�͂̑f�ނ��ė��p���Ă���̂ł���B �������A�����̏��߂ɂ��Ē��ڂ��ׂ��_�͂��邪�A�o�X�����N�C�G���̃e�[�}�������Ă��邾���łȂ��A�����ɁA���ׂĂ̂S����K220��Gloria�̃e�[�}����̈��p�����Ă���B����́A���t�܂łقƂ�Ǔ����ł���B����Gloria�̑�39-43���߂́A�ڒ����āA�ȉ��̂悤�Ɏ������B�������A�A���g�ƃe�m�[���́A�����x�̃X�y�[�X����邽�߂ɁA���N�C�G����Agnus Dei�̍ŏ���2�̏����Ƃ͐��������ƂȂ��Ă���B���N�C�G����Agnus Dei�́A�eHostias'�̑�52���߂Ɠ��l�ł���B 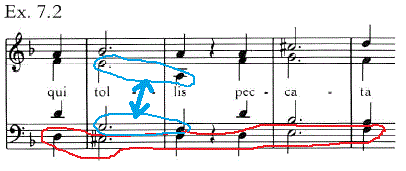 K220��Gloria����39-43���� Agnus Dei�̑�6-9���߂́AK220��Gloria�̑�78-81���߂Ƌɂ߂Ă悭���Ă���(Ex. 7.3).�B 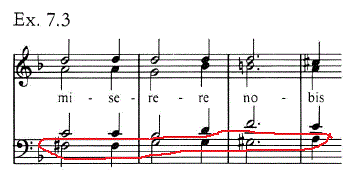 K220��Gloria�̑�78-81���� ���[�c�@���g�͊����ȉ����������Ă��邱�Ƃ��m���Ă���̂ŁA���ӎ��̂����ɈȑO�̃A�C�f�A��ʂ̃s�b�`�ōė��p���邱�Ƃ͍l���ɂ�����������Ȃ��B�������AK220��Gloria�ɂ����āAEx. 7.2�́A����̒����Ƃ̊֘A���͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A����͍ŏ��̓z�Z���ŏo�����A��53-6���߂ł̓j�Z���ւƂȂ�B����ɁA��67-71���߂ł́A�σz����/�n�Z���ɓ]������B���ɁA��53-5���߂͑�39-41���߂̐��m�Ȉڒ��ł���AAgnus Dei�̑�2-4���߂Ƃ����m�Ɉ�v���Ă���B�������ł̐��������������āB �@����قǎ��Ă��Ȃ��Ă��AAgnus Dei�̂��̕����ƃ��[�c�@���g�̂�菉���̃~�T�Ȃ̓��l�̌��t�̐ݒ�̊Ԃł̂��̑��̗ގ���������B �ȉ��̓_�́A���ɉ\���������B �@�W���X�}�C���[��K220��m���Ă����ł��낤����A�����������p�͍l������BK220 ��Gloria�̑�39-43���߂́A�o�X�ɂ��郌�N�C�G���̃e�[�}�ɓK���邽�߂Ɉڒ�������ꂽ�\���͂���B�c�O�Ȃ���A�W���X�}�C���[��K220�̃X�R�A�ɃA�N�Z�X�������ǂ����͂킩��Ȃ����A�ނ����ۂɁAK220 ��Gloria�ɂ����āA�o�X�����N�C�G���̃��C���e�[�}�����p���Ă��邱�ƂɈ�v���邱�Ƃɒ��ڂ������Ƃ́A�ƂĂ����蓾�����ɂȂ��B����2���I�̊ԁA�N�����̂悤�Ȃ��Ƃɒ��ڂ����`�Ղ͂Ȃ��B �A���Ƃ��W���X�}�C���[��K220��m���Ă����Ƃ��Ă��A�ŏ��̂Q���߂ŃA���g�ƃe�m�[�����������ꂽ���Ƃ́A�Ӗ����Ȃ����낤�B�Ȃ������������߂́A���m�ɃR�s�[����Ȃ������̂��H�@����A���[�c�@���g��15�N�ȏ゠�ƂŁA�������̏ڍׂ�Y��Ă��܂������Ƃ͑傢�ɂ��蓾�邱�Ƃł���B�����āA�����a���\���ɂ����āA�����I�ɏ��������Ă��܂����B �B�����������߂ɂ́A�Ȃ��Έʖ@��̃~�X�͂Ȃ����A�ꌩ���������ŁA��S���߂̃\�v���m�ƃA���g�ł��B�����x������A��9���߂̃\�v���m�ƃA���g�̊Ԃɂ�����B �i�����j �@�䂦�ɁA�W���X�}�C���[���AAgnus Dei�̍ŏ���9���߂̃��[�c�@���g�̃X�P�b�`�������Ă����ƐM����\���ȗ��R�͂���悤�Ɍ�����B�S�������܂߂��B �I�[�P�X�g�������ɂ��Ă͂ǂ����H�@�����̕����̃X�P�b�`�͑��݂���̂��H�@���̐�Ⴊ�A�Ⴂ���ɂ�����J��Ԃ��̔��������ƁA���@�C�I�����̂P�U�������̉��^���Ă���AK192 �̃j�Z����Agnus Dei�ł���B����ɁA���N�C�G���̃e�[�}�̗ގ���������B�j�Z���̃h�~�i���g����w�����ւƌ����������������ɓ{���Ă���BEx. 7.6. K192 ��Agnus Dei�ƃ��N�C�G���Ƃ̗ގ����ɂ������ʓI�Ȕ��t�`�������łȂ��A��P���߂̃��@�C�I�������^�́A���ꎩ�g�A���N�C�G���̃��C���e�[�}����R�����Ă���B  �eLacrymosa'�� �eHostias�̎��M���ɂ�����悤�ɁA�X�P�b�`�͏��Ȃ��Ƃ��A�A���ꂼ��̑�P���߂̓����I�ɁA���@�C�I������o�X���܂�ł����\���������B �@�����ŁA��10-14���߂ɂ��āA�l���Ă݂悤�B�a���i�s�́A���s���̒Z���̃h�~�i���g���瓯�咲�̒����ցiAmajor��Fdur)�ւƁA�h�~�i���g�̎O�a���ْ̋����������邽�߂̃��[�c�@���g�D�݂̐i�s�ƂȂ��Ă���B�V�����t���[�Y�̍쐬���A���S�I�~������Ȃ���B �����������́AEx. 7.6�̑��ɂ� bars 14-15�eRequiem aeternam'�Cbars 8-10 of the�eDies irae'�CEx.7.8�Ȃǂɂ�������B�����i�s�A�������a���Ɋ����Ȃ����̂́A�h���J�h�ɂ�������B 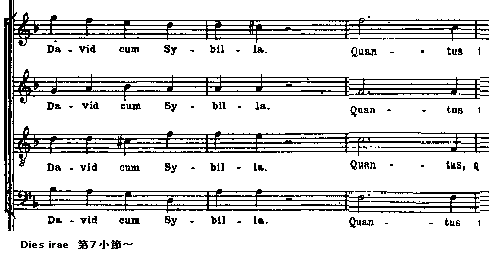 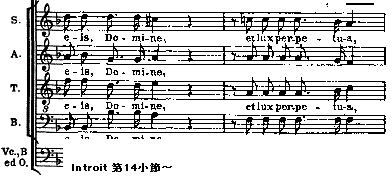 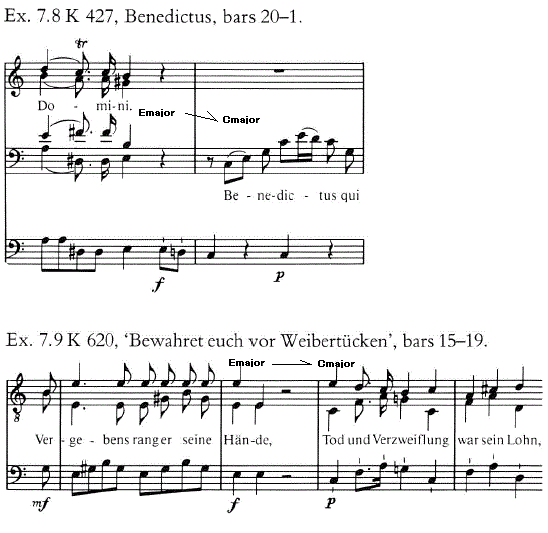 �@Handke�́A��12���߂̃\�v���m�p�[�g���Athe�eRequiem aeternam'�̑�11���߂̃\�v���m�ƍ������Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B��11-14���߂́Abars 3-8 of the Agnus Dei of K 275 (Ex. 7.10)�ɔ��Ɏ��Ă���Bbars 3-8 of the Agnus Dei of K 275�ɂ����āA�\�v���m�̓e�m�[���̔����K�㏸��\�����A�����Ԃʂł͂Ȃ��A���Ȃ킿�A7��/3�̒Z���x�i�����x�ł͂Ȃ��j�ɂ���āA�J�f���c�ւƃA�v���[�`�����Ă���B 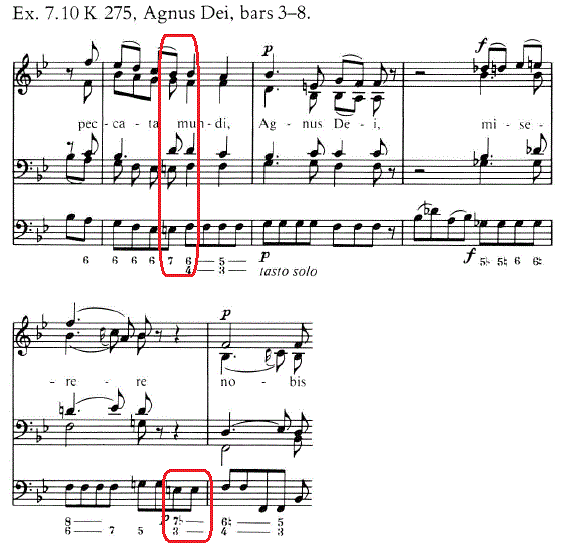 ���ۃ��[�c�@���g��1791�N7����2�t����K275��Agnus Dei �́A�������������ł́edona eis requiem'�̃��f���ł������悤�Ɏv����BEine kleine Freymaurer-Kantate (Ex. 7.11�j�ɂ����Ă��AIV���̒Z���x�w�����̊��S�I�~�ւ̓��l�̃A�v���[�`�Ƃ��Ă̂���Ȃ��Ⴊ����B 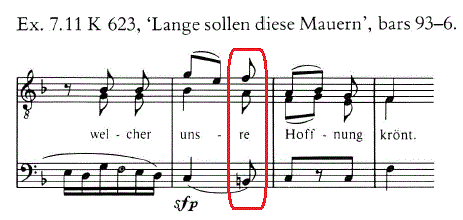 ����ɁA��13-14���ߎ��g�̃J�f���c�́A�A���g�ƃe�m�[���݂͌��ɃN���X���A�e�m�[���̓h�[�~�ƘZ�x�ቺ���A bars 135-7 of th e Gloria of K 192 (Ex.6. 16) �Ɠ��l�ɂȂ�B �@�́A��1-9���߂ɂ����Ă����l�ł���B���y�́A�����Ƃ������ׂ����̂ŁA��Ƃ���Agnus Dei of�@K 275����̏����̑f�ނ���̈��p�ɂȂ��Ă���B����́A�eRequiem aeternam'�ւ̖��ڂȊW�ɂ��ւ�炸�B ���l�̘_�c������䂦�A�K�p�����B���Ȃ킿�A�ǂ̏��߂��܂��A���ɍI���ȋU��ł���A���^�̃��[�c�@���g�ł�����A�ƁB�U��ł���Ƃ���������P�邱�Ƃ́A�ȒP�ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�W���X�}�C���[���A1791�N7���ɉ��t���ꂽK275�����\���́A����߂č�������ł���B ����A��10-14���߂́ARosen�̊��o�Ō����A�eRequiem aeternam'�̃��C���e�[�}�ɂ���Đݒ肳�ꂽ�����t���[�Y�ɂ��Ă��h�����h��������悤�Ɍ�����B���̉����́A�����Ƃ��K���Ȍ��t�ɐ����邪�Abars 1-9 of Agnus Dei�̃��N�C�G���̃e�[�}�̍Ō��statement����邱�Ƃɂ���Đ�����������B�h�~�i���g�ւƈ����L�����O���͌���I�ł͂Ȃ����B����ɁA����ȑO�Ƀq���g���^����������ɂ����āA���Ƃ���bars 11 and 14-15 of the �eRequiem aeternam' and bars 8-10 of the �eDies irae '�ɂ����Ă̂悤�ɁA�������ׂ��t���[�Y���^�����Ă���B�A���A�ǂ��ɂł��t���̉����͂Ȃ��������B ���̉ߒ��́A�����X�P�[�����\������s���Ȋ��o�̕t�^�ɂ��ẮA���[�c�@���g�̎�Ȃ����̂ЂƂł������B���������g�����̂悭�m��ꂽ��́AAndante of the Piano Concerto in G major K 453�Ő����Ă���B�����ł́A����I�ł͂Ȃ��`���̃\���t���[�Y�́A�h�~�i���g�a���ŏI�~���邪�A���x���J��Ԃ���邪�A���̍Ō�̏o���ɂ����Ă̂݁A�s�A�m�ɂ���āA�^�ɖ����ɉ������Ȃ����B���̂Ƃ��A�؊NJy��ɂ��V���������K�a�����A��茈��I�łȂ��悤�Ɏd�����Ă���B K453�̃A���_���e�ɂ����ẮA�ނ��A�����ْ��Ɖ����́A�ЂƂ̊y�݂͂̂ɂ��������Ȃ����A���N�C�G���ɂ����ẮA�����̑ΏƓI�ȃZ�N�V�����ƂƂ��ɁA�S�̂Ɋւ����K�͂ȃX�P�[���Ō����I�ɓ��ꂳ��Ă���B����܂ł̌ÓT�I�ȁu�����v�̌������g�����邽�߂ɂ́A�W���X�}�C���[�����̑�ȍ�ȉƂ��K�v���낤�B �@��K�͍\���͂����炭�A�Ȃ����[�c�@���g���hAmen"�t�[�K���X�P�b�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��A�A����ɁA���_�ł͂��邪�A���O�̊y�͂���Ȃ��n�߂�O��Agnus Dei���X�P�b�`�����̂��Ƃ��������i�X�P�b�`�V�[�g��ł́A�hAmen"�X�P�b�`�́A�eRex tremendae '�̑��e���O�ɑ��݂��Ă����j��������Ă���B ���N�C�G���S�̂́A���̊g�債���\�i�^�`���̈��Ƃ��đz�肳�ꂽ�B�eRequiem aeternam' �͒��ł���AAgnus Dei�͍Č����ł���B�h�W�J���h�̒��S�́A�^���Ȃ��A�hAmen"�t�[�K�ł���A���̎��́A���C���e�[�}�̋����ł���B���������\���ɑ��錩������������A���[�c�@���g���ŏ��ɁAAmen'��Agnus Dei�̎傽��T�ς��X�P�b�`�����̂́A����߂Ď��R�Ȃ��Ƃł���A�ƌ�����B �@��P4-16���߂́A�؊NJy��ɂ����11-14���߂��J��Ԃ��ł���B����͑�16���߂̍Ō�̔��ɂ����āA���r���[�ł��邪�A ����ɁA��Q�t�@�S�b�g�̒Ⴂ�h���́A�ڗ��B���́i�؊NJy��ɂ��j�J��Ԃ��́A�^���ׂ��ł͂���A��31-�R���߂̕��̌J��Ԃ��́A�i���Z���X�ł��邪�i��45���߈ȍ~�͂����������蓾�Ȃ��j�A��������W���X�}�C���[�̊y�z�ł���B�����炭�ނ́A�h���J�h�́eO Isis und Osiris' �̑�49-52���߂ɂ��čl���Ă����̂ł͂Ȃ����H�@�ނ́A�I�[�P�X�g�����Ō�̐��y�t���[�Y�̔����̂悤�ɍl���Ă����B�ނ��A'Lacrymosa'.�̑�19-21���߂ōs�����悤�ɁB �@�@��17���߂���24���߂܂ł̃Z�N�V�����́A���Y���I�ɑ�2-9���߂Ɠ���ł���B����́A�\���K�x�Ɏn�܂�A�I���B�i(Marguerre�́A���̊y�͂̒����̒����ɂ��āA���炩�Ɍ�������Ă���B�ނ��������A�n�Z���̃h�~�i���g�ŏI�~������17���߂���24���߂܂ł̊Ԃ̑�ւ́A�����Ċm�M�I�ł͂Ȃ��j�B�������A���ԕ��͌���Ă���B ��19���߂̑�R���̘a���́A�������Ȃ��B���y�o�X�̃����́A�������� �@�N�����A�����ɂ́A�����̃��[�c�@���g�ɂ������ꂽ��{�I�X�P�b�`�����݂���A�Ɛ��_�������ł��낤�B����A��19���߂̍Ō�̘a���́A���Ӗ��Ȍ��וi�ł���A�ł����\�ȍ�ȉƂł����A������ǂ̂悤�ɏ������̂�������͍̂���ł���B �\�v���m�������̂܂܂ɂ��āA�o�X����y�o�X�Ƃ̃��j�]���ł��郌���ɉ�����ׂ��Ƃ�����A�Ȃ��\�v���m���t�@���ɉ����A�o�X�������ɏグ���̂��W�����j�H 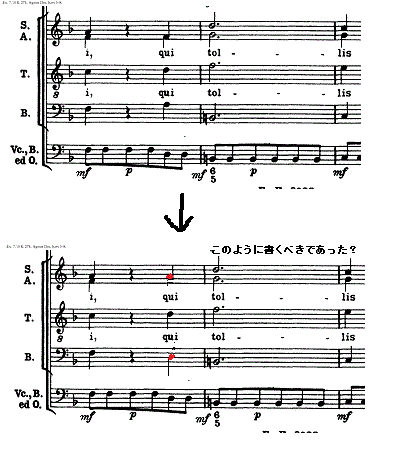 ��19���� �\�Ȑ����́A���[�c�@���g�̃X�P�b�`�������Ă͂������Aif it does not seem too far-fetched �A���Ȃ��Ƃ���19���߂܂ŗ���ƁA���Ǖs�\�ȏ�ԂɂȂ��Ă����A�Ƃ������Ƃł���B�����炭�W���X�}�C���[�́A�����ŏ�������19���߂̍Ō�̔��̘a�������āA���ꂪ��펯�Ȃ��̂ł��邩�ǂ������l���邱�Ɩ����A���ᔻ�Ɏ���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����낤���H�@����䂦�A��19���߂̃W���X�}�C���[�̈����a���́A�t���I�ɁA���[�c�@���g�̃X�P�b�`�̑��݂̗��Â��ƂȂ�؋��ƂȂ�̂�������Ȃ��B �@��25-31���߂ɑ�����͌����Ȃ��B�eRequiem aeternam' �̑�12���߂̃\�v���m���́A��11���߂ɂ�����\�v���m�Ƃ͎��Ă��邪�B ��10-14���߂ł̓��[�c�@���g���̓T�^�I�ȁh�g��h������A�����̃Z���X���������邱�ƂɎ�����B��10-14���߂́A��1-9���߂̊��S�Ȍĉ��ł��邪�A���ꎩ�g�́A�eRequiem aeternam' �ɂ����Ă��Ƃ��Ɛݒ肳��A��i�S�̂Ń����e����Ă������������W�ْ̋�����������ɂ́A�s�\���ł���B �g�傳�ꂽ���̌ĉ��́A ���炬�̊�����Y�����Ă���B�o�������킯�ł��Ȃ��A���ǂ̂Ƃ���A�����ɂ͌��t�̌J��Ԃ�������A�S�̂̍Ō�̃Z�N�V����������悤�ɂȂ������B �����������߂́A�eQuam olim Abrahae'�t�[�K�̍Ō�̏��߂̍Č������邢�́A�����Ƃ��āA�@�\����悤�ɂȂ������Ƃ͒��ڂɒl����B�E�l�C���͊����ł���A���ɁA���S�ȗ��Â����A�Œ���̑��������Ȃ������a���̎�舵���ɂ����ẮB �ꌩ���āA��29-30���߂̃\�v���m�ƃo�X�̊Ԃ��B���ܓx�̑��݂͊m���ɁA�����������߂��^�Ƀ��[�c�@���g�I�ł���Ƃ́A�l���ɂ����B���ɁA���[�c�@���g�����������ŁA�B�����x���D�Ƃ��Ă��B�������A���������i�s���ǂ̂悤�ɔ�����ꂽ��������͍̂���ł���AK220��Gloria�ɂ����ėD�ꂽ������邱�Ƃ��ł���B �@��31-3���߂�11-13���߂̍ēx�̊�y�I���s�[�g�ł���A�n�����ւƓ]������Ă���B��34-41���߂́A��2-9�Ɠ������Y���ł���AK220 ��Gloria(bars 53-7)�ɔ��ɂ悭��������������B �i�����j �@��41���߈ȍ~�̒����̂Ȃ���́A'Lux aeterna'�Ɍ����������̕s���肳���Ȃ��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���Bbars 9-10 �� 24-5�Ƃ̗ގ����ɂ��A�i���̑�41���߂�������l�́j���߂̉������i���O�x�j�����҂���A���������āA�edona eis requiem '���������σg�����ɂďo�����邱�Ƃ��A���҂���邱�Ƃ��낤�i���ꂪ�A�Ȃ���24���߂��C�Z���̃h�~�i���g�ł���˂Ȃ�Ȃ����A�̑傫�ȗ��R�ł���j�B �����A�σg�����̏o���́A�����ЂƂ̓T�^�I�ȃ��[�c�@���g���h�g��h�ɂ���āA��47���߂ւƒx�炳���B�����ł́A�σ��Z���ł̔��I�~�ւ̕W���I�A�v���[�`���s���ƂȂ��Ă���B���[�c�@���g�ȊO�̑��̒N���A���̂悤�ȋU��I�ȒP���Ȍ�����T�����ł��낤���H��38���߂���n�܂����]���̘A���ɑ��āA�����ł̌�m�b�����炩�ł���A�����ł́AK220��Gloria�����p���ꂽ���Ƃ��o���Ă����ׂ��ł���̂ɁB �@��41���߂����҂����ׂ��������Ȃ��܂܂ɂ��䂽�����߂ɁA�����ł́A���߂̉������͕K�v�Ƃ���Ȃ��B��41-4���߂́A��44���߂̍Ō�̔��̃A���g�ƃe�m�[���������A��10-13�̐��m�Ȏl�x��̓]���ł��邪�A��44-5���߂̓ˑR�̃J�f���c�ւƓ������B���̂����Ƃ������ׂ��A���������҂��ꂽ�g�j�b�N�̎O�a����IV����̌����Œu����������Ē��f���ꂽ�J�f���c�̔�I�Ȍ`���́A�܂��������[�c�@���g�ɂ���Ă���܂Ŏg��ꂽ���Ƃł���B���ɓ��l�ȗႪK275 �ɐ����Ă���(Ex. 7. 15)�B�i����Agnus Dei�́A��10-14���߂̃��f���ł������Ǝv����j�B 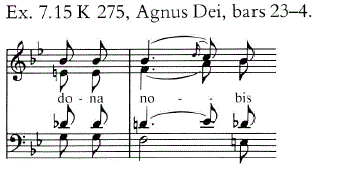 �����悤�Ȓ��f���ꂽ�J�f���c�́A�h���J�h�ɂ������A����́A�h�c��e�B�g�̎��߁h�ɂ�������B 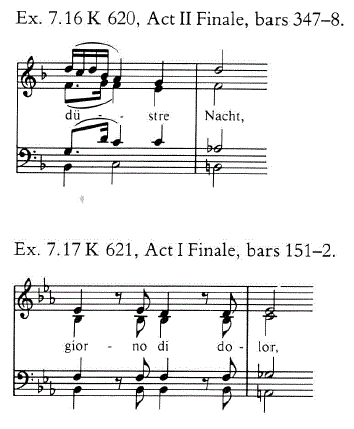 ������3�̗�͂������AAgnus Dei�̑�45���߂̑�P�]��`�Ƃ͈قȂ�A�����a���͍�����ɂȂ��Ă���B�������AK220 ��Gloria�̑�58���߂ł́A�h�h�C�c�̘Z�h�`���Ɠ����i�s�������Ă���B���̑�57���߂̃h�~�i���g�̎��x�ɂ́AVI����̃h�C�c�̘Z�x�������Ă���i���[�c�@���g�́AAttwood�ɑ��āAVI�����̃h�C�c�Z�x��IV����̌����̑�P�]��`�Ɠ����a���ł���A�Ɛ������Ă���j�B 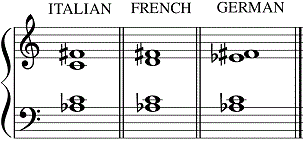 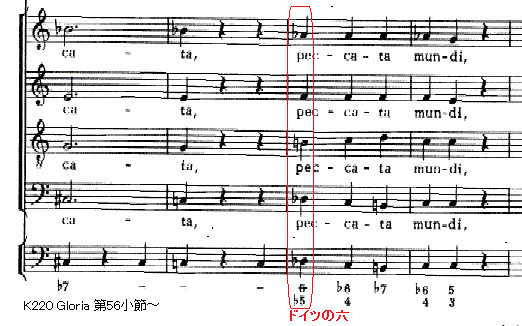 �Ȃ���45���߂ł̌�����������ł͂Ȃ����ɂ��ẮA�\���ȗ��R������B����́A��44���߂̍Ō�̔������S�a��������ł���B�����AK220�̃q���g���v�������ׁA�����āA��42���߂ł��̎g�p�����҂��ꂽG��47���߂ւƒx�ꂳ����ꂽ���Ƃ��l������A��45���߂͊��S�ɁA�o�X�ɂ�����G�́AG��ւƕω����邱�Ƃ��A�Ӗ��𐬂��̂ł���B ���̂悤�ɁA��45-9���߂͂����ЂƂ́h�g��h�ƂȂ�A��49���߂̍Ō�̔��ɂ����āA�h�C�c�̘Z�̓��肷�邱�ƂƂȂ�B 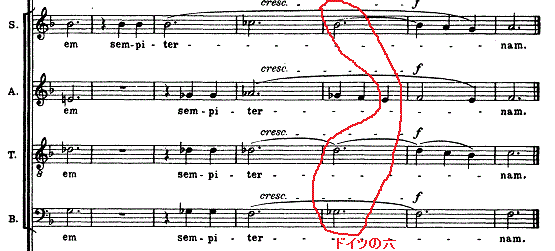 �Ō�̕��� ���l�̐i�s������AK481 no�σz�����̃��@�C�I�����\�i�^�̃A�_�W�I�̑�100-4���߂ɂ����ẮA�i�|���̃h��a����������B�ڒ������Ex. 7.18.�̂悤�ɂȂ�B �@���[�c�@���g�̃X�P�b�`���݂邾���ŁA���Ƃ��A���N�C�G���̂ЂƂ̃V�[�g�����ŁA�ނ��قƂ�Ǐ�ɁA�����L���⒲�����ȗ����Ă������Ƃ��킩��B�����āA�Վ��L�����B���܂�ɑ����������݂ɂ����āA����������Ȃ������̂ł���B����䂦�A�ނ́A��45���߂̃o�X��G�̑O�́�L�����ȗ������̂ł���B���ہA�W���X�}�C���[�̏�����G�͂قƂ�LjӖ��𐬂����A��19���߂̂悤�ɁA�B��̂����Ƃ��炵�������́A�W���X�}�C���[����������ɂ���ׂ����ۂ����l���邱�ƂȂ��Ƀ��[�c�@���g�̃X�P�b�`���R�s�[�����A�Ƃ������Ƃł���B �@��44-5���߂̑Έʖ@�ɂ����ẮA�Q�̖��炩�Ȋ�ȓ_������B��44���߂̍Ō�̑����͑�O�����������A�\�v���m�ƃA���g�͌��܂����S�ܓx�ƂȂ��Ă���B�������A���݂��Ȃ��O�x�́A��45���߂̘a���̑I���ɕK�v�Ȃ��̂ł���B�����āA���݂��Ȃ��O�x��Ex. 7.15��2�Ԗڂ̌����Ɣ�r�ł��邩������Ȃ��B ������ɂ��Ă��A���[�c�@���g�́A��O���̂Ȃ��h�~�i���g�a���͎���Ă����悤�Ɏv����B���x�̋����́A��O���̂Ȃ��ܓx�̋������ւ��邱�Ƃ��ł���̂��B �\�v���m�ƃA���g�̊Ԃ̌ܓx�ɂƂ��āA�����́A��29-30���߂Ő������ꂽ�Η�����i�s�����A���_�I�ɂ͔������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ� �B���ܓx���Ȃ�����ł���B����ɁAEx. 7.15�̃\�v���m�ƃo�X�̊Ԃł�����͓��l�ł���B ������ɂ���A�h�C�c�̘Z�̘a���I�����܂����́A�A���g���~�����邢�̓t�@�Ȃ̂��������܂��ɂ���B��҂̏ꍇ�A�A���g�ƃ\�v���m�̉����́A���܂Ƃ��������A���l�ƂȂ�B �@��46-51���߂́A'Lux aeterna'�ւ̏����̂��߂̕σ��Z���ւ̔��I�~�̂��߂������ׂ��]���X�L�[���������Ă���B�����āA'Rex tremendae'�ƁfHostias�f�̍Ō�̂悤�ȋ@�\��������B�fHostias�f�̑�46�|53���߂ւ̗ގ��͂��Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B ��47�|9���߂���17�|9���߂̕σg�����̐��m�ȓ]���ł��邱�Ƃɒ��ڂ������B�����āA���N�C�G���̎�e�[�}�́A�����Ă��Ȃ��B�\�v���m �ނ��A 'Lux aeterna' �ŁA���[�c�@���g���ǂ̂悤�Ȓ������l���Ă������́A�킩��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�`���I�Ȕł́A�W���X�}�C���[�̈ꎞ�I�� �eRequiem aeternam' �̌J��Ԃ�������ł���B�������A�σ��������K���Ȓ����������A�ƍl����̂́A����ł���B����́A���[�c�@���g�����N�C�G���ɂ����āA �eRequiem aeternam' �����łȂ��fTuba mirum'�ɂ����Ă� ��ɁA�i��Z���Ɂj��ւ���h�~�i���g�ł���ƍl���Ă��������ł���B����́A���N�C�G���S�̂ɑ���\�i�^�`���̑�Q���Ƃł����Ȃ��ꂽ�������̂ł���B ����ɁA��50�|1���߂��^���ł���Ǝ����A���[�c�@���g��'Lux aeterna'���σ������Ƃ݂Ȃ����Ƃ����悤�B�����炭�A���[�c�@���g���g�́AKyrie�t�[�K���l�A�eRequiem aeternam' �̌J��Ԃ����Ă��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���H �@�ЂƂ̒����A��Z���Ŏn�܂�y���͕���������������Ȃ��B�������킸�������߂ŁA���̓�Z���͑ł��̂Ă��Ă��܂��B�������͂��邪�A�����炭�A�O�Ⴊ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B'Rex tremendae'�́A���l�ɂӂ�܂��BK1�X�Q��Agnus Dei�̂悤�ɁB ������ɂ����Ă��AAgnus Dei�́A���Ȋ����^�̊y�͂ł���ƍl������ׂ��ł͂Ȃ��A 'Lux aeterna'��'Cum sanctis"���܂���K�͂ȍČ����̎n�܂�Ƃ��čl������ׂ��ł���B�����ɂ́A Agnus Dei�̒����ŗ]�����A���ɑ��n�ł�����Z���̊g�債���Đ���������B �@�܂Ƃ߁G�@ Agnus Dei�@�S�̂̐����́A��19���߂���Q�P���߁A�Q�Q���߂�ʂƂ��āA�m���ɐ^���ł���B ����䂦����͂����炭�A�R���X�^���c�F���W���X�}�C���[�ɓn�����X�P�b�`�̂����Ɋ܂܂�Ă������̂��܂�ł���B����́A��19�|�Q�P���߂͔��Ǖs�\�ł���A��45���߂ł́A�@�o�X�ɂ����āA�ȗ�����Ă���B�W���X�}�C���[�́A��14�|16���߂�31�|3���߂������A19�|21���߂́A��ǂ��A���s�����B�����āA��P���߂����f���Ƃ��āA�I�[�P�X�g���[�V�����������������B���������W���X�}�C���[�̍v�����������A�c��́A���[�c�@���g�̎��M���ƂقƂ�Ǔ����ɂȂ�B�����Ă��̉~�n��������ɂ����ẮA���̂��ɂ��邾���ʼn��l�����邱�ƂɂȂ�B ���̓_�ɂ����āA�u�^�킵���v�^�����̒����͊������Ă���B' Lacrymosa' �̊����ƁASanctus -�e Osanna' -Benedictu���̈�A�̗���S�̂́A�^�킵�����̂Ƃ��āA�̂ċ���ꂽ�B���̖{�̂��̂̂��́A��M�̖������グ�A���̏͂́A���[�c�@���g�̃��N�C�G���ɂ����郂�f�������グ��E�B |