| ”Missa
Pange Lingua"各論 |
| 音楽エッセイのページへ戻る 総論へ戻る |
このページでは、Josquin de Prezの”Missa pange lingua"の、各楽章について見ていきたい。 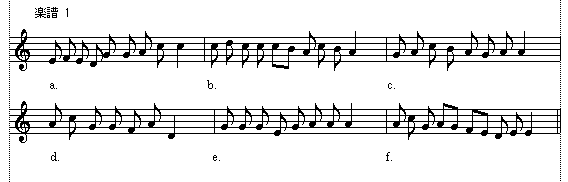 ↑Pange Linguaのグレゴリオ聖歌。フリギア旋法で書かれている(http://www.yk.rim.or.jp/‾guessac/text_48_04.html )より ①Kyrie Kyrieは式文にそって、Kyrie eleison-Christe eleison-Kyrie eleisonの三部構成をとる。まず最初のKyrie.入りは、まさにJosquinが開発した通模倣様式(これに関しては、フーガについて参照)で始まる。さらにはこのフーガが、上譜グレゴリオ聖歌をパラフレーズしているのが、このミサ曲最大の特徴である。このKyrieでは、上譜a,b,までが歌われる。 次のChristeの部分は、上譜グレゴリオ聖歌のc,dをパラフーレズする。最後のテノールの3連譜が特徴的である。 最後のKyrieは、上譜e,fのパラフレーズであるが、後半は、オスティナート様式、すなわち、同じフレーズの繰り返し出現となる。この部分は、グレゴリオ聖歌とは無関係である。 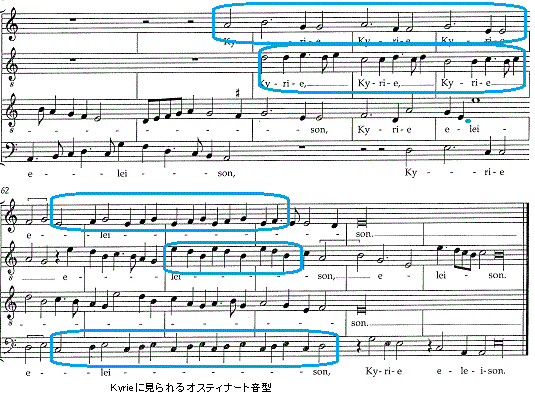 ②Gloria Gloria〜Filius PatrisまでとQui tollis peccata以降に分けられる。やはりPange linguaのパラフレーズではあるが、Kyrieほど明確ではない。上譜グレゴリオ聖歌のcまでは追っていけるが、d以降は不明瞭である。 Qui tollis以降は、最初のみaのパラフレーズであるが、あとは自由に書かれている。どちらかというとホモフォニックな感じである。 ③Credo Credo〜descendit decoelisまで Credoになると、cantus firmusのパラフレーズはさらに強くなり、やはり上グレゴリオ聖歌譜cまでしか追うことは困難である。 この部分の特徴は、途中で五度カノンが出現し、さらにはその旋律が、Liber Usualis P64にある、ミサ通常文の第一Credoの中の一節であることである。(以下) この旋律は、実際に礼拝で歌ったことがある方も多いだろう。ちなみに、私が以前所属していた立教大学付属礼拝堂では、以前、月1回はこのグレゴリオ聖歌を、日本語で歌っていた。昭和53〜57年頃の話である。 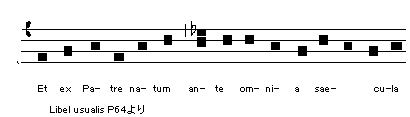 このグレゴリオ聖歌の旋律が、Et in unum Dominum以下で、以下のように使われ、五度カノンを形成しているのである。 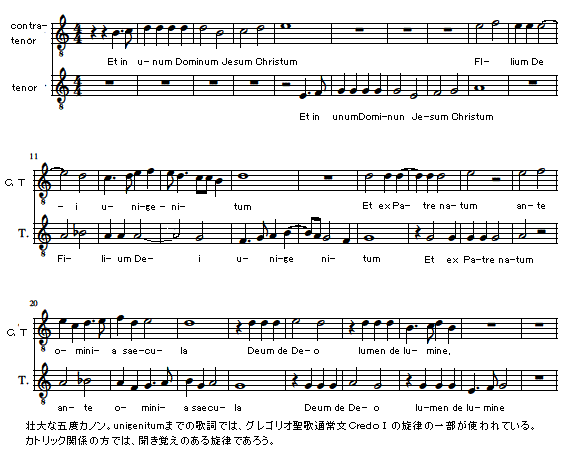 Et incarnatus〜et homo facta suntまで ここの部分は、完全なるホモフォニーである。このハーモニーを見ると、すでに、和声を作ることに関しては、完全に近代和声学が完成されている、といえる。ちなみに、一世代前のDufayの同じようなホモフォニーと比較してみよう。Dufayの場合、まだバスラインが旋法を意識して、近代的ではないことがわかる。 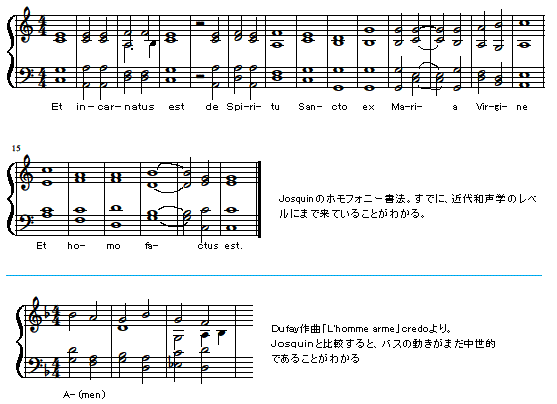 Crucifixus〜non erit finisまで この部分では、再度、Pange linguaのグレゴリオ聖歌のa部分からのパラフレーズが始まる。最上声部を追っていくと、何とかe部分まではトレースできるが、パラフレーズは極めて著しい。(下譜) 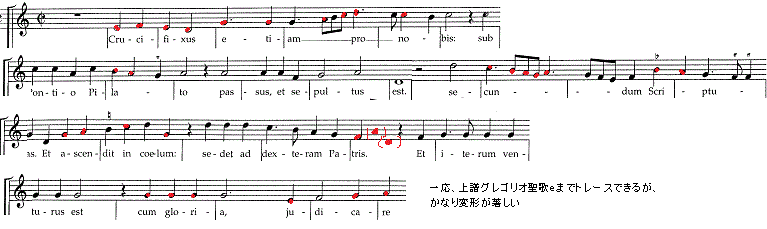 ここで重要なのが、Et resurrexitの部分である。復活を示す語であり、Josquinはここで曲想の転換を図る。そもそもリズムも強弱もはっきりしないのがルネッサンス音楽の特徴ではあるが、ここでは明らかにフォルテで入ることが想定されており、多くの演奏もそのようになっている。しかし、こうした例は、ルネッサンス期全体を通してみても、珍しいのではないか。 旋法の観点から見てみると、その前は明らかにドーリア旋法であるが、この部分からははっきりとミキソリディア旋法に切り替わっている。近代和声的に考えれば、短調から長調への転調である。 また、この部分は、supra以外の三声とsupraが分離していることにも注目したい。すなわち、下三声部はフガートでEt ressurrexitを叫ぶのに対し、最上声部supraのみはこの歌詞を歌わないのである。これはすなわち、復活の”三日目に”を示している。三声部で三日目を示しているのである。その後、この部分の後半はホモフォニックになって終わる。 Et in Spiritum〜 これより最後までは、グレゴリオ聖歌に関しては、上譜f部分をかろうじてトレースできるが、どちらかというと自由なホモフォニックパターンが続く。 ④Sanctus Sanctusに至り、まさにグレゴリオ聖歌が”帰ってくる”。すなわち、Gloria,Credoとかなりそれは変形されてしまっていたが、この楽章においては、グレゴリオ聖歌はほぼ原曲に忠実なまでに出現し、上譜dまでをトレースするのである。 ⑤Agnus Dei Agnus Deiは式文に沿って、3回出現する(楽譜の版によっては2回目が省略されている)が、注目すべきは、3回目において、cantus firmusが、突如として先祖がえりをすることである。 すなわち、これまで通模倣様式で、各声部の均等化が図られてきたのに、ここで最上声部において、Pange lingua上譜のa部分が、引き伸ばされて出現される。 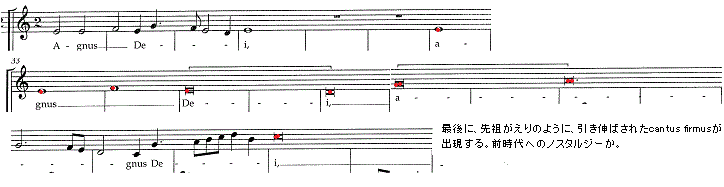 それはまるで、Josquinが、過ぎ去った時代へのノスタルジーを感じているように、私には映る。 |
| 音楽エッセイのページへ戻る デュファイその3へ戻る |