| Josquin de Prez "missa Pange Lingua"考 ‐過渡期の諸問題 |
| 音楽エッセイのページへ戻る 各論へ |
| まずは、Josquin de Prez作曲”Missa Pange Lingua”の以下の二つの演奏を聴き比べていただきたい。 1961年、Philippe Caillard Vocal Ensembleによる演奏(モノラル録音) Tallis singersによる演奏 演奏条件がかなり異なる(前者は1961年のモノラル録音、演奏者も多い。条件が近い演奏なら、Hilliard ensanbleのJosquin - Missa Pange Lingua- The Hilliard Ensemble参照)のだが、ルネッサンス期の音楽を聴きなれた方なら、違いがおわかりだろうか。前者は、後者と比較して、典型的ルネサンス期音楽に近く、後者は、若干中世的雰囲気が残っているのである。では、その違いは、具体的にはどのようなものであろうか。実はそれは、以下の2点である。 ①導音を積極的に導入しているか否か ②ランディーニ終止をより多く使っているか否か ①の観点から。前者のPhilippe Caillard Vocal EnsembleやHilliard ensambleの演奏では、導音が積極的に使われている。こうした部分は、楽譜上は以下のように書かれているが、Philippe Caillard Vocal Ensembleやhilliard ensambleの演奏では、♯つきで演奏される。(導音化) これに対して、Tallis singersでは、♯なしで演奏される。(導音化なし)  導音化することにより、完全終止の和声が随伴する(実際に和声がつけられるわけではない)ために、より近代的に聞こえるわけである。 逆に、近年の曲などでは、わざと導音をはずして、近代和声とは離れた特殊な効果を追求する場合もある。たとえば、以前、森田公一とトップギャランが歌った「青春時代」という曲では、次のように、導音化なしで終止する。 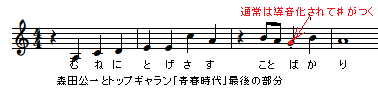 本来なら、終止のソの部分に♯がついて導音化して終わるところなのだが、この曲では、あえて♯がなく、近代和声の流れとは一線を画し、独特のメロディラインを作っているのである。 ところでYouTubeで検索してわかったことであるが、実は導音化した演奏は圧倒的に少ないことがわかった。実際、全楽章通した導音化した演奏は、この1961年演奏の古いものしか見つからず、かつ、この演奏は多人数での、昔ながらのものである。 ここからは私の類推であるが、’80年代頃より、ピリオド楽器で演奏する、いわゆる古楽ブームが起こったが、それはルネッサンス期の音楽の演奏にも波及し、導音化された近代和声的楽譜よりも、よりJosquinの本来の音楽が好まれるようになったのではないか。 そういえば、森田公一とトップギャランの「青春時代」がはやったのは’77年で、ちょうど古楽ブームが始まった頃でもある。あの頃には、日本の歌謡曲界においても、何か新しいことを始めようという熱気みたいなものがあった。古楽ブームは、日本の歌謡曲にも影響を与えたと考えるのは、少し考えすぎか。 次に②の観点から。Josquin のこのMissa曲は、16世紀にわたって10の写本によって伝えられているが、版によって、決定的な違いがある。それは、ランディーニ終止が使われているか否か、である。 Josquinの時代、すなわち16世紀末〜16世紀初頭は、前述のDufayによって開拓されたルネッサンス音楽期に突入してはいたが、後のパレストリーナやラッススなどの作品と比較すると、まだまだ生硬な面は否めなかった。すなわち、中世の代表的終止形であったランディーニ終止は相変わらずかなり使われていたし、何より、終止において三和音がそろうことはめったになく、いまだ完全5度の空疎な響きが支配していた。 そのために、Josquinの楽譜は、後に勝手に楽譜編纂者が、”時代に合うような”形で、改ざんを加えてしまったらしい。特にJena sourceと呼ばれるものはそれがはなはだしく、ランディーニ終止はことごとく近代和声的な完全終止に変えられたとのことである。(http://www.cmme.org/database/pieces/116参照) また、この曲の印刷譜が1539年に企画されているが、この時にもまた、”時代に合うような”形で、ランディーニ終止は消え去ったのである。 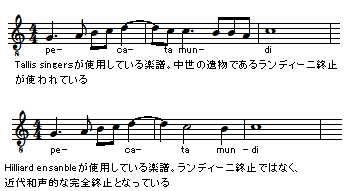 こうした版の違いにより、幸か不幸か、現代ではさまざまなJosquinの音楽を体験することができる。いずれにせよ、こうした問題は、過渡期の音楽特有のものである。 ●DufayからPalestrinaまで。それは織田信長から家康までの系譜ににている Josquinは、Dufayの革命を継承し、パレストリーナにその果実を伝えた作曲家である。Dufayの活躍がほぼ15世紀中頃、Josuquinが15世紀後半〜16世紀初頭、パレストリーナが16世紀中頃〜後半となり、こうした世代継承により、近代和声は完全に成熟した。 この三人の関係は、たとえば、織田信長→豊臣秀吉→徳川家康の関係にもたとえられよう。Dufayという革命家が、織田信長同様に中世を終わらせ、音楽をルネッサンス期のものへと急旋回させた。Josquinは、これを継承し、通模倣様式という、後の時代のゴールデンスタンダードを作り上げ、完成まであと一歩まで持って行った。そして最後に、パレストリーナが、近代和声を完成させ、この様式はもうこれ以上発展しようがないまでに、完ぺきに仕上げた。それは後に、パレストリーナ様式と呼ばれることになる。 16世紀後半、ルネッサンス音楽盛期の時代の人々にとっては、教会で近代和声が鳴り響くことは、もっともアヴァンギャルドな体験であっただろう。音楽とはこういうもの、これがすべて。これ以上はない。人類は数百年来、自然界から特定の音程のみをピックアップし、それらの音を結合する法則を発見し、それを使って、あざやかな音の織物を織りあげた。あたかも、繭から生糸を取り出して、あざやかな絹織物を作り出したごとく。 平安時代、十二単全盛の時代は、人が着る服装はこれがすべてで、これを頂点として、これ以外の服装は考えられなかったに違いない。十二単はそれはそれは美しいが、それ以外の美しい服装、機能的な服装が、その後の時代にはたくさん出現した。だが、当時の人は、そんなことは思いも及ばなかったことだろう。 音楽も同様で、ルネッサンス音楽は十二単にもたとえられるあざやかな織物であり、音楽の一つの頂点ではあったが、その後、17世紀に入ると、まったく異なる音楽が出現することになるなど、思いもよらなかったことであろう。 ●”Missa Pange Lingua"総論 このミサ曲は、Josuquinの最後のミサ曲であり、この曲において、いわゆる通模倣様式が確立した。また、パラフレーズされたグレゴリオ聖歌が全曲を貫いており、この点においては、これまでのcantus firmus様式をもっとも成熟させたものといえる。 すなわちこのミサ曲は、その形式において、一方では時代を切り開き、一方では時代を完成させた二重性があると言えるのである。 cantus firmus方式は、もともとは、Tenor優位であった。音の保持を意味するTenorという言葉そのものが、それを象徴していた。教会音楽においては、それはグレゴリオ聖歌であった。 グレゴリオ聖歌の一部をTenorとして保持し、これを中心に、その他のパートがからみついた。Tenorは王であり、その他のパートは下僕であった。中世を終わらせたDufay をもってしても、この関係は変わらなかった。 そして、この上下関係を破壊したのが、Josuquinなのである。彼は、Tenorを王の位置から引きずりおろし、他のパートを下僕より引き上げ、両者を対等の関係とした。そのための手段として用いたのが、通模倣様式である。 通模倣様式により、各パートは必然的に同等となり、Tenorの優位性はなくなった。そして、この形式こそが、後のゴールデンスタンダードになる。 さらに時代が進むと、そもそもcantus firmusそのものが不要となった。各パートの同等性を確保するための”手段”であった通模倣様式が、cantus firmusの必要性を駆逐してしまったのだ。 考えてみれば、各パートが対等になれば、cantus firmusが必要なくなるのは、自明のことである。 それまで作曲家は、まずはcantus firmusを頭におき、それを鉄骨として、建物を組み立てた。だが今や、鉄骨は不要となり、建材は同等の強度を有するようになった。作曲家は各種建材を平等に扱うことにより、建設を行うこととなった。 そして、ルネッサンス期を通じて、cantus firmusは消失し、通模倣様式のみが残った。前述のごとく、パレストリーナによりそれは究極なまでに発展させられ、次のバロック時代にまで継承された。 バロック時代においては、大バッハが、当時確立した平均律による調性の概念と通模倣様式を結合させ、近代的な”フーガ様式”が生まれた。(フーガについて参照) トニック、ドミナント、サブドミナントの概念で、フーガにより、曲は次々と転調を繰り返し、緊張が芽生え、聴衆を圧倒した。 偉大なる時代の終焉者大バッハによって、フーガは究極の完成を見て、次の時代、すなわち古典派に引き継がれた。 フーガは、古典派音楽においても、その威力を発揮した。たとえば、ソナタ形式における展開部では、緊張を高めるための手段として、フーガは多用された。その例は枚挙のいとまがない。 このように、Josquinは、cantus firmusという古くからの友人を殺し、あらたに通模倣様式という友人を迎えることにより、音楽界に革命を起こしたのである。 なお、この曲のパラフレーズ性に関しては、皆川達夫氏による詳細な解説があるので、それを参照されたい。 http://www.yk.rim.or.jp/‾guessac/text_48_04.html |
| 音楽エッセイのページへ戻る デュファイその3へ戻る |