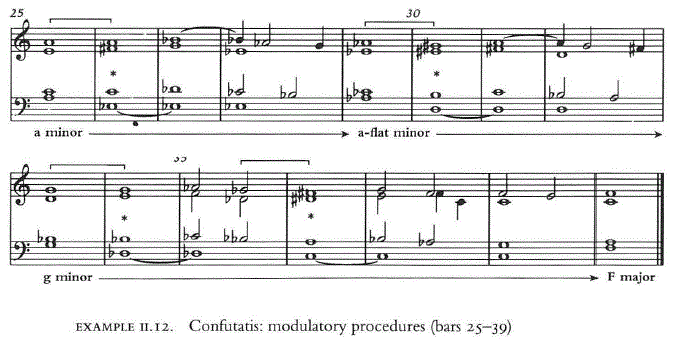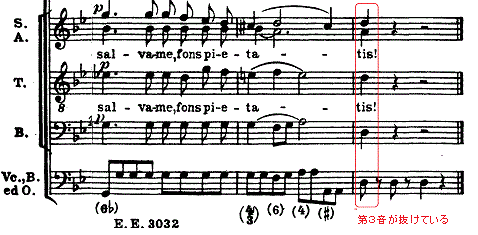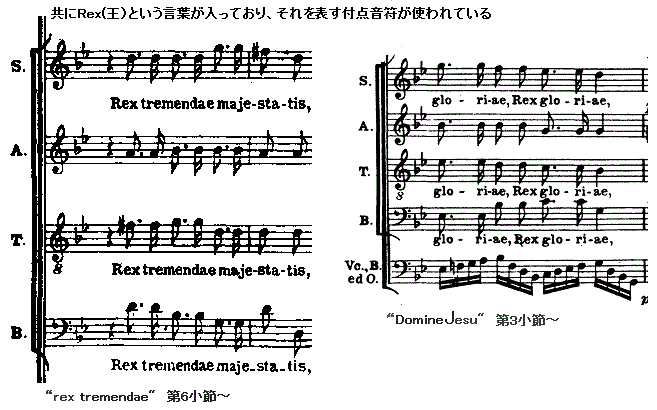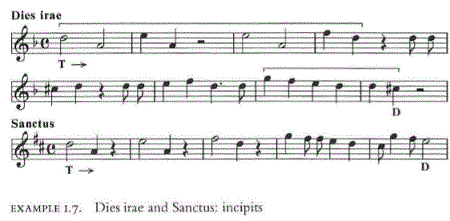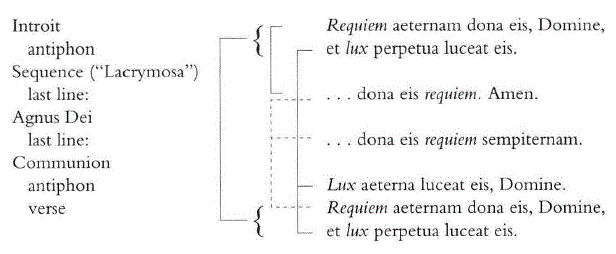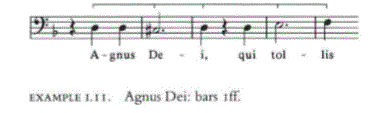|
Individual Aspects Mozart's Score
The Musical�@Context
Requiem�̂��߂̕�V�́A���[�c�@���g�ɑ���l�I�ȏd�v���������Ƃ͂Ȃ��B���̗������ǂꂭ�炢���͂Ƃ������Ƃ��āB�����̊O���̂��ƂŁA���[�c�@���g�͂��̐l���A���ݕv�l�Ƃ͋C�������ނ͂��������āA�X�̏��l�����闧��ɂ͂Ȃ������B�ɂ�������炸�A���X�e�t�@�m�吹���̋{��y���ɔC�����ꂽ1791�N5���ȗ��A�ނ̓��N�C�G����������ł����B�ނ́A�T��I���p�[�g���[�Ƃ��āA�����������@��������ɈႢ�Ȃ��B����́A����y�ւ̍�Ȃɔނ������A����܂ł̃L�����A�������悢�@��ƂȂ����B���������́A�R���X�^���c�F���v�ɑ��Ĉȉ��̂悤�ɘb���Ă������Ƃ̐M�҂傤���ƍ��߂�B�B�u�v�i���[�c�@���g�́A���N�C�G����Ȃ̐\���o�����ڂ��ׂ����ƂƂ��āA���ɘb�����B�����ɁA�h����y�̂�荂���`���h���ނ̓V�˂ɏ�ɃA�s�[���ł���悤�ȁA���̍�Ȍ`���ɂ�����ނ̍˔\��������邱�Ƃ�����Ă����B
�@�����̕����́A�h����y�̂�荂���`���h�����[�c�@���g���ǂ��v���Ă������������Ă���A����́A�ނ��h����(pathetic style�j�`�����Ӗ����Ă����A�Ƃ��Ă���BJohann
Christoph Adelung�́A�upathetic style�́A���܂�����������ɂ��Ă̎v�z�iidea)�̈̑傳�����߂邱�Ɓv�A�Ƃ��Ă���BJohann Georg Sulzer�́A�hdark emotions"���`���āA�|�p������A���Â��߂��݂ɑΛ�����͂������ƂƂ��āA�ȉ��̂悤�ɏ����Ă���B�i���j
���[�c�@���g�̃I�y����Ȃ̋@��ɂ����āA���N�C�G���~�T�̃e�L�X�g�����Â������\�����鑽���̋@��ɂ����āA����́A�h���̎�̍�Ȃւ̔ނ̍˔\���������߂́h�肢�𗝉����₷�����Ă���B
�@���[�c�@���g�́A�ނ̐l���̍Ō��10�N�ԁA�����̕���ɂ����āA���߂Ď肪�����i���������B����ł��A�ނ��V�����d�v���h�������Ȃ��������Ƃ́A�߂����ɂȂ������B���̑����́A���y�j�̗����ς����B
���̌X���́A1790�[91�N�ɂ͒ቺ��������ނ��둝�������B�u���݂͂�Ȃ����������́v�́A�ނ̍Ō�̃I�y���u�b�t�@�ł������i1790�N�P���Ɋ����j�B���ɁA�̗p���ꂽ��i�����炳���Ɓi���Ƃ��A�h���W���o���j��t�B�K���̌����ɂ�����W�̃\���ɑ��āA�U�̃\���j�A���炩�ȉ��y�I�\���̔����T���̑��傪�o�������B����́AString Quintets in D M��orK 593 and in E-Flat M��orK 614�Ct he Piano Concerto in B-Flat M��orK 595 (Mozart's 1ast)�Cor the C1arinet Concerto K 622)�ɂ�����P�������ꂽ���Y���|�����f�B�v���t�B�[���ɉ����ē����e�[�}�|���@�I����ւ̗ގ����ł���B
���̑��̓��l�̂��̂́A�c��e�B�g�̎��߂▂�J�i�O�����h�I�y���A���̒a���ȑO�́j�ɂ�����`���I�ȃI�y���Z���A�ɂ����Ă�������B�W���N�V���s�[���̓`���ƈقȂ�Z�b�R���V�^�e�B�[�{�̌��@�ɂ��ւ�炸�B�������A�s��I�ɒP�������������P���Ȋ�ւ̃��[�c�@���g�̌����i�ŔF�߂�ꂽ�ԓx���������悤�Ƃ��邱�Ƃ́A���ۂɂ͕s�\�ł���B
��X���������ׂ��ƐM����Ƃ���ł͂ǂ��ł��A��X�́A���[�c�@���g�̍Ō�̎d���͓`�L�I�ȁh����h�ł͂Ȃ��A�ނ̐��U���Z�����߂ɁA������Monteverdi�CSchutz�CBach�CHandel�CHaydn�Cand Beethoven�̏ꍇ�ɑ��݂���悤�ȁA�N�̌��ɂ���ĐZ�������悤�ȁA���I�Z���X�ɂ����Ă͌����āh�����i�h�ł͂Ȃ��A�Ƃ�����������n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�B
1787�N�ȍ~�̃��[�c�@���g�̉��y�̐V�����������̎n�܂�ɂ͉���~�X�e�C�N���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����ł���B�����ē��ɁA
1787�|88�N����́A���̌��I��_�������̍��߂�ꂽ�a���I�������A
���ݓI�ȑΈʖ@�A���������̑�_�������̂��炽�ȕ������́A�������A�ނ́h����l���h�ƌĂ�Ă���B
��X���A�Ō�̍�i�ٖ̕��I�v�f��V���ȃC�j�V�A�e�B�u�i���̃C�j�V�A�e�B�u�́A��ȉƂ̉^�����ނ��Nj�����̂������Ȃ������|�p�I�ȃS�[�����j�ւ̑����X�����������Ȃ���A����̓��[�c�@���g�̈Ӑ}�ƂƂ��ɉ��P����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���N�C�G���́A���[�c�@���g�̌l�I��`�ł���h����y�̍����`���h�ɓ��Ă͂܂�A���e�b�g�gAve verum corpus"K 618�̍�i�̃J�e�S���[�ɑ����Ă���B�d�v�Ȃ��Ƃ́A�ނ��A�p���X�g���[�i�̐��y�|���t�H�j�[�̓`�����A�ނ̐V�����T�O�ɂ����āA���ꂵ�Ȃ��������Ƃł���B�ނ̃{���[�j���ł̍�i�A�`���������������uQuaerite primum regnum dei(�܂��_�̍��Ƃ��̋`�����߂�)K
86�́A���̂悤�ȓ`���ɂ̂��Ƃ��Ă���ɂ��ւ�炸�B
�ނ̃E�B�[���ł̐����ɂ����āA�ނ̓o�b�n��w���f���ȏ�ɂ͖߂�Ȃ������B�����Ŕނ��A���̂悤�ȗl�����ʕ��������Ƃ͋^���Ȃ��B�ނ̈Ӑ}�́A�\���̗͂����߁A�e�L�X�`���[��������邽�߂ɂ����̃e�N�j�b�N�����邱�Ƃ������B
�|���t�H�j�[�̐T�d�ȒT���́A���Ƀo�b�n��n�C�h���̗l���ɂ����āA�t�[�K�ƃ\�i�^�`���̌����ɂ����āA�����ꂽ�B1782�N�̌��y�l�d�tK387�̑�l�y�͂ɂ����āA���ꂪ�������Ă���B�������Ƃ����N�C�G���ł�������B
�@
�@���N�C�G���̑�P�y�͂́A�Â����y���f������̓I�A�d�v�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�C���g���C�g�̉��y�f�ނ̂������ȕ������A�w���f���́u�L�������C�������̂��߂̑����A���Z���v(
The�@ways of Zion do�@mourn") HWV264 (1737)�̖`�������ɗR�����Ă��邩��ł���B����́A�I���W�i���̃g�Z������j�Z���ֈڂ���Ă���B

�w���f���́u�L�������C�������̂��߂̑����A���Z���v( The�@ways of Zion do�@mourn") HWV264 (1737)�̖`������
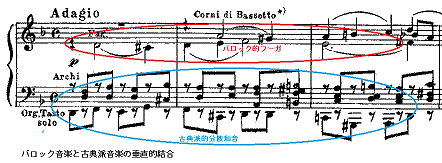
Introit�`��
�w���f���̑f�ނ́A��y����" Requiem aeternam"�̃��C���e�[�}�A���̃I�[�P�X�g���̑ΐ������܂�ł���B����ɁA�w���f���̊y�͂̌㔼�̍����ݒ�́A�L���ȃ��^�[�̑����^�̂����p���Ă���B
 �@ �@
���[�c�@���g�͓����e�[�}��p���Ă��邪�A��21���߂̓����ɂ́Atunus peregrinus��p���Ă���A��d�R���[���ݒ��ƌĂ��y�͂��`�����Ă���B
�@Kyrie�t�[�K�̑f�ނ́A�w���f���̕ʂ̍�i���痈�Ă���B����́AHWV265��Dettingen
Anthem�̍ŏI�����ł���B���[�c�@���g�́A�j�������j�Z���ɑウ�āA���̃e�[�}�Ƃ��̑ΐ����̑o�����ؗp���Ă���B�i�����j�B11.4).Abbe
Stadler�́A�ŏ��ɁA���[�c�@���g���w���f�����u�_���Ȃ鐺�y�̃��f���Ƃ��āv�I�сA���N�C�G���ɂ�����w���f���̓��@�ɒ��ӂ����v�Əq�ׂĂ���17�B
17�@Abbe Stadler�́A���[�c�@���g�Ɋւ��镶���ɂ����āA�قƂ�ǂ��̎������L���Ă��Ȃ��BMaunder�́AMozart'sRequiem�@pp. 74-94)�C�ɂ����āA�Y���������ȉӏ��ɂ����Ă��A�w���f���Ƃ̊W�ɂ́A�G��Ă��Ȃ��B
�@ Stadler�̐����́A���[�c�@���g�̃w���f���̑f�ނ̎g�������h�ؗp�h�ł͂Ȃ��A�Ƃ��Ă���_�ɂ����ẮA���������A�h���@�h�̑I���A�ɂ͌��E������B�ނ͂��ꂼ��Ɨ������āA�A���̑��̑f�ނƂȂ��Ă���B�����āA�V�����f�ނ𑝂₵�Ă���B
�f�ނ����W���A�`�������ߒ��ɂ����āA�C���g���C�g���t�[�K���w���f���̂Q�̍�i�Ɏ��Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��B���f�����ĉ��߂��A�ω�������ߒ��ɂ����āA���[�c�@���g�́A��P���߂���A���炩�ɂ������Ă���B�ނ́A�w���f���̌��̘a���̌��i�ȃ��Y����ގU�����A�o�X���C����ω������A�I�[�{�G�̑ΐ������e�m�[���̉���Ɉڂ��Ă���B���̌��ʂ́A�Έʖ@�I�����̂ɂ����ăw���f���̃I���W�i�������͂邩�ɍ������̂ƂȂ�i��20�[25���߂ɂ�����w���f���̃��`�[�t�̎g�������Q�Ɓj�A�S�̂Ƃ��āA�������ꂽ�ƂȂ��Ă���B
�@���N�C�G���ɂ́A�K���������[�c�@���g���g�̎�ł͂Ȃ����̔��z���܂܂�Ă���BStadler�����y�����悤�ɁA�u���[�c�@���g�̍Ō�̐��N�ɂ����āA���̔��z��ގ��g�̂��̂����D�悵���̑�Ȏt���ւ̑��h������Ă����v�B�������A�w���f���ւ̈ˑ��́A���̖`���y�͂ɂ����āA�����ł���B�����ł́A���[�c�@���g�̉��y�ւ̑����ȉe��������A���̑��̊y�͂ɂ����ẮA���̑f�ނ͉��y�̋��ʍ��Y�ł��낤���x�̂��̂ł���B
Erich Prieger�́A"Recordare�h�`���ɂ�����AWilhelm Friedemann�@Bach�̃V���t�H�j�A�Ƃ̗ގ������w�E�����B����ɂ���ɂȂ��āAH
artmut Krones�́A�gLacrimosa" of a I760 requiem by Francois-]oseph
Gossec�������Ɏ��Ă���Ǝw�E�����B�������A�o�b�n�Ƃ̗ގ����́A�S�Z�b�N�̂�������傫���A���������łȂ��A�Q�̊y��̉���Ȃǂ����Ă���B����A�S�Z�b�N�̃p�b�Z�[�W�́A���[�c�@���g�ł͋��ʂ�contrapunctus
syncopatus�݂̂ł���B����҂ɋ��ʂ̉��y�e�N�j�b�N����v���Ă���݂̂ł���B
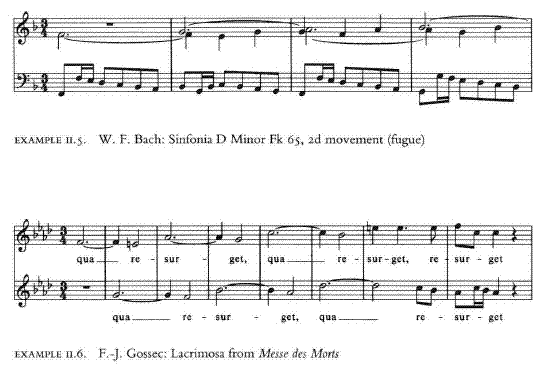
�����������ʐ��́A���[�c�@���g�̍�i�̌���ꂽ�����ɂ̂ݓK�p�����ׂ��ł���A�����̈�ʓI�ȉ��y�I��b����R��������̂ł���B�i�G���Ƃ��A�S�Z�b�N�̗�́A�y���S���[�W�̃X�^�o�[�ƃ}�[�e���ł�������j�B
�@���[�c�@���g�̃w���f���̑����A���Z������̈��p�́A�ނ��A���e�������O�ɁA�ӎ��I�ɑ������y�̓`���Ɣގ��g���v�悵�Ă������N�C�G���W�����������グ�����Ƃ������Ă���B�ނ̓��ɂ��������M.haidonn��1771�N�̃��N�C�G����A�S�Z�b�N��Messedes
morts,Gassmann�̖����̃n�Z�����N�C�G���ł������B����ɁA���ӂł���������l���̒m���ɖ����������A���[�c�@���g�́A�I���g���I�⋳��y������Ă������i����Reutter��Missa.S.Caroli���j�B�������A�ނ��ǂ̍�i�����グ�A�ǂ̍�i���������茤�������̂��Ƃ�����ʂ͕s�\�ł���B
�@�w���f�����܂߁A���[�c�@���g�̒m���̏d�v�ȃ\�[�X�̈�́ABaron van Swieten
and Count Esterhazy�C�ɂ���Đ��i���ꂽ�R���T�[�g�����[�c�@���g�����グ�����ڂł������B1788�N�ɁA���[�c�@���g�́AC. P. E. Bach's oratorio AuJerstehung und Himmel-Jahrt Jesu W q 240�����t�����B���̋Ȃ́A�d�v���e���͂̋�����i�����������łȂ��A�܂��A1787�N�ɏo�ł��ꂽ����̐V������i�ł��������B���ɁA���N�C�G���ɂ�����I�u���K�[�g�I�Ȋ�y���`�[�t�̈����ɂ�����ΏƓI�ȖL���ȕω�(e.g.�C�gConfutatis�C"
bars 1ff. and 7ff)�C�́A���[�c�@���g�̈ȑO�̍�i�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ������l���ł���A�S�Z�b�N�̖��c�ł��邪�AC.
P. E. Bach�������ĂыN��������B
���[�c�@���g�͂܂��AJ . S. Bach�̐��y��i�ɂ��S�������ABWV243Magnificat�́Avan
Swieten'�̐}�����ɂ����̃X�R�A���������B���[�c�@���g�������m���Ă������͂킩��Ȃ����A�o�b�n�́A�e'Suscepit
Israel�C"�ő�Xpsalm tone���g���Ă���B�ނ̓o�b�n�̐��y���y�ɐ��ʂ��Ă����̂ŁA�o�b�n�̒�q�ⓖ���̉̎��ʂ��āA���[�c�@���g�́Amotet�gSinget
dem Herrn'BWV225�C�̎ʕ��������Ă����BStadler�́A���[�c�@���g�̃o�b�n�̎�e�Ɋւ��Ă��܂��A���y���Ă���B
�@���[�c�@���g�����N�C�G���ɂ����Ď����������Έʖ@�̊T�O�́A�w���f�����͂邩�ɗ��킵�Ă���Ƃ��������́A�m���ł���B�C���g���C�g�̑�20�|27���߂̂̓��@�f�ނ́A�w���f���̃I���W�i���ł͂��邪�A���̑Έʖ@�́A�o�b�n����̂��̂ł����B���[�c�@���g�̓o�b�n���������A���̉e���������Ƃ́A���N�C�G���ɂ����Ė��炩�ł���B����̓t�[�K�傾���łȂ��A�����̃Z�N�V�����ɂ����Č�����B���Ƃ��Aexample:�gRex
tremendae�C" bars7ff.;�gRecordare�C" passim;" Confutatis";�gDomineJesu�C"bars4
ff.�C21 ff.�Can d 32ff�ȂǁB���������A�ւ́ANissen�ɂ����āA�������F�߂���B�u�ߋ��̉��y�̐��Ȃ鑸���́A���݂̉��y�ɖL���ɕ�܂��Ă���B�v�i�㗪�j
IndividualAspects
Mozart7s Score
���[�c�@���g�̃��N�C�G�����f�ЂƂ��Ă̂������Ă��邱�Ƃ́A��ʂ̒��O�ɂ͖��炩�ł͂Ȃ��B��i�́A�`���I�Ȍ`���ŁA���Ȃ킿�A�W���X�}�C���[�����������`�ŁA�܂��͌�̕ҏW�҂ɂ���Ċ������ꂽ�o�[�W������1�ŁA���t�����B
�����̋��ʓ_�́A���{�̒f�ЂƂ��Ă̓��������ł������_�܂ŕ���������Ă���Ƃ������������L���Ă���B
���[�c�@���g�����ۂɏ�������i�̌`���������Ǝv���Ă���l�́A���̎ʖ{�̃\�[�X�i�ނ̍�i�ȊO�̂��̂ɂ͊��Ɋ܂܂�Ă�����́j�A�܂��� Leopold Nowak��NMA�Ƃ����ŏ��ɏo�ł������M���̔łɓ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���[�c�@���g�̎��M����m�邱�Ƃ́A�^�̃e�L�X�g�ւ̌����ւ̑O������ł��邾���łȂ��A��Ȏ҂̈Ӑ}�ɂ��Ă̘_�c�ł�����B���[�c�@���g���g���������X�R�A�́A12���\�ł���A�����ʂ́A�V�X�e���ɕ��\�i���W�߂Ă��Ă��A�ނ́A����炷�ׂĂ������Ƃ��Ӑ}���Ă����B���Ȃ킿�ނ́A�ŏ��ɏ��������̂����̂܂܍ŏI�I�ȍ�i�ɂȂ邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����B���Ƃ��ނ��A�S���̐��y�p�[�g�Ɗ�y�o�X�݂̂ŏ����n�߂Ă��Ă��B���������āA����͂����鑐�e�ł͂Ȃ��B����́A���[�c�@���g�̍�ȃv���Z�X�̑��i�K�ł���A�ނ�����̌`�ŁA���y�I�Ō`���I�Ɋ��������ŏI�I�ȃe�L�X�g�����L����i�K�ł���B���Ȃ킿�A���́i�S���̐��y�p�[�g�Ɗ�y�o�X�݂̂��j���i�X�R�A�́A��Ȃ̃v���Z�X���Œ�i�L�^�j���Ă���B�t���X�R�A�������2�i�K�́A���łɏ����i�K�ɐݒ肳��Ă����f�ނ����������A����W�����Ď������邱�Ƃł������B
�@���[�c�@���g�̏��@�́A1770�N�ォ�瓯���ł������B����́A�ނ��Z���X�R�A�ŁA���y�̖{�����i�̔��W�̑�|����ȐL�W�������Ȃ����A�ŏ��̒i�K�ł���B����́A�僔�@�C�I�����A��y�\���A�g�b�v�̐��y�p�[�g�A�o�X�A�d�v�Ȕ��t���^�A�|���t�H�j�[�傩��\������Ă���B���̒i�K�ŁA�I�[�P�X�g���[�V�������Ȃ����B�������A���[�c�@���g�̃I�[�P�X�g����i�ɂ����ẮA���i�K�́A��{�I�Ȑ��y�Ƃ������̏]���I�ȃp�[�g���쐬����Ă����B���N�C�G���ɂ����Ă���́A���y�S�����y�o�X�ł������B�T�^�I�Ȍ`���ɂ����āA�ȉ��̂悤�ȁA�W���X�}�C���[�̐��������m�ł���B�u���[�c�@���g�͂S���̐����Ɗ�y�o�X����Ȃ������A�I�[�P�X�g���[�V�����͂����������ł��̔��z�������������ł������v
�@���y�p�[�g�̗D�ʐ��́A�X�R�A�ɂ����Ă����łȂ��A��Ȃ��ꂽ�y�͂̍\���ɂ���Ă��������B���[�c�@���g�̌���̃I�y���ƃn�Z���~�T���r����ƁA�I�[�P�X�g���̗v�f�́A���t��I�u���K�[�g�̖����ɂ����āA���N�C�G���ɂ����āA���̏d�v���́A�����炩�ɏ��Ȃ��B
�gRecordare�h�̂����Ƃ������I�[�P�X�g���̓�����13���߂ł���B�ŏ��̍����́A�V���ߕ��ł���B�c��́A�e�L�X�g�̃p���O���t�̊ԂŁA�����Ƃ��Ă̑����̒Z���p�b�Z�[�W�ł���B�gTuba
rnirum�C"�gR.ex tremendae�C"�gLacrymosa�C" and�gHostias"�́A���ׂĂQ���߂̊�y������������Athe
�gDies irae�C"�gConfutatis�C" and�gDornine ]esu�͂��ꂪ�܂������Ȃ��B�R�`�S���߂̌�t���gDies irae"
and�gTuba
mirum."�Ō�����B�X�̊y�͂̍\���́A��ɁA���y�̔��W�ł���B
Instrumentation
���[�c�@���g�́AAntonio
Lotti��h���X�f���{���]ohann Adolf
Hasse�ɂ���č�Ȃ��ꂽ�~�T�Ȃ̂悤�ȁA��K�͂ȋ@��̂��߂̑�K�͂ȍ�i�͌v�悵�Ȃ������B�����������Ƃ́A�ނ����N�C�G�������������Ƃɑ��鉉�t�́A�`���A���C�A�E�g�ɍ��{�I�ȉe����^�����B�ނ̃R���Z�v�g�́A���e�b�g�uAve
verum corpus�vK
618�̏ꍇ�̂悤�ɁAI790�̍c�郈�[�[�tII�̎���A����y�������ڂƃ��j���[�A�����琶�����ʓI�ȏ����ɂ���ĉe�����Ă���\��������B���[�[�t���n�߂����v�́A�I�[�X�g���A�̃��e���ꋳ��y�Ɍ������������ۂ��A1783�N��������I�ɋ֎~���ꂽ�B�����A�E�B�[���ɂ͐V��������y�͂قƂ�Ǐ�����Ă��Ȃ������B�������A1790�N�ȍ~�́A�Ăэ�ȉƂɂƂ��Ė��͓I�Ȃ��̂ƂȂ����B���y�I��1�̌���̊Ȍ����ƁA
"Ave verun1 corpus"�̊O���́A��y�I�ȋ���y�Ƃ��Ă̐U�镑���f���A���N�C�G���ɉԂ��炫�ւ�V�����X�^�C���҂��Ă����B
�@���[�c�@���g�͏��K�͂ȃA���T���u���̂��߂Ƀ��N�C�G������Ȃ����B�B���̃^�C�v�̍�i�̌��l�ȑ����ɂӂ��킵���g�����y�b�g�ƃe�B���p�j�͂��邪�A�z�����͂Ȃ��B�g�����{�[���͂��邪�A�ނ�͍������T�|�[�g���邽�߂����̑��݂ł���B�B�ڗ�������^����ꂽ�o�Z�b�g�z�����́A���j�[�N�ȍ\���v�f�ł���A���̉��F�́A�I�u���K�[�g�E�o�X�[���ɂ���ĖL���ɂȂ��Ă���B�t���[�g�A�I�[�{�G�A�N�����l�b�g�͂Ȃ��B�o�X�R���e�B�k�I�O���[�v�́A�I���K���Avio1one�A�`�F���ō\������Ă���B
�I�[�P�X�g���͌����ɃA���T���u���Ƃ��Ĉ����Ă���B
�gTuba
mirum"�̒��ɂ́A�g�����{�[���p�̊�y�\��������A���ɁA�\���X�g�ɂ������B�S���̏��@�́ATutti��solo�ɂ킩��Ă���B��i�ɂ́A�I���g���I�̂悤�ȁA�����̃A���A�͂Ȃ��B�Q�̊y�݂͂̂��A�\���J���e�b�g�ʼn̂���B
�@K427�̃~�T�Ȃ̂悤�ȁA���B���e�B�I�[�]�I�ȗv���͂���Ȃ��B�����́A�|���t�H�j�[��ł����A�u���b�N�\������̂ŁA�w���f���̃I���g���I�����f���Ƃ��Ă���B
Styles�CTextures�Cand
Forms
�����̊y�͂́A�͂邩�ɐ��������A�����āA�����̑��l������̓��[�c�@���g��1780�N��㔼�ɁA���̃I���g���I���w��Hande�̈�Y�ł���B���[�c�@���g���w���f������w�ŏ��́A�����đ��̂��Ƃ́A�R�̊�{�����ł���B����́E�E�E
�@�z���t�H�j�b�N�i�a���j
�A�J���^�[�r���i�́j
�B�͕�i�t�[�K�j
�R�̗l���̋�ʂ́A����炪���y�́A�Ȃ����͊y�̓Z�N�V�����ɂ���Ƃ��ɁA���炩�ɂȂ�B�䂦�ɁAKyrie�̃t�[�K���@�́A�����gDies
irae�C"�ɂ������{�I�Șa���̃f�N���}�V�I���ɂ���Ē��ڃt�H���[�����BOffertory�ɂ�����gQuam olim
Abrahae"�̃t�[�K�́A�Q��versicle�̋ψ�ȉ́i�J���^�[�r���j��ݒ肷��B
�@
���l�ȃR���g���X�g�́A��菬�����X�P�[���ł͂��邪�A�אڂ����l���������m�ɂ����݂���B�gRex
tremendae�h�́A�z���t�H�j�[����͕�ւ̓ˑR�̑J�ڂ̗�ł���B��R�|�T���߂́A�l�������ɂ��u���b�N�a���ł���B��6-7���߂́A���_�����̃u���b�N�a���ł���B��V���߈ȍ~�́A���荬�������������A���x�̔Z���͕��texure���܂�ł���B
�����^�C�v�̋�ʂ́A�\���X�g�݂̂̊y�͂ł�������B�gTuba
mirum"�iSequence�̃X�^���U7�j�̃\�v���m�̃Z�N�V�����ł́A�ŏ���5���߂́A�͂����肵�������I�ȗ���������Ă��邪�A�z���t�H�j�b�N�ȃf�N���}�V�I�����A��45���߂ɂ����āA�}�ɑ����ė���B�����āA��49-50���߂̃J�f���c�ŏI���B4�l�̃\���X�g�͑O�̃z���t�H�j�[�����̃��@���A���g��W�J���A�ω�������B
���̊ԁA�\���͖L���ȃ����f�B���A���@�C�I�����𗬂�Ă���B
�قȂ鐺���̃e�N�X�`���[�̃��[�c�@���g�̔����́A�e�X�̊y�͂ɁA�Ǝ��̐��i��^���A�L���ŗl�X�ȓ����̍\������������B;����͔ނɁA���ɁA�P���Ƀe�L�X�g�ɏ]�������łȂ��A���y�`�����Ȃ��Ƃ߂Ă���v�f��i��������B���Ƃ���Introit�́A�قȂ����Z�N�V�����ňȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���B
�P.�gRequiem
aeternam" (bars r-14); �͕�I�e�[�}���� Handelian subject
1
2. �gEt�@lux�@perpetua"(bars 15-19): �z���t�H�j�[���� A
3. �gTe decet hymnus"
(bars20-25):9th palm tone with Handelian subject II = solo
4. �gExaudi"
(bars 26-31): 9th psalm tone�ƍ���B �A���g�ȉ��̖͕�I�z���t�H�j�[�l���ƂƂ���
5. �gRequiem
aeternam" (bars 32-42): combination of subjects 1 and II
6. �gEt lux
perpetua"(bars 43-48): A material�Cfollowed by homophonic half
close.
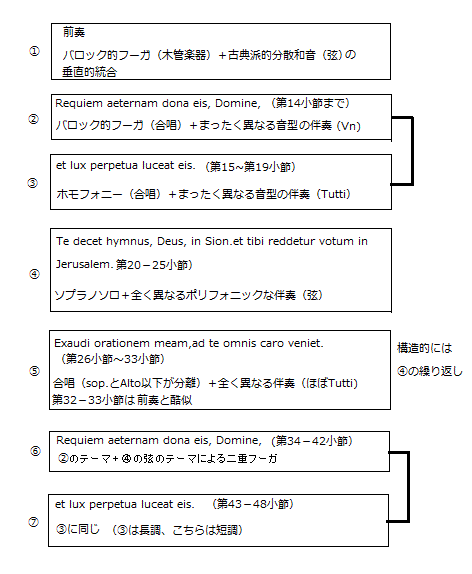
�gDomine Jesu"
�́A�ȉ��̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B
�@�J���^�[�r���I���A�@�i��P�`�U���߁j
�A�傫�Ȓ���������f�B�B�������͊ɂ₩�ȃ|���t�H�j�[�i��7�`14���߁j
�B���A���瓱���ꂽ�ɂ₩�ȃ|���t�H�j�[�I�Č��i��15�`20���߁j
�C�R���e�B�k�I�̑Έʖ@���A�A�������]��������͕�I�i�t�[�K�j���W�i��21�`31���߁j
�D���A������J���^�[�r���ւ̉�A�B�J�m���B�i��32�`43���߁j
�@�P�Ƀe�N�X�`���[�ނ��邱�Ƃ́B���[�c�@���g�̉��y�̈Ӑ}�𐳓��Ɏ戵��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��X�́A���܂��܂ȕω��ɂ��X�̃J�e�S���[�͈͓̔��ŁA�₦����������Ă��邩��ł���B����́A�g
Kyrie" �� �gQuam olim
Abrahae"�̂Q�̃t�[�K�ɓK�p�����B���҂Ƃ��A�ŏ�����stretto(��肪�g�ݍ��킳���Ă���j�ƂȂ��Ă���BKyrie�̃t�[�K�́A��ɑΐ����������ȃt�[�K�ł���A�gQuam
olim
Abrahae"�̃t�[�K�́Acolla�@part�̌��y���Ȃ��A���R�ȃt�[�K�ł���B��67���ߌ�ɁA���̋ǖʂɂ���āA���������B���l�ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A�Q�̃t�[�K�̃e�[�}�f�ނ̈������̈Ⴂ�ƁA�����̈Ⴂ�̍\���I�ȘA�����ł���B
�g
Kyrie"�̃t�[�K�́A�^�Ƀw���f���R���ł��邪�A�����t�[�K�̊��K�I�p�^�[���ɏ]���Ă���B�����ł͓��ꐫ�ƈ��萫���ۏ���Ă���B�gQuam
olim
Abrahae"�̃t�[�K�͑ΏƓI�ɁA���̓����������Ɂi�����I�[�v���ɂ��Ă����āj�A�t�[�K�̃e�N�X�`���[�̒i�K�I�ȉ����ւ̓����J���Ă����B
�@Amen�t�[�K�́A�X�P�b�`�Ƃ��Č������Ă��邾���ł��邪�A����polythematicism���A���[�c�@���g�́A���̂Q�̃t�[�K�Ƃ͈قȂ�v�����������A�����l���ŏ����ꂽ�Z�N�V���������u�Ă邽�߂̔ނ̈Ӑ}���������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
��i�̃X�L�[���ɂ����āA�T���āA�Z�N�G���c�B�A�ɂƂ��ẮA�t�[�K�ŏI��炷���Ƃ���ɕK�v�ł���A�����́A�T�̃��C���Z�N�V�����ŏI����Ă���B�T�̃t�[�K�̕ʂ̓����́A�����̉C�����S���q�ƂR���q�Ō��݂ɕς�邱���ł���B"Hosanna�h�t�[�K�i���̃W���[�X�}�C�A�[�̊����x�̒Ⴓ�͖������āj�́A�����e�[�}���`�������b�ƂȂ�A�gQuam
olim Abrahae"�t�[�K�̊�{�I�����k�ɂ��A�\���I���萫�̊�b����������A����I�ɃI���W�i���ȊT�O�ł���B(Ex.
11.9)
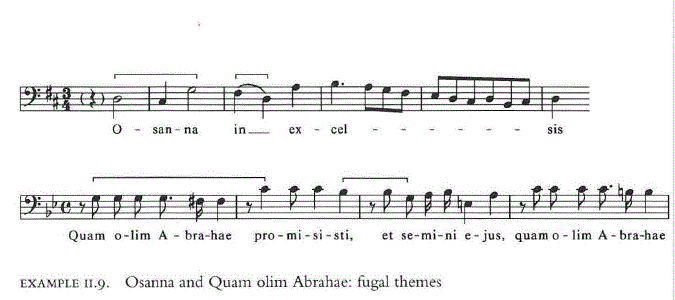
"Hosanna�h�t�[�K�̓Ǝ����́A�V���R�y�[�V�����I�n�܂�ƁA�Ƃ�킯���̖L���ȓ��I�֊s�ɂ���B
�@�t�[�K�ւ̃��[�c�@���g�̃A�v���[�`�́A�`���ɏ]�����ƂƑł����Ă邱�Ƃ̂Q�̖�S�ɂ��Ă�1�̒ł���B�������Ă��邤���ɉ�X�́A�u���݂̉��y�̖L���Ȉߕ���Z���ߋ��̉��y�̐_���ȑ������v�̓���Ɋւ���j�b�Z���̃R�����g���v���o���B46
���N�C�G���S�̂��A�l���I�ȃt���[�����[�N�ɖ��ߍ��܂�邱�Ƃ́A����䂦�A���R�ł͂Ȃ��BIntroit
��Kyrie�̉��y�̓X�^�[�g�n�_�ł���A�قȂ����e�L�X�g�̌J��Ԃ��̓S�[���ł���B���[�c�@���g�̓w���f���̃��f���̓`�����p���A�v���C���`�����g��psalm
tone�������邱�Ƃɂ���Ă�����������A�����ɁA�V�����X�^���v����ۂÂ��Ă���B�Â����̂���V�������̂ւ̑J��ς��́A���łɍŏ��̏��߂Ŗ��炩�ł���A�|���t�H�j�[�͉��F�̉A�e�ɂ��A�L���ɂ��ꂽ�B
�@�d�v�ȐV�����v�f�́Acolla
parte���̂܂܁i�C���g���C�g�̑�V���߈ȍ~�̃o�Z�b�g�z�����ƃg�����{�[���j����A�����ȃI�u���K�[�g���t�i��20���߈ȍ~�̌��y��j�܂ŁA���܂��܂ȕ��@�ŁA���[�c�@���g���ނ̊y��Q��W�J���邱�Ƃł���B���[�c�@���g�́A�����ȃA�E�J�y���͔����悤�Ƃ��Ă���B���X�Ⴆ�A"Rex
tremendae�̏I���́usalva me�Cfons
pietatis�v�ł̂悤�ɁA����ȓ_�ɂ����ẮA�I�u���K�[�g���t���J�b�g���Ă��邪�B
��y�I�v�f�̏]�����́A���ɁA���[�c�@���g���I�[�P�X�g���̓���������Ȃ��ōς܂��悤�ȏꍇ(Dies
irae�C"�gConfutatis�C"�gDomine
Jesu")�A���ӂ������B���������Ƃ���ł́A�I�[�P�X�g���̓��ʂȋ�����������āA���y�Ƃ̋�ʂ̂��߂̐��ݐ����A���y�̂���Ɠ����悤�ɑ��݂���B���[�c�@���g��particello�������悤�ɁA�ނ����y���@�W�����邽�߂Ɏg�p����̂͌��y�킪��{�ł���B�؊NJy��̋@�\�͑�K�͂ȃT�|�[�g�ł���A�����āA������"Harmoniemusik�̗̈悩�痣��邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@�I�[�P�X�g���̎����I�Ȗ����́Acolla
parte�ł̃T�|�[�g�̖����𗣂�Atone color�̂悤�ȃ��Y���I�����������邱�Ƃɂ��A�X�R�A���������邱�Ƃł���B�gDies
irae�h�̌��y��̔��t�ƁgConfutatis"�i��24���߁`�Ō�j�ɂ�����g�������̔�r�́A���Y���`��A�N�Z���g�̃V�t�g�������ɁA���y���T�|�[�g���A���y�\�������߂邩�A�������Ă���B
�����I�ɃI�u���K�[�g�̔��t�������y���`�����ꂽ�����́A���y�̃e�N�X�`���[�𗊂邱�ƂɂȂ�A�C���̐T�d�Ȏ�i�ɒB���鑊���ȈႢ�ɏI��邱�Ƃ����蓾��B����ɁA�y��́A�T���߂Ȃ����œƗ������v�������Ă���B��ɖ͕킳��Ă��鐺�y�f�ށi�gTuba
mirum"������\���g�����{�[�������̗�j�A�i���y�ƃI�[�P�X�g���́j�ΏƓI�ȑf�ށiRex tremendae" and
�gConfutatis");���y�Ɗ�y�݂̌��̒n�����̓K�����B
�@���̍Ō�̃e�N�j�b�N�́A���ɁA�gRecordare."�̃v�������[�h�ɂ����āA�悢���ʂ������炵�Ă���B����̓��N�C�G���ɂ���������Ƃ�������y�p�b�Z�[�W�ł���A����́A���y�Ɗ�y�̑Έʖ@�̓����̗�ƂȂ�B�o�Z�b�g�z�����́A�Q���̃V���R�y�[�V�����̑Έʖ@�ł���A���y�̑�ւƂ��ē����Ă���i���}X�j�B���̊ԁA�`�F�����R�����y�I�ΐ������o���i���}Y�j�B���̃Z�O�����g�i��V�|13���߁j�ł́A��y�̑ΐ�����3�p�[�g�ƂȂ�A�㕔�̉�����߁A���̊ԁA�h���y�h�̃V���R�y�[�V�����́A�o�X�ɑ��āA�����Ă����B���̌����́A�����ɁA��d�Έʖ@�̋K���ɏ]���Ă���B��14���߂���̉̎�̓���ɂ����āA�o�X�̑�14���߂̎s���������A���̗���͑S�̂Ƃ��āA�g�債�Ă����B���̊y�͂̃����h�l�`���́A�T���āAX��Y�̂Q�̑ΐ����̑Θb�ɂ���Č`������Ă���B����Y�f�ނ̎g�����́Aritornello�̂����Ƃ��āA�����͂�����Ă���i�㗪�j�B
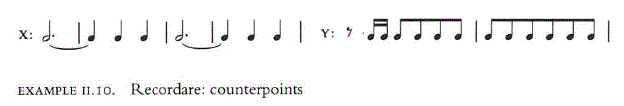
Harmonic
Design
���N�C�G����i�����グ�鑽���̂ӂ��A���Ȃ킿�A�����f�B�A���Y���A�Έʖ@�A���y�E��y���@�Ȃǂ́A�A�i���[�[��l���I��]���E���o���B�������A1780�N��ȗ��A���[�c�@���g�̑����̂��̑��̍�i���Q�Ƃ���A�����ł��Ȃ��i���������ɂ͂���B���[�c�@���g�ɂ�邻�̑��̍�i�ɔ����d�v�ȕ��s�������Ă��A���N�C�G���̘a���̃f�U�C���ɂ́A���I���W�i���ŁA���挱�I�ɓƗ����āA����܂ł̂ǂ̍�i�����V�����A�e�N�j�J���ȗv�f������B
�@��{�I�ȃL�[�̑I���̂��߂̃��[�c�@���g�̃X�^�[�g�_�́ASequence�ɂ�����gDies
irae�C�h�̃h�[���A���@�ł���B����́A���N�C�G���S�̂���ۂÂ��Ă���B���Ƃ����̃��[�h�Ɋ֘A���������̃����f�B��������Ȃ��Ă��B�j�Z�������C���L�[�ł��鎖���́A�j�Z���֘A�L�[�̃X�y�N�g���������̍�i�Ŏg���邱�ƂقǏd�v�ł͂Ȃ��B
�@���_�A���[�c�@���g�ɂ��j�Z����i�́A���ɂ����낢�날��(�㗪�j�B
�@���N�C�G���ɂ����āA�j�Z���ɏœ_�Ă�ƁA���[�c�@���g��1783�N��K427�̃n�Z���~�T�����A�傫�Ȑ�����ۂ��Ă���B�����ł���C�����́A���N�C�G���̌X�̊y�͂Ƃ��đI�����ꂽ�L�[�͈̔͂���͊O��Ă���B��O�̓g�j�b�N�ł���j�����ł���B
�@���N�C�G���̍ŏ��ƍŌ�̃j�Z���Z�N�V�����́A�茘���a���̈�ɗ��܂��Ă���i���ꂼ��σ��������g���Ă���j���A�U�̃Z�N�G���c�B�A�y�͂́A���L���������g���Ă���B�i�㗪�j
�@���[�c�@���g�̉��y�ɂ�����]���̖L�x���́A�傫�ȃX�p���ł������ȃX�p���ł��A���|���Ă���B�����āA���[�c�@���g�̃A�E�g���C���I�X�R�A�ł��킩��悤�ɁA�����́A���y���@����Ǝ��ɔ��W���Ă����B�������̗Ⴊ�A���[�c�@���g���g�p�����a���I����̂��܂��܂ȃ^�C�v��������Ă���B
�@�אڂ��鉹�ɂ��y�́B�gRecordare"�̌����̑�104���߂́A�w�����̃J�f���c(bars
105�C118�C122�C126�C130).�̘A���ւ̊J�n�ƂȂ��Ă���B�����̃J�f���c�̂Q�Ԗڂ́A��蒷���g�債�Ă���B�h�~�i���g�ł���n�����́Abars
I05�CI07�Cand 109�ɂ����ĕ\����Ă��邪�A���̑��̏��߂ł́A��106���߂̃V����̌��R�[�h���108���߂̃����Ń~���[�g�����B���̉ߒ��́A�a���̐U��q�I�����̈��ł���A��110�|115���߂̃o�X�ɂ�����h�A����A�V�A�V��Ń}�[�N����Ă���B�Ō�ɑ�116���߂ɂ����āA����ɒB����B
�@�����ƒZ����Stepwise�I�Ȍ��B�gDornine
Jesu"�ɂ����āA���[�c�@���g�́A�O�a���I���`�[�t�����グ�A�����f�B�I�v�f�͘a���I���W�ƈ�̂ƂȂ��Ă���B
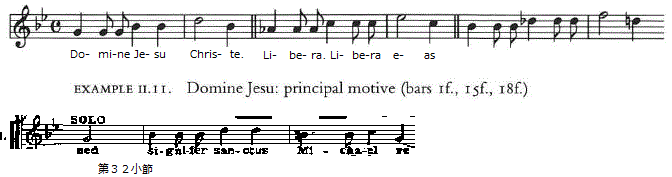
�Z���A�������݂̂��̃w�b�h���`�[�t�̘A���I�㏸�́A�\�v���m�݂̂Ɍ���邪�A��32���߂ɂ����镔���́A�S���̌ܓx�㏸�J�m���ƂȂ��Ă���B
�B��シ��a���I���Y���B�gHostias"�̍ŏ������́A�J���^�[�r���������@�̊T�O�ŁA�a���I�ɂ͗}���I�ł���B���̒��ԃZ�N�V�����́A��21���߂���44���߂܂łɁA�σ���������σz�����ւƖ߂��Ă����B
�C�G���n�[���j�b�N�I�ω��B
�@Constantin
Floros�́A���̇C�̃e�N�j�b�N�̃��f���́A�E�B�[���̃X�e�t�@�m�吹���̋{��y��������Georg Reutter�i��̕��j��Missa S.
Caroli�́gMiserere"���炫�Ă���A�Ƃ��Ă���BReutter�̍�i�́A�����K��G���n�[���j�[�ɂ��ƂÂ��W���I�ȓ]���V�X�e�����Ƃ��Ă������A�ڍׂ́A���[�c�@���g�Ƃ͈قȂ�i�������j�B
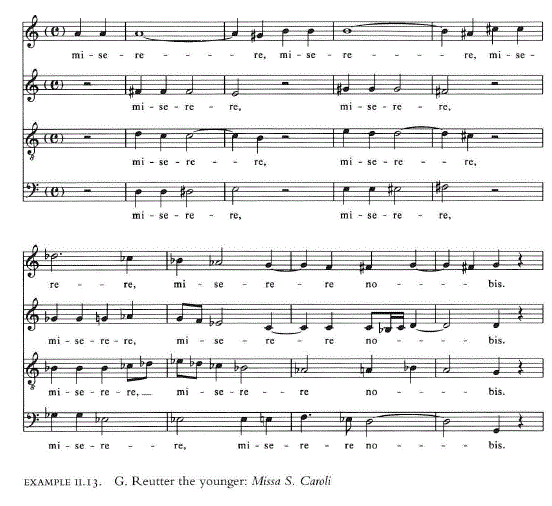
�@�ɂ�������炸�A���[�c�@���g�̃��N�C�G�����@�ւ̏����ɂ����āA���̃G���n�[���j�b�N���@�͎����ꂽ�B�ނ͂����炭�A�~�T�Ȃ�I���g���I�Ȃǂ̐��y����̓`�����������A�w���f����M.�n�C�h����������ɂ����Nj����Ă������B�������A���̍�i�����f���ƂȂ������̂��A���[�c�@���g�̂��ꂼ��̍�ȉƂ̍�i����̋����́A��ɁA�����ւ̐e�����ȏ�̂��̂�v�������B
�@�e�y�͂̏I�~�ւ̋����́Aunderlining
important formal
division�ɂ���āA���N�C�G���̑S�̓I�Șa���f�U�C���ɏd�v�Ȗ����������Ă���B�`���y�̗͂��p�[�g�iIntroit��Kyrie�j�́A���ꂼ��A��S�U���߁A��T�O���߂ł�caesura�̌�ɁA2���ߔ��ɂ킽��V-I�I�~�ŏI����Ă���BOffertory�ɂ������R���ߔ��ɂ킽��IV-I�̏I�~�`�i�A�[�����I�~�j�́A�قȂ��č\������Ă��邪�A���ꂼ��@�\�I�ɂ͓����ł���A��͂�caesura�Ő�s����āAOffertory�ɂ����ē�x�J��Ԃ����t�[�K���I�������Ă���BAgnus
Dei�̑�45���߈ȉ��̔��I�~�́A�U���߂ɂ킽���Ă���B�����ɔ�ׂ�A�gLacrymosa"�̂Q���߂̃A�[�����I�~�́A����������Ȃ��悤�Ɏv���A�����Sanctus�́A10���߂œˑR�A�I�~����B�����́A�W���X�}�C���[�̎d���ł���A���[�c�@���g�̏I�~�`�Ƃ͂�������Ă���A�ނ̊y�͂̏I�~�̎�_�����炵�Ă���B
Words and
Music
���̐��������ׂĂ̎�ނ̐��y�ɓ��Ă͂܂��ʓI�Ȋώ@�ȏ�̂��̂ł���A ���[�c�@���g�̃��N�C�G���Ō��t�Ɖ��y���藣���Ȃ��ƌ����K�v�͂Ȃ����낤�B�������A���ꂪ�A��i�̈�ʓI�ȊT�O���猾�t���e�����y�ڂ����X�̉��y�I�A�C�f�A�̔����Ɏ���܂ŁA����ɂ킽��W���Q�Ƃ��Č�����Ȃ�A�������قȂ���ɂ����Č����B��i�̊T�O���A����ł͎��҂̂��߂̃~�T�Ȃɑ����A�����ł͒ʏ핶�~�T�Ȃ�Kyrie�ASanctus�AHosanna�ABenedictus�ɑ�����e�L�X�g�����[�c�@���g�����������Ƃ���n�܂邱�Ƃ́A�����ł���B����������AKyrie��Sanctus�̐ݒ�́i���Ȃ��Ƃ����̕����̓��[�c�@���g�ł���Ɖ��肵�āj�A�����ƌĂ����̂ł���A�g�҂̂��߂̃~�T�Ȃɑ�����T��̂��̕����ɂ����鉹�y�\���́A��ނ̂Ȃ��قǔM�S�ł���B
�@�ʂ̈Ⴂ�́A�Z�N�G���c�B�A��verse�Ǝc���prose�̊ԂɋN����B
�T���prose�́A�`���I�ȃ��e�b�g�l���ň����A�e�L�X�g�̃Z�O�����g�̕ω�����ѕs�K�����ɏ]���Đݒ肳���B
���e�b�g�X�^�C���̌����ɏ]�����e�L�X�g�̈����́AIntroit�Ŏn�܂�B����́A�ȉ��̂悤��6�̃Z�O�����g����Ȃ��Ă���B�i�uTe decet
hymnus�v�ƁuExaudi�v�̌��Introit antiphon�̌J��Ԃ��́A �T��ŋK�肳��Ă���j�B
�Pa.
�gRequiem aeternam" (bars r-14); Handelian subject 1
�Pb.
�gEt�@lux�@perpetua"(bars 15-19): new musical idea A
2a �gTe decet hymnus"
(bars20-25):9th palm tone with Handelian subject II = solo
2b. �gExaudi"
(bars 26-31): 9th psalm tone with new material B in the
accompamment=tutti
1a. �gRequiem aeternam" (bars 32-42): combination of
subjects 1 and II
1b. �gEt lux perpetua"(bars 43-48): A
material�Cfollowed by homophonic half
close.
�@
�@�ŏ��̎��̂��̑����I�����́A���łɁA�w���f���̎��gThe ways of Zion do
mourn�h�ɂ����āA������Ă���B�������A���[�c�@���g�̃��Y���ω��ɂ���āA���̐����͋��߂��Ă���BM.�n�C�h���́Ahymnus�Ƃ������t���L�[���[�h�Ƃ��A����͊ԈႢ�Ȃ��A���[�c�@���g�̃��f���ƂȂ����B�glux
perpetua"�̓��@�́AM.�n�C�h���̐ݒ�ɂ����ăI���W�i���ł���A�n�C�h���́ASchrattenbach�̃��N�C�G���̍Ō�̊y�͂ł��̓��@�����グ�A�A��i�S�̂ꂵ���B

�@�e�L�X�g�̕����̃��e�b�g�l���̉e���́A���N�C�G���T��̂��̑��̕��̕����ɂ��g�債�Ă���B����A�Z�N�G���c�B�A�̉��y�I�\���́A�e�L�X�g�̉��C�I�����ɂ���āA���ꂼ��̊y�͂Ō��܂��Ă���B�X�^���U�`���̌����ȋK��������ނ̉��y�̎x�z���ɑ��Ă܂ŁA���[�c�@���g�͂�����y������w�͂����Ă���B
�ނ������Ƃ��e�L�X�g�̃p�^�[������ɂ����̂́A�Z�N�G���c�B�A�̍ŏ��̊y�́A���ɍŏ��̂Q�̃X�^���U�i��P�|�W���߁j�ł���B����́A���ꂼ��̍s���S��ł���ʏ�̃g���J�C�b�N���Y���\���ł���B�s�ς̉��C�p�^�[���́A(aaa�Cbbb�C���̑��A�ł���B
/.�@�@
/.�@�@�@ /. �@/
Dies irae�Cl dies illa
solvet
saeclum l in favilla
teste David l�@cum
Sybilla.
��P�s(2 +2)�Ƒ�Q�s(1 +1)�ɁA��R�s�������B���ꂼ��̉��C(illa/favilla/
Sybilla)�́A���ꂼ��̍s�̍Ō�ŁA����̌����ŋ��������B���y�p�[�g��verse�x�z�̃��Y���́A���a���ƕs���a���̕s�K���Ȍ��ŋ�������Ă���B���ꂼ��́A��y�̃V���R�y�[�V�����ɂ��caesura���Ă���B�y�͂̂��̌�́A�f�N���}�V�I���̓��l�̗l���ƂȂ�B��P���@�C�I�����ɂ���ȃ����f�B�́A�P�U�������̐₦�Ԗ����g�������ł���A��y�I�ΐ������������Ă���B����́A���̊y�͂��`������Q�̃X�^���U�����т���B
�@�e�L�X�g����舵���A�Q�̈قȂ����l���̂��������ȒP�ȗ�́A��ʓI��������B���Ȃ킿�A�e�L�X�g�ɂ���ăK�C�h����āA����i�K�ւƒB����B����́A�X�̊y�͂̌`���I�ȃt���[�����[�N�����łȂ��A�����̉��y�I�{���ɂ��e�����y�ڂ��B����I�X�^�C���̖L���ȕ\���̌����ɔ������ꂼ��̊y�͂̐����ɏ]���y�z�̗N�o�́A���ɁA�Z�N�G���c�B�A�Ŗ��炩�ł���B�e�L�X�g�̂��ꂼ��̃Z�O�����g�́A���[�c�@���g�ɁA����A�y�z�̌���^����B���̐��������Ƃ����z�����͓��ɁA��ȉƂ̈Ӑ}���h�����Ă���B
�@�Z�N�G���c�B�A�̍ŏ��gDies�@irae�C�h�́A��Q�X�^���U����́gQuantus
tremor est
futurus�C"�̍s�ɋN�������B�Q��verse�X�^���U�́A�ŏ���40���߂łQ��̂���B��41���߈ȍ~�A���[�c�@���g�͑�1�s�𑼂��番�����A���ꂩ�炻����side
by side�Ƃ��Ă���B
�@��U�y�́A�gLacrymosa" (stanzas
18-20)�B���̊y�͂̍ŏ��ɁA���[�c�@���g�ɂ���Ă����炳�ꂽ�y�z�́A"tears and mourning" �g( ��P�s�BLacrimosa
dies illaa")�@Sighing and sobbing�́Amusical
word-painting�`���I�ȃe�[�}�ł���A���K�I�Ȍ`�́A�I�[�P�X�g���Ɛ��y�̗����̏��@�ɂ����āA���ɕ\���͖L���Ȃ��̂Ɏd�オ���Ă���B�������A��y�����Ƃ��Ƃ̃��`�[�t�ɌŎ�������ԁA���y�́A�킸���Q���ߌ�ɐV��������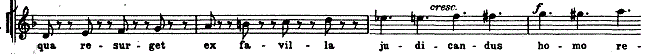 �������Ă��āA������\�����Ă���B �������Ă��āA������\�����Ă���B
�����͏����̉��F�Ɉ������������܂����A
�V����2�̏��߁ibars5ff�j�̌�ŐV�����B�\�v���m�̏����́A�ŏ���diatonicaly�ŁA�����Ĕ�����1�I�N�^�[�u�㏸���A���ɐF�ʓI�ɁA�X�^���U�̎�ȍl�������������Ă���8�A������2�Ԗڂ̍s�ŗ\������Ă���B
�@�Z�N�G���c�B�A�̎c��̊y�͂ɂ����鉹�y�I�ȓ��@�f�ނ̔��z�Ƃ��̔��W�́A�e�L�X�g���̓���̏d�v�ȃt���[�Y�ɂ���Ĉ����N������A���̊y�͑S�̂̓�����A���Ȃ��Ƃ����̌���I�Ȗ`���`�Ԃ����肷�铯���ł���f�ނ����W���邩�A�܂��͊y�͂��قȂ�\���I���e��L����2�ȏ�̃Z�N�V�����ɕ������邩�̑I���͂́A�Ƃ�킯�A�e�y�͂ɂ�����e�L�X�g�̗ʂɈˑ�����B
���[�c�@���g���Z�N�G���c�B�A���ו�����ꏊ�ɂ��Ă̌���́A�ŏ��̊y�͌�̂T�̊y�͂̂��ꂼ��̍ŏ��̃X�^���U�̐�������{�Ƃ��Ă���B
�@�قȂ邪���ڂɊ֘A�����y�z���܂Ƃ߂邱�Ƃɂ���č�Ȃ��邷�邱�̕��@�́A���ɍ��߂�ꂽ�e�N�X�`���[�������炵�A���y�\���̗͂��啝�ɋ��������B�������A���[�c�@���g�͑��l�ȑf�ނ��ɔz�����邱�Ƃɉ����āA���y�I�Ȉ�ѐ��������ĉA��ނȂ��\���͂ݏo���R���g���X�g�̂���f�ނ�A�����Ďg�p���Ă���B
"Confutatis"�ɁA���̓T�^�Ⴊ����B�����ł́A��s���鏬�߂̋�����́A
"voca me cum benedictis"�i��17���߈Ȍ�j�̃��Y���ɂ�����}���ȕω�������B����́Athe �gCall�@to the
Blessed. "�ɂӂ��킵�����̂ł���B�����ɁA�o���b�N�́u�o�Z�b�g�q�F���v61�ɑΉ������V�������̃C���[�W���o�ꂵ���B���̌�A��X�́A���y�̌Ǔ��ɂ����Ȃ���B�B����ɑ����āA�V���ȃC���[�W�������B����̋F��
"oro supplex"�ł���B����ȉ��~����]���ŕ`����Ă���6�Q�B
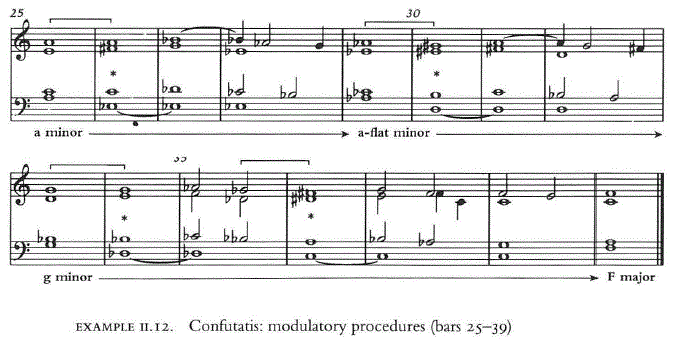
61��Ƃ��āA�o�b�n�̃}�^�C���Ȓ��̃A���A"Aus
Liebe will mein Heiland sterben"���V�I���g���I�́gJesu deine
Gnadenblicke",BWV105��"�gWie zittern und wanken"������B
62�@�j�b�Z���́A���̕������A�u���j�[�N�Ŕ��������t�ł���v�ƒ��ڂ��Ă���
�@�gRex
tremendae" (bars 18�j�́A�e�L�X�g���ˑR�̍\���J�ڂƁA����ɑ������[�c�@���g���n���������s���̕ω��������ʂ̗�ł���B�gsalva�@me"
(subito
piano�j�̋��тɂ����āA�����̃A���e�B�t�H���I�Ȕ������n������i�Q�������j�A��y���t�́A���̑Έʖ@�I��`��A�u�s�G�^�ւ̐�v�ւ̋F��ւ̍����̋ώ��ȃf�N���}�V�I���Ɉ�̂ƂȂ邱�Ƃ�Y��Ă��܂��Ă����i�G�EBeyer,
Levin�́A���ۂɂ��̍����������A�E�J�y���Ƃ��Ă���j�B���̕����́A�����́A�����Ȋ��S�ܓx�a���i��O���������Ă���j�ŏI�~���Ă���B�i���[�c�@���g�́A��P���@�C�I�����ŁAF�������A������Z�O�x�̘a���Ƃ��Ă���j�B
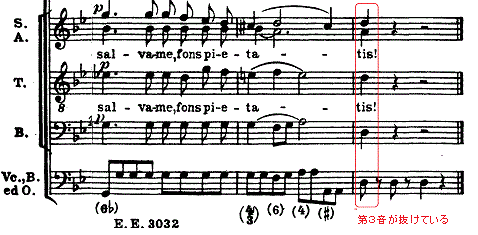
�@���y�I��i�ɂ���ăe�L�X�g�̌X�̕��������߂āA���ڂ̓��e��ڗ�������̂́A���N�C�G���̏d�v�ȓ������ł��邪�A�L�͈͂ɂ킽��A�ւ̑n�o�͏��Ȃ��Ƃ������ɏd�v�ł���B���ɂ́A��r�I�܂�ł͂��邪�A�e�L�X�g�ɂ�����قȂ����Z�N�V�����Ԃ̑������́A�X�̉��y�ւ̌��y���ĂыN�����B���Ƃ��A�gDomineJ
esu"�ɂ�����grex gloriae"�̃t���[�Y�̂悤�ɁB���̒��O�̉��y�ɂ͉��̏������Ȃ��A��R���߂ŕt�_���Y���`�ˑR�����A�Z�N�G���c�B�A��3�Ԗڂ̊y�́iRex)�̕t�_���Y�����Úg������A���ɂ��̊y�͂̑�U���߂̘a���́A�gDomineJesu"�̊y�͂��grex gloriae" ���grex tremendae
majestatis�h�̉��̉��^�ł��邱�Ƃ��v���N��������i�����j�B
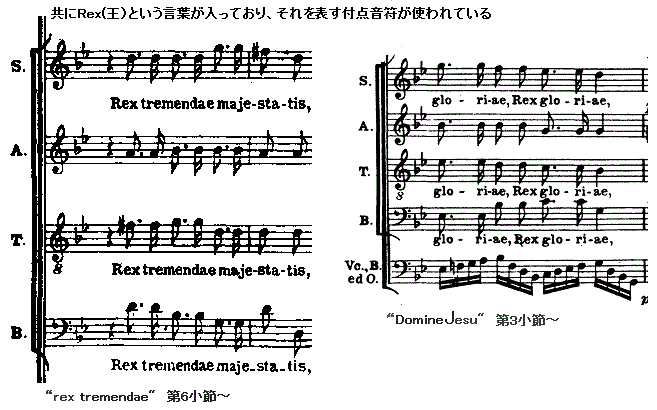
���t�Ɖ��y�̑������̗�
�@�e�L�X�g�̊֘A�Ȃ��ŁA�����ɉ��y�̌`���̑������̗Ⴊ�ASanctus��Sequence�̍ŏ��Ɍ�����B
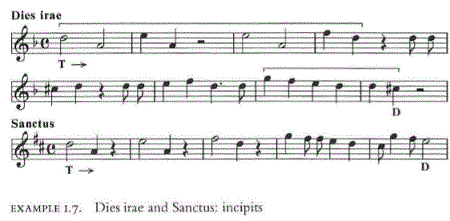
�@����A�e�L�X�g�́A�S�̃t�[�K�ɂ���Ă��̂��̋@�\�����Ă���B���ׂẮA���̍\���I���R�ɂ���āA�j�J��Ԃ������Ă���B���̃e�L�X�g�͈ȉ��̂S�ł���B
�g
Kyrie/Christe eleison";
�gQuam olim Abrahae";
�gOsannai n
excelsis";
�gCums anctis
tuis"
���ꂼ��͌Â߂������A�����̌_���k�̐��̔q�̂Ȃǂ̏���������v���N��������B���[�c�@���g�͂��ꂼ��̗��R�ŁA���y�I�`���ɂ����āA�e�L�X�g�ɍ����悤�Ȍ`�ɂ��āA�����āA�\���v��ɂ��ƂÂ��āA���̃��j�[�N�ȃX�e�[�^�X�ƂƂ��ɁA�t�[�K��I�������B
�@�������A���d�v�Ȃ��Ƃ́A���[�c�@���g���A�z�I�ȓ�����ڎw���āA�e�L�X�g�������ꂽ�֘A�l�b�g���[�N���܂Ƃ߂Ă��邱�Ƃł���B
���̂悤�Ȃ��L���W�́A�T��̃e�L�X�g�̓���̗v�f�ɍŗD�悳��A���̊Ԃɑ傫�ȃA�C�f���e�B�e�B������B
��ȉƂ́A�����̃t���[�Y���e�L�X�g�̂ǂ��ɗ��邩�ɉe����^���Ȃ����A�B���Ƃ��A�glux"��
�grequilem�C�Ȃǂ̃L�[���[�h�̌J��Ԃ��́A���y�̐����ȃX�L�[���Ő헪�I�d�v����тт邱�Ƃ�����B
�C���g���C�g�́glux
perpetua"��Communion�́glux
perpetua"�̊Ԃ̘A�ւ́A���N�C�G���̍ŏ��ƍŌ�̍�������J��Ԃ����Ƃɂ��AM.�n�C�h���ɂ���āA���[�c�@���g�����Q�O�N�O�ɓ����ꂽ�B���������[�c�@���g�́A����ɂ���Ƀ��`�[�t�I�ȉ�z���͂邩�ɂ������Ă����A
���}�ɂ����āA�ŏ��ƍŌ�̊��ʂ́A�S�̂̃��j�������g�I�t���[�����`�����Ă���B�����ɂ́A�t���[���ɑ�������̊y�͂ɂȂ���A�ցi�g
dona eis
requiem�h�j������B���[�c�@���g�̂������������A�ւɂ��Ă̗����͓��ɁA�gLacrymosa�C"�ɊY������B�Ȃ��Ȃ�A���̊y�͂̑�P���߂̘a���́A��i�S�̂̑�P���߂Ɠ���i�j�Z���j������ł���B
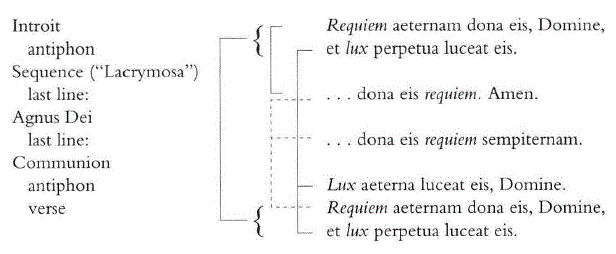
�@���炩�ɁASussmayr�́ASequence�̍Ō�ɁA���C����
"Requiem"�e�[�}���Ăяo������悤�ɂ����Ƃ��ɁA�m�ł����b��������B�ނ�
"Amen"�t�[�K�̐��k������k�������悤�Ƀ����f�B�ƑΈʖ@��������k�������B�ނ̗����ʒu�̋����́A
"Lacrymosa"�i��26���߁j�̏I���̒��O�̃����f�B�[�̈��p�ɂ����������Ȃ�������Ă��邪�A���̓_�ɂ����ẮA�C���I�ɂ͐������Ȃ��A�m���Ƀ��[�c�@���g���l�����悤�ȈӖ��ł͐��m�ɂ͎������Ƃ��ł��Ȃ�����(Ex.
II. 15).�B63

63
����́A���[�c�@���g�ɂ���Ĉ₳�ꂽ���Ƃ��Ƃ̑��e���̂��́A���邢�͎������̂��̂ł���B�����āA�W���X�}�C���[�̕�M�ɂ��A��̉����ꂽ�B����͂��ׂāAMaunder��1988�N�łł́A�폜����Ă���BWilhelm
Fisch�́A�gLacrymosa�h�̑�24�|28���߂̂��Ȃ��|���t�H�j�[��_���A�����ł��Ă��Ă���B�������ނ́A"Requiem�h�̍Č������C���e�[�}�ɂ��Ă͂��Ȃ��B
�e�L�X�g��̑������ɂ�������炸�A�u���N�C�G���v�e�[�}�ƁuLacrymosa�v�̏I���̉��y�I�A�ւ�Agnus
Dei�ɋy��ł��Ȃ��̂͂Ȃ����iExx�D1.11�Q�Ɓj�B
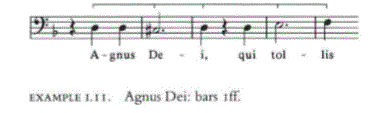
�����炭�́A�W���X�}�C���[���A���[�c�@���g�́h�f�ނ̓���h�ɂ��āA�y�z�ɂ����铝���I�T�O�𗝉����Ă��Ȃ��������߂ł���B�����Ȃ�ꍇ�ł��A
Sussmayr���A�gscraps�@of
paper����AMozart�̐^�̈Ӑ}����ɂ��悤�Ƃ��Ă����悤�Ɍ��������A���ꂪ�ASanctus�ȍ~�̃��N�C�G���̊����̔ے�ł��Ȃ������̗��R�ł���B���̎�_�́A��ɍ\���I�Ȃ��̂ł���A����scraps
of paper���A���[�c�A���g�̍č\�z�ւ̎����͗^���Ă��Ȃ��Ɗm�M���Ă���B����͔ނ����̏�ł͂Ȃ����̒��ŏ�ɕێ����Ă������̂ł������B���N�C�G���̏ꍇ�A�ނ͂�����Ɏ����čs���Ă��܂����B���������Ė������̍�i�ƁA�ނ̎����������l�����I���́A���N�C�G�����ނȂ��Y�قȒf�ЂɌ��т������ƂɂȂ�B
| 
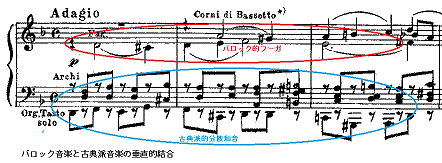
 �@
�@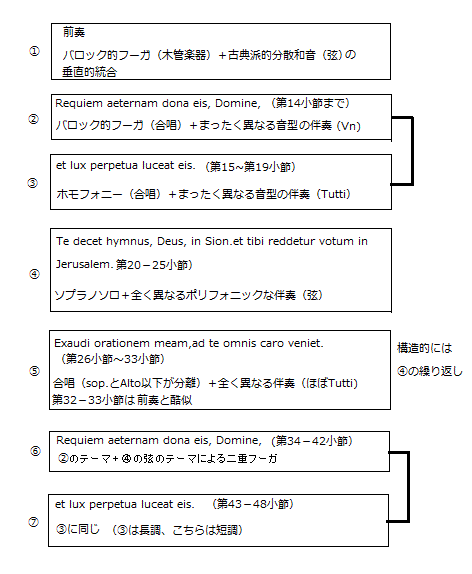
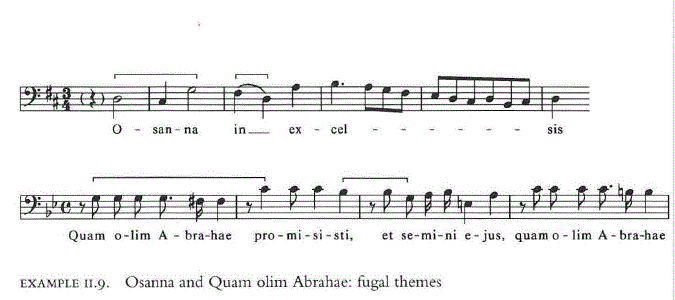
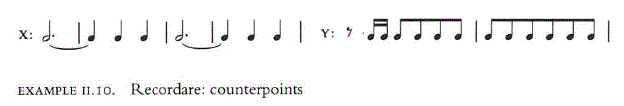
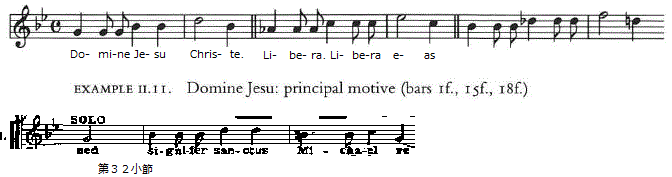
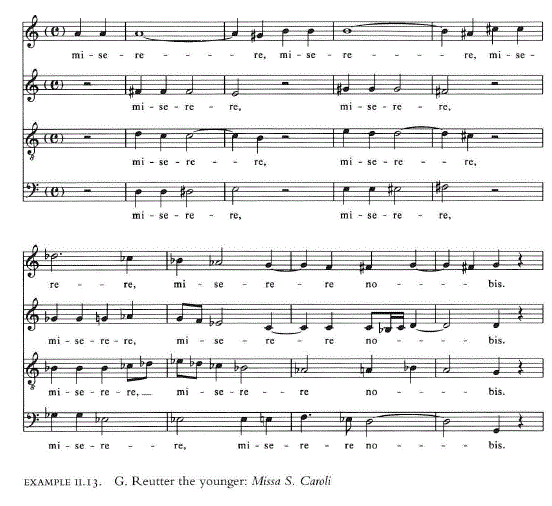

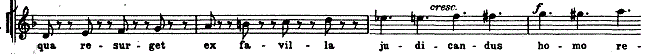 �������Ă��āA������\�����Ă���B
�������Ă��āA������\�����Ă���B