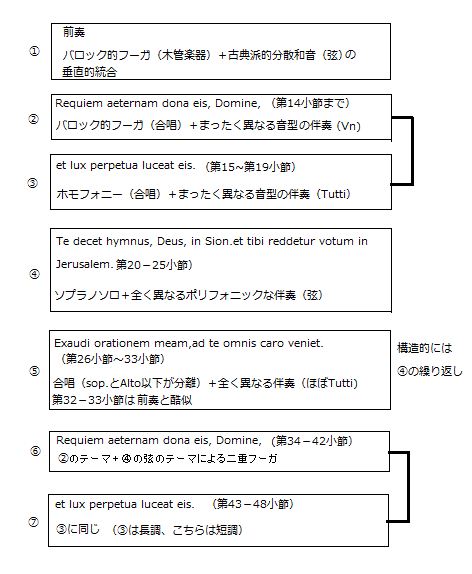Styles,T extures,and Forms
The choral movements are by far the most numerous,and their formal variety
and disposition are forcib1y rerniniscent of Handel,whose oratorios Mozart
had studied with profit in the 1ate 1780s.
合唱の楽章は、はるかに数が多く、そして、それらの多様性や性質はモーツァルトが1780年代後半に、そのオラトリオを学んだHandeの遺産である。モーツァルトがヘンデルから学んだ最初の、そして第一のことは、3つの基本原理である。それは・・・
①ホモフォニック(和音)
②カンタービレ(歌)
③模倣(フーガ)
3つの様式の区別は、それらが並んだ楽章にあるときに、明らかになる。ゆえに、Kyrieのフーガ書法は、“Dies
irae,"において、基本的な和音のデクラマシオンによって直接フォローされる。Offertoryにおける“Quam
olim Abrahae"のフーガは、2つのversicleの均一な歌を設定する。
同様なコントラストは、より小さいスケールで、四分音符に存在する。;“Rex
tremendae”は、ホモフォニーから模倣への突然の遷移の例である。第3−5小節は、四分音符によるブロック和音である。第6-7小節は、符点音符のブロック和音である。第7小節以降は、入り混じった音価を伴う、濃い模倣のtexureを含んでいる。同じタイプの区別は、単独の楽章でも見つかる。“Tuba
mirum"(Sequence,スタンザ7)のソプラノのセクションでは、最初の5小節は、はっきりした旋律的な流れを持っているが、ホモフォニックなデクラマシオンが、第45小節において、急に続いて来る。そして、第49-50小節のカデンツで終わる。4人のソリストは前のホモフォニー部分のヴァリアントを展開し、変化させる。
その間、表現力豊かなメロディが、ヴァイオリンを流れている。
異なる声部のテクスチャーのモーツァルトの備えは、各々の楽章に、独自の性格を与え、豊かで様々な内部の構造を強化する。;これは彼に、特に、単純にテキストに従うだけでなく、音楽形式をつなぎとめている要素を進化させる。たとえばIntroitは、異なったセクションで以下のようになっている。
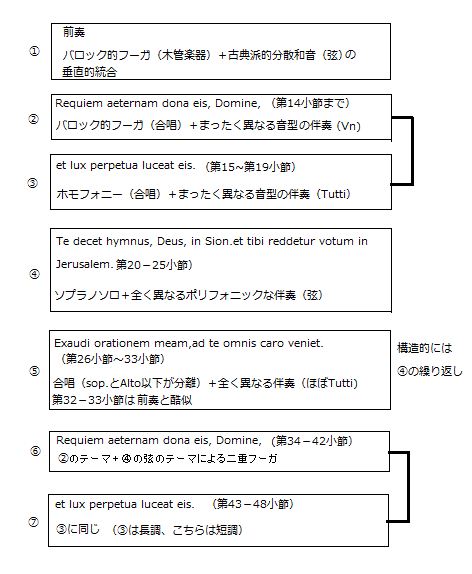
“Domine Jesu" は、以下のような構造になっている。
①カンタービレ的主題A (第1〜6小節)
②大きな跳躍を伴うメロディ。下声部は緩やかなポリフォニー(第7〜14小節)
③主題Aから導かれた緩やかなポリフォニー的再現(第15〜20小節)
④コンティヌオの対位法を伴う、連続した転調をする模倣的(フーガ)発展(第21〜31小節)
⑤主題Aを導入するカンタービレへの回帰。カノン。(第32〜43小節)
単にテクスチャーを分類することは。モーツァルトの音楽の意図を正当に取扱わない。なぜなら、我々は、さまざまな変化による個々のカテゴリーの範囲内で、絶えず驚いているからである。これは、“
Kyrie" と “Quam olim Abrahae"の2つのフーガに適用される。両者とも、最初からstrettoとなっている。Kyrieのフーガは、常に対旋律を伴う厳正なフーガであり、“Quam
olim Abrahae"のフーガは、colla partの弦楽器を伴わない、自由なフーガである。第67小節後に、stageによって、解決される。同様に重要なことは、2つのフーガのテーマ素材の扱い方の違いと、これらの違いの構造的な連続性である。
“ Kyrie"のフーガは、真にヘンデル由来であるが、合唱フーガの慣習的パターンに従っている。そこでは公式な統一性と安定性が保証されている。“Quam
olim Abrahae"のフーガは、対照的に、主題の統合を控え、フーガのテクスチャーの段階的な解決への道を開く。
Amenフーガは、スケッチとして現存しているだけであるが、そのpolythematicismがモーツァルトの、他の2つのフーガとは異なるプランを示し、同じ様式で書かれたセクション内を隔てるための彼の意図を強調していることは明らかである。
作品の公式スキームの中で、概して、セクエンツィアにとっては、フーガで終わらすことが絶対に必要であり、それらは、5つのメインセクションで終わっている。5つのフーガの別の特徴は、これらの韻律が4拍子と3拍子で交互に変わることである。"Hosanna”フーガ(そのジュースマイアーの完成度の低さは無視して)は、強くテーマを形成する基礎となり、“Quam
olim Abrahae"フーガの基本的主題を精緻にし、構造的安定性の基礎を供給する、決定的なオリジナルな概念である。"Hosanna”フーガの独自性は、シンコペーション的始まりと、とりわけその豊かな内的輪郭にある。
フーガへのモーツァルトのアプローチは、それをtransferしている間は、伝統に従うための2倍の野心の1つの現れである。我々は、今の音楽に訴える過去の音楽の神聖な荘厳性を統一する、ニッセンのコメントを思い出す。46
レクイエム全体が、様式的なフレームワークに埋め込まれることは、それゆえ、偶然ではない。Introit
とKyrieの音楽はスタート地点であり、異なったテキストの繰り返しはゴールである。モーツァルトはヘンデルのモデルの伝統を受け継ぎ、プレインチャントのpsalm
toneを加えることによってそれを強化し、同時に、新しいスタンプを印象づけている。古いものから新しいものへの遷り変わりは、すでに最初の小節で明らかであり、ポリフォニーは音色の影により、豊かにされた。
重要な新しい要素は、colla parteそのまま(イントロイトの第7小節以降のバセットホルンとトロンボーン)から、厳密なオブリガート伴奏(第20小節以降の弦楽器)まで、さまざまな方法で、モーツァルトが彼の楽器を展開することである。モーツァルトは、純粋なア・カペラは避けようとしている。時々例えば、"Rex
tremendaeの終わりの「salva me,fons pietatis」でのように、特殊な点においては、オブリガート伴奏をカットオフしているが。
器楽的要素の従属性は、特に、モーツァルトがオーケストラの導入をしないで済ますような場合(Dies
irae,"“Confutatis,"“Domine Jesu")、注意がいる。こうしたところで、オーケストラの特別な強さが示されて、区別のためのその潜在性が声楽のそれと等しさが存在する。モーツァルトのparticelloが示すように、彼が声楽書法を発展させるために使用するのは弦楽器が基本である。木管楽器の機能は大規模なサポートであり、そして、それらは"Harmoniemusikの領域から遠い冒険をしない。
オーケストラの実質的な役割は、colla parteでのサポートの役割を離れ、tone
colorのようなリズム的次元を加えることにより、スコアを強化することである。“Dies
irae”の弦楽器の伴奏と“Confutatis"(第24小節〜最後)におけるトレモロついての比較は、リズム形やアクセントのシフトがいかに、声楽をサポートし、音楽表現を強めるか、を示している。
部分的にオブリガートの伴奏を伴った声楽が形成されたやり方は、音楽のテクスチャーを頼ることになり、修正の慎重な手段に達する相当な違いに終わることがあり得る。さらに、楽器は、控えめなやり方で独立した貢献をしている。先に模倣されている声楽素材(“Tuba
mirum"を導入するソロトロンボーンがその例)、(声楽とオーケストラの)対照的な素材(Rex
tremendae" and “Confutatis");声楽と器楽の互いの地合いの適合性。
この最後のテクニックは、特に、“Recordare."のプレリュードにおいて、よい効果をもたらしている。これはレクイエムにおけるもっとも長い器楽パッセージであり、それは、声楽と器楽の対位法の統合の例となる。バセットホルンは、2声のシンコペーションの対位法であり、声楽の代替として働いている(下図X)。その間、チェロが対抗する器楽的対旋律を出す(下図Y)。次のセグメント(第7−13小節)では、器楽の対旋律は3パートとなり、上部の音域を占め、その間、”声楽”のシンコペーションは、バスに対して、下っていく。この交換は、厳密に、二重対位法の規則に従っている。第14小節からの歌手の入りにおいて、バスの第14小節の斜行が加えられ、その流れは全体として、拡大していく。この楽章のロンド様形式は、概して、XとYの2つの対旋律の対話によって形成されている。特にY素材の使い方は、ritornelloのやり方として、強い力を放っている。
|