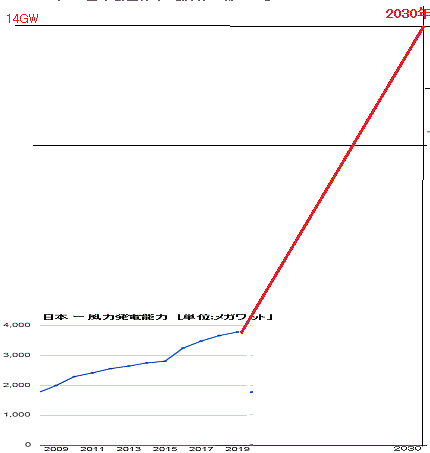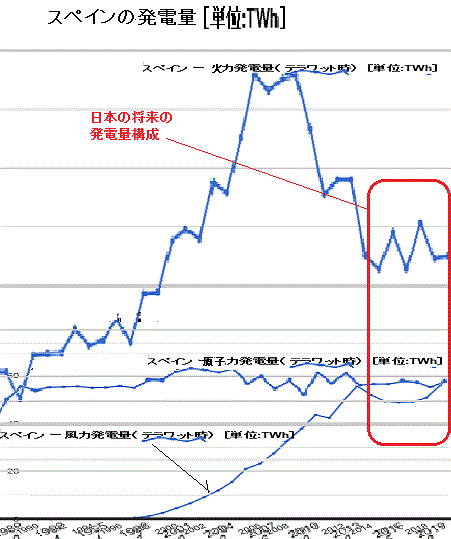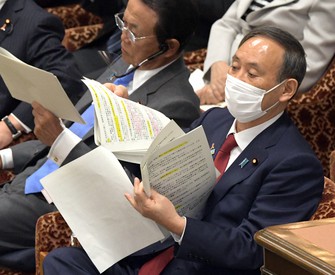|
出席者によると、「党名は投票で選んでもよい」との意見が出たが、枝野代表は「党名を投票で決めると、多数派工作が始まる。だから投票は行わない」として退けたという。(令和2年7月18日読売新聞記事より)
|
否、ナチスを選んだ当時のドイツ人の方が、まだその選択には合理性があった。あのベルサイユ体制は、そもそも民主主義的体制では、そこでドイツ人が生きていくことは不可能であり、独裁体制が必然だったからである。
その点、2009年の政権交代は、無駄以外の何者でもなかった。あえて言えば、サヨクに政権をまかせる危険を、B層も含めて、多くの日本人が知った、ということくらいか、その利点は。
それにしても、投票行動を忌避するとは、いったい枝野・福山体制とは何なのだ、ということになる。なぜなら、投票こそが、民主主義の基本中の基本なのだから。投票を否定するなんて、民主主義を掲げる組織ではあり得ないだろ? 明治維新の頃の、蝦夷共和国だって、総裁を決めるのに、投票を使ったのに。
多数派工作が行われるから、というのが、投票を忌避する理由のようだが、そもそも、民主主義とはそういうものではないか。多数派工作がうまいグループが勝つのは、それだけ人心をつかんだからであり、それこそがまさに民主主義社会である、ということ。
かつてチャーチルが「民主主義は最悪な政治形態だ・・・」と言ったように、民主主義とは決してきれいごとの制度ではない。
そしてまた、チャーチルの言うように、民主主義を否定すると、あとは独裁しかない。独裁者の恣意で運命が決まるよりはまだ自分のことは自分で決めたいという人が多かったからこそ、民主主義という制度が、世界的に選ばれてきたのだ。
枝野・福山立憲民主党はまさに、こうした世界の歴史の流れに逆行するもので、彼らは独裁こそが、民主主義よりもすばらしい、と思っているのである。チャーチルは無視して。
なにはともあれ、民主主義を最前面に押し出そうとする"民主党”が、民主主義を否定するとは、これほどのブラックジョークもあるまい。